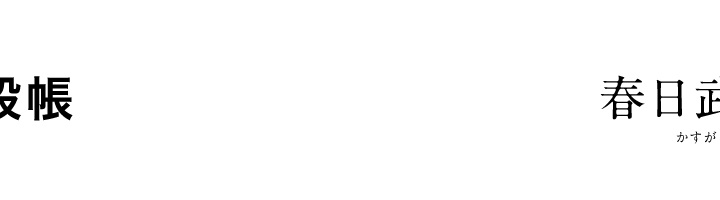精神科医、春日武彦さんによる、きわめて不謹慎な自殺をめぐる論考である。
自殺は私たちに特別な感情をいだかせる。もちろん、近親者が死を選んだならば、「なぜ、止められなかったのか」、深い後悔に苛まれることだろう。でも、どこかで、覗き見的な欲求があることを否定できない。
「自分のことが分からないのと、自殺に至る精神の動きがわからないのとは、ほぼ同じ文脈にある」というように、春日さんの筆は、自殺というものが抱える深い溝へと分け入っていく。自身の患者さんとの体験、さまざまな文学作品などを下敷きに、評論ともエッセイとも小説ともいえない独特の春日ワールドが展開していきます。
「懊悩の究極としての自殺」
わたしたちが漠然と信じている一種の迷信として、以下のようなものがある。人が苦しみ抜き、もはや救いは訪れず、懊悩の果てに追いやられたときにいったいどうなってしまうのか? その問いへの答である。言い換えれば、苦境が極限に達したときに人間はどう振る舞うのか。
おそらく二つの答が出てくるのではないだろうか。ひとつは、「自殺をする」。もうひとつは「気が狂う」。たぶんこの二つである。場合によっては悟りを開くとか神の啓示に目覚める場合もあるかもしれない。ただしそれは発狂のひとつの形に過ぎないと主張する向きもありそうだ。
たとえば平成三十年四月二十四日付・読売新聞朝刊の三面記事を紹介してみる。見出しは、《殺人手配犯 遺体で発見》となっている。
神奈川県清川村の宮ヶ瀬ダムで昨年8月に白骨遺体で見つかった男が、同県厚木市で2003年に起きた殺人事件の指名手配犯だったことが県警の鑑定で分かった。捜査関係者が明らかにした。県警は、男が飲食店の女性従業員につきまとった末に殺害に及び、その後ダムに飛び降りて自殺したと見ており、24日にも、容疑者死亡のまま殺人容疑などで書類送検する。
捜査関係者によると、書類送検されるのは、厚木市南町、アルバイト清掃員久保田匡慶容疑者(事件当時24歳)。03年11月9日午前1時25分頃、同市東町の駐車場で、飲食店から出てきた仲野志帆さん(当時26歳)(静岡県富士市)の胸を刃物で刺して殺害し、止めに入った男性店長にも重症を負わせた疑い。
ストーカー男が逆上して標的の女性を刺殺してしまい、しかしそのあとで、もはや自分の人生は終わってしまったと諦めたか、あの世まで相手を追いかけようとしたか、自責の念に駆られたか、いずれにせよ生きているなんて耐えられない状態に陥り、ダムに飛び降りて自殺をしたというわけである。
わたしたちはそのようなストーリーを、ありそうなことだと認識し受け入れる。ストーカー殺人などを犯してしまったら、刑期を終えて出所してもまともな人生など送れまい。もはや満ち足りて平和な生活など望めまい。惨めで苦しい日々しか待ち受けていないに違いない。そうなったら、悲観ないしは自暴自棄によって自殺をしてしまうのも無理からぬことだろうと考える。
だが、ろくでもない殺人犯のうち、自殺をする者はむしろ少数派だ。自分の人生がもはや「詰んで」しまったと悟っても、彼らは死を選ばない。
執拗な「イジメ」を受けて自殺する人がいる。失恋や失敗によって自らの命を絶つ者がいる。肉親や恋人や「かけがえ」のない人物が死んだからと、後を追う者がいる。でも、生き続ける者のほうが多い。はるかに多い。にもかかわらず、我々は絶望や喪失や苦境が自殺への扉であると信じている。
では発狂のほうはどうか。昭和四十三年に封切られた増村保造監督の『セックス・チェック 第2の性』という半エロ映画がある(緒形拳と安田道代=大楠道代が主演)。この中で、日本スポーツ連盟嘱託医である峰重正雄の妻・彰子(小川真由美が演じる着物姿の貞節な夫人)が、緒形拳演ずる粗暴な男・宮路コーチにレイプされる場面がある。そのショックで彰子は気が狂ってしまい、精神科の入院に収容される。映画では、鉄格子の窓から着物姿のままの彰子が外に向かって、焦点の定まらない目で楽しそうに調子外れな歌を口ずさんでいる光景が描き出される。まさにステレオタイプな《絶望→発狂》そのままで、これを新宿の映画館で観ていたわたしは、まだ高校生ながらも「いくらなんでもねえ」と思ったものである。だがそれはそうとして、やはり懊悩の極限としての狂気といった図式を信じていたのは確かであった。
結局のところ、自殺するか、あるいは生き続けるとすれば狂気の世界に迷い込むか、それこそが苦境が究極に達したところの人間の姿であるという合意が、世間には成立しているわけである。
「究極とは何か」
中村古峡(一八八一~一九五二)という心理学者がいた。夏目漱石門下の文学者であると同時に心理学も修め、診療所を開設するのみならず日本精神医学会を設立、雑誌『変態心理』を創刊している(この場合の変態は神経症的といった意味合いであり、アブノーマルな性嗜好を指しているわけではない)。通俗心理の著作も多い。
彼の著した『自殺及情死の研究』(日本精神医学会、一九九二)には明治や大正時代の自殺ケース、情死ケースが数多く紹介されていてなかなか興味深い。それらの中からここに二症例を引用してみたい。
大阪府・宮○やく(一七)はゴム會社の女工となつてゐたが、白粉をベタ〳〵と塗り立てて便所へ入つた處、同便所設備の防臭劑の化學作用で顔色が一度に黄色に變り、同輩にもからかはれたが生來ヒステリー性の女なので精神に異状を來し鐵道自殺を遂げた。(大正七年九月)
高松市・中山○妻某は、夫の留守に市で廉賣の米を買ひに行き、財布がないのに氣が付いて遺失したものと早合點し、夫に對し済まぬとて路傍で消毒用のフオルマリンを服用し、尚剃刀で咽喉を突いて苦悶中、通行人が發見し仔細を尋ねると、米とか金とかいふのみで死亡した。後で調べてみると右の金は飯臺の抽き出しにあつた由である。(大正七年八月)
最初のケースは、白粉をべたべた塗ってトイレに入ったら防臭剤と化学変化を生じて顔が黄色くなってしまい、恥ずかしさのあまりに鉄道自殺を遂げた。次のケースは、安売りの米を買いに行ったら財布がない。財布をなくした、それでは夫に申し訳ないとホルマリンを飲み喉を剃刀で突いて自殺を遂げた。しかし財布は家に忘れてきただけであったという笑えぬ後日談が続く。
これらに対して中村古峡は素っ気ないコメントを述べる。いわく、「彼等の住んでゐる世界は極めて小さいので、吾人から見て何でもない小さな事にも自殺する。叱られての自殺などといふのはそれで、人を使ふものはよく〳〵注意が必要である」と。なるほど、それはそうだとつい首肯したくなるが、果たしてそう簡単に言い切れるものなのか。中村からすれば貧しく無教養な庶民に該当するであろう人たちには、取るに足らない理由で自殺するケースがことさら多いのか。
ハイティーンの女工にとって化粧がどうした容色がどうしたといったことで頭がいっぱいだったとしても、それは決して不自然ではあるまい。貧しい家庭の主婦が財布をなくしたと知ったら、この世の終わりが訪れたかのように思い詰めても不思議はなかろう。世の中の基準から大きく隔たっているわけではない。それを、「彼等の住んでゐる世界は極めて小さいので、吾人から見て何でもない小さな事にも自殺する」と珍奇な話であるかのように言い切ってしまうのは、あまりにも乱暴ではあるまいか。
彼らにとっての切実な価値観が、中村にはいまひとつ「ぴん」とこなかった。それだけなのに、彼らが極めて小さな世界に住んでいるなどと偉そうに断定するのはいかがなものか。学会の権力争いだとか、研究論文を専門誌に掲載されるか否かといった話ならば大きな世界なのか。名誉だの栄光だのならば気宇壮大な世界なのか。
問題は、心の切り替えが器用に出来るかどうかなのではないだろうか。今現在自分が没入しているテーマが失望や絶望に終わったとき、そこで「ああ、すべて終わりだ!」と悲嘆のあまりに自殺へ短絡するか、一晩泣き明かすか、泥酔するか、心の許せる誰かに告白するか、居直って派手に散財でもするか、手近な対象に当たり散らすか、これも人生勉強だと我慢をするか、振る舞いの仕方は人それぞれであろう。
なるほど目下のテーマに関しては懊悩の究極に達してしまっているかもしれない。が、普通そんなときに人はとりあえずテーマから距離を置く。話をすり替えたり、斜め上の方向に関心を向けたり、とにかく自分を誤魔化す。そして時間を稼ぐ。時間を稼げば気持ちはそれなりに落ち着いてくるし、「あの葡萄は酸っぱいのさ」とばかりに感情をなだめすかせる作用が自動的に発動する。それが自然の形であり、もし自殺が帰結になるとしたら、馬鹿げた固執にこそ精神病理は求められるべきではないか。
ストーカー殺人を行ってしまったのも、自慢の顔が黄色く変わってしまったのも、財布を落とした(と思い込んでしまう)のも、いずれもそれだけでは自殺の理由としての絶対性を持たない。そうした事象へこだわり、精神的な視野狭窄をきたしてしまった挙げ句に自殺以外の選択肢を持たなくなってしまうような柔軟性の欠如が異常なだけである。言い換えるならば、精神的に視野狭窄をきたしている人間には、どんな些細でくだらないことであろうと自殺の理由として作用し得る。究極なんて言うと大層なことに思えるが、無限遠の距離に存在する究極もあれば、十センチ先に立ちはだかる究極もある。言葉に惑わされてはいけない。
「固執と視野狭窄」
この世を生き抜くために、人は無意識のうちにさまざまな戦略を駆使する。固執や精神的視野狭窄は、そうした戦略のひとつとしても登場する。
そもそもわたしたちにとって最大の苦悩は何であろうか。人それぞれにいろいろな意見があろうが、現実生活に即して考えれば、解決のつけようがない悩みがいくつも同時に生じてどこから手をつけていいのかすら分からない状態というのが「苦悩ランキング」のトップとはいわなくとも上位にランクインするのではあるまいか。ひとつひとつは日常レベルの悩みに過ぎなくとも、それらが同時多発的に発生して悩みのゴミ屋敷状態となったとき、わたしたちは心の底からうんざりするだろう。面倒で鬱陶しくて腹立たしくて、しかも無力感に苛まれる。こんな状況のほうがよほど死にたくなりそうだ。
でもそんなときに、人は回避する方策を編み出す。「こだわる」という営みである。どんなくだらないことでも構わない、とにかく固執する。固執するとどうなるか。精神的な視野狭窄状態となる。それはすなわち、固執している事象以外は意識の外に追い出されることに他ならない。スポットライトに照らし出されている対象とは正反対に、その周縁の闇に諸々の厄介事は沈んでしまうわけである。
もちろんそんなことをしても問題解決にはならない。でも、とりあえず気が楽になる。「とっ散らかった」状態が、シンプルになる(ような気がする)。ひと息つける。
別の表現をしてみるなら、「こだわり」は厄介な状況から目を逸らすための陽動作戦だ(神経症も、症状へのこだわりによって苦境からの逃避を図る点では同じ範疇に入る)。もちろんそんな奇策を弄すると事態は結果的になおさら悪化しがちだけれど、しばしば人はこうした伝家の宝刀に頼りたがる。
そしてここが問題なのだが、精神的にすぐ視野狭窄に陥ってそこから抜け出せないタイプの人がいるのである。そのような人がいったん悩みに囚われると、たちまち懊悩の究極に立ち至り、心の切り替えが出来ないまま「もはや打つ手なし!」と自殺に走ってしまうのではないだろうか。そのとき自殺の経緯について、「彼等の住んでゐる世界は極めて小さいので、吾人から見て何でもない小さな事にも自殺する」と断ぜられる可能性が出てくる。まあたしかに、視野狭窄となった目に映る世界は「極めて小さい」のだけれど。
世間を生き抜くための奇策の筈なのに、それが些細でつまらぬ理由で自殺をしてしまうメカニズムを担ってしまう可能性があるとは、まことに皮肉な話である。
「ゴキブリ責め」
なお言い添えておくと、発狂というものが「不可逆的で永続的な精神の混乱をきたし、現実との接点を失って妄想や幻覚の世界に生きるようになり、感情も不安定きわまりない状態となってしまう」といった類のものと考えているとしたら、それが懊悩の究極によってもたらされる可能性はまずない。未治療のまま放置された統合失調症のごく一部に、そのような症状に近いものを示す可能性はある。しかしそれが懊悩の究極から生じるわけではない。今のところ統合失調症の真の原因は不明で(脳神経におけるドパミン仮説の類は、部分的に関与はしていてもそれだけでは実体解明にまったく不十分である)、ましてや絶望だのストレスが直接の理由で生ずるわけではない。ストーリーとして納得がいくような因果関係は存在せずに統合失調症は発病する。
さて、わたしはかなりシリアスな甲殻類恐怖症で、その延長で昆虫もまったく苦手である。もしそんな当方が、以下に引用するような目に遭わされたらどうなるか。式貴士「カンタン刑」(『カンタン刑・式貴士恐怖小説コレクション』光文社文庫、二〇〇八年所収。同題の短篇は一九七五年発表)の一部を紹介する。
上を見ると天井に鏡が貼りつけてあった。コンクリートの床に打ちこんである枷(かせ)に手足をがっちりくわえこまれ、四肢を引きのばされた形で床に固定されている哀れな姿が目に入った。衣服は木綿の囚人服一枚らしい。
だが、その服が見えないくらいに、真黒なものが体中を覆って蠢いていた。胸に、脚に、手の上に、顔の上に、そして口の中いっぱいに……。
それが何千匹というゴキブリの大群だと知った時、さすがの草田八朗は、ふたたび絶叫した。
「クワーッ! ク、ク、ク、クワーッ!」
(中略)
上下の歯を思うさまこじ開けたまま、口が閉じられないようにつっかい棒代りの金輪が嵌めこまれていた。その上、ゴキブリの大好きな臭いの餌が口中に仕掛けられているらしい。
ピチピチ、シャリシャリ、サワサワ、グソグソ、ジョリジョリ、ゴキブリどもは八朗の狭い口腔の中ではね回り、ひしめきあい、のどちんこを摩擦し、細かい奴は鼻孔の中にまで出たり入ったり遊び回り、図々しい奴はのどの奥、食道近くまで這いこんでこようと、カリカリ鋭い爪を立て、チクチクと赤い粘膜をかじっていた。
このような刑罰を受けたら、それこそ発狂してしまうのだろうか。助け出されて精神科病院へ収容されても、病室で「虫の声」(文部省唱歌)を延々と裏声で歌い続けることになるのだろうか。
おそらくそうはならない。一種の緊急避難として解離状態に陥り、大量の脳内物質が放出され、一時的に精神活動が麻痺したり人格変換でも起きるのではないか。PTSDにはなりそうだが、少なくとも不可逆的に狂人と化して以後の生涯を精神科病院で過ごすようにはならないだろう。ゴキブリの刑は、ある意味でわたしには究極そのものであるがそれによって発狂には至るまい。一時的には気が狂ったような激しい反応を示しても、あくまでも一時的だ。口に金輪が嵌められていなくとも、舌を噛んで自殺を図ることもなさそうな気がする。
「情死のこと」
自殺の特殊なタイプとして、心中がある。定義としては、「同じ場所で同時に、二名以上の者が、一緒に自らの意志による合意のうえで、同じ目的のもとに自殺を行う」といったところであろうか。無理心中、後追い心中などの亜型もあるが、男女が悲恋の結果として心中にいたるものを情死と呼ぶ。
情死には究極といった意味合いが強い。懊悩の究極と愛の究極が合体したものと解されがちだからだろう。それこそドラマチックで、ロマンチックである、と。
もっとも自殺学の泰斗である大原健士郎は、「いわゆる近松時代(江戸前期)の情死の原因は、恋と金と恥といわれているが、小峰茂之という学者が昭和のはじめに情死を分類して、夫婦になれないための悲観、痴情関係、経済問題、家庭不和などをあげている。私が何例か調べた結果では、ふたりのなかをさいて結婚させないというケースはないわけではないが、それよりも先に、ふたりが社会や家族に対して不義理な生活をしている、その結果ずんずん自分たちの世界をせばめていって、自殺以外に道がなくなるというケースをとっている者が多い」(『自殺日本』地産出版、一九七三)とシビアな現実を示してみせる。さらに追い打ちを掛けるように、「私は、かつて過去に情死未遂で助かった例にアンケートを出して調べたことがある。それによると、驚いたことに、ふたりで死のうとまでした仲の人が助けられて、当然ふたりがいっしょになっているかと思えば、一~二年くらいの間に三分の二は別れているのである。/その理由を聞いてみると、『顔を見るのもいやになった。どうしてあんな男と死のうと思ったのか理解に苦しむ』というような答えが返ってくる」と。やはりそんなものだろうと思ういっぽう、いささか鼻白む。
ついでながら、大正三年十月に名古屋の娼妓芝雀(二六)と同じく名古屋在住の加藤文次(二一)とが情死を遂げ、その際に残された遺書が前掲の中村古峡の本に載っているので参考までに紹介してみたい。まず加藤文次が両親に残した遺書。
懐しき兩親よ、私は一夫人の為に、世を捨てねばならぬ義理になりました。唯何んとも言葉にすることの出来ぬ事があります、委細は森川君より聞いて下さい、何卒先達不幸を御許し下され度候。
素っ気なく、苦渋に満ちた文面である。面倒な立場に追い込まれてしまったけれども本当は死にたくない、自分は被害者である、といった気分が窺えないでもない。いっぽう五歳年上の娼妓、芝雀のほうは妙に馴れ馴れしいというかゲスなトーンなのである。まず両親宛の遺書。
乍早速一寸申上げますが、就きましては兩親様私は御先へ御無禮しますから、どうかまめでやつて下さいよ、どうか許して下さい、決して力を落さない様にして下さい、父母様どうか赦して下さい。
いまひとつシリアスさに欠ける。さらに彼女が楼主へ宛てた遺書。
早速ながら手紙にて申上げます。就ては誠に濟みませんが何うか赦して下さい、どうか赦して下さい、そして此事能く云ふて置きますがネー、私等が死んだら同じ一つの箱に入れて埋めて下さいよ、此事は兩名とも一心の頼みです、どうか赦して下さい、別にしたら一生うらみます、どうか一つ箱に入れて下さる様にくれぐれも御頼み申します、私の郷里の親たちにも承諾させて、どうか別にせぬ様に同じ穴へ埋て下さい、之ばかりは一生の願ひです、頼みます、文次様兩名の願は只是れ丈げですよ頼みます。
いやはや「此事能く云ふて置きますがネー」という口調、死んでいくくせに「一生うらみます」といった表現など、苦笑が浮かんでしまう。女のほうはたとえ死という形であろうと、とにかく娼妓の立場から逃げ出せることに浮き足立っているようで、加えて歳下の男との心中に夢中になっており、いささか軽躁状態ではないかと疑いたくなる。いっぽう男のほうは成り行きからいつの間にか死ぬ羽目になって仕舞った気配で、愛の究極とは言い難い雰囲気が漂う。そのぶん、妙なリアリティーが感じられて当方としてはどこか後味がよろしくない。
わたしの感想はともかく、情死という形式には暗黙の了解として「こればかりはまあ仕方がない」「愛の極致として大目に見るしかなかろう」といった心情が付与されているのではあるまいか。再び大原健士郎の言葉を借りるならば、「情死のところでちょっとふれておかなければならないことは、日本人は特に美しいものを好むということである。日本人には、美しければ罪は消失し、醜いものは罰に相当するのだというような独特の心情がある。たとえば、情死が美しいものであれば罰しない。そういう心情が、ことさら情死を美化したということも考えられる」。かなり荒っぽい意見であるが、言いたいことは分かる。つまり、少なくとも我が国では、情死は一種の様式美として成立しているのではないかというわけだ。
様式美という考え方は興味を惹く。なぜなら、様式美に則ればそれは許容され、ときには賞賛されるからである。死への恐怖も疚しさも、様式美を持ち出せばあっさりと払拭される。自殺に対する抵抗を減らす便利な装置として様式美は機能するかもしれず、もしかするとそれは情死だけに留まらないのではないか。自殺そのものを様式美として捉えて容認する感性すらあり得るとは考えられないか。なお自殺の七つの型の(1)として既に「美学・哲学に準じた自殺」を挙げてあるが、あちらは美の実践として(つまり作品として)大胆にも自殺を担ぎ出しているといったニュアンスを帯びているのに対し、様式美云々は、自殺のハードルを下げ自己正当化を図るといった方便としての色彩が強いところが大きな違いではないかと思う。
「国立三社長心中事件」
事件は一九九八年二月二五日に起きた。
同日、都下・国立市内のビジネスホテルに三名の会社社長がチェックインしたのだが、彼らは夜中にそれぞれの部屋で同時刻に首吊り自殺を遂げたのだった。縊死の直前には、一室に集まりテイクアウトの牛丼(並盛り)と缶ビールでささやかな宴を開いていた。自殺の原因は三人ともそれぞれの会社経営が行き詰まったためで、二五日は手形の決済日であったという。
三人の社長のうちリーダー格はMK(五一)で、カー・アクセサリーを扱う小売会社「ゲインズ」を経営していた。この会社はピーク時に従業員数一八〇名、年商六〇億、多摩地区だけで十数店の店舗を構えており、F1レースのスポンサーに名を連ねたり、競走馬アイネスフウジンの馬主となって一九九〇年の日本ダービーで優勝を経験したりしている。他の二人は小規模ながら自動車部品小売り会社社長のMS(四九)、川崎市の部品卸売会社社長YT(四九)で、MSとYTは幼馴染み、またMKとは取引関係のみならずプライベートでも親交が深かった。
一時期は我が世の春を謳歌していたものの、バブル崩壊や競合店の出現で三人の会社はみるみる業績が悪化していった。もはやF1レースだの、日本ダービーどころではない。互いに手形を融資し合って何とか耐えていたものの、遂に三社とも倒産は回避出来そうもないことが判明、すなわち会社危機の「究極」へと追い込まれたのだった。
彼らは経営の行き詰まりに対して大いに責任を感じていたらしい。社長としての自覚が強かったということであろうか。三人揃って遺書を残しているが、いずれにも「死んでお詫びする」という文言があったという。さらに、たとえばMKは四億円の死亡保険に入っていた(他の二名も同じく死亡保険に入っていた)。この受取金で資金繰りの足しにしてくれと遺書に記していたが、そんなものでは焼け石に水である。「ゲインズ」の負債は三七億円に達していたという。実際、彼らが亡くなった二日後、会社は自己破産手続きを取っている。
以上が「国立三社長心中事件」のあらましなのであるが、わたしの中では結構鮮明な記憶がこの事件については残っている。わざわざ三人が揃ってホテルで首を吊るというところに、当方のみならず誰もが奇異な印象を抱いたのであった。いくら仲が良かったとしても、中年男が三人一緒に自殺なんてちょっと不自然ではないか。同性愛関係を疑った言説までもが取り沙汰されていた(もちろんその可能性は否定されている)。
経営破綻→社長の自殺という図式は、「懊悩の究極としての自殺」という枠組みで一応の納得がいく。でもその割には、どこか余裕があるというか直線的でない。一緒にホテルにチェックインしてそこで縊死を図るとか、牛丼とビールでこの世に別れを告げるとか、微妙に切迫感に乏しい印象がある。最後の宴を終えてから三人はそれぞれの部屋に別れた訳だが、いざ一人になったとき、「オレはいったい何をやっているんだ?」と疑問を覚えなかったのか。律儀に自殺まで付き合う必要などあるまいに。三人で揃ってキャバレーに遊びに行くのならともかく、お揃いで首吊りなんて変じゃないか。そもそも自殺の直前に牛丼なんて食べる余裕があるものなのか。
実際にそれが行われたのだから、人間はそんなふうに行動することもあるのだなと思うしかない。かえって「これこそがリアル」と思うべきなのだろう。でも違和感が残る。恋人同士や家族での心中なら分かるが、中年男の心中というのはねえ。
このケースにおいても、補助線として様式美という発想が有効かもしれない。たとえば戦場で力尽きた勇者たちに近いイメージを彼らは自分たちに抱いていたのではないか。戦友同士で潔く自決して花と散る、とか。中年男が三人揃って一斉に首を吊るなんて考えるから間抜けな印象が生じるのであり、勇者たちの壮絶なる自決といった文脈で彼らは自己イメージを形成していた可能性はないか。事件ではなく伝説になるのだと自身を説得していた可能性はないか。そこまで想像力を暴走させなくとも、「潔さ」「死んで詫びる」「戦友」「気が動転しての自死ではなく、男らしく運命を受け入れての自死」といったあたりを心の支えとしてこの世に別れを告げていったような気がするのである。
わたし個人としては、誤解されたり困惑されるリスクなんかもはやスルーしたままちょっと中2病的な感性に走って心中に及んだような気がして、そこに痛々しさと共感を覚えないでもない。アメリカのように銃が簡単に手に入れば、こうした感性はなお一層エスカレートしそうだ。
それにしても、人はイメージによって生きるものだとつくづく思う。いや、生きるどころか、自殺するためのエネルギーとしても作用してしまうところにうろたえさせられる。
「自殺テンプレート」
究極の状態にまで追い詰められれば、心は余裕も柔軟性も失いがちだろう。そんなときに限って、自殺という選択肢が頭をかすめる。そして、追い詰められ自殺する者の振る舞い方に関するテンプレートが存在していれば、安易にそれに飛びついてしまうこともありそうだ。そうしたテンプレートのひとつとして、自殺における様式美といったものが確かに存在している。これを用いれば、さして躊躇せずに自決が可能となる。
情死のようにもはや浄瑠璃レベルの伝統芸能めいた自殺テンプレートもあれば、「死んでお詫びする」テンプレート、戦士の美学テンプレート、煩悶する哲学青年テンプレートなど、さまざまなものがあるに違いない。そうしたものの中には、感覚的に理解が難しいものも存在する。
二〇〇二年に、インターネットの自殺掲示板で知り合った男女が、板橋区のアパートで練炭自殺(心中)を遂げた事件があった。三二歳の女性が残した遺書には「相手は誰でもよかった」と書かれており、これを嚆矢として「ネットで心中相手を募集」「相手を事実上選ばない」「練炭」といった要素からなるネット心中が急速に増えた。二〇〇三~四年頃がピークだったようで、しかし現在でも散発的に行われている。
常識的に考えれば、ネットで知り合っただけの得体の知れぬ人物と心中するなんて理解が及ばない。どこか自分を粗末に扱い過ぎているように思えてしまうのだ。死とはもっと厳粛であって然るべきではないのか。ピザのデリバリーでも頼むような気軽さに、抵抗感を覚えずにはいられない。
だが死ぬ側にとっては、「たかが」この世から去るだけなのに大仰に考えたがるその心性のほうが、よほど鬱陶しいのであろう。他人を平気でないがしろにするようなお前らに、自殺に関していちいち説教される筋合いなんかない、といったところだろう。
彼らにとっては、ネット心中なんてせいぜい「冥界行きの夜行バス」の同乗者を募るといったノリなのではないか。見送りも餞別もいらないから、さっさとこの世から立ち去りたい、と。そうした心性が時代とシンクロしてある程度の普遍性を持てば、それはネット心中というテンプレートとして形を整えていく。そのテンプレートをそのまま落としどころとして実際に死んで行く者もいるだろうし、ああいろいろな自殺テンプレートがあるのだなと気付くことを介して、自殺をもっと客観的に捉えて最終的には死から距離を置くといった結論を出す者もいるだろう。
精神科医としての経験を含めて個人的意見を申せば、自殺テンプレートにすぐ飛びつくタイプの人は遅かれ早かれ自死を決行しそうな気がするし、それを自殺テンプレートであると冷静に認識出来る人は「我に返る」確率が高い。本書の存在意義も、もしかしたらそのあたりに関わっている部分が大きいかもしれない。
 1951年京都生まれ。日本医科大学卒業。医学博士。産婦人科医を経て精神科医に。都立中部総合精神保健福祉センター、都立松沢病院部長、都立墨東病院精神科部長などを経て、現在も臨床に携わる。著書に『無意味なものと不気味なもの』(文藝春秋)、『幸福論』(講談社現代新書)、『精神科医は腹の底で何を考えているか』(幻冬舎新書)、『臨床の詩学』(医学書院)、『老いへの不安 歳を取りそこねる人たち』(朝日新聞出版)、『鬱屈精神科医、占いにすがる』(太田出版)等多数。
1951年京都生まれ。日本医科大学卒業。医学博士。産婦人科医を経て精神科医に。都立中部総合精神保健福祉センター、都立松沢病院部長、都立墨東病院精神科部長などを経て、現在も臨床に携わる。著書に『無意味なものと不気味なもの』(文藝春秋)、『幸福論』(講談社現代新書)、『精神科医は腹の底で何を考えているか』(幻冬舎新書)、『臨床の詩学』(医学書院)、『老いへの不安 歳を取りそこねる人たち』(朝日新聞出版)、『鬱屈精神科医、占いにすがる』(太田出版)等多数。