2017年04月30日から2017年06月11日まで、千代田区の、「アーツ千代田 333メインギャラリー」で、「佐藤直樹個展『秘境の東京、そこで生えている』」が開催されました。板に木炭で植物を描いた作品はおよそ100メートルに及び、展示の方法も類を見ないものでした。そして、今も佐藤さんはこの続きをたんたんと描き続けています。展覧会を一区切りとしたわけではなく、展覧会から何かが始まってしまったということです。本連載は、佐藤さんの展覧会を起点に、文化人類学者の中村寛さんに疑問を投げかけていただき、「絵を描くこと」や「絵を見ること」「人はどうして芸術的なものを欲してしまうのか」など、世界についての様々な疑問について、語っていただく場といたします。
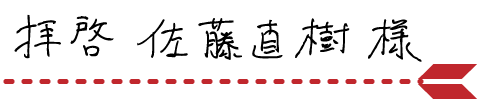
お返事がすっかり遅くなりました。前回のお手紙をいただいてから、半年近くの時間が経ってしまいました。
この半年間、雑誌『世界』でやっていた対談連載を無事に終え、いくつか他の原稿を公刊しつつも、共同研究プロジェクト「グローバル都市の底辺層の構造と変容」の一環でニューヨークに調査に行き、戻ってすぐにそのプロジェクトの研究会をおこない、前後して別の共同研究プロジェクト「覇権主義と美学――インディアン同化政策とアメリカ現代美術」のミニシンポジウムがありました。
「覇権主義と美学」のミニシンポジウムには、佐藤さんも来てくださりましたね。長時間にわたって参加いただき、ありがとうございました。参加された佐藤さんが、どのように聞いていたのか、うかがってみたいと思います。
僕としては、刺激の多い集まりでした。笠原恵実子さん(アーティスト)を中心に、建畠晢さん(美術評論家・詩人)、加治屋健司さん(美術史家)、鎌田遵さん(アメリカ先住民研究者)、高田佳奈さん(文化人類学者)という顔ぶれも、なかなかない組み合わせでしたし、あまり肩肘はらずに話せるインフォーマルな集まりを目指したこともあって、実りある会になりました。
コメンテーターに鎌田遵さんをお呼びできたのも、僕としてはうれしかったし、「学長」という肩書きとお役目を脱ぎ捨てた、美術批評家・詩人としての建畠さんの語りをひさしぶりに聞けたのもおもしろかった。
「学際的」とうたっている集まりや共同研究は多いですが、その内実は意外と、ただ専門の違う研究者が集まって個別に報告しているだけというものが多いように思います(『無痛文明論』の著者である森岡正博さんも、かつて同様の指摘をしていました)。ですが、今回の集まりは、小規模だったこともあり、ちゃんと互いの領域をある程度は侵犯できたのではないでしょうか。
さて、本題です。これまで、2017年春におこなわれた佐藤さんの個展『秘境の東京、そこで生えている』をきっかけに、主には絵を描くこと、絵を見ることについて、そしてそれに関連して音楽や詩などの表現について、やり取りをしてきました。
すこしあいだがあいたこともあり、ここまでを前半として一区切りをつけ、ここからいよいよ核心に迫っていきたいと思います。とはいえ、核心がなんなのか、はっきりとはわかっていないので、相変わらず手探りで進むしかないのですが……。しかし、迂遠に見えても、あたりまえのことを言葉にして確認しあい、必要となれば脇道にそれたり、道草をくったり、まわり道をしながら、探究をすすめるしかありません。なぜなら、「出発点」は、きっとこういうことだからです。
――「芸術」について、「美」について語ろうとするとき、「芸術ではないもの(非-芸術)」「美ではないもの(非-美)」について語らないと、「芸術」や「美」として名指された現象の構成が見えてこない。
これが、少なくとも佐藤さんとやり取りをしているときに、うっすらと立ちのぼる共通認識のように思えます。
たとえば、絵を描くという、一見単純に思える行為を支えているのは、描き手の意図や意志、技能だけではなく、それを支える経済的要件(画材が買えるか、アトリエスペースがあるか)、美術市場への参入要件(展示・売買可能なマーケットがあるかどうか)が深く関係しているように思います。そして、後者の要件には、社会関係資本(絵を描くことを継続できる人間関係があるかどうか)や文化資本(絵を見たり描いたりすることが「意図せずに」「自然に」選択できるかどうか、そもそも絵を描こうと思えたかどうか)が深くかかわっていると思います。
こうしたことも言葉にし、互いに確認をしながら、その過程で、これまで語らないできたことにも、徐々に踏み込んでいきたいと思います。
今月からはじまる佐藤さんの美学校での講座、『描く日々』に参加させていただきたいと思ったのも、そういう理由からです。
僕は絵が描けません。それなりに描ける人が「描けない」と言っているわけではなく、かなり、積極的に、描けないのです。立体物が描けないし、ドラえもんも、イヌも、ネコも、描けません。描くということに関して、よい思い出も一切ありません。
絵を描くことができる友人を、「すごいな」と思ったことは多々ありますが、「うらやましい」とか「自分も描けるようになりたい」と思ったこともない。おそらくそれは、あまりにも描けないからです。
そのような人間が「絵を描く」という営みに参加するとどうなるのか。僕自身も楽しみです。その経験をできるかぎり言葉で記述してみようと思います。いわば、「参与観察」です。
絵は、「うまいかへたか」ではない。そういう言葉をよく耳にします。本当にそうなのでしょうか。
たしかに、ある種の絵については、「うまい/へた」とは関係なく、味わい、楽しめるのかもしれません。だけど、音楽と同じように、最低限の技術というのがあるのかなとも思います。譜面を読めないミュージシャンはいますが、意図してそうするのでないかぎり、音程をはずしまくったり、リズムがずれまくったりしているミュージシャンは、おそらくいません。
絵にも、実際には、「へたな絵」、つまり最低限の基準に達していない絵、というのがあるのでしょうか。仮にあるのだとすると、その際の基準とはどういうものなのでしょうか。また、デザインの場合はどうでしょうか。「へたなデザイン」「最低限の基準に達していないデザイン」というものがあるのでしょうか。
しかしまた、こうした「へたな絵」「へたな音楽」「へたなデザイン」のうちのいくつかが、図らずも、時代の認識を更新していくということがある(あった)のでしょうか。
前回のお手紙の後半で佐藤さんは、フーコーに言及しながら、「新しい認識」「新しい方法」について書いていました。美術という制度が厳然と一方にあり、他方でポストモダンの名のもとに「新たな方法」が繰り出されていく状況がある、と書いていましたよね。
この箇所を読んで僕が思ったのは、制度としての美術が一方にあるにもかかわらず、正面からその内実が語られず、他方で「ポストモダン」の言説を利用するかたちで、そして美術制度に対する表層的で外在的な批判に援護されながら、「我こそは新たな表現者なり」「我こそは制度からはじかれたはみ出し者(アウトサイダー)なり」という美術市場での戦略が横行しているのかな、ということでした。
実際のところはどうなのでしょうか。このあたりのこと、佐藤さんと突っ込んでやり取りをしてみたいところです。
6月末から太田市美術館で個展があるようですね。
http://www.artmuseumlibraryota.jp/post_artmuseum/3330.html
エディトリアル・デザインと絵画とを両方展示されるとのこと。これまでなかった展示ではないでしょうか。楽しみにしています。
僕からも、佐藤さんにいくつかお知らせを。
ひとつは、国立ハンセン病資料館ではじまった企画展『キャンバスに集う~菊池恵楓園・金陽会絵画展 “生きるため、描き続けた。”』です。
http://www.hansen-dis.jp/02exb/exhibition
昨年4月から学芸員として働く木村哲也さんの企画で、国立ハンセン病資料館としては初めての絵画展のようです。
木村さんは、『来者の群像――大江満雄とハンセン病療養所の詩人たち」(水平線、二〇一七)の著者です。ハンセン病療養所のなかで生み出された詩(ことば)は、それこそ「うまいかへたか」を論ずるのが無意味に思えてしまうのですが、この本を読むと、大江さんは詩人として、かなり的確な選評をおこなっているのがわかります。だめなものは、なぜだめなのかの根拠を示しながら、「わたしはこの詩を評価しない」と言っているのです。「いいかわるいか」は、「うまい/へた」とはまた別の基準かもしれませんが、僕たちが議論する際の参照軸になってくれるかもしれません。
絵については、ハンセン病療養所でどのような活動があったのか知りませんが、まずはなんの前知識もないまま、この絵画展を見に行きたいと思っています。
いまひとつのお知らせは、書き上げたばかりの拙稿「スモーキン・ウィズ・ザ・スパイク・リー・ジョインツ――過去と同時代を串刺しにする」(『ユリイカ』2019年5月号所収)です。
http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3296
スパイク・リーの映画『ブラック・クランズマンBlacKkKlansman』(2018年公開)のアカデミー賞脚色賞受賞を受けて組まれた特集です。拙稿のなかでは、『ドゥ・ザ・ライト・シング』や『マルコムX』『ゲット・オン・ザ・バス』『バンブーズルド』といったリー監督の他の映画との関連をスケッチしましたが、『ブラック・クランズマン』と同年公開の『ビールストリートの恋人たち』(バリー・ジェンキンス監督)や、『グリーンブック』(ピーター・ファレリー監督)などとあわせて観るのも面白いと思います。
スパイク・リーの映画は、歴史を題材にしたものでも、同時代への想いが強く反映されているように思います。拙稿を同送いたしますので、ご笑覧いただければと思います。やはり、僕たちの議論の参照軸になればとの思いからです。
中村寛 拝
2019年5月8日
Profile
 1961年東京都生まれ。北海道教育大学卒業後、信州大学で教育社会学・言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。1994年、『WIRED』日本版創刊にあたりアートディレクターに就任。1998年、アジール・デザイン(現アジール)設立。その後、数多くの雑誌、広告、書籍等を手掛ける。2003~2010年「CENTRAL EAST TOKYO」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。現在は美学校講師、多摩美術大学教授を務める。画集に『秘境の東京、そこで生えている』(東京キララ社)、著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)、『無くならない――アートとデザインの間』(晶文社)などがある。 web
1961年東京都生まれ。北海道教育大学卒業後、信州大学で教育社会学・言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。1994年、『WIRED』日本版創刊にあたりアートディレクターに就任。1998年、アジール・デザイン(現アジール)設立。その後、数多くの雑誌、広告、書籍等を手掛ける。2003~2010年「CENTRAL EAST TOKYO」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。現在は美学校講師、多摩美術大学教授を務める。画集に『秘境の東京、そこで生えている』(東京キララ社)、著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)、『無くならない――アートとデザインの間』(晶文社)などがある。 web

文化人類学者/多摩美術大学准教授/人間学工房代表。一橋大学大学院社会学研究科地球社会研究専攻博士課程修了・博士(社会学)取得。専門領域は文化人類学。アメリカおよび日本を当面のフィールドとして、「周縁」における暴力や社会的痛苦とそれに向き合う文化表現、差別と同化のメカニズム、象徴暴力や権力の問題と非暴力コミュニケーションやメディエーションなどの反暴力の試みのあり方、といったテーマに取り組む。その一方で、《人間学工房》を通じて、さまざまなつくり手たちと文化運動を展開する。著書に『残響のハーレム――ストリートに生きるムスリムたちの声』(共和国、2015年)、編著に『芸術の授業――Behind Creativity』(弘文堂、2016年)、訳書に『アップタウン・キッズ――ニューヨーク・ハーレムの公営団地とストリート文化』(大月書店、2010年)がある。『世界』(岩波書店)の2017年10月号から、連載「〈周縁〉の『小さなアメリカ』」がスタートした。 web

