お盆休みに大阪の実家に帰省したとき、70代の父親に参院選はどこに投票したのか、なんとなく聞いてみた。投票先を聞き出すのはあまりよくないのかもしれないが、いっときの勢いを失ったとはいえ、いまだ維新の会が強い大阪の情勢を少しでも知りたいと思ったからだった。普段から保守的な言動が多い父の口から出たのは、意外にも、革新系の候補者の名前だった。私が少し驚いてその理由を尋ねると、「自分の母親(つまり私の祖母)と同じ名前の候補がいたので、親近感が湧いて投票した」ということだった。そういえば、数年前の選挙では、ある宗教団体系の候補者に「男前で頼もしそうやから、投票した」と言っていたなあ……。
前回の連載では、ひとびとの知識がコミュニティに依存していること、そのために実際以上に自分は「知っている」と錯覚しやすいこと、そして、選挙で正しい選択をするには、十分な政治的な知識を持っていないことを指摘した。しかし、逆に言うと、ひとびとの知識が集団に依存している、コミュニティで共有されているからこそ、あらゆる政党はコミュニティそのものの掌握を目指してきた、といえる。つまり、家族、地域、職場、学校、労働組合、サークル、宗教などの集団を押さえることで、ひとびとを政治的に組織してきたわけである。しかし、政党の組織力の低下がしばしば指摘されるように、近年コミュニティは衰退するいっぽうだ。市民社会で勢力を拡大し、議会の多数派となり、最終的には政権を掌握するという「陣地戦」(グラムシ)は、むかし以上に困難となっている。
アレクサンダー・トドロフ『第一印象の科学』では、候補者のルックスが選挙結果に大きな影響を与えることが指摘されている。トドロフによれば、候補者の顔だけでその選挙結果を七割ほど予測することが可能であるという。「より有能に見える政治家の方が、選挙に勝つ公算が高い」[1]とされるそうだ。そして、その影響を最も受けやすいのが無党派層である。
現実の投票者たちに基づいて調査を行った結果、候補者の見かけは、政治について何も知らない投票者たちだけに影響を与えることを発見したのである。いつもテレビにへばりついているような投票者については、この影響がさらに強く表れた。言い換えれば、見かけが最大の影響力を持つのは、政治に無知なカウチポテト〔寝椅子(カウチ)に横たわってポテトチップスを食べながらテレビやビデオを見て過ごす人〕に限る、ということだ。そうした人たちのいくらかは、浮動投票者や無党派層だ[2]。
また、候補者のルックスが大きく影響する選挙として、「投票者の知識不足、さして重要ではない選挙、候補者が三人以上いる場合に情報を得るのが大変な場合、そして党よりも候補者中心の選挙の場合」[3]が挙げられている。つまり、十分な政治的な知識を持たず、コミュニティとの結びつきが薄いひとは、候補者の見かけで判断しやすいというわけだ。私の父と同じように。
もちろん、「有能」そうな顔を持つひとがそのまま「有能」であるわけではない。トドロフが注意をうながすように、顔から人となりを判断する「観相学」にはなんら科学的根拠はない。外見と中身は一致しないのだ。しかし、ひとびとが、見知らぬ他人にたいしてわずかな情報から「第一印象」を形成し、不確かなステレオタイプをもとにして、その他人の能力や性質を誤って判断してしまうことは、まぎれもない事実なのである。
ダニエル・カーネマン『ファースト&スロー』が援用されるように、トドロフもまた、人間の思考には、「自動的で努力を要しない処理」(システム1)と、「意図的で統制的な処理」(システム2)という二つのモードがあるとする「二重過程理論」に依っている。つまり、「顔の印象を形成すること」は「自動的処理の一例」[4]なのである。そして、「見知らぬ人について判断を下すこと」において「最も簡単でやりやすい近道が第一印象」なのであり、「見識のない投票者はこの近道に飛びつく」のである[5]。もちろん、その近道は間違いだらけだ。
ただし注意が必要なのは、政治家のルックスにおいて重要なポイントは、以前流行した「美しすぎる◯◯」というように、「イケメン」や「美人」といった「ルッキズム」とかならずしも一致しない、ということだ。たしかに、政治家の「見かけ」において「有能さ」は大きな役割を果たすが、ほかの要素はそのときの政治状況によって変わるのだという。たとえば、戦争といった危機が迫るときは「支配的」「男性的」な顔が選ばれやすく、平和な時代には「知的」「寛容」な顔が重視される[6]。また、政治性によっても違いが出る。保守派は「支配的」で「男性的」な顔が選び、リベラル派は「非支配的」で「女性的」な顔を選ぶ傾向がある[7]。
ここで思い浮かぶのが、保守系雑誌の誌面である。かつて論壇時評を担当していたのでその手の雑誌を集中的に読む機会があったのだが、リベラル・左派系雑誌にくらべ、保守系雑誌は顔がとても多いのである。もちろん、リベラル・左派系雑誌もインタビューや対談などでは顔写真を掲載するが、保守系雑誌はちょっとしたエッセイにももれなく論者の顔がついてくるのである。書店で立ち読みしてもらえればわかると思うが、目次のページから、顔、顔、顔、なのである。
しばしば保守系雑誌は「エビデンス」のなさを指摘され、「フェイクニュース」の温床として批判されている。たしかに掲載される記事も、感情的なあまり、論理的に支離滅裂であることが多い。しかし、トドロフの指摘からいえるのは、顔写真をやたら掲載する保守系雑誌は、読者の「第一印象」を重視する誌面をつくっている、ということである。つまり、読者の「意図的で統制的な処理」(システム2)ではなく、「自動的処理」(システム1)に訴えることを目的にしていて、たとえ記事に論理的に難があったとしても、なんら問題ない、というわけである。たとえば、小説家の百田尚樹が保守派にあれほどの人気を集めるのは、百田の「支配的」で「男性的」な「見かけ」――いかついスキンヘッド、太くて濃いまゆげ、ずんぐりとした大きな鼻――にも原因があるのではないか。コミュニティが弱体化し無党派層が増えるなかで、選挙で勝つことを目指すとすれば、候補者の顔がより重要な要素となるのは間違いない。しかし、それははたして政治なのだろうか。
とはいえ、あらためて考えてみると、不確かなステレオタイプをもとにして他人を判断してしまうことなど、わかりきったことではないか。認知科学は、わずかな労力や時間でおおよその解を得る直観的判断が、ある条件下では一定の間違いをもたらす偏りを持つことを示してきた(ヒューリスティクスとバイアス)。つまり、合理的な選択から逸脱するような意思決定を実証的にあきらかにした。「現状維持バイアス」「確証バイアス」「楽観バイアス」などさまざまな「認知バイアス」が指摘されているが、しかし、これらのバイアスは歴史的にも経験的にも知られたものではないのか。たとえば、「ひとは見かけによらぬもの」ということわざがすでにあるように。
近代的な市民は自律的な個人を前提とし、そのような個人は合理的な選択をおこなうとされる。しかし、西洋にくらべて日本は遅れており、自律的な個人がほぼ存在せず、そのような個人によって形成される市民社会は成立していない。というのが、講座派マルクス主義や、その影響下にあった思想家たちの主張であった。日本には市民社会が成立する以前の封建制が残っていると彼らはみなした。たとえば、「日本には人権意識が根付いていない」といった人権後進国論や、「日本は西洋と異なる特殊な国である」といった日本特殊論も、もとを辿ればここにいきつく。しかし、もし、講座派マルクス主義の影響下にあった思想家が、市民という合理的なモデルから逸脱する意思決定を「封建制」という言葉で示したのだとしたら、どうだろうか? だとすれば、日本の思想家の仕事もちがった角度から読み直せるかもしれない。
ここでは吉本隆明を取り上げてみよう。吉本は「転向論」(1958)において中野重治の小説『村の家』を高く評価したが、「中野重治」(1960)では否定的な評価を与えている。吉本によれば、中野の詩や小説では「ぞっとする」といった快・不快の表現がよく見られるが、その感覚は「生活の事実に強いられて生きて来た生活者の意識にねざしている」[8]。このような「短絡する感覚的な論理」[9]は、中野重治の「うごかしえない美質」[10]でもあるいっぽうで、その限界でもある。「中野が、感覚的な現実把握に固執し、それをねじくりまわす文学的な作業をつづけるうちに、資質上の根である下層的な生活人を失って、もはや、文学的な作業をとどめるすべを失った」[11]からである。吉本が中野を「美意識上の常民」と呼んでいることに注意しよう。「常民」は柳田民俗学のタームだが、ここでは日本における市民社会以前の封建制を示す言葉として用いられている。くわえて、吉本は、「文学者、芸術家は、生活人であることをやめたとき、感覚的な現実把握を、論理的把握まで昇華させ、いわば方法的な体系のうえにたたないかぎり、時代の動向に耐ええない」[12]と述べている。
前回指摘したように、道徳的判断は「快・不快」といった直観的・情動的な判断に導かれるもので、「自動的処理の一例」(システム1)である[13]。ここでいわれる「感覚的な現実把握」と「論理的把握」は、吉本の対立図式「大衆」=「生活者」と「知識人」そのままであることはみやすい。そして、「大衆」=「生活者」と「知識人」の対立図式は、システム1=直観的な判断をおこなう非言語的・自動的な認知システムと、システム2=言語的・合理的な判断をおこなう認知システムと読みかえられる。つまり、吉本隆明が中野重治に指摘した「美質」とは、ヒューリスティクスに基づいた「生活者の意識」を体現するところだった。吉本において「大衆」=「生活者」と「知識人」のどちらを重視するかは、時代によって変化する。だいたい、1960年代以前は「知識人が大衆から「自立」せよ」と説かれるが、それ以後は「知識人は「大衆の原象」を求めなければならない」と言われるようになる。とすれば、吉本は「生活者の意識」=システム1を偏重する思想家だったといえる。同様の読み替えは、政治学者の丸山眞男においても可能だろう。たとえば、システム1に該当するのが「つぎつぎになりゆくいきほひ」という「古層」であり、市民社会の成立を目指した丸山はシステム2を偏重する思想家だった、というふうに[14]。であれば、日本特殊論から市民社会論自体を捉え直す、読み直すことができるのではないだろうか。
[1] アレクサンダー・トドロフ『第一印象の科学――なぜヒトは顔に惑わされてしまうのか?』作田由衣子監修、中里京子訳、みすず書房、2019年、p.1
[2] トドロフ、前掲書、p.70、〔〕内は引用者による補足
[3] トドロフ、前掲書、p.76
[4] トドロフ、前掲書、p.75
[5] トドロフ、前掲書、p.70-71
[6] トドロフ、前掲書、p.77
[7] トドロフ、前掲書、p.78
[8] 吉本隆明「中野重治」『吉本隆明全著作集7』勁草書房、1968年、p.330
[9] 吉本、前掲書、p.334
[10] 吉本、前掲書、p.335
[11] 吉本、前掲書、p.336
[12] 吉本、前掲書、p.336
[13] ジョナサン・ハイト『社会はなぜ左と右にわかれるのか――対立を超えるための道徳心理学』高橋洋訳、紀伊國屋書店、2014年
[14] 今回の論考は、與那覇潤氏との私的なやりとりに依るところが多い。氏には記して感謝する。
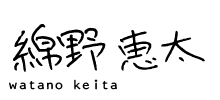 批評家。1988年生まれ。元出版社勤務。詩と批評『子午線』同人。論考に「谷川雁の原子力」(『現代詩手帖』2014年8-10月)「原子力の神―吉本隆明の宮沢賢治」(『メタポゾン』11)など。その他、『週刊読書人』や『現代ビジネス』などに寄稿。新刊『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社)が発売中。twitter
批評家。1988年生まれ。元出版社勤務。詩と批評『子午線』同人。論考に「谷川雁の原子力」(『現代詩手帖』2014年8-10月)「原子力の神―吉本隆明の宮沢賢治」(『メタポゾン』11)など。その他、『週刊読書人』や『現代ビジネス』などに寄稿。新刊『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社)が発売中。twitter

