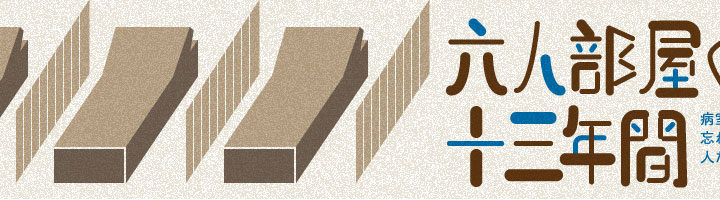「特別な人生には、ちがいないだろう」
「たしかにね、俺たち、普通の人生じゃないな、
と思うこともありますよ」
(『男たちの旅路 山田太一セレクション』里山社)
人生に空白期間ありますか?
人生に十三年間の空白がある。
私はずっとそう思っていた。
二十歳で難病になって、十三年間、闘病生活を送った。
病院に入院しているか、自宅で療養しているか、いずれにしろずっと部屋の中だった。
普通、二十代から三十代前半というのは、社会に出て働き、社会人としてのさまざまな常識やマナーやノウハウなどを身につける時期だろう。
同僚や先輩や上司、取引先の人、そして後輩など、様々な人間関係を経験する時期でもあるだろう。
また恋愛したり、失恋したり、ケンカをしたり、そういう恋愛ドラマが展開される時期でもあるだろう。
人生の中でも最も出来事が多く、成長したり、挫折したり、壁を超えたりする時期だろう。
そういったことが私にはまったくなかった。
だから、その十三年間を空白と感じていた。
社会に出てから年齢を問われたとき、実際の年齢をそのままに言うのが嫌だった。そこから十三年を引いてほしいと思った。
もちろん、その十三年間には、闘病ということはぎっちり詰まっている。しかし、それは通常の二十代から三十代の充実とは、まるで違うものだ。どこまでも個人的な体験だし、「つらい」の一言ですべてが表せるし、逆に語り出せば愚痴が尽きないようなものだ。だから、人生の年数としてカウントしたくはなかった。
六人部屋での人生見聞
しかし、最近になって、自分の病気について語る機会があり、問われるままに、入院中に見聞きした話などをすると、「へー、その話、面白いですねえ」などと言われることがある。
こんな話が面白いのかと、こちらはむしろびっくりする。
しかし考えてみると、病院の六人部屋で長期間過ごすというようなことは、通常の人には経験がない。刑務所暮らしの体験談が、当人には忘れたいようなことであっても他人には面白いように、病院の六人部屋の話にもそういうところがあるのかもしれない。
六人部屋での人間関係というのはかなり特殊だ。いろんな年代の人がいた。普通なら上下関係になるところだが、同じ「病人」というある種の平等な関係がある。
また、病気の重さによる序列というのもある。入院期間の長さによる序列というのもある。私のように難病で入院期間が長いと、会社ではかなり偉い五十代のおじさんでも、病院の六人部屋ではなんとなく下手に出たりする。まあ、そういうところも、昔の牢屋のようだ。
重い病人同士だと、言葉はあまりよくないが、ある種「戦友」のような、年齢や性格の一致不一致を超えた、強いつながりも生じる。
また、病室というのは特殊な場所で、当人のこれまでの病気から、親族の病歴から、いろんなことをベッドで看護師さんから聞かれ、それは他のみんなの耳にも入ってしまう。
そして、ベッドから動けない病人の場合、家族の込み入った相談や、お金の困ったことや、介護や子育ての問題にいたるまで、ベッドのところで家族と相談するしかなく、それもまた他の五人の耳に入る。
そしてほとんどの家族は病室でケンカをする。
ケンカは突発的に起きるから、ベッドを離れて面会室に行ける病人でも、六人部屋でもケンカをしてしまうことがあり、怒って出てくる言葉の中には、家族の秘密もたっぷり含まれている。
いろんな年代のいろんな家族の内実を、見聞きするつもりはなくても、たくさん見聞きしてきた。
これはかなり特殊な体験なのかもしれない。
ないと言えばない、あると言えばある
私は十三年間を完全な空白のように思っていたが、他の人が二十代、三十代に経験するようなことをまったく経験していないかわりに、そういう特殊な経験をたっぷりしてきたのかもしれない。
そのことに改めて気づいたのは、宮古島に移住して、島にやってくる観光客たちの感想を聞いたときだ。
観光客たちの感想は、大きく二つに分かれる。
「何もない島ね」という人たちと、「なんていろんなものがあるんだろう」という人たちがいる。
じつは観光客だけでなく、島の人たちにも、この両者がいる。
これはどちらも正しくて、何を求めて何に目を向けるかというちがいだ。都会にあるような娯楽施設などを求めれば、どこにも見当たらなくて、「何もない」ということになる。
しかし、都会にはない海や空や木々などを求めれば、「いろいろあって、とても豊か」ということになる。
私も自分の人生に何もないと思っていたが、そして今でもそう思っているが、一方で、見方を変えれば、興味深い体験をしているのかもしれない。
私の話ではなく、私が出会った人たちの話
というわけで、六人部屋で十三年間に経験したことを、ここで、思い出すままに書いてみたいと思う。
それが本当に興味深いかどうかは、私にはよくわからないので、読んでくださった方々にご判断いただくしかない。
なお、自分の病気のことについては『食べることと出すこと』(医学書院)に書いたので、ここでは自分のことではなく、六人部屋で出会った他の患者さんたちのことを書いてみたいと思う。(自分のことも少しは書くことになるかと思うが)
ここで書くのはすべて私が実際に体験したことだ。
ただし、個人が特定されてはいけないので、名前は変え、病名も変える場合があるかもしれない。(私は病名を書くのがあまり好きではないので、そもそもあまり書かないとは思うが)
ただ、書かれた当人はそれでも自分のことだとわかるだろうから、久しぶりに私に連絡を取ってくれれば、懐かしくて嬉しい。
それでは、病室という、ある種、非日常な空間で、人がどんな本音を垣間見せるのか、人生がどんな別の顔を見せるのか、家族がどんなふうに激震に耐えるのか、その悲喜こもごもを、思い出せる限り書いていこうと思う。
おつきあいいただけたら、嬉しいです。
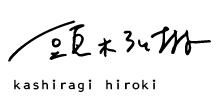 文学紹介者。筑波大学卒業。大学3年の20歳のときに潰瘍性大腸炎を患い、13年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いとなった経験から、『絶望名人カフカの人生論』(新潮文庫)を出版。その後、『カフカはなぜ自殺しなかったのか?』(春秋社)、『NHKラジオ深夜便 絶望名言1・2』(飛鳥新社)、『絶望書店 夢をあきらめた9人が出会った物語』(河出書房新社)、『トラウマ文学館』(ちくま文庫)、『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』(ちくま文庫)、『食べることと出すこと』(医学書院)、『自分疲れ』(創元社)などを刊行。
文学紹介者。筑波大学卒業。大学3年の20歳のときに潰瘍性大腸炎を患い、13年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いとなった経験から、『絶望名人カフカの人生論』(新潮文庫)を出版。その後、『カフカはなぜ自殺しなかったのか?』(春秋社)、『NHKラジオ深夜便 絶望名言1・2』(飛鳥新社)、『絶望書店 夢をあきらめた9人が出会った物語』(河出書房新社)、『トラウマ文学館』(ちくま文庫)、『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』(ちくま文庫)、『食べることと出すこと』(医学書院)、『自分疲れ』(創元社)などを刊行。