佐藤直樹さんは2013年3月、荻窪6次元で初の個展「秘境の荻窪」を開いた。中学2年生のときに1年間住んだことのある荻窪を歩きなおし、建物や木々、動物、地形などを木炭で描いたもの。長らくデザインの現場に身をおいてきた佐藤さんだが、それ以降、少しずつ絵を描く機会を増やしてきた。3331コミッションワーク「そこで生えている。」や、Tambourin Gallery Presents 「佐藤直樹と伊藤桂司の反展」では、毎日、会場へ通って、少しずつ絵を描いていって、その過程を披露していた。そのような試みは、純粋に、「絵ってなんだろ?」という疑問から出発している。
「絵画」というと、美術館の中だったり、画商が扱うものだったり、どこかありがたいもの、身近なものではないものに思える。でも本来は、幼児の頃、うら紙やダンボールに○や□や線を描いたり動物らしきものを描いたのも、絵のはじまりかもしれない。個人ではなく人類で考えてみると、ショーヴェの壁画はどのように描かれたものなのか? 人間がもつ根源的な欲求である「何かを描く」という行為とは何かを、自らが「絵画」を描く行為、「絵画」に入門しながら考えてみる、そんな連載である。佐藤さんの実作もお楽しみに。
「絵画作品」はいつから自明なのか
「絵画が運んで来る自由」は「生命」や「死」に関わっているなどと、大きなことを言ってはみましたが、そんな話を文字にしたところでよさげな絵が描けるというものでもありません。そのような認識を体現して(あるいは突き詰めて)いる者が言えば「なるほど」となるでしょうが、そうでない者が同じことを言っても「なんじゃそりゃ」ということにしかなりません。
何にも達しておらず、ただ描きながら考えているだけの者が、達観めいたことを書いたところで、どうにも胡散臭い話になってしまいます。けれども、それでもやはり、見失わないようにしなければならない道標は必要ですし、「入門」しようとしている「絵画」なるものが、結局のところ誰にも定義し切れないとなると、その都度あれこれ迷いながら確かめ確かめ言葉にしてみるほかない気がします。「生命」や「死」というのは要するに最後の最後に残された問題だということです。その確認の上に、少しずつ輪郭を浮かび上がらせるしかありません。
しかしながら、時空を超えた絵画に憧れるあまり、今起こっていることがよくわからないというのでは本末転倒ですから、このあたりから「現在」について考えてみます。正直なところ、「絵画作品」というかたちで昨今発表されている 絵画然とした絵画の中に、私自身が強く心惹かれるものは多くありません。まず「作品」というこの考え方自体が怪しい。怪しいなら怪しいで、怪奇とか怪異とか、怪物とか怪獣とか、怪談とか怪聞とか、そういったところに接触していれば魅かれもするのですが、「作品」と言いさえすれば「作品」ということだと、そこを自明化してしまった瞬間から、大事な部分が蒸発してしまう、生気が失われてしまう、そんなふうに感じられるのです。
それは「生命」ではなく「死」ですらありません。そこから目を背けさせる何か。そこまで言ったら言い過ぎでしょうか。しかし自明なものをただ自明なものとして疑わない態度というのは時に暴力的です。「作品」という概念は明らかに何かを隠蔽しています。美術史を繙けば浮かび上がることが多々ありますが、「自明性そのものを問う作品」(現代美術作品)の登場は必然的な帰結であったとも思います。ただやはりそれでも、私の心を離さずにいるのは、その元のところに存在したであろう「絵画」なるものの方なのです。「生命」や「死」に寄り添いながら「自由」を運んで来てくれる「絵画」をどうしても希求してしまうのです。
経済の方から考えてみる
「絵画」にとっての「現在」を考えるために、もう少し「近代」のことを考えてみます。西洋との関わりの中でしか考えようのない日本の近代は、じつのところまだずっと続いているのだと思います(現在の私たちが「日本」という言葉を使って指すものは「絵画」がそうであるように概ね近代に特有の概念なわけですが)。しかしその「近代」を新鮮なものとして捉える時期はとっくの昔に過ぎ去ってしまいました。そのため鮮度を求めて今はもう近代じゃなくて「現代」だという言い方をしています。そんなふうになってからもうずいぶん経ちます。戦後しばらくは「近代」を問題にしていたと思われますがわりとすぐに「現代」になったんじゃないでしょうか。なので今となっては「現代」だってちっとも新鮮じゃありません。けれども代わるものがないからずっと使っている。経済成長も止まってしまったようなので、いよいよ「現代」も耐用期間を過ぎつつあるのかもしれません。そんな「現在」です。
近代美術と現代美術の違いはいろいろな側面から説明されますけれど、これも経済から見るとわかりやすいと思うのです。近代には近代特有のお金持ちがいて、それ以前のお金持ちとは種類が変わったので、画家や絵描きに求められるものも変わった。ヨーロッパでは王侯貴族のためではなく市民のため、「自由・平等・博愛」なんかを掲げる新興のお金持ち(ブルジョワジー=中産階級)が主な顧客になった。日本もこれに倣いました。現代にも現代特有のお金持ちがいて、もっと違った刺激がほしいと言い出します。もっとぜんぜん異なったものを!誰も見たことのないようなものを!と。「いやそれは作家の方が先に言い始めたことだろう」と思いたい人もたくさんいると思います。それが芸術家なのだと。現代アーティストこそはそのように高度な自由を求める存在であると。そこはとくに否定しません。どっちだっていいのです。結局は同じことなのですから。そのような経済循環の中から生み出されているという意味においては。そこから自由ではないという点では。
そんなわけで、今ではお金持ちの種類も多様化し刺激の種類も多様化しました。複製技術も発達しましたし、発表の仕方もいろいろあります。お金がなければクラウドファンディングだって使えます。そんな時代の「絵を描いてます」「絵画の制作に取り組んでおります」とはいったいどのような営みなのか。そこのところはどうしたって考えざるをえません。より直接的に絵をお金に換えるのか、それとも何らかの方法で生き延びながら絵を描き続けるのか、やり方はいろいろあるでしょう。ただそれに伴って歪んだ精神状態に陥ってしまえば、そこから生み出される「絵画」も酷いものになってしまうに違いありません。そして精神を少しでも健康に働かせるためには「内」と「外」の循環がどうしても必要です。
片山健さんのこと
私の場合、精神の健康を保つにあたって、現代の人の中でもっとも頼りにしてきたのは、絵本作家の片山健さんでした。一九四〇年生まれの片山さんは、二〇代の時に『マッチのとり』(一九六六)という画集を自費出版で出しています。その数年後には福音館書店からも絵本を出していますが、そのまま絵本作家に邁進するのではなく、様々な種類のアルバイトを続けながら、『美しい日々』(一九六九)、『エンゼルアワー』(一九七一)、『迷子の独楽』(一九七八)などの画集を出しています。「食べて行くための絵」ではなく、「絵」が描きたいのだなと思いながらそれらの画集を眺めていました。ゴッホへの憧れを綴った文章を読んだ記憶もあります。絵が絵として成立するためには、そこに注ぎ込まれる強固な世界観が制作者の側に必要なのだなということも、これらの画集を眺めながら感じました。
その精神性は、普通に言われるところの「健康さ」とは違っていたかもしれません。けれども、行き場のない、その年齢ならではの、あるがままの「真実」が定着されているように思ったのです。つまり何もかも「持て余している」のです。「内」と「外」との境界の葛藤です。そして七七年の長男誕生を境に画風ががらりと変わって行きます。『どんどん どんどん』(一九八四)や『いる子ども』(一九八六)に描かれている「赤ん坊」は未知なる侵入者のようでした。そんなふうに描かれた「赤ん坊」を私は初めて見ました。同じ頃に描かれた『犬、猫、魚、その他。』(一九八六)には子どもと共に様々な生き物が登場します。かつては視野に入っていなかった者達が一気に境界を破って現れて来た感じです。長女誕生以降は『コッコさん』のシリーズが次々と生み出されています。そこには、子どもが出会う「初めての世界」が見事に描き出されているのでした。その時々の気分によって感じられる色や空気感の変化などまで。新しく「外」からやって来るものを受け止めるということ、その時に生じる様々な変化を恐れないということ、むしろその驚きのためにこそ私たちは生きているのだということ、そこに揺るぎない確信を与えてくれたのは片山健さんでした。「絵画」にはそこのところをきっちりと浮かび上がらせる力があるということも。鉛筆だったり油彩だったり水彩だったりアクリルだったり、描くべきものによって画材や画法が変わる、その必然も。
長新太さんのこと
世界の激変にさらされた「絵画」を、ただ守ろうとするのではなく、変化させることによって見事に生き延びさせた現代の人として、二〇〇五年に亡くなられた長新太さんの存在も外せません。長さんも片山さん同様、職業的には「絵本作家」としての側面が大きいと思います(「イラストレーター」や「漫画家」や「エッセイスト」の部分も重要ですが)。しかしそこのところはとりあえず置いておくことにします。職業の部分はどんどん変わりますので。長さんがもし今の時代の若者だとしたらどういう職に就いていたでしょうか。やはり絵本作家になっていたでしょうか。イラストレーターを名乗ったでしょうか。漫画家だったりエッセイストだったりもしたのでしょうか。それはわからないことです。それらの職名は後から付いて来たもののように思えます。
あらためて「絵画」に「入門」しようとしている自分にとって、なぜ長さんが気になるのか。書くべきことは限りなくあるのですが、ここではまず色の話からします。長さんの「作品」(あえてそう呼びます)は、ほとんどの場合、印刷物として私たちの元に届きます。絵本の形態が多いわけですけれど、印刷された色がとにかく独特なのです。廉価で普及させることを念頭に置いた通常のカラー印刷なので、シアン・マゼンダ・イエロー・ブラックの4色の掛け合わせで構成されています。その条件は他の皆と同じなのに、長さんにしか出せない色がいつも出ているのです。そしてここがとても大事なところですが、その色でなければ出来上がらない世界が描かれている。ファンタジックと言えば言えますが、たとえば『ちへいせんのみえるところ』(一九七八)の空の色などは、ものすごくリアルに響きます。複製を見ただけで原画を見た気になってしまうことの危うさについては前回にもその前にも書きましたが、絵本作家やイラストレーターは「複製された状態」をこそベストな状態にする仕事と言えます。「原画はもっといいんですけどねぇ」などと言ってはいられません。ですから印刷であれモニター表示であれ、複製の場所で初めて完成する絵というものも登場します。これはもっと言うと、受け手の脳内で完成することを目指した絵であるとも言えます。「描く」行為が完成するのは見ている人間の脳内においてである。長さんの「作品」に接するたびにそのことが思い起こされます。
しかし考えてみれば「絵画」とは元来そういうものであるはずです。長さんの絵は原画も素晴らしく、その前でいつまでも眺めていられる美しさを有しています。原画か複製かのどちらかに重点が置かれているのが普通ですから、これはなかなかに希有なことではないかと思っています。『絵本画家の日記』(一九九〇)には、日曜画家から腐されるような話も出て来ますけれど、ある様式の中にだけ「立派な絵画」の理想像を夢見る人達というのは今もいます。しかし多くの場合それらは旧態依然とした(つまり中途半端に古い)価値観に依拠しながら、自分達の地位を高く見せようとしているに過ぎません。それは「絵」とも「絵画」とも関係のない話です。
どうせ古い考え方をするのであれば「アニミズム」くらいまで遡るべきでしょうが、それは長さんの信奉するところでもありました。もうひとつが「生理的に心地いいもの」。そこには「真面目じゃない部分」「不真面目な部分」も含まれているとも。そしてこんな言葉が残されています。「子どものように、自由に描ければ、こんないいことはない。しかし、そうはいかない。/うまく描こうとか、人さまはどう見るだろうとか、そんなことを思うから厄介だ。/描くときだけ子どもにもどる。そういった術を身につければいいのだが、これは至難のわざだ。「老いて再び稚児になる」ということわざがあるが、これは、もうろくしても子どものようになることである。/一日もはやくもうろくして、本格的な老人となり(すなわち子どもとなり)自由にのびのびとイラストレーションを描こう。心配だからつけくわえるが、ギャラのほうは、子どもの小遣い程度では承服できない。」……なんと希望(とユーモア)に満ちた文章でしょう。
いまいちど門の存在を確かめる
引用した文章は「イラストレーションと私」というお題によるものです。ですから「自由にのびのびとイラストレーションを描こう」となっています。しかしこれは明らかに「絵」や「絵画」のことを思って書いていた文章であると思われます。一九二七年生まれの長さんは一〇代で空襲に合い、終戦後は映画の看板描きの仕事を始めます。確立したジャンルがあってそこで地位を築いたわけではなく、ただ「描く」ことから、すべてを手繰り寄せて行ったと言えます。私(たち)も、もう一度、そこから始めるべきなのです。
この門は何の門なのか。ただ「描くこと」というシンプルな門です。それは人がずーっと昔からやってきたことです。もう一度(そして何度でも)そこに立ち返ることにしましょう。師はいません。けれど門はあります。じつにいろいろな人が通過しています。ただし門の下の道は一本道ではなさそうです。この道とあの道が思わぬところで繋がっています。
 1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。
1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。
twitter / facebook


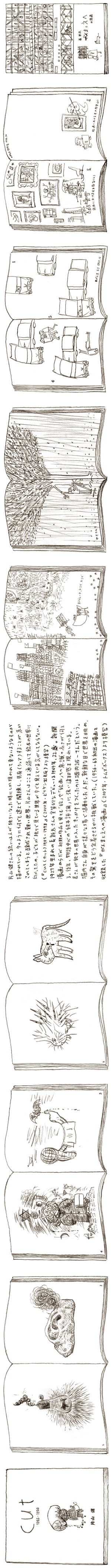
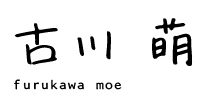 美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。
美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。