内田樹先生と三砂ちづる先生の往復書簡による、旧くてあたらしい子育て論。ともに離婚により、男手で女の子を育てあげた内田先生と、女手で男の子を育てあげた三砂先生。その経験知をふまえた、一見保守的に見えるけれども、実はいまの時代にあわせてアップデートされた、これから男の子・女の子の育て方。あたらしい世代を育てる親たちへのあたたかなエール。
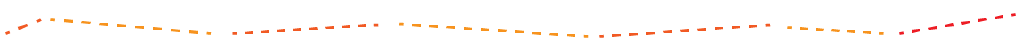
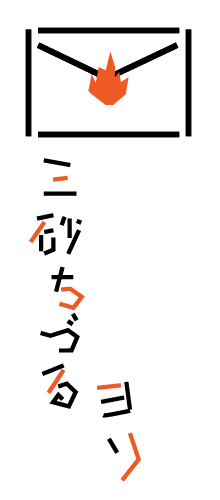
第2便・A
なぜすべてにそう悲観的なのか?
内田先生
お便りありがとうございます。
ご多用な中、往復書簡企画をお受けくださいまして、あらためてお礼申し上げます。便箋を取り出してペンを取っているわけではありませんが、こうして落ち着いてパソコンに向かって内田先生にお便りを書く、ということに喜びを感じます。どうぞよろしくお願いいたします。
お便りっていいですよね。メールもSNSもなかったころ、って、誰かに親しく文章を送る方法は手紙しかありませんでした。それって、2021年の今からさかのぼること、だいたい30年ほど前のことですから、私たちの世代にとっては、ついこのあいだのことですね。30年前にはすでに固定電話は十分に普及していましたから、電話は通じるけど、その頃電話代は結構高かったから延々と話すことなんできなかったし、ファックスはすでにありましたが、ファックスは誰の目に触れるものですから、あんまり個人的なことを書いて出すわけにはいかない。手紙しかなかった。
手紙は、書こう、と思って便箋を取り出して、ペンをとって書き始める、いやいや、これは違う、と思って便箋を破り捨てる、そして書き上げて、読み直して、封筒に入れる。読み直すと送れないだろうから、読み直さないで封筒に入れたこともありますが、とにかく、封筒に入れて封をして、宛名を書いて切手を貼って・・・といろいろな段取りがあり、あんまり感情的なことなんかは、その段取りの途中で思い直したりして、お便りを出すに至らなかったり、なんていうこともあったと思います。そして、その切手を貼った封筒を、ポストまで運んで行って、はい、とポストに入れる。その前に、やっぱり考えましたよね。これ、出していいのか、出したらもう終わりじゃないか、そんな手紙だったらやっぱり、ポストの前でたたずんだり、たたずんだ後、出さずに部屋に戻ったり、なんていうこともあった。
出した後、ああ、やっぱりこれはまずい、本人に読んでほしくない、と思えば、取り返すこともできた。日本郵便はいまもこのサービスをやっていて、そんなに高くない手数料を払うと、一旦出した郵便も、相手側の配送郵便局に近いところに連絡して、手紙を取り返してくれます。実は最近、別に出しちゃいけない手紙ではなかったのですが、単純な間違いに気づいて、このサービスを使ったことがあるのですが、実に手際よく、私の出した書簡が家のポストに戻ってきて、感心したことがあります。ともあれ、手紙って、出した後にでも、取り返すこともできる。すごいですよね。何が言いたいか、というと手紙って感情を言葉にして相手に届けるまでに、「ためらう」時間がいっぱいあったな、ということです。やり直しがきいたし、感情というのは、ためらって、自分の中で醸成して、それから相手に開示していくようなものだった。
電子メールが普及し始め、私自身が使い始めたのは1993年くらいではなかったか、と記憶します。よく覚えているのは、「長男が生まれた時に電子メールを使っていなかった」、「次男が生まれた時にも電子メールを使っていなかった」ことを記憶しているからです。
長男は1990年にブラジルの北東部セアラ州という辺境で生まれました。辺境と言いましても、住んでいた州都のフォルタレザは海岸部に位置する200万都市ではあるのですが、ブラジルの中心、サンパウロ、リオデジャネイロから何千キロも離れたところで、州都を出ると、延々とかわいた内陸部が広がります。
19世紀の終わり、ブラジルが共和国になった直後、宗教的指導者に率いられて2万5000人が最後まで最後まで共和国軍に抵抗したという、カヌードスの乱が起こったのは、この北東ブラジルの内陸部でした。かのマリオ・ヴァルガス・リョサが「世界終末戦争」で題材にしています。このタイトル、スペイン語の原文は”La Guerra del fin del mundo“で、直訳すると「世界の果ての戦争」です。もう、辺境中の辺境の、世界の果て。原文がスペイン語なのは、リョサがペルーの人だからです。ブラジルの人ではない。ブラジルの人ではないリョサが、ブラジルという国の根っこに関わるようなカヌードスの乱について大長編小説を書ける、というところがラテン・アメリカというところの大変興味深いところなんですが、今回のお便りでは深入りしないことにします。
ともあれ長男はブラジルの辺境で生まれました。そのときは、もちろんSkypeもLINEもWhatsAppもなく、国際電話はものすごく高かったから、とにかく日本にひとこと「子どもが生まれた」と電話をするくらいしかできません。もちろん、メールは、なかった。親しい友人でも、わたしに子どもが生まれたことを半年くらい知らなかったんじゃないかと思います。地球の裏から、気楽に、ふっとメッセージを送る手段はありませんでした。
次男は1992年にロンドンで生まれました。こちら、ラテン・アメリカの辺境ではなく、世界のロンドン、です。海外に出かけるたびに入国の際に「Place of birth」すなわち「生地」を書類に記入することが多いですけど、その書類に長男は、あまり知る人もないブラジルの辺境の地を記し、次男は、世界のロンドン、を書くのだよなあ、それってなんらかの影響を人に及ぼすものかしら、と、うらうらと思うようになったのは、だいぶあとのことです。
そのころ私はロンドン大学熱帯衛生医学校という大英博物館の裏の古い建物にある学校で働いていました。当時のイギリス式の産前産後休暇は、産前でも産後でも通算して六週間とれることになっていまして、いつとるか、は、自由に選ぶことができた。二歳になる前の長男がいたこともあり、自分自身が基本的に元気だったこともあり、産後に休みを取りたいと思っていたこともあり、お産をする予定の病院はイギリスの公立ヘルスサービスでは住んでいるところの指定でされることになっていて、私の場合は、職場の目と鼻の先にあるユニヴァーシティ・カレッジの産院、ということもあり、ぎりぎりまで職場で働いていたのです。ほんと、こういうこと、やってはいけません。働きすぎで結構たいへんなお産になり、ユニヴァーシティ・カレッジ産院の先生方に大変お世話になることになってしまいました。日本はお産の前に休暇を取ることが制度化されていますし、妊娠初期からもいろいろな制度を使えますから、妊婦の皆様は早めに産休とってもらいたいものです。
その時のお知らせも、長男のときと同じく、「また男の子、生まれた」と日本に一言電話したことだけ覚えています。
一般にメールが使えるようになることに先んじて、大学などのアカデミック組織でメールが使えるようになり、私が実際に初めて日本の大学に勤める友人にローマ字を使った電子メールを使ったのは、だから、このブラジルとイギリスでの出産の後だったと記憶します。ローマ字を使ったメールを送ったのは、当時すでに日本を離れてだいぶ経っていて、日本語と関係ないところで仕事していた(せざるを得なかった)ため、パソコンは日本製のものではなく、当時の日本製じゃないパソコンでは日本語入力ができなかったからです。そのあとは、あれよあれよという間に電子メールの時代が到来し、いまのSNSの時代へと続くのです。
なんと言っても私は地球の裏におりましたから、一瞬で自分のメッセージが日本に届いている、というのは誠に驚愕すべき事実でありました。でも一瞬で自分が書いたことが、それも結構長文が、相手に届くって、おお、怖い、と思ったことをよく覚えています。
これ、電話じゃない。文章だ。残ってしまうことだ。読み直されてしまうことだ。こんなものができちゃって、壊れなくてもいい人間関係が壊れちゃうだろうなあ・・・。瞬時に感情のやりとりをする方法なんてもともと相手を前にしてしかなかったはずだし、電話が発明されて、声だけでできるようになったとはいえ、まだまだ値段も高いから長電話できなかったし、どっちにせよ、電話の声って残りはしない。こんな長文の文章によるやりとり、しかも手紙のように一対一のパーソナルなやりとり・・・。
悲劇はそこにあらかじめ内包されている、と思っていたところ、職場(ロンドン大学衛生熱帯医学校)では、保健関係の国連組織(といえばどこかわかっちゃうと思いますけど)にエラい人として赴任していたなんとか先生が不倫相手の同僚に送るべきメールを、職場全員allあてに送っちゃった、後で必死の弁明をしていたけど、もう遅かった・・・みたいなことがティータイムの話題になっていたりして、おお、やっぱり恐ろしい、と思いましたが、こういう不倫話題は内田先生、苦手だそうですから、この話はここまでにします。
ともあれ私は電子メールの普及する直前に、父親がブラジル人の男の子二人の母親となりました。安藤さんからいただいた、この往復書簡のお題は「子育て」、しかも「男の子の子育て」でありますから、自分自身を語ることから逃れられないのは覚悟しているところではありますが、いろいろな意味でとても特殊な環境で子どもたちを育ててきたので、あんまり汎用性のある話はできそうにありませんが、お相手くださるのが、内田先生ですから、ゆっくりやっていきたいです。あらためてどうぞよろしくお願いいたします。
お書きくださっていた、「感情教育(éducation sentimetale)」、フランス語ですね。フランス語文脈ではよく使う言葉なのでしょうか。フランスはもちろん特別なところで、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ルーマニア語を話すほかのラテンのみなさまとはちょっと違うと思いはしますが、共通するところも、やはりあると思う。「感情」ということ、感情を表すということ、感情と付き合っていくこと、についてラテンの皆様の人類への貢献はすごく大きいように思います。この上記の男の子二人(もう30と28で男の子じゃないですけど)の父親がイタリア、スペイン、ポルトガルのオリジンを持つブラジル人であったこと、長男のゴッドマザーになってくれた親友がスペイン人女性であったこと、実際にブラジルでブラジルの親戚と深く関わりながら10年ほどブラジルでブラジル人家族として暮らしてきたこと、などから、子どもを育てることにおいて感情を大切にする、感情を育てる、ということをずいぶん学ぶことができたような気がします。
世界の様々な文化や民族は、得意分野があるように思います。それぞれ、人類としての発展のための得意な分野。やっぱりアカデミックな分野はアングロサクソンの皆様の貢献が大きいのは、イギリス、アメリカという国の覇権のみでなく英語という言葉のアカデミックな分野にぴったりの論理性を備えているからだ、と思います。論文、という形のものを書くとき、英語だとごまかしがきかない。日本語で書いているとなんとなく、ちゃんとしたことを書いているように見えても、英語にどうしてもできない、というときは、論理的に書けていない、ということだったりします。これって日本語だからかな、と思っていましたが、少なくともポルトガル語ユーザー、スペイン語ユーザー、フランス語ユーザーから似たようなことを聞きました。ポルトガル語で書いていると、なんだかぐるぐるおんなじこと書いちゃうんだよね、うん、フランス語もなんとなく勢いで書いちゃってるけど、論理的じゃなくなるんだよな、とか。でもこれ、私が医学系の分野で論文を書いてきたからかもしれず、人文科学の分野ではフランス語で書く、というのは特別な意味のあることらしいのは、キラ星のようなフランス思想、哲学のお名前を見てもわかります。内田先生のまさにご専門の世界ですね。
世界のいろいろな人たちの得意分野、の話でした。で、ラテン系の人たちは、というかラテンの言葉で豊かに表すことができることは、「感情」だと思います。感情と人間関係について語ることも好きだし、語る言葉もたくさんあるし、とても洗練された言い回しも多い。外国語を学ぶ、ということは、自分の中のあまり前に出ることがなかった部分が耕されると言いましょうか、言葉を与えられる、と言いましょうか、私自身は、関西弁ネイティブの日本人ですが、10年ブラジルに家族として住んだので、ポルトガル語スピーカーですし、イギリスの大学にも長く勤めたので、発音とかめちゃくちゃですけど、なんとか英語使って生きていくこともできる英語スピーカーでもある。英語を使っている私とポルトガル語を使っている私と日本語を使っている私では、同じ自分ですけど、前に出している部分が違います。ポルトガル語を話している私は、他の言葉を話しているときより、明らかに感情を前に出しています。
ブラジル人家族として暮らしていた頃、「なぜすべてにそう悲観的なのか」と言われたことがあります。「なぜ、悪いことばかり、困ったことが起こったことばかり、考えるのか?悪いことが起こった時は、全力で対処しなければならない。その時はどうせ、全力で対処しなければならないのだから、起こる前にあれこれ悪いことを考えてないで全てうまくいく、と楽観的に考えていた方がいい」としみじみと言われました。これ、よく言われる、日本人は悪いことばかり考えて、今を十二分に楽しめない、という、あれ、です。この悲観的なこと、物事の最悪ばかりを考えてしまうこと・・・しみじみとなんでかな、と考えましたね。そんな悪いことばかりなぜ考えるのか。災害の多い国で育ったからか、備えよ常に、というメンタリティで育ったからか。
しかし、内田先生の「平時から非常時へのモードの切り替えが恐ろしく下手というだけではなく、常日頃から「最悪の事態」を想定して、それに対する備えをしておくということができない」私たち、というのを読んで、あらためて、思いました。私たち、あれこれ悲観的に考えているように見えて、実は考えていないんじゃないのか。むしろ、考えることをシャットアウトしているのではないか。考えないで、起こったらどうしよう、どうしよう、と、ただの取り越し苦労、をしているだけじゃないのか。取り越し苦労のなにがいけないのか、は、今が楽しい、と思えなくなる。今を楽しい、幸せ、と思うと、「そんな幸せでいていいはずがない」になる。ひたすら低い自己肯定感。そういうのって、本当の意味で、「最悪の事態」を想定して、しっかり備えをする、という綿密な作業を妨げるものです。
「感情」とうまく付き合いながら、モードを鮮やかに切り替えつつ、冷静に綿密に現状を読み、備えを積み重ねる。この辺りのマインドセットの基礎は、どのあたりで、どう作られるのか、この辺りは「子育て」と深く関わりますね。
パンデミックのことも書きたかったのですが、長くなりますので、今日はこのくらいにしておきます。
どうかご自愛くださいませ。
三砂ちづる 拝
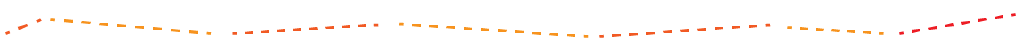
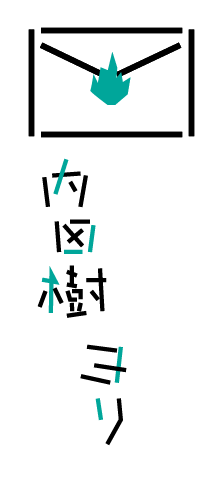
第2便・B
親子関係で決定的に重要なこと
三砂先生
こんにちは。内田樹です。
第二信拝受しました。ありがとうございます。
三砂先生って、ほんとうにすごいですよね。ブラジルとイギリスで子ども産んで、育てるなんて。僕にはとても無理です。
僕は外見とはうらはらにきわめて「安全運転」の人なんです。
もう半世紀も前のことですけど、隣に乗っていた女の人(前の妻です)が僕の運転を見ながらしみじみと「樹ってほんとうにつまらない男ね」と呟いたことがありました。スピード制限守ったり、一時停止で停止したりするくらいのことで「つまらない男」呼ばわりされるのもあんまりじゃないかとは思いますけれど、たしかに僕は同乗していて「わくわくする」ようなドライバーではないんです。冒険心というものが構造的に欠落しているんです。ほんとに。
クロード・レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』は「私は旅と冒険家が嫌いだ。」という一行から始まります。僕も「旅と冒険が苦手」なんです。「ビバ、おれんち」の男で、家から一歩も出ないで一日を過ごすことがまったく苦にならない。ですから、60歳になって、一階に道場、二階に自宅という家を建てて長年の夢を実現しました。書斎で仕事していて、稽古の時間が来たら階段を降りるだけという究極の職住近接です。コロナ禍で家に逼塞させられて息が詰まるという話をあちこちで伺いましたけれど、僕には正直言ってぴんと来ませんでした。「ステイホーム」が僕の場合は日常ですから。
ですから、海外で生活するということが実はものすごく苦手なんです。
若い頃はきっといずれは海外を旅する人生を送るんだろうと漠然と思っていました。「青年は荒野をめざす」がデフォルトの時代でしたからね。シベリア鉄道でヨーロッパに向かったり、長距離バスでインドに向かったりということを周りの人たちは当たり前のようにやってました。僕もその流れに乗って、大学四年生のとき、一夏をフランスで過ごしました。1974年で、『日本列島改造論』のおかげで土木機械を扱っていた父親の会社も急成長して、金回りがよくなった父親がポンとおこずかいをくれて、「これでフランスでも行ってこい」って言ってくれたんですよ。すごいですね。でも、円がまだ弱い時代でしたから、航空券購入だけで半分消えて、一月7万円(当時のレートで1000フランちょっと)で暮らすという超貧乏生活を余儀なくされました。
三か月間フランス各地を旅したので、たしかに見聞はずいぶん広まったんですけれども、最後の1週間は所持金がほぼゼロになり、帰りの飛行機のアエロフロートの機内食のまずいチキンが極上の美味に思えたくらいに痩せこけて帰国しました。
そのせいもあって、なかなか海外に行く気になれず。その次に海外旅行に出かける決意がついたのはその13年後でした(これはレヴィナス先生にどうしてもお会いしたくて、清水の舞台から飛び降りるつもりでフランスに行ったのです)。そのあともフランス人の友人に「一緒に夏休みを過ごそう」と誘われて、娘と二人で2月ほどを南仏とパリで過ごしたことがあり、神戸女学院に行ってからは定期的にフランス語の語学研修のつきそいでブザンソンに行ってました。でも、だいたいいつも憔悴し果てて帰国していました。滞在も後半になると「はやくうちに帰って、冷奴とぬか漬けとカマスの干物に大根おろし添えたのでビール飲みながら小津安二郎の映画を見たい」というようなことばかり妄想していました。
僕は留学生試験を受けたことがないんです。仏文の院生は博士課程になるとほぼ全員が給費留学生試験を受けるんですけど、僕は受けなかった。当時は週に三日ほど予備校や大学で非常勤講師をするほかは終日レヴィナスの翻訳をして、夕方からは自由が丘道場で合気道の稽古をするという「判で捺したような日々」を過ごしていました。僕はその生活に100パーセント満足していたので、その生活から離れたくなかったのです。
神戸女学院大学でも、サバティカルを僕は申請しませんでした。赴任して7年目からは1年間の休暇をとって海外で過ごす資格があったんですけれど、どうしても行く気になれなかった。娘がいるので家を離れられないということもあったし、合気道部の学生たちやゼミの学生を1年間置き去りにはできないということもありましたけど、そんなの理由にならないですよね。実際、同僚たちの中に「娘の弁当を作らなくちゃいけないから」とか「部活の指導があるから」とかいうような理由でサバティカルに行かないという人はいませんでしたから。
僕はほんとうに内向きの人間なんです。散歩をするとか、ドライブをするとか、そういうことさえしたことがないんです。春風に誘われてあてもなく歩き回るとか、ふと思い立って夕日に向かってバイクを走らせるとか、そういうことを一度もしたことがないんです。ほんとうに。用事があるところに向かって、最短時間、最短距離で移動するだけです。用事がなければずっと家にいる。
よく考えると、かなり異常な性格だとは思いますけれど、いまさら治しようもありません。
ですから、三砂先生みたいな生き方には、ほんとうに「ぜんぜん違うなあ」と素直に感心してしまうんです。そういう冒険的な生き方は僕には絶対に真似ができません。なにしろ「冷奴と小津」ですからね。海外で学位をとったり、子育てするなんて、絶対無理です。
なんでこんな話をしているかと言いますと、僕が育児にずいぶん熱心に取り組んだのは、別に「意識が高い」とかいうことではなくて、男にしては異常に内向きな人間だったからではないかと思うんです。旅と冒険が苦手で、うちにいるのが大好きだから、育児が少しも苦にならなかった。
離婚したあとは父子家庭で12年間男手ひとつで子育てをしたわけですけれど、実際にはその前の6年間も、嬉々として育児をしていました。保育園の卒園式の時には「保護者代表」に指名されて、謝辞を述べました。父親が「保護者代表」をしたのは僕が園創立以来はじめてだったそうです。まあ、毎日子どもを送迎して、保育園の行事にはフルエントリーするというような「変な父親」は僕の他にいませんでしたから。
ですから、僕が語る育児についての論には実はぜんぜん一般性がないのではないかと思うのです。世の男親たちが僕の書いたものを読んで「ぜんぜんオレと違う。こいつ変だよ」という印象を持ったとしても、そう思う方が圧倒的多数派で、僕は例外的少数派に過ぎないんだと思います。
僕は小さい頃は女の子とばかり遊んでいました。学校が終わると、クラスの仲よしの女の子たち数人と手を繋いで帰り、誰かのうちに上がり込んで夕方まで遊んでいました。僕が風邪をひいて学校を休んだときに女の子たち5人がお見舞いに来てくれて、父親に「樹には女の子しか友だちがいないのか?」と驚かれたことがありました。
もちろんそんなことはなくて、男の子のともだちもいたんですけれど、僕は6歳のときにリウマチ性の心臓疾患に罹って、心臓の弁膜に異常が残り、外で走り回るタイプの遊びについてはかなり制約がきびしかったのです。だから、どうしても室内で女の子としずかに遊ぶしかなかった。
男の子よりも女の子と仲良しという状態は10歳くらいまで続きました。それが11歳のときに平川克美君と同じクラスになって「男の子の親友」というものができて、それから急に男の子たちと遊ぶ方が楽しくなり、以後「ふつうの男子」になりました。
でも、僕の場合、ジェンダー意識の形成の最初期に刷り込まれたのが「女の子たちと一緒にいるのはほんとうに楽しいなあ」というほんわかした原体験だったんです。その経験が大人になって、人の親になったときに影響しなかったわけはないと思います。
父子家庭で子どもを育てたことについて、「よく、そんなことができたな」という驚きの声は何度も向けられましたけれど、よく考えると、「オレにはとても真似できない」というのは「それができたのは、内田が『変』だからだよ」という暗黙のメッセージも同時に発信していたのかも知れません。でも、僕はそれには気がつかなかった。
まあ、いいんですけどね。人はみんなそれぞれの仕方で「変」なんですから。
ただ、そういう自分のジェンダー的な偏りを勘定に入れておかないと、育児について僕の個人的経験を過度に一般化するリスクがあるかも知れないと思います。そのことを三砂先生に返信を書き始めているうちにふっと思ったのでした。
まとまらない話で済みません。でも、これは別に雑談に逸脱しているわけではなくて、前便で書いたように、「感情」が育児における中核的な問題ではないかという気がするからです。
子育てというのは何か「こうすればうまくゆく」というような万人向けのマニュアルがあるわけではありません(それについては三砂先生も同意してくださると思います)。そうではなくて、ひとりの子どもとひとりの親の間で営まれる感情と感情の「すり合わせ」という一回的な、追試不能な経験ではないかと思うんです。
だから、両者それぞれの感情の熟成度の差とか、感情の肌理の精粗とか、とても言葉にしにくいことが親子関係では決定的に重要になるんじゃないか。なんだか、そんな気がするんです。
すごく言葉にしにくい話なので、そんな面倒な話はふつうはあまりしません。でも、子育てというのは、「とても言葉にしにくいこと」を必死になって言葉に置き換えてゆくのだけれど、どの言葉も「言い足りない」か「言い過ぎ」かであって、言い終わってもぜんぜんすっきりしない…というオープンエンドな営みじゃないかと思うんです。
例えば、子どもは親とのかかわりを通じて母語を習得するわけですけれど、コミュニケーションが開始する時点では、赤ちゃんは母語を知らないわけですよね。「母語を習得しておくと親とのコミュニケーションにも便利だし、将来的な就職にも有利」というようなことを赤ちゃんは考えません。でも、母語運用者である親との「理解できない言語」のやりとりを通じて、赤ちゃんは短期間のうちにすぐれた母語運用者になる。この母語の習得のメカニズムが子育てのいちばん基本にある営みではないかと僕は思うんです。非常にプリミティヴな、「原始スープ」のような赤ちゃんの感情組成が、親の感情との接触を通じて、しだいに分節されて、複雑化してゆく。だから、親の感情的な熟成度が子どもの感情生活形成には決定的な影響をもたらす。母語習得と同じです。響きの良い音韻で赤ちゃんに語りかける親に育てられた子どもは響きの良い母語話者になる。それと同じで、親が豊かな感情の語彙を持っており、自分の感情を抑制したり、解発したり、表情やみぶりや声質で表象する技術に熟達していると、子どもの感情生活もそれだけ奥行きのある、厚みのあるものになる。そういうことってあるんじゃないかと思うんです。
そのメカニズムを解明するためには、まず親の側が自分の感情生活形成の行程を回顧的に分析してみる、ということが必要なのではあるまいか、と。そんなふうに思うんです。
「人間の感情は誰も似たようなものだ」と断定するより、「ひとりひとりの感情の形成過程はかなり違っている(だから、自分の感情生活を十分な吟味抜きに他者に適用してはならない)」ということを前提にしておいた方が、少なくとも親子関係で傷つけ合うリスクはずいぶん回避できるんじゃないかと思うのです。
この往復書簡は「男の子を育てること」という以外には特にテーマを定めないで、なんとなく始まりました。「なんとなく」始まったおかげで、三砂先生と僕が「なんとなく」とっかかりのトピックを選ぶことができた。その無作為な選択を決定づけているのは、おそらく三砂先生と僕のそれぞれの感情生活ではないかという気がするのです。
今日もまとまりのない話でごめんなさい。でも、こうやって「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」的にトピックを転々としているうちに、だんだん核心に迫ってゆくことができるんじゃないかと僕は思っています。ではまた。
内田樹 拝
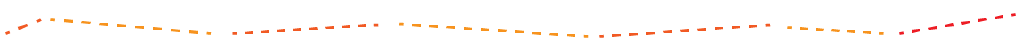
 内田樹(うちだ・たつる)
内田樹(うちだ・たつる)
1950年東京生まれ。凱風館館長。神戸女学院大学文学部教授。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。著書に『「おじさん」的思考』『こんな日本でよかったね』『コモンの再生』『日本習合論』など多数。『私家版・ユダヤ文化論』で第六回小林秀雄賞を、『日本辺境論』で2009年新書大賞を受賞。
三砂ちづる(みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。京都薬科大学卒業。ロンドン大学Ph.D.(疫学)。津田塾大学多文化・国際協力学科教授。著書に『女たちが、なにか、おかしい おせっかい宣言』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『オニババ化する女たち』『死にゆく人のかたわらで』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『少女のための性の話』など多数。

