佐藤直樹さんは2013年3月、荻窪6次元で初の個展「秘境の荻窪」を開いた。中学2年生のときに1年間住んだことのある荻窪を歩きなおし、建物や木々、動物、地形などを木炭で描いたもの。長らくデザインの現場に身をおいてきた佐藤さんだが、それ以降、少しずつ絵を描く機会を増やしてきた。3331コミッションワーク「そこで生えている。」や、Tambourin Gallery Presents 「佐藤直樹と伊藤桂司の反展」では、毎日、会場へ通って、少しずつ絵を描いていって、その過程を披露していた。そのような試みは、純粋に、「絵ってなんだろ?」という疑問から出発している。
「絵画」というと、美術館の中だったり、画商が扱うものだったり、どこかありがたいもの、身近なものではないものに思える。でも本来は、幼児の頃、うら紙やダンボールに○や□や線を描いたり動物らしきものを描いたのも、絵のはじまりかもしれない。個人ではなく人類で考えてみると、ショーヴェの壁画はどのように描かれたものなのか? 人間がもつ根源的な欲求である「何かを描く」という行為とは何かを、自らが「絵画」を描く行為、「絵画」に入門しながら考えてみる、そんな連載である。佐藤さんの実作もお楽しみに。
定義したり区分したりするのではなく
さて、今の時代に「絵画」を考える上で、私にとって決して欠かすことのできない存在である、片山健さん、長新太さんについて書かせていただいた前回でした。「時空を超えた絵画に憧れるあまり、今起こっていることがよくわからない」ということにならないように、「現在」について考えようとして、その営みのところに意識を向けてみたのでした。制度的な「絵画」の世界に加わりたいわけでも、逆にそういったことを問題視したいわけでもありませんので、ただ私が心惹かれてきた現代の作家のありようを見てみたのです。しかし奇しくもそれは「絵画の作家」というより主に絵本という媒体を舞台に表現の活動をしてきた人たちでした。
「絵画の歴史」は様々な観点から書かれていると思いますが、そこに片山健さんや長新太さんが登場しているという話を、私は寡聞にして知りません。他にも、谷内六郎さんであったり、茂田井武さんであったり、私にとって大切な存在はまだまだ挙げられます。が、こうした方々は「絵画の歴史」という文脈だと漏れていたりします。歴史を書く人にとっては扱い難いということなのでしょうか。他に類を見ない絵の描き出され方がなされていることは確かだと思うのですけれども。
がしかし、このような辿り方をしておりますと、自分が過去に感銘を受けたすべての「絵画的体験」について綴らなければならなくなり、入門どころの騒ぎではなくなってしまいます。あれやこれやと振り返りつつ語っているだけで、人生は終了してしまうことでしょう。絵画を巡るあれこれの話を楽しもうということではなく、いや楽しみたいのはやまやまですが、それはそれとして、ここでは入門がしたいのです。
「生命」と「死」の話
そんなわけで、前々回の最後、前回の最初のところに戻ります。「生命」と「死」の話です。「絵画が運んで来る自由」には「生命」と「死」が関わっていると書いたのでした。そこで本日は横尾忠則さんの『死の向こうへ』(一九九八/二〇〇八)に触れてみようと思います。
横尾さんは一九八二年、四十六歳の時にペインティングの個展を開き、画家宣言をしたとされています。それまでは売れっ子のグラフィックデザイナーでありイラストレーターでもあったわけですが、デザインやイラストではどうしても実現できないことがあると考えたのでしょう。いや考えたというより自然とそうなったということだと思います。私のように「入門したい」という欲望に取り憑かれたのではなく、一九八〇年にニューヨークで観たピカソ展の衝撃によるものだったとのことです。ピカソが死んだのは一九七三年なので、まだ生前の記憶が生々しく残っていた時期でもあったでしょう。『死の向こうへ』はそれから二十年近い歳月を経てから書かれた本です。そしてこの歳月こそが非常に重要なものに思えるのです。
横尾さんとの比較で語るのも痴がましい話ですが、私にも四十代で受けた衝撃というものがあります。私にとって決定的だったのは、二〇〇一年に東京国立博物館で行われた菅原道真没後千百年「天神さまの美術」でした。その頃の私もデザインの仕事に没入しており、妻から誘われた際に最初は相当な抵抗を示していたらしいのですが、とにかく無理矢理に連れて行かれ、そこで本当に大きなショックを受けたのです。
何と言ったらいいのでしょう、私はそれまで、現在の様々な創造活動の方が過去のそれよりも先を行っているものだと思っていました。誘われたのに抵抗したというのも没入していたデザインの仕事の勢いが削がれてしまう気がしたのだと思います。しかしその認識の浅薄さに愕然としてしまった。要するに高を括っていたのです。そこに展示されているものは、現在の自分たちには手も足も出ない水準の制作物ばかりでした。技術的な話ではありません。技術に拘泥することへの戒めも含めての話です。ともかく完全に打ちのめされたかたちでした。
そこにあった主題も「生命」と「死」を巡るものだったと、今ではそう思います。何しろ、菅原道真が悲運のうちにこの世を去ってからというもの、天変地異や疫病などの災いが広がり、その霊を慰めるために、これだけの美術品が生み出されるに至ったわけですから。
「作家」という主体を起点にして「さてこの人は何を主題に選んで描いているのでしょうか」と考えることの狭さというか、そういうふうに絵を見ていると読み違えてしまうのではないかということをこの時あらためて思いました。それよりも重要なことは、人にそれをさせている力とは何かを問うことです。この展覧会の素晴らしさは、創作というものの持つ力を大衆的な信仰のかたちとして読み解こうとしていたところにありました。
デザインとの関係
さて、そんなふうに「天神さまの美術」と出会ったものの、それでもしばらくはデザインの領域で少しでも成果を上げようという意識を持っていました。二十世紀から二十一世紀への移行期に生きる自分が「人にそれをさせている力とは何か」を考えようとすれば、デザインこそ天分だろうとも思いました。しかし徐々に、この「成果を上げる」という意識の持ち方自体が駄目なのではないかと考えるようになります。「絵画」に意識が向かうようになってデザインに気が行かなくなってきたといった話ではありません。むしろ逆です。デザインの領域で素晴らしい仕事をしている人はたくさんいますし、自分の仕事もそうであってくれればという願いは以前よりも増していると思います。しかしそれはあくまで日々の営みの結果としてもたらされることであって、合目的的な目標として掲げて何とかなるものではないだろう。そのように意識が変化していったのです。
横尾さんも「画家宣言はしたけれどデザイナー廃業宣言はしていない」ということを確かどこかでおっしゃっています。繰り返し横尾さんと自分を重ねる痴がましさは拭えませんけれども。そして時代は巡ってもう「~家」も「~ナー」も「~屋」も「~スト」も何もなくなっているのではないか。今はとりあえず便宜的に名乗らなくてはならない場面では何かを名乗っておけばいいだろうくらいの気持ちになっています。
明治以降の日本ではデザインのことを、図案とか意匠とか商業美術とか応用美術とか、その都度いろいろな言葉で呼んできました。最近ではより広く、計画的に行うことは何でもデザインと言うようになってきています。かつてデザインの名の下に開拓・開発されてきた先端的なものは一般化し、それが当たり前に組み込まれた複合的なメディアやシステムに、私たちは囲まれています。すべての人のつぶやきが、かつては特別なものだった「活字」(type)のかたちで、瞬時に表現されていきます。今はデザインそのものが根っ子からの変化を求められている時代なのだろうと思います。
加えて書くと、デザインという言葉に置き換えられる前から脈々と受け継がれてきた工芸的な表現の流れも関係していますから、その読み解きがこれからは重要になってくるでしょう。しかしこの話はまた別の機会に譲りたいと思います。何しろ、もともとは、すべてが未分化な、一体的行為だったわけで、「絵画」の話をうんと深くまで掘って行けば、いずれ必ずぶつかる問題です。
そして死の向こうへ
長い前振りになりましたが、『死の向こうへ』についてです。作家には自らを起点にしている部分と外部にある起点に応じようとしている部分があると思うのですが、横尾さんの活動は「自らを起点にしている」性格がことさら強く見えます。画家宣言などはまさにそれで、「外部にある起点に応じようとしている」のがデザインでありイラストレーションであると考えるとある意味わかりやすい。しかし私はそのようには捉えません。「外部にある起点」を、社会的要請のような中間地点にではなく、その先の「死」や「生命」の中に見出した時、いてもたってもいられなくなり、それが画家宣言に結びついたのだと思っています。
私もかつては横尾さんのことを「自らを起点にしている」作家の代表選手のように見ていました。しかし最近出版された『絵画の向こう側・ぼくの内側─未完への旅』(二〇一四)のあとがきにはその認識に関わるとても面白い記述があります。「文の大半は全て自分についての主観的な事柄や考えばかりである。こうしてゲラを読んでいると世間や客観的な事柄についてはほとんど関心を示さず、自己を伝える内容ばかりである。『私は私に最も興味がある』のは、特殊な性格なのかも知れない。絵を描いても主題は『私』、つまり自伝的な内容の絵が多い。」とここまでは今さら言うまでもなくそのとおりなのですが、それに続けて「それが最近急に嫌になってきた」と言うのです。「自分に対する執着、我が強すぎる」と。七十七歳になって言うようなことじゃありません。普通に考えれば。でも自然に出て来た言葉なのでしょう。
横尾さんは「絵画の向こう側」にあるものに呼応しているのだと思います。『死の向こうへ』の中では、「長い旅の一つの節目か分岐点」として「死」が語られています。「死」に対するこのような捉え方は、「絵画」を考えるために、「絵画」を描くために、とても大事なことに思えるのです。天神信仰の時代と違い、現代の生活を送る中で、「死」を「長い旅の一つの節目か分岐点」として捉えながら「絵画」に取り組むのは簡単なことではありません。
横尾さんが初めて「死」を意識したのは二歳の時だったと言います。台風で川が氾濫し濁流が橋を流してしまい、そこにかけられた不安定な仮説の浮き橋の安全を父親が確かめに行った際、不安な気持ちで母親の背中から見ていた。その時に「死」の観念に襲われたのだと。また空襲の時の記憶についても詳しく記しています。「生命」の危機に関わる状況というのは人に覚醒をもたらすものなのでしょう。
「絵画」の「発生」と「発見」
かつてはUFOや超能力方面の発言も多かったためスピリチュアルな人という印象も持たれているかもしれません。あるいは死後の世界への信心が強い人というような。しかし私は逆に考えるのです。つまり横尾さんのそうした興味の示し方の方がむしろ何かから導かれたひとつの現象であり、なぜそのような道筋を辿るようになったのかという問いの方がより重要であると。人生のかなり早い段階で「死という外部」との境界面に接するような体験があったからこそ、その強烈な印象によって、その後はそこから逆照射するように人生を捉えてきたと言えないか。すると脳内では人生の方が夢のように映し出される像にもなるでしょうし、何かを描く場合でも「外部からの命令」によって描かされているような感覚が起こるのではないか。それが「自己」を問うことになっている。ひいては「私」を描き出すことにもなっている。「自由に選んでいる」ということではないのです。
前にも書きましたが、人は物心のつく前から絵を描き始めています。気がついた時にはもう描いているのです。ですからその起点を捕まえられる人はいません。起点は絶対的な過去に存在しています。つまりそこには推論によってしか到達できません。私の場合はリンゴ箱を車両のように塗ったのが最も古い記憶になると書きましたが、よくよく記憶を辿ると他にもいくつか発掘されてきます。そしてそこには確かに「死」に関わる記憶が混じっています。
幼少の頃よく動物の死体を目にしていました。急に交通量が多くなったような場所だったからでしょうか。その記憶はその後も繰り返し様々に姿を変えて夢の中に出てきましたし、また描くものの中に忍び込んでもいました。それは意識が選択したものであるというよりも、どこからか命じられたような行為だった気がします。やはり絵というのは描かされているものなのではないか。近代以降の「絵画」は自発的で創造的な行為として称揚されることが多いわけですが、その無邪気さにはどうしても違和感が残るのです。もちろん様々な抑圧から解放されてきた歴史の過程で発揮された自発や創造の力はあったでしょうし、今もないわけではないでしょうが、それだけでは説明がつかない、まだ誰にも論じられたことのない、真っ暗な闇のような領域が残されています。そのことだけは間違いない気がします。
絵とはまずもってストロークの痕跡であり、ストロークが生そのものであるとすると絵とは一種の死体です。そして「絵画」はつねに事後的に「発見」される他ない。もちろん歴史的にどこかの段階で「発生」したものであることは確かです。しかしそこに立ち会えない以上、どこにその起源を見出すかは「発見」するしかない。人は自らが描くことによって、自分もまた、そこに新たなひとつの「絵画」を「発生」させていると思うかもしれない。しかし多くの場合それは「再生産」や「反復」に過ぎません。
作り手から発せられるベクトルを想定するがゆえに、アーティスティックであるとかクリエイティブであるとかいう観念が生まれます。しかしそんなものよりも、何がどのように通過しているかの方が遥かに重要ではないか。電流のようなものがどこかから流れ込み、それが動力に変換されたところだけを見て、モーターを讃えることにそれほどの意味があるとは思えないのです。入門というのは、電流の存在に気づき、自ら媒介もしくは媒体になることではないか。
浅草寺の雷門や増上寺の芝大門のように、誰の目にもわかりやすく門然として建っていてくれていたらよかったのですが、そのように「絵画」の門は存在していません。しかしそこはもう諦めましょう。なければつくればいい。ということで次回に続きます。
 1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。
1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。
twitter / facebook



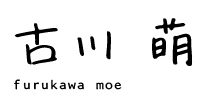 美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。
美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。