真珠夫人、感傷夫人に黄昏夫人……明治以来、数多く発表されてき
作品名:『賢夫人』小栗籌子 1908(明治41)年
『家庭教育 賢夫人』の8年後、明治36年11月24日から『中央新聞』で小林蹴月の連載小説『賢夫人』が始まった。蹴月は多作の流行作家で、新聞記者をした後に小説家、劇作家、俳人となった人物。今回この作品を取り上げるべきか迷ったが(理由は後述)当時の通俗小説のひとつの型としてごく簡単に紹介しよう。
物語は、貧しい男が女の赤ん坊を捨てるところから始まる。そこへ通りかかった裕福な津山周一とその妻お蓮が赤ん坊を連れ帰り、お君と名付けて育てる。ここから話は斜め上に展開する。まず周一がお蓮の妹に手を出す、それを知りお蓮は自殺を図る、赤ん坊の実父がお君を育ててくれたお蓮を自殺に追いやったとして周一と妹を襲う、妹は殺される、周一はアメリカに逃げる、自殺したはずのお蓮は命が助かりお君と暮らす、4年後に周一が現れお蓮に復縁を迫る、が断られて外に飛びだし海に落ちる、漁師に助けられ再び姿を消す、まもなくお蓮は病死、数年後にお君は落ちぶれた周一を発見、暮らし向きに同情して小切手を渡す、その夜のうちに泥棒に小切手を盗まれる、悲観した周一は自殺。……
読者の期待を引っ張る新聞小説らしいジェットコースター的展開で連載は7カ月続いたが、百九十回目にしてこれがまだ前編であることが告げられる。さらに恐ろしいことに賢夫人らしき人物がどこにも見当たらない。著者によると「回を重ねる殆ど二百。而も尚賢夫人の本題に入らざるにも拘わらず茲に一先ず筆を置く」。いったい蹴月はあらかじめきちんとプロットを考えていたのか。そもそも賢夫人が登場する予定はあったのか! 7カ月分の新聞を根性引き(マイクロフィルムのリールを回してひたすら閲覧する行為)させられた身としては、つい詰め寄りたくもなるのである。この小説が連載された明治36年末から翌年半ばといえば日露戦争開戦前後に当たる。与謝野晶子が「君死にたまふこと勿れ」(『明星』明治37年9月号)を発表し、江見水蔭なども新聞各紙に盛んに戦争小説を書いていた時期だ。戦時中だからといって必ずしも戦争をテーマにする必要はないが、とはいえ復縁を迫って断られ外に飛びだして海に落ちて死にかける間抜けな物語を読んでいると、少々頭が痛くなってくる。ともあれ、賢夫人の登場しない賢夫人小説として記憶の片隅にでも留めておくべく、あえて取り上げた次第。
さて、今回の本題、小栗籌子『賢夫人』に移ろう。
雑誌『新潮』明治41年5月号に発表された短編小説である。
籌子の夫は小栗風葉、尾崎紅葉の門下生のなかでも泉鏡花、徳田秋声、柳川春葉と並び四天王と称された明治きっての大人気作家である。風葉の作風は多分に露悪的で、兄妹相姦を描いた『寝白粉』をはじめいくつかの作品は発禁の憂き目に遭っている。酒と女の逸話に事欠かず、自らそれをネタにもしている。
対する籌子は士族の家に生まれ、儒教の薫陶を受けた女性である。高等小学校在学中に国学、漢籍、漢詩を私塾に学び、和歌結社に参加。結婚後に文部省中等教員検定試験を受け、国語漢文の教員をしながら小説、詩、随筆を書いた。「青鞜」賛助員でもある。風葉は籌子の家に婿として入ったが家族と折り合いが悪く、籌子だけが実家で暮らしていた時期もあった。
『賢夫人』は妻が読者に語りかける告白体で書かれている。
小説家の夫は出掛けるとしばしば悪友の作家を連れて帰り、妻である自分に横柄な態度をとる。夫婦だけのときは甘言を弄するくせに友達の前では罵倒する夫に、「其れ程女房を愛するのが恥ずかしいのか!」と腸が煮えくり返るが、我慢しておとなしく従っている。その姿に婆やは同情してしきりに「賢夫人」と誉めそやすが、憐れまれるのも嫌でつい夫をかばってしまう。そのくせ一人になると悔しさに声を忍ばせ泣く妻である。結婚一年目に夫は痛飲が祟って床についた。献身的に介護する妻に今までの態度を反省する夫は、病いが全快して妻が英語科検定試験に合格した暁には盛大にお祝いしようと言う。ここで妻が数年前から教員試験の準備をしていたことが読者に明かされる。床上げの日、近所に赤飯を配り快気祝いの料理を振る舞った妻は、疲れを癒すと言い置き実家に帰る。が、実家から出した手紙には今までの仕打ちへの恨みと、独立を考えていること、二度と夫の元へは戻らない旨が記されていたのだった。
表向き夫に忍従するが強烈な自我を内に秘め自立に向けて着々と準備する、これが当世の「賢夫人」の正体というわけである。
モデルは明らかに小栗夫妻で、会話や手紙の実在は不明だが、籌子が風葉に黙って3年間勉強し、郷里で教員試験を受けたことは事実である。儒教の教えを守り、良妻賢母を旨としていた籌子に、自活の必要性を感じさせ実行させるのが明治30年代後半という時代。これが20年、いや10年前であったなら黙って耐え忍んでいたかもしれない。
風葉の小説『黙従』(隆文館、大正2年)は『賢夫人』の家庭状況を妻側の視点で書いたものだが、新婚の妻を置いて一人で旅行に出掛けた夫が旅先から出した葉書に「此所でもお前の評判が好いよ。原田さん曰く、賢夫人!」としていたり、それを読んだ妻が「夫に放埒させて黙つてゐる意気地無しを、賢夫人だなんて冷やかして嗤つているのだ。こんな物ーー」と破る場面があり、籌子の『賢夫人』発表から5年を経ているものの明らかに呼応していることがわかる。
風葉と籌子、二人が描く夫婦のイメージは、自己中心的なモラハラ夫と怒りを抱えながらも付き従う妻という点で一切ブレがない。それが仮に実像だったとしても、籌子が夫を心から憎み、恥と捉えていたならばわざわざ世間に公表しようとは思わないだろう。なぜなら夫の恥はそのまま夫を選んだ自分の恥にもなる。それは籌子が夫と自分を同一視しているからではない。婿をとった士族の長女の高い自尊心の所以と見るべきだろう。夫婦はお互いにさまざまな思惑を抱きながら「作家小栗風葉とその家庭」を共謀しつつ作品化したのだ。
しかし、籌子の生き方はストイックでなかなかに伝わりにくい。
『青鞜人物事典 110人の群像』(大修館書店、平成13年)の籌子の項には「『作家の奥さん』と言われた賛助員」「(イプセン作『人形の家』の:引用者注)ノラのような『新しい女』を肯定し得なかった籌子の初期作品」とある。確かに「青鞜」メンバーには、夫の浮気から法廷闘争を繰り広げた岩野清子や、5歳年下の「若いつばめ」と事実婚に踏み切った平塚らいてう、後に妻子ある男性と不倫の末に結婚した与謝野晶子など、女性解放や男女同権を(先走りがちではあるが)正面切って実践した者が多い。そんななか夫を助け、支えながらも自己実現する籌子の生き方は「新しい女を肯定し得なかった」と捉えられがちではある。また当時の文壇にしても、籌子の小説は風葉作品の裏側として宣伝され、批評家から「楽屋落小説」と断じられた。なるほど文学作品としては掘り下げ方が足りないきらいはある。しかし、スランプに悩み酒に溺れる夫を、文学に馴染んでいた籌子が筆で助けようと考えたとき、家庭の事情をテーマにすることはある意味自然ではないだろうか。夫に「小笠原式(礼儀作法の流派。形式ばるの意:引用者注)に堅まりやがって」と罵られ、夫の友人には「野暮」と嗤われ、里帰りすれば妾のもとに通う父の愚痴を母から聞かされ、近所の目があるから夫の元に帰れと急かされる「女三界に家なし」を地で行くような現実を、客観し利用し作品化して表現者として立つ。同時に教員としての収入も得る。それが籌子なりのプライドであり、自分を活かす現実的な方法だったのだ。
晩年、夫妻は広大な邸宅を構えて庭園造りに精を出した。数多の危機を乗り越えた二人がペンを置き、仲良く揃って庭いじりを始めたのだ。夫婦とは、他人からは伺い知れないかくも奇妙な関係なのである。
前編で紹介した『家庭小説 賢夫人』は、良妻賢母、家庭教育の気運が高まった明治28年に男性が記した理想の「賢夫人」。13年後の明治41年に女性が書いた『賢夫人』は、日露戦争後に女性の社会進出が広がるなか夫を立てつつ自活の道を切り拓く等身大の(そして皮肉も込めた)「賢夫人」。ふたつを並べてみると隔世の思いがする。
〈おもな参考文献〉
小林蹴月『賢夫人』(『中央新聞』明治36年11月24日~明治37年7月8日 190回連載)
小栗籌子『賢夫人』(『新潮』明治41年5月号)
小栗風葉『黙従』(隆文館、大正2年)
らいてう研究会 編『青鞜人物事典 110人の群像』(大修館書店、平成13年)
大塚楠緒子 著者代表、吉川豊子 責任編集、岩淵宏子、長谷川啓 監修『新編 日本女性文学全集 第3巻』「解説」(六花出版、平成30年)
岡崎ゆき子「小栗風葉夫人」(『林苑』11(2)(113)、昭和32年)
成瀬正勝「岡保生著『評伝 小栗風葉』を読む」(『学苑』(通号381)、昭和46年)
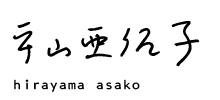 兵庫県生まれ、東京育ち。文筆家、デザイナー、挿話蒐集家。著書『20世紀破天荒セレブ――ありえないほど楽しい女の人生カタログ』(国書刊行会)、『明治大正昭和 不良少女伝――莫蓮女と少女ギャング団』(河出書房新社)、近刊に『戦前尖端語辞典』(左右社)、『問題の女 本荘幽蘭伝』(平凡社)。2022年3月に『明治大正昭和 不良少女伝』がちくま文庫となる。唄のユニット「2525稼業」所属。
兵庫県生まれ、東京育ち。文筆家、デザイナー、挿話蒐集家。著書『20世紀破天荒セレブ――ありえないほど楽しい女の人生カタログ』(国書刊行会)、『明治大正昭和 不良少女伝――莫蓮女と少女ギャング団』(河出書房新社)、近刊に『戦前尖端語辞典』(左右社)、『問題の女 本荘幽蘭伝』(平凡社)。2022年3月に『明治大正昭和 不良少女伝』がちくま文庫となる。唄のユニット「2525稼業」所属。
Twitter

