天気・体・社会。そこに関わる予感と予測の力。農家も流通業者も病気の人も、天気の恵みにあずかりながらも、ときに荒ぶるその流れにいかに沿うか腐心してきた。天気は予測できるのにコントロールできないという点で身体に似ている。どうやったら私たちは、天気とともに暮らし、社会を営むことができるのか。天気・体・社会の三者の関係を考える、天気の身体論/身体の天気論。
西島玲那さんは2020年10月に、13年間一緒に暮らした盲導犬のセラフを看取りました。亡くなるまでの数ヶ月、セラフは度重なるてんかんの発作に襲われます。その発作のきっかけのひとつと考えられていたのが気圧の変化でした。
そんなとき、玲那さんが頻繁に連絡を取り合っていたのが、身体表現性障害のさえさんでした。やはり気圧の変化によってめまいや頭痛の症状が出てしまうことがあるさえさん。不安定な天気の波間に見える、時間も空間も種も超えた交信です。
◎左側はぼーっとさせとく
盲導犬と目の見えないユーザーの関係。まずはそれが、ペットとしての犬と飼い主の関係とはかなり異なっていることを頭に入れておく必要があります。
一般的にペットとしての犬と飼い主は、まさに「飼い主」という言葉に象徴されるように、「主―従」の関係にあります。つまり、飼い主が犬をコントロールし、その行動に責任を持つ、という関係です。もちろんマクロな視点で見れば、「犬のおかげで人生が変わった」「いつも犬の行きたいところを散歩させている」など、犬に主導権があるように見える場合もあるでしょう。しかし、「道の右側に沿って歩く」「小さな子供に飛びかからないようにする」など、ひとつひとつのミクロ行動には、やはり人間の介入が、少なくとも介入の可能性が前提とされています。それが飼い犬の行動のパターンであり、飼い主に対する社会的な要請です。
他方で特別な訓練を受けている盲導犬は、飼い主によってコントロールされる存在ではありません。目の見えないユーザーの目の代わりとなって障害物の存在や道順を教える、というミッションにおいてまずそうですし、個々の行動においても、人間と犬は制御―被制御という主従関係にはありません。
そのことがよく分かるのは、人と犬をつなぐハーネスの使い方です。ペットの犬であれば、ハーネスやリードは、あくまで制御を可能にするツールとして用いられています。犬が行くべきでない方に行こうとしたら、飼い主はすかさずそれを引っ張るでしょう。しかし盲導犬とユーザーの場合、ハーネスは制御のツールではなく、犬の動きや体の向きをユーザーに伝える通信ケーブルとしての役割を持っています。「ん?何かあるぞ」「ここは行っていいの?」犬の動きから、さまざまな情報が伝わってきます。盲導犬に対しては、首につけるリードではなく、胸にかけるハーネスを用いるのも、その方が体全体の様子が分かりやすいからです。
目の見えないユーザー側も、盲導犬からの情報が入りやすくなるような工夫をしています。たとえば、ハーネスはふつうぎゅっと握りません。ハーネスの持ち手は、大きく分けて棒状のバーハンドルタイプと、ベビーカーのようなU字ハンドルタイプがありますが、いずれにしてもハンドルを強く握ってしまうと、あそびが奪われてしまい、犬が動きづらく、情報も入りにくくなってしまうからです。「ぐらぐらしている」くらいがちょうどいいのです。西島さんはU字ハンドルタイプを使っていましたが、ハンドルには「指をかけるだけ」だったと言います。
玲那さんの場合には、さらに自身の体についても、情報が入ってきやくするための工夫をしていました。その工夫とは、「ぼーっとさせておく」こと。セラフに近い左半身は、右半身とは少し違う使い方をしていた、と西島さんは言います。「自分の体の左側は、常にセラフ用に空けてる感じでした。左側は、全体的にすべてにおいてぼやんとさせとく感じ。何かを確認するような意識的な動作は、ほとんど右でやっていました。左手、左足、左側はにぶくさせていて、セラフの「右向いた」「左向いた」「帰りたがってる」というのが「しみてる」感じ」[1]。
「ぼーっとさせておく」とは、セラフを制御しないどころか、予期や目的といったあらゆる能動性を左半身から撤退させることを意味しています。そうすることによって、セラフの体の動きや、動きに現れるセラフの意志が、未加工の状態で西島さんの体に「しみて」くる。究極の遊び状態、もはや「留守」と言っていいような状態としての「ぼーっ」。散漫で注意力が低下しているように見えますが、むしろそうすることで、逆説的にも多くの情報をキャッチできるのです。「しみる」という表現は、玲那さんの体の一部が、セラフの体の延長のようなものとして明け渡されている感覚を表現しています。
この「左半分が自分のものでない」感覚は、セラフが亡くなってからも、しばらく残りつづけていました。「やっぱりまだまだ体の一部がふにゃふにゃ」してる、と年が明けてから西島さんは語っています。「左手はもう三ヶ月くらいはセラフのリードを握っていないはずなのに、リードを使ってセラフと手を繋いでいる自分の手をどこかに忘れてきたみたいに思えます。大袈裟ではなく、まだ自分の左側の、特に足と手は自分のものでなくなったような気がして、白い杖を握る力加減がうまくできてないみたいです。しょっちゅう杖を落としますもん。不便だけど、まだこのまんまの体でいたいですね。今の手が自分のものに思えるようになったら、それはそれでとてもさびしいですから」[2]。
◎天気予報はあまり見ない
一方のさえさんにも、意図的に「ぼーっとさせている」部分があります。さえさんには24時間つづくめまいや吐き気、頭痛の症状があり、その症状の強さは外界からの刺激に影響されます。匂いや音などその場所にある刺激も要因になりますが、天気、特に気圧の変化の影響も大きく受けると言います。影響を受ける要因のうち、天気が占める割合は「ふだんが6−7割、台風が来ると天気がほぼすべてを占めるようになる」[3]というのがさえさんの実感です。頭痛とめまいが特に気圧の影響を受けます。
このような症状を持つ人であれば、毎日の天気の予報に関しても相当に敏感なのではないか、と思われるかもしれません。ニュースやネットでよく情報収集をして、症状が体にあらわれる前に先回りして備えるのではないか、と。しかしながら、さえさんはそうでもありません。意図的に「ぼーっ」としているのです。以前は、気圧の変化をグラフで教えてくれるアプリを使ったこともありました。でも、案外うまくいかなかったと言います。「それが必ずしも当てはまるわけじゃなくて、安全なのにものすごく症状が強く出ることもあることが分かってきた。だからここ数年は、あんまり数値とか天気予報とかを当てにするのはやめて」います。
明らかに具合が悪くなりそうな低気圧がきているのに体調が安定していたり、逆に気圧が変化していないのに激しい頭痛に見舞われたりする。予想にはない気まぐれが天気にはつきものであるように、その体への影響もまた気まぐれです。影響はしていそうだけど、Aが起これば必ずBになる、というわけでもない。そもそも「台風が生まれる前兆」のように通常の予報には現れないレベルの事象が体調に影響を与えている可能性もある。だから天気予報を生活の指針にしてしまうと、あてが外れて「備え損」になったり、備えたことがストレスになってかえって体調をくずしてしまったりするのです。
それゆえ、さえさんは、天気予報は「予測で使うっていうより事後報告的な感じ」で使う、と言います。体調が悪い日があったら、後からニュースを見て、「やっぱりトリプル台風ができていたんだ」と確認する。こうした「答え合わせ」としての天気予報との付き合い方は、第2回で書いた幻肢痛当事者の方々にも通じるものです。天気に関わる病とともに生活するとは、少なくとも現代の科学的な予報の枠組みからははみ出る不確実さとともにあることを意味します。さえさんの「ぼーっ」は、先回りで対処しないことによって、自然の気まぐれに巻き込まれすぎないようにする工夫である、と言うことができます。
興味深いのは、「ぼーっ」とすることによって、つまり予測や構えから体を解放しておくことによって、セラフと西島さんの関係のように、逆説的にもある種の敏感さがうまれていることです。「備えない」というのは、一見すると「なすがまま」になるように思われます。しかし、実際にはそうではありません。むしろ自分の体に起こる予兆的な変化を、敏感に感じとれるようになるのです。さえさんは、台風が発生する前の日に独特の症状がある、と言います。「すごく抽象的で説明するのが難しいんですけど(…)、普段は5とか6ぐらいの吐き気で生活していて、グラフで言うとまっすぐな状態が続いているんですけど、台風が発生する前の日って、断続的にいきなりそのグラフが10までピーンと数秒跳ね上がる、わあ、つらい、泣きそう、みたいな症状が夜なんかに体の中で出るんですよね」。
予測的先回りをしないことによって、かえって未来の予兆をつかむことができる。ここには、天気にとりこまれやすい体ならではの、独特の時間構造があります。「予測」とは、現在までに得られている情報から、「降水確率〇〇%」のように、確率的に未来を推測することです。これに対して「予兆」は、「空が暗くなってきたから雨が降りそう」といった具合に、ある特定の出来事の前触れを現在において感じ取る、ということです。予測が「現在からの未来に対する問いかけ」であるとすれば、予兆においてはむしろ「未来が現在に対して語りかけて」いる。前者は能動的ですが、後者はむしろ「聞く」態度です。さえさんの場合、それをしらせるのは「泣きたくなるような吐き気」でした。
しらせが来たら、さえさんはそれに合わせるようにして生活を調整します。さえさんにとって、気圧によって影響を受けやすいのは、「頭痛とかめまいとか、そういうコントロールできるタイプの症状」です。ただしここで言う「コントロール」とは、症状そのものではなく、症状があった状態でどう生活をするか、という意味でのコントロールのこと。「体そのものはコントロールできないです。でもそれがあった状態でどう生活するかって言うコントロールは、何年もこういう状態が続いてると、だんだんできるようになってくるんです。生活を合わせていく感じっていうのかな。台風が来たときに台風そのものはコントロールできないじゃないですか。でも、来るからそのために備えをして、その間は家で過ごしたりすることはできる」。
台風がコントロールできないように、体もコントロールできない。病気になって7-8年は症状そのものを抑えようとして苦労していましたが、医者に「難治性だから一生付き合っていかなきゃいけないかもね」と言われてから、さえさんは徐々に「つきあうための工夫」を編み出す方向にシフトしていきます。予定がない日は体に委ねるけど、予定がある日は、前日に白湯を飲んだり、お粥を食べたりして、ほかのところに負担をかけないようにしておく。そうすることで、「会って話せるぐらいの体力を残すようにしています」。こうした「計算」をさえさんは常にしているけれども、その実際は「綱渡り」です。突発的な刺激があったらすぐに落ちてしまう。「たまたま落ちないでうまく綱渡りが出来てるけど、やっぱりいつ落ちるか分からないから怖い」と同じ病気の友達とも話す、と言います。
(後編へ続く)
[1] ポットキャスト「セラフとラジオとおしゃべりと」第1回。著者によるインタビュー。
[2] 著者とのラインでのやりとりより。
[3] 著者による、さえさんと西島玲那さんへの合同インタビューより。以下同様。http://asaito.com/research/2021/10/post_82.php
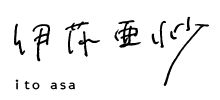 東京大学大学院人文社会系研究科美学芸術学専門分野博士課程修了(文学博士)。専門は美学、現代アート。現在、東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長。リベラルアーツ研究教育院教授。主な著書に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮新書)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、『手の倫理』(講談社選書メチエ)などがある。
東京大学大学院人文社会系研究科美学芸術学専門分野博士課程修了(文学博士)。専門は美学、現代アート。現在、東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長。リベラルアーツ研究教育院教授。主な著書に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮新書)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、『手の倫理』(講談社選書メチエ)などがある。

