ロックとはなんだったのか? 情熱的に語られがちなロックを、冷静に、理性的に、「縁側で渋茶をすするお爺さんのように」語る連作エッセイ。ロックの時代が終わったいま、ロックの正体が明かされる!?
60年代とは、どのような時代だったのだろうか。まずは1963年、ジョン・F・ケネディが暗殺された。リンカーンの死で知られるようにアメリカといえば時として要人の暗殺が起きる印象があるが、20世紀の前半において起きた暗殺事件といえば1901年のウィリアム・マッキンリー大統領暗殺と、ルイジアナ知事を務めたヒューイ・ロングが1935年に暗殺された事件、この2件くらいである。それがケネディ暗殺以降、アメリカはまるで幕末の日本かと思えてしまうほどに暗殺事件が増えるのである。彼の弟ロバート・ケネディがこれまた大統領候補指名選のキャンペーン中に暗殺されるのが68年であるが、65年には急進的な黒人解放運動の活動家であったマルコムXが暗殺される。同じく黒人解放運動の指導者マーティン・ルーサー・キング牧師が68年に暗殺された。69年の12月4日には、ブラックパンサー党の指導者であるフレッド・ハンプトンと党員のマーク・クラークが14人の警官隊に射殺された。この時、ハンプトンは21歳でクラークは22歳だった。ハンプトンは滅茶苦茶に優秀な若者で、ブラックパンサー党に入党するとめきめきと頭角を表し、カリスマ性で支持者を得た。ハンプトンの影響力を危険視したFBIと地元のシカゴ警察が共謀して、自室で眠っているハンプトンとクラークを謀殺したのである。酷いな警察。前にも書いたように、アメリカで歴代大統領の人気投票をすると、リンカーンがオールタイムで1位に選ばれるのである。黒人奴隷を労働力として使役してきた国家であるがゆえに、黒人解放運動が国民のアイデンティティと結びついているのがアメリカという国だ。であるにも関わらず、60年代の後半には黒人解放運動でリーダー的なポジションにあった黒人活動家が続けて暗殺されたわけだ。厄介である。コロナ禍においてBLM運動が起きたのは御存知の通り、リンカーンの時代から黒人解放運動を進めてきたのに、21世紀になってもアメリカの人種問題は根本的なレベルでは解決していないのだ。面倒な話である。そしてベトナム戦争はずっと続いていた。つまり、60年代というのは今よりもずっと暗い時代だったのである。と、書いたところでロシアがウクライナに侵攻を始めてしまったので、どうしようかと思ったわけだがそれでもやはり今よりも当時の方が暗い時代であったと言える。アメリカの大統領はオバマからトランプへ、そしてバイデンへと大きな揺れを見せはしたが3人とも暗殺されてはいない。先に処刑仮説を紹介したが、暗殺というのもヒトならではの行いである。ヒトに最も近いチンパンジーは我々と同じく集団を作って生活する社会的な動物だが、彼らの集団は基本的にアルファオスと呼ばれる、いわゆるボス猿が統治する独裁的な社会である。それに対して、ホモ・サピエンスは20万年くらい前からデフォルトの状態でかなり平等な社会を作って生活していたらしい。WOW。我々はナチュラルに公平でリベラルな動物なのだ。ただし、何故そうなったのかというと、おそらく我々が武器という道具を使うからなのだ。何しろヒトは集団になって道具を使えば巨大な象すら倒す動物である。ヒトの暴力性は素手のチンパンジーとは桁が違うのである。チンパンジーの社会においては、強いボスとタイマン勝負して勝ったオスが新たなボスになる。だから、アルファオスが交代しても社会の形態は変化しない。これからも、この先もずっと小さな独裁社会だ。それに対してヒトは集団で武器を使用することで、どんなに強いオスであっても倒せるのである。眠っている間に石斧で頭を殴れば、はたまた集団で取り囲んで石を投げつければ、どんなに強い個体でも殺せるのである。そして強いオスもそれを知っているから、弱い個体に対して気配りをする。だからヒトの集団においては独裁者による暴力的な統治が起きなかった。これが我々とチンパンジーとの違いである。つまり、兵器による抑止力や集団的自衛権といった、一見は現代的に思える事柄の多くは実は20万年前から存在した、ヒトにとっては普遍的な話なのである。ヒトはチンパンジーと違って際限なく人数の多い集団を作ることでも知られている。これはもちろん、ヒトが住む環境によって大きく左右されるのだが、農耕が始まり定住生活をするようになってくると、集団の数が増えて都市と文明が生まれる。そして、集団の人数があまりにも多くなると、それは原始的な国家となるわけですね。ところで、ヒトの集団はなぜ、どこまでも巨大な規模に膨れ上がるのだろうか? それはおそらく、他の集団と揉め事が起きた際に、大きな集団の方が有利だからである。個人の間で闘争、つまりケンカが行われる場合に、体が大きいほうが有利なのと同様、国家と国家が闘争する際には国家の規模が大きい方が有利なのは明白で、なんだか非常にタイムリーな話をしているような気もするのだけれども、これは農耕と定住が始まった1万年くらい前の時代の話をしているのです。
ヒトはまた分業制を発達させた。巨大な国家は帝国と呼ぶに相応しい存在となり、再びボス猿的なアルファオスが統治する社会を生み出してしまう。そこに、分業制も加わって階層社会が生まれるわけだ。西欧のいわゆる先進国は近代になるまで帝国主義でやってきたわけだが、我々はモラルを発達させる動物なので、近代以降は帝国はあまりよろしくないのではないか? という方針にシフトチェンジしたわけである。なんといっても帝国は格差社会を生み出すし、帝国と帝国が戦争をすると大勢人が死ぬのでよろしくない。大日本帝国が不幸だったのは、それまでずっと鎖国していたのが開国して先進国である西欧を目指し、西欧社会を真似する形で帝国主義をやらかしてしまった点にある。日本が帝国になった時点で、西欧のトレンドは脱帝国主義になりつつあったのである。ロシアの場合、ロシア革命で帝国を倒したのは良かったのだが、その後のスターリンによるソヴィエト連邦は構造的に帝国と全く同じものになってしまった。ロシア革命によって倒された帝国は、農奴たちから搾取していた階級社会である。ソヴィエトは連邦の諸国から搾取した。ヨーロッパの帝国主義は植民地から搾取したわけだが、ソヴィエト連邦は帝国とおおむね同じ構造になってしまった。だから、ソ連が崩壊した後もロシアはアルファオスによる独裁が続いているのである。中国もまた、共産主義になって良かったはずなのに、毛沢東というアルファオスが君臨する帝国になってしまったのは御存知の通り。スターリンも毛沢東も、最初は理想的な社会を作るつもりであったのに、独裁者になってしまったのは何故だろうか? 昔なら、ここで権力は必ず腐敗する、という話になるのだが21世紀においてはもう少し深い説明が必要である。マルク・ファン・フフトとアンジャナ・アフジャの『なぜ、あの人がリーダーなのか?』によると、新たにアルファオスになった猿は、もちろん強いから勝ち抜いてアルファオスになったわけだが、アルファになることで自信を強め、更に強くなって体も大きくなるのだという。そして、悲しいことに下の者たちに対して無理解で高圧的になってしまう。チンパンジーにしろ、ヒトにしろ、集団生活を行う動物においては、自然発生的にリーダー的な存在が生まれるし、リーダーに従う習性も生まれる、わけですよ。なぜかというと、その方が社会のあれこれが滞りなく進むからだ。たとえば、初対面の人間が集まって何かを行う際に、その顔ぶれの中から自然とリーダー的な存在が現れることを我々は子供の頃からよく知っているのではないだろうか。そして、その場で自然とリーダーになるようなヒトはたいてい他のメンバーから好かれやすいことも……。小学校で学級委員に選ばれるような子供は、そういう子供だったのではないだろうか。毛沢東も他人から好かれやすい人だったという。それでも、集団の規模が大きくなると、良からぬ独裁者になってしまうようなのだ。スターリンも毛沢東も、激しい政争を勝ち抜いてトップに立ったヒトなので、それ以前よりも闘争性は大幅にアップしたろう。いわゆる生存者バイアスの、更に激しいやつである。彼らはもう、それ以前の彼らには戻れないのだ。ここで思い出してほしいのは、ヒトという動物は時として暗殺を行うことである。ヒトの集団のリーダーであることは、チンパンジーの集団のリーダーであることよりもリスクが大きいのだ。そのリスクを誰よりも自覚しているのはもちろん独裁者本人である。いつ暗殺されるかもしれない恐怖は、周囲の人たちに対する猜疑心を高めるだろう。そして、そんな猜疑心の塊のような独裁者に対して、周りの人はどのように振る舞うだろうか? 何しろ独裁者に逆らったら粛清されてしまう可能性がある。当然のことながら、クラスメイトと付き合うような態度は取れなくなってしまうわけで、腫れ物を扱うような態度になるのは当然である。独裁者からすると、誰も自分には逆らわないけれども、誰一人信じられる友達はいない、てな状態になってしまう。独裁者は孤独なのだ。大事なことなので繰り返すけれども、ヒトは長い時間をかけて道徳を進化させてきたので、どうやら独裁が良くないことには気がついた。だから、百年、二百年といった単位で帝国主義というのがじわじわと衰退していったわけだが、皮肉なことに理想的な社会を築くために行われたはずのロシア革命、共産主義革命といったものが、帝国そっくりの独裁体制を生んでしまったのである。まるでループもののフィクションのように、何回やり直しても独裁になってしまう、わけである。
その点、元々は植民地であったアメリカは、大統領が暗殺されるような物騒な国家ではあったが、少なくとも独裁者が統治するような仕組みを作らずに済んだようである。ポイントは制度である。制度設計が成功しているか否かである。ロシア革命も壮大な社会実験だったし、アメリカの独立も壮大な社会実験だったのである。そして、ソヴィエト連邦や中国のような国においては、結局は独裁主義になってしまった。これは制度設計が失敗しているのだ。たとえばオバマとトランプでは、かなり違うわけではあるが、どちらも爆撃は行ったわけである。そして、あんなに好戦的に見えるトランプであるが戦争は起こさなかった。そういう意味でアメリカは、今のところは独裁者が現れて暴政を振るうような社会にならないための制度設計が上手く行われていると言えるし、また、平和のための自己家畜化が進んでいるとも言える。しかしながら、ベトナム戦争の時代においては、アメリカが帝国主義を復活させるのではないか? という心配が持たれたのである。その時代の日本の新左翼は、米帝という表現を好んで使ったが、これはアメリカが帝国主義で世界に戦争を起こそうとしているから、それを止めようという趣旨だった。
20世紀の前半において、最も成功した産業の一つに映画があった。19世紀の終わり頃に発明された映画は、短期間で成長しメディア産業の覇者となったのである。だからこそヒトラーたちも映画をプロパガンダに使おうとしたわけだ。サイレント映画時代の大スター、メアリー・ピックフォードとダグラス・フェアバンクスはソ連でも大人気で、この2人が新婚旅行でモスクワを訪れた際には大変な歓迎を受け、ソヴィエトの俳優であり監督でもあったセルゲイ・コマロフによって即興的に『メアリー・ピックフォードの接吻』というコメディが撮影されている。ネットやテレビがまだなかった時代において、映画は最も簡単に国境を超える、最強のメディアであった。しかし、戦前から映画大国であった国のうち、ドイツ、イタリア、そして日本の映画産業は敗戦によるダメージを負う。更に、ドイツを筆頭にヨーロッパの優秀な映画人たちが大量にアメリカに亡命していたので、人材が豊富になったアメリカ映画は戦時中から世界最高のレベルになった。映画の全盛期は1940年代から50年代である。しかしながら、そのハリウッド映画が60年代の後半に大きく変化する。往年の大スターではなく、若手の俳優を起用したアメリカンニューシネマと呼ばれる作品が何本も作られた。これはどういうことかというと、当時のロックを好んで聴くような世代が、成長して映画の造り手になったからだ。『俺たちに明日はない』や『イージー・ライダー』など、ニューシネマの代表とされる作品の多くでは主人公たちが、かなり無惨に死んでゆく。平和を愛するヒッピーたちが幸せに暮らしました、みたいな映画がもう少し残っていても良いと思うのだが、そういう映画はあまりないのだ。紆余曲折のあった恋人たちが、2人で手を取り合って逃げていく『卒業』ですら、最後の場面で主人公は不安そうな顔になる。ベトナム戦争下におけるヒッピーたちの生活を描いたミュージカル『ヘアー』は、1967年にブロードウェイミュージカルで初めてロックを使った作品として人気を得たが、これが映画化されたのは79年で、もうヒッピーの時代ではなかった。やはり、60年代というのは端的に言って暗く夢のない時代であったのだ。だとすれば、ヒッピーたちが起こしたフラワームーブメントと呼ばれる運動は、暗い時代において明るい夢が見たいという当時の若者たちの祈りのようなものだったのだろう。西欧には昔からユートピアの実現を夢見る思想の流れがあったが(その中興の祖はおそらくイエス・キリストである)、ユートピアを実現しようという運動の多くが、時として剣呑で血生臭い結果を呼ぶのに対してフラワームーブメントはあくまで自主参加的であり、ヒッピーたちの多くは本当に平和を愛していた。とはいえ、その牧歌的な夢は長くは続かない、のである。
愛と平和の祭典と呼ばれたウッドストックは69年の8月15日から18日の午前まで行われた。これはヒッピー、フラワームーブメントの貴重な成功体験として記憶されているわけだが、残されたドキュメンタリーフィルムは映画として公開されたから我々も観ることができる。そこに映っている人たちは、季節柄裸になっている人も多く牧歌的に見える。これぞ、良きヒッピーたちの姿である。映画としての『ウッドストック』は平和な野生動物のようなヒッピーを記録しているが故に素晴らしいのである。同じ時代のドキュメンタリーとして『ウッドストック』の前年68年にジャン・リュック・ゴダールがローリング・ストーンズを撮影したドキュメンタリー『ワン・プラス・ワン』があって、こちらも素晴らしく、かつ痛ましい作品になっている。結果的にゴダールは名曲「悪魔を憐れむ歌」が出来上がるプロセスに立ち会ってそれを記録したわけだが、当初はバンドのリーダーでもあったブライアン・ジョーンズがバンドのメンバーから浮いてしまい、脱退に至るプロセスまでも撮影してしまった。この映画の中のジョーンズは、他のメンバーたちからかなり浮いている。それはまるで、猿の集団の中で仲間の猿たちと打ち解けることができなくなった孤独な個体が、その集団から逸れてゆく様子を記録したようにも見える。ドキュメンタリーというのはおそらく、動物としてのヒトを描くところに価値があるのだ。この映画にはゴダールがオリジナルに撮った政治的なコントなどが挿入され、今観るとその部分も時代を反映したドキュメンタリーになっているのが興味深い。ゴダール自身、1967年には商業映画との決別を宣言し、68年のカンヌ映画祭には仲間たちと共に乗り込んで映画祭のボイコットを主張、これがフランスの五月革命につながる。
ブライアン・ジョーンズは翌69年の6月にローリング・ストーンズを脱退。残ったバンドのメンバーたちはミック・テイラーを新たなギタリストとして迎え、ロンドンのハイドパークで彼のお披露目コンサートを計画するが、7月3日にジョーンズが死体で発見され、ハイドパークでの講演は急遽彼の追悼講演となった。この時、警備員をしていたのがヘルズ・エンジェルズである。ところが、同じ69年の12月6日に行われたオルタモントのフリーコンサートでは同じく警備員をしていたヘルズ・エンジェルズによって観客の一人が殺されるという悲劇が起こったのである。初期のローリング・ストーン誌について書かれた『ローリング・ストーン風雲録』によると、この件はミック・ジャガーにかなりの責任がある。ハイドパークが成功裡に終わり、アメリカのウッドストックも素晴らしいイベントだと評価されたので、その流れに乗ってオルタモントが企画されたわけである。ハイドパークでも警備員として雇われていたヘルズ・エンジェルズのギャラは、タンクローリー1台分のビールであったという。いかにも、この時代らしいノリであったが、企画の発端から当日までの日にちが短く会場の変更などもあってトラブルが続出した。会場には当然のごとくドラッグでラリった人たちが詰めかけ、薬物の売買も行われたという。ストーンズのメンバーはヘリコプターで現場に到着したが、ミック・ジャガーは移動中に興奮した観客から殴られた。もう最初からラブ&ピースではなかったのである。興奮する観客と警備のエンジェルズが衝突し、演奏は一旦中断された。エンジェルズの一人にナイフで刺殺されたのは18歳の黒人青年メレディス・ハンターである。エンジェルズの方は彼がピストルを持っていたので正当防衛を主張した。しかし、現場から拳銃は見つかっておらず真相は闇の中だ。この日は暗がりに寝転がっていたところを車に轢かれて死亡した者、警官に追われて用水路に落ち水死した者など合計4人の死者が出た。ウッドストックから、ほんの数ヶ月でヒッピーたちの楽園は終了してしまったのである。この日のセットリストでローリング・ストーンズが最後に演奏したのが「ストリート・ファイティング・マン」というのがまた象徴的ではないか。この曲の背景にあるのは、この時代にあちこちで暴動が起きていたという事実である。60年代に公民権運動、女性解放運動などが盛んになったのは、人類にとっては良き事柄であったが、路上での社会運動は時として暴力に転ずる。やたらと暴動が起きる世情を反映したからこそ「ストリート・ファイティング・マン」という名曲が生まれたわけだが、この曲を聴いて戦意を高揚させてしまった人もいたのではないか。因果な話である。ミック・ジャガー自身も68年のロンドンはアメリカ大使館前で行われた反戦デモに参加していたから、サルトル的なアンガージュマンの気持ちもあって、こういう歌が書かれたわけだが、社会変革への期待と不安、ある種の諦念を描いたような名曲が結果的にストリートで暴力を振るう人たちにまで影響を与えてしまったのだとしたら皮肉である。ミック・ジャガー自身は、ずっと後の90年代のインタビューにおいて「今の時代の世相に合う歌ではない」と述べているが、人気のある曲でもあり現在に至るまで(2021年の公演でも)演奏し続けている。これはどういうことかというと、単にヒット曲だから演奏するというだけではなく、暴力的であった負の歴史を含めた20世紀の記録の一部として、繰り返し演奏されているのだと解釈すべきだろう。オルタモントの悲劇の一因は、ジャガーにもあり、本人がそれを自覚していないわけがないのだ。彼は聡明な人なので80年代に差しかかる頃からドラッグをやめて健康をアピールし、ジョギングしている姿を雑誌に載せるようになる。60年代のロックが反逆であったとすれば、70年代のロックは過剰な放埒である。それが80年代になると、ドラッグやアルコールとは距離をおいて健康的な生活を送るロックスターが現れる。今現在のミック・ジャガーは、コロナ禍においてもワクチン摂取に対するポジティブなメッセージを発している。まるで聖人である。つまり、80年頃からロックスターの道德化という現象が起きるわけだが、これについては後ほど詳しく説明する。実際、ジェームズ・ディーンがいた50年代の半ばから暴力を美的に描いた映画は増えていたわけで、ロックとカウンターカルチャーばかりが社会における暴力の増加を促したわけではないのだが、ロックに暴力的な側面があったことは事実であり消費者の方もそれを好み称賛したのだ。
ウッドストックの1週間ほど前には、女優のシャロン・テートが、チャールズ・マンソンが指導していたヒッピーコミューンのメンバーたちによって惨殺されている。マンソンは、成功しなかったとはいえミュージシャンで、ビーチ・ボーイズのデニス・ウィルソンとも交友があった。ビートルズの狂信的なファンだったマンソンはビートルズの『ホワイト・アルバム』に収められた数曲の歌詞を勝手に解釈して、自分の信者たちにその狂った妄想を吹き込んだ。マンソンは滑り台のことを歌った「ヘルタースケルター」から世界の混沌を読み取り「レヴォリューション」や「レヴォリューションNo.9」からは文字通り暴力革命を起こせというメッセージを読み取った……らしい。ポール・マッカートニーやジョン・レノンにしたら良い迷惑である。マンソン一味の犯行とオルタモントの悲劇はラブ&ピースのフラワームーブメントに文字通りの冷や水をかけたわけだが、カウンターカルチャーはマンソンとは対象的に孤独で、マンソンよりもラディカルな、まるで時限爆弾のような存在を生み出していた。1969年の6月、カリフォルニア大学バークレー校で数学の助教授を勤めていたセオドア・カジンスキーという若者が突然辞職する。バークレーといえばヤン・ウェナーがいたリベラルな空気の学校である。ウェナーがバークレーを中退したのは66年、カジンスキーが25歳で当時最年少だった助教授になったのが翌67年。すれ違いではあるが、同じ空気を吸っていたのは確かだろう。バークレーを去ったカジンスキーは2年ほど両親の元にいたが、71年からモンタナの人里離れた小屋で孤独な生活を送るようになった。おそらく、カジンスキーの時間は69年で止まってしまったのだ。彼は1978年から手製の爆弾を作っては郵送したり、時には自分で目的地まで爆弾を運んだ。ユナボマーである。カジンスキーによる小規模ではあるが凶悪な爆弾テロは彼が逮捕される96年まで続いた。
1970年の9月にはジミ・ヘンドリックスが、10月にはジャニス・ジョプリンが、翌71年の7月にはドアーズのジム・モリスンが、それぞれに先に亡くなったブライアン・ジョーンズと似たような死を遂げる。ロックスターの夭折に関しては、これも後ほど詳しく説明するが、政治的な暗殺に、マンソン・ファミリーの事件、そしてオルタモントの悲劇の後で、1年も経たないうちに歴史の残るレベルの、今でも大きな影響力のあるミュージシャンが次々と死んでいったのである。これだけ暗い時代であったからこそ、まるで小春日和のように明るい出来事であったウッドストックが平和の象徴として語り継がれたのだ。
ヒースとポターの『反逆の神話』でも触れられているが、連続爆発テロの犯人ユナボマーが逮捕されたのは、彼が匿名で当局に連絡を取り、『ニューヨーク・タイムズ』か『ワシントン・ポスト』に自分が書いた文章を掲載すれば、爆破事件を止めると言ったからだ。これに応じて両紙に掲載されたのが通称「ユナボマー・マニフェスト」で、正確なタイトルは「産業社会とその未来」である(ネットにあるので、今ならDeepL翻訳で読めます)。この論文を読んだカジンスキーの弟が、これを書いたのは兄に違いないと思って通報し、ユナボマー事件はようやく終結した。その内容であるが、冒頭から「産業革命とその結果は、人類にとって災害であった」とあるように、現代のテクノロジー社会への批判、そしてコマーシャリズムへの批判である。カジンスキーは、これらに対して革命を起こすと書いている。爆破テロは、彼なりの革命だったのだ。カウンターカルチャーの時代には、シオドア・ローザックの『対抗文化の思想』やチャールズ・A・ライクの『緑色革命』など色んなマニュフェスト的な著作が書かれたが、ユナボマー・カジンスキーのこの論文はそれらのエッセンスを抽出したようなものになっている。ヒースとポターも書いているように、多くの人は爆破テロには賛同できないけれども、カジンスキーが考えていたこと自体はあの時代を生きていた人たちにとっては、ごく自然に共感できる内容だった。何しろ四半世紀も隠遁生活を続けていたので、カジンスキーの頭の中ではカウンターカルチャーの思想が蒸留液のようにクリアに保存されていたのだろう。マニュフェストであるから、当然のごとく熱い文章である。カジンスキーのマニュフェストにおかしいところがあるとすれば、それは即ち当時のカウンターカルチャーが何を間違えていたのかということの手がかりになるのではないか。たとえばカール・マルクスは労働者が資本家に搾取されているのを見たからこそ、経済と搾取の問題を喫緊の課題としてとらえ、ああいう仕事を残したわけだが、カジンスキーの目には工業化された現代社会が喫緊の課題に見えたわけだ。このタイプの人は、よく工業化社会を批判する際に農業を称賛し、自然に還れ的なことを言うわけであるが、そもそも農業と工業は対立する概念ではない。ヒトは、農耕生活を始めたこの1万年ほどの間、ずっと環境に手を加え動植物を品種改良してきたわけである。農業というのは自然を加工する作業であり、その延長線上に工業化社会がある。だから、現在でもモヤシやキノコなどのように工場で生産される野菜はたくさんあるし、これからも増えていくだろう。こういうことは現代を生きる我々にとっては別段難しい話ではないが、60年代後半には公害問題が喫緊の課題であった。ヒトは目の前にある問題に対しては、冷静に考えることができなくなり、適切な判断をし損ねることがしばしばある。「ユナボマー・マニュフェスト」が発表された96年には、公害問題は60年代よりもかなりマシになっていたわけだが、隠遁生活を行っていたカジンスキーにはそれがわからなかった。工業化社会のテクノロジーは確かに様々な問題を生み出したが、テクノロジーによって出現した問題点は、さらなるテクノロジーの発達によって問題解決とまではいかなくても、かなりの問題削減ができる。ここが肝要なのだが、そもそも環境問題というのは有史以前からある。津波であるとかナイル川の氾濫とかですね、こういうものに対してヒトは色んな技術を発達させてきた。灌漑や干拓もテクノロジーによる環境の加工である。そして環境問題にゴールはない。それこそ人類の歴史が終わるまで継続的に続くのである。農業と工業を対立事項だと思ってしまったのは大きな誤謬であり、環境問題にゴール、正しい解決方法がありえるように思ってしまうのも、この時代ならではの誤謬だろう。そして、もう一つ大きな誤謬があったとすれば、それは経済に纏わるものではないだろうか。あの時代の、コマーシャリズム批判、商業主義批判は正しかったのだろうか?
〈参考文献〉
マルク・ファン・フフト、アンジャナ・アフジャ『なぜ、あの人がリーダーなのか?――科学的リーダーシップ論』小坂恵理訳、早川書房、2012
ロバート・ドレイパー『ローリング・ストーン風雲録――アメリカ最高のロック・マガジンと若者文化の軌跡』林田ひめじ訳、早川書房、1994
ジョセフ・ヒース、アンドルー・ポター『反逆の神話〔新版〕――「反体制」はカネになる』栗原百代訳、ハヤカワ文庫NF、2021
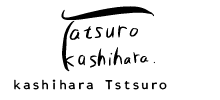 映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
twitter

