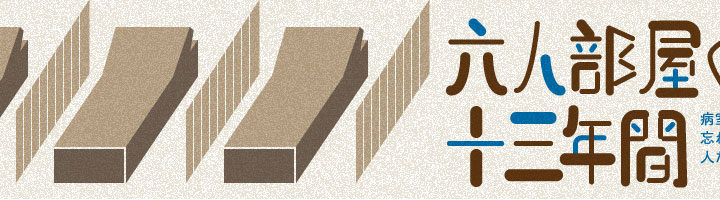「特別な人生には、ちがいないだろう」
「たしかにね、俺たち、普通の人生じゃないな、
と思うこともありますよ」
(『男たちの旅路 山田太一セレクション』里山社)
医師、看護師、去りし後
病院の六人部屋には、医師も来るし、看護師さんはかなり頻繁に出入りする。なにしろ、六人も患者がいるわけだから。
それでも、患者六人だけで話をしている時間もそれなりにある。
そのときどんな話をしているかは、わりと医師も看護師さんも知らないのではないかと思う。
今回はそのお話をしてみたいと思う。
六人で言葉づくり
医師や看護師がいないときに、六人でいちばん熱心に話していたのは、自分たちの病状を医師にどう伝えるかということだった。
たとえば、あるとき、入院は初めてというおじいさんが、みんなにこう相談してきた。
「先生が『ここがズキズキするんですね』と言うから、つい『そうです』って言ってしまうんだけど、本当はズキズキという感じとはちがうんだよね」
もう何度も手術をしている入院経験が豊富な50代のおじさんが、「だったら、ちゃんと言ったほうがいいよ。診断に関わるかもしれないから」と忠告する。
営業職という愛想のいいおじさんが、「本当はどんな感じの痛みなんですか?」と、おじいさんに問う。
「それがねえ……」とおじいさんは表現に迷う。
「ずーんとか、しくしくとか」と、技術職のおじさんが、いくつか候補をあげる。
「それともちがうんだよね」とおじいさん。
自分の身体の痛みだから、もちろんよくわかっている。しかし、それを言葉で説明するのは、とても難しい。痛みだけでなく、苦しさも。
言葉でうまく言えることはわずかで、多くのことは言葉では言い表せない。そのことを私は病院の六人部屋で知った。
ヴァージニア・ウルフもこう書いている。
文学における病気の描写を妨げるのは、言葉の貧しさだ。英語は、ハムレットの思索やリア王の悲劇を表現できるものの、悪寒や頭痛を表現する言葉をもたない。一方だけが発達してしまったのだ。ただの女学生でさえ、恋に落ちると、シェイクスピアやキーツに自分の心を代弁してもらえる。だが、頭痛に苦しむ人間に、その痛みがどういうものか、医者に向かって述べさせてみなさい。すると、言葉はたちどころに枯渴してしまう。彼に役立つできあいの言葉はないのだ。自分で言葉を作り出さねばならない。
(ヴァージニア・ウルフ『病むことについて』川本静子編訳 みすず書房)
そんな言葉を作り出すために、私たちはよく頭を寄せ合った。
中原中也がサーカスのブランコがゆれる様子を表現するために、「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」という独特のオノマトペを作ったように、私たちも自分たちの痛みや苦しみを表現するために、ぴったりと思える言葉を探し求めていた。
今になって思うと、ずいぶん文学的なことをしていたものだ。当時はそんなふうにはまったく思っていなかったが。
学校の国語で教えるのは説明文のみで充分で、文学は必要ないという意見があるが、文学は実生活で必要のない浮き世離れした芸術とばかりは言えない。説明文は言葉で説明できることを説明するものであり、文学は言葉では説明できないことをそれでもなんとか言葉で説明しようとするものだと思う。言葉で説明できることを、きちんと読み書きできるようにすることも、もちろん基本として大切だが、たとえば病気をして、自分の病状を医師に説明しなければならないという、それこそ生きるか死ぬかという究極的に実用的なシーンで、詩人のような、新しい言葉、新しい表現を作る文学的な力が要求されてしまうのだ。
医師を待つ患者は、出待ちの役者
「ズキズキ」だと、脈打つようなリズムがある感じだけど、おじいさんによると、そうではなくて持続する痛みとのことで、でも「ずーん」というような重さもないと。
で、けっきょく「すーん」と痛いと言ってみてはどうかということになった。いろんな職種や専門の人たちが、頭をそろえて考えたわりには、くだらない。人間の必死な営みというのは、しばしば滑稽なものだ。
「すーん」では、意味が通じないかもしれないが、それで「『すーん』って?」と医師に聞かれたら、「『ズキズキ』みたいにリズムはなくて持続的で、でも『ズーン』という重い感じでもない」と説明したらいい、ということになった。
だったら、最初からそう説明すればいいじゃないかと思うかもしれないが、それは素人の発想だ。
医師に対して、最初から長々とした説明はしにくい。忙しそうにしているし、患者がくどくど言いだすと聞き流す医師もいる。医師のほうから、「それはどういうこと?」と聞くように仕向けるほうが、ずっといいのだ。それならちゃんと聞いてもらえる。
「すーん」には、そういう患者の知恵というか策略も含まれているわけだ。
で、いよいよ医師がやってくる時間になった。
こういうときの患者というのは、出待ちの役者のようだ。こうふうに言おうと決めたセリフを何度も暗唱し、どんな表情でどんな言い方をするか、身振りまで考えて、しくじらないようにイメージトレーニングをする。
おじいさんの緊張が他の五人にも伝わってきて、みんな心の中で「がんばれ!」と応援している。
医師が病室に入ってきた。他の五人は、あえて目をそらし、新聞を広げたり、何気ないふりをよそおう。でも、おじいさんと医師のやりとりに神経を集中している。
医師がおじいさんの身体にさわって、「ここがズキズキ痛むんだよね」と言う。
(ここだ!)と五人は心の中で思う。
おじいさんは、「そうなんです。ここがズキズキ痛んで」と少し笑ったりする。
医師が病室を去る。
なぜそれくらいのことができないのか
おじいさんは、他の五人のほうを見て、気まずそうにする。
でも、もちろん、誰も責める者はいない。みんなにも、おじいさんの気持ちがわかるからだ。
これを読んでいる方々には、よくわからないかもしれない。自分の病状に関わることだし、医師だって正確な情報を求めているはずだ。医師の表現を少しくらい否定したり、説明が長くなったりしても、不機嫌になる医師のほうがむしろ少ないのではないか。なぜ、いい歳をして、こんなことくらい言えないのだ。そう不思議に思うほうが当然だろう。
しかし、はたから見れば、「なぜそれくらいのことができないのか」ということが、いざ自分が本当に同じ立場に立たされてみると、なるほどできないものなのだ。
『アクト・オブ・キリング』というドキュメンタリ映画で(ヴェルナー・ヘルツォーク製作)、1965年にインドネシア起きた100万人とも200万人とも言われる大虐殺で、1万人以上を虐殺した殺人グループのリーダーで、自分自身で1000人も殺したというアンワルという男が出てくる。
罪悪感はまったくなく、どうやって殺したか、殺された人たちがどんなに怯えてみっともなかったか、嬉々として自慢気に語る。
ところが、当時の状況を再現するドラマをやることになって、アンワルは被害者役を演じる。たんなるドラマで、もちろん本当に拷問されたりするわけではない。ところが、演じているうちに、アンワルは被害者の恐怖というものを理解し始める。なさけない奴らだと軽蔑していたのに、自分が被害者の立場に立ってみると、恐怖が身体にしみこんできたのだ。アンワルはついに嘔吐が止まらなくなる……。
ちょっと例が極端だったかもしれないが、同じ場所で同じ出来事を体験した者でも、どういう立場にいたかで、他の立場の人間の本当の気持ちは理解できないものなのだ。
お代官様と農民
長く入院するような命にかかわる病気で入院している人間が、医師に対して、だんだんどういうふうになっていくかというと、それは時代劇のお代官様と農民のような感じだ。
お代官様に命を握られているし、自分の苦しみを増すことができるのも軽くすることができるのもお代官様なのだ。だから、どうしたって、普通には話ができない。ストレスがかかる、のどがつかえる、卑屈になる。
もちろん、いい医師も多い。でも、それでも、それは「いいお代官様」なのだ。農民の仲間ではない。いいお代官様の機嫌をそこねたくない。いいお代官様のままでいてほしい。だから、やはり気を遣う。
『白い巨塔』で描かれるような、何人もの医師や看護師をぞろぞろとひきつれた、教授とか部長とか偉い医師の回診のときには、なおさら患者も緊張する。
回診の前には、担当医師の不満をさんざん言って、「回診のときに、担当の医師を変えてほしいって言おうかなあ」などと言っていた人でも、いざ回診となると、「○○先生のおかげで調子がいいです」などと担当医師をことさら持ち上げたりする。
回診の場の雰囲気では、なかなか不満は言いにくいし、担当医も緊張した様子でいるから、そこでおとしめるようなことを言うと、あとがこわいのだ。もちあげておくほうが、あとでよくしてもらえるかもという打算もある。しかし、それ以上に、〝ついそうしてしまう〟のだ。悲しいことに、被害者というのは、しばしば加害者をかばう。自分でもなぜそうしてしまうのか、わからないままに。
もちろん、横柄な患者もいる。医者なんか、見下している。たとえば、自分のほうが稼いでいると。たいていは鼻持ちならない人物だが、しかし、一方であこがれてしまう。自分の命を握られていながら、まだ大きな態度がとれるというのは、すごいことだ。
そういう患者に対して、それでも慇懃に対応している医師の微笑みには、「そんなに偉そうにしていても、いざ死にそうになったら、助けてくれと泣いてすがりつくくせに」というあざけりが感じられてならないが、そんな医師ばかりではないと思いたい。
飛行機の中で、他の乗客や乗務員から不愉快な対応をされて、「なんだおまえらは! みんな患者のくせして!」と怒鳴った医者がいたらしい。彼とっては、世の中の人間は医師と患者に二分されるのだ。儲けていると威張る人の場合は、金持ちと貧乏人に分けているのだろう。何かしらの才能のある人は、才能のある人とない人に分けているかもしれない。
それぞれ、ひどく偏っているが、一般的な世の中では、そうした複数の基準が乱立しているから、まだいい。病院という場ではどうしても、助ける力を持つ者/助けてもらわないと自力ではどうしようもない者、という二分だけになってしまいやすい。
本当の話は医師や看護師のいないところで
ともかく、患者というのは不思議なもので、自分の症状の本当のところを、医師や看護師にちゃんと伝えられずにいる。
医師が去った後、「今、大丈夫って言っちゃったけど、ほんとはここ痛いんだよね」と、六人部屋の他の患者に相談したりする。言っときゃいいのに、と思うのだが、自分もけっこう似たようなことをやってしまう。
そんなことができるはずもないが、もし六人部屋で患者たちだけで話をしているところを、医師や看護師がモニターか何かでこっそり視聴してくれたら、すごくよく病状を理解してもらえるだろうに、とよく思ったものだ。
本当の話は、医師や看護師のいないところで行われるのだ。
『マイ・ディア・ミスター 〜私のおじさん〜』という韓国ドラマで、相手をおとしいれるために盗聴していたのに、相手の本当の姿を知るにつれて心ひかれていくという設定があった。盗聴という卑劣な犯罪行為が、美しい心のつながりを生み出すのは意外だった。この設定は、おそらくドイツ映画の『善き人のためのソナタ』が元で、やはり韓国ドラマの『愛の不時着』でも使われていたが、『マイ・ディア・ミスター 〜私のおじさん〜』では最もじっくり時間が使われていたので、それだけ説得力も増していた。
自分が相手の目の前に立ったのでは、相手の本当のところはなかなかわからない。自分の存在が、観察が、相手を変化させてしまう。見られていないと相手が感じているときに、ようやく本当の姿が見える。
病院でも、病気を治すために入院していて、病状を伝えるべき相手はなんといっても医師や看護師なのに、その本当のところは医師や看護師がいないときにしか、なかなか明らかにされないのだ。
医師も看護師のいないときの病室を、当然のことながら、医師や看護師は知らない。残念なことだ。
誰も聞いてくれないから、お互いに語ったり聞いたり
六人部屋の患者どうしで、他にはどんなおしゃべりをしていたかというと、お互いの病気の愚痴の言い合いもやはり多かった。
『軒づけ』という落語がある。浄瑠璃を語るのが好きな素人たちが集まって、軒づけをする。他人の家の軒下に立って、浄瑠璃を語るのだ。下手なら「お断り」「お通り」と遠慮なしにダメ出しされてしまう。でも、気に入ってもらえれば、鰻のお茶漬けを御馳走してもらえることもある。で、がんばって、何軒も軒づけをするのだが、誰も聞いてくれない。
「もうこらあかんわ。わてらの浄瑠璃、どこへ行たかて、誰も聞いてくれんなあ。しょうがない。ほんならもう、いつものようにお互いに語ったり聞いたりすることにしまひょかな」(『米朝落語全集 増補改訂版』第六巻)
もうまったくこれと同じで、病気の愚痴なんて、誰も聞いてくれる人はいないから、病人どうしで「お互いに語ったり聞いたりする」しかないのだ。
病人どうしなら、そういう話も共感して聞けるかというと、そんなことはなく、やっぱり退屈だ。「一昨日は調子がましだったんだけど、昨日は痛くて、でも先週ほどではなくて、それはやっぱり食べ物のせいかとも思うんだけど、今日はまたちょっと変で……」なんて話を延々されたりするのだから、「他人の病気とペットの話ほど退屈なものはない」と言われるのは、なるほどその通りだなあと思ったものだ。
だが、こんな話を聞いてくれる人は他にはいないだろうと思うからこそ、われわれだけでも聞いてあげなければと思う。それに、こっちも話を聞いてほしいから、相身互い(あいみたがい)だ。まさに、下手な浄瑠璃を我慢して、順番に語って聞くという状態だった。
不幸自慢に勝つ不幸
そういうとき、「不幸比べ」が始まることもある。
たとえば、誰かが「あの痛みはちょっとあれ以上はないと思う」と言うと、別の人が「いや、私のあのときの痛みは、医者もあれほどひどいのは診たことがないと言っていた」とか言いだす。
どっちの病気のほうが大変かという勝負も自然と始まってしまうことがある。痛みの度合や頻度とか、手術の回数とか、後遺症とか、社会復帰の難しさとか、さまざまな基準があり、なかなか複雑な勝負となる。
その勝負がつきかけると、「でも、みなさんはちゃんと奥さんがいるから。私は病気が原因で出て行かれてしまいましたから……」などと言いだす人が現れる。病気自体の大変さだけでなく、それによってどんな不幸が起きたかということの勝負も始まってしまう。
勝負がつかないまま、食事の時間になったりして、うやむやになると、じつはそれがいちばんいい。みんなそれぞれに、自分がいかに大変かを発表できて、それを否定もされないのだから、ある程度の満足がある。
問題は、勝負がついてしまうときだ。
まず、負けが確定するとき。これはあっさり決まることが多い。私が入院していたのは、たいてい消化器外科の病棟だったが、お腹のヘルニアの人がよく入ってきた。30代や40代で、手術は初めてという人が多かった。痛みと手術の不安で、当人はとてもつらそうなのだが、こういう人はたいてい他の五人にあまり相手にしてもらえなかった。
「それくらいのことで騒ぐもんじゃないよ」などと、はっきり言う人もいて、びっくりしたものだ。パジャマをめくって自分の手術痕を見せて、「これは○○のときの手術で、こっちは○○のときの手術で」などと見せつける人もいた。やくざが自分の刺された傷を自慢するような感じだ。
ヘルニアというのは、腸壁から腸が飛び出していて、手術するわけだから、「そんなことくらい」とはとても思えず、なぜみんな軽いあつかいをするんだろうと不思議に思っていた。ある患者さんから聞いた話では(だから正確かどうかはわからないが)、手術と言っても表面だけで、開腹手術ではないからということだった。それなら、たしかに大きなちがいだ。
とはいえ、術後も痛そうだった。でも、あまり痛がると、これだから初心者はという感じで、ベテランたちから舌打ちされてしまい、かわいそうだった。
しかし、負けて、軽くあつかわれるのは、やはり幸せなのだ。
問題は、この勝負に勝ってしまう場合である。その場の全員が、ああ、これは、この人がいちばん大変だ、と認めてしまうことがある。
一瞬、その人は勝ち誇って、喜んでしまう。自分の大変さが認められたのだ。それも、苦労というものを知っている人たちからだから、値打ちがある。
苦労しているのに、それを認めてもらえなかったり、軽視されるのはつらいことだ。よけいに苦しくなる。ちゃんとわかってもらえて、ちょっとほっとする。
だが、その後すぐ、暗く落ち込んでいく。深く深く。それはそうだろう、自分がいちばん大変だと、誰もが認めるなんて、こんな悲しいことはない。
落ち込んでいくその人を見て、みんなも気まずく沈黙する。かける言葉もない。さっきまで、おれのほうがおれのほうがという熱気あふれるやりとりだったのに、なんともいえないむなしさが漂う。
不幸比べほど、勝って嬉しくないものはない。「あなたには負けますよ」と言われたら、たまったものではない。
負けて悔しく、勝って落ち込むのだから、こんなことはしないに限ると、私は病室で身にしみた。それ以来、病室に限らず、他人と自分と、どっちのほうが不幸かということは、考えないようにしている。
そもそも比較なんか不可能なのだ。お姫さまがケーキが食べられないって泣いてるのと、貧しい子どもが食べるものがないって泣いているのは、どう見ても、貧しい子どものほうがつらそうなわけだが、精神的な意味で言えば、どっちだかわからない。自殺するのはお姫さまのほうかもしれない。3000万の借金と300万の借金では、3000万のほうが大変と言えそうだが、3000万のほうの人がなんとかなって、300万のほうがそのせいで命を落とすことだってある。
自分の人生で、あの時よりこの時のほうが大変だったという比較はできる。でも、他人と自分で、どちらのほうが大変かという比較は不可能だ。
だから、誰かに対して「甘い」と言ったりすることは決してない。つい思ってしまうことはあるが、あわてて打ち消すようにしている。そういうときは、六人部屋が思い浮かぶ。
心の病と身体の病
不幸比べとも似ているが、「心の病と身体の病のどちらのほうが大変か」とか、「外から見てわかる病気とわからない病気のどちらが大変か」とか、そういうことも話題になった。
身体の病気をしていると、心の病気の人からしばしば「身体の病気のほうがずっとまし」と言われる。何度目かの入院の人たちは、たいていそう言われた経験があった。命にかかわる病気の人でも。初めて入院した人は「へーっ、そうなんですか」と少し驚く。私も最初は、ほんとにそんなことを言う人がいるのかなと思ったが、あとから自分も何人もの人から言われて、なるほどこれかと思った。
なぜ心の病気の人が、身体の病気のほうがましと思うのかというと、身体の病気はどこがよくないか、はっきりしていることが多い。たとえば、レントゲンに写ったりする。その点、心の病気は、はっきりしないことが多い。だから、「本当に病気なのか」と疑われたり、「気の持ちよう」と言われてしまったりする。はっきりしている身体の病気のほうがましだ、というわけだ。
しかし、これも不幸比べと同じで、ましと言われたほうは、やはりむっとしてしまう。身体の病気だって、はっきりしているものばかりではない。たとえば難病は、原因も不明で、完治する治療法もない。骨折などなら、たしかに「気の持ちよう」とは言われないが、内臓の慢性的な病気では、「気の持ちよう」とどれだけ言われることか(『食べることと出すこと』(医学書院)の「ブラックボックスだから(心の問題にされる)」の章でくわしく書いた)。身体の病気になった苦悩から、心の病気になる人もいる。
身体の病気の六人部屋では、そんなことを言い合って、「身体の病気のほうがましなんて、わかってないよなあ」と、心の病気の人に対しては言い返せなかったうっぷんを晴らすのである。なにしろ、こっちも心の病気についてはよくわかっていないわけで、言い返すわけにもいかないのだ。身体の病気の仲間内で愚痴ることしかできない。
外から見てわかる病気とわからない病気
「外から見てわかる病気とわからない病気のどちらが大変か」も同じようなことで、外から見てわからない病気の人は、「外から見てわかる病気の人はうらやましい」と言ったりする。
なぜかというと、外から見てわからないから、本当にどれくらい大変なのかが、周囲の人たちには判断がつかない。当人の自己申告だから、大げさなのではないかと疑われてしまう。電車などでつらそうにしていても、誰も席をゆずってくれないし、優先席に座っていると、にらまれたり、けられたりする。見てわかる病気なら、こんな苦労はしなくてもすむのに。
そう言われて、外から見てわかる病気の人は、なんとも言えない気持ちになるそうだ。外から見てわかる病気の人からすれば、見てわからないほうが、どれほどましかもしれないと思う。
人と出会うときも、見てわからない病気なら、まず普通に知り合って、それから折りを見て病気のことを打ち明けるという手順を踏むことができる。しかし、見てわかる病気だと、出合ったとたん、相手はこちらの病気に気づく。まず「病人」として出会ってしまうのだ。このちがいは大きい。そして、病人に対する差別や嫌がらせに遭う機会も、当然多くなる。
そもそも見た目というのは、社会生活を送る上で、かなり大きい。他人の視線というものを、どうしても人は意識してしまう。たとえば「女性化乳房症」という、男性の乳房が大きくなる病気がある。思春期や更年期などのホルモンバランスが崩れるときに起きる。良性の病気で治療の必要はない。しかし、胸がかなり大きくなってしまったときは、人目をひいてしまう。だから、見た目のためだけに手術をする人も多い。その気持ちはわかるだろう。
私の病気は、外からはわからない。しかし、プレドニンという薬の量が増えると、ムーンフェイスと言って顔が丸くなったりする。また、漏らしてしまえば、見える病気になってしまう。私の場合は、なるべく気づかれたくないと思って、人の目から自分の病気を隠して暮らしている。
六人部屋で学んだ教訓
ようするに、病人どうしでも、自分と異なる病気の人の苦労は、本当にはわからない。経験していないから当然だ。しかし、自分の病気の苦労はいやというほどくわしくわかっている。経験しているから当然だ。だから、つい他の人のほうがましに思えてしまう。
それは仕方ない。しかし、それを口にしてしまうのは、まずい。あなたたちはましと言われれば、言われたほうは不愉快だ。では、あなたたちのほうが大変と言われれば嬉しいかというと、それはそれですごく不愉快だ。
不幸比べは、監獄にいる者どうしが、こっちの監獄のほうがましとかひどいとか言っているようなもので、勝っても負けてもむなしいし悲しい。
そもそも、比較する必要はないのだ。
人はついつい比較してしまう。古いドラマが面白かったとき、それだけ言えばいいのに、「今のドラマのつまらなさに比べて」などと余計なことを付け足してしまう。ある業界の大変さを訴えるのに、他の業界なら楽だけどと言ってしまったり、働く女性の大変さを訴えるのに、専業主婦は楽だけどと言ってみたり。ピースの箱と並べたほうがサイズがよくわかるのはたしかだが、じつはよくわかっていないかもしれないものを比較対象にするのは、誰かを踏み台にすることになってしまいかねない。
何かを言うとき、他との比較はなるべくしないほうがいいというのも、私が病院の六人部屋で学んだことのひとつだ。
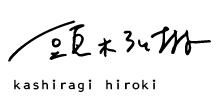 文学紹介者。筑波大学卒業。大学3年の20歳のときに潰瘍性大腸炎を患い、13年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いとなった経験から、『絶望名人カフカの人生論』(新潮文庫)を出版。その後、『カフカはなぜ自殺しなかったのか?』(春秋社)、『NHKラジオ深夜便 絶望名言1・2』(飛鳥新社)、『絶望書店 夢をあきらめた9人が出会った物語』(河出書房新社)、『トラウマ文学館』(ちくま文庫)、『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』(ちくま文庫)、『食べることと出すこと』(医学書院)、『自分疲れ』(創元社)などを刊行。
文学紹介者。筑波大学卒業。大学3年の20歳のときに潰瘍性大腸炎を患い、13年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いとなった経験から、『絶望名人カフカの人生論』(新潮文庫)を出版。その後、『カフカはなぜ自殺しなかったのか?』(春秋社)、『NHKラジオ深夜便 絶望名言1・2』(飛鳥新社)、『絶望書店 夢をあきらめた9人が出会った物語』(河出書房新社)、『トラウマ文学館』(ちくま文庫)、『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』(ちくま文庫)、『食べることと出すこと』(医学書院)、『自分疲れ』(創元社)などを刊行。