佐藤直樹さんは2013年3月、荻窪6次元で初の個展「秘境の荻窪」を開いた。中学2年生のときに1年間住んだことのある荻窪を歩きなおし、建物や木々、動物、地形などを木炭で描いたもの。長らくデザインの現場に身をおいてきた佐藤さんだが、それ以降、少しずつ絵を描く機会を増やしてきた。3331コミッションワーク「そこで生えている。」や、Tambourin Gallery Presents 「佐藤直樹と伊藤桂司の反展」では、毎日、会場へ通って、少しずつ絵を描いていって、その過程を披露していた。そのような試みは、純粋に、「絵ってなんだろ?」という疑問から出発している。
「絵画」というと、美術館の中だったり、画商が扱うものだったり、どこかありがたいもの、身近なものではないものに思える。でも本来は、幼児の頃、うら紙やダンボールに○や□や線を描いたり動物らしきものを描いたのも、絵のはじまりかもしれない。個人ではなく人類で考えてみると、ショーヴェの壁画はどのように描かれたものなのか? 人間がもつ根源的な欲求である「何かを描く」という行為とは何かを、自らが「絵画」を描く行為、「絵画」に入門しながら考えてみる、そんな連載である。佐藤さんの実作もお楽しみに。
「表現」以前の問題として
入門の門の話をしているうちに連載も七回を費やしてしまったわけですが、そうこうしている間にも絵は描かれ続けています。連載第三回(約九ヶ月前)の時にはベニヤ板四〇枚くらいだった絵もその倍の八〇枚くらいになっています。幅にして七二メートルといったところです。まだ伸びて行く感じではあるのですが、ここに来て、新しく考え始めていることがあるので、今日はその話をします。約一年後に展覧会を開くのですが、そのためにステイトメントなるものを書いたのでまずはそれを読んでみてください。タイトルは「なぜ今になってこのようなかたちで描き始め、止まらなくなっているのか。」です。
「絵って何なのかなぁ」ということは子供の頃から考えてきたのですが、50年くらい考えてもわからないので、おそらく、死ぬまでわからないのでしょう。最初に意識したのは幼稚園の年少組か年中組の時でした。独りで鯉幟を描いていたのです。ところが人に見られていると気づいた瞬間、そのことを意識するようになってしまい、大事なものを手放してしまった感覚が残りました。対象との間にだけ存在していた関係に、何かが介入して来て、元の関係のことがわからなくなってしまったような。
人目を意識すること自体が悪いわけではないと思います。イラストレーションやコマーシャルアートにとってはむしろ重要な要素でしょう。ただ、そのような意識を持つ前から人は絵を描き始めているわけなので、その初源には何があるのか、あったのか、そこまでのことになるとまだよくわかってはいません。個々人の中がどうなっているのかも、類としてどんな経緯を辿って来たのかも。アールブリュットやアウトサイダーアートといったものが人に感動を与えるのは絵の本質に触れているからに違いありませんが、そこで言えるのは要するに「真相はわからない」ということだけです。
何万年も前に洞窟の入口付近ではなく奥の暗がりで人が絵を描いていた時、それは何を意味していたのでしょうか。何かの確認だったのでしょうか。遊びの一種だったのでしょうか。サービス的な行為だったりもしたのでしょうか。慰安や娯楽に関わる何かでもあったのでしょうか。自己顕示的な要素もあったのでしょうか。社会階層的な何かに関わってもいたのでしょうか。そういった要素が絵に潜んでいたとしても、それは後からのことであって、最初の最初にあったことではないと思うのです。呪術との関係で絵の発生を説明する人もいますが、もしそうだとして、最初の最初から呪術があったわけではないでしょう。
夢現の時に像が浮かんで、それを描こうとしていることがあります。そんなことをするのに、上述したような起源がその理由として必要であるとも思えないのです。夢現の行為は人に見られることを前提にしていませんし、だいたい絵としては定着させようもありません。内面的な何かと言えば言えるのかもしれませんが、自意識というのとも違っている気がします。だとすると、目に見えない何かとやりとりをするためにこそ絵は描かれなければならなかったと言えないでしょうか。人がそれなしには生き続けられなかった、目に見えない何か。今のように多層なシステムによって生かされていると、感じ取り難い何か。存在の気配としか言いようのないもの。
そういったものとの交信は、大昔にはあったかもしれないし、昨今だと特別な人にしかできないのだろうと何となく思っていました。が、それがどうやらそうでもなさそうだという体験がありました。それを感知できたのは思春期の一時期を過ごした荻窪を歩いていた2011年でした。かつては何気なく通り過ぎていた場所でしたが、数十年という時間の経過のせいかわかりませんが、建物と言わず木々と言わず、ただそこに生えるように存在しながら、無言のままこちらを見ている感覚が訪れたのです。言葉にしにくい感覚ですが、見ている主体はこちらにでなくあちらにあるように思われました。
そして、その直後に大地は大きく揺れたのでした。
今回の展示は、それ以降に描いた絵が中心になっています。この20~30年というもの、主にデザインの仕事をしてきて、その間、絵はほとんど描いていません。また、それ以前の絵もほぼ残っていません。デザインの分野には優秀な人もたくさん出て来ていますから、もう自分までが無理にやらなくていいだろうというのが正直な気持ちですが、描く行為は再開したばかりなので、ほとんどがこれからのことです。巡り巡って、独り鯉幟を描いていた頃に戻りつつある感覚があります。主に生えているものが感知されるので、まずはそれを描かなければなりません。何のためって、存在そのものに向けて描いているのです。今言えるのはそこまでです。
ここに書いてあるのは、要するに「そんなわけで、ただ描いています」ということだけです。他人からすれば「そうですか」という話に過ぎません。私自身が個人として「存在そのもの」との間に成立する関係を探っているだけです。ありていに言って、このような行為は誰からも求められていません。幼少の頃の話などもしていますが、つまるところ「存在そのもの」との蜜月の時間は子供時代にしか持ち得ないということでもあります。そして「独り鯉幟を描いていた頃に戻りつつある感覚」というのは、いったん身に着けた社会性を帳消しにしようとしているということになるんだと思います。そんなこと、できないんじゃないでしょうか。普通に考えたら。
絵画にとって「社会」とは何か
「何万年も前に洞窟の入口付近ではなく奥の暗がりで人が絵を描いていた時」に、今のような「社会」や「経済」は背景にありません。他の動物とは異なる、人としての採集や狩猟という、道具を使った行為が発生するプロセスで、描くことも起こったのでしょう。観察の切実さがそのまま描写の力に結びついて。縄文土器に多く見られる、女性の肉感を彷彿させるイメージや文様も、人が生き延びるのに必要な行為と重なって生まれているものだろうと思います。
しかし、現在の「絵画」に、そのような必然性はありません。そこで個々が個々の必然を言い募るような状況が生まれます。またその一方で合理的に説明のつく経済性も求められます。それが資本主義社会の自然法則のようになっています。経済性が優位になるより前は、政治の力が強く働いており、連載の第一回に名前を出した長沢芦雪さんにしろ円山応挙さんにしろ石田幽汀さんにしろ、統治あっての画業でもあったわけです。西洋の美術史を見ても、 18世紀くらいまでは統治との関係が明確で、ある種の外圧があった時に、そののっぴきならない状況を打破するため、それまでの常識を超える「表現」が生まれています。が、このような説明からだと、経済性を相対化できたとしても、社会性という枠組を外して考えることができな くなります。この「社会」というやつが曲者なのです。もしかしたら「経済」よりやっかいかもしれません。
人間はどこまで行っても社会的動物なのですから、 絵の話だって「社会」を抜きにはできません。どんな時代に生きていてもです。過去に描かれた絵を読み解くには時代背景を巡る知識だって必要になります。ただ、過去を読解する場合にはそうなんですが、今現在のこと、これからのこととなると知識は誘導してくれません。過去形で「こういう社会だったからこういう絵が生まれたのか」ということは言えても、現在形で「こういう社会だからこういう絵になってしかるべき」と言うことには何の意味もありません。
目の前にあるものを描く時、まずその存在があって、そこから何らかのものをキャッチしていると考えてみてください。問題はその時、何をキャッチしているのか、です。光の屈折が重要な場合もあるでしょうし、輪郭の滑らかな曲線が重要な場合もあるでしょう。変化の速度であるようなこともあり得ます。それは社会的な通念によって規定されることにも思えます。時代性だったり文化性だったりの。しかし、ここが大事なところですが、誰に何を伝えるかということ以前に、「それ自体に心奪われる」瞬間があるわけです。おそらくそれがなければ絵というものは成立しません。そして、人が何に心奪われるかというと、もちろん人それぞれではあるでしょうが、共通するのは、自分自身が「生きる」ために必要な物なり事なりにもっともよく反応しているだろうということです。
対象が具体的な物体や物質であることもあるでしょうし、定着させづらい現象のようなものであることもあるでしょう。また、式で表した方がいいような、原理のようなものである場合もあるはずです。しかし、いずれにしても、それは〈自然(じねん=おのずからしからしむ)〉をどう捉えようとしているのかということになっているはずです。問題は受け取り方(=受容)なのです。差し出し方(=表現)よりも前に。〈自然〉とは、「自然(しぜん=ネイチャー)」とイコールではありません。ネイチャーは人間が働きかけるべき対象としてあります。それは人間こそが主体であるという考えから来ています。絵はそこから生まれたわけではありません。絵はそういった考えを持つようになる遥か昔に生まれています。表現というよりも表出というべき行為が受容を強めるということはあると思います。たとえば、山に入ると周囲の〈自然〉と呼応するような感覚が生まれます。最初に唄が生まれた瞬間というのは何かの受容と表出が完全に重なっていたのではないかとも思えます。何かと何かが共振したような。狼の遠吠えのような。
〈自然〉を探る
こちらを じっと見ているように「生えている」ものがあるとして、そのことが感知されるようになったとして、それをそっとそのままにしておいては駄目なのか。もちろん、かまわないでしょう。自分などよりもずっと感受性の強い存在はつねにいて、今もあちこちで人知れず様々な〈自然〉と対話を重ねていると思いますし、それを描くか描かないかはたいした問題ではない気もします。
しかし、人の世にあって「見えないものの存在」が共有されている様子もない中で、自分たちの生命力が弱まるのを感じつつある時に、〈自然〉の力を汲み上げて世に投げ込むような作業が必要になっているのではないか、ということも普通に思います。資源の消費を最低限に抑えながら、〈自然〉の持つ生命力を世の中の側に供給するようなことができたら。それを描くということの核心にできたら。これは試してみるに値することではないか。そのように考えると、絵を描くことというのは、科学的な探求ともそんなには違わないことではないかと思うのです。そして科学的な探求というのは、社会性の内側と外側を自由に往復することなしにはできないことですから、その覚悟でやるしかないんだろうと。
連載第一回では「絵画」という言葉の由来についても触れました。つまり明治期に西洋から入って来た概念を日本ではどう使いこなそうとしていたかという話です。それで言うと「科学」にも同じような問題は存在していたことでしょう。しかし近代合理主義のど真ん中に座す「科学」の影響力は、「芸術」の比ではなかったでしょう。国語・ 算数・理科・社会と音楽・図工・体育の授業数を比較すればすぐにわかります。それはさておき、日本にも「和算」のようなものはあって、もちろん大陸との交流はあったわけですが、独自発達している。結局それも、その地に留まりながら〈自然〉を相手にしているということだったんじゃないか。
ここで素朴な疑問が頭を擡げます。すると絵画というのは科学の一様式でもありうるのだろうかと。レオナルド・ダ・ヴィンチが活躍したルネサンスのイタリアではそうだったのでしょうし、博物学や生物学から植物画が発達したような歴史もあります。ともかく、今普通 に流通している「絵画」「美術」「芸術」「アート」「イラストレーション」「グラフィック」「インフォメーション」「テクノロジー」「サイエンス」「科 学」といったカテゴリーとは別の、〈自然〉との向かい合い方が必要になっているんじゃないか。そんな気がして仕方ないのです。
どう耳を攲て、どう目を凝らすか。それがすべてであるように思うのです。〈自然〉に対する向き合い方、その方法は、各々が自分で決めるしかありません。どこにも確実なやり方は存在していません。そして、私の場合ですが、ものごころつく前から描いていて、そのことに気がついた時というのはその途中段階だったわけですから、その前にまで遡る感覚が掴めなければ、探求の名に値しないと思うのです。そこのところを放ったらかしにして、スルスルッと「美術」や 「アート」に滑り込んでしまうことには警戒せざるを得ません。そんなカテゴリーに収まってしまって平気でいられるということは、そこに納まり切らないものへの好奇心を失っているということでもあるでしょう。
中途半端なことをやっていたら、ずるずるとおかしな力に引っ張られてしまいます。やはり私(たち)はまったく新しい門を打ち立てるしかないのだと思います。最初は何もなかったのですから。ただの吹きっ晒しだったのですから。
 1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。
1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。
twitter / facebook



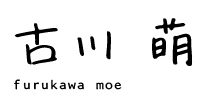 美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。
美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。