「上」からではなく「下」からの制限
アメリカやヨーロッパでは、ポリティカル・コレクトネスやキャンセル・カルチャーの勢力が増していると同時に、その風潮に対する懸念や反対を表明する議論もなされている。そのなかでも特に目立つのが、ポリティカル・コレクトネスの風潮が学問の自由を侵害していることを批判する議論だ。
日本では、学問の自由に対する制限は「上」からやってくるというイメージが強いかもしれない。つまり、政府や省庁といった国家権力が大学に介入して、研究の内容や人事をコントロールする、というものだ。2020年9月に起こった、日本学術会議に推薦された会員の任命を菅義偉元首相が拒否した事件などを思い起こすと、本邦において学問に対する「上」からの制限を危惧することには充分な理由があるとはいえるだろう。また、中国のような権威主義的国家では国の体制や権力者を批判するような研究が弾圧されていることは、公然の事実である。民主主義国家でもあるアメリカにおいても、ドナルド・トランプ元大統領が気候変動や科学関連の研究予算を大幅に削減してそれに反対する科学者が抗議運動を行なった事例をはじめとして、学問の自由が「上」から制限されることが問題視される場合はある。
しかし、昨今のアカデミアで起こっているキャンセル・カルチャーで問題となっているのは、学者たちが他の学者を糾弾するという「横」からの制限、または学部生や院生などの学生たちが学者に対して集団的に抗議するという「下」からの制限によって、学問の自由が危機に晒されることだ。
たとえば、2020年7月、認知心理学者のスティーブン・ピンカーに対して、彼をアメリカ言語学会の「アカデミック・フェロー」および「メディア・エキスパート」の立場から除名することを請願するオープン・レターが、同学会の会員たちによって発表された。このレターには、博士課程の学生や助教授・教授を中心とした600名以上の会員たちの署名が付けられていた。
オープン・レターのなかで主に問題視されていたのは、アメリカの警官による黒人の射殺問題やアメリカの警察制度に関してピンカーがツイッターに投稿してきた意見の内容であった。黒人射殺の問題については、多くの学者が「アメリカの社会には制度的なレイシズムが存在しており、警官による黒人の射殺問題も制度的なレイシズムのあらわれである」という理論を提唱しており、ブラック・ライヴズ・マター運動の活動家たちもこの理論に同意している。ピンカーはこの理論に賛同しておらず、彼の投稿は、黒人射殺の問題の原因が他にある(アメリカの警官は他の国の警官に比べて銃を発砲する機会が多すぎること、黒人のほうが白人よりも警察に通報される機会が多くて警察が犯罪現場で遭遇する可能性が高いことなど)という意見をピンカーが持っていることを示唆していた。これに対して、オープン・レターは、ピンカーの投稿は「制度的なレイシズム」の存在を否定して「人種差別の暴力に苦しむ人々が挙げてきた声をかき消す」ものであると批判したのである。
上記の事例においては、ピンカーの専門となる研究の内容が直接的に批判されたわけではなく、専門外の分野も含めた事象に関して彼の抱いている意見が批判されたことに留意しておこう。また、オープン・レターで訴えられているのはあくまで学会内での特別な地位からピンカーを除名することであり、ピンカーの研究そのものを制限したり学問の世界から彼を追放したりすることを目的としているわけではない。これらのことから、「オープン・レターはピンカーの学問の自由を制限しようとするものではなかった」と擁護する声もある。
しかし、ある学者が社会や政治に関わる問題について特定の意見を発表したことを理由にして、その学者に認められた何らかの地位を奪うというペナルティを課そうとする行為は、かなり危険なものだ。ピンカーが「人種差別の問題を矮小化している」と非難されて地位を奪われようとしたことは、アメリカ言語学会に所属する他の学者たちや、ネットやメディアを通じて騒動を見聞していた別分野の学者たちにも強い印象を与えたはずだ。彼らのなかには、「制度的なレイシズムが存在するという言説には疑いを抱いており、警官による黒人射殺事件の原因は他にあると考えているけど、その意見を表明したら自分もピンカーのように非難されてアカデミックなキャリアに支障が生じるかもしれないから、黙っておこう」と思った人もいるはずである。
この事態は、警官による黒人の射殺問題に対処するうえでも有害となる。この問題の原因は「制度的なレイシズム」であるという理論は、あくまでひとつの仮説や意見に過ぎない。「制度的なレイシズム」という理論の真偽を確かめて、理論の正確さや妥当さがどれくらいであるかを測るためには、この理論と対立する別の意見を表明する自由が保証されなければならない。もし「制度的なレイシズム」が存在しなかったり、その影響力が実際以上に過大視されていたりしたら、黒人の射殺問題の背景に存在する他の原因を発見して対処する必要があるだろう。しかし、「問題の原因は制度的なレイシズムではない」という意見を非難したり弾圧したりすればするほど、見逃されている原因の発見や対処が遅れることになるのだ。
焦点になっているトランスジェンダーをめぐる問題
ピンカーの事例に限らず、特定の意見を発表した学者が、論文などの撤回を要求されたり、講演や討論会などに登壇する機会を奪われたり、学会や大学での地位や研究するためのポストを剥奪されたりするという事態は、欧米では多々起こっている。ある学問分野やアカデミアの内部で少数派である意見に対して、論文などによって反論するのではなく、多数派がオープン・レターや抗議運動などの手段を用いてペナルティを与えることで意見を取り下げさせようとする事態は、すっかりお馴染みのものになってしまっているのだ。
そのなかでも近年になって特に目立っているのが、トランスジェンダーの人々に関連する意見をめぐる問題だ。
イギリスの哲学者であるキャスリーン・ストックは、「法律や制度を設計する際には、生物学的性別よりも性自認のほうが基準とされるべきである」という考え方を批判する議論をおこなうなど、生物学的性別を重要視する主張を続けてきた。そのために、彼女はトランスジェンダーの人々に対して差別的であると問題視されてきた。たとえば、2021年に大英帝国勲章がストックに授与されたが、それに対抗するかたちで、600名以上の哲学者の署名が付けられた「哲学におけるトランスフォビア」を懸念するオープン・レターが発表されたのだ[1]。また、ストックに対する学生や活動家からの抗議活動は激しく、脅迫的なものにまで発展して警察による身辺の警護が必要となり、彼女は勤めていたサセックス大学を辞職することを余儀なくされたのである。
2017年にはカナダの哲学者レベッカ・トゥベルがフェミニスト哲学誌『Hypatia』に「トランスレイシャリズムを擁護する(In Defense of Transracialism)」という論文を発表した。この論文では「ジェンダーが社会的に構築されているなら人種も同様に社会的に構築されていると言えるのであり、“自分の人種を変えたい”という主張は“自分のジェンダーを変えたい”という主張と同様に認められなければならない、ということになるのか?」というトピックに関する議論が展開されていた。これに対してソーシャルメディアを中心として非難が起こり、トゥベルの論文の撤回を『Hypatia』に求めるオープン・レターが発表された。そのレターには多くの学者の署名がなされており、賛同者は830人にも上ったのだ。
『自由論』でスチュアート・ミルが問題視していること
思想の自由や意見の自由を含む「表現の自由」を擁護した議論のなかでも古典的なものが、ジョン・スチュアート・ミルによる『自由論』だ。
表現の自由については「国家や権力による弾圧や検閲から表現を守るためのものであり、市民間の批判によって表現が萎縮することまでを防ぐためのものではない」といった主張がなされることも多い。そのような主張では、問題ある表現について多数派が批判を浴びせることでその表現が取り下げられたり、社会の規範や良識に反する表現が市場や学問で流通することが自主的に規制されたりすることは、国家や権力による弾圧とはまったく種類が異なる問題であるとされる。むしろ、意見や表現に対して自由な批判が行われることは民主主義の社会では当然の営みであり、批判の結果として特定の表現が発表されることがなくなるのも民主主義の帰結である、と論じられるのだ。
しかし、『自由論』やその他の著作でミルが問題視しているのは、国家や権力による弾圧や検閲だけではない。彼は「世間」や「多数派」によって「異端」や「少数派」の意見や表現が封殺されることについても、大いに危惧している。そして、ミルの議論のポイントは、少数派の意見が発表される場が守られることは少数派にとってだけでなく多数派や社会全体にとっても利益をもたらすから必要である、ということにある。
トゥベルの論文に対して反駁する論文を提出するのではなく、オープン・レターによって撤回が求められたことは、多数派による少数派の意見の抑圧の典型的な事例だと言えるだろう。オープン・レターが効力を発揮するのは、そこに書かれている内容の説得力や妥当性によってではなく、数百人の署名が付けられることによってだ。また、哲学という学問では他の分野に比べると「異端」とされる意見や世間では人気のない意見が取り上げられることが多い。難しいトピックやセンシティブなテーマについても論理的に突きつめて考えたうえで自由な議論が展開されることにこそ、哲学という分野の価値がある。だからこそ、哲学者たちが数を頼りにするオープン・レターという手段に訴えたことやそのレターが受け入れられてしまったことは、哲学業界やアカデミアの内外にとって衝撃的な事態であったようだ。
たとえば、ジャーナリストのジェシー・シンガルによると、オープン・レターのなかでトゥベルの論文に対してなされている指摘はいずれも的外れであり、レターの執筆者たちが「トゥベルの論文はトランス女性に対して差別的なものに決まっている」と決めてかかったことにより誤読したとしか考えられないものである[2]。そして、オープン・レターに署名した哲学者たちの全員がトゥベルの論文を読んでいたとも考えづらい。批判者たちの誤読に基づいた要約や「差別的な論文が掲載された」というネット上のうわさ話に惑わされて署名した人も相当数いることだろう。シンガルは、トゥベルに対する糾弾は「魔女狩り」のような有様になっていたと指摘する。
社会心理学者のジョナサン・ハイトは、トゥベルの論文に対する哲学者たちの反応は、特定の意見だけを受け入れてそうでない意見を排除する権威主義がアカデミアのなかで横行している事態の典型例だと論じている[3]。彼が危惧しているのは、いちど差別的なものと見なされた意見や保守的なものだと見なされた意見に対して、(論文による反論ではなく)憤慨した集団による糾弾が行われるのが当たり前になっていることだ。また、ハイトが以前から問題視しているのが、アメリカの大学で人文学や(経済学以外の)社会科学や専攻する研究者のなかで保守主義的な意見を持つ人やリバタリアニズム的な意見を持つ人の数が年々減っており、文系の学問がリベラルな意見を持つ人だけに独占されるようになっている、という事態だ。それに伴い、意見が「差別的」と見なされる範囲もどんどん拡大している。
「動機づけられた推論」と「制度的反証」
ある学問をする人たちの間で政治的な意見の多様性が失われると、その学問の内における議論のプロセスが不公平で偏向したものになる、とハイトは主張する。彼はカール・マルクスとミルの主張を対比させながら、大学の目的について以下のように論じる[4]。
マルクスは、私が“社会正義大学”と呼ぶ大学にとっての守護聖人だ。社会正義大学は権力構造や特権を転覆させて世界を変革することを目的としている。社会正義大学にとって、政治的な多様性は行動の障害である。ミルは“真実大学”の守護聖人である。真実大学は、誤りのある個人たちがお互いのバイアスや不完全な推論を指摘して挑戦し合うプロセスに真実を見出している。このプロセスは全ての人を賢くする。そこにいる人々の知的傾向が均一になったり、そこが政治的な正当さを主張する場所になったりした時に、真実大学は滅んでしまう。
心理学者であるハイトは、個人がひとりで行う思考は「動機づけられた推論」になりがちであることを指摘する。人の思考は「物事はこうなっている」ということを偏見なく客観的に判断するために機能するとは限らない。むしろ、まず「物事がこうであったらいいな」「もし物事がこうであったら自分にとって都合が良い」といった動機が存在したうえで、その動機に基づいて「物事はこうである」と自分に信じさせるための主張を形成したり、その主張にとって有利な証拠を探したりするように機能することのほうが一般的だ。
動機づけられた推論を行う傾向は、一般人だけでなく研究者にも存在する。しかし、通常の学問においては「制度的反証」が保証されている。ある研究者が論文で展開した議論が動機づけられた推論に基づくものであったとしても、その動機を共有していない別の研究者が論文の内容を査読したり別の論文を書いて反証したりすることで、最初に論文を発表した研究者は自分の間違いや偏向に気がつくことができる。このプロセスが繰り返されることで、ひとりで動機づけられた推論を行なっていてはたどり着くことのできないような知識や真理に近づくことを、学問は可能にするのだ。
しかし、ある学問に関わる研究者たちの間の政治的見解が均一になったら、その研究者たちは政治に関して同じような動機を共有してしまうことになる。自分と同じ政治的動機を持っている研究者が論文を書いたときに、間違いや偏向を査読で指摘したり論文で反証したりすることは難しい。「物事がこうであったらいいな」という願望を共有している人たちの間では、その願望を補強してくれるような主張や証拠を否定するという動機ははたらかない。そのため、知識や真実に近づくどころか、謝った理解や虚偽の主張がその学問の研究者たちの間で伝播してしまうおそれもあるのだ。それを防ぐためには、「物事はそうではない」ときっぱり言える、他の人たちとは違う政治的見解を持っている研究者の存在が必要になる。
特定の意見を持つ研究者を排除して同じような意見を持つ研究者ばかりが集まった学問では、制度的反証は機能しない。そして、制度的反証が機能していない状態にある学問から生み出された知見は、その知見が真理であると立証するプロセスに集団的な歪みがあって信頼が担保されていないために、その学問の外側にいる人たちがその知見を真理と認めて受け入れる根拠はなにも存在しなくなってしまう。
言うまでもなく、オープン・レターによって論文を批判することは、制度的反証とは正反対である。学術誌に掲載された論文が後から多数派の要求によって撤回されることは、論文による反証というプロセスを怠るだけでなく、査読というプロセスの意義を踏みにじるものでもあるからだ。また、学界のなかでは少数派である意見を論文に書くと査読や反証ではなくオープン・レターによって批判されるリスクがあるという状況では、その学会の多数派と動機を共有しない研究者は、自分の主張を論文で展開することにも尻込みするようになるだろう。オープン・レターによって論文の撤回を迫られたり個人名を挙げて非難されたりすることは、精神的に多大なプレッシャーがかかるばかりでなく、アカデミックなキャリアや社会的な評判にも影響する可能性が高いからだ。結果として、少数派の意見はますます封殺されて、多数派による「動機づけられた推論」の間違いが訂正される機会はなくなり、制度的反証の機能は崩壊する。そのような状態になった学問は、外側にいる人たちにとって何の価値もないものとなるだろう。
自分たちのものと異なる意見を査読や反証ではなく制裁やペナルティによって退けようとすることは、それだけ危険な行為なのである。
「危害原則」と「意見の自由」
ミルが『自由論』で提出したトピックのなかでも、最も有名であり現在でもよく持ち出されているのが「個人の自由は、他人に危害を与えない範囲内において最大限に認められるべきだ」とする、「危害原則」である。
この原則は人間の行う諸々の活動や表現、信じる宗教や実践する生き方などの幅広い領域に適用できるものだが、本稿では、「意見の自由」という範囲に絞って扱おう。……この自由に危害原則を適用すると、以下のようになる:意見を発表する自由が存在することは、その意見が正しいか間違っているかを問わず意見を発表する本人にとっても他の人たちにとっても有益である。したがって、他人に危害を加えない限りにおいて、意見を発表する自由は最大限に認められるべきだ。
逆に言えば、それが他人に危害を加えるものであれば、意見を発表する自由を制限することは認められる。たとえば、ミルによると「穀物商は貧しい人から略奪している」という意見を公の場で言うことは通常は認められるべきだが、興奮した群衆が穀物商の家の前に集まっているときにその意見を連呼すると、暴動を引き起こして穀物商に危害を与える可能性が高いだろう。後者のような事例では意見の自由を制限することも許容され得る。
哲学者のジョセフ・ヒースは、危害原則には「危害」という概念がきちんと定義されていないという問題があることを指摘する[5]。ミルが挙げている事例ですら、意見を言っている人が穀物商に対して直接に「危害」をもたらしているわけではない。穀物商に対して危害を与えるのは、あくまで、意見によって扇動された群衆だ。そして、意見を言っても群衆が扇動されない可能性も存在する。この事例において意見がもたらす危害は間接的なものであるし、実際に危害が生じるかどうかはあくまで可能性の問題なのだ。
広がる「危害原則」の乱用
ヒースを含む多くの論者が指摘しているのは、現代では「危害」の範囲が拡大解釈されており、それによって危害原則も乱用されていることだ。
基本的に、「その表現によって不快になった」とか「その行動のせいで心が不安になった」ということは、危害原則における「危害」にはあたらない。不快感や不安はだれのどんな表現や行動にも感じ得られるものであり、それだけで自由が制限されるとなると、実質的にどんな表現や行動も禁止することができてしまうからだ。
しかし、最近の左派や進歩派は、「意見や表現によって不安にさせられることは、メンタルヘルスに影響を与えてうつ病や自傷行為などに結び付く」などと論じることで、不快感や不安を「危害」に直結させるロジックを発展させた。さらに、「マイクロアグレッション」や「ステレオタイプ」がマイノリティに危害をもたらしているという主張が普及したことで、過去に比べてはるかに多くの行為や表現を「危害」であると解釈することが可能になったのだ。そして、これらの拡大解釈は、マジョリティのものとされる意見を危害原則によって排除することに利用されている。
シンガルは以下のように書いている。
…ある種の議論を「暴力」と呼ぶことが一部の学界でいくら流行しようとも、少し立ち止まって、[議論のことを]このように捉えるのがいかに見当外れで逆効果であるかを考えることは大切だ。トランスの人々は、アメリカや世界中の大半の部分で、毎日のように現実の物理的な暴力の脅威にさらされている。[だが、]マニアックな哲学論文でアイデンティティとアイデンティティ移行についての詳細をはっきりさせようとすることは、暴力的な行為ではない。この種の「言論は暴力だ」という物言いが定着してしまったのは実に残念なことだ。トランスの権利(または他の周縁化された集団の権利)に反対する人にとっては、暴力に対する正当な抗議までをも「ヒステリーだ」と一蹴することがかなり簡単になってしまうからである。
ヒースによる批判はさらに具体的で辛辣だ。
トゥベルの論文の場合、撤回を要求する論拠が存在しなかった以上、ネットの陳情の目的は明らかに懲罰的なものだった。陳情が要求しているのは明らかに[論文の]検閲であったのに(それ自体はリベラリズムに反している)、撤回を要求する(こちらはリベラリズムに反しない)という体裁をとっていたのである。
陳情書における、論文の撤回を求めるための中心的な議論は、トゥベルの論文が生じさせた「危害」に関する問題や、論文の掲載が「危険」であるという主張によって構成されていた。多くの人は「フェミニスト学術誌に掲載された、アイデンティティと社会的構築に関するまったく抽象的な議論を扱っている論文が、どんな危害を生じさせられるというのだろう?」と訝しがった。一部の署名者はトランスジェンダーの自殺率の高さを指摘して、「トランスジェンダーの人々の[アイデンティティに関する]主張に疑問を投げかけたり議論をけしかけたりする者はトランスジェンダーの人々を自傷行為に追いやっている」と主張することで、陳情書を擁護しようとした。
この主張が間違っていることは明らかだ。自殺率の高い社会的グループに属する人を動揺させることが「危害」と見なされるべきであり、言論を撤回させることを正当化するのに十分な理由となる、という考え方における「危害」の解釈は擁護できるものではない。銃を所有する若い白人のアメリカ人男性の自殺率も非常に高いが、彼らの気持ちを傷つけることを懸念する人はいないだろう。より一般的に言うと、このようなかたちで「危害」が適用される範囲を拡げていくと、実質的には、あらゆる行為について「危害が含まれる」と解釈できるほどに「危害」の範囲が拡がってしまうのだ。そうなると、表現の自由は徹底的に弱められてしまう。署名者たちの主張では、明らかに、一部の人々が不快に感じる特定の意見を禁止するために「危害」という概念が恣意的に改変されているのだ。
ヒースやハイトは多くのトピックについて相反する意見を持っている。しかし、学問や言論の自由という問題については、両者ともがミルの『自由論』に言及している。
1859年に書かれた『自由論』は、現在に至るまで、表現の自由を支持する主張の支柱となっている。昨今における学問の自由や意見の自由(とその自由に迫っている危機)について考えるうえでも、ミルの議論に立ち戻ることは避けられない。
以下では、『自由論』の第二章「思想と討論の自由」を参考にしながら、「思想の自由市場」論と呼称されることも多いミルの主張について、その概要を解説しよう。
「思想の自由市場」論のあらまし
「思想の自由市場」論の考え方を簡単にまとめると、以下のようになる:ある物事についての事実や真理とはなにかを知ったり、なんらかの論点についての妥当な解答とはどういうものであるかを理解したりするためには、どんな意見でも発表できて、異なる意見を持つ者同士が議論できる場所が不可欠だ。
ある人が持つ意見や少数派の意見を多数派が「間違っているはずだ」と決めつけて、議論の俎上に載せもせずに排除することは認められない。わたしたちが真理にたどり着くためには、対立する意見をぶつかり合わせることで、より真理に近い意見はどちらかということを判断する必要がある。したがって、どんな意見を持つ人であっても、議論の場に参加できるようにするべきだ。異端である意見を排除すればするほど、わたしたちは真理から遠ざかってしまうからだ。
多数派の意見と少数派の意見のどちらが正しいか、あるいはどちらにも正しさがあるかどうかということ自体が、そもそも議論を経なければ判明しないことである。そして、実際の事態が以下の三つのうちのいずれであったとしても、少数派の意見を弾圧したり制限したりしてはならない、とミルは論じる。
一・多数派の意見が間違っていて、少数派の意見が正しい場合
二・多数派と少数派のどちらの意見にも、それぞれに正しさがある場合
三・多数派の意見が正しく、少数派の意見が間違っている場合
このうち、ひとつめとふたつめの場合については、少数派が意見を言う自由が守られるべき理由を理解するのは簡単であるだろう。
まず、そもそも、現時点で多数派である意見のほうが誤りであって、少数派の意見のほうが真理だということがあるかもしれない。天動説と地動説との論争をはじめとして、このような事態は歴史上に多々存在してきた。現時点で多数派である意見のほうが誤っているとすれば、少数派の意見を排除し続ける限り、わたしたちは永遠に真理にたどり着くことができなくなってしまう。
また、実際の議論においては、「片方の意見は完全に正解であり、もう片方の意見は完全に間違っている」という状況のほうが珍しい。多数派の意見はおおむね正しいが一部の誤りが含まれており、少数派の意見は基本的には間違っているが一部の真理を含んでいる(あるいはその逆)、という状況も多々あるだろう。このような場合には、意見をぶつかり合わせることで、多数派の意見のどこがどう間違っていて、どのように修正すればいいかが明確になる。逆に言えば、一見すると完全に間違っているような意見であっても、その意見を提示することが許されないような状況では、一見すると正しいように思える意見に含まれている一部の誤りが気付かれないままになってしまうのだ。
では、「多数派の意見が正しく、少数派の意見が間違っている場合」はどうだろうか?現時点の意見が正しいと確信が得られていて、少数派の意見が間違っていると判断することが可能である場合には、少数派の意見をわざわざ取り上げて相手にする必要がないのではないか?
ミルによると、「世間で受け入れられている意見は正しいが、その正しさをはっきりと理解し、深く実感するために、反対意見の誤りと闘うことが不可欠な場合」が存在する(ミル、p.112)。また、彼は以下のようにも書いている。
…どんなに正しい意見でも、十分に、たびたび、そして大胆に議論されることがないならば、人はそれを生きた真理としてではなく、死んだドグマ[教条]として抱いているにすぎない。(ミル、p.87)
現時点で世間に受け入れられている意見が誤りを含まない真理であったとしても、議論が存在しない場では、わたしたちはその真理が「なぜ正しいのか」を示す根拠を知ることができない。ある意見の「正しさ」を知るための最善の手段とは、反論をぶつけて、反論に対して矛盾なく解答されるかどうかを判断することである。議論を経ることなく、「この意見は正しい」と言い張られているだけでは、わたしたちはその意見の正しさを理解することも信頼することもできない。「正しいと言われているのだから正しいのだ」と無批判に受け入れてしまうか、「正しいと言われているが、ほんとうに正しいのか?」という不安を抱いたままになってしまうことになるだろう。
創造論の支持者がなくならない理由
哲学者のジョナサン・ウルフは、「多数派の意見が正しく、少数派の意見が間違っている場合」の具体的な事例として、進化論に関する問題を挙げている。
ウルフによるとダーウィンの理論にはおおむね正しいながらもいくつかの欠点があり、知性的で科学の訓練を受けた人であっても、ダーウィニズムを認めずに生物の起源に関する他の仮説を支持する、ということは有り得てきた。しかし、進化論を支持する生物学者たちは、「知性のある人ならみんなダーウィニズムを認めるだろう」と考えて、進化論に対する反論をまともに取り扱うことをしてこなかった。そのため、宗教的原理主義者がダーウィニズムに対する洗練された反論を提出したときに、生物学者たちはその反論に答えることができなかったのである。結果として、宗教的原理主義者は「ダーウィニズムは反論にも答えられない虚偽の理論だぞ」と喧伝して、自分たちの唱える「創造科学」の支持者を増やすことができてしまった。
創造論の科学的な価値は「ゼロ」であり、実際には進化論に釣り合うものではないことは、ウルフも認めている。だが、反論を相手にしてこなかった進化論は、ミルが言うところの「死んだドグマ」になっていたために、本来得られるべき支持者を失っていたのかもしれない。
……とはいえ、とくに科学や歴史などなんらかの形での「事実」を取り扱う学問において、正しい意見に対する反論を取り上げることについては、危惧を抱く人も多い。
現代の社会ではわたしたちは子供の頃から学校で科学的な思考の方法を教えられており、生物学や化学などについても基本的な知識は学ばせられるとはいえ、すべての人が成人した後にも科学的な思考方法や知識を保持しているとは限らない。わたし自身がいわゆる典型的な「文系」の人間であるからわかるのだが、多くの人にとっては、自然科学(や社会科学)には「ブラックボックス」のようなところがある。
わたしが科学的な知識を「事実」だと原則として受け止めているのは、たとえば生物学や天文学や薬品化学などの理論や研究の積み重ねを科学者のように理解しているからではなく、「科学的な学問である以上は厳密な議論や査読などのプロセスが存在しているはずであり、そこから生み出された知識は信頼に値するだろう」という、ある種の権威主義に基づいている。
とくに現代ではミルが生きた時代に比べても科学という制度が発展しており、幅広い分野の科学に関して骨子となる理論や最新の研究成果をすべての市民が理解するということは、そもそも不可能である。したがって、「この科学的知識は正しい」という了解が広く社会に行き渡るためには、「権威」に対する信頼という要素はどうしても必要になってくる。
しかし、たとえば、生物学者が創造論者の意見を取り扱って議論がはじまった段階で、生物学に詳しくない人たちからは進化論と創造論が「対等」な理論に見えてしまうかもしれない。生物学者たちは普段からの研究やこれまでの勉強を通じて進化論の科学的な厳密さを理解しており、創造論の間違いを理解できているとしても、第三者は進化論について生物学者のように厳密な理解をしているわけではない。そのため、創造論のように的外れな理論にも「もっともらしさ」を感じてしまう可能性がある。そして、進化論について反論がされているというだけで、その反論の質や妥当さとは関係なく「反論がされているんだから、進化論が真理だというわけではないんだな」と思ってしまうかもしれない。結果として、創造論者の意見を取り扱って反論するだけでも、「進化論は生物の起源に関する正確な理論だ」という世間の了承が揺らいでしまうおそれがあるのだ。
歴史修正主義は無視すべきなのか?
アメリカなどの国に比べると、日本では創造論の影響はそれほど強くない。しかし、主流派である意見と異端である意見が対等に扱われるだけでも問題が起こる分野は、他にもある。たとえば、医学や公衆衛生などにおいては、主流派とは異なる(そして、科学的にも間違っている)意見が流通するだけでも個人や社会にとって危害を及ぼすおそれがある。このような意見になんらかのかたちで制限を加えることは、「危害原則」によって認められるだろう。
具体例を挙げると、Twitterは新型コロナウイルスやそれを予防するためのワクチンに関して誤解を招く情報を発信することについて警告やアカウント凍結などのペナルティを課している[6]。とくに医学に関する情報について、プラットフォームやメディアは異端の意見を取り上げたり流通させたりすることに慎重になるべきだという点については、多くの人が同意するはずだ。
歴史学においても、異端である意見の扱いには慎重になるべきかもしれない。多くの歴史学者は、ホロコーストや南京大虐殺の存在を否定する「歴史修正主義者」の主張をまともに取り扱うべきではないと考えている。歴史修正主義者は歴史学の学位を持たない素人の著作家であることが多く、その主張は通常の歴史学の議論に求められるような厳密さや手続きに欠けていることが大半だ。また、歴史に関して正しく把握することを目的にするのではなく、個人的な利害や政治的なイデオロギーのために結論ありきの主張をしているとしか思えないような事例もある。さらに、すでに否定された議論が何度も繰り返し主張されることもある。そのような議論が歴史学者によって取り上げられて反論の対象にされること自体に、外側にいる人たちに「ホロコーストや南京大虐殺が存在したかどうかはまだ議論の対象になっているんだから、存在しなかった可能性もあるんだな」と思わせてしまう危険性があるだろう。
「歴史修正主義は無視するべきである」と歴史学者が考える理由について、武井彩佳は著書『歴史修正主義』のなかで以下のように解説している。
多くの人は無視するのが一番だと考えた。ホロコースト否定論に注目すること自体が、否定論者の宣伝になるからだ。歴史家ヴィダル=ナケは、ホロコースト否定論者について「月がチーズでできている」と主張するような人と譬えて、彼らと天文物理学者は議論できないと言った。ホロコースト否定論者は学術レベルを満たしておらず、対話自体を拒否すべきだということである。つまり、彼らを同じ土俵に上げてはならないということだ。
しかし、ホロコースト否定論者は月がチーズでできていると確信しているから、主張するのではない。月がチーズでできている「可能性」を繰り返すことで、人々の認識の揺らぎを呼び起こすことを意図している。真(ファクト)と偽(フェイク)のあいだの境界が曖昧になれば、当然視されているあらゆることの土台が緩み、その上にある社会制度が軋み出す。こちらの方がより深刻なのだ。(武井、p.113-114)
上記のような危惧があるために、歴史修正主義者の主張を取り扱う際にも、彼らの主張が主流派の歴史学の主張と「対等」ではないことを強調する必要がある、と言われることは多い。
2000年、ホロコーストを否認したイギリス人作家のデヴィッド・アーヴィングと、彼を批判する本を出版したアメリカ人歴史学者のデボラ・リップシュタットおよび出版社のペンギン・ブックスとの間での裁判が開廷した。2016年には、この裁判を題材にしたイギリス・アメリカ合作の映画が公開された。この映画の原題は『Denial(否定)』であったが、邦題が『否定と肯定』となったことについては、国内で批判が起こった。この邦題は、ホロコーストの事実に関する「否定論」と「肯定論」の主張が対等に並び立つものであるかのような印象を与えてしまうからだ。
ホロコーストの否定を法律で禁じるべきか?
前節で示した、歴史修正主義に対する歴史学者の危惧はもっともなものだ。
しかし、歴史修正主義者や反ワクチン論者などの主張を無視することや、主流派の意見と対等のものとして扱わないこと、彼らが意見を発表する自由を制限することにも、危険は存在する。
オーストリアではホロコーストの否定が法律によって禁止されており、これに違反したアーヴィングは2005年に逮捕されて2006年から3年間の服役を受けることになった。倫理学者のピーター・シンガーは、当時に発表した記事のなかで『自由論』を引用しながらオーストリアの法律や裁判所の判決を批判している[7]。シンガーが指摘するのは、アーヴィングを投獄することは、彼以外の否定派が抱いている「ホロコーストはなかった」という(誤った)信念を弱めるどころか強化してしまうことだ。アーヴィングの意見に少しでも賛同している人は「ホロコーストの事実の肯定派は、証拠や議論によってアーヴィングの主張に反論することができなかったから、逮捕や投獄という手段で彼の口を塞いだのだ」と考える可能性が高いだろう。
第二次世界大戦直後のオーストリアが民主主義を確立する過程においてはナチスの理念やプロパガンダを支持する言論を制限する措置も妥当であったが、現代のオーストリアでは既に民主主義が普及しておりナチズムが復活する危険は現実的なものでないから、言論の自由という理念を優先することのほうが重要である、とシンガーは論じる。ホロコーストの否認を禁止する法律はオーストリアのほかにもドイツ・イタリア・フランス・ポーランドに存在するが、この法律はどの国でも廃止されるべきだ。その代わりに、ホロコーストが起こったという事実や、その背景にある人種差別的なイデオロギーがなぜ否定されるべきかということについては、国家が責任をもって市民に教示しなければならない……というのが、シンガーの主張だ。
歴史修正主義に限らず、ワクチンに関する議論においても、異端の意見が主流派と対等に扱われなかったりメディアやプラットフォームで制限されたりすることを根拠として、異端の意見を抱いている人たちが「自分たちの意見は正しいものであるからこそ、証拠や議論によって反論することができない主流派は不当な手段によって自分たちの意見を制限しているのだ」と主張することはある。
とくに「事実」に関する問題については、多数派の意見が正しく少数派の意見が間違っている場合に論争が起きることにも起きないことにも、それぞれ特有の問題が存在する。論争を行うこと自体が誤った意見の宣伝になるかもしれないが、議論を制限することは誤った意見をより強固なものとするだろう。結局のところ、ある意見の誤りは、対立する意見を持っている人との議論によってしか示されないものだからだ。……しかし、誤りであると自分でわかっていながら「月がチーズでできている」と繰り返す人には、議論も無意味である。
この問題はかなり難しく、簡単に結論が出るようなものではない。たとえば、反駁された議論を何度も繰り返すような人の主張を主流派の議論に比べて格下げして扱うことや、事実について正しく認識することよりも個人的な利害やイデオロギーを目的として主張していると疑われる主張についてはその「疑わしさ」を周知するという措置は必要であるように思われる。一方で、シンガーが指摘しているように、特定の意見について刑事罰の対象にするなどの苛烈なペナルティを課すことは逆効果となる危険がある。問題となっている事実の種類や深刻さによって、適切な対処方法は異なってくるだろう。「危害原則」などを指針としながら、個別の事例ごとに最良のバランスを探していくしかなさそうだ。
「規範」に関する問題にはより公正な議論が必要となる
わたしが思うに、「思想と討論の自由」や「意見の自由」がとくに重要になるのは、「事実」よりも「規範」に関する問題だ。
世間の人々は、ある物事についてどう扱うべきか、ある問題についてどう対応するべきか、ある人たちと別の人たちの利害が対立しているときにどう解決するべきか、といった「〜べき」(規範)が関わるトピックについて、各々に異なる意見を抱いていることがある。このとき、事実についてのトピックのように、「多数派の意見が正しく、少数派の意見が間違っている」または「小数派の意見が正しく、多数派の意見が間違っている」ときっぱり判断できることはほとんどない。規範に関して人々が抱いている意見の大半には、それがどんなものであっても、なんらかの正しさや「理」が含まれている。そのため、規範に関して二つ以上の意見が対立しているときには、それらの意見のどれをも排除せずに公正な議論を行うことが必要とされるのだ。
アカデミアの世界に目を向けると、規範に関する学問では事実に関する学問のように「主流」と「異端」がはっきり分かれていないことに気づくだろう。
たとえば、倫理学や政治哲学の教科書では、功利主義やカント主義や共同体主義やフェミニズムなどの対立する理論が、いずれも並び立つ対等なものとして扱われている。
倫理学者や政治哲学者は、対立する様々な理論について学んだり検討したりしたのちに、論理や証拠や直観に基づきながら判断して、ひとつ(または複数)の理論について「この理論は他の理論に比べても正しいものだ」と結論づけて、その理論を支持することになる。彼は、自分が支持する理論の正しさを主張して、他の人たちも自分と同じ理論を支持すべきだと説得するだろう。……とはいえ、他の理論を支持している学者たちが自分と同じような過程を経たうえで「この理論は他の理論に比べても正しいものだ」と結論づけていることも、倫理学者や政治哲学者は織り込み済みだ。
基本的に、規範が関わる学問で行われる議論ではどちらかの主張が「正解」や「真理」であると客観的に判定されることは期待できない。さらに、「不正解」や「誤り」が確定するとも限らない。明らかに筋が通っていない理論や他の人たちから賛同される見込みがほとんどない理論、客観性や中立性のない恣意的な理論や自己中心的な理論は論駁されて退けられるだろう。だが、一定の妥当性や説得力があっていちど支持を得た理論は、その後も残り続ける(たとえば功利主義は20世紀の後半に勢力を失ったが、その支持者は残りつづけたし、21世紀になってからは勢いを取り戻している)。
規範に関する学問で行われる議論の意義は、道徳や政治といった物事についてとり得る考え方や、具体的な問題について抱き得る意見が明晰になることだ。考え方や意見を明確なかたちで主張して、他の立場からの批判や反論がなされることで、その考え方や意見の問題点や特徴が浮き彫りにされていく。あまりに筋が通っていない考え方や理に適っていない意見は反論に耐えられず、説得力がないことが周知されて支持者を失っていくだろう。一定以上の強度を持った考え方や意見についても、批判を受けて修正されたり、再反論のために考え方や意見の強みをよりはっきりとさせることが必要になったりする。この過程を通じて、議論に参加している人々は、自分自身と相手が抱いている考え方や意見についての理解を深めていくことができる。
そして、規範に関する議論で哲学者たちが提唱する理論や主張の大半は、世間において人々抱いている考え方や意見から乖離したものではない。哲学者の議論で行われているのは、世間の人々には見当もつかないような正解や真理をどこかから引っ張り出して教示することではない。哲学者たちが行っているのは、世間の人々が抱いている見解の矛盾を整えて論理的なものにしたり、その見解の背景にある前提や推論の構造を明示したり、その見解を他の物事に適用するとどんな判断になるのかを提示したりすることなのだ。
わたしたちは様々な考え方や意見を心の内に抱いていたり他人に言ったりSNSに書いたりするが、それらの意見は自分でもうまくまとめられていなかったり、論理がきちんとつながっていなかったり、本題とはあまり関係のない余計な主張が混ざっていたりすることが多い。しかし、書物や講義を通じて哲学者たちの議論に触れることによって、雑味を取り除いてクリアにまとめられた「説明」を得られて、自分の考え方や意見(とそれに対立する他人の考え方や意見)についてより明晰に理解できるようになるのだ。
なお、議論がうまく進行するためには、異なる立場の人たちが議論の場に参加することが必要になる。わたしたちが論敵の意見を自分の頭のなかで想像するときには、それを「論破」しやすいように相手の意見を非論理的なものや間違ったものとして想像する誘惑から逃れることは困難であるからだ。たとえば功利主義者しかいない場所でカント主義に対して反論しようとしても、功利主義者たちが「カント主義者たちの考え方はこのような議論に基づいており、カント主義者ならこの問題についてはこのような意見を主張するだろう」と想定するものは、カント主義者たちが実際に行なっている議論や主張からは必ずズレたものとなるだろう。一方で、議論の場にカント主義者が参加していれば、彼の主張を最善のかたちで聞くことができる。
人の意見は、それをほんとうに信じている人から直接聞くことができなければならない。本人なら自分の意見を熱心に語るし、なるべくこちらにわかってもらえるよう精一杯努力するはずだ。
つまり、人の意見はもっとも納得できる形で、そしてもっとも説得力のある形で受けとめなければならない。その問題を正しく眺めようとするときに遭遇し、対応せざるをえない難事が、どれぐらい手強いものなのか、きちんと実感しなければならない。それを避けていたら、自分がいだいている心理のうちにある、その難事に対応してそれを除去してくれる部分を、けっしてほんとうには把握できないであろう。(ミル、p.91 – 92)
シンガーの「障害者差別」問題
上述したことは、倫理学や政治哲学の理論に関してだけでなく、規範が関わる具体的な問題についても当てはまる。
たとえば、シンガーが『実践の倫理』などの著書で行なった主張は様々な批判の対象となってきた。そのなかでもとくに問題となったのが、「両親の同意があるなどの条件が満たされるとき、重度の障害を持つ新生児を安楽死させることは許容されるべきだ」という主張だ。
新生児の安楽死に関するシンガーの議論を詳しく紹介することは本稿の目的ではないが、彼の主張のポイントを簡単に紹介すると、以下のようになる。
まず、新生児は意識や自己認識に関する能力が未発達であり、「自分とはこういう人間だ」「自分はこれからこう生きたい」という信念や選好を持っていない。このような存在が自分自身の「生」について利益を持っているとは言いがたいから、新生児を殺害することは、成長した子供や成人を殺害することのようには不当ではない。むしろ、意識や自己認識に関する能力という点では、新生児は成人や子供よりも胎児のほうにはるかに近い。したがって、新生児を殺害することの不当さは、妊娠中絶によって胎児を殺害することの不当さとほぼ同等である。だから、特定の条件で胎児の殺害が許容されるなら、同じ条件で新生児の殺害も許容されるべきだ。
また、一部の親は、重度の障害を持った子供を産んで育てることに不安やプレッシャーを感じて、その子供の代わりに健常な子供を新たに妊娠して育てることを望む。そして、重度の障害を持つ子供よりも健常な子供のほうが、本人がその人生で幸福を感じられる見込みは高いだろう。これらの理由から、出生前診断によって胎児に重度の障害があると判明したとき、妊娠中絶によってその胎児を殺害することは許容されると考えられる。それならば、重度の障害がある胎児と同じように、重度の障害を持つ新生児を安楽死させることも認められるべきである。(シンガーの主張を要約)
言うまでもないだろうが、この主張は「障害者差別」であるとして、アカデミアの内外から批判されてきた
倫理学や社会学や障害学などのアカデミックな領域においては、シンガーの議論に反論する論文や書籍は多数発表されている。また、その主張が原因で、シンガーが公的なイベントで自身の意見を発表することはたびたび中止に追い込まれている。たとえば、1991年にドイツの哲学シンポジウムで行われる予定だった講演は学者や市民グループによるボイコットのために中止されて、2015年にも同じくドイツの哲学イベントに招待されていたのが取り消されてしまった[8]。また、2020年にも、ニュージーランドで行われる予定だった講演が現地の市民やメディアによる批判のために中止されたのだ[9](なお、このように抗議運動によって講演を取り止めさせて、問題があるとされている意見を持つ人が公の場で発言することを妨げる活動は、「ノー・プラットフォーム」と呼称されている)。
しかし、仮にシンガーの主張が障害者差別であるとしても、その議論は現時点の社会で一定以上に受け入れられている意見を洗練させたものであることには留意すべきだ。結局のところ、出生前診断によって障害があると判明した胎児を中絶させること(選択的中絶)は、現在の社会でも許容されているのだ。シンガーの主張は選択的中絶の背景にある論理を一歩進めて、胎児だけでなく新生児もこの行為の対象にされるべきである、と論じるものである。
もちろん、現在の社会で認められている選択的中絶についても「障害者差別」や「生命の選別」であると批判されているし、選択的中絶を禁止するために法律や社会のルールを変えるべきだという声もある。しかし、差別であるかないかに関わらず、医療関係者や市井の人々の一部は「出生前診断に基づく障害児の選択的中絶は許容される」という意見を抱いている。この時点で、選択的中絶の問題は議論の対象にならざるを得ない。選択的中絶を否定する側にも肯定する側のどちらにもそれぞれの「理」や「正しさ」があるだろうから、両者の主張について論点や前提や議論の筋道を明示したうえで、それぞれの主張の良し悪しについて考える必要がある。
そして、シンガーが著書や論文で行っている主張は、選択的中絶を肯定する側にとっては自分たちの主張を明確に認識するために役立つし、選択的中絶を否定する側にとっては相手の主張を明確に認識するために役立つであろう。つまり、シンガー(や他の生命倫理学者たち)が「重度の障害を持つ新生児の殺害は許容されるべきだ」という主張を展開する自由が保証されていることは、わたしたちのだれにとっても有益であるのだ。
自分が言いたいことしか知らない人は、ほとんど無知にひとしい。彼の言い分は正しいかもしれないし、誰も論駁できなかったかもしれない。けれども、彼もまた反対側の言い分を論駁できず、あるいは相手の言い分の中身も知らないなら、彼がどちらの言い分を選ぶにせよ、その根拠はゼロである。(ミル、p.91-92)
また、シンガーの主張は「国家や社会の利益のために障害者は殺害するべきだ」というナチズム的な思想に結び付けられることも多い。2016年に起こった相模原障害者施設殺傷事件に関しても、犯人の植松聖とシンガーの思想は類似していると主張する議論は国内や海外で散見された[10]。
しかし、シンガーが主張しているのは「障害を持って生まれてくる当人」「生まれてくる障害者の両親」「障害を持った人を中絶・安楽死した場合に代わりに生まれてくるであろう存在」それぞれの幸福や利害を考慮したうえで障害を持つ胎児や新生児の殺害が許容される(場合がある)ということであり、「国家や社会の利益のため」に殺害することを認めるものではない。
この違いがシンガーの議論では明示されていることも、選択的中絶の肯定派と否定派の双方にとって有益だ。肯定派は、選択的中絶を認めながらもナチズム的な思想に反対するという考え方が存在し得るのを知ることができる。もし彼がシンガーの主張を知る機会がなければ、自分自身で誤った前提や推論に基づく主張を展開して、「選択的中絶を認めるなら、国家や社会の利益のために障害者を殺害することも認めるべきだ」という信念を抱くようになってしまっていたかもしれない。
否定派は、ナチズム的な思想に基づかずに選択的中絶を擁護する考え方が存在し得るのを知ることで、自分たちが批判している意見の実体についてより深い理解を得られる。もし否定派がシンガーの議論に触れずに「ナチズム的な思想を論駁すれば選択的中絶を許容する議論も否定できる」と考えていたなら、ナチズム的な思想とは異なる理路によって選択的中絶を許容している人々の意見に反論することができず、有効な主張を展開できなくなるだろう。そうすると、「選択的中絶は禁止されるべきだ」という彼らの意見の説得力も失われて、その意見が社会的に認められる可能性は低くなってしまう。
意見の弾圧は「地下に潜らせる」結果をもたらす
ミルは、「真理は常に迫害に打ち勝つから、迫害は真理が通過すべき試練である」という意見に対して、以下のように反論している。
真理は迫害されて傷つけられるようなものではないから、真理への迫害は不当なことではない、と主張する理論である。われわれは、この理論が新しい真理の受け入れに積極的に敵対するものだと批判することはできない。しかし、人類に新しい真理をもたらした人への迫害を許容する点は賛成できない。(ミル、71)
シンガーが意見を発表したことについて、講演を中止に追い込むなどの手段でペナルティを課すことは無益だ。彼が論文や著作で意見が発表される自由は守られているとしても、講演によってそれをさらに広く知らしめる権利は失われてしまう。それ以上に、アカデミックな手続きを経た反論ではなく非正式的な抗議によって意見や人格が非難されることは、その意見を発表し続けるモチベーションを彼から失わせるかもしれない。さらに、シンガーがキャンセルの対象になっているのを目にした彼よりも立場の弱い学者や若い学者は、「障害者差別」と批判される部分のある意見を持っていたとしても、その意見を論文などのかたちで発表するのを尻込みするようになるはずだ。
とくに規範に関する意見を弾圧することは、その意見を抹消すると言うよりも、意見を「地下に潜らせる」という結果をもたらす。もしシンガーや他の生命倫理学者たちが障害を持つ新生児の安楽死や出生前診断に基づく選択的中絶を擁護する議論を発表しないようになったとしても、それらの主張と類似していたり共通していたりする意見は世間に残り続けるだろう。アーヴィングが逮捕されたのを見たホロコースト否認論者と同じように、彼らは自分たちの意見をますます強めるかもしれない。「選択的中絶を批判する人たちと議論しようとしても、人格非難をされたり不当な方法で黙らせられたりしてしまうのだ」と考えた人たちは、表向きに意見を発表することを控えるようになるかもしれない。だが、自分たちの意見に基づいた行動は粛々と実践し続けるだろう。
これは、選択的中絶に限らず、人々の意見が割れていて議論の対象となっているどんな問題にも起こり得ることだ。
たとえば、トランスジェンダー女性の利害とシスジェンダー女性の利害をどう調整するか、両者の権利が対立しそうな場合にはどう調停すればいいか、という問題に関する議論が現代の社会で必要になっていることは明らかだ。言うまでもなくトランスジェンダー女性はマイノリティであり、自身のアイデンティティが社会的・制度的に承認されていないことで、さまざまな不利益を被っている。その一方で、シスジェンダー女性のなかには、トイレや更衣室や刑務所などの女性専用スペースに身体的には男性である人が入れるようになることで自分たちに危険が及ぶことや、トランスジェンダー女性が女子スポーツに参加することで身体的には女性である人が活躍する機会が奪われることを懸念する人がいる。
トランスジェンダー女性やその支持者は、シスジェンダー女性の抱いている懸念が誇張されたものであることを指摘したり、その懸念は差別的な偏見に基づいたものであると論じたりすることもある。……しかし、仮に差別的な偏見に基づいたものであるとしても、実際にかなり多くのシスジェンダー女性がその懸念を抱いているという事実は無視することができない。
シスジェンダー男性であるわたしの目から見ても、この問題は選択的中絶の問題と同じように未解決だ。どちらの側の意見にも「理」や正しさが存在しているようであり、どちらの意見が正しいかを判断したり利害を調停する落としどころを見つけたりするためには議論が必要になる。
だからこそ、トゥベルやストックの論文や主張をオープン・レターによって非難して、彼女たちの意見にペナルティを与えることは無益なのである。懸念を抱いているシスジェンダー女性たちは、「自分たちの意見は哲学者にすら反論できないものであるから、非正式的な手段で黙らせられたのだ」と思うようになるだろう。彼女たちはもはやアカデミックな議論に期待を抱けなくなり、自分たちだけで練り上げた議論を喧伝するようになる。だが、その議論はアカデミックなものとは異なり反論や批判を受ける過程を経ていない独善的なものだ。また、事実に関する問題で彼女たちが参照する情報も、一方の側によった信頼性の薄いものとなるだろう。そうなると、トランスジェンダー女性に対して彼女たちが抱いている懸念は消えるどころか増してしまい、危うく過激なものに変化する可能性のほうが高い。
論争の片方の側に「自分たちの意見は相手側の意見と比べて対等に扱われておらず、不利で不公平な状況で議論を強いられている」と思わせてしまうのは、もう片方の側にとっても有害なことなのだ。
議論につきまとう「報酬」の問題
ここまでは、主に大学やアカデミアにおける「思想と討論の自由」について扱ってきた。
ミルが『自由論』で扱っている対象はアカデミアに限らず、市井の議論やメディアにおける議論についても想定されているだろう。……とはいえ、昨今の状況を見ると、全てのメディアにおいて「思想と討論の自由」が無制限に擁護されるべきだと言いづらいこともたしかだ。
たとえば、TwitterをはじめとしたSNSで行われる「議論」が有害なものとなりやすいことは、いまや誰の目にも明らかである。プラットフォームの構造のために、Twitterでの議論や極端なものになりやすく、特定の個人の人格を非難する攻撃も引き起こしやすい。妥協点を探ったり相手の主張を理解したりしようとする穏当で前向きな態度よりも、勢いのいい言葉で相手の主張を切り捨てたり妥協することなく自分たちの側の要望を押し通したりする態度のほうが、リツイートや「いいね」やフォロワー数の増加などの「報酬」を得られやすいからだ。
結果として、Twitterでの議論の大半は、議論の相手ではなく「自分たち」のほうを見ながら行われることになる。また、公益のことを考えながら長期的に利害の妥協や調整を測ることよりも、相手を「論破」することで短期的に「自分たち」が気持ち良くなることのほうを優先してしまう。これらの現象には「集団的分極化」や「フィルター・バブル」などの名前も与えられてきた。「ハッシュタグ・アクティビズムが世の中を変える」などと騒がれることもあるが、いまや、見識ある人にとって「Twitterやその他のSNSでの議論が公益に資する」という主張はとても信じられないものになっているだろう。
とはいえ、主張には「報酬」が伴うために、客観的な事実に基づいた議論を行うことや自分の意見を真摯に表現することよりも、より多くの「報酬」を得るために本人も本気で思っていない主張を展開する……という問題は、インターネット以前から存在していた。原稿料や印税を得たり読者数を増やしたりするために過激な意見を発表したり虚偽を伝えたりするという問題は、著作家やジャーナリストという職業には宿命的につきまとっている。
たとえば、著作家であると同時にブロガーであるわたしにとっても、「報酬」のことは常に頭の片隅にある。ブログを書くときにはSNSでシェアされてPVが付いたほうがそうでないよりもうれしいが、そうなると、「極端な主張や人々の感情を煽る文章を書いたほうが話題になるぞ」という誘惑が生じるのだ。いちおう自分としてはその誘惑を振り切っているつもりであるが、それができるのは、わたしのブログにはアフィリエイトがほとんど貼られてなくて金銭的な「報酬」が発生しないからだ。広告収入を得ることや知名度を上げることを目的としてブログを書いている人は、より多くシェアされてPVが付くことを目的にして書かざるを得ないだろう。このとき、自分の書いている内容が事実や堅実な論理に基づいているかどうかは後回しにされてしまう危険がある。
SNSやブログほどではないにせよ、同様の問題は論壇誌やその他の雑誌にも付きまとう。大半の論壇誌には左翼的であったり右翼的であったりなどの「色」が付いている。多くの読者は、自分の価値観や政治的傾向と一致する雑誌を購入するものだ。そのため、ある雑誌で登用される著作家たちの政治的傾向には偏りが生じるし、著作家たちのほうも雑誌の「色」を意識しながら自分の原稿の内容を調整したりすることになる。……すべての論壇誌が公平で中立的なものになると雑誌間の違いがなくなり多くの雑誌が潰れしまうだろうから、マーケティングのために雑誌に「色」が付くのは仕方がないことではある。また、論客や論壇誌がそれぞれの旗色をあえて鮮明にすることで議論が活発化する、という側面もあるだろう。しかし、事実や客観性を重視することや、自分の意見を隠すことなく公開するという「真摯さ」は失われざるを得ない。
ミルの主張する「思想と討論の自由」が成立するためには、議論の当事者の双方に「真摯さ」が存在することが前提となる。そして、わたしが考えるに、大学や学会などのアカデミアとは議論における「真摯さ」を担保するための制度であるのだ。
論文を書いて発表することとブログや雑誌に記事を書くこととの大きな違いが、論文で書かれている意見や結論の内容は「報酬」と直結しないことである。アカデミアが適切に機能しているなら、論文は結論によって評価されるのではなく、結論を出すまでの手続きの厳密さ、議論の構成、正確性や新規性などの基準によって評価されることになる。ある論文が高い評価を受けたとしても、その論文の結論が査読する人や掲載誌の読者にとって都合が良かったり快適だったりするからではなく、結論に至るまでの立証や議論の構成が優れているということが理由であるのだ。逆にいえば、基準を満たしさえしていれば、研究者は「読者にどう思われるか」ということを気にせずに主張を展開することができる。
このことは、社会のなかで未解決となっている問題や深刻な利害の対立が発生している問題ほど、SNSや論壇ではなくアカデミアで議論したほうがいい理由にもなる。シンガーの著作やトゥベルの論文のように、学問的な基準を満たす議論であっても結果として特定の人々にとって不愉快であったり「差別的だ」と思われたりするような主張になることはあるだろう。しかし、最初から誰かを傷つけることを意図している論文や差別的なメッセージを喧伝することを目的としているような論文は、そもそもアカデミックな基準を満たさず、却下されてどこにも掲載されない可能性が高い。論文を書く人はまず自分自身が抱いている意見について冷静に検討したうえで、それでも「書くべきだ」と判断した意見を、客観的で公正な基準を満たしながら筋道立てて書くことになる。結果として、その意見がどんなものであれ、アカデミックなかたちで書かれた意見はSNSや論壇に掲載されるものと比べて留保や条件の多い穏当なものになる。だからこそ、アカデミックな場での議論とはSNSや論壇に比べてはるかに安全なものとなるのだ。
したがって、シンガーやトゥベルの議論を「マイノリティに対して攻撃的なメッセージが掲載されているから」という理由でペナルティを与えて、アカデミックな場から制限したり排除したりすることは本末転倒だ。先述したように、意見そのものを封殺することはできない。自分たちの意見がアカデミックな場で制限されたり排除されたりするほど、同じ意見を持っている人たちは論壇やSNSという場で主張を喧伝するようになるだろう。そこで行われる議論は、はるかに危険(で非生産的)なものとなる。
アカデミアとは「言論の闘技場」のようなもの
ここまでのわたしの議論が正しければ、思想と討論の自由は、なによりもアカデミックな場で守らなければならない。規範に関する議論においては、アカデミアとは一定の基準に従いながら意見を交わし合い論争を行なう、「言論の闘技場」のようなものである。しかし、これまでに見てきたように、議論の手続きではなく主張の内容や結論を理由にして、議論による反論ではなくオープン・レターや抗議運動などの方法で特定の意見を抑圧しようとする傾向は、アカデミックな場においてこそ強くなっている。
本来、アカデミックな議論に参加する人には、自分のものと異なる意見や自分にとって不愉快な意見にも向きあうことについての準備や覚悟が要請されるはずだ。だが、本稿の前半でヒースが指摘していたように、「危害」の解釈を拡大することで異なる意見を抑圧するという方法が定着してしまった。
また、大学院に進学して学者を目指す人のなかには、アカデミアを「闘技場」ではなく「避難所」のように捉えている人が増えているようだ。世間で傷つきやすい立場にいる人や差別を受けやすい立場にいる人のことを守って、彼らの意見や利害を積極的に代弁して、彼らが安心感を持って過ごしやすい場にすること。あるいは、自由市場や資本主義のもとでは肯定されづらいオルタナティブな価値観を擁護して、多様性を担保する場であること。そういうことが大学の目的であると定めて、その目的に反する議論や意見には抗議や制限を行なう必要がある、と考えている人が増えているのである。
「道徳的・政治的な目的のためには、アカデミックな場でも議論を制限することが必要になる」という発想は、見かけ以上に浸透している。ハイトが「社会正義大学」の守護聖人としてマルクスを挙げており、ウルフも「自由」というトピックに関してミルとマルクスを対比させていることは示唆的だ。政治科学者のエイプリル・ケリーウォスナーが指摘するのは、「新左翼の父」と呼ばれているヘルベルト・マルクーゼが唱えた「寛容」に関する議論が、現代の学者や若者の多くに受け入れられているということだ[11]。マルクーゼは、権力や立場の差を考えずに全ての言論の自由を等しく認めることは、実際には強者を利して弱者にとって不利益をもたらす「抑圧的寛容」であると論じた。彼によると、右派の言論を認めず左派の言論に対してのみ寛容になる「開放的寛容」こそが真の寛容なのである。
マルクーゼの名前が出るとは限らないが、同様の議論をする人は現代にも多々いる。彼や彼女は、マジョリティとマイノリティとの間には権力勾配が存在するから、マイノリティの意見を優遇することでようやく対等な議論が成立する、と論じる。したがって、シンガーやトゥベルのような「抑圧的」な意見を排除することも、対等な議論のために必要とされる、と主張するのだ。
「開放的寛容」の問題点は、「右派の言論は制限されるべきだ」ということが議論する前から前提されていること、そしてこの前提によって議論自体が制限されるために、そもそもの前提が正しいかどうかを確かめる手段がなくなることだ。このような事態は、まさにミルが『自由論』で批判しているものである。
もちろん、封ずる側は相手の意見の正しさを否定する。しかし、自分たちはけっして間違わないといえるはずもない。人類全体に代わって問題を判定したり、ほかのすべてのひとびとから判断の手立てを奪ったりする権限もない。
その意見は正しくないと確信しているからといって、意見の公表を禁ずるのは、自分たちにとって確実なことは絶対的に確実なことなのだというに等しい。議論を封ずることは自分たちは絶対に間違わないというに等しい。(ミル、p.47)
傷つきやすい立場や差別を受けやすい立場の人が安心感を抱ける場所が必要だとは、わたしも思う。しかし、アカデミアが率先してそのような場になろうとすると、それだけで、アカデミアは「闘技場」という本来の役割を果たせなくなってしまう可能性が高いのだ。
「傷つき」や「抑圧」に配慮しすぎることの危険性
最後に、「危害原則」の問題に戻ろう。
ヒースが論じているように、「言論によって不安にさせられること」が危害であると主張して、表現を制限する根拠にしようとすることは、最近の欧米の若者の間で顕著となっている。しかし、同様の発想は1990年代から存在していたようだ。
ジャーナリストであり同性愛者の権利を守るための社会運動も行なっているジョナサン・ローチの著書、『表現の自由を脅すもの』の原著が出版されたのは1993年だ。本書のなかでローチが問題視しているのは、当時のアメリカにおいて「あなたは他人を言葉でもって傷つけてはならない」という原則が浸透していったことである。
彼によると、正しい知識にたどり着くための研究や討論においては、どこかで誰かが傷つく事態は必ず発生する。その「傷つき」の対象とは人種的マイノリティや性的マイノリティには限らない。たとえば、一見すると人の生活やアイデンティティと関係のなさそうな地球科学や生物学の研究ですら、地球平面説や創造論を信じるキリスト教原理主義者を傷つけてしまう可能性がある。また、1991年にサルマン・ラシュディの小説『悪魔の詩』の翻訳者が刺殺された事件をはじめとして、イスラム教原理主義者たちは物理的な暴力をもって実際に表現の自由を脅かしてきた。
キリスト教やイスラム教の原理主義者が傷つくからといって、思想と討論の自由が制限されることがあってはならない。同じように、マイノリティが傷つくからといって、思想と討論の自由が制限されることがあってはならない。ローチの主張は、他人が傷つくことに配慮するのに慣れ切った現代のわたしたちの目からすると、かなりタフで強烈なものだ。
私は、人道主義者や平等主義者が、道徳的に高い立場にあるという主張は偽りであるということ、そして、人を傷つけることを許容、ときには推奨しさえもするという誓約をもつ知的自由主義が、唯一の本当に人間らしい体制であるということを示したいと思う。私は、「言葉で傷つけられた」人々には、補償という形で何かを要求するという道徳的権利はいっさいないということを示したいと思う。自分が傷つけられたというので何かを要求する人に対する正しい答えとは何か。それは、「お気の毒、だけどあなたは生きていくでしょう」というに尽きる。「人種差別主義者」「同性愛恐怖者」「女性差別主義者」「神を冒瀆する者」「共産主義者」、あるいは、どんな化け物であろうと、これらのものを処罰せよと主張する人たちはどうかといえば、彼らは知的探求の敵であり、彼らの騒がしい要求は全く無視されて然るべきであり、いっさい付き合ってはならない。(ローチ、p.44)
その一方で、彼の議論には30年後の現代を予言していたかのような鋭さもある。
それが無神経なように聞こえるとしても、 気持ちを傷つけられない権利というものが確立されると、より礼儀正しい文化に至るどころか、誰が誰にとって不愉快だとか、誰がより多く傷つけられていると主張することができるかといったことをめぐって声高な泥仕合が一杯起きるだろう。(ローチ、p.205)
ローチは、言葉による攻撃と物理的暴力が同等のものと見なされるようになると、「つらくてきつい批判」も暴力として扱われるようになるだろう、と指摘する。そうすると「科学」(学問)そのものが暴力として見なされるようになり、「人を傷つける思想や言論を取り除く権限を持った当局者」が立てられて、意見が権力によって取り締まられるようになるだろう(ローチ、 p.207)。これは、現在のアメリカの大学で起こっている状況を、多かれ少なかれ言い当てている。
わたしが『表現の自由を脅すもの』を最初に読んだときには、『自由論』に比べても過激であるし、現代には受け入れられない議論であると感じた。しかし、現代の欧米や日本のアカデミアで起こっている様々な事態を見聞しながらこの二冊の本を読み返しているうちに、「傷つき」や「抑圧」に配慮することの危険性を以前よりも強く認識するようになったのだ。
おそらく、SNSや論壇を含めた市井の議論では、わたしたちは他人を傷つけることに関して十分に警戒するべきだ。市井の議論でわたしたちが発する主張は粗雑であったり過剰であったりするし、「報酬」に対する意識などの不純な動機も含まれている。そのようなとき、わたしたちは論敵と見なした相手や自分とは異なる立場にいる人たちのことを、不必要に傷つけてしまう可能性が高い。……したがって、市井の議論においては、「危害原則」が出番となる場面も多いだろう。反ワクチンや誤った医療情報を喧伝する主張に対する制限をはじめとして、特定の場面においてはある種の意見を発信する自由は制限するべきかもしれない。
しかし、アカデミックな議論を危害原則に基づいて制限することは、ほとんどの場合は認められないだろう。ある種の議論においては、学問的な基準を満たしており、だれかを傷つけることを目的としたものではないとしても、結果としてだれかを傷つけてしまうことは避けられない。そして、たとえ傷つくのがマジョリティや原理主義者ではなくマイノリティであるとしても、ローチの言うように、それは「思想と討論の自由」を守るために必要とされるコストなのだ。……この自由を捨ててしまったら、アカデミアの存在意義はなくなり、民主主義の理念は形骸化して、わたしたちの社会は現在よりもさらに悲惨な場所になってしまうだろう。
参考文献:
『自由論』ジョン・スチュアート・ミル(著)、斉藤 悦則(訳)、光文社古典新訳文庫、2012年。
『歴史修正主義 ヒトラー賛美、ホロコースト否定論から法規制まで 』武井彩佳、中公新書、2021年。
『政治哲学入門』ジョナサン・ウルフ(著)、坂本 知宏(訳)、晃洋書房、2000年。
『表現の自由を脅すもの』ジョナサン・ローチ(著)、飯間良明(訳)、角川選書、1996年。
[1] https://sites.google.com/view/trans-phil-letter/
[2] https://nymag.com/intelligencer/2017/05/transracialism-article-controversy.html?mid=twitter-share-di
[3] https://heterodoxacademy.org/blog/on-rebecca-tuvel-consequences-of-orthodoxies-in-academia/
[4] https://heterodoxacademy.org/blog/one-telos-truth-or-social-justice-2/
[5] https://theline.substack.com/p/joseph-heath-woke-tactics-are-as?s=r
[6] https://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/medical-misinformation-policy
[7] https://www.project-syndicate.org/commentary/free-speech--muhammad--and-the-holocaust-2006-03
[8] https://theconversation.com/cologne-peter-singer-and-disinvitations-43412
[9] https://www.theguardian.com/world/2020/feb/19/peter-singer-event-cancelled-in-new-zealand-after-outcry-over-disability-stance
[10] https://www.sbs.com.au/news/the-feed/article/is-peter-singer-dog-whistling-perpetrators-of-disability-hate-crime/kha1sizmr
[11] https://quillette.com/2016/03/01/how-marcuse-made-todays-students-less-tolerant-than-their-parents/


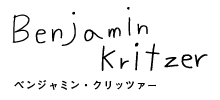 1989年生まれ。批評家。立命館大学文学部英米文学専攻卒業(学士)、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科卒業(修士)。
1989年生まれ。批評家。立命館大学文学部英米文学専攻卒業(学士)、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科卒業(修士)。