女性も男性も、それぞれ不利益を受けている日本
見方によっては、日本で女性が不利益を受けていることは明らかだ。
世界経済フォーラムが毎年発表している「ジェンダー・ギャップ指数」の2021年版によると、日本の順位は156か国中120位であり、先進国のなかでは最低クラス、東南アジア諸国よりも低い[1]。例年、日本ではとくに「ジェンダー間の経済的参加度および機会」および「政治的エンパワーメント」の指標が低いことがポイントだ(逆に、「教育達成度」と「健康と生存」の数値は他の先進国とほぼ変わりない)。日本の女性は、政治や経済という「公」の領域から、いまだに締め出されつづけている。
また、2021年に小田急電鉄小田原線で起こった刺傷事件では、容疑者が取り調べで「幸せそうな女性を見ると殺してやりたいと思うようになった」と発言したことから、女性という属性をターゲットにしたヘイトクライムや「フェミサイド」であると論じられた[2]。自身も強姦事件の被害者であるジャーナリストの伊藤詩織も論じているように、日本は性犯罪の被害者に対する社会的サポートに欠けているうえに、刑法で性犯罪の加害者の罪を処罰することも難しい制度になっている[3]。日本の女性は、痴漢や強姦から殺人まで、さまざまな性犯罪や暴力犯罪のリスクに晒されていると言えるだろう。
その一方で、見方によっては、日本では男性が不利益を受けていることも明らかだ。
厚労省の発表している自殺者の年次推移を見ると、1978年から2020年まで、各年の男性の自殺者数や自殺率は女性の2倍前後でありつづけてきた[4]。ただし、近年のアメリカでは男性は女性の3倍、ヨーロッパや南米やアフリカなどのほとんどの国でも男性の自殺者数は女性の2倍や3倍であり、他の国に比べると日本は女性の自殺率も高いほうだ。とはいえ、2016年の調査によると日本の自殺率は約90ケ国中6位であり、その自殺者のおよそ7割が男性であることを考えると、日本の男性は世界の男女に比べても自殺のリスクに晒されているとは言えるはずだ[5]。
また、日本の男性は、女性よりも不幸感を抱いている。2017年の世界価値観調査に基づいて男性の幸福度と女性の幸福度を比較してみると、日本では女性のほうが幸福度が高く、男性との差は世界で2位だ[6]。さらに、OECDが発表している幸福度白書の2020年版(How’s Life 2020)における「ネガティブな感情の抱きやすさ(negative affect)」の指標を見ると、他の国々では女性のほうがネガティブな感情を抱きやすいのに対して、日本だけが唯一、男性のほうがネガティブな感情を抱きやすくなっている[7]。男性の不幸さという点では、日本は世界でも際立っているのだ。
「変えたほうがいい」という点で一致はしているものの
このように、日本では女性も男性のどちらも不利益を受けている。これは、矛盾した事実であるのか?
「矛盾していない」と答えることもできるし、そう論じられることも多い。
たとえば、社会学者の筒井淳也は、ジェンダー・ギャップと男性の幸福度の低さの両方の問題に触れながら、海外に比べて「男性的な働き方」がスタンダードとなりつづけていることが両方の問題の原因であると指摘している[8]。ジェンダー・ギャップ指数の「経済」の指標ではとくに「管理職ポジションに就いている男女の人数の差」のスコアが低いが、これは、日本の管理職は長時間労働や転勤など「専業主婦ありき」の働き方をするという前提がいまだ根強いためである。家事育児との両立も困難になるから女性は管理職になるのをためらい、男性は「自分が稼がなければならない」というプレッシャーを感じながら過酷な労働に耐えることになる。結果として、女性は経済の領域から締め出されて、その領域のなかにいる男性は不幸を感じる、という状況ができあがってしまうのだ。
つまり、性別役割分業を前提とした昔ながらの労働モデルは、キャリアアップを困難にさせたり経済的な領域で活躍することを尻込みさせたりすることで、女性に「機会の不平等」をもたらしている。一方で、男性は長時間労働や転勤によって体力・精神力を磨耗させられたり家族と関わるタイミングを奪われたりすることで「不幸」にさせられている。かたちは異なっているが、このどちらも不利益や被害ではある。
また、多くの女性はどこかで結婚して経済的に夫に依存せざるをえないから、人生の設計図を自分の意志で描くという意味での自由が制限されていると言える。そして、生活時間の大部分が労働に奪われたりキャリアのために夢を諦めさせられたりするという点で、男性の自由もまた制限されているのだ。ひとくちに「自由」と言ってもその定義や内実は多様であり、女性と男性では制限されている自由の種類が異なるといえそうだが、いずれにせよ、自由を制限されることも不利益や被害だ。
女性と男性が被っている不利益の原因が同じである場合には、話は簡単だ。改善できるのであれば、日本的な労働モデルは改善したほうがいいのだろう。実際、このことには多くの人が同意している。日本的な「メンバーシップ型雇用」ではない欧米の「ジョブ型雇用」にも特有の問題点があることが指摘されているとか、あまりにも長く存在してきたモデルであるうえに既存の権益や慣習が深く絡み合っているためにどこから手をつけていいわからないとか、さまざまな課題や困難が待ち受けてはいるのだが、ともかく変えたほうがいいという点では男女の双方が同意しているのだ。
だが、男女の受ける不利益の原因が異なる場合には、話はややこしくなる。
ゼロサムゲームになってしまう理由
どちらの性別にせよ、自分たちが被っている不利益について訴えて改善を要求すると、もう片方の性別が「こっちの不利益のほうが深刻なのだから、こっちの原因のほうを先に改善せよ」と言ってくる。「自分が不利益を被っている」という認識を強く抱いている人は、物事についてゼロサムゲーム的に考えることが多い。別々の問題のそれぞれの原因について並行して対処をすすめることが可能だというイメージを持たず、原因に対処するためのリソースが有限であり、奪い合わなければならないかのようなイメージを持つのだ。なかには、自分の被っている不利益が放置されること以上に、他人の不利益が改善されそうになることを問題視して騒ぎ立てる人もいる。
そして、問題の原因が共通している場合にすら、互いに互いを責め立てあうこともある。日本の労働モデルによってキャリアを制限されてしまった女性のなかには「自分が会社で活躍する機会は男性に奪われた」と考える人もいるようだ。逆に、長時間労働によって疲弊した男性のなかには「自分がこんなに苦労して不幸になっているのは、金を稼ぐ役割を女性に押し付けられたからだ」と考える人がいるようである。
それは個人的な不平不満や愚痴にとどまらず、ある種の理論や思想にまで発展する。ジェンダー論などでは、日本の労働モデルに留まらず世界的な資本主義全般が家父長制によって構築されたものであり、男性が(経済や政治などの)公的な領域における機会や利益や権利を独占しつつ、女性を私的な領域に押し込めて抑圧して搾取するためのものである、といった主張がなされることが多い。そして、アカデミックな世界ではあまり目立たないが、逆の立場からの考え方もある。つまり、女性は(恋愛や家庭という)私的な領域において優位で権力を持っており、男性を公的な領域に追い立てて競争させておいてその果実を搾取している、という主張だ。
前者の考え方は、以前からフェミニストたちが提唱してきたものだ。後者の考え方は近年になって目立ってきたものである。その提唱者たちは、「弱者男性論者」と呼称されることが多い。どちらの考え方についても、ある点では的を射ているかもしれないし、ある点では誤っているかもしれない。
こうして紹介すると、女性と男性との状況は鏡写しであるようにも見えてくるし、対称的なものであるように思えるかもしれない。
だが、「自分は不利益を被っている」と認識している人たちは、どちらの側であるにせよ、自分たちの状況を対称であるとは見なさないものだ。
とくに最近のジェンダー論やフェミニズムは、男女の置かれている状況の非対称さを示すことで、女性の被っている被害が男性のそれよりも深刻であることを論じようとしてきた。そして、弱者男性論者の主張は、そのようなフェミニズムの主張(そして、後述する男性学者たちの主張)に対抗するかたちで登場してきたものであるのだ。
男性が受けている不利益を説明する理論はほとんどない
これまで、男性と女性が受ける不利益の非対称さを論じる言説は、フェミニズムによるものが大半だった。したがって、女性が受けている不利益については、それを説明して強調するためのさまざまな様々な理論や概念が発達してきた。
たとえば、経済や政治におけるジェンダー・ギャップや大学で理数系の学部を専攻する女性が少ないことについては、女性は若い頃から学校やメディアなどで「女に政治は向いていない」「女に数学は向いていない」などの言説を見聞させられることでそれらの分野に進むのをためらってしまうなど、ジェンダー規範や「女性差別的な文化」が一因であると論じられる。そのほかにも、前回に論じた「男性特権」や小田急線の殺傷事件に関する議論で用いられた「フェミサイド」など、女性の受けている不利益のかたちを定義して名前を付けて単語にした言葉は多々あり、その種類は近年になってますます豊富になっている。
そして、フェミニズム的な議論や概念の発達は、アカデミズムやメディアの世界における議論にとどまらず、実際の人々の行動や組織の政策にも影響を与えるようになっている。小田急線の事件の後には全国でフェミサイドに抗議することを目的としたデモが起こった[9]。アファマーティブ・アクション(積極的是正措置)のために、大学や私企業は理系の女性に向けた奨学金を給付している[10]。フェミサイドにせよジェンダー・ギャップにせよ、その原因が女性に対する「差別」であるのなら、社会の構成員である個人や組織はその差別をなくすために何らかの行動をしなければならない、ということだ。「日本にはさまざまな領域で女性差別が存在している」という見方はいまや人口に膾炙しており、女性が受けている不利益を是正することの必要性は、社会的に認識されるようになっているのだ。
ここに、ひとつの非対称性が存在する。男性が受けている不利益について説明する理論はほとんど発達しておらず、概念化もされていない。したがって、男性が受けている不利益は、女性のそれのように社会的に注目を浴びて問題視されることがほとんどない。
たとえば法務省が発表している犯罪白書によると、女性が被害者となった殺人罪の認知件数は416件であるのに対して男性が被害者となったのは507件である[11]。過去の統計を見ても、殺人事件や強盗事件などの暴力犯罪の被害者は女性よりも男性のほうが多い[12]。これは日本に限らず世界的に共通する一般的な傾向だ。また、理数系の学問の男女比が男性に偏っているのと同じように、人文系の学問の男女比は女性に偏っている。多くの大学では、文学部や心理学部、国際系の学部などに入学する学生は女子のほうが多いのだ。……しかし、ある殺人事件の被害者が男性であったとしても、そこで「性別」が社会的に注目されることはほぼない。また、心理学部や文学部に男性が進学しないことについてジェンダー規範が一因であると論じられることはあまりないし、ましてや「男性差別的な文化」が取り沙汰されることはまずない。
ほかにも、世の中で起こっている問題のなかには、不利益を被っている人の数としては男性のほうが多いのに女性が当事者となった場合のほうが注目されるものがある。ホームレスになる人の数は以前から男性のほうが多いが、コロナ禍や不況で女性のホームレスの数が増えたことは問題視されるようになった(そして、ホームレスに対する暴行・殺人事件も以前から起こっていたが、その被害者が女性であったときには報道されたりSNSで話題になったりする頻度は明らかに多かったように見受けられる)。冒頭で述べた通り自殺者の数も男性のほうが多いが、2020年はコロナ禍が原因で女性の自殺者数が前年に比べて912人増加して7026人となった。その一方で男性の自殺者は前年比で23人の減少となったことから、「女性の自殺」の問題はとりわけ重要視されるようになり、その背景にある原因や構造について議論されている[13]。だが、その2020年ですら男性の自殺者は16681人であり、女性の2倍以上だったのだ。
ジェンダーギャップが生まれるのにもそれなりの理由がある
とはいえ、これらのいずれの問題についても、人数とは別の理由から、「女性が不利益を被っていること」について注目されるのが妥当だと見なすこともできる。
たとえば、殺人事件や暴力犯罪の被害者となる割合は男性のほうが多いとはいえ、加害者の割合はさらに男性のほうが偏っている(殺人事件の検挙人員における女性の割合は、例年20パーセント強しかない)[14]。また、女性が「女性であること」を理由に暴力や殺人の対象に選ばれている(ヘイトクライムやフェミサイドの犠牲になる)のに比べると、男性が「男性であること」を理由に犯罪の被害に遭うことはほとんどなさそうだ。男性が暴力犯罪の被害に遭いやすいことは、男性の就いている職業や所属している集団や住んでいる地域などが女性のそれに比べて暴力を受けやすいものであるという、間接的な理由のほうが大きいだろう(もっとも、「職業や所属集団や居住地域が非対称であること」に不平等や差別を見出すこともできるかもしれないが)。さらに、男性は一般的に女性に比べてリスクに鈍感で無防備であり、酔っ払ったり羽目を外したりもしやすければ、他人を挑発したり他人の怒りを買ったりするような行動もしやすい。これらの男性に特有な行動の傾向も、男性が殺人や暴力の被害者になりやすいことの大きな要因であることは否めないはずだ。
また、女性の割合が多い学部(文学部や心理学部、看護学部など)よりも男性の割合が多い学部(理数系の学部や法学部、医学部など)のほうが卒業後に高収入な職や社会的地位が高い職を得やすいことから、両性ともに専攻する学部に偏りがあるとしても、それがもたらす不利益は女性のほうが大きいと判断することはできる。ホームレスや自殺の問題についても、これまでは比較的当事者になりづらかった属性であったのに最近になって当事者となる数の人が増えたのだとしたら、それはある種の異常事態であり、注目が集まることは当たり前だ。たとえば「男性の自殺者の多さ」は数十年以上にわたって継続してきた慢性的な傾向であるからこそ対策が難しい一方で、「コロナ禍で女性の自殺者が増えたこと」は最近になって起きた短期的な出来事であるからこそ、原因が特定しやすく対策も取りやすいかもしれない。したがって、このような問題について「男性の被害者に注目せずに女性の被害者にばかり注目するのは男性差別だ」と論じることも、的外れではある。
だけれど、上述したような要素を考慮してもなお、男性の被害はあまりに無視され過ぎているように思える。
女性が受けている不利益のほうをより強調すべき理由も、それなりにあるだろう。しかし、それだって程度問題であるはずだ。世の中の報道や街場の議論、本屋に並ぶ著作物などには、女性の被害のほうが強調されやすいという性別バイアスがやはり存在するように見受けられるのだ。
特権に実態はあるのか?
どれだけ合理的な理由があるとしても、気持ちの問題としてそれに納得できるかどうかは別の話だ。
女性の受けている不利益や被害の問題ばかりがメディアなどで取り沙汰されている状況は、それ自体が、一部の男性にとって心苦しいものとなりえる。自分の属性が受けている被害には注目されないどころか、自分の属性が加害者として批判や糾弾されてばかりでいるということからは、「社会は自分たちを気にかけていない」とか「自分の被害はだれにも共感したり同情したりしてもらうことができない」というメッセージを受け取っても無理はない。そして、社会的地位が低かったり収入が低かったりする男性、あるいは孤独であったり不幸であったりする男性にとってほど、そのメッセージは重たく響くだろう。
前回の記事で論じた「男性特権」といった概念にも、ある種の逆進的な作用がある。いい会社でいい地位についているなど経済的な領域で活躍できている男性や、女性の少ない理数系の学部や医学部や法学部などに進学したことで人生の展望を有利にできた男性については、「自分は下駄を履かされてきたのだ」と自覚させて反省させることにも意味があるだろう。しかし、経済や政治の領域や一部の学問の進学率などにおいて男性特権が存在するとしても、世の中にはその特権を行使する機会も持てなかった男性がごまんといる。元々の能力や気質、生まれ育った家庭の環境に経済状況、地域的な事情や通った学校のレベルなどのさまざまな事情から、大学に進学すること自体が実質的に不可能な男性もいれば、理数系の学部や法学などの経済的に有利な学問が選択肢に入れられない男性もいるし、日本的な労働モデルに適応して会社で出世することが困難な男性も多々いるのだ。
また、大学に進学しなかった人や地方在住者も含めると、ほとんどの男性にとって医学や政治の世界には縁がない。だから、多くの男性にとっては、医学部入試の女性差別や女性政治家の少なさといった問題は、社会問題であることは認められるとしても、自分の人生と直接に関係のある問題ではないはずだ。それらの領域にジェンダー・ギャップがあり、女性差別があるとしても、それはそもそも医者や政治家を目指せる程度には恵まれた人たちの世界での問題なのであり、他の世界の男性たちがその下駄を履けるわけではないのだ。
しかし、男性特権という概念にかかると、どんな状況であっても「男性である」というだけで特権があることにされる。特権を行使できて利益を享受して生きてきた男性であっても、特権を行使する機会もなくさして利益を感じずに生きてきた男性であっても、同じように責任が問われて、同じように罪悪感を抱いたり反省したりすることが求められる。
アファーマティブ・アクションの是非
ここまでは他人事のように書いてきたが、「男性の被害が無視されていること」から受け取れるメッセージは孤独であったり不幸であったりするほど重くなるというのは、わたし自身の経験に基づいたことだ。
多くの人の人生がそうであるように、現在33歳であるわたしの人生にも、それなりの浮き沈みはあった。大学院を卒業したのちに就職に失敗して、フリーターとして過ごしていた数年間はとくに沈んでいた時期であり、孤独感や不幸感はかなり増していた。そして、自分の将来の展望も見えず、自分がいま陥っている状態からなにをどうすれば脱出できるのかもわからないという状態でいるときには、自分以外の他人に助けの手が差し伸べられているような事例について知ると、言いようのないフラストレーションを抱いてしまったものだ。
とくに覚えているのが、東京大学が女子学生向けに家賃補助支援制度を導入したというニュースである[15]。この制度は東大の女子学生の少なさを改善するための施策であり、女子は男子に比べて両親から一人暮らしを反対されやすいことが、家賃補助というかたちの支援になった一因であるようだ(大学からの支援があれば両親を説得する理由となるし、両親の支援が得られずに独力で進学する場合にも助けとなる)。そして、一般的に、男子は女子に比べて両親から一人暮らしを反対されることが少ない。だから、家賃支援というかたちで女子にのみアファーマティブ・アクションを行うことは効率的であり合理的だ。……とはいえそれはあくまで一般論であり、男子のなかにも、一人暮らしを両親に反対される人もいる。わたしもそのひとりであり、東京の大学に進学できなかったことについて、長らく恨みを抱いていた。一度も地元を出る機会を得ないままフリーターになり、キャリア的・経済的な理由から将来に一人暮らしをする展望もまったく見えなってしまった状況では、その恨みはさらに強まった。だから、女子にだけ家賃支援がされるという報道を見たときには、他人事ながらかなりイヤな気持ちを抱いてしまったものだ。そして、若かった頃のわたしと同じように、両親から一人暮らしを反対されたせいで東京に進学できなかった男子学生も、女子に対する進学支援について知ると忸怩たる思いを抱くかもしれない。
ついでに書いておくと、男性の自殺率の高さという問題についてわたしがとくにこだわっているのも、フリーターであった時期に自殺することを考えたことが何度かあって他人事ではないからだ。……とはいえ、先述したように、女性の自殺率について注目されることにもそれなりの合理性がある。いくら自分に当事者性がある問題でも、報道や制度の背景にある合理性を無視して「男性側の不利益や被害が考慮されていない」と強調することは、逆恨みにしかならない。
しかし、不幸であったり孤独であったりするという状況は、まさにその「恨み」を募らせる。逆恨みであることを自覚できて、女性に対する支援策に対する文句を実際に口に出すことは差し控えたとしても、「自分のことは配慮してもらえなかった」という思いはダメージとして残りえる。これは感情の問題であるからだ。
「ことば」はむしろ溢れている
男性が被っている不利益や被害については理論化や概念化がほとんどなされていないために、男性が自分たちでそれらを語ることも難しい。
このこと自体が、女性と男性との間にある非対称のなかでも、かなり重大なものだ。
韓国のフェミニストのイ・ミンギョンの著書の題名は『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』であるが、大きめの本屋に行けば、フェミニストによる「ことば」だらけであることに気付かされる。アカデミックなものから個人的なエッセイまで、日本のものもあれば欧米や韓国からの翻訳もあってと、特にここ数年ではフェミニズムの本は雨後の筍のごとく出版されつづけている。それらの本の多くでは女性が受けている不利益や被害について客観的なデータや主観的なエピソードが示されたのちに、問題の原因となっている男性たちや諸々の制度(家父長制とか資本主義とか国家とか新自由主義とか)に対する批判がなされたり怒りが表現されたりしたうえで、社会を改善する必要が論じられたりシスターフッドのメッセージが示されたりする。実際の社会において女性が受けている不利益や被害はなかなか改善しないのに比べると、それについて女性が語る「ことば」だけは、むしろ溢れている状況であるのだ。
そして、「ことば」は、本を出版する機会を持つアカデミシャンやエッセイストに限らず、市井の女性たちでも放つことができる。昨今では、学校に行ったり本を読んだりしなくても、インターネットで検索したりSNSでフェミニストのアカウントをフォローすればフェミニズムの理論や概念にはいくらでも触れられる。女性たちは、自分の受けている不利益や被害について、すでに認められているかたちで語ることができて、共感や連帯を誘うことができる。……そして、女性に比べると、男性は自分たちの被害や不利益を語ることばを、ほとんど持っていない。
フェミニズムのメッセージを伝える本の多さや、近年ではシスターフッドをテーマにした映画などのフィクションが増えていることには、率直に言って羨ましさを感じるところがある。現実の状況がどうであれ、本屋に行ったり映画館に行ったりすれば、女性はエンパワメントされるだろう。その一方で、男性をエンパワメントする議論やフィクションは、今の世の中にはほとんど存在しない。
男性学にはなんの期待も抱けない?
ジェンダーや性別に関する学問としては、フェミニズムのほかにも「男性学」という分野が存在している。男性学はたしかに「男のつらさ」について理論化や概念化を行い、男性のための「ことば」を作ろうとしてきたかもしれない。しかし、わたしを含めた多くの男性にとって、男性学はなんの期待も抱けないものとなっている。
ひとくちに男性学といっても社会学や精神分析から当事者研究やフィクション研究などの多様な学問が関わっており、「男性学者」「男性研究者」などの肩書きを自称する人もいれば、そう自称はしないが研究の対象が「男性性」であったりジェンダー論の枠組みを用いながら男性について論じたりする人もいる。当人たちがどう思っているかはさておき、問題意識や議論のトピックはだいたい一緒であるから、「男性学」とひとまとめにしてもいいだろう。
また、男性学はフェミニズムと関わりの深い学問であるために、個別の問題について論じる際にも、フェミニズムの道具立てを流用することが多い。
アイデンティティに関わる学問では、ある理論や概念は規範を主張するためのものであるのか事実について分析したり記述したりするためのものであるのか、という境目が曖昧になることが多い。フェミニズムの場合には、社会には「家父長制」や「男性中心主義」などの女性差別的な制度やイデオロギーが存在することを前提としたうえで、それらの制度やイデオロギーによる権力作用やジェンダー規範が社会のなかの個人や組織の思考や行動に影響して、女性差別をはじめとする様々な問題を引き起こしている、といった議論がされがちだ。……これは単純化した説明であるが、ポイントとなるのは、個別の問題に関して分析されたり記述されたりするときにも、その背景には「社会は女性差別的である」という前提があるということだ。また、男女の行動や選択について「当人にとっての利益を合理的に追求している」とする経済学的な考え方に基づいて分析することや、「生得的な男女差が影響を与えている」とする生物学的な前提に基づいて論じることは、忌避されることが多い(むしろ、経済学や生物学自体に性差別的な前提が潜むとして批判されたりする)。
社会は女性差別的であるとするならば、社会は男性にとって有利なものである。このような前提があるために、そもそも有利なはずである男性が被っている不利益や男性たちが感じている「つらさ」について論じること自体が、難しく複雑な作業となってしまう。
たとえば「有害な男らしさ」が存在するとして
男性学でよくあるタイプの議論は、家父長制や性別役割分業によって社会的な地位や高収入なキャリアを得ることが「男らしさ」と定義されているから、男性は「男らしさ」を追い求めて長時間労働も厭わずに出世競争に明け暮れてしまい、それにより肉体的に疲弊するうえに趣味や家族に費やす時間もなくなって精神的な癒しを得られなくなることから「つらさ」を感じる、というものだ。
あるいは、粗暴な振る舞いや相手の話を聞かないガサツなコミュニケーション、感情よりも論理を重視してしまったり弱音を吐いたり涙を見せることをためらってしまったりなどの「有害な男らしさ」がメディアや教育を通じてインストールさせられてしまうことによって、人間関係を維持することがヘタで孤独になったり、自分が抱いている苦悩について自覚して対処することや他人に苦悩を打ち明けることができなくなって不幸が増したりする、と論じられることもある。
これらの議論にはそれなりの妥当性がある。多くの男性が、自分の健康や精神的な豊かさを犠牲にしてでも、自らすすんで長時間労働を行ったり激務に就いたりしていることは確かだろう。また、男性は女性に比べてコミュニケーション能力やセルフケア能力に欠けていることが男性の孤独や不幸の一因になっているという主張は、わたしの目から見ても説得力がある。……しかし、丸々受け入れることはできない。反論できるところも多々ある。
たとえば、「有害な男らしさ」が存在するとしても、それはメディアや教育などによって社会的に構築されるものばかりではなく、男性という性別にもとから備わっている生物学的な傾向も含まれていることは、進化心理学や脳科学の知見から指摘できるだろう。
男性が弱音を吐かなかったり涙を見せなかったりすることの影響も、過大視されているきらいがある。わたしはわりと簡単に弱音を吐いたり泣いたりするタイプだが、そのことがわたしの人生のクオリティにさしてポジティブな影響を与えているようには思えない。
また、最近では、「男らしさが悪いものだと言われても、そこから簡単に降りることはできない」という反論がよく聞かれるようになった。結局のところ、生きていくためには自分で金を稼いでキャリアアップするか誰かに扶養されるかする必要があり、そして実際問題としてこの社会では男性が女性に扶養される事例は少数である。共働きであっても、男性のほうがより多くの収入を稼いで女性のほうが育児によりコミットすることが、良し悪しはともかくとして一般的な事例であるのだ。したがって、キャリアアップを諦めて低収入にとどまることは、幸せで充実した生活を過ごしたいと思っている男性にとってはリアリティのある選択ではない。
とくに労働と扶養に関する問題については、そもそも男性が社会的地位や高収入なキャリアを追求している原因は女性のほうの選択や選好にある、という反論もなされている。つまり、多くの女性が経済力の高い男性をパートナーに望むために、男性は恋人や配偶者を得られずに孤独になることを避けるために「男らしさ」を追い求めざるをえない、ということだ。
この反論に対しては、家父長制社会や性別役割分業によって女性の賃金は男性のそれよりも低くされているから、女性は嫌でも男性に経済的に依存せざるをえなくなっているだけだ、という再反論がなされている。それに対して、高収入な女性であっても男性を扶養したがらないという指摘がさらになされることもある。……わたし自身の経験をふまえても、キャリアアップについて考えをめぐらすのは、その当時に付き合っている恋人の存在を意識してのことが多かった。わたしは社会的地位や権力にこだわりがあるほうではないが、恋人との関係を維持するうえで「しっかりした収入や職業」を相手から求められることが何度かあったし、その際には対応せざるを得なかった。多くの男性が同様の経験をしている。良し悪しはさておき、パートナーからの要望は、ジェンダー規範とか家父長制のイデオロギーとかいったものよりもはるかに直接的に男性の行動や意識に影響を与えるものなのだ。
いずれにせよ、女性のつらさの原因の一部が男性の行動や選択にあるように、男性のつらさの原因の一部が女性の行動や選択にあることを否定するのは難しいだろう。両性のつらさの原因が共通している場合には男女の利害は一致するが、互いが互いのつらさの原因である場合には、男女の利害は対立していることになる。しかし、男性学は「社会は女性差別的である」というフェミニズムの前提を共有しているため、女性のほうの不利益を強調して、男性のほうの不利益を見過ごしたり過小評価したりしてしまいがちだ。男性と男性学との間には、利益相反的な関係があるかもしれない。
ジェンダー論では取り上げられない「孤独」の問題
雑誌でジェンダー論が特集されるときには男性学者とフェミニストの両方の名が載っていることが多いし、同じ学会に所属していたり、メディアやイベントを通じて関ったりすることも多いだろう。理論的な前提をフェミニズムと共有していることのほかにも、男性学に関わる人たちとフェミニズムに関わる人たちとの距離が近いこと自体が、男性学の議論に大きな影響を与えているようだ。
フェミニストのなかには、男性学が男性のつらさや不利益に焦点を当てることを許さない人たちがいる。男性特権が実在していると信じている彼女たちは、男性のつらさや不利益が存在するとしてもそれは特権を持つことの取るに足らないコストや副作用に過ぎず、不平不満を言う前に自分が特権から不当な利益を得ていることを自覚して反省することのほうが先だ、といった主張をするのだ。具体的には、澁谷知美や江原由美子などのフェミニストが、男性学が「男の生きづらさ」を扱っていることについて批判している[16]。そして、男性学者たちには澁谷や江原のような批判を無視したり跳ね除けたりすることができないようだ。
このような事情があるために、男性学では男性のつらさや不利益についてシンプルに論じることもできなくなっている。まずは男性特権について反省して、この社会では女性(や性的少数者やその他のマイノリティなど)が男性に比べてはるかに重大な不利益を受けていることを示したうえで、その後にようやく「男の生きづらさ」を取り上げる、というまわりくどいかたちでしか論じられないのだ。また、男性が受けている被害や不利益についても、その原因は「ホモソーシャル」や「男性集団」または「男性性」など、社会の状況や制度や他の属性の人々ではなく、男性という属性の内部のみに見出さなければならない。
たとえば、臨床心理士であり研究者でもある西井開の著書『「非モテ」からはじめる男性学』では、女性と付き合ったことがない「非モテ」の人たちが感じる苦悩の原因は、恋人がいないことや女性から好意を向けられないことではなく、男性集団からからかわれて排除されることにある、と論じられている。また、社会学者の平山亮は、インタビューのなかで男性が自殺することの原因は「男性が支配の志向にこだわりつづけてしまう」ことであると主張した[17]。
まず、西井の主張については「非モテ」の当事者たちのなかにも共感できる人はいるようだが、非モテの苦悩の原因について「恋人がいないこと」よりも「男性集団からからかわれて排除されること」のほうを強調するのは、かなり不自然で無理があるように感じられる。それは非モテの苦悩の一因となるかもしれないが、主因になるようには思えない。西井の著書を読んでもわたしは説得力を感じなかったし、議論の展開の仕方が「無難」な結論を導き出すために不自然に誘導されるように読めてしまった。恋人がいないこと……つまり付き合ってくれる女性がいないことによって生じる苦悩について論じたところで必ずしも女性の責任を問うことにはならないが、苦悩の原因には女性の行動や選択が関わっていることを示すことにはなる。それよりも、問題の原因を男性集団や男性間のコミュニケーションに帰着させたほうが、女性やフェミニストでも安心して受け入れられる議論となる。男性集団や男性的なコミュニケーションが悪いことはフェミニストにとっては自明なことであるし、非モテの問題が男性同士の問題であるのなら女性は他人事として眺めることができるからだ。実際、先述した澁谷は『「非モテ」からはじめる男性学』を好意的に評価しているし、ほかにも多くの女性たちが西井の議論を好意的に受け止めているようだ。
西井のものに限らず、男性同士の関係の過酷さや暴力性を強調して、「暴力」や「権力」や「支配」などのネガティブなワードで表現しながら、従来的な関係性の代わりに「男性同士のケア」を称揚するという議論は、最近では頻繁に見かけるようになった。しかし、これらの議論には、男性が抱える苦悩の原因を「男性集団」というわかりやすいターゲットに閉じ込めることで、他のところにも原因がある可能性から目を逸らさせたり「男性の苦悩は他の属性の人々も目を向けるべき社会問題である」という主張を封殺したりする機能がある。そして、無難であるからこそ最近の男性学は多くの女性に受け入れられており、女性のほうから男性に対して「男性学の本を読むべきだ」と推薦する状況も見受けられるようになっている。同様の事態はフェミニズムでは決して起こり得ないことは留意するべきだ。男性が平穏な気分で読めて気軽に女性に推薦できるような無難な議論をするのではなく、男性を不安にさせて居心地を悪くするような「挑発的」な議論をするほうがフェミニズムの本懐であると、多くのフェミニストは思っているだろう。
そして、平山の主張にはさらに深刻な問題が存在する。自殺の問題については個人的な事情からわたし自身も調べており、人に自殺という選択をさせる原因について論じた心理学の本なども読んできたが、男性の自殺率の高さを「支配の志向」に見出す議論は見たことがない。たとえば、カウンセリングなどを通じて自殺という問題について現場で向き合ってきたトマス・ジョイナーは、孤独は人を自殺に導く大きな要因であることを指摘したうえで、女性よりも孤独になりやすいことが男性の自殺率の高さの原因である、と論じている[18]。
ジョイナーは男性が孤独になりやすいことの要因として「物質主義」や「地位や名声に対する執着」などの男性に備わった生物学的な傾向も挙げている一方で、「女性と比べて男性は人間関係を維持するためのスキルや意欲を若い頃に獲得しない」といった社会的な要因も挙げている。ジョイナーの主張には男性学の議論に近いところもある。だが、重要なのは、ジョイナーは男性の自殺率の高さを問題だとみなして改善するための議論を行なっており、自殺の予防につながる具体的な提案も行っているのに対して、平山の主張は男性に対する非難や断罪にしかならないことだ。まさに自殺を検討したことのある当の男性たちに対して、自分の言葉がどのような感情をもたらすかを考慮したようにも思えない。
男性たちの「生きづらさ」の議論の必要性
現状の男性学や、「男性性」について取り上げた社会学や哲学などの議論は、現状の社会に適応してうまく人生を過ごしている男性に対して反省を促せられるものにはなっているし、男性特権や男性集団の問題をあげつらうことで女性たちの気分を良くするものにもなっている。だが、被害や不利益を受けている男性たちの「ことば」を代弁するものにはなっていない。そして、当の男性たちもそのことを理解しているために、男性学やそのほかの学問に対する呆れや失望の声も表明されるようになっているのだ。
上述したような状況に対する反動から、近年では、弱者男性論者たちの主張が勢いづいている。アカデミアではなくインターネットを主戦場とするアマチュアが中心ではあるが、その影響力はバカにならない。男性と女性との利害の対立をことさらに強調して、女性嫌悪を煽る言論も目立つようになっており、多くの男性がそれに影響されてしまっている。
男女に利害の対立があるとしてもそれを実際以上に誇張して表現することは誤っているし、女性を嫌悪したところで男性の人生が好転するはずもない。わたしには、弱者男性論はそれを支持する当の男性たちを不幸にするものであるように見受けられる。もちろん、嫌悪の対象となる側である女性にとっても、弱者男性論が流行するのはたまったものではないだろう。……だが、実際問題として、多くの男性が弱者男性論に吸い寄せられている。自分たちの不利益や被害について取り上げて向き合ってくれる「ことば」が、ほかにないからだ。
だから、男性たちの「生きづらさ」を正面から取り上げた議論が必要なのだ。
その際に男性特権などの疑わしい理論や概念を用いる必要はなく、現実の社会の状況についてごまかすことなく目を向ければいい。不利益や被害のかたちをひとつずつ明確化していって、それが生じる原因を客観的に分析して、社会や個人がとれる対策を検討していけばいい(たとえば自殺の問題に関しては、ジョイナーの著書ではそれが実践できている)。分析した結果、特定の問題については男性の利害と女性の利害がバッティングしていることが明らかになるかもしれないが、その際にはどちらの改善を優先したりどう利害を妥協させたりするかも、その都度に考えていけばいい。本来、世の中に存在する問題とはそうやって解決していくものだ。男性の問題だけが後まわしにされたり無視されたりするいわれはないのである。
参考文献:西井開、『「非モテ」からはじめる男性学』、集英社、2021年。
[1] https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2021/202105/202105_05.html
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
[2] https://www.tokyo-np.co.jp/article/122491
[3] https://president.jp/articles/-/46392
[4] https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/R03/R02_jisatuno_joukyou.pdf
[5] https://www.mhlw.go.jp/content/h30h-1-10.pdf
https://www.sankei.com/article/20170530-RZEI624YOZLKBPDZ5UCDXVNDKQ/
[6] http://honkawa2.sakura.ne.jp/2472.html
[7] https://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm
[8] https://president.jp/articles/-/35456
[9] https://www.tokyo-np.co.jp/article/123766
[10] https://www.shibaura-it.ac.jp/news/nid00001842.html
https://globaledu.jp/shinfdn2022
[11] https://www.moj.go.jp/content/001365735.pdf
[12] https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/44/nfm/n_44_2_5_3_6_1.html#H005003006001E
[13] https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/jisatsu/16/dl/1-01.pdf
[14] https://www.moj.go.jp/content/000105802.pdf
[15] https://kimino.ct.u-tokyo.ac.jp/90/
[16] https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66706
[17] https://wezz-y.com/archives/49587/3
[18] https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79839


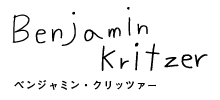 1989年生まれ。批評家。立命館大学文学部英米文学専攻卒業(学士)、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科卒業(修士)。
1989年生まれ。批評家。立命館大学文学部英米文学専攻卒業(学士)、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科卒業(修士)。