「キャンセル・カルチャー」という言葉はご存知だろうか?
いまでは様々な意味をこめて使われるようになっている言葉であるが、基本的には「著名人の過去の言動やSNSの投稿を掘りかえして批判をおこない、本人に謝罪を求めたり、出演や発表の機会を持たせないようにメディアに要求したり、その地位や権威を剥奪するように本人の所属機関に要求したりするような運動および風潮」のことだと言える。
キャンセル・カルチャーという言葉が日本でも紹介されるようになったのは2019年〜2020年頃であるが、この言葉がとりわけ注目を浴びて人口に膾炙するようになったのは2021年からだろう。東京オリンピック・パラリンピックの開閉会式をめぐって、キャンセル・カルチャーという言葉がまさにぴったりと当てはまる出来事が、立て続けに起こったからだ。
まず、開会式の楽曲の作曲担当者の一人であったミュージシャンの小山田圭吾が辞任する事件が起こった。その原因は、太田出版から発行されていたサブカルチャー系雑誌「クイック・ジャパン」1995年8月号に掲載された小山田へのインタビュー記事にある。このインタビューは、当時同誌で連載されていた「いじめ紀行」というシリーズのなかでなされたものであるが、そこで小山田は、小学校から高校にかけての学生時代に知的障害者の同級生をいじめ続けていたことを肯定的に語っていたのだ。
ネット上においては「いじめ紀行」の内容を取り上げて小山田を批判するブログが何年も前から存在しており、小山田のインタビューの内容も一部の間では知られていたが、オリンピックという世界的イベント、そしてパラリンピックという「障害者の機会均等」を理念とするイベントに彼が参加することは、大々的な批判を呼び寄せた。それに伴い、インタビューの内容はマスメディアにも取り上げられて世間一般に周知されることになった。当初、オリンピックの組織委員会は「行為は断じて許されるものではないが、開会式が迫るなか、引き続き、準備に努めていただく」として続投させることを表明していたが、その表明が火に油を注ぐことになって、批判の声はさらに高まる。そして、結局、小山田から辞任を申し出ることになったのである。
小山田に続いて、開閉会式のショーディレクターであった、元お笑い芸人で現演出家の小林賢太郎をめぐる騒動も起こった。1998年5月に発売されたビデオ「ネタde笑辞典ライブ Vol.4」に収録された、当時の小林が結成していたお笑いユニット「ラーメンズ」によるNHKの人気教育番組「できるかな」をパロディにしたコントのなかで、ジョークの文脈で「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」というセリフが発せられていたのだ。このコントの動画は以前からインターネット上にもアップロードされていたようではあるが、開会式の直前になって、誰とはなしに問題視する声がネット上に投稿されるようになった。そしてアメリカのユダヤ系団体「サイモン・ウィーゼンタール・センター」が「東京オリンピックの開会式のディレクターによる反ユダヤ主義の発言を非難する」という声明文を出し、小林は「思うように人を笑わせられなくて、浅はかに人の気を引こうとしていた頃だと思います」としながら謝罪文を発表して、オリンピックの組織委員会は小林を解任したのであった。
小山田と小林の辞任・解任は、1990年代に掲載されたインタビューや発表されたコントが2021年になってから問題視されて、オリンピックという世界的イベントに関わる機会や名誉を奪うに至ったという点で、まさにキャンセル・カルチャーの典型例であったといえる。
インターネット以前からあったキャンセル・カルチャー
キャンセル・カルチャーという言葉が知られるようになったのは2020年代からだとしても、この言葉が指し示す現象は、日本でも以前から起こっていたかもしれない。
たとえば、「炎上」という言葉は2000年代の中頃、SNSが普及する以前でブログが主なネットメディアであった頃から使われていた。元々はブログの記事のコメント欄に批判や誹謗中傷が集まる現象を指していたようであるが、現在では、個人がSNSに投稿した内容に批判が集まることや、企業が発表した製品や広告に差別的要素が含まれていたり漫画やドラマ・アニメなどのフィクションに侮辱的表現が含まれていたりすることが問題視されて否定的な意見が多く投稿されたり議論が巻き起こったりすることも、「炎上」と表現されるようになっている。
近年では、批判を起こしやすい要素をわざと投入することで、話題になって注目を浴びることを狙う「炎上マーケティング」もおこなわれるようになってきた。とはいえ、基本的には、「炎上」が起きることはその対象となる個人や企業にとっては不利益な事態となる。当事者が想定していなかった大量の批判を呼び寄せることは、個人にとっては精神的な負担が多大にかかるし、企業にとってもブランドイメージに傷が付いて経営上の影響を生じかねさせないものであるからだ。
また、キャンセル・カルチャーがSNSの普及に伴って隆盛したことは明らかであっても、「インターネット時代に特有の現象だ」とまで考えるは間違いであるかもしれない。社会道徳に違反したり差別的であったりなどの問題のある人または表現について抗議が巻き起こって、批判対象の人が就いている立場を解任させたり雑誌での連載を中止させたり、あるいは批判対象の表現をテレビで放映させないように要求する……つまり「キャンセル」を求める運動は、インターネット以前から頻繁におこなわれてきた。
とくに日本のマスメディアは事なかれ主義であり、ごく少人数からのクレームでも簡単に屈してしまうことは、昔から問題視されてきた。たとえば、タレントが不倫などのスキャンダルを起こすと、出演しているCMや番組がすぐに放映されなくなるし、犯罪をおかした場合には(それが薬物所持など、直接的には他人を傷付けない犯罪であっても)出演している映画が公開中止になるだけでなく、既に販売されているCDや映像作品すらもが回収の対象になってしまう。わたしが子どもの頃に楽しんで観ていたバラエティ番組のコーナーも、「暴力的だ」というクレームが入ったことが原因で打ち切りになっていた。そして日本のメディアには「自主規制」の悪習も存在しているようであり、誰からのクレームも入っていない時点から、物議を醸したり批判されたりするおそれのある表現の掲載や放送を事前に取り止めてしまうこともある。
したがって、キャンセル・カルチャーは最近になって登場したものではなく、元々から社会に存在していた傾向や風潮がインターネットやSNSによって増幅されたものとみなしたほうがいいだろう。
民主主義の社会では当たり前の営み?
キャンセル・カルチャーについて考えるときに失念してはならないのが、基本的に、この単語は「他称」として使われる言葉であるということだ。つまり、抗議のための提言や運動などをおこなっている人たちが自分たちの行動を表すために使う言葉ではなく、むしろその抗議に対して否定的な意見や感情を持っている人たちによって使われる言葉なのである。
海外だと事情はやや複雑であり、「キャンセル・カルチャー」はともかく「キャンセル」という単語自体は、抗議をしている人たちによっても積極的に使われている。欧米のSNSでは、俳優やミュージシャンやインフルエンサーなどが差別発言をしたり不祥事を起こしたりするたびに、「●●をキャンセルしよう」というハッシュタグがトレンドにのぼっている(たとえば、わたしが英語圏で不祥事を犯したら「#cancel_Benjamin」がトレンドになるかもしれない)。……とはいえ、そのようなキャンセル運動が絶え間なくおこなわれる状況を指す「キャンセル・カルチャー」という単語や、日本ではあまり使われていない類語の「コールアウト・カルチャー」は、欧米でも否定的な文脈で用いられることが多いようだ。有名なところでは、バラク・オバマ元大統領はキャンセル/コールアウト・カルチャーの両方の単語を用いながら、懸念を表明している。
近年ではオバマのようなリベラル派のなかにもキャンセル・カルチャーに批判的な人が増えてくるようになったとはいえ、この単語を用いて抗議運動のことを否定する人の多くは保守派や右派である。逆にいえば、海外でも日本でも、キャンセル(と他称される)行動をおこなっている人の多くはリベラル派や左派であるのだ。そして、彼や彼女たちは、自分たちの運動を「反差別運動」や「市民としての抗議」、あるいは「マジョリティに対する批判」や「マイノリティへの連帯の表明」などと自認しているだろう。キャンセルと呼ばれる行動の多くは、インターネットやSNSという現代的な領域で実践されているから新奇に見えるだけで、実際のところは昔ながらの民主主義が実践されているだけなのかもしれない。権力を持っている人やメディアへの露出が多くて社会的な影響力が強い人が不当な行為をおこなったり、社会的な良識に反したり、他者を傷付けたりしたときに、その人の言動を批判したりその人の関わる組織の責任を追求したりするために抗議運動が巻き起こってデモや集会がおこなわれる、というのは民主主義の社会では当たり前の営みであるとみなすこともできる。
リベラル派や左派のなかには、「キャンセル・カルチャー」とは自分たちに対する保守派や右派の不当な言いがかりでしかなく、この言葉を用いた議論は反動的なものにしかなり得ない、と反論する人もいるようだ。彼や彼女からすれば、自分たちはただ正当な「抗議」や「批判」をしているに過ぎない。その行為に「キャンセル」とのレッテルを貼ることは、抗議や批判の声を封殺して告発を無力化することであり、民主主義を否定することでもあるのだ。したがって、キャンセル・カルチャーを懸念する議論に耳を傾けたり相手にしたりする必要はない、と彼や彼女は主張するのである。
上述の議論には、たしかに的を射ているところもある。とくに日本語圏では「キャンセル」という単語が乱用されていることは否めない。たとえばある俳優の言動やあるアニメの表現について、その俳優の出演を取り止めさせたりそのアニメの表現を修正させたりすることを要求するのでもなく、ただ単に「この言動/表現にはこのような問題がある」と指摘することすらも、キャンセル行為と呼ばれる場合があるのだ。指摘する人のほうとしては、俳優の人格やアニメ作品そのものの是非とは切り離して、一部の言動や表現についての是非や巧拙を論じているつもりであっても、それが第三者に伝わらず、人格や作品そのものの否定として受け止められる。これには、一般の消費者にありがちな「論評」や「批評」に対する拒否反応も関係しているだろう。
また、差別的な言動や反社会的な行為をしている人について批判の声が挙げられないような社会では、不平等が放置されて不正が横行することになり、多くの人にとっては生きづらく抑圧的な世の中になるかもしれない。「キャンセル」というレッテルが妥当であろうとそうでなかろうと、そのような行為が民主主義を機能させてきて、世の中を改善する役割を担ってきたことは否定できそうにもない。数十年前に比べると現代では差別や不平等の規模や程度は大幅に減少していることや、「なにが差別であり、なにが不正であるか」という点に関して社会は昔よりもずっと敏感になっており、過去なら放置されていた差別や不正も看過されないようになっていることを、忘れてはならない。わたしたちはつい目の前で起こっていることにばかり気を取られてしまい、現代の世の中がひどいところであるように思ってしまうが、昔に比べると現代はずっと道徳的で安全な世界になっている。その要因のなかでも大きいのが、過去になされてきた人権運動や反差別運動であるのだ。つまり、リベラルであろうが保守であろうが、わたしたちは過去に実践されてきた民主主義運動≒キャンセル・カルチャーの恩恵を受けながら生きているのである。だとすれば、いまさら「キャンセル」行為を否定するのもお門違いではないだろうか?
……と、上述したように論じることもできるかもしれないが、これはこれで極論だ。なにしろ、あのオバマ大統領ですら懸念を表明しているのである。一般市民の多くも、「キャンセル・カルチャー」と他称される現象や風潮に対して、どこかしらイヤな気持ちを感じているようだ。SNSはキャンセル行為の主戦場であると同時に、それに反対する意見表明も盛んに投稿されている。民主主義的な抗議運動や批判活動に原則として賛成する人のなかにも、それが「行き過ぎ」になると看過できない、と考える人がいる。現代のメディアで繰り広げられるキャンセル・カルチャーは従来の抗議活動とどう違うのか、わたしたちはキャンセル・カルチャーのどこをどのように「イヤ」に感じるのか、もうすこし掘り下げて考えてみよう。
民主主義的営みか? 社会的制裁か?
冒頭で述べた通り、2021年の日本では、東京オリンピックの開閉会式に関わった二人の芸能人がキャンセルされた。ところで、もうひとつ、キャンセル・カルチャーと直接的に関連することではないかもしれないが、わたしの印象に残った出来事がある。それは、2019年に起こった東池袋自動車暴走死傷事故の加害者に下された判決だ。
事故が起きた直後、警察は逃亡や証拠隠滅のおそれがなかったという理由から加害者を現行犯逮捕せず(逮捕の要件を満たさなかったためだ)、またメディアでは「容疑者」と呼称されていなかった(事故直後には警視庁による事情聴取がおこなわれておらず、刑事手続きに入っていなかったからとされる)。しかし、加害者が旧通産省工業技術院の元院長であり、勲章も授与されていたエリートであることから、「加害者は“上級国民”であるから逮捕されず、マスメディアも丁重に扱ったのだ」と憶測する書き込みが相次いだ。そして、そもそも母子二人が死亡した凄惨な事故であることや、加害者が公判中に「ブレーキとアクセルの踏み間違いはなかった」から自動車の欠陥が事故の原因であるとして無罪を表明したことも相まって、ネット上における加害者へのバッシングは激化し、自宅周辺に動画投稿者が訪れたり街宣車が周回して「日本国民の恥」との罵声を浴びせたりするまでに至ったのだ。
2021年の判決では、加害者に対するバッシングが「過度な社会的制裁」とみなされ、量刑を決定するうえで被告側に有利な事情として考慮されることになった。その結果として、検察の求刑であった禁錮七年を下回る、禁錮五年の実刑判決が下されたのである。これは、処罰感情を抱いていた遺族の心情を裏切る結果でもあったのだ。
さて、前節では、他人に対するキャンセルを求める行為は民主主義的な営みであると表現した。しかし、同じ行為を「社会的制裁」と表現することもできる。規範的な政治学の議論などであれば、正統性のある手続きや客観的な理由に基づいた民主主義的な要求と、正統性のない手続きや主観的な感情に基づいた社会的制裁とを区別することができるかもしれない。
しかし、実際問題として、その二つの境界は曖昧で脆いものだ。
そして、あまり正統性のないものを含めて、社会的制裁という行為を無下に否定することも難しいかもしれない。どんな社会であっても、「法律」とは別の領域に「道徳」といったものが存在しているはずであるし、それを消し去ることはそもそも不可能だろう。だれがどのような犯罪を犯しても怒りや軽蔑の声を挙げる市民がただの一人もおらず、その犯罪者に法の裁きが下されるのを皆が粛々と待つだけという世の中は、見方によっては理想的な社会であるだろうが、すこし不気味過ぎる。それに、法律とは、道徳の発展や変遷によって下から突き上げられるかたちで変化させられていくものだ。たとえば、近年では世界各国で#MeToo運動が「性的な加害行為」や「性的同意」に関する社会通念を変化させており、それに伴い刑法の改正も議論されるようになって、一部の国では法改正が実現している。だが、たとえ法改正にまでは至らなくとも、#MeTooによって告発された男性が実際に性的な加害行為をしていたのだとすれば、その人は被害者の女性だけでなく第三者からの怒りや軽蔑の対象になっても仕方がないはずだ。ある人の行為が違法であるかどうかと、道徳的に負の評価が下される対象になるかどうかは、また別の話なのである。
とはいえ、社会運動は法律ではなく道徳の領域に属しているがゆえに、運用や手続きが恣意的であり、法律が持っているような公平さや平等を欠いている、という問題を抱えている。#MeToo運動の場合には、「性的加害をされた」という告発の真偽を判断したり確かめたりすることができず、原則的に告発は真として扱われなければならない、という点が問題だと指摘されてきた。これも難しいところではあり、既存の法律では性的加害の存在や性的合意の不在を(法的に認められるかたちで)立証することが難しく、そのために泣き寝入りさせられてきた女性が数多くいたからこそ、法律とは別の領域で運動を実践する必要があった……ということが#MeTooが隆盛する要因のひとつであったはずである。しかし、告発の真偽を確かめなかったり、あるいは立証のハードルを下げたりすることは、「告発される側」にとって不利益となることもまた事実だ。#MeToo運動に対してはその当初から「虚偽の告発がなされたときにどうするか」という問題が懸念されてきたし、その問題はほとんど解決できていないように見受けられる。
法的な適正手続きの重要性
デュー・プロセス(法律的な適正手続き)の欠如は、社会的制裁やキャンセル・カルチャーにも付きまとう。東池袋自動車暴走死傷事故の加害者は、現在ほど経済的な格差が激しくなく、若者やロスジェネと高齢者や団塊世代との世代間対立が顕著でない時代に事故を起こしていれば、あれ程までのバッシングの対象にはならなかっただろう。事故当時87歳という年齢や「上級国民」という境遇が彼に対する世間の敵意を煽ったことは明白であるが、本来、それらの属性は「事故を起こして母子を殺したこと」の罪の重さや道徳的な問題性とは無関係の要素であるはずなのだ。
小山田についても、彼がおこなった行為が他の不法行為ではなく「いじめ」であったことこそが、ネット上における批判が以前から継続していて、オリンピックという世界的な舞台で活躍する機会を目前としたタイミングで失脚することになった要因である。学生時代にいじめられた経験を持つ人は多いし、そのうちの少なからぬ人数が、成人した後にもいじめられたことについての恨みやトラウマを抱えている。そのなかには、自分をいじめた張本人だけなく、他の学校でいじめをしていた人やいじめを容認したり助長させたりしていた人のことも、恨みや敵意の対象にするようになる人がいる。いじめられていた人がそうなるのは仕方がないことであるし、批判できるようなことでもないだろう。しかし、ある行為が多くの人からの「恨み」と対象となるかどうかと、その行為に対して与えられて然るべき罰の大きさとは、本来は無関係であるべきなのだ。
「とはいえ過去のいじめがあまりにひどいのだから、小山田が開会式を辞退することは当然だ」と考えている人のなかでも、小林の解任は妥当でないと判断する人は多いはずだ。わたしの目から見ても、実際の他人に物理的・精神的な危害を与えてきたとする小山田と、コントのなかで不謹慎で過激なジョークを放った小林とでは、その行為の不当さや悪質さの度合いはまったく異なる。問題となっているコントについては台詞の書き起こしを読んでみたが、ホロコーストに関するもっとドギツいジョークを放っているものは1990年代当時の欧米の映画やドラマのなかにも存在していたのであるし(もっとも、その大半はユダヤ系の出演者や製作者によるものであることには留意すべきだが)、さほど差別的だとも思わない。実際のところ、先に小山田に対する非難が盛り上がっていたという経緯がなければ小林は無事であっただろうし、組織委員会が事なかれ主義ではなくもっと堂々と対応できていれば結果は異なっていたかもしれない。つまり、小林がキャンセルされてしまったことには、偶然や運の悪さも大きく影響しているはずなのだ。
もちろん、法律だって完璧に運用されているわけではない。地方裁判所の裁判官が頓珍漢な判決を出したというニュースは頻繁に話題にのぼっているし、同じ罪を犯しても弁護士の力量によって不起訴になるか有罪になるかが分かれたりすることはごまんとあるだろう。
とはいえ、理念としては、法廷は問題となっている行為に対して相応の判決を出すように機能することを目指している。加害者の属性、関係のない人間が持つ恨みなどのネガティブな感情、時の情勢や世の流れなど、事件や行為と無関係な要素が判決に影響しないように努められているはずだ。情状酌量の余地が考慮される場合はあるが、その際にも過去の判例などの「基準」に基づいた判断がなされる。なにより、特定の犯罪に対する量刑の上限は明確に規定されており、それ以上の罰をくだすことは裁判官にも不可能だ。
法律という領域では、客観性や専門性がある程度以上は担保された手続きや運用がなされることが前提となっており、「行き過ぎ」を起こさないための制度的なブレーキも設定されている。それは、残念ながら社会的制裁やキャンセル・カルチャーなどの「道徳」の領域には期待できないことである。
ネットリンチか? 称賛か?
「ネットリンチ」という単語も、キャンセル・カルチャーとは切っても切り離せない。実際のところ、ある人が別の人に対してネット上で非難の言葉を呈しているとき、その本人は正当で適切な批判をしているつもりであっても、第三者の目からすれば大多数の人が一緒になって行なう「私刑」にその人も加担しているとしか見えない、ということがある。
以下は、『ルポ ネットリンチで人生を壊された人たち』という本からの引用だ。
最初に何人かが「ジャスティン・サッコは悪人だ」と意見を述べた。その何人かに対して即座に称賛の声があがった。かのローザ・パークス(訳註:バスに白人席と黒人席があった時代に、運転手に注意されても白人に席を譲らなかった黒人女性)のように、差別に敢然と立ち向かった人として扱われたのだ。すぐに「称賛」というフィードバックがあったことで、称賛された側はそのままの行動を継続する決断を下した。(ロンソン、p.480)
ここに含まれている「称賛」というキーワードは、キャンセル・カルチャーが起こる理由を理解するうえで重要なポイントとなるように思える。
つい先ほど、非難の言葉を投げかけている人は第三者の目からすれば私刑にしか見えないことがある、と書いた。だが、その同じ行為が、別の人からすれば称賛の対象ともなる。自分が嫌いな相手や気に食わないがいたときに、そいつに対して非難を浴びせてくれる人がいたら、ついその人のことを褒めたくなるものだ。
SNSを眺めていると、抗議運動や社会的制裁の音頭をとったり旗を振ったりする役を担う人の数は、意外と少ないことに気付かされる。リベラル派や左派のグループと保守派や右派のグループとに大別することはできるが、各々のグループのなかで「こんなひどいことを言っているやつがいるぞ」「こんなに悪いことが起こっているぞ」という風に非難の対象となる人物や事件を発見して喧伝する人は、だいたいいつも一緒で代わり映えしないのだ。そのような旗振り役の人たちのもとには、対立する陣営からの反論や罵倒が寄せられていると同時に、価値観や問題意識を共有する仲間からの共感や応援の声も集まっているものである。むしろ、非難行為に対する批判の声が大きくなればなるほど、それに対抗するかたちで、仲間たちからの称賛の声も強まるのだ。
進化心理学のなかには「美徳シグナリング」という概念がある。通常、相手を非難したり社会で起こっている問題を指摘したりするなどの道徳的な振る舞いは、相手の行動や考え方を改めさせたり問題を解決したりするなど、「状況を改善させる」ことを目的しておこなわれるものである、と考えられるだろう。しかし、美徳シグナリングの概念によると、状況を改善させることは道徳的な振る舞いの目的ではない。声高に誰かを非難したり不道徳な状況に対する懸念を表明したりすることで、周囲の人たちに「自分は道徳的である」ことや「自分はみんなと同じ価値観を持っている」ことをアピール(シグナリング)するのが、道徳的な振る舞いの本質であるのだ。進化論的に考えると、自分の道徳性を知らしめて評判を上げることは異性からの関心を惹いて生殖するチャンスを得ることにつながり、自分が仲間たちと同じ価値観を持っていることを集団に知らしめることは集団内での居場所を確保して生存に貢献することになる。
美徳シグナリングはあまり学術的な概念ではないし、批判も多い。どんな行動についても「生存と繁殖」に還元して分析する進化心理学の考え方が、現代社会の人間の行動を分析するうえで必ずしも適切であるとは限らないだろう。実際には、だれかを非難したり社会で起こっている問題を指摘したりしている人の大半は、自分の行動によって状況が改善することを期待しているはずだ。……とはいえ、「非難」という行為には周囲に自分の美徳をアピールする効果もあること、それによって称賛という「報酬」を得られるという副次的なメリットもあることは、やはり重要だ。最初は純粋な問題意識や正義感から他人を非難していた人であっても、その行為によって報酬を得る経験をすることで、より多くの報酬を期待して、より頻繁により過激な非難をおこなうようになる、というのは想像に難くないのだ。
多数派の人々が非難に加担しない理由
たとえば、不祥事が発覚して話題になっている芸能人についてSNSやニュースサイトのコメント欄で非難することは、ふつうに考えれば本人にとって時間のムダでしかないことだ。一般市民が生活のなかで芸能人と関わる機会はほとんどないものだし、社会的非難が集まったことによりその芸能人がテレビに出なくなったところで、わたしたちの生活になにか大きな変化がもたらされるわけでもない(テレビ番組の出演者が入れ替わって、番組が前よりつまらなくなるか面白くなるかというだけだ)。しかし、「非難」という行為には美徳をアピールする効果や「報酬」が伴うことを理解すれば、キャンセル・カルチャーや社会的制裁に加担する人が存在する理由も理解できるようになる。
むしろ、ここで忘れてはならないのは、報酬が伴うわりには非難という行為をおこなう人は少ない、ということだ。前節でも述べたとおり、社会的制裁の旗振り役の数は限られている。インターネットは少数の意見が極端に目立ちやすい仕組みになっており、一見すると大々的なネット炎上であっても、実際に書き込んでいる人はネットユーザーの総数に比べるとごく僅かしかでない。ネットの世界は、炎上や社会的制裁に加担する少数派と、そうでない多数派に分かれているのだ。キャンセル・カルチャーが目立つようになっているからといって、それに大多数の人が参加しているかのように錯覚してはならない。
では、多数派の人が「非難」に加担しない理由は何だろうか?
先の文章では、社会的制裁は(法律に対比される)「道徳」の領域に属する、と述べた。だが、道徳とは多層的なものである。道徳に関するわたしたちの感覚や、明文化されていない日常的な規範のなかには、「ズルをしたり他人を傷付けたりして集団に害をもたらすやつは、いくらでも非難して構わないし、集団から排斥してもよい」といった苛烈に懲罰的な傾向が含まれているだろう。だが、それと同時に、「他人のことを非難ばかりしているやつも、ロクでもない」とみなす傾向も含まれているのだ。
会社や学校、サークルやクラブなどの人間の集団とは、多かれ少なかれ「なあなあ」に運用されているものだ。聖人君子はなかなかおらず、少しばかりのズルやサボりは大半の人間がしている。さらに、わたしたちは独善的な存在であり、他人がしているズルには敏感である一方で、自分がズルをしていることは自覚すらできないことがある。人間の道徳心理では、「他人の目のなかのおが屑は見えても、自分の目のなかの丸太は見えない」という状態がデフォルトになっているのだ。したがって、他人のズルを告発して非難することには、自分がしているズルを告発し返される危険が付きまとう。非難や告発が推奨される集団はすぐに「万人の万人による闘争」という状況に陥り、生産性や効率性が失われて、業績を出したり大会で活躍したりするなど集団の本来の目的を果たすことができなくなるだろう。非難ばかりする人が、集団にとってプラスになるとは限らない。だからこそ、健全な集団ではある程度までのズルやサボりに対しては直ちに苛烈な制裁が下されることはなく「ほどほど」で済まされるし、他人を非難することよりも仕事したり練習したりなど自身の義務を果たすことのほうが評価されるような雰囲気が醸成されているものである。
現実の世界では、非難という行為には称賛というリターンだけでなく、コストやリスクが設定されている。非難の対象とした相手に実際に問題があり、非難は正当であったと周りから認められたなら、その非難はやはり称賛されるだろう。しかし、本人は正当であると思っていても周囲からはそう評価されないような非難をしたり、非難した対象から自分の問題を逆に指摘し返されたりした場合には、非難をした人のほうが鼻白まれたり軽蔑されたりすることになる。そのため、現実の集団のなかで非難をする際には、多かれ少なかれ「覚悟」が要求されるのだ。大半の人は非難をする前に「自分のほうにも落ち度はないか」「これはほんとうにわざわざ告発して非難するほどの問題なのか」と考えをめぐらすだろうし、考えたのちに非難を取り止めることもあるだろう。「いや、やはりあいつは非難に値する」と決断した場合にも、もし避難の正当性を示すことができず周囲の人を説得できなかったら、逆に自分が非難の対象になることを受け入れなければいけない。個人の独善性を捌きながら、集団の効率性を維持するためには、非難にコストを課す「道徳」も不可欠であるのだ。
言うまでもなく、このような「道徳」は現状維持的に機能するし、集団のなかで立場の弱い人にとって不利にも機能する。力を持っている人や既に周りからの信頼を得られている人は多少のコストをものともせずに他人を非難することができる一方で、味方がいない人はだれかに傷付けられたとしてもそれを告発するための覚悟が他の人よりも多く必要とされるのだ。このことには不正さや不当さがあることは否めない。インターネットのようなメディア空間が、集団内で立場の弱い人が自集団で起こっている(が、法廷に訴えられるような類ではない)問題について外の集団に訴えることを可能にして、立場の弱い人の状況を改善することに貢献してきた、という経緯も失念すべきではないだろう。
……とはいえ、ネット上で他人を非難する際には、現実の集団で他人を非難するときのような「覚悟」が必要とされないことにも、問題が伴っている。非難の対象も、非難の様子を眺めている第三者たちも、会社や学校のように現実的な利益を共有する集団の仲間ではない。所詮は他人事であり、称賛する側も無責任になれるからだ。さらに、今時はほとんどのSNSに「いいね」ボタンやシェア機能が設定されていることは、自分の言葉で表現する手間を省いて他人の投稿に賛同の意を表明することを可能にした。これらの要素により、インターネット上で他人を非難することは、現実の集団内で他人を非難することよりもずっとお手軽に称賛を得られやすくなっている。「称賛中毒」となる人が出てきても無理はないのだ。
それでも大半の人はインターネットで他人を非難しておらず、ネット上の称賛も求めていないことは、逆に驚くべきことかもしれない。きっと、大体の人は、ネットで称賛を得ることの虚しさや不毛さがわかっているのだろうし(たくさん「いいね」をもらえたからといって、だからなんだというのか?)、現実の世界でやるべきことをやっていて、それに対して然るべき評価をもらっているのだろう。
キャンセル・カルチャーについて考えるときにわたしにとってもっとも奇妙に感じられるのは、ネット上では毎日のように繰り広げられている光景なのに、現実の世界における自分の周囲でキャンセル行為に加担している人の顔はさっぱり思い浮かばないことだ。おそらく、読者の方々の大半にとっても同じだと思われる。前述したように、ネット炎上に加わる人は少数派だ。まともな人付き合いをしていれば、そんな人たちと関わる機会はないのかもしれない。
しかし、本稿で述べてきたように、キャンセル・カルチャーは民主主義の伝統に連なる営みでもある。もしかしたら、これまでの歴史においても、民主主義とは良くも悪くも「まともではない人たち」によって担われてきたのかもしれない。そして、わたしたちが不正や不平等が昔よりも減って多少は快適になっている世界に住んでいるのが先人たちのおかげであるのと同じように、いま「まともではない人たち」によってなされているキャンセル・カルチャーは、弊害を生じさせると同時に世の中を善くもしている可能性は充分にある。キャンセル・カルチャーはイヤなものであるが、そう感じているわたしたちは他人がおこなっている非難や制裁にタダ乗りしているだけであるという可能性からも、目を逸らしてはいけないのだ。
参考文献:
ジョン・ロンソン(著)、夏目大(訳)、『ルポ ネットリンチで人生を壊された人たち』、2017、光文社。
参照URL:
https://www.sankei.com/article/20210722-3JOMY5ORBVPRPFVYRXZ3VGAGGQ/?outputType=theme_tokyo2020
https://www.chunichi.co.jp/article/295865
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210719/k10013148591000.html
https://www.nikkansports.com/olympic/tokyo2020/news/202107150000916.html
https://www.sankei.com/article/20211019-DYZRSCNNNNO5HC4JNX3QG5XF5Q/


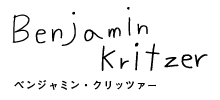 1989年生まれ。批評家。立命館大学文学部英米文学専攻卒業(学士)、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科卒業(修士)。
1989年生まれ。批評家。立命館大学文学部英米文学専攻卒業(学士)、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科卒業(修士)。