「幸福」「意味」とはどういうことか?
古代から、人間は「幸福」や「人生の意味」について悩んできた。どうすれば幸せで有意義な人生を送れるのか? そもそも、「幸福」や「意味」とはどういうことなのか?
すこし前までは、こんな難しい問題について考えて答えようとするのは、宗教家と哲学者と文学者しかいなかった。とくに哲学においては、現代においても幸福論や人生の意味論は主要なテーマとなっており、多くの哲学者がこの難題について日夜考え続けている。また、本屋に行けば、過去の有名な哲学者たちによる幸福論や人生論を現代の著者が解説している新書本やソフトカバーの単行本を、いくつも探すことができるだろう。
ただし、過去の時代にいた哲学者がいくら有名であったとしても、彼の唱えていることが正しいとは限らない。幸福論は多数の哲学者によって書かれてきたからこそ、すべての幸福論を並べてみたら、ある哲学者の言っていることと全く正反対のことを別の哲学者が言っている、ということもざらに起こっているはずだ。こんな場合には、単純に考えて、少なくともどちらかの一方の意見は間違っている。そして、間違った幸福論を唱えている人のアドバイスに従ったら、幸福に近付くどころか遠ざかってしまうはずである。
この連載の第一回で紹介した「ダーウィニアン・レフト」論とは、要するに「道徳について考える場合には、自然科学の知見を含めた、正しい事実認識に基づかなければいけない」というものであった。誤った事実認識に基づいて道徳判断をしようとしても、判断を誤って、他人に迷惑をかけたり危害を生じさせたりするおそれがある。同じように、自分の幸福や人生について考える場合にも、正しい事実認識に基づいておいたほうがいい。そこで判断を誤ると、自分が損をしたり失敗したりするおそれがあるからだ。
そして、現代では、心理学や経済学などをはじめとする自然科学や社会科学の観点から幸福について論じた研究が蓄積されている。哲学者による幸福論や人生論を参考にしようとする場合にも、どの哲学者の意見を頼りにするかは、科学的な知見に照らしあわせたうえで選択するべきだ。人間や社会というもののあり様について科学が明らかにした事実とあまりにかけ離れた議論は、いくら有名な哲学者が唱えているものだとしても、真に受けないほうがよいであろう。
上記のことを意識したうえで、今回は、古代のギリシアやローマで活躍した「ストア派」の哲学者たちの意見を紹介しよう。エピクテトスやセネカ、マルクス・アウレリウスなどなど。ただし、彼らの原典を引きながら紹介することは、現在のわたしにはちょっと力量不足なので、やめておく。
その代わりに、心理学をはじめとする現代的な学問の知見と照らしあわせながら21世紀におけるストア哲学の価値を説いたアメリカの哲学教授、ウィリアム・アーヴァイン氏による議論を紹介しよう。いわば、「ストア哲学入門」のさらに入門、という内容になる。
そして、アーヴァインが論じるようなストア派の考え方に対してわたしが抱いている疑問や不安についても、あわせて述べさせてもらうことしよう。
人生は一度きりしか生きられない
さて、アーヴァインによると、人は「間違った人生を生きる」ことを避けるために、人生哲学を持つべきだ。
だれにせよ、自分の人生は一度きりにしか生きられない。そして、確たる指標や考えを持たず、身のまわりにいる人々や偶然に起こる出来事、時代や社会の流れなどに振りまわされて右往左往しながら生きてしまうと、死の床についたときになってようやく、「自分は間違った仕方で生きていた、自分は人生を無駄にしてしまった」ということに気が付く羽目になるかもしれない。その一方で、ただしい人生哲学を持ち、それに従って生きることさえできれば、ぼうっとしているうちに無駄で有害なものに気を散らされることを避けて、ほんとうに価値のあるものを追求する人生を過ごすことができるかもしれない。
ストア哲学は、なにが「価値のあるもの」であるかということを考えるとともに、「無駄で有害なもの」についても考える思想だ。ひとことでいうと、それは「欲求」である。わたしたちの心は、放っておくとついつい欲求に振りまわされてしまうものである。だが、ストア哲学者たちによると、欲求をコントロールして「心の平静」を得ることこそが、有意義で幸福な人生を過ごすために目指すべきものなのだ。
欲求のメカニズム
そもそも、欲求とはなにであるか?アーヴァインは、「生物学的インセンティブ・システム」という表現を用いながら、欲求のメカニズムを説明している。
わたしたちの身体には、空腹になれば「食事をしたい」という欲求を生じさせたり、喉が乾けば「水が飲みたい」という欲求を生じさせたりすることで、生存のために必要な行動をわたしたちが行うように動機付ける仕組みが備わっている。また、「不潔な場所から離れたい」「危険な人物と会うことを避けたい」「身体を酷使する仕事をサボりたい」などの負の欲求も、生存にとって悪影響となる物事を回避するためにわたしたちを動機付ける仕組みだといえる。
そして、生存に関する欲求だけでなく、繁殖に関する欲求も、わたしたちの身体には備わっている。ある年代までの男女は、「セックスしたい」という欲求を強く持ち続けて、セックスできる相手がいないときには強く悩まされて、セックスをするために様々な行動を取るように動機付けられる。また、めでたく恋人ができた人であっても、「フラれたくない、捨てられたくない」という負の欲求を抱き続けるものだ。そして、結婚をして、安定してセックスできる相手を確保した人の多くは、こんどは「子どもがほしい」という欲求を抱くことになるだろう。
食事をしたいという欲求が充たされたりセックスしたいという欲求が充たされたりすると、わたしたちはなんらかの「快感」を得る。その一方で、「不潔な場所から離れたくない」「恋人に捨てられたくない」という負の欲求が充たされない場合には、わたしたちには「不快感」が生じる。そして、欲求を充たした場合に得られる快感や負の欲求を充たせられなかった場合に生じる不快感の存在について身体が覚えていたり頭で理解していたりするからこそ、前者を獲得して後者を回避するように、わたしたちの行動が動機付けられるのだ。つまり、快感は「報酬」として、不快感は「罰」として、それぞれがインセンティブとしての機能を持ってわたしたちの行動に影響を与えているのである。
生存と繁殖に貢献するインセンティブ・システム
欲求を通じて生存と繁殖へとわたしたちを動機付けるインセンティブの仕組みは、進化の歴史を通じて発展してきた。たとえば、胃のなかになにも残っておらず身体を動かすエネルギーが尽きかけている状態であっても「お腹が空いた」と思えず食事に対する欲求が湧かないような人は、まともに生存することもできず、子どもを残すことができる前に死んでしまう可能性が高いだろう。また、自分自身の生存に関するインセンティブ・システムが正常に機能している人であっても、「セックスしたい」という欲望をまったく抱かず「子どもがほしい」ともまったく思わないのであれば、その人が子孫を残す可能性はほとんどないはずだ。そのような人たちが淘汰されていくことで、生存と繁殖に貢献するようなインセンティブ・システムを持った人の遺伝子だけが残っていき、現代のわたしたちにも引き継がれることになったのである。
ただし、生物学的インセンティブ・システムは、あくまで生存と繁殖のみのために発達してきたのであり、わたしたち個人の幸福を考慮して設計されたものではない。
たとえば、ひとくちに食欲といっても、糖分や塩分や脂質が多く含まれた食事に対して、わたしたちはより強い欲求を抱くものだ。その理由は、人類史のつい最近まで、人間は糖分や塩分や脂質を入手する機会が限られている環境で生きてきたことにある。限られた栄養分に対する強い欲求が設定されることで、それらの栄養分を摂取する貴重な機会が訪れたときにも、逃さずに摂取することができるようになったのだ。
しかし、科学技術が発達して生産力の工場した現代社会では、過去のようには糖分や塩分や脂質は不足していない。わたしたちが生きる環境の変化は、生物学的インセンティブ・システムの発達を凌駕する、きわめて速いスピードで起こった。そのために、糖分や塩分や脂質に対する強い欲求はわたしたちの身体のなかに残り続けており、ついついこれらの栄養分を過剰に摂取してしまうことになる。だが、たとえば糖分を過剰摂取したら糖尿病となるように、栄養の過剰摂取は長期的にはわたしたちの身体に病気を引き起こすことになる。言うまでもなく、病気はわたしたちに苦痛を与えて、わたしたちを不幸にしてしまう。だが、生物学的インセンティブ・システムは、「特定の栄養分に対する強い欲求を設定することで、それが有り余っている時代にわたしたちはどうなるか」ということまで考慮して設定されていないのだ。
繁殖に関する欲求も、わたしたちの幸福を考慮してくれるとは限らない。たとえば、所属している集団の人間関係の状況や本人の身体的魅力、あるいは経済状況の問題から、だれかとセックスすることがどうしても困難であるという人は多くいるものだ。あるいは、恋人がもうすでに他の人に心を奪われてしまって、なにをどうしても相手が自分のもとから離れることは防ぎようがない、という状態に陥る人もいる。このような人たちにとっては「セックスしたい」という欲求や「恋人にフラれたくない」という負の欲求は充たされることがないものであり、それらはただ焦燥感や不満感や苛立ちを引き起こすものでしかなく、学業や仕事など人生においてやらなければいけないことに対する集中を妨害してしまうものでもある。しかし、生物学的インセンティブ・システムは個人が経験している状況などおかまいなしに、セックスや恋愛(そして、それらを経て子どもを残すこと)に対する欲求をわたしたちに押し付けてくる。うまくいかない状況ならセックスや恋人のことをあきらめられるくらいに弱い欲求しか持たないような人は、そもそもセックスをせずに子どもを残さない可能性が高いために、そのような人の遺伝子はとっくに淘汰されてしまっているからだ。
つまり、生物学的インセンティブ・システムはあくまでわたしたちをある年齢まで生存させて子どもを残させることを目的にして設計されたシステムなのある。欲求に振りまわされて辛く惨めな人生を送ることになっても、子どもさえ残してしまえれば、生物学的インセンティブ・システムの目的は達成されてしまうのだ。そこで、わたしたちの幸福が考慮される必要性はないのである。
後天的な条件付けで先天的システムを上書き
だが、わたしたちの行動のすべてが、生物学的インセンティブ・システムに支配されているわけではない。
インセンティブ・システムは、手に痛みを感じたら手を引っ込めてしまう、という「反射」のシステムとは異なる。欲求とはあくまで行動を動機付けるだけのものであり、欲求に抗って行動を抑えることは可能なのだ。そもそも、すこしでも食欲を感じたら他のことが考えられなくなって一目散に食べ物に飛びついてしまうような人間や、性欲を感じたら手近な異性を襲ってセックスをしようとする人がいたとしても、そんな人たちは生存も繁殖もまともに行うことはできないだろう。インセンティブ・システムは報酬と罰をもってわたしたちの行動をコントロールしようとするが、わたしたちの側にも、そのコントロールに従うかどうかを選択する能力は与えられているのである。
躾をされた犬は食事を目の前にしても我慢ができるように、動物であっても、後天的な条件付けによって、先天的なインセンティブ・システムを上書きさせることができる。人間であれば、家庭や学校における教育や諸々の集団への順応を通じて、社会一般や特定の集団に存在するルールを理解したうえで、それにあわせて自分の欲求をある程度までは自覚的にコントロールすることもできるだろう。そして、人間には理性があるために、「生物学的インセンティブ・システムは、わたしたち個人の幸福ではなく、生存と繁殖を目標として設計されている」という事実を理解することもできるのだ。
生物学的インセンティブ・システムがどのような報酬や罰を設定しているかを経験や知識に基づいて理解しながら、「自分が幸福になること」や「自分がよい人生を生きること」を目標に据えたうえで、生き方や考え方の戦略を練ることで生物学的インセンティブ・システムを出し抜くことが、人間であるわたしたちには可能なのだ。これを、アーヴァインは、進化という「奴隷主」に対して「奴隷」であるわたしたちが反乱を起こすことにたとえている。
現実の奴隷の状態を考えてみよう。たしかに奴隷たちは、主人とそのインセンティブ・システムから逃れることはできないかもしれない。だが、それでも彼らは、屈従によってみずからの人間としての価値が奪われるのを拒否するかもしれない。とくに仲間の奴隷を助けるためとあれば、全力を尽くそうとするかもしれない。そうなれば当然、ときとして主人の命令を拒むことになる。主人の目標達成に手を貸せば、みずからの生きるプランが設定した目標を損なうからだ。たとえば彼らは、仲間の奴隷を鞭で打てという主人の命令を拒むかもしれない。そうすればむろん奴隷監督から罰せられるだろう。だがそれは、意味ある人生を送るためにはわずかな代償にすぎない。宇宙的に見たら意味あるものではないかもしれないが、個人として見れば大きな意味をもつ。大事なのはまず間違いなくそこなのである。
私たち「進化の奴隷」もまた、自分たちのおかれた状況に対して、これと同じような戦略を使うことができる。自分自身が生きるための個人的プランを作り上げ、それを進化の主人が課したプランに重ねるのである。こうすれば私たちはもはや、進化の主人の命令に従っているだけの存在ではなくなる。みずからの人生を手にし、その人生で何かをーーみずからが意味あるものと考える何かをーーしているはずだ。そしてそれによって、私たちはできうるかぎりにおいて、自分の生活に意味を与えていることだろう。
ここで心に留めておきたいのは、みずから生きるためのプランを形成するとき、私たちは進化の主人を欺いているということだ。彼が私たちに欲望する能力を与えたのは、それによって彼の目標とする私たちの生存と繁殖が達成されやすくなるからである。だが私たちに与えられた欲望能力には、いくつかのオプションから選択する能力もまた含まれる。BIS(生物学的インセンティブシステム)が罰を与えるような事柄さえ選ぶこともできるのである。それゆえ、自分のライフプランを形成するというのは、事実上、この選択する能力を「濫用」していることにほかならない。私たちはその能力を、進化の主人が定めた目標を達成するためではなく、自分のために定めたべつの目標ーー進化の主人の目標とは相容れない目標ーーを達成するために使っているのだ。友人や隣人、あるいは職場のボスを欺くのは悪いことかもしれないが、進化の主人を欺くのは道徳的に何ひとつ問題ではないと私は思う。
(アーヴァイン、2007、p.281-282)
「進化の主人」に対して反乱を起こす方法は様々にあるだろう。キリスト教やイスラム教のような宗教が課す戒律に従って生きることができれば、欲求に振りまわされる人生からは脱却できそうなものだ。仏教も欲求をコントロールすることには定評があり、とくに禅の発想は現代の欧米でも注目されて、多くの人が実践している。そして、アーヴァインは、理性を駆使して欲求をコントロールする実践的なライフハックとして、ストア哲学を現代に復活させたのである。
ストア哲学の欲求コントロール
では、具体的には、ストア哲学では欲求をどのようにしてコントロールされるのか?
その主たる方針は、世の中には「自分の力でなんとかなること」と「自分の力ではどうにもできないこと」があることを認めたうえで、前者のみに力を尽くすことだ。
たとえば、コミュニティで一番の美女に恋慕の感情を抱いたところで、引く手あまたの女性が自分のことに興味を持って好意を抱いてくれて、他の男を差し置いて自分を選んでくれるかどうかは、相手次第である。そのようなことについて悩んでしまっても、時間と気力を消耗するだけだ。もし、美女のことで悩むのに使ったエネルギーを、代わりに運動であったり勉強であったりなどの自己研鑽に使えていれば、より快活に日々を過ごすことができていただろう。
恋愛でなくとも、たとえば社会的な地位や評判といったものに対する欲求が充たされるかどうかは、最終的には他人次第だ。収入をどれだけアップできるかは偶発的な事情に左右されるし、努力を積み重ねて築いた財産であっても、なんらかの失敗や災害によってあっという間に失われるおそれは常に潜んでいる。
自分の外側にいる他人や偶発的な事情に左右される物事に希望を抱いたり人生における幸福を見出そうとしたりすることは、分が悪い賭けであるのだ。それよりも、日々の生活において自分の能力を研鑽したり自分の心身の調子を良くする習慣を身に付けたりするなど、自分がコントロールできることに力を尽くしたほうが、安定して幸福を得ることができる。つまり、負ける可能性のあるゲームは避けて、勝てるゲームだけをすることが、ストア流の幸福の秘訣であるのだ。
とはいえ、実際のところ、まともに社会生活を送っている人間であれば自分のコントロールの範囲外の物事についても関わらなければならない。また、「自分のコントロールが完全には及ばないが、努力次第である程度まではコントロールが効いたり、目標が達成されたりする可能性を高められる」という物事にも、人生では多々直面することになるだろう。
そんなときには、「目標を内部化する」ことが重要になる。スポーツの試合でたとえるなら、「試合に勝つ」ことから「試合でベストを尽くす」へと、目標をずらせばよいのだ。ベストを尽くすことができれば試合に勝てる可能性も大幅に高められるだろうが、仮に負けたとしても、どのみち目標は達成されることになる。「試合に勝つ」という目標は、対戦相手の実力などの外部要因や偶然が絡んでくるために、達成されるかどうかは常に不安定だ。しかし、目標を内部化することで、どんな結果になったとしても心の平静を保ったままポジティブな感情を得ることができるようになるのだ。
「目標の内部化」という戦略は、仕事に対する向き合い方にも適用できる。結果として出世できたり立派なキャリアが築けたりするかどうかということにこだわるのではなく、仕事に対して自分がどれだけ真剣に取り組めるか、ということを目標にすればいい。同様のことは、恋愛を含んだ、他人との関わりにも当てはまる。他人の心とはコントロールできないものであるが、自分自身が恥じたり後悔の気持ちを残したりすることなく、他人に対して最大限に誠実に向き合うことを目標とすればいいのだ。そうすれば、うまくいったり運が良かったりする場合には社交や恋愛から得られる喜びを味わうことができるし、そうでない場合にも、自分の目標が達成されずに不幸や空虚感を味わうことは避けられるのである。
ネガティブ・ビジュアリゼーション
しかし、「欲求をコントロールすればいい」「目標を内部化すればいい」という発想には、「言うは易く行うは難し」という感想を抱く人もいるだろう。実際、多くの人は「欲求は抑制したほうが良い生き方ができる」ということについて理性では同意しているだろうが、日々の生活でそれを実践することができないからこそ困っているのである。
アーヴァインによると、古代のストア哲学者たちは机上の空論を唱えていたのではなく、欲求をコントロールするための具体的なテクニックを編み出して、それを実践していた。さらに、ストア流のテクニックは、現代における心理学の知見とも一致しているのである。
欲求を抑えるテクニックのなかでも基本となるものが、「ネガティブ・ビジュアリゼーション」だ。人生がいまよりもつらいものになることや、自分が築いてきた地位や財産が失われること、恋人や配偶者や子どもなどの大切な人々が亡くなってしまうことを想像する、という行為である。当たり前に存在していると思っているものがなくなってしまう事態を想像することで、逆説的に、いま自分が手にしているものの価値やありがたみを再発見することができる。それは、手にしていないものを獲得しようとする欲求を抑制することにもつながるのだ。
ネガティブ・ビュジュアリゼーションは、マーケティングの世界ではお馴染みの、「アンカリング(錨)効果」という心理学的知見を活用したテクニックである。
たとえば、まったく同じシャツを同じ値段で売るとしても、単に「定価3200円」で売るより「定価は4000円だが、20パーセントの割引セールにより3200円」という価格設定で売るほうが、客の購買意欲をそそりやすい。定価の4000円という金額を「錨」として客の潜在意識に沈めることで、3200円という金額を安価に感じるように仕向けられるからだ。同じように、ネガティブ・ビジュアリゼーションでは、「自分が手にしているものがなくなってしまった状況」を錨にして自分自身の潜在意識に沈めることで、いま自分が手にしているものの価値を感じやすくなるように、自分自身を仕向けさせるわけである。
アーヴァインによると、ネガティブ・ビジュアリゼーションは定期的に行うことが重要である。順調に日々を過ごしていると、「いま自分が手にしているものは、当たり前に存在し続けるものだ」とついつい思ってしまい、潜在意識に沈めた錨がいつの間にか外れてしまうからだ。
また、ネガティブ・ビジュアリゼーションは時間をかけて行う必要はないが、具体的な状況を想像しながら集中して行わなければいけない。たとえば「恋人が亡くなる」ということを想像する場合には、死んだことを相手の家族から電話で知らされる場面や葬式に参加している場面など、相手が亡くなった場合に実際に自分の身に起こりそうなことを想像したほうが効果的であるのだ。リアルな場面を想像すればするほど、生きている恋人と会ったときの喜びや感謝の気持ちは深くなるのである。
フレーミング効果を活用
アンカリング効果とあわせてストア哲学者たちが活用してきた心理学的テクニックは、「フレーミング(枠組み)効果」を活用したものだ。自分が経験している状況を認識する枠組みを変化させることで、その状況に対して自分が抱いている感情を変化させられる、というテクニックである。つまり、同じ事態にあっても、「気の持ちよう」次第によってその事態から自分が受ける影響は変えられる、ということだ。
たとえば、わたしたちには自分のことを正当化する傾向があるため、他人とのあいだでトラブルがあったときには「自分は悪くなくて、相手のほうが悪い」と枠組みで認識してしまうことが多い。しかし、「相手の悪意によって自分が傷付けられた」という考えを抱いていると、相手に対する怒りや被害者意識からストレスを感じてしまい、心の平静や幸福から遠ざかってしまう。それよりも、「自分にも悪い点があった」という枠組みで認識することで、怒りや被害者意識からは解放されて、同じようなトラブルが起こらないように反省したり欠点を改善したりすることにもつながり、生産性のある幸福な日々を過ごしやすくなるのだ。
そのほかにも、自分が直面している状況を悲劇ではなく喜劇として認識することができれば、いやな出来事があってもユーモアを持ちながら笑い話として処理することができる。または、自分の人生を運命論的に捉えるという枠組みもある。そうすると、どれだけ理不尽な不幸が起こったとしても、「最終的には、この不幸にもなんらかの意味がある」と見なしたり「この出来事は自分が成長するための試練として起こっているのだ」と見なしたりすることができて、前向きに生きることができるだろう。このように、フレーミング効果を駆使すれば、他人や社会などの外部要因や偶然によりどんなことが起こったとしても、「こういう感情を持ちたい」と自分が思う方向に感情を調整できる可能性がある。
感情の影響力は、しばしば過大評価されている。18世紀イギリスの哲学者デビッド・ヒュームによる「理性は情念の奴隷である」という言葉は有名だ。しかし、アンカリング効果を用いたテクニックにせよフレーミング効果を用いたテクニックにせよ、「感情」というものがどのようなタイミングで生じたりどのように機能したりするかを認識したうえで、発生する感情の種類やその感情が自分に与える影響を「理性」によって戦略的にコントロールする、という点が肝心となっている。感情と欲求は一直線に結びついていることをふまえると、これこそが、生物学的インセンティブ・システムという「奴隷主」に対して反乱を行う「奴隷」が手に取るべき、強力な武器だといえるだろう。
老人のための考え方?
さて、わたしがストア哲学……というか、アーヴァインの本に初めて触れたのは、ちょうど30歳のときであった。とくに『良き人生について:ローマの鉄人に学ぶ生き方の知恵』を最初に読んだときには、いたく感銘を受けたものだ。
30歳とは、「若者」と呼ぶにはそろそろ厳しくもなってくる年齢である。ただ単に快楽や刺激を得ながら生きることにも飽きや疲れを感じてきて、自分の身に降りかかる様々な出来事や他人との関係に振りまわされることへの虚しさを抱くようになり、自分の人生をいかに生きるべきかということについて改めて考え直すには、ぴったりの時期であった。『良き人生について』を読んだ当時は一年半近く付き合ってきた恋人と別れた直後だったということもあり、自分の外側に存在しておりコントロールが効かない他者ではなく、自分の心の平静を保つことや物事に対して自分がどう向き合うかということから人生における意味や幸福を見出す、という考え方には深く同意できるところがあった。
ただし、30歳とは、「若者」としての気分や感覚にまだ引きずられている年齢でもある。結婚をしたり天職に就いたりして落ち着いている人もいるだろうが、まだまだ人生の方針が見つからず物事の優先順位も定められずに迷っている人も多い年齢であるだろう。そんな年齢においては、地位や財産に対する欲求を捨てたり他者との関わりから得られる喜びを後回しにしたりして、自分の心の平静をなによりも重視する生き方を選択することには、尻込みしてしまうところもあった。実際、同世代の友人たちにストア哲学の考え方について紹介しても、賛同が得られないことが多い。アーヴァインも、自分が教える若い学生たちがストア哲学の考え方を受け入れることを拒みがちである点について嘆いている。
ストア哲学には「老人のための考え方」という側面がどうしても存在するのだ。たとえば子どもの頃からストアの考え方を実践することができて、恋人や親友のことを想って心が揺さぶられることもなく、「自分が活躍して地位や名声を取得してやろう」という野心を抱くこともいちどもないまま生涯を過ごすことができた人が存在するとしても、そのような人生を羨ましいと思えて、「自分もそんな人生を過ごしたい」と考える人の数は少ないはずである。
幸福を得るためには感情が必要
先述したように、生物としてのわたしたちが抱く欲求は、生存と繁殖を目的として設計されたものであり、わたしたちが幸福になるか不幸になるかを考慮して設計されたものではない。財産や地位に対する欲求、あるいは性欲や食欲などの明らかに低次元な欲求を充たすことだけを目的として日々を過ごしてしまった場合には、たしかに、意味がなくて不幸な人生となってしまう可能性が高いだろう。
しかし、「自分の人生には意味がある」と確信を持って思えるようになるためには、生きていくなかで「自分はいま意味のある人生を過ごしている」という感情を抱くことが必要となるはずだ。そして、理性が戦略を駆使することで感情をコントロールできるとしても、無から有を生み出すことはできない。心の平静を保つだけであれば理性のみに頼ることもできるかもしれないが、幸福を得るためには、けっきょくは感情が必要となるはずなのだ。
心理学者のダグラス・ケンリックの著書『野蛮な進化心理学:殺人とセックスが解き明かす人間行動の謎』では、「人生の意味とはなにか」という問いについて、進化心理学の観点から説明することが試みられている。
ケンリックは、まず、マーケティングの分野などで有名な心理学者であるアルフレッド・マズローによる「欲求のピラミッド」の理論を持ち出す。
マズローは、人間の欲求を、飢えや乾きや身の安全などを求める「生理的欲求」、恋人や友人を求めたり世間における地位や名声などを求めたりする「社会的欲求」、そして自分の才能を発揮したいという「自己実現」への欲求とに分別した。ピラミッドの基底部にあるのは生理的欲求であり、頂点にあるのが自己実現への欲求だ。どんな人間であっても、まずは飢えや乾きが充たされたり自分の身の安全が保証されたりすることを必要とする。しかし、それらの欲求がいちど充たされると、その次には他者からの親愛の情や、社会からの承認がほしくなる。それらを得られたら、こんどは、自己実現を目指したくなるのが人間というものである……と、マズローは論じたのだ。
ケンリックは、マズローの描いたピラミッドを進化心理学の観点から補修した。補修されたピラミッドでも基底部にあるのは生理的欲求に変わりないが、ピラミッドの頂点にあるのは自己実現ではなく「子育て」となっており、その下には「配偶者の獲得」や「配偶者の維持」がある。マズローのピラミッドでは上部に位置していた社会的欲求や自己実現への欲求は、ケンリックのピラミッドでは中間部に移動されている。生物として見た場合の人間の究極の目標は「繁殖」である以上、社会的地位を得て財産を築いたり自己実現をして魅力のある人間になったりすることも、異性を惹きつけて一緒に子どもを養い続けるという目的のための手段にすぎないと見なせるからだ。
自己実現を頂点に据えるマズローのピラミッドが個人主義的なものであったのに対して、子育てや配偶者を上部に据えたケンリックのピラミッドでは、「他者との結びつき」に関する欲求の重要性が高く見積もられている。そして、ストア哲学の発想と類似点があるのは、明らかにマズローのほうであるだろう。生理的欲求に価値を見出すべきではないのはもちろんのこと、他者からの承認や地位などの社会的欲求も、「自分の力ではどうにもできないこと」であるから執着してはいけない。ストア哲学が「心の平静」を目標としていることとマズローが「自己実現」を頂点に据えていることも、他者に左右されずに自分の意思と能力に基づいて実現できるものを理想にしているという点で、共通している。
他者がいないと充たされない
その一方で、ケンリックのピラミッドの上部にある欲求は、他者がいないと充たされないものだ。ストア哲学の考え方に基づけば、充たされるかどうかが不安定であるから抑制されなければならない欲求である。しかし、ケンリックは、わたしたちが「人生の意味」や幸福を感じられるようになるためにはこれらの欲求を充たすことが欠かせない、と論じる。社会的な生物である人間にとっては、他者との結びつきや家族を築くことへの欲求は根深くて重要なものだ。それを充たすことができなければ、いくら心の平静を保てたり自己実現できたりしたとしても、人生には空虚さが残り続けるかもしれないのだ。
人間主義を標榜する心理学者たちは、ときとして、どう見てもひとりよがりとしか思えないほど個人的な現象を重視するーー世界の見え方がお気に召さないなら、考え方を変えればいい。つまり、何事も自分次第というわけだ。自身の心を見つめ、独自の考えにふけり、自分の好きなことをするのは、ある基準においてはけっこうなことだ。だが突き詰めていえば、人間はそのようにできてはいない。私たちはそこまで自己中心的じゃないのだ。また、周囲の人々と一線を画していると思っている場合でも、それは別に高次の存在になっているのではない。大人になっても他者の要求に気を配れない人は、実は自己実現ができているのではなく、病的な状態であるだけかもしれないのだ。
(ケンリック、2014、p.163)
理性を重視するストア派の哲学者たちであれば、セックスに対する欲求は低次のものとして一蹴して、価値を認めないだろう。しかし、ケンリックは、セックスをすることやセックスを通じて配偶者と関係を維持することや子どもを生み出すことと、自己実現や人生の意味などの高尚な物事に対する欲求は密接に関係している、と論じているのである。
ライフステージに応じての実践を
では、実際のところ、どちらの側の言い分がただしいのだろうか?
いまのところ、わたしとしては、「時と場合による」としか答えられない。
先述したように、子どもや若者である時分からストア哲学を完璧に実践しようとすると、その人の人生は中心に空洞が空いたような虚しく不健全なものとなるはずだ。意味のある人生を送るためには、どこかの段階で、他者との結びつきを求めたり、自分ではどうにもならないことに対して欲求を抱いたりすることが必要となるはずなのである。
その一方で、歳をとって、ある程度の財産を蓄えて家庭も築いた段階になれば、欲求を抑制して心の平静を保つことの重要性は増していくはずだ。財産が欠乏している状態では人は不幸になるが、財産を蓄積すればするほど幸福になれるというものでもない、ということは経済学の研究などでもよく指摘されている。中年くらいになれば、必要以上に多くのものを得ようと欲求するよりも、たとえばネガティブ・ビジュアリーゼションを行うことでいま得ているものに満足して欲求を抑制したほうが、人生を有意義に過ごしやすくなるだろう。
なお、ケンリックも、人間の欲求はライフステージによって変動するということを指摘している。どんな人でも「繁殖努力」期である青年時代まではセックスに対する欲求が強くなるが、ある年齢を過ぎた頃から「子育て努力」期へと徐々に移行して、セックスそのものに対してではなく家庭を築くことに対する欲求のほうが強くなっていくのだ。もしかしたら、ストア哲学も、ライフステージに応じて実践するのがちょうどいいのかもしれない。繁殖努力期のあいだは魅力的な異性を獲得することや自分自身の魅力を増すことに向けて精一杯努力するべきであり、様々な欲求は努力に火をつけるガソリンとなるから無理に抑えるべきでないが、それらの欲求が無駄で重荷となってくるライフステージに差しかかってきたら、欲求に対するコントロールを徐々に強めていけばよいのである。
ただし、不遇な生い立ちであることや、自身の能力や魅力が根本的に不足していたりするなどの理由で、どれだけ頑張っても「配偶者の獲得」といったピラミッドの中間段階にある欲求すら充たせられないという人だって、世の中には多く存在しているはずだ。
そういう人たちについては、不利な境遇のなかで欲求を充たそうと無理に頑張るよりも、早い段階からストア哲学を実践したほうが、有意義な人生を過ごしやすくなるかもしれない。「自分の力ではどうにもできないこと」への切望はさっさと捨ててしまって、自分にも達成できることに集中したり、あるいは自分の境遇について考える際のフレーミングを変えたりすることで、ふつうであれば他人よりも不幸になるはずの人生でも幸福に過ごせる可能性が出てくるかもしれないのだ。
ただし、このように考えるとストア哲学は対処療法的な幸福論ということになるし、「負け組」のための幸福論ということになってしまいかねない。
そうでなくても、他者に振りまわされることを拒んで自分がコントロールできる範囲の幸福を強調するストア哲学の発想には、自閉的な雰囲気が付きまとう。わたしたちの多くは、自分の外部にある物事に対する欲求や希望を捨てて自分の内側だけに幸福を求めるというストア哲学の考え方に、多かれ少なかれ拒否感を抱くはずだ。
しかし、だれであっても人生のどこかの段階からは「心の平静」を目指したくなるということだって、また確かなはずなのである。人それぞれの事情や特性に合わせながらほどほどに実践するぶんには、やはり、ストア哲学は現代にも通じる有益な幸福論であることは間違いないだろう。
<参考文献>
ウィリアム・アーヴァイン(著)、竹内和世(訳)、『欲望について』、白揚社、2007年。
ウィリアム・アーヴァイン(著)、竹内和世(訳)、『良き人生について:ローマの鉄人に学ぶ生き方の知恵』、白揚社、2013年。
ウィリアム・アーヴァイン(著)、月沢李歌子(訳)、『ストイック・チャレンジ:逆境を「最高の喜び」に変える心の技法』、NHK出版、2020年。
ダグラス・ケンリック(著)、山形浩生・森本正史(訳)、『『野蛮な進化心理学:殺人とセックスが解き明かす人間行動の謎』、白揚社、2014年。


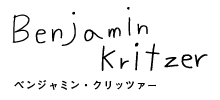 1989年生まれ。批評家。立命館大学文学部英米文学専攻卒業(学士)、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科卒業(修士)。
1989年生まれ。批評家。立命館大学文学部英米文学専攻卒業(学士)、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科卒業(修士)。