真珠夫人、感傷夫人に黄昏夫人……明治以来、数多く発表されてき
作品名:『真珠夫人』菊池寛 1920(大正9)年
さて、『真珠夫人』である。
本連載を人に説明する際によく「『真珠夫人』とか『武蔵野夫人』のようにタイトルに夫人とつく小説を時代順に読んで、当時のフィクションと現実の夫人像に迫る」のように言い、ある種「夫人小説」の代名詞としていた。
それだけ有名なこの小説に関する評論やエッセイは浜の真砂ほどもあり、通俗小説のエポックメイキングな作品として、またメディアミックスを含めた「現象」として、作者菊池寛の作家人生に於ける位置づけとして、もしくは読者個人の思い出や衝撃として、さんざん語られてきた。
今さらこの有名な作品と著者に付け加えることは何もない。かもしれない。
が、冒頭に示した主旨の連載であるならば、『真珠夫人』を軸にした虚実の夫人、いわゆるモデル問題をメインにしてみるのが筋かもしれない。
またモデルか、と思う向きにお伝えしたいのはこの小説、モデルではないのにモデルにされたと思い込んだ当時を代表するいわゆる名流夫人がいたのである。
ともあれ、まずは『真珠夫人』にまつわる事実の確認をしておこう。
それはつまり冒頭にひいた「さんざん語られてきた」ことのおさらいになる。
本作は1920年(大正9年)6月9日から12月22日まで全196回、『大阪毎日新聞』『東京日日新聞』(現『毎日新聞』の大阪本社、東京本社にあたる)に同時連載された、菊池寛にとって初の長編小説であり朝刊連載である。
当時の菊池は一般には無名で「作者を知らない読者は、掲載紙が「東日、大毎」であるために、菊池幽芳氏が本名で書き出したとばかり思っていた。そして本名の小説の方が面白いという評判までが立った程」(鈴木氏亭『菊池寛伝』)だった。前年に「大阪毎日新聞夕刊」で連載していた「藤十郎の恋」は舞台化もされているが、それでも一世を風靡したわけではない。
言ってみれば大抜擢だったわけで、これはひとえに「大毎」の学芸部長だった薄田泣菫の目利きによるものだ。
といっても、芥川龍之介の推薦があってのことであるし、一度の交渉ですんなり話が進んだわけでもない。が、森鴎外や志賀直哉らのハイブロウな作品が「大毎」読者(泣菫が「低級だからそのつもりで」と志賀宛の手紙に書いた、そんな読者)と嚙み合わなかった後に登板し、その任務に十分すぎるほど応えたのは事実である。
では、具体的にどれほど人気だったのか。
まず「『大阪毎日』だけで、之が為め五万以上の読者が殖えたそうだ」(『新潮』34〈11〉)とか「『大毎』の読者を一日に一万人ずつふやしたという伝説をもつ」(「新聞独占の形成道程」『思想』〈368〉)などの言説がある。さすがに後者は大袈裟ではないかと思うがいずれにしても類例のない流行り方で、連載中にもかかわらず前編として単行本が発売され、数え切れないほどの芝居にもなり、映画化は最終的に4回を数えた。芝居は河合武雄一座と伊井蓉峰、喜多村緑郎一座が競って公演したが、芥川龍之介、久米正雄、宇野浩二、菊池寛らが講演のために来阪した折には5、6箇所の劇場で芝居がかかり、菊池の風呂を芸者が覗きに来たという逸話がある(「文壇風聞記」)。また、志賀直哉は連載から7年後の昭和2年に信州の山間部で車掌や若者が熱心にあらすじを話しているところに居合わせ、「菊池寛が一とういいわ」という娘に「菊池寛は私の知人だよ」とか「(登場人物の一人杉野直也について)ナオヤというのは私の事だ」と言ったらみんな驚くだろうと想像したと書いている(『豊年蟲』)。
熱狂は文学者を目指す青年たちにも及んだ。「新聞小説など、軽蔑してい」た学生の林房雄が「第一回から読んで、非常に驚き魅きつけられ、最後迄見通した」(「真珠夫人を読んだ頃」)り、「既に文学青年で、通俗小説、大衆小説を単純に軽蔑して居」た倉島竹二郎が「すっかり魅入られて、毎日、新聞が来るのが待ち遠しいほどになってしまった」(「真実の人菊池寛」)。なお、帝大の学生だった川端康成は連載当時に菊池寛宅に上がっているが『真珠夫人』は「熱心に読んだのは必然」「新聞小説として新鮮で生彩ある感じだったという以上に、詳しい印象はおぼえていない」としている(川端康成「解説」)。
ではその「生彩」さのありかをさぐるために、簡単にあらすじを見ていこう。
実際に読んでみたい人は青空文庫に無料公開されているので参照されたい。
会社員、渥美信一郎はタクシー事故に遭い、たまたま乗り合わせた青木淳という青年から鞄の中のノートを捨てて欲しい、そして時計を渡して欲しいという遺言を受け取る。慎一郎はノートを手がかりに荘田瑠璃子の屋敷に赴き、彼女が財産家の未亡人であり、その美貌で男性たちを翻弄していることを知る。
もともと瑠璃子は男爵の娘で、同じ華族の杉野直也という恋人がいた。ふたりは荘田勝平という船成金の園遊会に招かれた際、密かに荘田の悪口を言っていたところを本人に聞かれてしまう。荘田は瑠璃子の美しさと華族の傲慢さに腹をたて、瑠璃子を妻にしようと目論んだ。瑠璃子の父は貴族院の議員で清廉潔白な人物だが家は抵当に入っていた。そこに目をつけた荘田は縁談を持ちかける。父は抵抗したが荘田の奸計で万策尽きたとき、瑠璃子は「ユーディット」(旧約聖書外典『ユディト記』に出てくる女性。故郷を守るために自ら敵陣に入って敵将の寝首を掻く)として結婚すると宣言。それはつまり結婚はしても貞操は守ることで荘田を生涯苦しめるという計画だった。
宣言通り瑠璃子は荘田と寝室を共にしなかったが、とうとう逃げられなくなったある日、知的障害のある荘田の長男が父を殺してしまう。
あっけなく未亡人となった瑠璃子は空虚な気持ちからサロンに男性たちを集めて恋愛遊戯にふける荒んだ生活に陥る。
ノートを託された信一郎も瑠璃子に魅了されサロンに出入りするようになるが、そこに死んだ青木淳の弟、稔がいることを知る。稔は兄同様に瑠璃子に惹かれており、実は瑠璃子も同じだったのだが、荘田の遺児、美奈子が稔を慕っていることを知り、母として潔く身を引く決心をする。ところが稔は瑠璃子を逆恨みし、彼女を刺して自殺。瑠璃子は今際の際に駆け付けた恋人の杉野直也に両親がいなくなった美奈子を託して絶命した。
それからしばらくして、画家を目指して家を飛び出した瑠璃子の兄が描いた一枚の絵が二科展に現れた。「真珠夫人」と題された瑠璃子の肖像画で、この絵は世人の称賛を浴びたのだった。
まず、主人公の渥美信一郎がいわゆる新中間層と呼ばれるエリートサラリーマンであることが今までになく新しい。そして、のっけから人が亡くなり、謎の遺言を手がかりに探偵小説ばりの展開が始まるのも斬新だ。さらに、自動車、白金(プラチナ)製の女性用時計、サロン、二科展などの道具立てもモダンである。園遊会も田口掬汀辺りが書けばどことなく明治初期かと思うような古臭いものになりがちだが、菊池は「丘の上には、数本の大きい八重桜が、爛漫と咲乱れて、移り逝く春の名残りを止めていた。其処から見渡される広い庭園には、晩春の日が、うら/\と射している。五万坪に近い庭には、幾つもの小山があり芝生があり、芝生が緩やかな勾配を作って、落ち込んで行ったところには、美しい水の湧く泉水があった」のように生き生きと描く(これは菊池寛にしては珍しかったため友人たちが「おい、菊池が自然描写をする」と囃し立てたとは小島政二郎の言)。さらに瑠璃子のサロンで通俗小説論が繰広げられるなど、メタな仕掛けもある。
とかく新聞小説といえばジェットコースター的展開が必須だが、今までの家庭小説のように狭い人間関係のいざこざやお涙頂戴で引っ張るのではなく、多様な人物たちの無理のない心理描写で次を期待させる。人を逸さぬストーリー展開は2002年に再ドラマ化してあらためて大ブームになるくらいに今でも通用する巧さである。
なにより美しい瑠璃子が「明治時代の美人のように(中略)人形のような美しさ」ではなく、皮肉も言えば本音も言う理性的且つ能動的な女性であることが画期的だった。「妾〈わたくし〉、男性がしてもよいことは、女性がしてもよいと云うことを、男性に思い知らしてやりたいと思いますの。男性が平気で女性を弄ぶのなら、女性も平気で男性を弄び得ることを示してやりたいと思いますの。妾〈わたくし〉一身を賭して男性の暴虐と我儘とを懲らしてやりたいと思いますの。男性に弄ばれて、綿々の恨みを懐いている女性の生きた死骸のために復讐をしてやりたいと思いますの」などと言い放つ女主人公。誰もが読む新聞というメディアで、建前ではなく本音を語る瑠璃子のような女性が登場する小説が載ること自体、瞠目に値したのだった。
それにしても、長編小説が初めての菊池寛がなぜここまで万人を熱狂させるほどの作品を書けたのか。
次回は本作の着想やモデルについて、またモデルにされたと勘違いした自意識過剰の名流夫人について掘り下げる。
〈おもな参考文献〉
鈴木氏亭「新聞小説に革命を齎した『真珠夫人』」『菊池寛伝』(実業之日本社、1937年)
澤木知彦「『大阪毎日新聞』と菊池寛の入社前後をめぐって――薄田泣菫の役割を中心に」『日本大学大学院国文学専攻論集』12(2015年)
「真珠夫人の後編」『新潮』34(11)(新潮社、1921年)
「文壇風聞記」「真珠夫人の後編」『新潮』34(1)(新潮社、1921年)
荒瀬豊「新聞独占の形成道程」『思想』(368)(岩波書店、1955年)
志賀直哉「豊年蟲」『近代日本文学21 志賀直哉集』(筑摩書房、1978年)
川端康成「解説」『菊池寛文学全集』第八巻(文藝春秋新社、1960年)
小島政二郎「「真珠夫人」思い出話」、林房雄「真珠夫人を読んだ頃」、倉島竹二郎「真実の人菊池寛」『菊池寛全集』第六巻〈第六回配本〉付録「菊池寛全集通信・3」(高松市菊池寛記念館、1994年)
鹿島茂「菊池寛アンド・カンパニー 第十二回『真珠夫人』創作秘話」『文藝春秋』(文藝春秋社、2022年)
篠田太郎「真珠夫人」『国語と国文学』12(10)(至文堂、1935年)
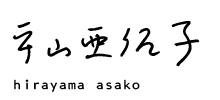 兵庫県生まれ、東京育ち。文筆家、デザイナー、挿話蒐集家。著書『20世紀破天荒セレブ――ありえないほど楽しい女の人生カタログ』(国書刊行会)、『明治大正昭和 不良少女伝――莫蓮女と少女ギャング団』(河出書房新社)、近刊に『戦前尖端語辞典』(左右社)、『問題の女 本荘幽蘭伝』(平凡社)。2022年3月に『明治大正昭和 不良少女伝』がちくま文庫となる。唄のユニット「2525稼業」所属。
兵庫県生まれ、東京育ち。文筆家、デザイナー、挿話蒐集家。著書『20世紀破天荒セレブ――ありえないほど楽しい女の人生カタログ』(国書刊行会)、『明治大正昭和 不良少女伝――莫蓮女と少女ギャング団』(河出書房新社)、近刊に『戦前尖端語辞典』(左右社)、『問題の女 本荘幽蘭伝』(平凡社)。2022年3月に『明治大正昭和 不良少女伝』がちくま文庫となる。唄のユニット「2525稼業」所属。
Twitter

