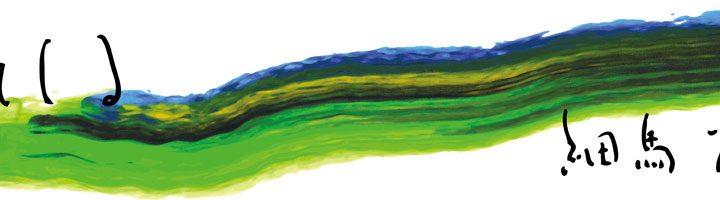歯医者で「痛いですか?」ときかれるとき、みんなどうしているのだろう?
わたしの行きつけの歯医者の先生は、まるで人が返答できない状態でいるときを狙いすましたように「痛いですか?」ときいてくる。そう尋ねられても、こちらは口をあんぐりと開けており、いままさにドリルがきゅうきゅうとあの頭にさわる音をたてて歯を削っているのだ。「いたくないです」と言おうとすると、「えあああえええ」、というわけのわからない声になる。首を縦横に振って身振りで示したいのだが、あいにく顔を固定されている。手を上げ下げするとうっかり機器に触りそうで怖い。もし万が一、手が先生の腕に当たって、ドリルが歯肉を間違って削り出したらどうしよう、などと、いつもなら一笑に付すことのできるスプラッターな想像が、やけにリアルに迫ってくる、それが歯医者という場所だ。
しかし、ドリルが歯の神経を強引に削って患者が失神したとか、ドリルが誤って頬を貫いたという人にいままでお目にかかったことはない。世界のいたるところで起こっているはずのこの危機的状況は、何度となく回避され続けているのだろう。
わたしの場合は、最近、偶然に解決した。あるとき、わたしが痛さに思わず「うっ」と喉の奥でうめくと、先生は「あ、痛い?」とドリルを離してくれたのである。
これは使える。
以後、「痛い?」と問われて痛いときは、同じ調子で「うっ」と喉を鳴らすことにした。では痛くない場合はどうするか。無言で何もしないと繰り返し「痛い?」と聞かれるので、頭を縦に振りたいのだが、頭が固定されているので、目玉だけが上下する。最初は虚しい動きだと自分で思っていたのだが、先生は黙って作業を続行する。どうやら、目玉の上下で意志は伝わっているらしい。
こうして、イエスは目玉の上下、ノーは「うっ」という、先生とわたしのローカルルールが確立した。ちなみにこの歯科医では3台の椅子が並列しているのだが、あちこちから「うっ」と聞こえるかといえばそうでもない。人によっては手元で手をひらひらさせているかもしれないし、顔をしかめているかもしれない。おそらく先生は患者ごとに微妙に異なるルールを作り合っているのだろう。
異なるローカルルールがその場でできるということは、そのようなローカルルールを生むルールなり前提があるはずだ。それはどういうものだろう。
***
会話分析には「隣接ペア」という考え方がある。これは一つにはわたしたちがよく用いている会話のパターンを言い当てる考え方である。
わたしたちは問いに答え、依頼に応じ、命令にことばで返答する。こうした営みでは、片方の発話に片方が応じるという形式が取られる。このとき、二つの発話を隣接ペアと呼ぶ。たとえば、タロウがハナに「楽しい?」と尋ね、ハナがすぐに「うん」と答えたとしよう。このとき、「楽しい?」「うん」という二つの発話は隣接ペアである。答えは肯定である必要はない。「楽しい?」「楽しくない」でも隣接ペアだ。
隣接ペアという考え方の奥深さは、これがわたしたちが会話をするときの一種の予測モデルになっているという点だ。問いを発した話し手は、相手はほどなく答えを返してくるだろうと予測する。聞き手は聞き手で、いま問うている相手はほどなく自分が答えを返すことを期待しているだろうなと予測する。そんなことは当たり前ではないか、と言われるかもしれないけれど、これらの予測があるのとないのとでは大違いだ。予測するおかげで話し手は、相手が「う」と言おうが「ほい」と言おうが「ぷ」と言おうが、それを問いに対する答えとして解釈しようとする。首を縦に振ろうが横に振ろうが振っているのが手であろうが足であろうが、それは何らかの返事ではないかと考える。聞き手は聞き手で、相手はたとえ自分が手を振ろうが足を振ろうが目を上下させようが、それを何らかの返事として解釈するだろうなと期待する。
予測モデルとしての隣接ペアがあるおかげで、わたしたちは他では見られないような応答をその場で作り出すことすらできる。たとえば「痛いですか?」に対して、ある患者が目を上下させる。謎めいた表現だが、これは「痛いですか?」に対する何らかの応答に違いない。「あ、窓の外に円盤が!」でも「あ、頭に画期的なアイディアがひらめきました」でもなく、「痛いですか?」に対する応答だと思ってもらえるだけで、一歩前進である。では目を上下させるしぐさは「痛い」を意味するのか「痛くない」を意味するのか。それを確かめるためには再びドリルで歯を掘り進め始めてみればよい。確たる反応がなければそれは「痛くない」だったのであり、再び目が上下すれば「痛い」だったのだろう。上下している目が涙目だったりしたら、さらに確度は高まる。
このように、予測モデルとしての隣接ペアは、わたしたちが応答を行うための前提となり、新たな応答のやり方を作り出すためのエンジンとなっているのである。
***
裏を返せば、予測モデルとしての隣接ペアの力は強い。特に、歯の治療のように、医師と患者の緊密な共同作業が行われる際には、隣接ペアという予測モデルは必須である。ここは痛みますかと尋ねられた直後に発声される「う」という声も、口を開けて下さいと依頼された直後に開く口も、隣接ペアの力によって治療の受け答えとして解釈される。たとえわたしが「痛いですか?」と問われたまさにそのときに、窓の外に空飛ぶ円盤を発見して「う」と言ったとしても、その発見が伝わる可能性はゼロに近い。
では、ほんとに空飛ぶ円盤を見かけてしまったらどうするか。「う」などと悠長な発声をしている場合ではない。目をぱちくりさせ「あああああああ!」とか「ぐるるるるる!」とか、隣接ペアを、いや、治療自体を中断させるくらいの、医師がたじろいで思わずドリルを口からはずすくらいの表情や奇声を用いるべきなのだ。隣接ペアという頑強な予測モデルをぶちこわし、「痛いですか?」という問いをなきものにして、空飛ぶ円盤を目撃したことを相手に理解してもらうには、それくらいとんでもない大胆さが必要なのである。
Profile
 1960年生まれ。滋賀県立大学人間文化学部教授。専門は人どうしの声の身体動作の調整の研究。日常会話、介護場面など協働のさまざまな場面で、発語とジェスチャーの微細な構造を分析している。最近ではマンガ、アニメーション、演劇へと分析の対象は広がっている。『介護するからだ』(医学書院)、『うたのしくみ』(ぴあ)、『今日の「あまちゃん」から』(河出書房新社)、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』(新潮選書)、『浅草十二階(増補新版)』『絵はがきの時代』(青土社)など著書多数。ネット連載に「チェルフィッチュ再入門」、マンバ通信の「おしゃべり風船 吹き出しで考えるマンガ論」などがある。
1960年生まれ。滋賀県立大学人間文化学部教授。専門は人どうしの声の身体動作の調整の研究。日常会話、介護場面など協働のさまざまな場面で、発語とジェスチャーの微細な構造を分析している。最近ではマンガ、アニメーション、演劇へと分析の対象は広がっている。『介護するからだ』(医学書院)、『うたのしくみ』(ぴあ)、『今日の「あまちゃん」から』(河出書房新社)、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』(新潮選書)、『浅草十二階(増補新版)』『絵はがきの時代』(青土社)など著書多数。ネット連載に「チェルフィッチュ再入門」、マンバ通信の「おしゃべり風船 吹き出しで考えるマンガ論」などがある。