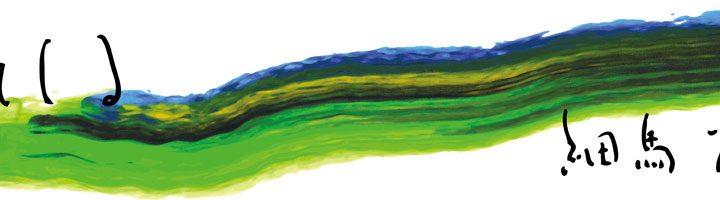年末にぎっくり腰になってしまった。
よく、腰が抜けるというけれど、ぎっくり腰で立たなくなるのは、単に抜けるというよりも、群発する痛みに対して体が瞬時に立つことを放棄するという感じだ。放棄するといっても、ただ全身が脱力するというのではなく、股関節から大腿まわりの筋肉のどこかがきかなくなって、それを他の筋肉で補おうとしながら結局果たせず、もうだめだと雪崩をうつようにあきらめていく、というのが高速に起こっている。だから、ばたんと上半身ごと倒れるのではなく、下半身の腰のあたりからへなへなとその場にへたりこんでしまう。
それにしてもこうしてぎっくり腰になってみると、「ぎっくり」というオノマトペは誠に味わい深い音だ。「ぎ」という決定的な音が無音の「っ」で強調されたのちに、「く」というややくぐもったことばが来る。この「く」でまさに腰がくずおれる感じ、尖った痛みがそのまま体の変調となってあらわになる感じがして、何度唱えても「ぎっくり」とはまさにあの、腰に一撃が来た瞬間とそのあとのへなへなとなる感じをよく捉えているなと思う。
***
日本語では子音と母音(もしくは単独の母音)が音の単位になっている。これを「モーラ」という。日本語のオノマトペには、「ぱっと咲く」の「ぱ」、「ぎっと鳴る」の「ぎ」のように一つのモーラ(子音+母音)で表されるものと「ぱかっと開く」の「ぱか」、「ぎくっとする」の「ぎく」ように二つのモーラで表されるものがある。「ぎっと鳴る」なら、「ぎ」のイメージだけを考えればよいのだけれど、「ぎくっとする」だと、「ぎ」と「く」の両方について考えなければならないから、ちょっと話がややこしい。
昔は、こうした二つのモーラから成るオノマトペを考えるときに、単純に第一のモーラだけに注目するか、第一のモーラのイメージと第二のモーラのイメージとを混ぜ合わせることで説明していた。これに対して言語学者の浜野祥子は、さまざまなオノマトペを比較した上で、第一のモーラと第二のモーラでは同じ音であっても象徴されているものが異なるという説を唱えた。
1998年に発表された彼女の説によれば、第一のモーラはものごとの性質を表す一方、第二のモーラはものごとの動きの性質を表す。もう少し詳しく書くと、第一のモーラの子音は重さやその触感/動きを表し、母音は形/大きさを表す一方、第二のモーラの子音は動きを表し、母音は運動の形/大きさを表す。わたしなりに言い換えてしまうと、第一のモーラは瞬間のできごとを空間的に捉えた感じ、第二のモーラはできごとの時間経過を微細に見ている感じ、というところだろうか。
たとえば同じkの音でも、第一モーラにくるときは硬い(軽く小さく細かい)表面を表し、第二モーラにくるときは開くこと、(内から外に)飛び出ることなどを表す。また、母音の「う」は、先行する子音の小ささや突出性を表す。
では、浜野説に従って「ぎく」について考えてみよう。「ぎ」は第一モーラで、gの音は大きく硬くて粗い感覚を示す。これはさしずめ第一の衝撃の大きさ・硬さ・粗さを表しているということになるだろう。一方、「く」は第二モーラだから、先に述べたように衝撃自体の性質よりもその動き、時間的な変化を担っている。kの飛び出す性質、「う」の突出性を合わせると、それはなにものかが内側から突出してくるイメージを表していることになる。
これは何かに驚いて「ぎく」っとするときの情動の現れのイメージ、硬く粗い「ぎ」が内側から突出してくるイメージによく合っている。ちなみに「ぎ」と「く」の間に入る「っ」は促音と呼んでいるけれど実際には無音区間で、これが入ると音のもたらす象徴がより強調されると言われている。「ぎくり」よりも「ぎっくり」、「びくり」よりも「びっくり」。声に出すと「っ」のもたらす強さが実感できるだろう。
***
「ぎっくり」というのは、単純に驚くときにも使うけれど、「ぎっくり腰」のように身体的なできごとに用いられるとまた別の感じが出る。わたしたちは、痛みを感じるだけでなく、痛みに対して体を大きく動かしてしまうことがある。特に突発的な痛みに対してはそうだ。ぎっくり腰の「く」には、単に痛みだけでなく、痛みに対する体の反応に近いイメージが感じられる。そしてこの体の反応は、もちろん、痛みに対して内側から外側に突出してくるのであるのだが、それは痛みによって力を得るイメージというよりは、痛みに耐えがたくなった体から力が抜けていくイメージである。
試みにいくつか「くり」で終わるオノマトペを思い出すと、むっくり、ぷっくりのように、何か兆しが現れるような語がある一方で、こっくり、ぽっくり、がっくりのように、下方に落ちるイメージを表す語もある。もともと「く」の音には、くぎ、くい、くき、くさ、くびのように、細く突出した名詞が目立つ一方で、古語の消(く)、屈(く)す、暗い、くすむ、朽ちるなど、消え落ちていくイメージを持つ語も多く見られる。陰影に富んだ音なのだ。
それでわたしは、浜野説にさらに消えゆく「く」のイメージを手前勝手にくっつけて、「ぎっくり」の音に、痛みに対して体が下方へと崩れていくイメージを感じ取っている。学術的に正しいかどうかはわからないのだが、少なくともそういうイメージを思い浮かべながらぎっくりぎっくりと唱えると、なんだか自分の体に表れ消えるものを考えるのが楽しくなってくる。これは理論というよりは、痛みをなだめるための歌のようなものかもしれない。
Profile
 1960年生まれ。滋賀県立大学人間文化学部教授。専門は人どうしの声の身体動作の調整の研究。日常会話、介護場面など協働のさまざまな場面で、発語とジェスチャーの微細な構造を分析している。最近ではマンガ、アニメーション、演劇へと分析の対象は広がっている。『介護するからだ』(医学書院)、『うたのしくみ』(ぴあ)、『今日の「あまちゃん」から』(河出書房新社)、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』(新潮選書)、『浅草十二階(増補新版)』『絵はがきの時代』(青土社)など著書多数。ネット連載に「チェルフィッチュ再入門」、マンバ通信の「おしゃべり風船 吹き出しで考えるマンガ論」などがある。
1960年生まれ。滋賀県立大学人間文化学部教授。専門は人どうしの声の身体動作の調整の研究。日常会話、介護場面など協働のさまざまな場面で、発語とジェスチャーの微細な構造を分析している。最近ではマンガ、アニメーション、演劇へと分析の対象は広がっている。『介護するからだ』(医学書院)、『うたのしくみ』(ぴあ)、『今日の「あまちゃん」から』(河出書房新社)、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』(新潮選書)、『浅草十二階(増補新版)』『絵はがきの時代』(青土社)など著書多数。ネット連載に「チェルフィッチュ再入門」、マンバ通信の「おしゃべり風船 吹き出しで考えるマンガ論」などがある。