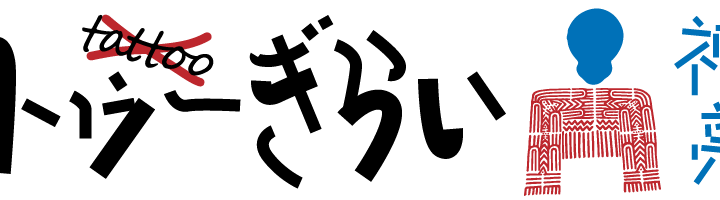あなたはタトゥーが好きですか?嫌いですか?
そう尋ねられたら、大半の人が「嫌い」と答えるだろう。少なくとも、2019年の日本社会においては。実際、タトゥー(刺青)に対する嫌悪感には根深いものがある。
関東弁護士会連合会が2014年に20~60代の1000人を対象に実施した意識調査では「イレズミを入れた人を見た時に、どのように感じましたか?」(複数選択可)という質問に対して、「不快」「怖い」といった否定的な回答が多くを占めた。
「不快」…51.1%
「怖い」…36.6%
「何も感じない」…14.2%
「個性的」(格好良い・お洒落)…11.2%
「強そう」…6.2%
「見たことはない」…8.3%
「『イレズミ』や『タトゥー』と聞いて、何を連想しますか?」(複数選択可)という質問も同様で、「アウトロー」「犯罪」といったネガティブな回答が、「芸術・祭・ファッション」「スポーツ」などのポジティブなイメージを大きく上回っている。
「アウトロー」…55.7%
「犯罪」…47.5%
「芸術・祭・ファッション」…24.7%
「スポーツ」…5.5%
「その他」…9.6%
優しさで窒息する前に
タレントのりゅうちぇるさんが昨年、両肩に妻子の名前のタトゥーを入れたことを公表すると、ネット上に批判の声が巻き起こった。
「タトゥー入ってたらプールとか温泉とか連れていってあげれないよね…子どもがかわいそう」
「子どもの名前入れた?芸能人だから何でもやって許されるの?日本に住んでるんだから、今の日本を理解した方が良い。ただのエゴイスト」
「テレビの出演減りますよ」「必ず将来後悔する。日本人には似合わない」
なんと思いやりにあふれた人たちだろう。会ったこともない芸能人の、さらにその子どものレジャーの心配までしてあげるだなんて。ねっとりと絡みつくような、湿度の高い優しさに窒息しそうになる。
後悔する権利
「将来後悔する」というのも、タトゥー批判の定番だ。
私は冷たい人間なので、家族や特別親しい友人でもない限り、どこかの誰かが何を後悔しようと、あまり関心を持てない。でしゃばってお節介を焼く気になれないのだ。
「後から悔いる」から後悔なのに、先回りして後悔を心配するというのもおかしな話である。そもそも後悔は、是が非でも避けるべきものだろうか。
一切の後悔のない、のっぺらぼうな人生など願い下げだ。「わが生涯に一片の悔いなし!!」と叫んで様になるのは、死に際のラオウだけである。
人は誰しも後悔する権利があるし、不幸になる自由がある。
「後悔するぞ」という助言めいた言葉の裏には、親切心の糖衣で包んだ脅し文句が見え隠れする。気に入らない人間が不幸な目に遭って後悔しそうだと思うのなら、「ざまあみろ」と静かにほくそ笑んでおけばいいじゃないか。
自分事と他人事
「この体で、僕は大切な家族の笑顔を守るのです。なので、この体に、大切な家族の名前を刻みました。隠すつもりもありません。でも意地でも出したいわけでもありません。自然に生きていきたいです。偏見が無くなりますように」
りゅうちぇるさんはInstagramでこう反論した。覚悟を決めた人間に対して、外野がいたずらに口出しすべきではないだろう。
自分の体と人の体を区別する。自分事と他人事の間に、明確な一線を引く。それだけで、世のいさかいの大半は回避できる。
他人に理想を押し付け、変えようとするから衝突が起きる。変えられるのは自分だけ。人は変えられない。だったら放っておけばいい。優しさはバファリンだけで十分だ。
私は何もタトゥーを称賛、推奨したいわけではない。もし政府が「明日から全国民にマイナンバーのタトゥーを入れて管理します」と言い出したら、即座に反政府レジスタンスに身を投じるだろう。
誰かがあなたの体に無理やりタトゥーを入れようとしてきたら、全力で怒っていい。でも、それがあなたの体でないのなら、華麗にスルーする方が精神衛生に資すると思うのだ。
タトゥー禁止令
私がタトゥー関連の取材を始めたのは、新聞記者をしていた2015年。医師資格なしに客にタトゥーを入れたとして、大阪府警が相次いで彫り師を摘発していると知ったことがきっかけだった。
医師の国家試験は超難関。彫り師になるために医師免許の取得を義務付けられるとしたら、事実上の「タトゥー禁止令」にもなりかねない。
それってどうなの?大阪府警の捜査幹部に疑問をぶつけると、まったく意に介さない様子で「逆に、それでどうなの?と質問したい」と鼻で笑われた。一体なんの問題があるのか。そう言わんばかりの口ぶりだった。
摘発された当事者の一人である彫り師の増田太輝さんは、医師法違反の罪で在宅起訴され、異例の法廷闘争を決意。罰金30万円の略式命令を拒否し、「彫り師の仕事をきちんと認めてほしい」と無罪を訴えて正式裁判を申し立てた。
タトゥーは医療か、アートか――。増田さんのニュースは新聞でも大々的に報じられ、にわかに注目を集めつつあった。
ところが前述の捜査幹部は、タトゥー施術による感染症リスクや衛生環境を引き合いに出し、こう吐き捨てた。
「芸術家と言われるけど、不潔だよね。誰でも勝手に彫っていいのかと聞かれれば、私は親としては否定したい」
「パパ」は大阪府警
念のために付言すれば、増田さん含め多くのタトゥースタジオでは、針やインクを入れるキャップは使い捨てのものを使用しているし、それ以外の器具も滅菌器で消毒している。
それ以上に引っ掛かったのが、幹部の口をついて出た「親としては」という言葉だった。
「パターナリズム」(父権的干渉主義)という用語がある。国家が国民の父親になり代わり、あれやこれやと介入し、世話を焼くことを意味する。
さしずめ「パパは大阪府警」といったところか。パターナリズムを体現するかのような捜査幹部の発言に戸惑いつつ、私はこの光景に既視感を覚えていた。
ダンスとタトゥーの相似形
2010年代に入って、全国各地でダンスクラブの摘発が相次いだ。「無許可で客を踊らせた」という風俗営業法違反容疑によるもので、その余波は社交ダンス教室やサルサバーなどにまで及んだ。
なぜ、ダンス教室までもが法律の規制対象になるのか。騒動のさなか、タンゴ関係者との会合で警察庁の担当者はこう説明した。
「規制を法律から外すと、ダンス教室と称して『水着の女子高生と抱き合って踊れる』といった営業をされる可能性がある」。お父さんはいつだって、過保護で心配性だ。
不条理な取り締まりに危機感を募らせたクラブ利用者やミュージシャンたちは、ダンス営業規制の撤廃を求める署名運動を展開する。坂本龍一さんや、いとうせいこうさんら著名人も呼びかけ人に名を連ねた。
最終的に15万筆を超える署名が集まり、超党派の国会議員連盟が発足。並行して、風営法違反容疑で逮捕された大阪のクラブ「NOON」の元経営者、金光正年さんが無罪判決を勝ち取るという動きもあった。
司法・行政・立法をまたにかけた大きなうねりが結実し、2015年に改正風営法が成立する。こうして条文から「ダンス」という文言は削除された。
私は摘発劇から法改正に至るまでの動きを追いかけ、著書『ルポ風営法改正〜踊れる国つくり方〜』にまとめた。根底には、ダンスという人間の原初的な営みを法律で取り締まることに対する、拭いがたい違和感があった。
タトゥーの彫り師に医師資格を求めるというナンセンスな事件に直面し、この時の記憶がありありと蘇ってくるのを感じた。
文化と規制が擦れるところ
風営法によるダンス規制と、医師法によるタトゥー規制にはいくつかの共通点がある。
ひとつは、戦後間もなくつくられた法律が長い時を経て「亡霊」のように立ち現れ、取締り強化の道具に使われたこと。風営法も医師法も1948年に制定されているが、摘発が活発化したのは2010年代以降だ。
もうひとつは、ともに大阪府警が摘発の発火点となったこと。風営法では金光さん、医師法では増田さんが法廷闘争に立ち上がった。
そして最後に、文化と規制が激しく摩擦を起こしていること。ダンスもタトゥーも太古から続く身体表現でありながら、時に権力と鋭く対立してきた。
背景がよく似ているがゆえに、私はタカをくくっていた。医師法の問題も早晩カタがつくだろう、風営法と同様の経過をたどるだろうと。
だが、その見立ては間違っていた。ダンスとタトゥーでは、社会との摩擦係数が大きく異なる。取材を進めるなかで、嫌というほど思い知らされることになる。
「タトゥーぎらい」と同調圧力
医師法問題のみならず、タトゥーへの逆風は強い。
入浴施設やプールには当たり前のように「タトゥー禁止」の張り紙が貼られ、芸能人がタトゥーを入れようものなら烈火のごとく非難される。
長年、東京で開催されてきたタトゥーイベント「キング・オブ・タトゥー」も、会場の確保が困難になって2017年に中止を余儀なくされた。
こうした摩擦の根っこには、「タトゥーぎらい」の感情が横たわっている。この連載の狙いは「タトゥーぎらい」の論理と心理を読み解き、摩擦係数を下げるための処方箋を示すことだ。それはとりも直さず、日本社会の同調圧力について考えることでもある。
ネット上には今日も「〇〇ぎらい」があふれている。月曜日は俳優の違法薬物、火曜日はミュージシャンの不倫、水曜日はお笑い芸人の不祥事……。
日替わり定食のように提供されるスキャンダル。もっともっと、誰かを、何かを嫌いたい。心置きなくぶん殴れるサンドバッグがほしい。「タトゥーぎらい」も、そんなサンドバッグ欲求の一断面なのかもしれない。
ラグビーW杯では、タトゥーを入れた選手たちが数多く来日した。来年の東京五輪では、さらに多くの選手、観客が日本を訪れるだろう。
だからと言って、「タトゥーぎらい」の人たちに向かって、「好きになってください」「考えを改めてください」と説いても何の意味もない。「うるさい、黙ってろ」と言われるのがオチだ。
なぜ私たちは「〇〇ぎらい」を欲し、脊髄反射的に叩いてしまうのか。タトゥー嫌悪の諸相を読み解くことで、この問いの手がかりを探れないだろうか。
冒頭でタトゥーが好きか嫌いかを質問したが、連載を通して「好き」でも「嫌い」でもない第3の選択肢を提示できたら、と考えている。

1983年、埼玉県生まれ。早稲田大学法学部を卒業後、2005年に朝日新聞社入社。文化くらし報道部やデジタル編集部で記者をつとめ、2015年にダンス営業規制問題を追った『ルポ風営法改正 踊れる国のつくりかた』(河出書房新社)を上梓。2017年にBuzzFeed Japanへ。関心領域はサブカルチャー、ネット関連、映画など。取材活動のかたわら、AbemaTV「けやきヒルズ」やNHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」にコメンテーターとして出演中。