ロックとはなんだったのか? 情熱的に語られがちなロックを、冷静に、理性的に、「縁側で渋茶をすするお爺さんのように」語る連作エッセイ。ロックの時代が終わったいま、ロックの正体が明かされる!?
1971年にジム・モリソンが死んだ辺りで、ヒッピーたちの楽園は70年代の初頭には潰えた感がある。そして70年代のロックは、60年代とは違った色合いを見せるようになってゆく。新しいバンドがいくつも登場して、ロックのイメージを塗り替えていったのである。69年にレッド・ツェッペリンとキング・クリムゾンが最初のアルバムを出している。つまりハードロックとプログレッシブロックという二つの潮流が、その存在感を主張し始めたわけだがそれに伴ってアルバムジャケットも凝ったアートワークになっていった。文化進化である。70年代こそはロックの黄金期だ。この時代のロックを一言で言い表すとしたら、それは絢爛豪華ということになろうか。ド派手で華美な方向へ、つまりは巨大な産業化へと向かったのである。レコード産業は右肩上がりで、コンサートも照明や舞台装置など、派手な演出を取り入れるようになった。一番わかりやすいのは、この時代のローリング・ストーンズである。ミック・テイラーが加入したのでハードロック的な楽曲をアルバムに加え、舞台装置は大がかりになった上にグラムロックが流行っていたのでミック・ジャガーは濃い化粧をしていた。派手派手である。70年代ロックの総合商社か。実際、ジャガーは経済学部にいた人なので、この頃には既に経営者の視点でバンドを運営していたのではないか。60年代の時点で元々は単なる流行歌手であるロックスターが、社会的な影響力を持つ文化人足りえることに気がついていた人である。この、企業の経営者が自らパフォーマンス乃至プレゼンを行うというスタイルはおそらく、60年代カウンターカルチャーの後継者の中で最大の成功をおさめたシリコンバレーの活動家たちに大きな影響を与えている。スティーヴ・ジョブズとビル・ゲイツがロックンロール誕生の年である1955年生まれなのは偶然ではない。彼らは十代の多感な時期にジョン・レノンやボブ・ディランがエレキギターで世界を変えるのを目撃したのである。ジョブズが亡くなった今も我々は、彼のパフォーマンスを動画で観ることができる。大勢の聴衆を相手に楽しげにAppleのビジョンを語るジョブズは、パフォーマンスアーティストであり、メッセージの送り手である。おそらく、この頃になるとミュージシャンたちはロックが資本主義の権化であることに気がついていた。なので、キッスのジーン・シモンズ、ブラック・サバスにいたオジー・オズボーンのような人たちは経営者としてのセンスを身につけ、言ってみればサーカスの座長のようなスタンスで活動を行うようになる。後にバンドを脱退し、ソロになったオズボーンはクワイエット・ライオットにいた若くて有能なギタリスト、ランディ・ローズを抜擢する。ローズは飛行機事故によって悲劇の死を迎えるが若きギターヒーローとして伝説的な存在となった。その後もオジー・オズボーンバンドは何人もの著名なプレイヤーたちを輩出している。後にヴァン・ヘイレンのボーカルだったデイヴィッド・リー・ロスがバンドを脱退してソロになった際にはスティーヴ・ヴァイという若手のギタリストをバンドに招聘している。オズボーンもリー・ロスも、その後は元いたバンドに戻ったりしている。二人ともバンドのフロントマンである自覚こそあったものの、ステージの上で歌う自分の横にはギターヒーローが必要であることをよくわかっていたのだ。スターであるボーカルと、そのバックバンドという構成ではロックにならないのである。極論を言うと、メンバーが一人変わっただけで別のバンドになってしまう。それがロックというミニマムな文化である。だからこそ、レッド・ツェッペリンはドラムのジョン・ボーナムが死ぬと速やかに解散した。潔い。ボーナムなしにレッド・ツェッペリンは成立しない。それは決してロマンチックなボーナムへの哀悼だけではなく、物理的にボーナムのドラミングを再現できる人材が存在しないことを意味している。極端に個性的なドラマーを擁したバンドで、ドラムが最初に死んでしまった大物バンドとしてはザ・フーがいる。ザ・フーのキース・ムーンはボーナムよりも二年ほど前に死んだ。ザ・フーは彼の死後、スモール・フェイセズからフェイセズでドラムを叩いていたケニー・ジョーンズをドラムに迎え、活動を続けた。この選択は決して間違っていたとは思えないのだが、やはりムーンがいた頃とは違うのだという感触を多くのファンが持った。つい最近、ローリング・ストーンズのチャーリー・ワッツが癌で亡くなってしまったわけだが、バンドはスティーヴ・ジョーダンをサポートメンバーに迎えてツアーを行った。もはやオリジナルメンバーはボーカルとギタリストの二人しかいないわけだが、これはミックとキースさえいればローリング・ストーンズなのだ、というような話ではない、のである。ローリング・ストーンズのファンというのは若い人もいるだろうけれども、50年前からずっとファンだったような人が世界中にゴロゴロいるのである。彼らの多くは、ジョーダンが30年以上前からこのバンドに関わってきたことを知っているし、ジョーダンがワッツを尊敬していることも知っている。ベースのサポートメンバーであるダリル・ジョーンズにしても、オリジナルメンバーであるビル・ワイマンが脱退してから30年近くローリング・ストーンズと関わってきたわけで、今やビル・ワイマンがいるローリング・ストーンズを生で観たことのある人というのはおじさんおばさんしかいない。ロックバンドにおいて、とりあえず目立つのはボーカルとギターであるが、リズムセクションもフロントの二人以上に重要である、ということをロックが好きな人の多くは周知している。ロックを好む層の何割かは自分でバンドをやったことがあり、ドラムとベースがいかに重要なポジションであるかを経験的に知っているからである。初心者のアマチュアバンドであっても、ドラムが上手いとそれなりに演奏が整うし、演奏していて気持ち良さも感じる、というのをアマチュアバンドの経験者の多くが、個々の経験として知っているからこそロックは、それ以前のポピュラーミュージック以上に、裏方的なドラマーやベーシストをリスペクトするようになったわけだ。かてて加えて、ローリング・ストーン誌がロック評論という文脈を確立させたことにより、ロックを如何に語るかという文化が成熟した。変な言い方になりますが、ロック語りというのは生物学的な競争である。ロックを批評する文化が成立することによって、わたしは貴方よりも優れた論旨でこのバンドを語れるんですよ、というマウンティング文化が確立されたのである。それは、非常にいやらしいスノッブな作法にもなるのだが、ロックを語る行為が一種の競技になったことで、ポピュラーミュージックを語る際の視点が多様化されたのは重要である。カッコいい曲を聴いた時に、とりあえずボーカルがカッコいいとか、ギターリフがカッコいい、ギターソロがカッコいい、といった感情が先に出てくるのは当たり前である。演奏している人たちは、その楽曲を魅力的にするために己のスキルを駆使しているから、近代以降のポピュラーミュージックにおいては、全てのパートがボーカルの魅力をサポートするような構造になっている。歌手とバックバンドという構造は、バンドのメンバーが協力してお神輿を担ぎ、ボーカルを支えているわけだ。フランク・シナトラやエルヴィス・プレスリー、我が国の三波春夫といったアーティストは、この前近代的なシステムに則って大衆音楽としての支持を得た。彼らはソロシンガーとして、既成のビッグバンドの演奏で歌ったり、有能な演奏者を個人で抱え込んで雇ったりした。ロックが生まれる前の文化である。オジー・オズボーンやデイヴィッド・リー・ロスがソロ活動をした時、彼らは若手のギタリストを抜擢し、そちらにもスポットが当たるようにした。この二人に関して言えば、座長ボーカリストとバックバンドという昔風のスタイルで経営を行うことは可能であった、にも関わらず若手で有能なギタリストを抜擢し、そちらにもスポットライトが当たるようにしたわけだ。自分だけが注目されるより、若いメンバーにもスポットが当たった方が良いのだという判断があったわけだ。ロックバンドというのは、そもそものスタート地点では近所の友達が集まってやるものだから、縦割り社会的な関係性はない。デビューして印税が入るようになると作詞作曲をしているメンバーと、そうでないメンバーの間に収入面において格差が生じ、それが原因で解散することもあるのだが、基本的には民主的なのである。チャーリー・ワッツが亡くなった時にキース・リチャーズが、酔っ払ったミック・ジャガーが電話で失礼なことを言ったので怒ったワッツが髭を剃り正装をした上でミックをぶん殴ったというエピソードを披露した。これは80年代のことらしいので、殴った方と殴られた方は、この時点で20年以上共に仕事をしてきたわけである。普通の会社で部下が上司を殴ったらクビになる可能性が高いが、ご存知のようにチャーリー・ワッツは死ぬまでローリング・ストーンズのドラマーであった。その上で、趣味的にジャズのドラマーとしても活躍し、そちらでも良い仕事を残している。企業としてのローリング・ストーンズを考えた場合、社長というかCEOはやはりミック・ジャガーだと考えて良いだろう。ローリング・ストーンズは、創業時の代表であったブライアン・ジョーンズが会社の運営を滞らせるような存在になったので、仕方なく彼をクビにしたらその直後にブライアンが死体で発見されたという悲しい過去を持つ。オルタモントでフリーコンサートを行ったら、警備員のヘルズ・エンジェルズが観客の一人を刺し殺すという事件に発展した悲しい過去も持つ。社長としてのミック・ジャガーは色々と大変な経験をしてきたわけだが、騒乱の60年代、装飾過多の70年代を経た80年代においても、ミックがチャーリーに失礼なことを言ったら、正装したチャーリーがミックを殴り、それを後にキースが語るという文脈があったのである。ローリング・ストーンズの歴史において、一貫してワイルドなキャラを演じ70年代においてはホテルの窓からテレビを投げたりしていたキースが、この2020年代に1980年代を回想するエピソードにおいては、古い友人たちのトラブルに巻き込まれたお人好しのポジションになっているのは興味深い。ローリング・ストーンズの場合、ボーカルの社長が良くないことをすると、ドラムのチャーリーが正装して社長を殴りに行くのである。ロックバンドというのは資本主義的なシステムに依存しながら、ドラムよりボーカリストの方が偉いというような縦割りの価値観を拒否しているわけである。その根元にあるのはロックバンドが近所の友達や、その兄弟が集まってできた最小限の共同体だからだ。オジーはランディを雇用したが、それ以上に彼を引き立てた。営利的な経営をしながら、個人の個性が尊重されていたのだ。
70年代のロックは産業として成長したが、50年代に小型トランジスタラジオの製造でロックンロールの普及に貢献した日本という国が、またしてもロック普及のハブとして機能する。まず、経済成長を遂げたので多くのロックバンドが日本を無視できなくなった。日本のイベント会社も、60年代の後半から欧米のロックバンドを頻繁に招聘するようになる。ビートルズはキャリアの途中でライブを行わなくなったので、彼らが海外で公演したのはドイツを除くと日本とフィリピンしかないわけだが、フィリピンでは大統領夫人であったイメルダのパーティを欠席したことでトラブルになり、メンバーたちは逃げるようにフィリピンを離れた。70年代においては、欧米のロックバンドがツアーを行えるアジアで唯一の国が日本だったのである。71年にBS&T、シカゴの武道館公演が行われ、グランド・ファンク・レイルロードが後楽園球場(屋根ができる前の東京ドームである)で、ピンク・フロイドもレッド・ツェッペリンも来日、それぞれが伝説的な公演を行った。そして72年、ディープ・パープルが来日する。日本側からの申し出により、この公演はレコーディングされて当初は日本のみのオリジナルライブアルバムとして発売されたが、後に『Made in Japan』というタイトルで全世界で発売され、めちゃくちゃに売れて今でも売れているのである。ライブアルバムなので製作費は安い。ディープ・パープルはイギリスのバンドなので、これがイギリスでの公演の記録ならば、そこまでは売れていかなったろう。中身はもちろん良いのだが、世界的ヒットとなった鍵はおそらく「メイド・イン・ジャパン」という言葉にある。日本という、敗戦国でありながら、異様な経済成長を遂げつつあった国でのライブだったから、謎の付加価値が生まれたのだ。終戦から20年をこえて、60年代のうちにSONYやHONDAといった日本企業の名前は世界中に知られていた。この時代においてメイド・イン・ジャパンとは、優秀な製品であることを意味したのである。ともあれ、ディープ・パープルのおかげで武道館の名前が海外のアーティストたちに知られるようになった。ロックという音楽は黒人から白人へ、さらにアメリカからイギリスへ、といった貿易によって成長してきた文化である。ビートルズが勲章をもらったのは、もちろん外貨を獲得したからである。それ以来、イギリスのミュージシャンたちにとってアメリカで売れることは大きな意味を持つようになっていた。イギリスでトップになるのと、アメリカでトップになるのでは経済効果の桁が違うのである。だがしかし、ポピュラー音楽においてアメリカでNo.1になるというのは、ほぼほぼ世界一になるのと等しいわけであるが、アメリカでそこまでの成功をおさめられなかったとしても、戦後の経済成長で購買力が増した日本で売れるという道があったのである。たとえば1975年にクイーンが初来日した際には、もちろん武道館での公演が行われフレディは振袖を着て登場したわけだが、この時点で既に日本には熱狂的なクイーンファンが大勢いたのである。音楽雑誌『ミュージック・ライフ』の東郷かおる子がグラビアでクイーンを何度も取り上げていたからだ。バンドの方も日本と東郷かおる子との繋がりは大事にしていた。初来日の時点で、決して売れていなかった訳ではないのだが生まれて初めてやってきた日本で空港に着くやいなや数千人のファンが押し寄せ、記者会見をすることになったのだ。クイーンと『ミュージック・ライフ』の接点は、別件の取材でニューヨークに来ていた東郷かおる子が、たまたま見かけたロジャー・テイラーに声をかけたことに始まるのだが、その際に自分たちのバンドがグラビアページを飾っている『ミュージック・ライフ』を見せられたテイラーは驚きかつ喜んだという。そりゃそうだろう。この時点でのクイーンは、まだこれからという時期である。その頃、大半の欧米人は日本語を読めなかったが、読めない言語で書かれた雑誌のグラビアに自分たちの写真が使われていたのである。70年代といえば、1ドルが300円の時代である。大半のイギリス人にとって、日本は遠い国だったし、日本から見たイギリスもまた遠かった。距離はロマンを生むのである。ブリティッシュ・インヴェイジョンの波が起きたのは、イギリスの若者たちが海の向こうの黒人ブルースやロックンロールに遥かな憧憬を抱いたからだ。遠距離恋愛の恋人たちではないけれども、距離があると想像が膨らみロマンが増す、のである。イギリスのバンドにとって、アメリカでライブを行うことは物理的に遠くまで行くことだったわけだが、日本はさらに遠い。その日本で信じられないような歓迎を、クイーンのメンバーたちは受けたわけだ。日本のクイーンファンから見ると、遥か遠くのイギリスから、遂にクイーンがやってきたのである。ご存知のようにフレディ・マーキュリーはある時期から髪を短く整え、髭をたくわえたキャラに変貌するが、この頃はまだ長髪でメンバー全員が美形キャラであった。ここで日本独自のブリティッシュロック需要が派生する。戦後の日本において急速に発達した文化の筆頭は漫画だろう。少女漫画家たちは、自作の中にデヴィッド・ボウイやロバート・プラントをモデルにしたキャラクターを登場させ、これが読者に対する啓蒙として機能した。また徹夜の多い漫画家たちは眠気覚ましにハードロックを聴きながら仕事をした。クイーンは後にライブ・エイドの辺りで文字通りの世界的な成功をおさめたが、メンバーたちは一貫して親日的で、特に『ミュージック・ライフ』との繋がりは大切にしていた。世界的な成功をおさめた後でも売れる前からの人間関係をないがしろにしないという点で、ロックは少年期から青年期で獲得した繋がりを大切にする文化なのである。そして77年にデビューしたチープ・トリックは正真正銘、日本から売れたバンドだった。ボーカルとベースがイケメンで、ギターとドラムが変なおじさんという編成のチープ・トリックは、アメリカには珍しいタイプの英国的な諧謔と洒落っけのあるバンドで、『ミュージック・ライフ』も『ロッキング・オン』も推していたから日本ではすぐに売れたものの、アメリカ本国では今ひとつ。それが78年に出した『チープ・トリックat武道館』が大ヒット。遂に世界中で知られるバンドになった。この辺りから、おそらくBudokanという固有名詞にはSONYやHONDAに似た魔法のようなオーラが漂いはじめていたのである。70年代から80年代にかけて、日本での公演をライブアルバムとして出したアーティストは他にも大勢いる。ロックだけではなくてジャクソン5にテンプターズ、マイルス・デイヴィス、ハービー・ハンコック。ノーベル文学賞のボブ・ディランにも『At Budokan』がある。戦後の日本が経済大国たりえたからこそ、日本でのライブアルバムを出せば、まず日本で売れるし、日本で売れている証拠にもなるから他の国でも売れるだろう、という魔法のようなインセンティブが成立したのだが、それはディープ・パープルの『Made in Japan』がアメリカでプラチナディスクを獲得したことに始まるのである。イギリスのロックバンドが、日本で録音したレコードがアメリカでドカンと売れたのである。国から国への貿易が付加価値を生んだ、のである。近年では、BABYMETALのメンバーが海外のフェスに出演した際に、大物アーティストとの写真をよくネットにあげていた。あれはもちろん、大物アーティストたちがBABYMETALに敬意を表しているからであるからなのだが、それと同時にジューダス・プリーストのロブ・ハルフォードなんかは何度も来日公演を行い、『イン・ジ・イースト』という日本でのライブアルバムもある。ロブから見たらBABYMETALのメンバーは、良い思い出がたくさんある日本からやってきて立派なパフォーマンスを行う、孫くらいの年頃の女の子たちなのだ。音楽的にも、自分たちがやってきたヘヴィメタルの、現代的かつ日本的なアプローチであることは聴けばわかるわけで、ベテランのミュージシャンが孫と写真を撮るような笑顔になってしまうのも当然ではないか。戦後の日本はアメリカナイズされながらも、英語教育が今ひとつ成功しておらず(多くの日本人は義務教育で英語を学ぶので英語が全くわからない人はまずいない反面、英文は読めるのに英語での会話は苦手な日本人とか、その逆の日本人が大勢いる)日本のロックバンドが英語圏に進出するまでに時間がかかったが、日本と同じく第二次世界大戦の敗戦国である西ドイツのスコーピオンズは、初期から英語で歌っており英語圏でも成功をおさめつつ日本にも来てライブアルバムを出しており、日本のファンもかなり多く、特にプロのギタリストにシェンカーやウルリッヒ・ロートのフォロワーがいる。もちろん彼らの演奏が魅力的だからなのだが、それだけの話ではない。スコーピオンズは、彼らにとっての外国語で歌っているので、ネイティブのイギリスやアメリカのロックよりも日本人にとってはヒアリングしやすいのである。アメリカの英語とイギリスの英語がけっこう違うことは良く知られているが、英語を母国語としない日本人にとっては、アメリカ、イギリスの英語よりもシンガポールやフィリピンの人たちが話す英語の方が聞き取りやすい、といった現象がしばしば起きる。初期のスコーピオンズに在籍したギタリスト、マイケル・シェンカーも活動範囲としては英語圏のミュージシャンである。もちろん、ドイツには英語を使わず母国語で歌うロックバンドもたくさんいて、独自の文化を築いている。ジャーマンロックという言葉を聞いた際にスコーピオンズやシェンカーの名を思い浮かべると同時に、CANやファウストといったドイツのプログレバンドを思い浮かべる日本人は多いのではないだろうか。日本とドイツは自国のロックが盛んな国である。英語圏の人たちには理解し難いかもしれないが、日本のロックの多様性は日本の戦後を、西ドイツのロックは西ドイツの戦後文化を反映している。ロックはまさに戦後のポピュラーミュージックであり、敗戦国が戦勝国との関係を修復し貿易を行うための経済活動の一貫だったわけだ。
ここで面白いことが起きる。ロックが極めて経済性の強い音楽であり、商業主義によって成長する音楽であることが明らかでありながら、ロックを巡る言説の多くが一貫して商業主義に批判的なのである。日本だと産業ロックという言葉があり、欧米ではスタジアムロック、アリーナロックといった言い方がある。もちろん、ただ単にビッグビジネスになったバンドをスタジアムロックと呼ぶ場合もあるのだが、ロックでお金儲けをすることを揶揄するような使い方もされる。たとえばバンドの経営者的な立場であるミック・ジャガーなりジーン・シモンズなりが自分だけ沢山のギャラを手に入れ、他のメンバーから搾取していたとすれば、それは批判の対象になるし、実際にそういう話もたまに報じられるのだが、バンドがお金を儲けること自体が悪いわけがない。そもそもロックバンドというのはアコースティックな音楽よりも維持費がかかるのである。バンドがツアーを行うにあたっては、ドラムセットやギターアンプなどの機材を運ぶ必要がある。売れる前のバンドならば、自分たちで機材を運ぶかもしれないがガソリン代は必要になる。ロックの誕生以来、星の数ほどのバンドが結成されては消えていったわけだが、その大半は売れなくてバンドの維持費が無くなったからである。そこまで有名ではないけれども、それなりに長く続いているバンドには、それなりの数の根強いファンがいる。固定ファンの存在が、バンドの維持費を担保しているわけだ。今でこそ、買い支えるという考えが普通になったけれども、昔は経済学的な視点でロックを見る人が少なかった。世界で最初にスタジアムで演奏したロックバンドはビートルズなわけであるが、これは収容者数が桁外れに大きいスタジアムで興行を行うことによって、1枚1枚のチケット代金を安くおさえられるからだ。当時のビートルズのファンは、限られたお小遣いしか持っていない十代の若者たちだったので、安価なチケット代で大勢の観客を収容できるスタジアムでの興行は最適な選択肢だったのである。それなのに、ロック的な言説においてはお金儲けは良くないことだという考え方が支配的であった。この考え方は、後に登場するパンク世代のバンドマンや、カート・コベインのような人たちを長く苦しめることになった。それもこれも、上の世代のロック評論家が商業主義を批判しながらお金儲けを続けたからである。70年代に入って産業化したロックからカウンターカルチャー色が薄れたのは、おそらくアーティストたちが自分たちのやっていることが資本主義そのものであることに気がついたからだ。自分たちのバンドが売れれば、家族親戚だけではなく、仕事で関わる多くの人たち、それこそコンサートの警備員に至るまでの雇用が生まれ、より多くの人たちが幸せになるわけである。ここでヒースとポターの『反逆の神話』を見返すと、この二人が自分たちが思っていたほどには革新的なことをやれていないことがわかる。彼らはカウンターカルチャーがコマーシャリズム・商業主義とコンシューマリズム・消費者主義というお釈迦様の掌の上にあることを指摘したのだが、それを何となく悪いことのように語ってしまっている。ちょっとわかりやすく言いますと、60年代のカウンターカルチャーにおいては、商業主義そのものが良くないという言説があったわけだが、これはもちろん現代の視点からすると空虚な迷妄である。良くない商業主義があるのは事実である。それは、ブラックで良くない経営者がいるというのと同じ話なのだ。良くない商業主義があるのであれば、良い商業主義に方向転換しろというのが21世紀においては正しい。ヒースとポターは、この点においてカウンターカルチャーを批判しながら、カウンターカルチャーと同じ穴にハマっている。フィーリングで何となく、資本主義、商業主義は良くないよね? みたいな考え方から離脱できていないのだ。この辺の弱点は『反逆の神話』日本語文庫版の解説で、稲葉振一郎が指摘している。ヒースとポターは、欧米の知識人によくあるように、資本主義か社会主義か? という二択問題に対して及び腰で、的確な答を出せていないのだ。ヒースは頭の良い人だから己の弱点を自覚していたようで『反逆の神話』を書いた後に『資本主義が嫌いな人のための経済学』を書く。これはヒース自身の葛藤を描いたような本なので読む価値は大きいのだが、決定的な答に直面するのを回避した本でもある。フランスの知識人たちが、毛沢東を高く評価しながら(その実態は騙されていただけだったが)、自分たちの国家がソ連や中国のような体制になることを望まなかった。もしくは、そうなるような行動を取らなかったのは象徴的である。共産主義の方が良いのなら、英米仏も共産主義になれば良いではないか。少なくとも、その国の知識人はそう主張するのではないか。資本主義は格差を生む、だからこそ知識人の多くは資本主義を絶賛できない。さりとて、スターリンや毛沢東のような独裁者を生んでしまう共産主義にも同意できない。てな感じで20世紀の知識人の多くは二択問題に対してずっと優柔不断であった。頼りないな知識人。ヒースはモロに、この20世紀の欧米知識人の弱点を継承している。ヒースに代表される、資本主義か共産主義という二択問題の前で躊躇してしまうのが近代以降の欧米知識人だったわけだ。ヒースは資本主義について、かなり考えたわけだが資本主義とは何なのか? 資本主義の正体を突き詰めることはできなかった。とはいえ我々は21世紀を生きる現代人なので、この問題を解決する必要がある。幸いなことに、ヒースの苦悶以降に色んな研究者が興味深い論文を発表している。今こそ、資本主義とはどういうものなのかを語れる時が来たわけであるのですが、聞きたいよね? それならば説明しましょうか。資本主義の正体について。
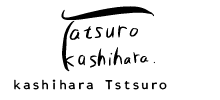 映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
twitter

