ロックとはなんだったのか? 情熱的に語られがちなロックを、冷静に、理性的に、「縁側で渋茶をすするお爺さんのように」語る連作エッセイ。ロックの時代が終わったいま、ロックの正体が明かされる!?
カリフォルニア工科大学で認知科学や神経経済学を専門としているスティーヴン・クォーツと政治学者のアネット・アスプが書いた『クール──脳はなぜ「かっこいい」を買ってしまうのか』によると、1950年代の初め頃にアメリカの男子高校生がクラスで存在感を示すためには、スポーツで結果を出すしかなかったという。その頃にJ・D・サリンジャーが書いた『ライ麦畑でつかまえて』は世界中でベストセラーになった。スポーツで一等賞になるような価値観とは無縁の、ある種の生きづらさを抱えた少年の物語だ。ちなみにジェネレーションギャップという言葉が注目されたのもこの時代である。それから数年後にロックンロールが誕生する。アメリカの高校生たちはリーゼントヘアと革のジャンパー、ジーンズを発見した。スポーツでNo. 1にならなくても、仲間たちから評価される新しい価値基準が生まれたのだ。
ここで文化の多様性というのは何故に重要なのかという視点が必要になってくる。ヒトは尊厳とかプライドとかを大切にする動物だ。他人から自分が価値のある人間だと思われたいのはホモ・サピエンスという動物の特性である。しかしながら、個々人の値打ちを決定するのは他の個体との競争だ。他人から値打ちのある個体だと思われたいからこそ、ヒトはひっきりなしに競争をおっ始める。競争というのは争いであって、これが極端になるとマクロでは国家間の戦争になるしミクロでは殴り合いの喧嘩になってしまうので、あまりよろしくないわけだが、さりとて人類から競争する心がなくなってしまうのも困るのである。何故なら競争する心は人類の大切な「やる気」と深いところで結びついているからだ。
我々は、他人から評価されたいからこそ、頑張るぞ! という気持ちになれるわけです。もしも世の中にスポーツ競技が1種類しかなかったら、世の中は今よりもギスギスした社会になっていただろう。たとえば長距離走の選手が短距離走の選手と、短距離走で競走した場合、まず間違いなく短距離走の選手が勝つが、負けた長距離走の選手は別に悔しいとは思わないだろう。何故ならば、長距離走で競い合った場合には必ず自分が勝つからである。ボクシングのチャンピオンが卓球のチャンピオンと卓球で競えば必ず負けるし、ボクシングで競えば必ず勝つ。競技の種目が多ければ多いほど、傷つく人の数が少なくなるし、チャンピオンに対する尊敬の念も抱きやすくなる。つまり、波風立たない世界になるわけだ。だからeスポーツであるとか、けん玉、ヨーヨー、ペン回しなどの遊びの分野に世界大会があるのはかなり素晴らしいことだと考えていい。競い合うことがヒトの本能と結びついているのであれば、出来るだけ平和な方法で競い合える種目を増やし、様々なルールを設定するのはなかなかに人類の叡智ではないか。というのも、規範・ルールこそが安定した社会を築くためのツールだからだ。何らかの競技に参加して、若い頃からルールというシステムに触れることは、大人になってから社会の一員として生きてゆくうえでかなり役に立つのではないか。
19世紀フランスの天才数学者エヴァリスト・ガロア、ロシアの文学者アレクサンドル・プーシキン、ミハイル・レールモントフの三者には共通点があって、3人とも決闘で亡くなっているのである。現在では、ヒトのオスはプライド、名誉を傷つけられた時に相手を殺してしまったりすることが多い動物であることがわかってきたのだが、19世紀にはまだそういう知識も視点もなかった。ガロアにしろプーシキンにしろ、レールモントフにしろ当時としては抜きん出た知性の持ち主だったことは間違いない。そんな頭の良い人たちであっても、プライドを傷つけられたから決闘をするという、極めて動物的な行動をとって死んでしまったのだ。彼らはそれが、動物的な本能と深いところで結びついた行為であることを知らないまま決闘を行った。19世紀といえば、科学、数学、文学、いずれも相当に発展していた、現代とそれほど変わらない時代である。しかし、今どき決闘で命を落とすような人はあまりいない。19世紀と今とでは一般常識が大いに異なるからだ。これが文明化である。
ヒトの道徳心は常に進化しており、我々は常に前の時代に生きた人たちよりも温和な方向に進んでいる。昭和のテレビドラマなどを観ると、公僕である刑事がタバコの吸殻を路上で踏み潰したりする場面が多々あって、現代を生きる我々の目から見ると非常に野蛮に見えたりもするのだが、40年から50年ほど前の時代においてタバコの吸殻を路上で踏み潰していた人たちは、その時代の倫理観に従っていただけである。道徳心は緩やかに進歩しながら進化するのだが、どうやら後の時代になるほどその速度は速くなるようである。
ここで一旦、進歩と進化を切り分けて考えたい。進化というのは原則的に、必ずしも良い方向に向かうわけではない。ただ分岐するだけだ。遺伝子による進化も文化の進化も基本的には同じことである。それに対して、良い方向に転がったケースを進歩と呼ぶのが妥当な線だろう。道徳心が進化することは基本的には良いことではあるが、あまり急激に進むと好ましくない方向に向かってしまう恐れもあるのだ。たとえば、動物倫理などの視点から肉食は良くないという動きが近年になって高まっており、ヴィーガンの人も少しずつ増えている。ただし、肉食を止めるのが基本的に正しいことであったとしても、人類全体がいきなり、一斉に肉食を止めるような原理主義に走るのは好ましくない。世界中で食肉産業に従事する大勢の人たちが職を失って、そのうちの何人かは餓死するかもしれないし、食肉用に飼育されてきた牛や豚、鶏などがヒトから必要とされなくなることによって絶滅してしまう可能性もあるからだ。『火の賜物』を書いたリチャード・ランガムの仮説が正しいとしたら、ヒトは肉を加熱して食べることで大いに繁栄した動物である。それが肉食をやめるということは、自然の理に逆らう行為でもある。肉食をやめるのが正しい行為だとしても、時間をかけて緩やかにやめた方が大きなトラブルは起きないだろうし、大豆から作られた代用肉や科学的に培養された培養肉の研究も進んでいるから、近い将来には倫理的な肉食が可能になるかもしれない。ここで注目すべきは、代用肉や培養肉の研究を進めるのに既存の食肉産業が深く関わっている点である。肉食を積極的に推し進めたいはずのハンバーガーチェーンが、大豆ミートのハンバーガーを売り出すのは、動物倫理などの社会の趨勢を踏まえた上での倫理的な行動である。カウンターカルチャーが大きな力を持った20世紀であれば、肉食を止めようとする革新派ヴィーガンと肉食を続けようとする保守的なハンバーガーチェーンが激しく対立することになったかもしれない。しかし、社会全体の道徳心が高くなった今世紀においては、資本家であるハンバーガーチェーンの方が革新派との対立を好まなくなっている。対立は分断を生むだけなので、ハンバーガーチェーンの方から積極的に妥協点を見出そうとする姿勢を取るわけだ。これぞ倫理の進化である。
基本的に我々ヒトは常に良い方向に向かっている。だからこそ医療技術が発達して平均寿命が伸びる。公衆道徳が発達すると殺人などの暴力事件が減少する。世界規模の戦争が起きることもなくなった。これぞ進歩である。人類の歴史をかえりみると、今が最も平和な時代であり、明日は今日よりも更に平和な時代、という公式がほぼほぼ成立する。
ともあれ50年代のアメリカの若者はロックンロールを発見した。もはやスポーツだけで優劣が決まる時代ではなくなったのだ。髪型を整え、ジーンズに革のジャンパーを着てエレキギターを持てばスーパースターになれる、かもしれない。前回紹介したバイオロジカルマーケットにおけるマーケット、市場が拡大したのである。
優れたロックバンドを結成するためには、自らが優秀な楽器演奏者であることが好ましい。その上で優秀なベーシストやドラマーを探す必要がある。そう、ここにもバイオロジカルマーケットがあるのだ。10代の中頃といえば、特にバイオロジカルマーケットの市場活動が盛んになる時期である。男の子はそれ以前よりもたくましくなり、女の子はそれ以前よりも女性らしい体型になる。肉体的な面で男女の違いが明らかになるからこそ、生物学的な市場活動が活発になるのだ。ベイルート生まれでイギリスで学んだ社会学者のキャサリン・ハキムは、その著作『エロティック・キャピタル』で、性的な魅力は一種の文化資産であるという妙に説得力のある仮説を唱えた。これを簡単に説明すると、モテは資産なのだという話である。そして、体を鍛えたりお洒落にお金をかけたりすることで、この資産に磨きをかけることができる。ヒトには、他人の目から見て、魅力的に見えるように努力し、そこにリソースを注ぎ込む癖がある。それはつまり自分への投資なのだ。たとえばロックンロールがポピュラリティーを獲得した社会においては、誰よりもエレキギターを上手く演奏できる能力は巨大な資産となる。ベースが上手いのも、ドラムが上手いのも資産である。だからアマチュアのミュージシャンたちは、お互いの演奏を聴くことでお互いの技量を品定めし合いながらメンバーを選んでバンドを組むのである。とはいえ、ロックバンドをやりたいと思った若者が最初にやるのは何かというと、とりあえずは近所の友達に声をかけるのだ。ロックバンドをやりたい! という思いは往々にして衝動的なものだから、上手い下手よりはまず頭数を揃えなければ話にならない。
ビートルズにせよ、ローリング・ストーンズにせよ、元々は近所の友達の集まりである。ヴァン・ヘイレンやAC/DCのように実の兄弟で組んだバンドでプロになり、世界的な成功を収める人たちもいるのはご存じの通り。近所にいる幼馴染や兄弟といった身近な顔ぶれだけでもバンドは組める。つまりバンドという文化は参入するための障壁が低いのだ。
多くのロックバンドが解散したりメンバーチェンジを繰り返すのは、仕事仲間として優秀でありなおかつ友人としても気の置けない関係を維持できるようなメンバーを固めるのが至難の業だからだろう。とはいえ、天文学的な確率ではあるが10代のうちにプロとして活動してゆくだけの力量があり、なおかつ音楽的にも一緒にやれて、友達としての関係を続けることができるようなメンバーが集まることもある。そういった好条件が重なれば、近所の友達を集めただけのバンドで世界制覇することも可能になるのだ。
1950年代のアメリカのロックンロールは、基本的には一過性の流行音楽であった。1957年にリトル・リチャードが引退、58年にエルヴィス・プレスリーが陸軍に招集され、ジェリー・リー・ルイスは13歳の少女を妻にしていたことが問題となり、チャック・ベリーは14歳の少女と交際していたことが問題視された。チャック・ベリーは数多のミュージシャンから尊敬されるレジェンドの中のレジェンドだが、1990年には自分が経営するレストランの女子トイレに盗撮するためのカメラを設置したことで逮捕されている。なかなかの最低人間である。そして59年にバディ・ホリーが飛行機事故で、翌年にはエディ・コクランが交通事故で死んでしまう。ロックンロールはここで一旦、終わったとされている。ただし、ロックンロールは10代の少年少女の音楽であったが故に、次の世代にバトンが渡されていた。10代でロックンロールに接した少年たちが大人になって、自分たちのロックンロールを演奏し始めたのだ。デビュー前のビートルズがリーゼントヘアだった写真が残っているのは文化的に大いなる遺産である。
そう、ブリティッシュインヴェイジョンが起きて状況が変わったのである。ロックンロールの誕生よりずっと前、20世紀の前半にスキッフルという音楽文化があった。いつどこで始まったのかもよくわかっていないが、手作りの楽器や洗濯板をかき鳴らしたりする、あり合わせの楽器によるバンドミュージックだ。音楽的にはジャズでもあり、ブルースでもあり何でもありの混血文化である。要はその辺にあるものを叩いて鳴らしてアドリブで演奏するような文化だ。日本でも、横山ホットブラザーズがノコギリを鳴らして演奏しますね。基本的には、ああいう感じだと思っていただきたい。このスキッフルが、1950年代のイギリスでブームになった。ジョン・レノンが初めて組んだバンド「クオーリメン」もスキッフルのバンドだった。
アメリカでロックンロールが誕生した時に、イギリスではスキッフルが流行していたというのはかなり重要だ。イギリスにはそれ以前からジャズ文化があったが、スキッフルは器用なアマチュアが音楽に参入するハードルを下げたのである。
ロックンロールはアメリカの白人が、アメリカの黒人の音楽を物真似して始まった文化なのだが、それを更にイギリスの白人が物真似する、という現象が起きたわけです。そもそもアメリカの黒人音楽はアフリカから連れてこられた奴隷が生み出したものである。その際に母国での言語や太鼓のような打楽器を禁止されたこともあって、アフリカの伝統音楽とはかなり違うものになったわけだが、手作りの楽器や洗濯板などの身近にある物を演奏に使ったのは重要である。たとえばヨーロッパのクラシック音楽はモーツァルトが活躍した18世紀あたりで既に洗練の局地に達していた。18世紀に発明されたピアノは、音域の広さなどから完全楽器と呼ばれたが、それで素晴らしい演奏をするためには相当な修練を必要とするし、そもそもお金持ちの貴族でもない限りピアノに触れる機会がない。ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト氏に音楽的な才能があったのは確かだろうが、そもそも彼の父親は宮廷音楽家なのである。つまりモーツァルトの音楽は世襲的に相続した文化資産の上に成り立っていたわけだ。それに対してアメリカの黒人奴隷たちは、先祖から受け継ぐべき音楽的な資産を奪われた状態で、自然発生的に自分たちの音楽を生み出すしかなかった。クラシック音楽はストレートに文化進化を重ねた結果、貴族とかでないと演奏者になる機会のないハイカルチャーになっていたわけだが、アメリカの黒人奴隷による音楽はその辺に転がっている洗濯板を鳴らしたりして演奏するものだったので、参入障壁がかなり低かったのだ。ロックが黒人音楽から受け継いだ最大の文化的な遺産は、この音楽への参入障壁の低さである。つまり、ロックンロールは、誰でもロックスターになれるかもしれないという夢を世界中に撒き散らしたのである。
世界中に色んな民族音楽があるのはご存じだろう。音楽はヒトの本能と結びついているので、民族音楽のない民族というのは、ほぼほぼ存在しない。たいていの民族音楽は、その土地ならではの文化から生まれ、長い時間を積み重ねて洗練されたものなので、よその土地から来た人が簡単に真似できるような代物ではない場合が多い。非常に優秀な音楽家であっても、モンゴルのホーミーを聴いて、その場で同じことをやるのはほぼ不可能ではないか。世界最高レベルのギタリストに三味線を渡したら、それなりの演奏をするだろうけど、本職で津軽三味線を弾いてきたような人と同じような演奏ができるとは思えない。アフリカ土着の音楽の、最高の演奏者を連れてきてピアノの前に座らせたら、それなりに凄い演奏をするかもしれないけれども、モーツァルトのようにはいかないだろう。
何が言いたいかというと、基本的に全ての音楽は民族音楽みたいなものなのだ。クラシックはヨーロッパ人の民族音楽なのである。そして、全ての民族音楽は、長い時間をかけて洗練されたが故に、他の土地から来た人が簡単に再現するのがかなり困難なのだ。
たとえば日本の北海道にソーラン節という民謡がありますね。あれは元々、青森で鰊漁の際に歌われたワークソングで、鰊場木遣り歌とか、鰊場音頭と呼ばれたものが少しずつ変化して今の形になった。近代の音楽なので、わりと記録が残っておりどのような文化進化が起きたのかわかりやすいのだ。アメリカの黒人奴隷の音楽も、おそらくは似たようなプロセスを経て黒人霊歌やR&B、ブルースといったものが生まれていったのだと思われる。ソーラン節を上手く歌えるのはもちろん北海道生まれの人だろう。たとえばフランス人であっても生まれてすぐに北海道に来て、日本語を母国語のように話し、ソーラン節が身近にある環境で育ったのならば関西や四国、九州で育った人よりは上手にソーラン節を歌うのではないだろうか。民族音楽というのは基本的に各々の環境下において習得するものである。たとえば、アメリカで育った人や、アフリカで育った人が北海道にやってきてソーラン節に感動したとする。その人は、熱心にソーラン節を覚えようとするかもしれない。だが、その人が歌うソーラン節は、北海道育ちの人が歌うソーラン節よりはいささか奇妙に聴こえるのではないだろうか。逆に、日本人であっても子供の頃から西欧のクラシック音楽の教育を受けた場合には、クラシック音楽の専門家として成功することも可能である。実際、海外で活躍する日本人のクラシック音楽家は何人もいる。クラシックは楽譜を教材として教育、指導する方法が発展したので、こういうことが可能になったのだ。それに対してロックンロールは指導や教育によるものではなく、黒人の模倣から始まった。更にイギリス人が黒人を模倣したアメリカの白人を模倣することで文化が連鎖したわけである。青森の鰊場木遣り歌と、それに影響を受けた北海道のソーラン節でも微妙に違うのである。黒人からアメリカ白人へ、さらにイギリスの白人へと伝言ゲームのような伝達がなされたわけで、そりゃあオリジナルとは違ったものになるのは当然だろう。メソッドに基いた教育、指導を伴わない物真似では、オリジナルと同じものは生み出せないのだ。だからこそロックというジャンルではすぐに新しいものが、新種が誕生するのである。数々のメソッドが確立されたクラシック音楽の中で、革新的なことを行うのはかなり困難だろうし、伝統的な民族音楽の中で革新的なことを行うのも困難だろう。それに対して、ロックにおいては比較的簡単に革新的なことが起きるのだ。たとえば20世紀の終わり頃にワールドミュージックのブームがあり、革新的な変化を遂げた各国の民族音楽を我々は聴くことができたが、あれはロック以降の文化であり、ロックやディスコミュージックが世界中に流れたことを受けての動きである。
アメリカ黒人からアメリカ白人に、アメリカ白人からイギリスの白人にと、バトンが渡される度に化学変化のようなことが起きている。もちろんイギリスにいた白人の若者たちは、プレスリーのような白人のロックンロールだけでなく、アメリカの黒人のブルースもダイレクトに聴いていた。この、ブリティッシュインヴェイジョンの代表をとりあえずビートルズだとしても問題はなかろう。真に驚くべきは、後にビートルズのような楽曲を演奏するバンドがアメリカからも出現したことである。つまりアメリカの黒人に影響を受けたアメリカの白人に影響を受けたイギリス人に影響を受けたアメリカ人の音楽が出現したのである。ビートルズを聴いたアメリカ人の中に、これはアメリカのロックンロールの影響を受けているけれども、オリジナルのアメリカ音楽よりもカッコいいんじゃないか? だったら、こっちを真似しよう! と思った人が少なからずいたのだろう。もちろんブリティッシュインヴェイジョンにはビートルズだけではなく、ローリング・ストーンズもいたしキンクスもアニマルズもいた。70年代以降のアメリカでブレイクしたバンドの多くはブリティッシュインヴェイジョンの影響を多大に受けている。アメリカのロックンロールは一時代を築いたが、ブリティッシュインヴェイジョンというハブがなかったら、60年代後半以降のアメリカンロックは我々が知っているものとはかなり違うものになっていただろう。
ブリティッシュインヴェイジョン以降のアメリカの動きとして重要な人が2人いる。ジミ・ヘンドリックスとボブ・ディランだ。アメリカでギタリストとして仕事をしていたヘンドリックスは、アニマルズでベースを弾いていたチャス・チャンドラーに見出されて渡英、エレキギターの革命家として歴史にその名を残す。そのままアメリカで雇われギタリストを続けていたとしても、それなりの名を残したかもしれないが、一旦イギリスに渡りそこからデビューしたのは大きかった。アメリカ人の目からから見ても、イギリス人の目から見ても桁外れに凄いことがはっきりとわかったからだ。
後にノーベル文学賞を受賞するボブ・ディランは、フォークソングの旗手としてかなり若い頃から注目されていた。デビューも二十歳そこそこだが、文学者、詩人としての実力は早くから認識されていた。ジャズ評論家でもある歴史家にしてマルクス主義研究の大家でもあるエリック・ホブズボームはかなり早い段階で詩人としてのディランを高く評価していたし、ミック・ジャガーもディランの詩を評価していた。
1965年にニューポートフェスティバルでディランはエレキギターを持って演奏した。その時点でフォークソングの世界ではディランは既に第一人者であったが、彼がエレキギターを持ったことで従来のファンからはブーイングが起きたという。これはエレキギターを使ったロックンロールがティーン向けの低俗な文化だと思われていたからである。しかしディラン自身は少年の頃にロックンロールを聴いていたので、その魅力をよく知っていた。ちなみに同じ1965年の8月にビートルズはニューヨークのシェアスタジアムで歴史に残るライブを行っており、10月には外貨獲得でエリザベス2世女王からMBE勲章を授与されている。ビートルズを理解する上で重要なのは、彼らは短期間で滅茶苦茶に売れて、なおかつ音楽的に変貌し、解散してしまったということである。ビートルズ以前に、ポピュラー音楽がここまで大きな社会的影響力を持ったことはなかったし、ビートルズ以降もない。人類史の特異点である。マイケル・ジャクソンやイーグルス、AC/DCはビートルズ以上に売れるレコードを作ったが、文化的な影響力ではビートルズにかなわない。
ビートルズが突出して売れたのは客観的な事実である。ビートルズ解散後、第2のビートルズと呼ばれるようなバンドがいくつも出現したが、それらはどれも初期のビートルズを模倣したような音楽だった。後期のビートルズのような音楽でデビューしたバンドがいたとしても、第2のビートルズとは呼ばれないのだ。それくらい、初期のビートルズは売れる音楽だった。その、誰よりも売れたビートルズが少しずつ変容するのである。ビートルズの音楽が短期間で変化したのはよく知られているが、音楽性の変化よりも先に内面の変化があった。初期のビートルズの楽曲のタイトルを見ればわかるが、「彼女は君を愛している(She Loves you)」とか「私はあなたを抱きしめたい(I Want To Hold Your Hand)」と歌っていた人たちが、「仕事がつらい夜 (A Hard Day’s Night)」であるとか「助けて! (Help!)」といった歌に変化するのだ。実存主義である。
50年代のロックンロールには60年代半ばからのロックにあるような深い思想性はあまり感じられなかった。10代の男女が踊り、出会い、恋をしたりするのに特化した音楽だったからである。デビュー当時のビートルズやローリング・ストーンズも似たようなものだった。だが、最初から詩人であったボブ・ディランがエレキギターを持ってロックというフィールドに参入し、他愛のないラブソングを歌っていたビートルズが実存主義めいたことを歌うようになった1965年、ローリング・ストーンズは、満足できないことを延々と訴える「Satisfaction」を発表する。こちらも実存主義の臭いがするではないか。ロックに文学性と実存主義が侵入したのだ。ディランの文学性に着目していたミック・ジャガーは、自分たちのバンドにも文学性のある歌詞を採用するようになったのである。
50年代のロックンロールは10代の少年少女が口うるさい親に反抗する音楽であったが、60年代のロックは社会に反抗する音楽へと変貌したのである。旧来のロックンロールとの差別化をはかるために、60年代後半のロックはニューロックとかアートロックと呼ばれることが多かったが、時間が経つにつれて単なるロックになった。
カナダの哲学者ジョセフ・ヒースとコラムニストのアンドルー・ポターが『反逆の神話』で熱く語ったカウンターカルチャーの時代が到来したのだが、もちろんヒースが同書の中で嘆いたように良いことばかりではなかった。
〈参考文献〉
スティーヴン・クウォーツ、アネット・アスプ『クール──脳はなぜ「かっこいい」を買ってしまうのか』渡会圭子訳、日本経済新聞出版、2016
J・D・サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』野崎孝訳、白水Uブックス、1984
リチャード・ランガム『火の賜物──ヒトは料理で進化した』依田卓巳訳、NTT出版、2010
キャサリン・ハキム『エロティック・キャピタル──すべてが手に入る自分磨き』田口未和訳、共同通信社、2012
ジョセフ・ヒース、アンドルー・ポター『反逆の神話〔新版〕──「反体制」はカネになる』栗原百代訳、ハヤカワ文庫NF、2021
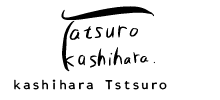 映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
twitter

