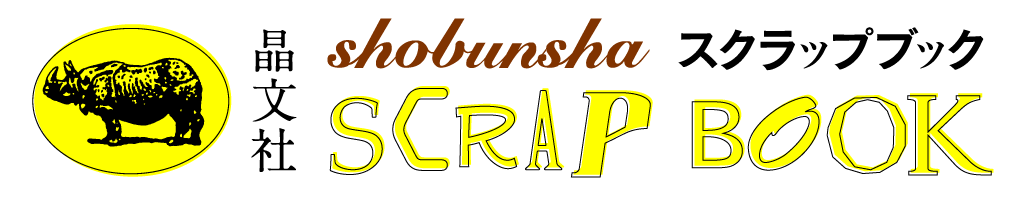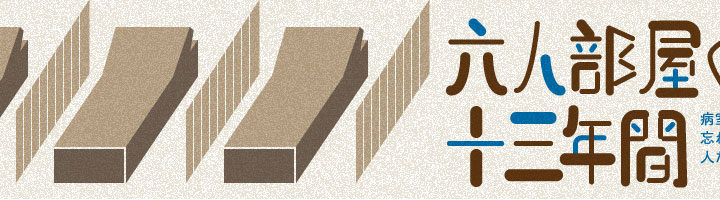「特別な人生には、ちがいないだろう」
「たしかにね、俺たち、普通の人生じゃないな、
と思うこともありますよ」
(『男たちの旅路 山田太一セレクション』里山社)
来る人の多くが
「もう御病気はすっかり御癒(おなお)りですか」
と尋ねてくれる。
私は何度も同じ質問を受けながら、
何度も返答に躊躇(ちゅうちょ)した。
(中略)
或人は私の説明を聞いて、面白そうにははと笑った。
或人は黙っていた。
また或人は気の毒らしい顔をした。
客の帰ったあとで私はまた考えた。
(夏目漱石『硝子戸の中』)
六人部屋の見舞い客
病室にはたくさんのお見舞いの人たちもやってくる。六人部屋だと、その数もかなりになる。もちろん、誰も来ない人もいるのだけど……。
今回は、お見舞いの人たちについてお話ししてみたいと思う。
六人部屋での会話は、どうしても聞こえてきてしまうので、病人とお見舞いの人との会話もずいぶん聞いた。聞く気はなくても、つい耳に入ってしまう。喫茶店で隣りの席の会話が耳に入ってくるのと同じだ。
自分のお見舞いの人と話しているときには、そうも感じないのだが、他の病人のところに来ているお見舞い人との会話は、客観的に聞いているせいか、なかなか興味深かった。
くやみより難しいお見舞い
あなたは、病院にお見舞いに行ったことがあるだろうか?
家族や、ごく親しい人が入院して、お見舞いに行くのなら、本当に心配して行くのだから、気持ちのままに行けばいいだけで、とくに難しさもない。
しかし、会社の上司とか、取引先の人とか、そんなに親しくない親戚とか、そういう相手が入院していてお見舞いに行くとなると、億劫(おっくう)なだけでなく、どう口をきいたらいいのか、何を持って行ったらいいのか、なかなか難しい。
落語に『くやみ』という噺がある。ある人が亡くなって、いろんな人がくやみ(人の死を悲しみ惜しんで言う言葉)を言いに来るのだが、どれもひどい内容で、いつの間にか自分の商売に宣伝になったり、自分の妻とののろけ話になったり。大切な人が死んで悲しんでいるところに行って、何か言うというのは難しいものだ。
入院のお見舞いの場合は、まだ死んではいないが、病気になっている当人に向かって口をきかなければならないのだから、ある意味、くやみより難しい。ずいぶん変なことを言ってしまう人も多い。お見舞いの人が帰ってから、病人が怒っていたり、へこんでいたりすることも少なくない。
「あなたはがんばっているね、私だったら無理」
お見舞いの人がつい言ってしまう言葉で、いちばん多いのが、「あなたはがんばっているね、私だったら無理」ということだ。
これはおそらく、「人に『かわいそう』と同情してはいけない。『がんばっているね』と尊敬したほうがいい」という、最初は誰が言い出したのか知らないが、そういうアドバイスが世の中に広く浸透しているからだろう(このアドバイスに私は反対だが、それはまた別のときに)。
病人に対して、「あなたは病気になって、かわいそうね」と言う人は、さすがにあまりいなかった(病人が子どもの場合は、たくさんいたが)。
「かわいそう」の代わりに「がんばっている」と言うわけだが、これも言われるほうとしては、ほめられて嬉しいというような言葉でない。
好きで病気になったわけでもなければ、好きで闘病しているわけでもない。たとえば、崖から落ちそうになって、岩肌に生えていた草を必死でつかんで、ぶらさがっているとしよう。これを離したら、落ちて死んでしまう。そんなとき、「あなたはがんばっていて、えらいね」と言われたとして、嬉しいだろうか? がんばりたくてがんばっているんじゃない! と、言いたくならないだろうか。
それでも、「がんばっているね」だけなら、まだいいのだが、さらにほめようとして、「私だったらとても無理」と付け加える。
これはたいていの場合、悪気はない。あなたはすごいということを、さらに強めようとし、そのために自分を下げて、相手を上げているのだ。「あなたは起業に成功なさってすごい。私だったらとても無理」と言ったりするのと同じパターンをつい使ってしまうわけだ。
しかし、どうだろう。崖から必死でぶらさがっているとき、「私だったらとても無理」と言われたら。「いやいや、あなただって、絶対に必死でぶらさがりますよ」と言い返したくならないだろうか。
「死んだほうがまし」
それだけなら、まだいいのだが、病人の身体にたくさんの管がつながっていたり、食事が極端に制限されたものだったりすると、「私だったら、とても耐えられない」「オレだったら、死んだほうがましだな」などと言い出す。
これは、耐えているあなたは偉いということを言いたくて、ほめそこなっているだけの場合もある。しかし、悲惨なことになっている知り合いを目の前にして、お見舞いの人の心の中に、そういうことになっていない自分に対する喜び、「この人は不運だが、自分は幸運だ」という抑えがたい喜びが、ふつふとわいてきてしまっている場合も少なくない。
実際、悲惨な状態で横たわる知人を前にして、それを見おろすお見舞いの人の目に、ぎらぎらとした、死んでいく獲物を見おろす肉食獣のような輝きがありありと感じられてくることも少なくない。それは、隣りのベッドから見ていてもこわいほどだ。
もちろん、お見舞いの人自身は、そこまで自覚していないだろう。同情の目で見ているつもりだ。しかし、帰り道で、「あの人は病気でもあんなにがんばっているんだから、元気な私はもっとがんばらなくちゃ」などと、大いに勇気を得て、ますます元気になり、お腹も空いてきて、栄養たっぷりな食事を勢いよく食べたりする。そういうとき、精進料理とかは決して食べない。がぶりと噛みつけるような肉類とか、のどにぐいぐい通していける麺類とか、脂っこくて味が濃くて汁がほとばしるようなものを食べたくなるはずだ。
病院の門の近くには、かなりの高確率で脂っこいラーメン屋がある。最初は不思議に思っていた。通院している人たちを目当てにしているのなら、もっと消化のよさそうな感じにしたほうがいいだろうにと。お粥の専門店とか。もちろん、脂っこいものを禁止されている病人だからこそ、あこがれるということもある。腸閉塞で入院していた人が、退院してすぐに、病院の前のそういうラーメン屋で退院祝いの食事をして、そのまま再入院してきたこともある。
だが、そういうラーメン屋のお客の多くは、お見舞い客なのだ。それもお見舞いをした帰りだ。なんて読みの深い出店の仕方だと感心してしまう。
難病映画はなぜヒットするのか?
そういうお見舞い客は、けっしてひどい人なわけではない。
そういう心理は誰にでもある。だからこそ、世の中にはたくさんの難病映画がある。そのストーリーはたいてい、難病でもうじき死ぬ美少女がいて、でも明るく健気に生きていて、一方、健康なんだけど、生きる意味や意欲を失い気味の男がいて、なぜか恋仲になり、男が女性の死を悲しみ、生きる意欲を取り戻す、というような内容だ。
つまり、死んでいく人を踏み台にして、生きる意欲を高める。そういう心理が人にはある。
まあ、そうでなければ、いつか死ぬと決まっている人生を、しかも実際に周囲で人が次々と死んでいく中で、明るく楽しく生きていくことはできないだろう。
戦場で、周囲の仲間が次々と弾に当たって死んでいく中で、自分は生き残れたとき、「次は自分が弾に当たるだろう」とおびえるよりも、「自分は生き残る側の人間なんだ」と英雄的な気分になっていくのが、人間というものだ。
それにしても、そうした難病映画などでよくある。「オレ、彼女の分までがんばって生きていくよ」というようなセリフは、さすがにひどいと思う。死んでいく人が「私の分まで生きて」と頼んだのならいいが、そうでなければ、あんまりずうずうしいだろう。命のロウソクの残りを、勝手に自分の分につぎたされたのでは、たまったものではない。
もし私の死んだ後で、私の知り合いがそんなことを言ったら、なんとしても化けて出て、「勝手に人の分まで生きようとするな!」と言ってやりたいものだ。
「でも、大丈夫だよね」
病気をしている知り合いには、助かってほしいと思う。よほど恨みでもない限り、これが自然な気持ちだろう。
だから、お見舞いに行って、病人から「いや、もう大丈夫なんだよ。あとは退院を待つだけでね。元通りに戻れるよ」などと言われると、大いにほっとするし、どう口をきいたらいいか心配していたのが、一気にほぐれて、その人が休んでいた間にあった面白い話などを始める。
ところが、病人が暗いことを言い出すと、お見舞いほうはあわててしまう。どう返事をしたらいいか、困ってしまう。
たとえば、病人が「手術になりそうなんだ」と言うと、お見舞いの人は「でも、手術をすれば大丈夫なんだよね」と明るい方向に持っていこうとする。
「それが難しい手術でリスクもあって」とさらに病人が暗いことを言うと、「きっとうまくいくよ」と何の根拠もない明るい見通しを言う。
「手術がうまくいっても、元通りには戻れないんだ」と病人が決定的なことを言うと、「そんなことないよ。きっと大丈夫だよ」と、お見舞いの人は、だんだん病人の発言を否定さえし始める。
お見舞いの人としては、励まそうとしているわけだし、暗いことを言われて、どう返事をしたらいいか困ってしまい、明るいことを言うしかなくなっているわけだ。
しかし、病人のほうにしてみれば、根拠のない励ましで、こちらの深刻な心配を簡単に否定されるわけだから、だんだん腹が立ってきたりもする。
それで、わざと重いこと暗いことを言い続けたりする。そうして、お見舞いの人を困らせるのだ。お見舞いの人のほうも、あせりながら、とにかく、「でも、きっと大丈夫だよ」を連発する。
横で見ていて、不思議な闘いで、どちらの気持ちもわかる気がした。
お見舞いの人もきっと帰り道でぐったりしているだろうし、病人のほうも、重いこと暗いことを言い続けたせいで、自分がさらに落ち込んでしまう。
「オレはもっと大変だった」
「放っといても治るような病人でも、簡単にやってはいかんらしい。病人というのは多少そのお医者はんに、重う診てもらいたいという気持ちがあるさかい」と、桂米朝は『犬の目』という落語の枕で言っている(『米朝落語全集 増補改訂版』第一巻 創元社)。
これは医者に対してだけでなく、お見舞いの人に対しても、少しそういうところがある。
軽い病気でも、お見舞いの人から「ぜんぜん大丈夫なんだってね」などと言われると、軽くむっとしてしまう。当人にとってはやっぱり大変なことだし、入院までするくらいなんだから、そう簡単に言われたくないという気持ちが働いてしまう。ことさらに、症状や苦しさを訴えてしまう。
そうすると、お見舞いの人の多くは、「そうなんだ、大変だったね」と、ちゃんと受けとめてあげる。しかし、中には、人の大変さを認めるのが嫌いな人もいる。「人間てやつは他人を苦悩者と認めることをあまり喜ばないものだからね」とドストエフスキーが『カラマーゾフの兄弟』で書いているように(『ドストエフスキー全集』第十巻 小沼文彦訳 筑摩書房)。
そして、自分のほうが大変だったという話を始める人がけっこういる。その人自身に病気の経験があれば、そのときの自分に比べたら、おまえはたいしたことはない、という意味のことを言う。単純骨折で入院している人のところにお見舞いに来た人が「オレは複雑骨折して……」と言い出せば、それはもう、単純骨折の人は、自分のほうが軽いと認めざるを得ない。しかしそれだって、病人にしてみれば、今まさに自分は大変な思いをしているのに、他と比べてましだとか、甘いとか言われるのは、あんまり気分のいいものではない。
まして、お見舞いの人が、「知り合いに複雑骨折した人がいて、その人はもっと大変だったよ」などと、自分自身ではなく、知り合いの話をして、それよりおまえのほうが軽い、それくらいで嘆くのは甘いと言い出した場合、病人の不満もかなり高まる。誰なんだよ、それは、と内心思ってしまう。知り合いまで持ち出されたら、世界でいちばん悲惨な人にならない限り、嘆けないことになってしまう。
それでも、病気どうしの比較ならまだましで、「オレは仕事でもっと大変な思いをした」と言い出す人も少なくない。徹夜し、駆けずり回り、人間関係にも苦労した、それに比べたら、病院のベッドでおとなしく寝ていればいいのだから、まだ楽だというように。病気と仕事とどちらのほうが大変かという、異種格闘のようになると、これはもう主観的なことなので、「たしかに、あの時の先輩のほうが大変でしたね」などと返事しながらも、本当に納得している病人は少ない。
落語はリアル
落語に『くやみ』には、いつの間にか自分の商売に宣伝をしたり、自分の妻とののろけ話をする人が出てくると、先に書いた。それは落語だから大げさにしているのであって、現実にそんな人がいるわけないと思うかもしれないが、そんなことはない。少なくともお見舞いの人には、そういう話をする人がたくさんいた。
なぜ商売の宣伝を始めるようなことになるのかというと、まず病人のほうが、「病気をして、こうして入院までしてしまって、仕事も休まなければならないし……」と仕事の心配を口にするのだ。そうすると、「そうだよね。仕事のことが心配だよね」とお見舞いの人がそれを受けて、「あなたの仕事は、休むとお客を他にとられる心配があるからねえ。うちも以前、近くに別の店ができて、お客をとられそうになったことがあるんだけど、そのとき、仕入れから何から、あらためて見直して、けっきょくそのおかげで、今も繁盛しているんだけどね。そうはいったって、難しいよ。今だって、日々、工夫の積み重ねだよ。だからこそ、この前もお客さんからほめられてね。そういう言葉を聞くと、嬉しいよね、やっぱり。他の店とはちがうからね、うちは。また退院したら、知り合いといっしょに来てよ。サービスするから」などと、なぜかいつの間にか自分の商売の宣伝になったりするのだ。
妻ののろけ話のほうは、以前も書いたように、病気をすると家族にゆさぶりがかけられて、もともとあったヒビが大きくなってしまうことが多い。そういう家族との葛藤を、まず病人のほうが口にするのだ。「妻が週に一度くらいしか来てくれなくてね。『以前、私が熱を出して寝こんだときに、あなたは食事ひとつ作ってくれなかったし、冷たかった』とか、ねちねち言われるんだよね」などと愚痴ると、お見舞いの人が「そうかあ。それは自業自得のところもあるから、しょうがないなあ。でも、入院しているんだからね。週一はちょっと冷たすぎよね。うちなんか、やっぱり毎日来てくれたなあ。帰れって言っても、なかなか帰らないんだよね。心配だし、そばにいたいって。看護師さんがいてくれるんだから大丈夫、おまえも疲れているんだから早く帰れって言っても、なんだかんだ世話を焼いて、なかなか帰らなくて困ったよ」などと、これもいつも間にかのろけになったりする。
人は、何かきっかけさえあれば、仕事の話をしたり、自慢話をしたりするもののようだ。落語はさすがにそういうところをよくとらえているのだなあと、あらためて感心させられた。
いつでも横になれる縦こそが幸せのかたち
昼間からパジャマでベッドに寝ている病人を見て、思わず、「うらやましいですねえ」と言ってしまうお見舞いの人も、けっこういる。
病人のほうも、「暇で暇で、時間をもてあますよ」と言ったりする。「そんなに暇なんてうらやましい」と、これもつい口から出てしまう。
それはそうだろう。忙しくて、いつも時間に追われて、ほっとする時間もなく、ぎゅうぎゅうに混んだ終電で座ることもできないまま、ようやく家に帰ろうとするとき、ああ疲れた、早く休みたい、もし今すぐやわらかいベッドの上に横になれたら、どんなにしあわせだろう……などと、しみじみ思うこともあるはずだ。一日中、パジャマ姿のままで、ベッドでごろごろして過ごすというのは、忙しい人の夢だし、たまにそれが実現すると、本当に快くて、心も身体もしみじみ休まるものだ。
だから、誰に遠慮することなく、何日もそんな生活を続けられる病人の境遇を目の当たりにして、むろん病気ということはわかってはいるのだが、つい「うらやましい」と感じてしまうし、それが口からこぼれてしまうのだ。
しかし、何日か休むのは、たしかに楽で、心身ともに休まるが、これが長期間になると、じつはだんだんつらくなってくる。しかも、大部分の時間をベッドの上で寝ていなければならないとなると。
だんだん身体が痛くなってきて、不思議なこりが発生して、身の置き所がない感じになってくる。その苦痛はだんだんと高まっていき、やがて耐えきれないほどのものになる。もうすでに横になって休んでいるのだから、これ以上、休みようがない。それだけに、この苦痛は、癒しようがなくて困る。本当につらい。
忙しく働いていて、横になるから、楽なのだ。休むことの喜びは、動いているからこそ得られる。ずっと寝ていることは、寝ることの至福を失うことなのだ。
私は十三年間、ほとんどの時間を横になって過ごした。なので、横になるのが楽という感覚を失っていた。動けるようになってしばらくして、「あーっ、疲れた」と、ふとんに大の字になってみた。これをやってみたかった。あこがれだった。気持ちよかった。
楽しいゴロゴロは、ある程度、健康でないとできない。いつでも横になれる縦こそが、幸せのかたちだ。
ずっと休んでいるくらいなら、ずっと働いているほうが楽だというのが、両方を比較してみての、私の感想だ。もちろん、ずっと怒られ続けているとか、睡眠もとれないとか、そういうブラックな働き方は別にしてだが。
なので、仕事がきつくても、「横になっているよりはまし」と思って、いつもがんばることができる。人が聞くと、変に思うかもしれないが。
「そばにいる人間のほうが大変」
病人の家族やお見舞いの人が、病室の外で、たとえば花瓶の水を入れ替えたりしながら、立ち話をしているのが耳に入ることもあった。
「ねー、ほんとはそばにいる人間のほうが大変よね。病人さんは寝ているだけなんだから」
などと愚痴っていることがよくあった。
たしかに、病院に通って、あれこれ面倒を見て、さらにいろんな手続きとか、病人から頼まれたことをこなしたりしていると、てんてこまいで疲れるだろう。
病人当人は、その間、ずっとベッドで横になっていて、あれをしてくれ、これをしてくれと指図しているだけなのだ。しかも、自分でできないから、もどかしくて、いらいらして、そうじゃない、これをしてないじゃないか、あれを忘れているぞ、などと文句も多い。そんなことを言われながら、献身的に面倒を見なければならないのだから、それは愚痴も出る。
しかし、先にも書いたように、横になっていることはつらい。しかもそれに加えて、病気の痛みや苦しみ、心配や不安などもたっぷりあったりするのだから、やはり「当人」というのは嫌なものだ。
私は、面倒を見る側になりたいものだと、病院でしみじみ思った。どんなに大変でもいいから、当人の側は嫌だと。
ただ、それは経験していないからかもしれない。面倒を見る側の本当の大変さを知らないのかもしれない。面倒を見ている側が、病人より先に、急死することもある。たまたまかもしれないが、過労のせいかもしれない。
まあ、どちらのほうが大変かという比較は、しょせんむなしいし、できることではない。
ただ、「こっちのほうが大変なのに」と、お互いに愚痴をこぼして耐えるしかないのだろう。
おまえは落伍者だと言いに来る
これまでのは、それでもまあ、悪意はない言葉だ。
はっきりと悪意のある言葉も、意外にお見舞いの人の口からよく出てくる。
それは家族のこともあるし、親戚のこともある。「あなたがこういうふうになることを、ずっと願っていました」と、はっきり言った親戚もいて、六人部屋がしんと凍りついたこともある。よほどの恨みがあったのだろう。
そこまで深刻なものではないが、仕事関係の人からは、かなり悪意や嫌味の混じった言葉が出てくることが多かった。二十歳で病気になって、社会に出たことがなかった私は、「社会というのはやはり競争なんだな」とおそろしい気がした。「職場の人間」というのは、自分が知っている「同級生」などとは、やはり大きくちがった。
たとえば、胃の病気をして入院している人のところにお見舞いに来て、「昨夜は、こんなぶ厚いステーキをぺろりと食べて、ぜんぜん平気だよ」というようなことを、それこそ平気で言う。肝臓で入院してる人のところに来て、大いに飲んだ話をする。故障でレースをリタイヤした人間のところに来て、オレのマシンは絶好調だぜと、さらに踏みにじるわけだ。競争意識があるからこそだろう。おまえは負けたんだということを、病人にしっかり自覚させようとするのだ。
病人には40代後半から50代前半くらいの人が多かったが、出世競争もそういう年齢の頃が、最後のクライマックスなのだろうか。最終コーナーをまわって、最後にどこまで順位を上げられるか、熾烈な闘いの最中なのかもしれない。
そこで思いがけず病気になってしまった人の失意はかなりきつそうだった。それをまたえぐりに来る人たちがいるわけだ。
それでもまだ、攻撃にくる人がいるだけましなのかもしれない。もうこの人は終わったという感じで、最初だけは部下が数人来て、いたましそうな顔をして、かける言葉がなくて困るという感じで、そこそこに帰って行き、その後はもう仕事関係の人は誰も来ないということもある。
孤独というのは、誰も知り合いがいないことだと思っていたが、知り合いはいるのに近づこうとする者がいなくなるというのは、これもまたきつい孤独に見えた。
「傷つく言葉リスト」には反対
まともなお見舞いの言葉は記憶に残らないもので、思い出されるのは自然と、「よくそんなことを言うなあ」というものばかりになってしまったが、べつに「お見舞いでこんなことを言わないようにしましょう」ということをリストアップしてるわけではない。
私は、言葉を禁じることには反対だ。そういうことをすると、「何を言ってはいけないのか」を勉強するまで、相手と会えなくなってしまう。こんなバカバカしいことはない。
しかも、どんなに禁じたところで、言う人は言う。そして、そもそも気遣いのあるやさしい人たちが、必要以上に萎縮して、「相手を傷つけてしまうのがこわいから」と言って、相手に近づかず、遠巻きにするようになってしまう。これでは本末転倒だ。
そういう経験はよくあるだろう。たとえば「パワハラはやめましょう」と注意したとしても、パワハラをやっている当人は「誰だ、そんなことをしているのは?」とか周囲を見回して、ぜんぜん自分のこととは思わない。一方、パワハラなんかやっていない人が「もしかすると自分もやっているのかも」と萎縮してしまう。受けとめてほしい相手は受けとめてくれず、受けとめなくていい人だけが受けとめて、重圧を感じてしまうのだ。せめて、後者に重圧を与えないようにしたほうがましだ。
言葉なんて、どうでもいいのだ。表面的にひどい言葉でも、そこに親身な気持ちがあれば、本当に傷つくことはない。言葉遣いが完璧でも、冷ややかな心を隠し持っていれば、それもやはり伝わる。
けっきょく気持ちの問題で、そこはどうしようもない。くり返しになるが、言葉狩りは、言葉の暴力を減らす効果は薄く、やさしい人を遠ざけてしまう効果が強い。やめておいたほうがいいと、私は思っている。
取材でも、「病人には、どういうことを言わないほうがいいですか?」と聞かれることがある。上のような返事をすると、たいていガッカリされる。「これだけは言ってはいけない、病人が傷つく言葉リスト10」みたいなものを作成できるほうが、記事としては見栄えがするのだろう。
しかし、ひどいことを言う人はそんな記事は、はなから読まないし、気にして読むような人は、そもそもそんな記事を読む必要はないのだ。
病人を傷つけてしまうことをおそれずに、近づいてきて、話しかけてきてほしいと思う。もしかすると、失言して深く傷つけてしまうこともあるかもしれない。しかし、それは普通の人間関係だって必ずあることだ。近づくということは、傷をつけることもあれば、癒すこともある。それは当然のこととして、傷つけることだけを気にしすぎないでほしいと思う。病人の側も、「こう言われて傷ついた」とあまり言わないようにしたいものだ。
じゃあ、ここまで書いてきたのは、なんだったのかと言われると、これもくり返しになるが、決して「こういうことは言わないようにして」ということではない。
六人部屋でかまい見えた、人間というものの一面の描写にすぎない。
お見舞いの品
お見舞いに行くとき、何を持って行ったらいいのかも、かなり困ることではないだろうか。
一般的にはお花が多い。私が入院したときも、みんな花ばかり持ってくるので、別のものにしてほしいと頼んだのだが、「こういうときは、花を持ってくるものなの」と言われてしまった。病人が求めるものより、こういうときにはこういうふうにするのだという慣習のほうが優先されるものなのかと、不思議な気がした。
まあ、好きな女性から、バッグや指輪を買ってくれと言われると、無理をしてでも買う男はいるが、「キッチンの三角コーナーがすごくほしい」と言われても、なかなかプレゼントする男はいないだろう。相手が必要としているかどうかより、こういうときはこういうものという、ひとつの型があるようだ。
切り花が枯れていくのを見るのは、だんだん死んでいくのを見るようだし、枯れてきたから捨てるというのも、病人にとっては、なんだか気持ちがよくない。自分も枯れてきている側なのだから。それで、せめて鉢植えにしてほしいと頼んでみたが、「根付くと言って、お見舞いに鉢植えは持ってこないものなんだよ」と教えられ、これも拒否された。
そんな駄洒落のようなことで、枯れていく花ばかり見せられるのかと、理不尽な気がしたものだ。
果物籠というのも一般的だ。しかし、これは食べられない病人もいる。お菓子もそうだ。自分の知り合いの病人に渡すだけでなく、六人部屋の全員に配る人もいる。私は食べられない人だったので、丁重に断るのだが、「まあ、そう言わず、置いておくだけ」とか、たいてい無理に置かれてしまう。そういう如才のない人というのは、細やかな気遣いをするようでいて、意外に押しが強く、相手の気持ちは無視したりする。林檎をむいて、皿に入れて置いたりする。しかし、こっちは手をつけることができない。おそなえを置かれて、ますます自分がお地蔵さんのような気分になってしまう。
嬉しかったお見舞い
私が嬉しかったお見舞いは、田舎の友達から宅配便で送られてきた、ダンボール箱いっぱいの漫画だ。
といっても、最初は、何をしてくれるんだと、腹が立った。
ナースセンターで受け取ったようで、看護師さんが重いダンボールを抱えてやってきて、「こういうことは困ります」とかなり怒られた。
ベッドのそばに置いておくと、掃除のときにも邪魔で、これも文句を言われた。
私自身も、漫画を読むような気分ではまったくなかった。突然、難病になった絶望の最中で、何か読もうなんて気持ちにはまったくなれなかった。
「退屈してるとか、思ってるんだろうな」と、のんきな友達に腹が立った。こっちの気持ちをわかってくれていないと思った。
しかし、捨てることもできない。体重がげっそり落ちて、ティッシュボックスでさえ重く感じるほどだったから、漫画の詰まったダンボール箱なんか、とても持ち上げられない。看護師さんに頼んだら、また怒られる。
しかたなしにずっと置いておいた。ちょっと読もうともしてみたが、まるで無味乾燥に感じられた。元気なときなら大笑いするようなシーンでも、まったく無感動、無表情……。ただページをめくるロボットのようなもので、何も心に入ってこなかった。
ところが、その中に、漏らす漫画があった。電車の中で大を漏らすのだ。私も病気で漏らしてしまって、ひどくショックだったときだから、これは心が動いた。それをきっけに漫画を読めるようになり、そこから本を読むようになり、それが本を書くという、今の私の仕事につながっている。
私の運命を変えたお見舞いの品と言っていい。
あとから聞いたら、その田舎の友達は、私は知らなかったのだが、子どもの頃に長期の入院をしたことがあったそうだ。やはり経験者はちがうと感心したものだ。
誰も来ない
お見舞い客が多いか少ないかには、かなり差がある。
そもそも、家族の数にも差がある。おじいさんで、娘や息子の数が多く、それぞれに孫までいると、子どもがうじゃうじゃ来る。二人の夫婦から、こんなにも数が増えていくものかと、失礼ながらねずみを思い出したりしたほどだ。
一方で、夫婦二人だけで子どもがいないと、家族のお見舞いは奥さんひとりだけだ。
さらに、独身ということもある。
独身でも、友達も仕事関係の人のお見舞いが多い人もあるが、それも少ない人、さらにはひとりもお見舞いが来ない人もいる。
ある三十代の男性は、とても人当たりがよく、おしゃべりも好きで、いかにも友達が多そうだったのに、お姉さんがたまに来るくらいで、まったくお見舞いの人が来なかった。自分でも「友達がいない」と言っていた。これは不思議だった。もしかすると、借金がたくさんあったりして、みんな近寄らないようにしているのかもしれない。それとも、ふだんは社交的ではないのに、六人部屋ではがんばって仲良くしていたのか。
会社の社長という人が入ってきたことがある。そういう人はふつう、個室に入る。ところがたまに、ひとりはつまらないといって、わざわざ六人部屋に来る人もいる。
そういう人のところには、当然、お見舞い客が多い。次々と花が増えていって、ベッドの周囲が花畑のようになる。壮観だ。六人部屋全体にも花の香りが充満する。
一方で、お見舞い客のない人のところには、何もない。点滴台があるだけだ。
このように、花で表される貧富の差のようなものも、なんとも印象的だった。
さだまさしの「療養所(サナトリウム)」という曲に、お見舞い客が誰もやって来ないおばあさんが出てくる。これを聴いたときは、六人部屋のことを思い出して、泣けた。
宗教の勧誘
最後に、病院でのお見舞い客の話では、どうしても避けることのできない、宗教の勧誘について。
心が弱っている人や、大きな不幸に見舞われた人のところには、宗教の勧誘がやってくる。
だから、病人のところにも、当然、やってくる。
宗教は病人を重要なターゲットとしている。苦悩していて、治りたくて必死なので、勧誘しやすいし、お金を引き出しやすいからだ。
病気をすると、蜜に引き寄せられる蜂のように、勧誘の人たちが飛んできて、群がる。
とくに、西洋医学ではなかなか治らない病気になった人のところには、かなりしつこくやってくる。
私は難病なので、まさにそれに該当する。だから、私のところにもやってきた。
最初にやってきたのは、統一教会だった。
原理研
私は大学三年のときに難病になったのだが、私の大学(筑波大学)では、当時、統一教会の活動がとても盛んだった。たしか「原理研」と呼ばれていた。
元学長が統一教会と懇意だったとのことで(そういう噂だった。真偽は知らない)、大っぴらに勧誘が行われていた。いろんな地方からやってきた1年生が入居する学生宿舎にも、親切な先輩というのが訪ねてくる。そして、映画のビデオが見放題で、食事も安い(無料だったかもしれない)お店があるから、いっしょに行こうと誘ってくる。新入生で、まだ周囲のお店のこととかまったくわからないから、そういうお店があるなら、たしかに知りたくなる。
私の部屋にも来た。あまりに話がうまいのと、その先輩たちの雰囲気も気になったので、これはおかしいと思って行かなかった。いっしょにいた友達が、「行こう、行こう!」「なんで行かないの?」と部屋の中から後押しするから、困ったものだ。私も宗教とは気づいていなかった。何か詐欺的なものだと思っていた。
入学後のオリエンテーションのときに、「統一教会からの勧誘があるから気をつけるように」という説明があって、初めて事情がわかった。私の家は神道で、分家は神社なので、そういう家に宗教の勧誘に来る人はさすがにいなかった。だから、私は宗教の勧誘というものを、そのときまでされたことがなく、他の宗教についても、まったく無知だった。統一教会という名前も初めて聞いたし、こんなふうに学内で勧誘が行われるということにもびっくりした。まるで免疫がないので、大丈夫だろうかと、すごく不安になったのをおぼえている。初めてのひとり暮らしで、いろいろ覚悟はしていたが、宗教の勧誘からも自分ひとりで身を守らなければならないということは想定外で、覚悟がなくて、あせった。
あいつは信者になったらしいと噂される人も何人かいて、見るからに貧しくなっていく様子が、とてもおそろしかった。献金しているからだと、人から教えられた。献金するということも知らなかったから、驚いた。
それでも三年生まで無事に過ごしたのだが、そこで難病になったしまった。
高校の同窓生から勧誘される
入院してまもなく、田舎の同じ高校という男が、病院にお見舞いにやってきた。
私が入院しているというのを、たまたま耳にしたということだった。
親しくしていた相手ではない。名前も顔も知らない。同じ大学にいることさえ知らなかった。
同じ高校というだけで、わざわざ見舞いに来るとは、と驚いた。私は出身が同じというだけで親しくしたりするのは好きではないが、このときは少し嬉しく感じた。病院にお見舞いに行くなんて、義理があっても億劫なものだ。ぜんぜん行かなくてもいいのに、やって来るとは、やさしい人だと感心したのだ。故郷から遠く離れたところで病気になって、きっと心細いだろうから、同郷の人間が顔を出してやれば、少しは気持ちが安らぐのでは、と気遣ってくれたのだろう。そう思うと、本当に少しあたたかい気持ちになった。
だから、こちらもすごく愛想良く対応していたのだが、話をしている途中で、どうも調子がおかしくなった。
救いに来てくれたというのだ。救い? ちょっと言い方が大げさじゃない? と首をかしげていたら、宗教だった。
大学に入ってから、統一教会に入信したのだそうだ。
宗教に同郷とかそういうことは関係ないが、同じところからやってきた人間が、当地で宗教に染まったということには、やはりショックを受けてしまった。
そして、カッとなってしまった。わざわざお見舞いに来てくれたと、喜んでいただけに、がっかりしてしまったのだ。喜んで対応してしまったことが、恥ずかしかった。相手からしたら、入れ食い状態の魚に思えたことだろう。
怒って、「帰れ! 帰れ!」と帰してしまった。彼は怒られるのには慣れているようで、いっこうに平気で、その様子に、ようやくこわくなった。
次は集団でやってくるのではと、しばらく不安だったが、それっきりだった。まだましな人だったのだと思う。
集団でやって来たのは、親戚のほうだった。
親戚から勧誘される
ようやく外泊許可が出て、一時的に部屋に戻ったときのことだ。
親から電話があり、東京にいる親戚がお見舞いに行きたいそうだ、と言われた。遠い親戚で、昔一度あったことがある程度だった。同い年くらいで、東京に住んでいることは知っていたが、まったく交流はなかった。
それがわざわざ東京から筑波まで見舞いに来るというのだ。
短い外泊許可でようやく部屋に戻ったところだし、身体は弱っているし、起き上がるとトイレに行きたくなるから困るなあというのが正直な気持ちだった。
ただ、親が言うには、その子は、アメリカに留学して、むこうでつらい目にあって、心を病んだようになって戻ってきたのだそうだ。つらい目にあったどうし、話がしたいんじゃないか、ということだった。
そう言われると弱い。私は自分が不幸だったから、他人の不幸への同情もすごく深くなっていた。「われわれは自分が不幸なときには、他人の不幸をより強く感じるものなのだ」とドストエフスキーが書いている、まさにそういう心境だった(「白夜」『ドストエフスキー全集』第二巻 小沼文彦訳 筑摩書房)。
OKしたところ、親戚はすぐその日にやってきた。
ドアを開けてびっくりした。その親戚ひとりではないのだ。後ろにずらっと十人以上の男女が並んでいる。
びっくりして、「えっ、この人たちは?」と聞くと、「この人たちもみんな、弘樹さんとお話がしたいそうです」と親戚は平気で言う。
すぐに思い出したのは、知り合いの病人が宗教の勧誘をされたときの話だ。喫茶店で相手と会っていたら、なんと周囲の客がみんなその宗教の仲間で、断ると囲まれたというのだ。そうやって集団でやってきたりするのかと、ぞっとしたものだ。
まさにそれだ! と気づいた。
あわてて、玄関のドアを閉めようとした。親戚が手をかけて、閉めさせまいとした。手をはさんでもいけないと思い、親戚の身体を手で押しのけ、なんとかドアを閉めることができた。
あのとき、風が吹いてもよろめくほど身体が弱っていたのに、よくあんな力が出たものだ。火事場の馬鹿力というやつだろう。
親戚はチャイムを鳴らし続け、ドアを叩いたり、猫なで声を出したりしていたが、やがて帰って行った。
おそろしい体験だった。親戚に油断してはいけないということを学んだ。
退院して最初にかかった電話は
最初に退院した日(入退院をくり返したのだが、その最初の退院の日)、家に戻って、ああ、ようやく退院したと思って、ほっとしていたら、電話が鳴った。
親か友達だろうと思って、「ようやく退院したよ! 大変だったよ!」などと話をしようと思ったら、「お墓を買いませんか?」という勧誘の電話だった。正確にはお墓にする土地だったかもしれない。
なんというタイミングだと嫌な気がして、「まだ若いんで、お墓とか買いませんから」と言ったら、「でも、あなたは今のうちに買っておかれたほうがいいのでは?」と、何か含みのある言い方をする。こちらが難病と知っている様子なのだ。なぜ??? と不思議だった。
次の電話は、宗教の勧誘だった。まったく知らない人からだった。「どうして電話番号を知っているんですか?」と聞いたが、答えてくれない。ランダムにかけていて、たまたまかと思ったが、これもどうやらこちらが難病と知っている様子なのだ。病気が治るというような勧誘の仕方なのだ。
その日はそれから、お墓を買えという電話と、宗教の勧誘の電話が、いろんなところから、ひっきりなしにかかってきた。これには本当に驚いた。
どうやら、病院からそういう情報が漏れるらしい。病名と住所と電話番号のリストを売る人がいると、後から聞いた。
退院したばかりで、まだ寝ていなければならないし、また入院することにもなるような状態だというのに、なんでこんな余計な面倒までと、なさけなかった。
勧誘されてしまった六人部屋の人たち
こんな勧誘の仕方では誰も入信しそうにないものだが、そんなことはなかった。六人部屋にいる間にも、たくさんの人が勧誘にひっかかってしまった。
なぜか? 病気が治らないからだ……。藁にもすがるというが、まさにそういう心境になってしまうのだ。自分ががんばっても治らない、医師にも治せないとなると、もう頼るものが他にないではないか。
だから、宗教に入ってしまった病人を、ダメだと思う気持ちはまったくない。
しかし、そういう病人の弱った気持ちにつけこむ宗教は、許せない。
宗教だけではない、怪しい自然療法や、サプリ、万病の治る石とか水とか、いろんなものが六人部屋にはやってくる。オカルト博覧会だ。
ぜんぜん知らない人がいきなりやってくる場合もあるが、たいていは親戚や知り合いだ。
「病気になったと聞いて、心配してやってきたの」と、そういう人たちは、最初はとても親身でやさしい。
「これはわざわざどうも」と、病人のほうも、丁重に対応する。
だが、だんだん話が怪しい方向に展開していく。
「私もね、前はいろいろ病気になって大変だったの。でもね、これを飲むようになってから、ほら、この通り、ピンピンしてるのよ。あなたもちょっと試してみたらどうかな? 薬じゃないから、身体によくないということはないし、ものは試しだから」
そういう話になると、病人のほうは、「はあ……」と困った様子になる。なにしろ入院中だから、「私はこれからちょっと用があって」と、外出したりするわけにもいかない。逃げ場がないのだ。勧誘するほうはしつこいから、何時間でもしゃべっている。「ちょっと体調が……」などと横になろうとしても、「じゃあ、なおさら、今すぐこれをひとくち」とか言い出すから、始末におえない。
その日の面会時間が過ぎても、また別の日にくる。何度でも来る。
そんなこんなで、いまの間にか、妙なものを買わされていたり、けっきょく入信したりしてしまうことは、決して少なくなかった。
宗教の勧誘をする人にとっては、病気の親戚や知人は、カモの中のカモ、逃せない魚なのだろう。
資産がなくても油断はならない
「私はお金がないから、大丈夫」と言っている人がいたが、そんなことはない。
宗教や怪しい勧誘は、そんなに甘くない。
お金がなくても、借金させる。
また、当人からお金をしぼりとることができなくても、勧誘アリとして働かせる。今度は自分が、親戚や知人のところに勧誘に行かされるのだ。
使い道はいくらでもあるわけだ。
そうして、悲惨な姿になっていった人を何人も見ている。
先にも書いたように、そういう人を軽蔑する気持ちはまったくない。ただ、かなしい。ただただ、かなしい。
少しでもそういう人が減ってくれればと思って、書いてみた。
今となっては懐かしい
コロナ以降、お見舞いも禁止の病院が多い。
お見舞いの人が来て、元気が出たり、腹を立てたり、泣いたり、落ち込んだり悩んだり……そうしたお見舞い八景も、懐かしいものとなってしまったのかもしれない……(宗教の勧誘などは別として)。
(この項了)
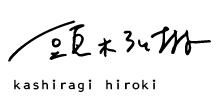 文学紹介者。筑波大学卒業。大学3年の20歳のときに潰瘍性大腸炎を患い、13年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いとなった経験から、『絶望名人カフカの人生論』(新潮文庫)を出版。その後、『カフカはなぜ自殺しなかったのか?』(春秋社)、『NHKラジオ深夜便 絶望名言1・2』(飛鳥新社)、『絶望書店 夢をあきらめた9人が出会った物語』(河出書房新社)、『トラウマ文学館』(ちくま文庫)、『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』(ちくま文庫)、『食べることと出すこと』(医学書院)、『自分疲れ』(創元社)などを刊行。
文学紹介者。筑波大学卒業。大学3年の20歳のときに潰瘍性大腸炎を患い、13年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いとなった経験から、『絶望名人カフカの人生論』(新潮文庫)を出版。その後、『カフカはなぜ自殺しなかったのか?』(春秋社)、『NHKラジオ深夜便 絶望名言1・2』(飛鳥新社)、『絶望書店 夢をあきらめた9人が出会った物語』(河出書房新社)、『トラウマ文学館』(ちくま文庫)、『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』(ちくま文庫)、『食べることと出すこと』(医学書院)、『自分疲れ』(創元社)などを刊行。