海の中での潜水のごとく、ひとつのテーマについて皆が深く考え込み話し合う哲学対話。小学校、会社、お寺、路上、カフェ……様々な場で哲学対話のファシリテーターを務める著者は、自らも深く潜りつつ「もっと普遍的で、美しくて、圧倒的な何か」を追いかけてきた。当たり前のものだった世界が、当たり前でなくなる瞬間、哲学現在進行中。「え? どういう意味? もっかい言って。どういうこと、どういう意味?」……世界の訳のわからなさを、わからないまま伝える、前のめりの哲学エッセイ。
ゆっくり、ゆっくり、店員さんがわたしのマグカップを梱包している。
箱をゆっくりと開け、わたしに中身の確認をうながす。箱がうまく閉まらない。何度も開いては閉じ、開いては閉じ、ようやく箱が元の形に戻ってくれる。店員さんはふうっと安堵した息を漏らすと「プチプチをします」とわたしの目を見て言う。割れないように梱包いたしますので少々お待ち下さい、などといった紋切り型の言葉ではない。彼女はきっと、箱と格闘しながら「これからプチプチ、これからプチプチ」と思っていたのだろう。心の中でつぶやいていた言葉が、そのままずるりと出てきたように、店員さんとわたしのあいだに落ちる。
息苦しいマスクの中でわたしは「はい」とかすれた声で小さくつぶやいて、ゆっくりと箱がプチプチに覆われていくのを見ている。産まれてはじめて、プチプチを触ったかのような手つきで、店員さんは箱をくるむ。すでに相当な時間が経過している。店内にはそれなりに人がいて、わたしの後ろには若い男女が並んでいる。時間のわりに、梱包は丁寧ではない。もったりとしたふるまいで、気まずい沈黙だけが流れている。居心地は悪く、不快感がわたしの血管をじっとりと満たしていくのがわかる。
わたしは、どんよりとした苛立ちに心を浸しながら「どうか世界がこれ以上速くなりませんように」と祈った。
*
最近、電車の中で韓国の男性アイドルグループの動画を見るのが好きだ。プロフェッショナルなダンス。魅力的な表情や目つき。透き通った声。この年になってようやく、アイドルの凄さを知ったわたしは、感動しながら動画を再生する。
だがわたしのスマホは、ほとんどつねに通信制限がかかっている。youtubeをひらくのに一駅分かかる。ようやく見えたサムネイルをタッチすると、再生が開始するまでさらにまた一駅分かかる。やっと再生されたダンス映像は、廃墟から発掘されたビデオテープのようにガビガビで、キレキレのダンスがカクカク動く。そんな映像だから、当然顔はつぶれていて、誰が誰だかわからない。服装で誰が誰なのかを推測しようとするが、無益な試みに終わる。
いらいらとロード中の画面を何度も見つめる。それと同時に「どうか通信制限がこの世からなくなりませんように」と願う。
*
哲学対話は「話す」よりも「聞く」営みである、とはよく言われる。鷲田清一の名著『「聴く」ことの力』にて「わたしたちは語ること以上に、聴くことを学ばねばならない」という文は「哲学はこれまで喋りすぎた」という反省に裏打ちされている。
哲学だけでなく、わたしたちは常に喋りすぎている。日常で、会議で、SNSの中で。じっくりと聞くのではなく、何か「いいこと」を話さないといけないというオブセッションに急かされて、夢中で口を動かしつづけている。沈黙がこわい。よどみ、停滞がおそろしい。議論での沈黙は、その場への不参加だと思われる。真っ白な画面に、めちゃくちゃに文字を打ち込むように、急き立てられて話しつづける。もっといいことを、もっと意義深いことを。もっと人を動かし、もっと尊敬され、もっと「ここにいていい人間だ」と思ってもらえるようなことを。
以前、ある生放送に出演したとき、残り時間の少ない中、ラッパーのダースレイダーさんに「ぼくも(下の名前が)レイなんですよ」と言ってもらえ、嬉しさと何か返さねばという焦りで「それはよかったです」と答えてしまった。おどろくほど空虚な言葉。空白を埋める、焦燥にまみれた応答。自分でも呆れるし、放送を見ていた友だちからは「よかったってなんだよ」とLINEがきた。
ラジオでは数秒間沈黙があると放送事故になるという。数十秒間沈黙が続くと、エマージェンシーテープとして、音楽が自動に流れるらしい。わたしたちの人生はいつでも生放送である。放送事故を恐れて、わたしたちは沈黙を空疎な言葉で埋め尽くす。陽気な音楽が流れ始めたって、本当は誰も困りはしないのに。
わたしたちは急いでいる。わたしたちは速度を求めている。もっと速く、もっともっと速く、より多く、より豊かに、より意義深く。より豊穣な実りを。より膨大な成果を。だが哲学対話は「急ぐな」と言う。「立ち止まれ」とささやき「問い直せ」と命じる。
そして、哲学対話は「待て」とも言う。
*
小学生のころ電車に乗ったとき「次は祐天寺」とこなれた口調で言う車掌さんの様子が、いつもと違ったことをおぼえている。静かに朝日が当たる車内で、ガチャガチャとマイクをつなげる音がして、車掌さんの低い声が流れる。
「次はァ、ゆう」
そう言って車掌さんは黙り込んだ。まばらに座る乗客は黙ってそれを聞いている。あのときは、スマホなんてなかったから、みんな、心細いような目で窓の外を見ていたものだった。
「………………………………………………………………………」
サーーーーという、マイクがつながったままの音はしている。スピーカーを見ても仕方がないのに、乗客はどうしたのかと見上げる。わたしも見上げる。
中目黒駅を出発した東横線はもうすぐ祐天寺駅に着いてしまう。乗客は一丸となり、緊張感をにじませた表情で、次の言葉を待っている。
「……………………………………天寺です。」
向かいに座る女性がほうっと息を吐く。あんなにもみんなで車掌さんの声を待ったことはなかった。誰もが次の言葉を待ち望んでいた。出自も性別も異なるひとびとが、すさまじく張り詰めた空気の中で「聞く」をしていた。
あのときの車掌さんのことを思う。はたして次は本当に祐天寺駅なのか?ゆう、と、てんじ、の間には、何があるのか?われわれはどこへ向かっているのか?彼の中に多くの問いが生まれては消え、わたしたちの日常を揺るがす。つるつるでなめらかな時間にたくさんのスペースを差し込んで、隙間をつくって、わたしたちを中断させる。目的地に機械的にすすむ電車が、あの時間の、あの電車の、あの車両の、あのときになる。
数年前の哲学対話でも似たようなことが起こった。何かを熱く語っていた参加者のひとりが、突然固まり、沈黙した。両手はろくろを回すポーズのまま静止し、目は見開かれている。そこに集まったひとびとは、全員がお互いに初対面で、ばらばらで、何一つ共通点がなかったが、誰も彼の沈黙を邪魔せずに息を呑んで彼のつづきの言葉を待った。その瞬間、これまですいすいと進んでいた対話がむしろ違和感を帯びたものに様変わりする。
逡巡、困惑、どうやったらこれを伝えられるのか、どうやったら相手を傷つけないかと考えをめぐらすあの間。そしてそれを、決して見逃すまいとするように集中してじっと待つ瞬間。それはわたしたちの人生に起こる放送事故でもあり、つるつる、すべすべ、サクサクとした日々に、挟まれるささやかな休息である。
だからわたしたちは愛そう、通信制限を。
永遠にまわりつづけるロード中の輪っかを。
何度も回線落ちするzoom会議を。
話の途中で、黙り込むあなたを。
はやさ、なめらかさ、淀みのなさが価値である世界へのささやかな抵抗。舌なめずりをした資本主義の触手が、わたしたちの目を覆い隠す前に。便利と安全をうたいながら、脆さや問いかけ、ただ存在するということへの排除を宣告される前に。
こんなことを書くと「スローライフを楽しもう」「ていねいな暮らしで人生にゆとりを持とう」といった主張と思われるかもしれない。生活をバカにせず、丁寧に生を紡いでいくことは重要だ。だがわたしが考えるのはもう少し、自分の身の回りというより、他者を巻き添えにしたものであるし、時に苦痛に満ちたものである。
「待つ」ことはつらい。ただし「待たされること」を「待つこと」に捉えかえすとき、それは決断と主体性を帯びたものになる。「急ぐ」ことを拒否する態度になりうる。待つことは、目を覚ましていることだ。苛立ち、焦りを感じながらも、それを注意深く拒むことだ。
*
いつかのお寺での哲学対話は、黙って寺内を歩き回ったあと、再び集まって問いを共有し、対話を始めるというものだった。主催ながら寝不足で疲れていたわたしは、荷物番を買って出て、ひとびとが寺内を歩き回る時間、ぼうっと畳の上で庭を見て過ごした。時間になり、ぞろぞろとひとが帰ってくる。対話がはじまり、ひとびとが、日常に差し込まれた空白の時間に考えを巡らせた問いを交換する。
ふと「永井さんは何を考えていましたか」と問われ、うろたえる。しまった、何も考えていなかった、と思う。だが沈黙をおそれたわたしは「みなさんを待っている間、”待つ”ってどういうことかな、と考えてました」と咄嗟に応えた。あまりにとりとめのない問いのせいか、ひとびとからは特にリアクションはなかったし、わたしは適当なことを言ったなと自分で呆れて、それからすぐに忘れた。
だが、あれから数年経って、その問いがしゅわしゅわと静かな泡を立てて、ゆっくりと目の前にあらわれてきたのを感じる。レジの店員さんがびびびびび、とセロハンテープを引っ張っている。ゆっくりと貼られるテープ、ふわふわのプチプチ、奇妙な沈黙。待つとは一体何なのか。レジで、立ちっぱなしの足の痛みを感じながら「なんだ、実は面白い問いだったな」と問いに話しかけてみる。問いはゆっくりと長い年月をかけて、わたしの目の前にふたたび浮上したのだ。
「きみがそう思うまで、ずっと待っていたよ」
しゅわしゅわと音を立てながら問いは言った。


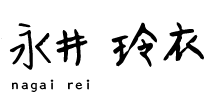 哲学の研究と、学校・まち・寺社・美術館などで哲学対話を開催中。好きなものは、詩と漫才と植物園。
哲学の研究と、学校・まち・寺社・美術館などで哲学対話を開催中。好きなものは、詩と漫才と植物園。