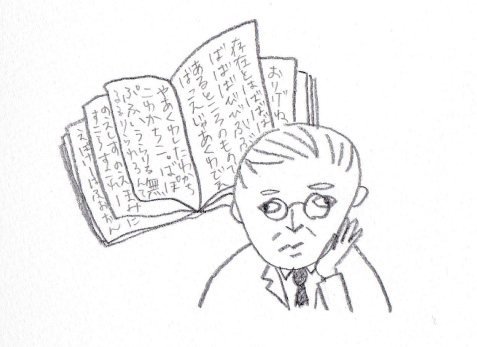海の中での潜水のごとく、ひとつのテーマについて皆が深く考え込み話し合う哲学対話。小学校、会社、お寺、路上、カフェ……様々な場で哲学対話のファシリテーターを務める著者は、自らも深く潜りつつ「もっと普遍的で、美しくて、圧倒的な何か」を追いかけてきた。当たり前のものだった世界が、当たり前でなくなる瞬間、哲学現在進行中。「え? どういう意味? もっかい言って。どういうこと、どういう意味?」……世界の訳のわからなさを、わからないまま伝える、前のめりの哲学エッセイ。
たしか中学生のころ。
わたしたちは冷たい体育館の床に座っていた。先生がぴっと目の前にある跳び箱を指さして「永井、見本を見せてくれ」と言った。姿勢良く一番前で座って聞いていたわたしは、さっと立ち上がり、跳ぶ準備をする。
みんなが見守る中、わたしは奇怪に手を振り回し、つんのめりそうになりながら助走をつけ、からだと手を同時に前に出して跳び箱に手をつき、右足を強く打ち付けて、ひっくり返るようにしてマットに倒れ込んだ。別に問題はない。これがわたしの跳躍なのだ。
体育館はしんと静まりかえっている。「大丈夫か」。やっとのことで先生が口をひらく。
わたしはマットに寝っ転がったまま、高い体育館の天井をぼんやり眺めていた。跳躍が失敗したのではない。先生が選ぶのを失敗したのだ、と思った。
*
わたしは対話がこわかった。
人前で話すこと。他者、時には見知らぬ人の意見をじっと聞くこと。他者に質問されること。人と一緒に考えること。他者を傷つけないか、おそれながら話すこと。他者に傷つけられないか、おそれながら聞くこと。
大学に入学して一年目からゼミがあります、と聞いたときに「こんなはずでは」と思った。プラトンの『ソクラテスの弁明』やアウグスティヌスの『告白』、カントの『啓蒙とは何か』が文献に選ばれた。どれも難しかった。授業が始まり、狭い部屋に押し込められた同年代の人たち。彼らは店員を呼ぶ気軽さで、どんどんと挙手をしていく。誰かの意見に誰かが反応し、あちらでは誰かが反論をしている。どっと笑いが起こる。誰かが、ユーモアたっぷりのエピソードを交えて意見を披露したのだ。先生が嬉しそうに微笑んでいる。みんなは笑い、考え、対話していた。日々は過ぎ、時は流れた。わたしだけがじっと緊張し続けて、とうとう一年間、ただの一言も発することができなかった。
ゼミだけでなく研究会でも、他の授業でも同じだった。中高時代は、いちばん嫌いな授業は、数学でも英語でも体育でもなく、ホームルームだった。わたしはいつも、石のように押し黙り、この世から自分を消した。黙っているやつほど考えている、と先生たちはよく言うが、わたしは1ミリも思考を前進させることなく、石よりも石になった。
対話をおそれて押し黙っていた学生時代から何年か経ち、いつの間にかわたしは人前で話すことが多くなった。なぜか、哲学的な対話の場をひらく人になった。今日も小学校に出向き、哲学対話の授業をする。子どもたちに、輪になって座ってとお願いする。ぐるりと輪になると、お互いの顔が分かる。誰かが話しているとき、わたしたちはその人の顔をじっと見つめる。時に、それは違うよ、などと否定の声が向けられる。誰かが、誰かの心を傷つけるようなことを言う。別の誰かがむっと嫌な顔をする。隣のあの子は、授業も3回目だというのに、まだ一度も話さずうつむいている。誰かが一生懸命言った言葉が、誰にも受け止められずに床にどさっと落ちる。対話とは、対話とは、相も変わらずなんと難しいんだろうか。
顔を上げると、教室の後ろのロッカーの上に、子どもたちが授業で書いたであろう習字がびっしりと貼ってあるのが目に入った。
仲間仲間仲間仲間仲間仲間仲間仲間仲間仲間仲間仲間仲間仲間
目がくらむ。仲間とは何だろう。彼らは仲間だろうか、わたしも仲間だろうか。わたしは今でも、対話がこわい。
人と一緒に考えることを仕事にしてるよ、と10代の頃のわたしに言ったら、うんざりした顔をして、なんでそんなことを、と言うだろうか。
*
大学院生の頃、学会準備のため論文を授業でプレ発表した。サルトルの他者論をベースにした倫理学の論文で、倫理的コミュニケーションのひとつとして「呼びかけ」という概念を提起したのだ。サルトルによれば呼びかけとは、強制や懇願ではない。ある具体的な状況の中で、自らの自由でもって、相手の自由に呼びかけることだ。主にそれは文学、つまり作者と読者の間で起こるものだとサルトルは言っているが、彼は、バスの乗客が遅れて走ってきた男を引っ張り上げる例を挙げてもいる。バスに跳び乗ろうとする男は、乗客に引っ張り上げてもらうことを求めている。だが、それはあくまで呼びかけであって、相手の自由に委ねている。乗客の方も、手を差し出すが、それは拒絶される可能性を含んだ上での呼びかけである。互いの自由によって成り立った呼びかけによって二人の手は繋がれ、男はバスに跳び乗ることができる。なんだかよく分からない例だが、とにかくわたしはサルトルの「呼びかけ」に関するメモをまとめて下地にし、「承認」や「コミュニケーション」についての、倫理学の論文を書き上げた。
論文の読み上げ発表を終えると、目の前に座っていた先生が厳しい表情をしていることに気づく。出来の悪い論文や発表を強めに叱咤する怖い先生だったので、わたしは思わずごくりと唾を飲み込む。確かに、結論に向かうまでの3章の論理構成はやや不安定だ。承認論の先行研究も不足していたかもしれない。ヘーゲルにも言及した方が良かったか。先生が「あのね、永井さん」と言う。静かな声だ。
「このバスの例はあぶないよ」。
え、と声をもらす。倫理的に危ういという意味ですか、と聞く前に、先生が続けて言う。「走ってるバスに跳び乗るのは、あぶない」。あっ。そこなんだ。予想外の反応に「フランスのバスなので・・・」などよく分からない言い訳をしてしまう。フランスだろうが、東京だろうが、別に危険度は変わらないだろう。だが本番の学会発表も近かったので、まあサルトルが出した単なる具体例だし、と特に直さずにそのまま発表した。
数年後、ある先輩と久しぶりに再会したとき、先輩が「前に永井さんの学会発表聞いたよ」と言ってくれた。彼は研究領域も近かったので、どうでしたか?と聞いてみると、先輩が言った。
「あんま覚えてないけど、バスのやつがなんか危ないなって思ったよ」。
こいつもか。
バスはただの例だし、わたしの発表の主眼はそこではない。わたしの主張が、バスに跳び乗るどうでもいい例であまり伝わっていない。バス以外のことを覚えていろ。バスのことだけ忘れてくれ。

当時は危険な跳び乗り行為に注目が集まったことに拍子抜けして笑ったが、今思うと、その危うさも含めて、サルトルの例は他者のコミュニケーションを言い当てているような気がしている。
対話というのはおそろしい行為だ。他者に何かを伝えようとすることは、離れた相手のところまで勢いをつけて跳ぶようなものだ。たっぷりと助走をつけて、勢いよくジャンプしないと相手には届かない。あなたとわたしの間には、大きくて深い隔たりがある。だから、他者に何かを伝えることはリスクでもある。跳躍の失敗は、そのまま転倒を意味する。ということは、他者に何かを伝えようとそもそもしなければ、硬い地面に身体を打ち付けることもない。もしくは、せっかく手を差し伸べてくれた相手を、うっかりバスから引き倒して傷つけてしまうこともない。
バスに向けて走るわたしに、誰が手を差し伸べてくれるだろうか。誰が気が付いてくれるだろうか。他者に何かを伝えようとすれば、誤解され、無視され、時には相手を傷つける可能性すら生じるというのに。でも、サルトルの言うようにきっと、それは強制であってはならない。多くのリスクを背負い、あなたの自由を尊重した、呼びかけでなければならない。そして、その呼びかけが完全にあなたに伝わり、そしてあなたの呼びかけもまた、わたしに届くということは、原理的にあり得ない。
他者とわかりあうことはできません、他者に何かを伝えきることはできません、という感覚は、広く共有されているように思う。わかりあうことができないからこそ面白い、とか、他者は異質だからこそ創造的なものが生まれる、とかいう言説もあふれている。その通りだ。その通り。全くもって、完璧に、同意する。だがわたしはあえて言いたい。
それでもなお、わたしはなお、あなたとは完全にわかり合えないということに絶望する。
つい先日、社会人向けの哲学対話で「自由とは何か」をテーマにしたとき、「わたしたちは、できるはずのことができないときに不自由を感じるんです」と言った人がいた。だって、わたしたちは、空を飛べないということを、不自由だと言わないでしょう。そもそもできないことを、わたしたちは不自由だと嘆かないんです。
なるほどと思う。となると、他者とわかり合えないことを嘆くわたしは、それができると思っているのかもしれない。だが、他者と完全に通じ合うことは、跳ぶどころか、空を飛ぶようなものだ。大きく跳躍することを超えて、空高く飛翔することだ。空を飛ぼうとするわたしは、跳び箱を失敗した中学生のときのように、みんなの前で無様で滑稽に墜落するだろう。冷たい体育館の床に横たわり、高い天井をぼんやり見つめるだろう。
でも、わたしはせめて分かり合おうとしあいたい、と思う。完全に通じ合わなくてもいい。分かり合うことはゴールではない。分かり合うのではない、分かり合おうとしあうこと。互いに空を飛ぶことを夢見ること、それだけでいい。

信頼できる人に向けてならまだしも、見知らぬ人に向けて飛翔するのは、本当にこわいことだ。無防備で、無謀で、おこがましいことだ。だからこそ、対話はおそろしいものでありつづける。
以前、何かの哲学対話の途中で、ある男性に「対話はぬるい」と言われたことがある。男性は「ぬるいのはやめて、もっと人と意見をぶつけてはっきりと勝ち負けを決めるべきだ、もっと闘わせるようなものでなければならない」と言った。
ぬるい、ということは、対話は簡単だと思っているのかもしれない。仲間と一緒に、みんな仲良く。そんな響きを聞き取ったのかもしれない。だが本当は、対話とはめちゃくちゃに難しく、時につらいものだと思う。そして、哲学対話は、その難しさに否が応でも直面しなければならない。人と考えること、自分の考えを伝えること、人の考えを聞くこと、その難しさにめまいを覚えながら続けなければならない。
勝ち負けを決めるのは簡単だ。こっちの方が分かりやすいです、とか、論理的、面白い、声が大きい、とか。傷つけ合うことが認められた中で、闘うことはもっと楽ちんだ。本当に、簡単だ。
男性はため息をついて「自分は人と考える、なんてことは好きじゃない」と言った。
わたしはうつむきながら「だから、やるんですよ」とつぶやいた。
一週間が経ち、外部講師をしている小学校に行く時が来た。今日のテーマは、子どもたちがやりたいと言った「ことばはなぜ違うのか」だ。もたもたと準備をしていると、子どもたちにはやく、はやく、と急かされる。彼らはさっさと輪になって座っている。
空いた椅子に腰掛けると、ロッカーの上に貼られていた「仲間」の習字が、全て入れ替わっているのに気づいた。代わりにそこは、「飛ぶ」という字が壁一面に並んでいた。
飛ぶ 飛ぶ 飛ぶ 飛ぶ 飛ぶ 飛ぶ
飛ぶ 飛ぶ 飛ぶ 飛ぶ 飛ぶ 飛ぶ
飛ぶ 飛ぶ 飛ぶ 飛ぶ 飛ぶ 飛ぶ
はやくやろうよ、と子どもたちが話しかける。既に何人かが挙手をしている。哲学対話を始めたがっている。
彼らはもう飛んでいる。わたしも飛ぶことにしよう。
*イラストも著者


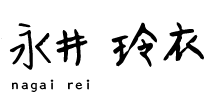 哲学の研究と、学校・まち・寺社・美術館などで哲学対話を開催中。好きなものは、詩と漫才と植物園。
哲学の研究と、学校・まち・寺社・美術館などで哲学対話を開催中。好きなものは、詩と漫才と植物園。