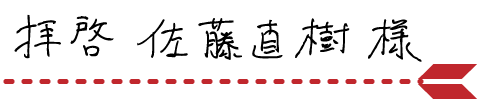2017年04月30日から2017年06月11日まで、千代田区の、「アーツ千代田 333メインギャラリー」で、「佐藤直樹個展『秘境の東京、そこで生えている』」が開催されました。板に木炭で植物を描いた作品はおよそ100メートルに及び、展示の方法も類を見ないものでした。そして、今も佐藤さんはこの続きをたんたんと描き続けています。展覧会を一区切りとしたわけではなく、展覧会から何かが始まってしまったということです。本連載は、佐藤さんの展覧会を起点に、文化人類学者の中村寛さんに疑問を投げかけていただき、「絵を描くこと」や「絵を見ること」「人はどうして芸術的なものを欲してしまうのか」など、世界についての様々な疑問について、語っていただく場といたします。
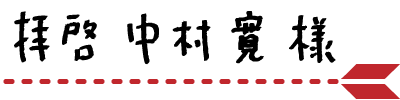
お手紙いただいてから3ヶ月以上が経過してしまいました。荻窪での個展が終わって、しばらくは人に見せることを意識せず、できるだけ静かに、ただ描くことだけ続けようと思いながら、生活を成り立たせるためのあれこれで忙しくしていました。
個展は「本屋Title」の辻山さんに声をかけていただいて成立したもので、井伏鱒二の『荻窪風土記』のことも辻山さんから教えていただきました。そんなわけで、今回の個展は『荻窪風土記』を読むところからスタートしています。読みながら、当時の風景を想像しました。それがどれくらい的を得たものなのかはわかりません。しかし、いかに見当外れの想像だったとしても、今ここでこのようにしか存在していないと思われる世界から抜け出すのには十分なことだったと思います。井伏さんが歩いた道筋とできるだけ近いそれを探しながら、ふらふら歩いていると、井伏さんではなく自分の方がすでにこの世にいない、幽霊のような存在に思えたりもしました。
さしあたって、自分にできるのは、そこにあるものをただ観察することだけだろう、と。それを誰かに伝えるとか、そのために記録するとか、そんなことを思ったところで、伝わるわけでも、記録できるわけでもないでしょうから。ただ、観察したことを自分に向かって確かめるために描いているところはあって、2013年に荻窪を歩きながら描いた時もそうでしたが、それが結果的に「絵」になっていく。そういう順序です。ですから、「ケヤキ」や「荻」であることに意味があるわけではないというか、たとえば今、中村さんとこうしてやりとりをしながら、一応、日本語を使ってはいますけれど、中村さんが日本人であるかどうかとか、男性か女性かとか、どこの大学の教員であるとか、そういった点はあまり話の本質と関係ない、ということに近い気がします。ですが、植物や水や鉱物などはこちらに関心を示してくれるわけではありません。ですから、どんなレスポンスの期待も伴わない「観察」が主になります。
今回はそれでも何か描くつもりで歩き始めているのですが、2013年の時点では、本当に何が描けるかもわからず歩いていました。ここのところは自分でもよくわからない行動だと思います。さらにそれより前、2010年から2011年にかけて荻窪を歩いていた時、見たものを絵にする気持ちすらありませんでした。デザイナーとしての長年の行動様式が染み付いていましたし、「作品制作」というような意識はなく、アートセンターである3331のオープンにあたってデザインディレクターとして会場構成的な制作をしたことから「荻窪の6次元でも何かできないか」という依頼を受けて「どうしたものか」と周囲をうろついていただけでした。
この話は別のところにも書きましたが、その時の感覚は、どうにも説明のしようのないもので、絵の展示をすることに決め、その準備に入ったところで震災がありました。そういったことに対して、何か特別な意味づけをしたい気持ちが、しばらくはあった気がします。けれども、今はそれもなくなってきました。なぜこの時期から急激に「描く」ことが迫り上がってきたのか。確かにあの震災がなければ、今でも、それまでのデザインの仕事の継続を中心に活動していたかもしれません。しかしこればっかりはわからないことです。
今回、荻窪で「観察」することをし、結果として描かれたものがあり、現時点で134メートル強の幅になっている絵の中にそれは収まっている。絵は変化しているようなので、その流れをとめるつもりはない。とまる時にはとまるだろう。どんなに長くたってせいぜい数十年、百年には満たないわけです。しかも、誰かに引き継がれるような行為ではなさそうだ。美術史的な意味で刻まれることを望んでいるような行動でもないし、マーケットも存在しない。好きでやっているというのとも違っていて、趣味とも言えない。好奇心を持って見ている人はちらほらいても、絶対的な切実さでこのような行為を求めている者はどこにもいないでしょう。自分以外には。
そうであるなら、どうせ今生の刹那なのだから、もっと筆の赴くまま、もっと自由に、植物や水や鉱物から受けたインスピレーションのようなものを、「私」ならではの絵として描けば良いのではないか。なのに、なぜ姿形を似せたような、「ケヤキ」のようだったり「荻」のようだったり、水の溜まった窪地の岩のようであったりするものを描いているのか。そんな疑問も起こってしかるべきです。けれど、「私」はそこまで信用に足るものではなくて、多分に身体的な行為としてこうなっているような気がするのです。「私は足で考える」のであり「足だけが何か堅いものに出会う」とジャック・ラカンは言ったそうですが、今の自分は体全体で考えることに身を委ねようとしているところがあります。物心つく前からしていたような行為を、今また辿り直そうとしていて、何らかのかたちで「出会った」ものを反射的に描写していた、かつて自分の身に起こっていた出来事を、身体的に思い出そうとしている感覚なのです。信用に足ることとして思い浮かべられる最初の地点にあったもの。それはある意味で、社会化することに抵抗を示していたとも言えるわけで、今やっていることにしても、そこに向かっている気がするのです。
だとしても、それが植物や水や鉱物ばかりなのはなぜなのか。今はそういうものとしか「出会う」ことがないということなのか。子供の頃を振り返ると、かなり早い段階から動物やら乗物やら特撮のヒーローやらに反応していました。それも「出会い」であったのでしょうし、一心に描いてもいたわけです。ただ、もっと前まで遡った時に、何が見えていて、何が聞こえていて、何に触れていたのか、ということの方が重要です。そこのところの記憶はない(からこそ重要でもある)のですが、その段階でもう何かを描き始めていたはずです。手を弄っていたはずです。それを探るのに、外から証拠を集めてきて、こういったものを目にし、このような線を引いていたのではないか、というような探り方をしても意味はなく、「原風景」のようなものがその先にあるはずなのです。
自分をできるだけ「その状態」に近づけて、「現時点の身体にできること」を駆使するところからしか、「そこ」には辿り着けない、という確信が今はあります。長い間、社会的な適応を優先する中で眠らされていたものを呼び覚ます上で、植物や水や鉱物に特別な力を感じている、としか今は言えないのですが。
わたしはかなり小さい頃から美術教育として提示されたものは極力拒否するようにしてきました。「美術教師が言うことに従うのはやめておこう」と(そんな自分が今では美術大学の教員をやっているのですから事態は複雑です)。ただ、ある期間に渡って、母親が描いていた姿を見てはいて、それが教育だったのだろうと言われればそうなってしまうのですが、そういう意味で言えば子育ては放棄されていたようですから、何が見えていて、何が聞こえていて、何に触れていたのかを再構成した時に、そこに人の姿がない、ということも大いに考えられることではあります。
行為の根っ子にあるものを、言語的に説明し切ることにどんな意味があるかはわかりません。2018年になって荻窪で描いた、わたしなりの「風土」や「世界」が、どうしてこのようなものでなければならなかったのか、という話をすることも。ただ、2013年の「秘境の荻窪」とかなり異なる感触を持っていたことは確かで、その話をすることは必要かもしれません。
2013年の段階ではまだ「思い出に浸っていた」のだと思います。久々に多感な時期を過ごした荻窪を歩き回って、その頃から残っている家屋などを描き始めていたところで震災が起こり、少し落ち着いてから再び訪れた荻窪で目に入ってくるようになったものは、植物に変わっていました。あまりの出来事に、より「変化しないもの」を求めたのでしょうか。懐かしかった家屋も、倒壊して無くなっていくだけなのかもしれない。けれども、それでも、荻窪であることは重要でしたし、記憶の範囲内で、自分の存在を支えてくれるものを、何が何でも探したかったのでしょう。
しかし、2018年に歩いた時には、もうそのような気持ちはなくなっていました。増殖する植物以外に描いているものがまったくないわけではないのですが、かなり集中的に続きを描いているモチーフなので、他のものが顔を出すことはあまりありません。ただ、「新・荻窪風土記」では、2013年以前に描いていたものも展示に含めるようにしました。もっといろいろなものを描いて、いろいろなものを繋げたい気持ちもあるにはあるのです。
わたしもわたしなりに、「文体」の実験をしているつもりでいて、その点で中村さんと違いはないような気もします。わたしの場合は「絵の文体」ということになるのでしょうが。「匂いのある風景」を描きたい気持ちもあります。風も吹いてほしいですし。2013年の絵はあまりに拙いですが、ただ単に「よい文体」で描けば良いとも思っていません。「思い出に浸っていた」なりの良さだってあるかもしれないですし。2018年の荻窪の絵がそれに比べてどうなのかということも今はまだわかりません。描けば描くほど表現力の限界に直面します。感じ取る力だけは少しは掘り起こされて豊かになってきていると信じたいところですが。
流行や潮流のことも考えます。自分の絵も、後から冷静に眺めれば、それなりに分析可能な諸条件の元で描かれていたことが浮き彫りになるでしょう。わたしが好きなつくり手は皆、生きている時にはあまり評価されず、世間とうまく折り合いをつけられなかったような人たちです。フィンセント・ファン・ゴッホしかり、フェルディナン・シュヴァルしかり、ヘンリー・ダーガーしかり。大道あやさんや丸木スマさんなど、生前に評価されている人もいますが、あやさんは60歳から、スマさんは70歳から描き始めており、その意味で流行や潮流からは隔絶していました。これらの人の「方法」は決して類型化できません。考えはしても、自分がやるとこういうふうになってしまう、どうしてもなってしまう、というところに向かうしかなかったのだろうと思います。
『荻窪風土記』を読むと、地震後のデマや差別の問題が浮かび上がってきます。状況は今も変わっていない気がします。そんな中、多くの社会問題を前に、自分は引き蘢って絵を描いている。無関係を決め込むのか。社会問題を作品に繰り込むことはしないのか。そういった自問は常につきまといます。当然1920年代にも存在していた問いです。現時点で思うことは、無関係を決め込むことはせず考え続けるし行動の選択もする、しかしそれを意識的に作品化することはしない、ということになるのでしょうか。
社会についての危機感は当然あります。インターネットの普及や国家を凌駕する世界資本の成長によって、デマや差別に関わる問題にしてもかつてのそれとはまた別の新しい局面に入っているのかもしれません。続く世代の人たちのことも気になります。社会問題は社会問題、作品制作は作品制作、と簡単に峻別できるのか、大いに疑問です。たとえ生きている間に作品を発表しなかったとしても、制作の継続、そのようなスタンスの維持といったところに、社会の問題は接続されているからです。そういった点では、学問と芸術、芸術と学問はもっともっと交流すべきではないかという思いもあります。
「くぼんだ土地」はとても示唆に富むテキストでした。荻窪を離れて、今また、外神田のかつて錬成中学校だった場所で描くことを続けていますが、あらためてその周辺を歩き、以前よりも一層、土地の凹凸が意識されるようになったことに気づきました。普段の忙しい都会的な生活の中では、土地の凹凸のことが意識に上ることなどほとんどありません。とくに「くぼんだ土地」のことなどは。そして、実際の土地の形状から、もっと象徴的なものが想起されます。土地は決して固定的ではなく、いわば呼吸をしています。そこにはあらゆる「運動」の元になっているような力があります。こうした話も、学問と芸術、芸術と学問を交差させながら活発化させるべきではないかと思い始めているところです。
「空想傷痕──辺見庸氏の『たんば色の覚書』(毎日新聞社)を受けて」からも多くのことが想起されました。現代の「暴力」の問題は、今の自分にはとても考え切れませんが、今自分が描いているのは、自ら内在させてきた「暴力」を顕在化させないため、という面が間違いなくあると思っています。描くことによって何かを鎮圧している。ですから、それ自体が何か素晴らしい行為なのかといえば、そんなことはない。ただ、もしそうであっても、というよりそうであるならなおさら、描かれたものには何らかの普遍的な要素がなければならないはずなのです。
描く対象が植物や水や鉱物であるから普遍的というような話ではありません。今描いているものは、いずれもっと大きな何かの部分になっていくでしょう。逆に、描いている最中の、どんな部分を切り出してみても、それがちゃんとした全体になっているような絵が描けないものなのか、ということを夢想しています。それはつまり、一本の線も疎かにしないということですが。まだまだ一向に先は見えてきません。今のところまだ、ひたすら描き進めることを続けているだけです。
最終的に「描くということはこういうことだろう」という現在の人工的フレームからどうやって逃れたらいいのか、今はまだわからずにいます。たとえば、ミシェル・フーコーは自ら「新たな方法」を採っていたのでしょうか。それとも旧来からあった方法を駆使して「新たな認識」に至ったのでしょうか。自分の立ち位置を、あのような知の巨人と比べても仕方ないかもしれませんが、美術という制度は今も厳然と存在しており、その一方でポストモダンの名の元に「新たな方法」が繰り出される様子を見続けていると、どちらかに組みするしか選択肢がないかのような状況から逃れる「方法」のことはどうしても考えざるを得ないのです。
2018年11月7日
佐藤直樹拝
Profile
 1961年東京都生まれ。北海道教育大学卒業後、信州大学で教育社会学・言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。1994年、『WIRED』日本版創刊にあたりアートディレクターに就任。1998年、アジール・デザイン(現アジール)設立。その後、数多くの雑誌、広告、書籍等を手掛ける。2003~2010年「CENTRAL EAST TOKYO」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。現在は美学校講師、多摩美術大学教授を務める。画集に『秘境の東京、そこで生えている』(東京キララ社)、著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)、『無くならない――アートとデザインの間』(晶文社)などがある。 web
1961年東京都生まれ。北海道教育大学卒業後、信州大学で教育社会学・言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。1994年、『WIRED』日本版創刊にあたりアートディレクターに就任。1998年、アジール・デザイン(現アジール)設立。その後、数多くの雑誌、広告、書籍等を手掛ける。2003~2010年「CENTRAL EAST TOKYO」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。現在は美学校講師、多摩美術大学教授を務める。画集に『秘境の東京、そこで生えている』(東京キララ社)、著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)、『無くならない――アートとデザインの間』(晶文社)などがある。 web

文化人類学者/多摩美術大学准教授/人間学工房代表。一橋大学大学院社会学研究科地球社会研究専攻博士課程修了・博士(社会学)取得。専門領域は文化人類学。アメリカおよび日本を当面のフィールドとして、「周縁」における暴力や社会的痛苦とそれに向き合う文化表現、差別と同化のメカニズム、象徴暴力や権力の問題と非暴力コミュニケーションやメディエーションなどの反暴力の試みのあり方、といったテーマに取り組む。その一方で、《人間学工房》を通じて、さまざまなつくり手たちと文化運動を展開する。著書に『残響のハーレム――ストリートに生きるムスリムたちの声』(共和国、2015年)、編著に『芸術の授業――Behind Creativity』(弘文堂、2016年)、訳書に『アップタウン・キッズ――ニューヨーク・ハーレムの公営団地とストリート文化』(大月書店、2010年)がある。『世界』(岩波書店)の2017年10月号から、連載「〈周縁〉の『小さなアメリカ』」がスタートした。 web