セクハラ被害を言語化することはむずかしい。ましてや、それが「よきことをなす人」たちの組織内で起きたときの場合は、さらに複雑な事態となる。そもそも、セクハラはなぜおきるのか。「よきことをなす」ことが、なぜときに加害につながるのか。被害を言語化するのにどうして長い時間が必要になるのか。セクハラをめぐる加害・被害対立の二極化を越え、真に当事者をサポートするための考察。
2022年4月から相談窓口設置が義務化
ハラスメント相談窓口の設置が全ての企業に義務化されることになったことはご存じだろうか。大企業はすでに2020年に義務化されているが、今年(2022年)の4月からは中小企業も義務化されることになったのである。パワハラ防止法などともいわれる労働施策総合推進法の第30条の2の第1項に以下の通り定められている。
「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」
▶参考情報:https://www.mhlw.go.jp/content/000486035.pdf
この事態によって、オーバーかもしれないが日本中の中小企業が戦々恐々としているように思う。もちろん内部の人間が窓口になるのは至難の業なので、多くは外部委託になるだろう。ネット上では社労士や弁護士のホームページ上で、間接的に委託を受けますよといった案内が増加している。また大企業からの委託を受けている団体が、さらに中小企業を対象に業務拡大を図っているのも現実である。
「そんなことありえない」という信仰
このような法的規制によって、昭和・平成にわたる職場環境は激変するだろう。パワハラはもちろん、セクハラ・マタハラ(妊娠・出産にまつわるいやがらせ)に関する相談窓口を設置しなければならないからだ。怒鳴ったり物を投げたりといった「熱血」上司は影をひそめることになり、女子社員をからかうことが当たり前ではなくなる。
しかし、「よきことをなす」ひとたちが形成する団体や集団は、このような規制とは相変わらず無縁のままである。なぜならば、自分たちが行っているのはよきことなのだから、ハラスメントといった「よくない」ことなど起こりようがないと信じているからだ。これを信仰と呼びたい。
この信仰は、よきことをなすひとたちばかりではなく、そこに参加しようとするひと、周囲の賛同者、ファン、支持者と幾重にもわたり広く共有されている。その前提となっているのは、集団内部には権力的関係などありえないという認識である。いくら外部の世界に醜いことが起きようと、よきことをなすこの団体ではそんなことはありえないのだ。
「よきことをなす」団体とは?
まっさきに挙げられるべきは宗教団体である。すでに多くの映画では描かれてきたが、近年日本でも神父による性虐待被害者(男性・女性)からの告発が相次いでいる。宗教二世という命名で、宗教をもつ親からの被害を訴えるひとたちも登場した。
また私のような心理職をはじめとする対人援助の世界もそのひとつだ。心理的・対人関係や家族関係に問題を抱えたひとたちの相談・援助活動はよきことに違いない。古代からよきことをなしてきたのは、病者を治し癒すひとたちであり、近代以降の医療もそこに加えるべきだろう。またさまざまな障がいをもつひと、性的マイノリティ、何らかの被害を受けたひと、子どもや高齢者などの社会的弱者などにかかわる福祉関連の職種およびその団体だ。また、教育の世界も含まれる。学校教育に加えて、大学のような研究機関も加える必要があるだろう。
宗教・医療・福祉・教育に加えて、組織化されていないが芸術も挙げたい。
いっけんよきこととは無縁のようだが、芸術・創造活動も入れる必要があるだろう。写真や美術などアート系と呼ばれる世界におけるセクハラ、女性差別も、近年女性たちの発信によって表面化している。
よきことを社会的正義と言い換えれば、メディアこそそのど真ん中だろう。新聞社、テレビ局といったメディアは不偏不党という社会的正義に裏打ちされているからだ。伊藤詩織さんの事件で告発されたのはテレビ局(当時)の男性だった。
そのものずばり、社会的正義を掲げた団体も加えよう。政策や制度、社会の仕組みなどを正面から変革することを目指すムーブメントや団体である。
尊敬の念が翻訳・誤訳される
今、自分の目の前にいる人への気持ち・感情・思いをどのような言葉で表現するか。これは簡単なようでむつかしい。語彙もそれほど多くなかったりする。そして、自分が発した言葉や態度が相手にどのように受け止められるか、受け止めてほしいように期待どおりに届くかどうかは確証がない。考えてみれば恐ろしいことだが、実際そういうことはよく起きる。私がこれまでかかわってきたハラスメント問題は、大学の教員によるものである。外部機関として加害者対応を委託されてお会いしたのである。具体例を述べることは個人情報保護の観点から無理だが、いくつもの事例から感じたことがある。
自分にはとうてい及ばないような素晴らしい活動をしているひとに対して抱く感情が尊敬だ。大学院生であれば、指導教官に対して尊敬の念を抱くのは当然だろう。先生の論文や著作を読んでその内容に感動し、あこがれることもあるだろう。
この「あこがれ」「尊敬」という感情・気持ちは、おそらく相手が持っている「権力」「優位性」に対してではなく、文章や論文、勇気ある活動、理念に対してである。する側の立場で読めば、これは当たり前のことだろう。そこに性的なものなどないと断言できる。
ところが、「あこがれ」「尊敬」された側の男性は、それを「好意」「関心」と翻訳しがちなのだ。嫌悪するひとや関心のない人を尊敬などしないだろうから、ここまでは許容範囲だ。ところがそれを「性的関心」と解釈する人が跡を絶たないのだ。それが誤訳であるなどと「よきことをなす」ひとたちは思いも寄らない。エレベーターに一緒に乗れば抱きつく、食事に誘い酒を飲ませる、時には「僕の女になってくれ」とか、ホテルに誘ったりする。なぜこうなるのか、どうして尊敬が性的関心と誤訳されてしまうのか。
尊敬する・されることと「欠如」の自覚
私もときどき「尊敬しています」と言われることがある。正直、これはとても居心地が悪い言葉だ。もともと距離があって遠くに居るひとなら「うれしいですね」で終わる。正直ちょっと嘘を言われているような気にもなるが。しかしその居心地の悪さの理由は、対等だった関係性が急にグラグラと崩れそうな気がするからだ。近しい関係だったのに、私が上に、相手が下にという勾配が生まれてしまう気がするのだ。
たぶん、尊敬するという気持ち・まなざしは、自分にないものを持っている相手に対して生まれるし向けられるのだ。そこには欠如の自覚がある。
欠如した存在が、それを持っている存在に向けて仰ぎ見るとき、「尊敬される側」はそれをどう感じ、どのような光景と見るのだろう。ここでひとつの典型的な例を挙げてみよう。
2人の供述
○○先生は私の論文のテーマをとても評価してくれました。ゼミではそれほど発言するほうではなかったのですが、先生はいつもゼミ生を公平に扱ってくださいました。テーマをほめられたことは支えになり、図書館で文献を調べたりすることも苦ではありませんでした。論文提出まであと1年ちょっとしかありませんので焦っていましたら、ある日先生から「焦りは禁物だよ。ゆっくり確実に仕上げていけばいいものができるよ」と言ってくださったのです。ほんとうにうれしくて、新しい文献に関して質問をするために、研究室を訪問するようになりました。偶然同じ交通機関だったので帰りもいろいろ質問しながら歩くこともありました。
Aさんはとても努力家で、学部卒業後教員をしていたのですが、辞めて僕の大学院に入りました。ゼミ生の中では目立った存在ではなかったのですが、とても熱心だったのです。ゼミが終わってから質問を何度もしてきたり、研究室の前で待ち伏せをしたりしました。年齢の違いから友人もいないようで、質問に答えながら何かと助言をしてあげました。帰る方向にいっしょなので地下鉄の駅までいっしょに歩くようになりました。距離をどんどん近づけてくるのが気になったんですが、とっても不安そうで僕が面倒見てあげないと論文が書けないんじゃないかと思ったんです。
A子さんは○○教授からエレベーターの中で抱きしめられたことを初めとして、その後3か月にわたり、人のいないところで手を握られるなどした。メールの回数も増えた。内容は「あなたは僕の指導があったからここまで論文が書けたが、研究者の世界はもっと広いから思いあがってはいけない」といった内容で、A子さんの自信を崩すものだった。教授の行為をどう断ればいいのか、もともと自信がなかった自分を認めてくれる唯一の人だから我慢すべきなのか、そう考えているうちに、ある日地下鉄の駅を降りようとすると呼吸ができなくなる気がした。心療内科では軽度のパニック障害と言われた。
同意のサインを探す
A子さんにとってあこがれ尊敬する存在である教授にとって、A子さんは自分の傍に寄ってきた不安気で自信無さげな存在だった。救ってほしいとばかりにまとわりついてくる姿は好意の表れに違いない、妻子がいることを知りながら近寄ってくるのなら覚悟の上だろう、と思った。
覚悟の上というのは、責任をとらなくていいというシグナルなのだ。いくつかのセクハラ事件として騒がれたものに共通しているのは、相手が同意した、相手も承知のうえだ、好意を持っていたという「信頼」である。それは従来疑いもないものとされてきた。男性の視点だけが流通してきたからだ。
多くの男性は、それなりに用心している。強制的であることがまずいことくらいわかっているからだ。お金を払う性産業の場以外では、レイプなどの強制的行為はしない。合意と踏んだとたんにセクハラは起きる。合意とは何か、それは相手も好意を持っており、覚悟しており、同意しているという判断だ。そのサインをずっとうかがっている。口調や態度、視線などから「同意してる」というサインを読み取ろうとしている。
非対称性が生む誤読
しかしその判断は、非対称的で上下関係においては残念ながら狂う。なぜかと言えば、彼らは権力的で上下関係にあるという自覚がないからだ。権力は、欠如している側からしか見えない。A子さんがどれほど権力性を感じているかは、教授には見えないのだ。
教授は、これまでの人生でA子さんほど自分を頼り近寄ってこられたことなどなかった。自分に好意を向けるのは覚悟の上だろうから、身体に接触することはむしろサービスだと思っていたはずだ。
私の描き方は明らかにA子さんの側に立っている。2022年にこの描写に違和感を感じるひとは少ないだろう。それだけ、される側の感じ方や困難さが共有されるようになってきたのは望ましいことに違いない。
でも同じことを1980年代に書いたらどうだったろう。A子さんの行為が非難されたに違いない。「先生がかわいそう」「誤解されるような行動をするA子さんが悪い」と。
このように、立場の違いでまったく感じ方や解釈が変わってしまうことは、詳しくは昨年刊行した拙著「アダルト・チルドレン」でも述べている。目の前に座るクライエントの立場に立つ(言い換えれば味方になる)かどうかで、話される内容の聞こえ方が変わってくるのだ。
ハラスメントや暴力と言った言葉は、そもそも受ける側(被害者)の立場に立った言葉であることは言うまでもない。まるで中立的な言葉のように使われているが、そもそもハラスメントもDV・虐待も、被害者(それを受ける側)に立った言葉として登場したのである。本連載でもこのことは繰り返し述べることになるだろう。
次回はもうひとつのキーワードから考えてみたい。
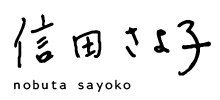 1946年生まれ。公認心理師・臨床心理士。お茶の水女子大学大学院修士課程修了。1995年に原宿カウンセリングセンター設立、現在は顧問。アルコール依存症、摂食障害、DV、子どもの虐待などに悩む本人や家族へのカウンセリングを行なってきた。『母が重くてたまらない』(春秋社)、『DVと虐待』(医学書院)、『加害者は変われるか?』(筑摩書房)、『家族と国家は共謀する』(KADOKAWA)、『アダルト・チルドレン』(学芸みらい社)、『家族と災厄』(生きのびるブックス)など、著書多数。
1946年生まれ。公認心理師・臨床心理士。お茶の水女子大学大学院修士課程修了。1995年に原宿カウンセリングセンター設立、現在は顧問。アルコール依存症、摂食障害、DV、子どもの虐待などに悩む本人や家族へのカウンセリングを行なってきた。『母が重くてたまらない』(春秋社)、『DVと虐待』(医学書院)、『加害者は変われるか?』(筑摩書房)、『家族と国家は共謀する』(KADOKAWA)、『アダルト・チルドレン』(学芸みらい社)、『家族と災厄』(生きのびるブックス)など、著書多数。

