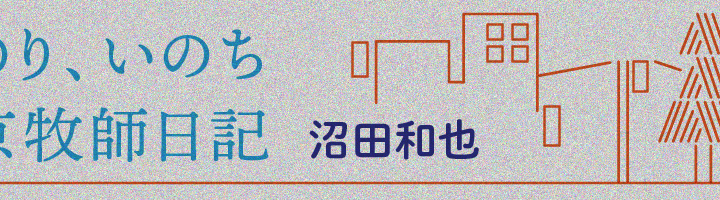教会のなかで出遭う人。教会の外で不意打ちのように出遭う人。一時は精神を病み、閉鎖病棟にも入った牧師が経験した、忘れえぬ人びととの出遭いと別れ。いま、本気で死にたいと願う、そんな人びとと対話を重ねてきた牧師が語る、人との出遭いなおしの物語。いのりは、いのちとつながっている。
死にたいと語る人に、どんなふうに応えたらよいのか。さまざまなメディアが「独りで抱え込まず、相談を」と訴える。もちろん、善意の手を差し伸べようとしているのだし、そこに示される電話なりインターネットなりに問い合わせれば、誠実に耳を傾けてくれる相談員が待っているだろう。だが、そもそも本気で死にたい人が、誰かに相談しようとするケースは少ない。誰かに相談できていたなら、死にたいと思うほど追い詰められることはなかったからである。「独りで抱え込まず、相談を」という啓蒙は無意味ではまったくないが、いちばん届いて欲しい人に届かないという歯がゆさがあることもまた事実である。
一人の人間が追い詰められ、失望し、孤立し、SNSなどで「死にたい」という一言を発するに至るまでの事情は、それぞれ異なる。幸運にも(それはあくまで支援者の側から見て、相手が死ぬ前に連絡をしてくれたという意味での「幸運」であって、それ以上の意味はない)その背景について相手が語り始めるや、そこには幾重にもかさなり、複雑に絡みあった、生い立ちや環境にまつわる苦しみの連鎖がある。わたしもしばしば、その重層性と複雑さとを前に、いったいどこから手を差し伸べたらいいのかと立ちすくむ。
イエスは孤立するなかで「死にたい」と感じている人に救いの手を差し伸べたことがあったのだろうか。というより、そもそも、イエスの前に「死にたいんです。どうにかしてください」というような人が現われただろうか。うつむく現代人の前にイエスが現れたとする。「何をしてほしいのか」とイエスがその人に言う。その人は、こう答えるのではないか。
「放っておいてくれませんか。あなたには分からない」
‟一行はエリコに来た。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒に、エリコを出られると、ティマイの子で、バルティマイという盲人が道端に座って物乞いをしていた。ナザレのイエスだと聞くと、「ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください」と叫び始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますます、「ダビデの子よ、私を憐れんでください」と叫び続けた。イエスは立ち止まって、「あの人を呼んで来なさい」と言われた。人々は盲人を呼んで言った。「安心しなさい。立ちなさい。お呼びだ。」盲人は上着を脱ぎ捨て、躍り上がってイエスのところに来た。イエスは、「何をしてほしいのか」と言われた。盲人は、「先生、また見えるようになることです」と言った。イエスは言われた。「行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。」盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。“ マルコによる福音書10章46~52節 聖書協会共同訳
イエスの時代、こんにちのような社会福祉は存在しない。身体に障害を持つ人は物乞いをして生きるほかなかった。だが、イエスと出遭ったこの目の見えない人の言動からは、「われわれは物乞いをして生きるしかない」という状況から、なにがなんでも脱出したいという強い意志がうかがえる。どんなに人々から斥けられようが、それでも人々の社会に入りたい、自分も社会のなかで生きたいという、強い意志である。拒みに拒まれた末、ついにイエスの使いから呼び出されたときには、彼は「上着を脱ぎ捨て、躍り上がって」イエスのところに来る。もはや身体が制御できないほどみなぎる喜びが、躍り上がる躍動としてこの人からあふれだす。この人とイエスとの関係を要約すれば、次の二言になろうか。
「生きたいんです!」
「だいじょうぶ、あなたは神を信頼した。必ず生きることができる」
しかし現代、わたしに「死にたい」と打ち明ける人で、こんな人はほぼいない。なにもかもに疲れ果て、もうこれ以上生きてはいたくない。宗教に意義があるのは認めるが(だから牧師であるわたしに連絡をしたともいえる)、救いまでの道のりはあまりにも遠く感じられ、自分には無縁である...そういう人ばかりである。
聖書にもエレミヤ書やヨブ記に見られるように、「生まれてこなければよかった」と詠嘆する表現が見られる。そうした言葉を読む限り、古代の人々もまさに現代のわたしたちのように苦悩していたのだと実感する。ただ、古代の社会は、死にたいと思う以前に、今よりもずっと死が身近にあった。自殺などしなくても、疫病や飢饉、戦乱などで多くの人が死んだ。平時であっても、ちょっと病をこじらせれば人は亡くなった。寝付いてから亡くなるまでの時間も短かった。聖書には「霊」という言葉がヘブライ語とギリシャ語でそれぞれרוּחַやπνεῦμα と表現されている。それらの語はいずれも、もともと風や息という意味を持っている。というのも、人が生きている状態すなわち霊が宿っている状態は、すなわち息をしていることだからだ。息を引き取ったら、人は死ぬ。つまり、息すなわち霊が身体から吹き出て、二度と吸い込まれることはなく、そのまま神のもとへと帰ったということである。古代社会に人工心肺装置は存在しなかった。だから脳死という倫理的に判断が難しい問題も、誰も想像さえしなかった。
以前、國學院大學の博物館に、居家似岩陰遺跡から出土した全身の人骨が数柱展示された。(企画展「縄文早期の居家似人骨と岩陰遺跡─居家似プロジェクトの研究成果─」)12~15歳程度や若年成人女性の遺骨が数柱、ガラスケース内に展示されていたのである。8500~8000年くらい昔の骨であるが、いずれも若いので歯並びは美しく、骨もしっかりしていた。この女性たちは早死にしたのだなと思っていたが、解説には「縄文早期人は早死であった可能性」とも記されていた。つまり、この女性たちがたまたま早死にしたのではなく、だいたいの人がこれくらいの年齢で死んでいたかもしれないのである。ひょっとすると、彼女たちは白髪の老人を見たことがなかったのではないか。岡村道夫も『縄文の生活誌』のなかで、十五歳からの平均余命は十五年から二十年、四十歳まで生きられる人はごくわずかだったと語っている。イエスが生きた時代のイスラエルの人々は、そこまで短命ではなかったとは思うが、出産時の母親や新生児の死亡率は今よりはるかに高かっただろう。高齢者だけでなく子どもや若者の死にも、人々は日常的に遭遇していたはずである。
小津安二郎の『早春』だったろうか。まだ若い会社員が肺を患い寝込んでいる。彼は同僚たちに見舞われたその日の晩、痰がのどに詰まって死ぬ。葬儀に集う人々は号泣するでもなく、淡々と友人の死を受け入れる。一方で、定年を迎えたサラリーマン(笠智衆)の言葉も印象的である。「子どもたちも独立し、自分も終わりが見えてきた」旨、彼は語るのである。彼はまだ50代半ばくらいのはずである。いや、「まだ」50代半ばという表現は、小津の世界にはふさわしくないのだろう。彼の作品世界において、若者はときにあっさり病に斃れ、50も過ぎれば人は自らの死を意識する。それも、とくに不安を覚えることもなく。この作品が公開されたのは1956年である。たしかに作品はあくまで小津の世界を表現したものであって、当時の社会そのものを映し出しているわけではない。だが、それが当時の観衆に大きな違和感を抱かせることなく受け入れられ、社会的にも評価されたのである。この時代の人々にとって、まだまだ死は近かったのではないか。そうであるなら、たった65年前であるにもかかわらず、死に対する人々の感覚は、現代を生きるわたしたちとはまったく異なっていたことになる。
キリスト教の伝道のため、アマゾンの少数部族ピダハンのもとへ家族ごと移り住んだダニエル・L・エヴェレットは、彼らの素朴な生活と、いつも笑顔で幸福そうにしている現実を前にして、次第にキリスト教の必要を疑い始める。その疑問はやがて彼自身の信仰の必要性そのものに向かう。なにより、ピダハンほかアマゾンに住む人々の、死に対する構えに彼は揺さぶられたと思われる。あるとき、彼の妻と子供がマラリアで死にかけたときのことである。彼はこう語る。
‟ピダハンたちは、西洋人が彼らの二倍近くも長生きできると見込んでいることなど、知る由もない。見込んでいるどころか、それが権利だと考えているくらいだ。アメリカ人は特に、ピダハンの禁欲をもち合わせていない。とはいえ、ピダハンが死に無頓着だというわけではない。父親は、それで子どもを救えると思ったら、何日でもボートを漕いで助けを求めに行くだろう。わたし自身、夜中に思いつめた眼をしたピダハンの男に起こされたことは何度もある。すぐにきて、病気の子どもか伴侶を見てやってくれないかと。その顔に刻まれた苦悶と心痛は、ほかの何ものにも劣らず深いものだった。だがピダハンが、必要なときには世界じゅうの誰もが自分を助けるべきであると言わんばかりにふるまったり、身内が病気か死にかけているからといって日課をおろそかにしているところを見たことがない。冷淡なのではない。それが現実なのだ。ただわたしは、まだそれを知らなかった。“ ダニエル・L・エヴェレット著、屋代通子訳『ピダハン「言語本能」を超える文化と世界観』みすず書房、85頁 傍点筆者
アメリカ人にとって、つまりエヴェレット自身にとって、自分や自分の愛する人々が長生きすることは自明であり、もしもそれが脅かされるなら、日課すなわちなにもかもを投げ出してでも「世界じゅうの誰もが自分を助けるべきである」。それが彼の世界理解であった。世界理解は、それが揺さぶられない限り、世界理解として意識にのぼることすらない。だが彼はピダハンと出遭い、それが決して自明ではないことを知る。やがて彼はキリスト教さえも自明ではないと思うに至り、信仰を捨てるのである。彼がキリスト教を捨てるに至ったことを、わたしは衝撃と共に受けとめた。他人事とは思えなかった。わたしもまた「世界じゅうの誰もが自分を助けるべきである。自分は救われて当然の存在である」という自意識を、しかも無意識の自明なる前提としているのだと気づかされたからである。そして多くの現代人の苦悩も、この前提と深く関係していると思われたのである。
「誰もが自分を助けるべきである」。それは危険時の話である。もう少し敷衍してみよう。こうならないだろうか。「誰もがとは言わないにせよ、多くの人が自分に好ましい評価をすべきである」。そんなことを口にする人はいない、口にする人はよほどの傲慢であると言われるかもしれない。もちろん誰も表立っては口にしないだろう。だが多くの人がほぼ無意識の前提として「自分は正当に評価されるべきであり、そうでない場合にはその歪みは是正されるべきである」という価値観を内面化しているのではないか。それがあってこその、「なぜ自分は評価されないのか」「なぜ自分は孤立したのか」という苦しみなのではないか。
社会ではなくあなたの心(がまえ)が問題なのだと言いたいのではない。社会構造もまた人間が構築しているものだ。しかもそれはピダハンとは比較にならないほど複雑化している。ピダハンなら、自分が生活している社会の隅から隅まで、おおむねどんなことが営まれているのかを知っているだろう。福音書の時代に生きた人々も、自分たちの住む町のこと、そこにいる人々のだいたいの雰囲気を知っていたのではないか。遠い場所で起こるニュースなど知らなくても、この世の不思議については律法学者が教えてくれるさまざまな知恵で事足りたことだろう。いっぽうで、わたしたちは自分が暮らす社会の、そのほとんどを知らない。いや、社会の全体像を知っている人など、はたしているのだろうか。世界の矛盾すべてを説明してくれる学者や聖典など、わたしたちは知らないし、求めてもいない。自分では理解も把握もとうてい不可能な、この複雑な社会のなかで、わたしたちは事故や病気に遭遇しない限り、かつてないほどの長命を生きなければならない。そのような社会に、なんの歪みも矛盾もないということはありえない。わたしたちは全体像の分からない複雑なものに絡みとられ、身動きができずに苦しむ。死はそうした複雑さをとつぜん断ち切るかのように、不気味なものとして、あるいは理想として、苦悩する人の前にその姿を顕す。
ピダハンの人々は、死について詮索しない。彼らには創世神話がなく、来世への明確な信仰もない。彼らの平均寿命はおおむね40代であるという。子どもか大人かにかかわらず、マラリアで命を落とす人も多い。そんな彼らは、死を誰にでも訪れる、避けられないものと考えている。一方でイエスの時代を顧みれば、そこには精緻な信仰世界がある。だが、死が日常的なものであるという点では、ピダハンと大きくは変わらない。古代イスラエルの人々は、自分たちに死がとても近いからこそ、死の向こうにある救済をありありと想像できたのだろう。だが、教会に「死にたい」と連絡してくる人にとって────「死にたい」という言葉にもかかわらず────死は遠いし、死後の世界も遠い。あまりにも遠すぎて、死も死後の世界も、まるで存在しないかのごとくである。ときおり「死にたい」ではなく「消えたい」と語る人もいる。死にまつわる肉体の具体的イメージがそこにはない。モニターから画像が消えるように、ふっと電源が落ちる語感である。他人の死を看取る経験が少ない人にとって、自分の肉体の死を想像することは難しいのかもしれない。
わたしは牧師として、悩み苦しむ人と向きあっている。牧師の拠り所は、なんといっても聖書である。わたしの目の前で苦しむこの人を、神が見捨てるはずがない。もしもこの人の目の前にイエス・キリストがいたら、慰めに満ちた言葉をかけるに違いない────そこまで考えて、いつも立ち止まる。イエスの目の前に、長命を自明として「早く死にたい」と嘆く、そんな人はいただろうかと。イエスのもとにはむしろ、生きたい、だから救ってほしい、そういう人が殺到したのではないかと。もしもそうであるなら、わたしはイエスの言葉をこの目の前の人に対して、どのように適用できるのだろうかと。
だが、このように悩むとき、まさにイエス・キリストは、問いかけるわたしの前に立ち現れてくるのである。このまま蛇の生殺しのように生きるのはたくさんだ、もう死にたい...そのように願う、まさに現代に生きているこの人に、イエスはなんと答えるのか。そのように問うとき、わたしはイエスと切り結ぶ。わたしはイエス・キリストという真空に浮かんだ単語を信仰しているのではない。まさにこの問い、わたしが出遭う他人との関係において生じる、この問いのなかに含まれる主語「イエス」こそ、わたしが出遭い、信頼している相手なのだ。
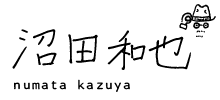 日本基督教団 牧師。1972年、兵庫県神戸市生まれ。高校を中退、引きこもる。その後、大検を経て受験浪人中、1995年、灘区にて阪神淡路大震災に遭遇。かろうじて入った大学も中退、再び引きこもるなどの紆余曲折を経た1998年、関西学院大学神学部に入学。2004年、同大学院神学研究科博士課程前期課程修了。そして伝道者の道へ。しかし2015年の初夏、職場でトラブルを起こし、精神科病院の閉鎖病棟に入院する。現在は東京都の小さな教会で再び牧師をしている。
日本基督教団 牧師。1972年、兵庫県神戸市生まれ。高校を中退、引きこもる。その後、大検を経て受験浪人中、1995年、灘区にて阪神淡路大震災に遭遇。かろうじて入った大学も中退、再び引きこもるなどの紆余曲折を経た1998年、関西学院大学神学部に入学。2004年、同大学院神学研究科博士課程前期課程修了。そして伝道者の道へ。しかし2015年の初夏、職場でトラブルを起こし、精神科病院の閉鎖病棟に入院する。現在は東京都の小さな教会で再び牧師をしている。
twitter