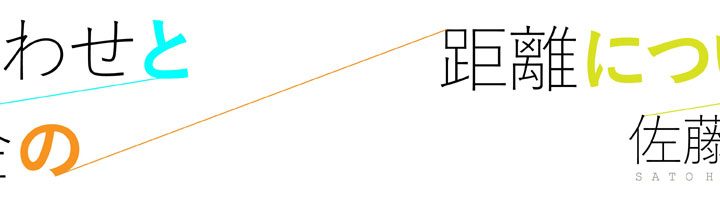交際費は家計においていつもリストラの真っ先にあげられるもののひとつだ。
余計なものは一切使いたくないのだろう。そうしたくてはならない家庭があるのもよく分かる。しかし、そうでない方たちまで、祝儀や香典は平均に合わせる。中元や歳暮は虚礼だからと絞り込む。実際は中元歳暮は虚礼のところだけに絞り込む。お金は全て自分たちのためだけに使うもの。そういうことなのだろう。
ところがこの数年で気がついた。私はお年玉や中元、歳暮を贈ることが少し待ちどうしいのだ。
若いころの中元や歳暮は、ギラギラしたものだった。まさに虚礼である。仕事の関係先への夏冬の挨拶はフリーランスで働くものにしては、「ひとつこれからも、よろしくお願いいたしやす」という気持ちで人事権を握る人に送ってた。今でもそういう仕事絡みの虚礼の贈答品というのは少なくないだろう。
子どもの頃にも記憶がある。サラリーマンだった死んだ父に歳暮や中元が山ほどきた。営業や企画部にいる時はそれこそ山ほど届けられた。それが閑職になったらなくなった。子どもながらにそういうものかと良く覚えている。
今でも贈答品の多くは仕事先に送る。しかし、もう10年以上前に仕事の関係がなくなった人が少なくない。退職もしてしまった人もいる。つまり、仕事の利害関係のない仕事先の人に送っている。仕事関係が無くなった時は、贈るのをやめるひとつの良いタイミングだ。実際にそうして送るのを辞めた方も多い。贈答時期になると、百貨店から今まで自分が贈った人のリストがカタログと共に送付されてくる。そして、贈答の品を選ぶ前に、そのリストから、送る人、送らないけれどリストには残す人、リストから削除してしまう人を遠別するのだ。
その時に思うのだ。この人、どうしよう……。
もう仕事の関係は無いなと思っても、贈り続けたいと思う人がいる。いま、10人ほどだ。送ると礼状が来て、「もう仕事もしてないし退職もしてるから送らなくていいですよ」と気づかってくれる。しかし、また送る。
仕事の関係は多くでイーブンだ。求められた仕事をしてそれ相応の報酬をもらう。必要がなくなったら終る。もちろんそういう仕事がほとんどで、それでいいしそうやって食べて来た。しかし、そういうイーブンの仕事の関係になれるまでには過程があった。
きっとこいつは何かできるのではないか? とチャンスをくれた人がいる。新しい仕事にはなかなか慣れずに迷惑もかけたのに、成長するのを待ってくれた人がいる。つまり、この人と出会わなかったら、いまこうしていられないという人がいるのだ。若く未熟な自分をガマンして使ってくれた。使い続けてくれた。当時のことを思い出すと頭が下がり、心が温かくなる。果して、いま自分は若い人たちにあんな寛容な態度で接しているだろうかと思う。
もちろん、長いこと共に仕事をして心を通わしていると思ったのに、しっぺ返しをされて辛い思いもたくさんしてきた。だからこそ、いま送っている人たちへは感謝の気持ちしかない。
実はひとり、送れなくて気になっている人がいる。ある大手出版社のMさんだ。Mさんとの出会いは偶然だった。30代も半ばにある映画に出演することになった。撮影に参加するのは2週間。海外ロケだったので、昼夜問わず現場にいることになる。撮影初日に監督から毎日の撮影日誌を書けと命じられた。帰国するときに、電話番号と名前を渡され、この人に会いにいき日誌を本にしてくれと頼みにいけと言われたのだ。映画のプロモーションに使えると思ったのだろう。それがMさんと出会ったきっかけだ。出版社の面談室で1時間ほど話して、別れ際に「日誌は本にはできませんが、佐藤さんとはまた話をしましょう」と言ってもらった。
放送の仕事ばかりしていて、原稿を書く仕事をしたいと思っていたので嬉しかった。言葉通り、Mさんは、それからいろんなところに食事や呑みに連れて行ってくれた。3ヶ月に1度くらい、フレンチから文壇バーまで何回もご馳走になった。2年近く経ったころにやっと、ひとつ原稿を書いてみますかと言ってくれた。月刊誌のルポの仕事だった。取材をして書く、原稿用紙20枚ほどの仕事だった。
何とか書いてほっとしていたら、半日もしないうちに、赤ペンが入った原稿が戻されてくる。
テーマの設定から、取材対象に関すること、文章の書き方に関しても、文体やプロが原稿を書くときの作法まで徹底的にしごかれた。私の書いた文章は掲載できるレベルではなかったのだ。だから、20枚の原稿を仕上げるのに、時に100枚以上も書かなくてはならなかった。仕事で海外出張が入っていても容赦はなかった。出発前に出した原稿は、海外のホテルに着くと直しを求めるメモと共にファクスされていた。
30代後半のころは仕事もめっぽう忙しかったので、このMさんの原稿の仕事が入ると眠る時間が取れなくなった。ふらふらになり何回も放り投げようかと思った。しかし、Mさんのダメ出しが知的で本質を付いている。それが自分もすとんと理解できる。かつ温厚なのだ。感情的になったことは1度もない、だから放り投げることはできなかった。
時には脳科学の最前線について書けといわれ、日本を代表する脳科学者へのロングインタビューをさせてもらうこともあった。準備のための本を何冊も必死に読みヘトヘトになって仕事をした。厳しくしてもらったからか、掲載された記事は読者の人気投票で名うてのジャーナリストの書く文章と毎回トップを争っていた。ボツになったのは、故大島渚監督へのロングインタビューだけだ。
Mさんが月刊誌の編集部を離れる時に、1度だけ六本木のイタリアンでご馳走させてもらった。もちろんその後も、中元、歳暮を送っていたのだが数年後に転居して宛先不明で送れなくなってしまった。どうも、もともとの文芸の世界に戻ったようで、文芸誌の編集長もされたようだ。
Mさんのおかげで何とか文章を書けるようになった。技術を伝授してもらった。Mさんだけでない。そんな忘れられない人たちに支えられた自分の人生が愛しきものに思える。
そんな温かい気持ちにさせてくれる人が10人以上もいる自分は幸せものだと年に2度確認する。それが歳暮と中元の時期なのだ。
それが、まったく仕事の関係もない人からいろいろと頂き物をするようになった。例えば、長年やっていたラジオのリスナーの人たちとSNSを通じて交流が始まり、年に2~3度、経済やマネーの勉強会を開く。その人たちからいろいろと送ってもらう。
地元のおいしい酒、帰省先のパッションフルーツ、旅先で見つけた珍しいもの、旬の果物、実家の庭のゆず、家庭菜園で取れたジャガイモ、年に2回お茶を下さるかたや、ラジオショッピングを聞いていたら、佐藤さんにもどうかと思って送ってくれる人もいる。仕事の関係がまったくないのに頂く。死んだ両親にこんなのもらったよと話しかけてから頂く。そして、こんなに良くしてもらうのにふさわしい人物でないと思うと、そうならなくちゃいけないんだと気持ちを引き締める。
気持ちの通うことは、人生でどれだけ幸せなことなのだろう。
この数年はお年玉をほとんど関係のない若い人に渡すようになった。岡山から30を過ぎて単身出て来て美容院で懸命に働く青年、シャンプー担当の中年の女性。でかい身体の私を一生懸命、揉み解してくれる整体の先生。若いころから通っていた新宿ゴールデン街の思い出の店、店長が亡くなり閉店かと思ったら青年が店を守ってくれている。近くの居酒屋で働く福島出身の大学生の若者と大阪出身の役者志願の青年は、少ない人数で忙しく働いているのにいつも笑顔で迎えてくれる。そして、お互いに助け合っているところが見ていて気持ちいい。
そういう誠実に働く若い人の姿は自分の背筋をぴんとさせてくれる。しかし、バブルの時代だった私の若いころと比べると、そういう仕事を世間はきちんと評価していないような気がする。だから、12月になると銀行で5千円札や1万円札の新券をもらっておき、ポチ袋に入れてさっと渡す。「俺はこの1年の仕事ぶりを見てたぜ、ご苦労さん、ありがとう」そんな気持ちだが、実際は「これ、少ないけど、気持ちだけ」って言って渡す。みな一応に私の出すポチ袋に表情を変える。こちらが驚くほどとても嬉しそうな顔をしてくれる。ああ、気持ちが伝わって良かったと私の方が嬉しくなる瞬間だ。
多くの人が昔は良かった、薄情な時代になったという。私はそうは思わない。薄情な人はいるが、それはいつの時代もいるものだ。いや、確かに少し増えたのかもしれない。それなら、できる範囲で世の中を明るく暖かいものにする側に廻ろうと思うのだ。自分の若い時に受けた恩義をいまの人たちに伝えていきたい。
時にモノやお金のやり取りは、
Back Number
- 第12回 いざという時のためにお金を使うか、いざという時が来る前にお金を使うか。それが問題だ。
- 第11回 僕が特上のにぎり寿司を食べられない理由。
- 第10回 ダウントンアビーのようなお屋敷ではないけれど
- 第9回 60歳を過ぎたら、自分の好みで洋服を買うのを辞めてみよう。
- 第8回 中年以降のパソコン、スマホの正しい買い方は人まねです。
- 第7回 オデッセウスと編み物
- 第6回 お金は自分や家族のためだけに使わない方が幸せになる
- 第5回 海外パック旅行で見えてくるもの 後編
- 第4回 海外パック旅行で見えてくるもの 前編
- 第3回 老後破産教に入信していませんか?
- 第2回 「おすそわけ」は廻りも自分も幸せにする。
- 第1回 前書きにかえて、10円玉の重み
Profile
 経済評論家。1961年生まれ。慶應大学商学部卒業、東京大学社会情報研究所教育部修了。大学卒業後、外資系銀行でデリヴァティブを担当。東京、ニューヨーク、ロンドンを経験。退職後、金融誌記者、国連難民高等弁務官本部でのボランティア(湾岸戦争プロジェクト)経営コンサルタント会社などを経て独立、現職に至る。『年収300万~700万円 普通の人が老後まで安心して暮らすためのお金の話』(扶桑社)、『普通の人が、ケチケチしないで毎年100万円貯まる59のこと』(扶桑社)、『お金をかけずに 海外パックツアーをもっと楽しむ本』(PHP)、『アジア自由旅行』(小学館/島田雅彦氏との共著)『日経新聞を「早読み」する技術』(PHP)など、多数の著作がある。 Facebook
経済評論家。1961年生まれ。慶應大学商学部卒業、東京大学社会情報研究所教育部修了。大学卒業後、外資系銀行でデリヴァティブを担当。東京、ニューヨーク、ロンドンを経験。退職後、金融誌記者、国連難民高等弁務官本部でのボランティア(湾岸戦争プロジェクト)経営コンサルタント会社などを経て独立、現職に至る。『年収300万~700万円 普通の人が老後まで安心して暮らすためのお金の話』(扶桑社)、『普通の人が、ケチケチしないで毎年100万円貯まる59のこと』(扶桑社)、『お金をかけずに 海外パックツアーをもっと楽しむ本』(PHP)、『アジア自由旅行』(小学館/島田雅彦氏との共著)『日経新聞を「早読み」する技術』(PHP)など、多数の著作がある。 Facebook