テレビのバラエティ番組の定番のひとつに「お金持ち」の豪邸訪問がある。タレントから事業家などさまざまなお金持ちの邸宅を尋ね、リポーターが取り上げる。
ある番組で美容業界で成功した社長の家を紹介していた。広いリビングに掛かっている現代絵画を指差して「何か、高そうな絵ですね」と質問する。
ニューヨークの著名な現代画家の「油絵」が映っていた。実は私もこのアーチストの「版画」なら一枚持っているので、すぐにピンときた。
美術番組ではないけれど、誰が描いた作品なのかとか、この絵のどこが気に入って買ったのかとか、作品そのものについて触れたり、尋ねたりすることは一切なく、お決まりの質問をする。
「おいくらだったんですか?」
下品な質問だと思う。けれども、視聴者の興味も実はそこにあるものだ。
質問された方も、「1000万円だったかな、安いもんですよ。私、金持ちなんで」と言いたげな顔をしながら、1000万を別な表現に置き換える。例えば、「ちょっとしたベンツが買えるくらいかな」とほんの少しだけぼやかしてみせる。ただし、表情は俺、大金持ちなんで、でへへ、というままだ。
リポーターはその金額にわざとらしく大げさに驚いてみせる。
「すごいですね~」
絵画だけでなく、置いてある家具や、使っているティーカップ、着ている洋服やもちろん宝石など、とにかく高そうなものの値段を質問する。
そういう自称成功者に対して、多くの視聴者は羨望のまなざしで画面を見る。
そして、思う。「この人はいったいお金をいくら持っているのかしら?」
しかし、「あんなに、お金があれば、何の不自由もないのよね、羨ましいわ」とは、あまり言わない。それは、思うだけだ。口に出して言うのは、どちらかというと批判の言葉が多い。下品だ、成金趣味だ、金の使い方を知らないなどと言うものだ。半分、これ嫉妬である。
誰でもお金があることは羨ましい。しかし、この自称成功者は金を稼ぐ事に成功しただけであることも年齢を重ねたものなら知っている。
テレビに出てくる金満生活をする人たちをそれほど幸せそうだとは思えないことも多い。私などは、この人はお金を数えきれないくらい手にいれることはできたけれども、果して同じくらい幸せは手にしているのかなと思ってしまう。
むしろ、お金を稼ぐ事に一生懸命になって、昔は持っていた幸せなものを捨ててしまったのではないかと思うくらいだ。
番組では個人的な資産を築く事に成功した社長とその会社で働く若者の生活を対比してみせた。これほど豪華な生活をするのは会社の従業員の目標になるためだとも言った。すごい理屈である。なぜなら、美容師の生活はとても厳しい。その会社で働く従業員に、月にあと1万円、いや5000円でも給料を上げてやれば、どれほど感謝されるだろうにと私は思うのだ。まだファミリーのような会社なのだ。何で映画「男はつらいよ」のタコ社長のように、従業員の給料を払うために必死に働く社長になれないのかと思ってしまうのだ。
おいしいお米を丁寧に炊いたごはんは、どんな日本人をも幸せにする。しかし、私などはおかわりをすることはあってもそれ以上は要らない。山ほど炊いてもらってもムダにするだけだ。おいしいからといって、食べきれないほど欲しいとは誰も思わない。
先日ふるさと納税の返礼品が届いた。高級な国産の豚肉4キロだ。届いた肉の量を見てびっくりしてしまった。これは食べきれない。冷凍にしておくにしてもムダにしてしまう。日本の畜産農家が汗水垂らして作ってくれた。そして、命あった肉をムダにしてしまう。困ってしまって、どうしようか考えた。
そして、若い放送人だけれどフリーランスで収入が不安定で子どもを授かったばかりの知り合いと、小さな事業を立ち上げたばかりの長岡出身の青年、いつも笑顔のトレーナーの3人に連絡を取った。
うまい豚肉1キロもらってくれないか?
「すごく助かります」「月末まであと3千円しかなくてどうしのごうか悩んでいたんですよ」「肉ならいくらでも食いたいです。またいつでも言って下さい」数時間で必要な人のところにうまく収まった。そして、3人から、ありがとう、と言ってもらって、私はとても幸せな気分になった。
そして、思い出した。ああ、自分はお裾分けで幸せになったんだと思ったのだ。
子どものころの食卓には、よくお裾分けのおかずがのっていた。多く作っても少しでも手間は同じ。自分の家で食べきれない分をちょっとした器に入れて、お隣に持って行く。お隣からもらう。
勝手口から「お口に合うかしら」などと言って持って来るのだが、抜群に美味しい。
そして、料理のコツをお互いに情報交換したりする。お互いが幸せになり、口だけでない近所の絆ができて行く。
人が生きて行くのに大切な食べるという行為に関して、無制限に求めるということを私たちはしない。むしろ、頃合いを越えて、持っているものがムダになりそうだったら、それを誰か必要な人に分け与えたいと思うものだ。洋服だって、家具だって、多くのものが同じである。無尽蔵に欲しいとはあまり思わない。
ところが、どうだろう。お金だけはそうでないのだ。もっと、もっとと思ってしまう。お金に対する欲望はとまるところをしらない。とくに21世紀になる少し前から世界を席巻している、グローバリズム経済の洗礼を私たちの日本社会も受けて、もっと欲しい、もっとお金があったらいいのにと思うようになってきた。お金に対する無尽蔵の欲望をもつことは果して幸せなのか立ち止まって考えることが無くなってしまった。むしろ、もってるお金、つまり資産に比例して、幸福も増して行くと思う人たちも増えてしまった。
無尽蔵の欲望。私たち日本人の本来の美徳はそこにない。少なすぎては困るが多すぎても持て余す。ちょうどいい頃合いがいいのだと、少し遠慮する。欲望をコントロールする。それを良しとしてきたように思う。それは、金に対しても同じはずだ。もちろん、グローバリズムになる前からも、金に対する欲望に歯止めがない人もいただろう。しかし、我々は、それを守銭奴といって蔑んでいたものだ。
お金とはいい距離感が必要なのだ。それを意識していないと、もっと金が欲しいという欲望に私たちの心はすぐに絡めとられてしまう。
バラエティ番組で見たお金持ちに対して、私たちは羨ましいという思いと、何かこういうのは嫌だなという二律背反する気持ちを意識して行きたい。
もっとも、大金持ちの人は、この文章を読んで、けっ、
毎日を普通に生きているはずなのに、お金に心を絡めとられている人がいる。その一例が「老後破産」教に入信した人たちだ。老後のことを、お金を準備することだけに奔走する人たちだ。
次回はとっても危険な「老後破産」教についてお話したい。

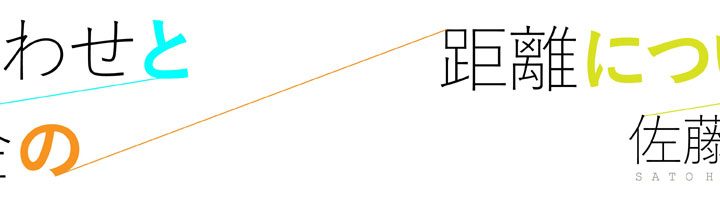
 経済評論家。1961年生まれ。慶應大学商学部卒業、東京大学社会情報研究所教育部修了。大学卒業後、外資系銀行でデリヴァティブを担当。東京、ニューヨーク、ロンドンを経験。退職後、金融誌記者、国連難民高等弁務官本部でのボランティア(湾岸戦争プロジェクト)経営コンサルタント会社などを経て独立、現職に至る。『年収300万~700万円 普通の人が老後まで安心して暮らすためのお金の話』(扶桑社)、『普通の人が、ケチケチしないで毎年100万円貯まる59のこと』(扶桑社)、『お金をかけずに 海外パックツアーをもっと楽しむ本』(PHP)、『アジア自由旅行』(小学館/島田雅彦氏との共著)『日経新聞を「早読み」する技術』(PHP)など、多数の著作がある。
経済評論家。1961年生まれ。慶應大学商学部卒業、東京大学社会情報研究所教育部修了。大学卒業後、外資系銀行でデリヴァティブを担当。東京、ニューヨーク、ロンドンを経験。退職後、金融誌記者、国連難民高等弁務官本部でのボランティア(湾岸戦争プロジェクト)経営コンサルタント会社などを経て独立、現職に至る。『年収300万~700万円 普通の人が老後まで安心して暮らすためのお金の話』(扶桑社)、『普通の人が、ケチケチしないで毎年100万円貯まる59のこと』(扶桑社)、『お金をかけずに 海外パックツアーをもっと楽しむ本』(PHP)、『アジア自由旅行』(小学館/島田雅彦氏との共著)『日経新聞を「早読み」する技術』(PHP)など、多数の著作がある。