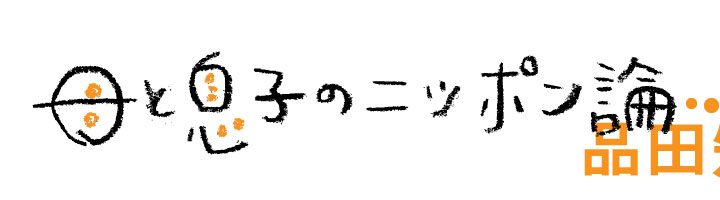母となった人の多くが「息子が可愛くてしょうがない」と口にする。手がかかればかかるほど、可愛いという。女性たちは息子のために、何を置いても尽くそうとする。それは恋人に対するよりも粘っこくて重たい心かもしれない。息子たちは、そんな母について、何を思っているのだろうか。そのような母に育てられた息子と、娘たちはどのように関係を作っているのだろうか。母と息子の関係が、ニッポンにおける人間関係の核を作り、社会を覆っているのではないのか。子育てを終えた社会学者が、母と息子の関係から、少子化や引きこもりや非婚化や、日本に横たわる多くの問題について考える。
NHK大河ドラマ「直虎」(2017年11月12日放送)をつけたら、徳川家康が「おおかたさま」つまりは母に「おイエをまもるために、息子を斬れ」と一喝され、自分の嫡男である信康を自害へと追いやる行動に移す場面がでてきました。やれやれまた、母には頭が上がらないって話するのか。史実がどうだったかはともかく、それで人に納得してもらうストーリーに仕上げていることに驚きます。奇妙じゃありませんか。権力を手中に収めている最高権力者でさえ、母には頭が上がらないという構図に落としているのですから。おそらく、プロデュースする側は女性の地位を高く描いているつもりなのでしょう。大河ドラマにはいつも「おのこ(男子)」を産み、立派に育てることがいかに地位確保のために大事であったのか強調されるシーンがでてきます。そして、必ず母は強し。母である瀬名が信康を命をかけて守ろうとするシーンで涙を誘う。これでもかこれでもかと、語られている母と息子の濃い関係は、正直いって飽き飽きするほどニッポン的人間関係を、いまも増幅させています。
地域の代表者は男性に
ところで、公の場における女性の地位はいまや国際的に見るなら、異次元のレベルに低く保たれているニッポン。10月の選挙で微増したものの、国会議員の女性比率は10.1%で世界193カ国中160位。もちろん先進国では最下位をキープ中です。日本より下位にランクされている国をみると、イスラム圏の国に混じって、タイとかスリランカなどの仏教国やトンガとかハイチなどの島嶼国が目立ちます。意外に元気で働きものの女性も多い国ではありませんか。働いているかどうかと女性の地位は関係するとは限りません。つい高度成長期前の日本では自営業の妻として女性の半数は働いていたのですから。
いまでこそ女性がPTA会長になることもあるようですが、つい最近の内閣府の調査結果でも、女性会長の割合は12.5%しかいません。自治会長になると4.9%にとどまっているのです。女性を地域の顔にすることが、ふつうの市民にとって、とても抵抗があるとわかる数字です。「女性が地域活動のリーダーになるために必要なこと」を聞くと「男性の抵抗感をなくすこと」が52.1%と最も高くなっていました。そう答える人は男性に多いようです((平成28年度男女共同参画社会に関する世論調査(http://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-danjo/2-2.html)))。日頃の活動はすべて女性が支えているとすらいえるPTA活動で、根回しや意思決定も実質的に女性が仕切りながら、やってくれる人がいれば顔としては男性を会長にすえる。実際には、最後にかぶせられる帽子のような存在でもよいのです。副会長以下の役職者で支えるから実質的にかかわらなくてもいい、と頼み込んだりもして探すこともあります。女性に白羽の矢があたることがありますが、その場合は、高学歴であったり社会的に高い地位についているなど、外から見て会長職にふさわしい、わかりやすい基準が求められます。この実質的に仕事をすることと切り離して代表には男性という顔をたてるという組み合わせは、いわゆる理想的な奥さんのいる家庭の様子を、地域集団において再現しているともいえます。どんなに家のなかのことを妻が取り仕切っていても、ここぞというときには「主人を立てる」ことが円満な家庭を築くコツであるとされ、堂々と「夫操縦法」という言葉が出てくる。「操縦したい/操縦されたい」の組み合わせカップルはいまも続々誕生中でしょう。
「かあちゃん」は怖いもの
うちの「かあちゃん」に怒られる、と男性が言うとき、「かあちゃん」は妻であることが多いでしょう。はっきり「俺、異常なマザコン」と語っている北野武は、好きになった女性は母のように自分を包んでくれる人、なのだと言っています。そして、かあちゃんは同時にビシビシと時には力づくで鍛える人として、語られています。ニッポン人にとって、かあちゃんが母を意味すると同時に妻にも使える用語になっている理由は、まさに機能的には入れ替えてもかまわない等価なものであるからでしょう。
サザエさん一家の権力関係を漫画から丹念にひろうと、一家の主婦であるフネさんが主人である波平さんに説教する場面などが出てきます。描かれ方から推定するに、夫が妻に、つまりかあちゃんに頭があがらない家族として描かれているわけです。時代的にはサザエさんより少し後、高度成長期の家族を色濃く映し出すアニメ、ドラえもんにでてくるジャイアンのかあちゃんは何かと子どもを殴っている場面も登場しますし、のび太の家もお母さんがお父さんよりも、強そうに描かれています。ジャイアンのかあちゃんが剛田雑貨店を営んでいるほかは、みな専業主婦の設定なのに、働いていようといまいと、家庭のなかの母の地位は高く描かれます。より現代に近づくと、クレヨンしんちゃんの母みさえも、息子に振り回されつつ旦那を尻に敷いている強い妻となっています。この時代になると、家事はもはや「妻が夫にやってあげるもの」になっていますが...。ニッポンのファミリー向け人気漫画では、常に家庭内での地位に関して女性が強そうに描かれてきたといえそうです。
ちなみに、学術的にも夫と妻の勢力関係についての研究は蓄積があります。夫婦の関係性は、役割をどう分業するかという側面とともに、何かを決める意思決定を最終的にどちらがするのかといった側面からとらえる方法などがあります。いまのところ、日本の夫婦のどちらの地位が高いのかという結論ははっきりしていないようで、どちらかというと、家の中ではある程度平等であり、近年はさらに平等である方向に向かっているといわれます((松信ひろみ編,2016,近代家族のゆらぎと新しい家族のかたち[第2版],八千代出版.))ですから、「かあちゃんに頭があがらない」といういいまわしがあるからといって、その実質がどうなのかはもちろん疑っておかなくてはなりません。それにしても、ことさらに「オレは恐妻家」とか、「奥さんの尻に敷かれている」とか、喜んで口に出す男性が世間に相当多数いる社会であることは疑いようがありません。
グレートマザーへの畏れ
「かあちゃん」が怖いという心性のある社会で、なぜ女性の社会的地位が低いのでしょう。「地域の顔としては女性をおくには抵抗がある」、というふうに私的空間と公的空間で女性の地位が反転していく手がかりを、ユング派の心理学で用いられているグレートマザー(太母)という元型(アーキタイプ)から考えてみたいと思います。
グレートマザーとは全人類に共通して存在する地母神であり、個人の母親という概念を超えて人々が共通して無意識に持っているものだとされています。河合隼雄の解説によれば、人格化された地母神は、穀物の生成や、あるいは万物の生成をつかさどり、また逆に、死への神として、すべてのもの飲みつくしてしまうような属性を持っています((河合隼雄,ユングと心理療法,1999,講談社+α文庫.))。河合氏は、日本に多いとされる学校恐怖症の治療に向き合うなかで、グレートマザーに巻き込まれる恐怖にさいなまれていると解釈できる少年の夢を紹介しています。ユング派の心理学では、夢は無意識を見せるものとされ、大切に向き合います。学校恐怖症の男の子は、何もかもを飲み込んでしまう子宮をイメージさせる「肉の渦」にまきこまれそうになり、恐ろしくなって目を覚ました、という事例が紹介されています。
西洋の枠組みでとらえられないニッポン的な自我のありようを、精神分析学は模索しつづけています。河合隼雄は日本を母性社会ととらえており、日本社会は西洋のように自我の確立をめざしてこなかったと述べています。自我の確立にとって危険な感情である「甘え」を保存しつつ発展した文化として、ニッポン社会をとらえているのです。河合によると西洋のような「自我の確立をめざす文化においては、新生児の体験する「甘え」の感情をできるだけ早く消し去ることに強調点がおかれる」はずだといいます。一方、日本でそのような子育ては人気がでませんでした。例えば、子どもを幼い頃から別室で寝かせる西洋とは違い、3歳以下の日本の子どもの別室就寝は1%以下でしかありません。このように西洋と東洋で違う自我の有りようについて、河合氏は西洋的自我の確立の方向に治療を方向づけるべきかどうか迷っていると、心情を正直に吐露しました。西洋の心理学者が分析家たちが「母なるもの」のポジティブな面を見直そうとしている潮流とも出会ったからでしょう。ある意味とてもニッポン的な曖昧な表現である、「母なるものの完全否定によって自我を確立させたくない」、という河合氏の意向は社会の奥底で大事に守られ、再び現代に息を吹き返してきたと思います。ただしそれは、グレートマザーへの畏れを抱いたまま成長をした人々が、大人成員として振る舞い続けているということを、同時に意味します。このような日本人的な自我を持つ男性が、公的空間に出たらどうするでしょう。無意識に女性を畏れている男性集団は女性を自分より高い地位につけることに抵抗するのではないでしょうか。
阿闍世(あじゃせ)コンプレックス
日本型母性社会の深層心理から理解するためには、フロイトのエディプスコンプレックスに対置する阿闍世コンプレックスが手掛かりになるでしょう。古澤平作によって独創されたこの概念は、1932年にフロイトに提示されたものの長らく日があたりませんでした。1970世界にも発信されていった内容は、仏典の「涅槃経」からの改作を経た物語として知られています。阿闍世の物語はその母韋堤希(いだいけ)が自らの容色の衰えとともに、夫の愛が薄れていく不安から王子をみごもろうと思いたち、予言者に相談するところから始まります。仙人の生まれ変わりが子どもになると聞き及び、早く子どもを授かりたいという身勝手から仙人を殺してみごもった王子が阿闍世です。長ずるにおよんでそれを知った阿闍世は殺意を抱き、母を殺害しようとした結果、罪悪感から悪病に苦しむことになります。自分を殺害しようとしたにもかかわらず、その悪病にかかった息子である王子をゆるし、息子は献身的な看病をする母親の苦悩を認めて母を許す、愛と憎しみの悲劇です。この物語は3つの心理的構成要素からなっていると解説されています((小此木啓吾,1982,日本人の阿闍世コンプレックス,中公文庫.))。1つ目は一体感=甘えと相互性、2つ目は怨みとマゾヒズム、3つ目はゆるしと罪意識、となります。
エディプスコンプレックスでは、自分の父を殺し母を妻とするという運命を予言されていたエディプスが、その神託から逃れることができずに、予言どおりに2つの大罪を犯してしまい、その責任を負うためにみずから目を抉り放浪の旅に出るという悲劇です。つまり、運命的であろうと罰からは逃れられないというわけですが、阿闍世コンプレックスではいってみれば、とばっちりを受けたのは仙人でしょう。「跡継ぎの子ができない」と妻にプレッシャーをかけている王、つまり父は物語の外にいる希薄な存在となって、家族の関係者は誰も罪を贖ってはいません。このような自我のありようが、公的な立場にあっても最後に深々と頭をさげて謝ったり土下座したりすることでゆるしを乞い、罪を許すという身内関係が受け入れられやすい社会をもたらしていると、小此木は指摘します。
ところで、家族人類学者のエマニュエル・トッド氏は潜在的な「母殺し」の欲望が転化する歴史的事象の一つとして魔女狩りを取り上げています。魔女狩りが頻繁に行われた地域は、母親の家庭内地位が高くかつ不安定でもある権威主義家族の優勢な場所だという現象がみられるのです。老齢の女性、つまり母親の象徴として魔女に潜在的な女性への蔑視が噴出するというわけです。ニッポン人の深層心理構造において、子どもがいようといまいと成人女性が常に潜在的に母へと読み替えられていく力学が働いているとするなら、男性は幼く可愛いロリコン的に扱える女性への愛は成就しても、大人の女性への畏れは消えず対等に付き合えないのではないでしょうか。女性への関係が、包容力のある母にかわる対象として依存するか、小児愛的に一方的に可愛がるのか2択になっていたら、対等な関係を好む大人の女性は恋愛対象になりえません。献身的な日本の母親は娘を自立した存在へと育てながら、息子は依存させる存在として可愛がっているのですから、ミスマッチの増加と恋愛の不成立はなお存続しているように思われます。
女性蔑視を掲げる象徴的な集団
菅野完氏は安倍政権を支える右翼組織「日本会議」の行動原理を「左翼嫌い」と「女性蔑視(ミソジニー)」であると指摘しました((ダイヤモンド・オンライン編集部,2016,安倍政権を支える右翼組織「日本会議」の行動原理(上),ダイヤモンドオンライン( http://diamond.jp/articles/-/91567?page=3)))。具体的には、憲法24条改正、夫婦別姓反対、男女共同参画事業反対などの項目が掲げられ、従軍慰安婦問題にもつながっている述べています。つい先ごろ、その不幸な象徴ともいえる殺人事件が富岡八幡宮の宮司跡目争いにおいて生じました。背景には、「日本会議」とも関係の深い神社本庁の女性宮司」に対する差別的態度があります。
自民党の憲法24条改正案では、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。」と入れるよう主張されています。この条文は現憲法にはないのですが、民法上の規定においては夫婦、親子、あるいは親族の扶養義務がすでに厳しい日本社会で、憲法にもこのような記述が明文化されたらどうなるか。単純にいえば、国が個人に対して福祉を提供する根拠が減り、戦前のように戸主に扶養義務を課していく制度へと戻っていくでしょう。当然ながら、生活保護制度への根拠が弱くなり現在より支給が抑制されるはずです。
でも、家族の中で役割を全うすることが人生の価値であると思っている人は女性に多いのです。若い人も結婚時に夫の姓を選ぶ人は相変わらず多いし、選択的夫婦別姓制度は法制化の兆しが見えません。選択制に反対して、自分だけでなく他人にも同姓を強要したい根拠はなんでしょう。自分が大事にしている価値を他人が守ろうとしないことへの憎悪なのかもしれません。戸籍制度を残し夫婦同性を強要する国はいまあまり見当たらないのですけれども、外の世界を知らないニッポン人は、この特殊な制度が世界中にあるものだと思い込んでいます。学生に「戸籍とか夫婦同姓って現在世界ではめずらしい仕組みだよ」と話すと「知らなかった」と驚きます。教育過程でそういう知識を得たり議論する場が設けられていないのです。ローカルなルールを、グローバルなルールだと思い込めるのは自信に満ちた態度とはいえ、一歩間違えばただの無知ともなります。
街宣活動をしている人も例外でなく、「夫婦同氏」の法制化が明治31年の民法改正に始まっていることを知らない人もいます。私は以前、スーパーマーケットの前で「夫婦別姓反対、伝統日本を壊すな」とマイクで絶叫していた街宣車の人に向かって、「伝統って、いつの話ですか?明治半ばまでの日本は、夫婦別姓でしたよ」と話したら、「そんなこと、あるわけないだろう!」と怒鳴られたことがあります。引き下がらなかったら、街宣車から上司らしき人が降りてきて「すいません。不勉強な者が話しておりました」と謝られたことがあります。オイオイ、勉強してから話してほしい。逆にわかっているのに「伝統」って軽く言うなよ、と呆れた記憶があります。当時の夫婦同姓への改定は、西洋の伝統の導入で、東洋からの離反でしょう。背景には、西洋列強と肩を並べるために中国的なるものと距離を取ろうとする差別意識があったと思います。いまや西洋は「夫婦同氏」でもなくなっているのですけれども。
右翼は何にこだわっているのでしょうか。日本の伝統や文化といった人あたりの良い言葉をつかいながら、母の地位をないがしろにしないよう、イエ制度から子どもが逃げ出さないよう、声をあげているのではないでしょうか。跡継ぎが残らず嫁がこない不満を「自由な社会にしたからよくない」と。若い人を吸い上げていく都会的なるものを嫌悪しているだけではないでしょうか。女性蔑視という言葉でとらえるよりは、女性を家族関係の中での役割に留めておきたいという願望のようにもみえてきます。しかし、母なるものに訴えようとする運動は、依然として人々へのアピール力があります。ニッポンに深く埋め込まれた力学を呼び覚ますからです。
母への畏れとセクシュアルハラスメント
ここのところ、世界で爆発的に広がりつつある#Me Too運動。あれほど女性進出が広がったアメリカでさえ、セクシュアルハラスメントの病根がこれほど根深かったとは驚きでした。ニッポン人にとどまらず、社会進出をする女性たちが増加することへの、男性の潜在的な畏れと関係があると感じます。ヒラリー・クリントン氏の落選は、政治的主張以前にユングの元型でいうところの、オールド・ワイズ・マン(老賢人)とグレート・マザー(太母)の構図に持ち込まれた時点で、厳しいものとなってしまったのかもしれません。グレート・マザーを畏れていると口に出して男性がいうことはないでしょう。ひっそりと、いろいろな理由を探してオールド・ワイズ・マン(とてもワイズと言い難いにせよ)に投票するという行為で、現代の「母殺し」という欲望を満たしたのです。
平たく言えばマザコンを隠すためにセクハラをする、という感じでしょうか。母なるものへの依存という根源的な畏れは、女性を押さえつけておかなければ安心できない心理を呼び覚ますのです。ハリウッドの大物プロデューサー、ワインスタインとごく親しいというタランティーノ監督。これでもかという暴力を繰り出すところが、マザコンを公言する北野武と近さを感じさせます。キタノのHANA–BIのように映画監督であれば映像で暴力をくりだし、潜在的母殺しを妻との無理心中といったシーンで成就してしまうことができます。それがかなわないプロデューサーは、現実世界で女性に不当な権力をふりかざしていたということでしょうか。
そして、言葉を発する側が女性であることで、世間から手ひどいしっぺ返しをくらうこともあります。小池百合子氏の「排除」があれほどネガティブに捉えられたことを、阿闍世コンプレックスから読み解くならば、ゆるしを与える側の性であるはずの女性から発せられた、父性を感じさせる厳しい言葉遣いに世間は激しく反発したのだといえます。心理学的には父性原理とは切断するもので、母性原理とは包摂するものであるからです。それゆえ、これまでマイルドな言葉づかいを信条としてきた小池氏の見せた、一瞬の父性的な表現が、命取りになったのでしょう。
女性蔑視の源が母への畏れにあるならば、なくす方法が見えてきます。息子の養育から3つの心理的要素を外せばいいのです。甘やかしすぎず、怨みをいだかせずマゾヒズムに陥らずに、罪の意識を負わせたりゆるしを与えたりしない関係をめざすのです。母と息子関係がそうなっている親子はもちろん多いでしょう。自分もその一員である女性という集団の未来に降りかかる差別の源を、自分たちが作り出し続けるのはもうやめたいものです。
Profile

1964年、三重県尾鷲市生まれ、愛知県で育つ。早稲田大学卒業後、シンクタンク勤務をへて東京工業大学大学院修了。博士(学術)、社会学者。現在、早稲田大学文学学術院ほか非常勤講師。主な著書に『子育て法革命』(中央公論新社)、『家事と家族の日常生活:主婦はなぜ暇にならなかったのか』(学文社)、「平成の家族と食」(晶文社)など。