内田樹先生と三砂ちづる先生の往復書簡による、旧くてあたらしい子育て論。ともに離婚により、男手で女の子を育てあげた内田先生と、女手で男の子を育てあげた三砂先生。その経験知をふまえた、一見保守的に見えるけれども、実はいまの時代にあわせてアップデートされた、これから男の子・女の子の育て方。あたらしい世代を育てる親たちへのあたたかなエール。
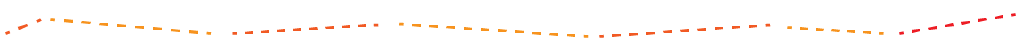
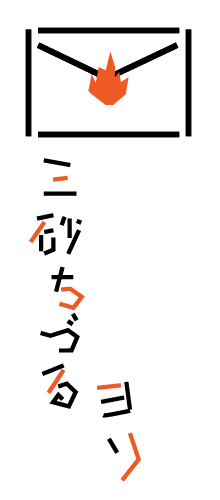
第11便・A
当時の女の子たちは失神していた
内田先生
お便りありがとうございます。ご無沙汰してしまいました。今年、2022年の夏も暑いですねえ。38度とか40度とか・・・体温より高くなってきました。この夏、沖縄、八重山によく行っていますが、そちらでは大体30度前後、32、3度より上がることはないですから、日差しは強いものの、風が吹きますし、東京より涼しい感じがしますね。沖縄県はまさに避暑地の様相を呈してきました。
ゲームやガジェット。おもしろいんですけどねえ、子どもたちが夢中になるのも、わかるんですけどねえ。e-スポーツの時代ですから、子どものみならず、若者も大人も夢中だし、世間的にもみとめられているわけです。世間の母親たち(父親もですが)どうやって小学生、中学生くらいの子どものゲーム時間を制限するか、に苦慮するというか、一体どの年齢でこどもをこういうことに曝露させていいのか迷う、というか、そんな感じだったと思うんですが、いまや、親たち自身もゲーマーですからね。新型コロナパンデミックで小学校でもタブレットが供給されるようになりましたし、もう、次世代は生まれた時からこういう世界にすっかり親和性のある形で育っていきます。どうしようもない。それでも、なお、親たちにためらいが残るのも、この世界が、耽溺するほどに魅惑的であり、その世界に没入してしまうことが、わかっているからですね。
その耽溺が、いわゆる「没我」の世界、「ゾーンに入る」世界か、と言われるとね、それはやっぱり、なんだかね、ちがう、と思いますよね。前回のお便りの最後に書いてくださっているように、身体的に「ゾーンに入る」ものすごく気持ちの良い経験、というのとは、おそらく異なる。ゲームの世界で「限界を超え」、「自我をつきぬける」経験自体は、できるのかもしれないけれど。おっしゃるように、私たちが少年少女だった頃にゲームやガジェットはありませんでしたが、すでにマンガや映画、音楽に小説、そういったものはありましたし、十分に魅力的でした。活字の小説より、さらに、マンガ、生演奏の音楽より、さらに、レコードやカセットに録音された音楽、そういった、もう、一手間かかったもの、あるいは視覚的に強調されたもの、繰り返せるもの、の方が、ずっと「没入させる力」は強かった、と思い出します。
1950年代生まれの私の世代は、黎明期にあった少女マンガと共に育ってきたので、マンガへの没入感は子どもの頃から親しみのあるものでした。普通の本もかなり読んでいましたが、いわゆる小説などとは、没入感が異なることは、初めから意識できました。小学校に入る頃から「少女フレンド」を読み始め、「なかよし」、「りぼん」、「マーガレット」、「少女コミック」と、成長とともに精緻化されていく少女マンガの世界に耽溺していったのは、この時代を生きた女の子たちの喜びでしたね。少年ジャンプが創刊されたのは小学校4年生の時でしたから、マンガ界は活気付き始めていました。大島弓子のデビューにも萩尾望都のデビューにもリアルタイムで立ち会ったことは幸運でしたし、中学校の部活をテニス部にしたのも志賀公江の「スマッシュをきめろ!」(「エースをねらえ!」の大ヒットで日本中の中学生がテニス部に入るようになる少し前のことです)を読んでいたせい、寝ても覚めてもこのマンガの世界に生きていて、初めてラケットを手にした時の喜びを忘れることがありません。「ポーの一族」、「トーマの心臓」は、のち、没入し過ぎて、勉強にならないため、高校時代の受験前には、単行本を新聞紙で包んだ上に、紐をかけて、簡単には出せないようにして、ベッドの奥におしこみました。やることがあまりに原始的で、かわいいものです。受験が終わった後、まっすぐ向かったのは、当時マンガ立ち読みし放題だった大阪の駸々堂書店で、竹宮惠子の「ファラオの墓」を立ち読みで読破しました。まだ、マンガ喫茶とか、なかった頃の話です。何時間、いたんだろう。それこそ没入しすぎて覚えていません。なんと、寛容だった駸々堂さん、ありがとうございます。ごめんなさい、竹宮先生、全部立ち読みしてしまって・・・。その後、精華大学学長になられた竹宮先生に(内田先生、素敵な対談本を出しておられますね)、B L(ボーイズラブですが)を卒業論文のテーマにした4年ゼミの学生が、長い質問の手紙を出したところ、とんでもなく丁寧、かつ、内容の濃いお返事をくださって、一学部生にここまでおつきあくださる竹宮先生に感服しました。再度、心の中で、「ファラオの墓」立ち読みしてごめんなさい、と謝ることでした。
音楽も、まことに忘我の経験。そういえば、当時の女の子たちは、失神していました。きっとよくおぼえてらっしゃいますよね。1960年代から、そうですねえ、80年代ころまででしょうか。世界中のロックコンサートで、日本のグループサウンズのコンサートで、女の子たちは、きゃーっと言って、失神していたのです。プレスリーが踊れば失神し(これは50年代末かも)、ビートルズが日本に来た、と言っては失神し。マイケル・ジャクソン(同い年です)のコンサート映像では、失神する女の子をカメラで追ったりしていました。それがひとりやふたりではないのですよね。同時代の世界中の女の子が同じような音楽を聴いて失神していた。それが、ある時から、失神しなくなった。90年代くらいからは失神しなくなったんじゃないでしょうか。コンサートでの熱狂は今も変わらず続いていて、ある意味ずっと大規模にもなったと思いますし、小さなライブハウスでの熱狂も、ファン心理も、以前より重層的で深いものになっているようですが、でも、いまどき、誰も失神しません。あるとき、これはなんだろうなあ、なにがかわったんだろうなあ、と考えたことがありますが、よくわかりません。調べてみたことがありますが、誰もこういうことを研究している方は見つかりませんでしたし、私もわからない。当時の音楽やグループが特別だった、ということもないように思います。音楽は当時の流れを引き継いで、ずっと進化しているのですからね。これって、ひょっとしたら、内田先生の言われる、幼い頃の「ゾーンに入る」とか「フロー体験」と、なんらかの関わりがあったのではないか、とふと、思ったりしましたが、おそらく違うな、と、書きながら、思っている。「忘我」の「フロー体験」と、「失神」とは、方向性が違います。
*
前回のお便りで、私たちが例としてあげている幼い頃の「忘我」の経験は、サンゴ礁の海で海に溶けてしまったり、道端の植物にこころうばわれてじっとみいってしまったり、夏の日差しのもと、冷たい川の流れの中で100%の気持ちよさを経験したり、風の中、竹と同化したり・・・それはすべて、なんらかの形で、人間がつくりあげたものではない環境、というか、自然のなにかに接することで、起こってきていることでした。音楽やマンガやゲームに没入すること、あるいは、アカデミックハイ。あるいは、書くこと、創作活動における、先が見えてくるような、ハイな経験。それらは全て、人間の記号的な知的作業のうちに営まれていることです。ところが私たちが例に挙げている子どもの頃に経験する「ものすごく気持ちの良いこと」は、人間の記号的な知的作業とほぼ関係ないところで、突然、その世界に“ほうり込まれた”ようになって、その世界と一体化する、という形で立ち現れていますね。ありていな言い方をすれば、“自然”に同化させられている。
これらの幼い時の身体感覚は、ゲーム、ガジェット、音楽、マンガ、映画、アカデミックな作業、執筆・・・なんでもいいのですが、人間の“知的営み”に入るようなものへ没入感よりも、「先駆的に」、あるもののような気がします。母親のおなかのなかで育ち、この世に生まれてきて、いったんは、きりはなされたような状態にありながら、それでも生まれてきた人の感覚は完璧で、幼い人はおそらくこの世界と全て繋がっていることを全身で理解している。おそらく乳幼児は、すべてこれ「フロー体験」みたいな感じで生きているのではないかと思います。産む側の女性の経験を私はずいぶん聞き取りしてきていますが、文字通りの「フロー体験」、つまりは、ものすごく気持ちがよくて、時間の感覚がないような、自分が周囲に溶けてしまったような感覚をよく語ってくれます。お産の時にそういう感覚を持つ女性は少なくないのです。こういう母親と生まれてくる子どもの感覚はおそらく一致しているのだと思います。その感覚を、科学的には証明せよ、といわれても、することの難しい事案ですから、なんとも言えないのですが。
「フロー体験」そのもののような赤ちゃんは、その後の人生を生きていくために、首がすわり、腰がすわり、立ち上がり、言語を獲得し、周囲と言語や身体的な身振りでコミュニケーションをとるようになり、五感が分化していき、その五感で扱えるものに対処するようになっていくプロセスの中で、その「フロー体験」のようなものは薄れていき、それこそ「人間社会」に適応できるようになっていく。でもそういう中でも、自分とは異なる存在を感じられるような状況に、ゆったりとおかれると、不意に、その「一体感」というか「フロー体験」みたいなものが、自分に戻ってくる。それは、おそらく幼いうちは何度も体験されているものだと思いますが、それを明確に思い出すことができ反芻できる経験として意識できるようになるのは、少し大きくなってからのことだろうと思います。意識的にそれと感知できて、それを言語で表現できて、のちの人生でも思い起こせるもの、である必要があるとすれば、それはやはり10歳まで、くらいまでに体感されることではないか、と思えます。逆にいえば、言語獲得を経たのち、生まれた頃の「フロー体験」とそれが同一のものだ、という絶対的な感覚を、感じやすいとともに、それを記憶することもでき、言葉で反芻できる年齢が、10歳くらい、と言えるのかもしれません。
もちろん10歳前後以降でも、人間はそういう経験に開かれています。つまりは、身体的な没我の経験というのは大人になった人間にも訪れるものであり、とりわけ、女性は出産時にそういう経験をする人が少なくないものですから、私自身はそういう経験を「原身体経験」と呼んで、出産経験のスケール化、など記号化の極みみたいな疫学研究をしたこともあります。後の年齢でも開かれてはいるものの、この10歳頃までの、人間が生殖期に向かう前の、明瞭な体験、というのは、具体的に人間にとって大きな転換期である思春期、そしてのちの成人期の困難をうまく乗り越えやすくするきっかけを提供するようのではないでしょうか。
それらの身体的な経験が10歳前後までに先駆的にあると、内田先生がお書きになっているように、「必要な時にはいつでもそこにもどる」ことができるようになる。そのような経験をしていることが、その後のマンガや、本や、音楽や・・さらに現代ではゲームなどの記号的な没入感を、より深く愉快にもし、また、そこから抜け出すことにも、愉悦を感じられるようになるのではないでしょうか。あくまで仮説ですがね。
そう思えば、先の世代としては、どうやって子どもたちが10歳までに身体的な没入感を感じられるような経験を提供できるのか、という話になります。でも、それって、そういう経験がいいですから、できるだけ子どもにそういう経験をさせてあげましょう、といった、新しいお稽古ごととか、サマーキャンプにもっと参加させて、より自然な環境に子どもをおいてあげましょう、とか、そういうお膳立てができるようなこととは、違うような気がします。
経済学者、内田義彦の書いたトンボ釣りの話が思い出されます。今は、トンボ釣り、という言葉自体、もう、わからない人が増えているのかもしれませんが、要するに、トンボを捕まえることです。ご飯を食べるより、何をするより、トンボを釣るのが大好きな子どもがいて、喜んでトンボ釣りに熱中している。これをやめさせようと思うと、それは簡単で、大人が、毎日、毎日、命令して、「トンボを釣ってこい」といえば良い、「やれ」と言われると、楽しみであることが楽しみでなくなり、苦痛になってくる、と。
大人がお膳立てして環境を提供する、というのは、なんだか少し、このトンボ釣りの話と似ているような気がしてなりません。子どもたちに「フロー体験」を10歳前後くらいまでにしてもらいたいのですが、そのために、何かをする、というは、どうも本末転倒な気がするのはそのためです。できそうなことは、とにかく、子どもがぼうっとできる静かな時間、大人からすると意味のないような時間がたくさんあること、そして、ゲームやガジェットへの曝露を少しでも後ろ倒しにする、くらいしか思い至りませんが、このことは具体的な次世代へのアドバイスとして、もう少し考えを深める必要がある気がします。
立秋も過ぎたのに、今日も暑い日になりそうです。どうかご自愛ください。
三砂ちづる 拝
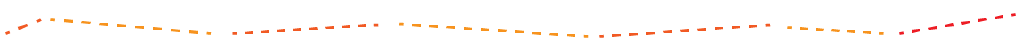
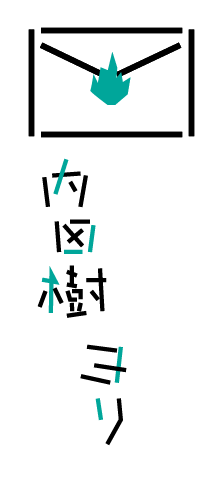
第11便・B
師に全幅の信頼を置く
三砂先生
こんにちは。内田樹です。
お手紙頂いてから1月近くご返事できずにすみませんでした。
この夏休みは7冊本を抱えていて、うち1冊だけは何とか仕上げて出版社にゲラを戻しましたけれど、残り6冊は今同時並行で書いています。これもその一冊なんです。『資本論』解説、カミュ論、権藤成卿の復刻本の解説、米中論、勇気について、そしてこの子育て論を並行して書いています。支離滅裂なラインナップですね。
どうしてこんなになんでもかんでも引き受けてしまうんでしょうね。自分が苦しい思いをするだけなんですけれど、それでも面白そうな企画を持ち込まれると、つい「やります」と言ってしまうんです。
でも、その時点では書きたいことが頭の中にあるわけじゃないんです。頭の中にはまだ何もないんです。でも、何となく「書くことをこれから思いつくかもしれない」という予感がする。まだアイディアにはなっていないのだけれど、「アイディアの予兆」のようなものがそのオファーを受けた時にふっと目の端をよぎる。そんな感じです。実際に書き始めてみると、たしかにその「予兆」から何かが浮かび上がって来る。さざえのつぼ焼きをつまようじで引き出すとき、ていねいにひっぱりだすと「つるっ」と中味が出てきますね。あんな感じ。
それに、僕が書いているものって、どれもネタが古いんです。なにしろ『資本論』にアルベール・カミュに農本主義者・大アジア主義者ですから。いったいいつの時代の話をしているんだよと言われそうです。でも、気がついたら、僕のところに来るのって、そういう企画ばかりなんです。いつの間にか、「古老に聴く」というタイプの取材がほんとうに増えました。
最初に来たのは「1969年の三島由紀夫VS東大全共闘の行われた時の時代の空気はどんなものでしたか」と訊かれたとき。そういうタイトルのドキュメンタリー映画に「時代の証人」としてちょっとだけ登場しました。そしたら、次は「1968年の第一次羽田闘争の山崎博昭君の死にどんな衝撃を受けましたか」を訊かれ、次は「1972年の早稲田大学内ゲバ殺人によって以後の学生運動はどう変質しましたか」を訊かれました。
ある出来事がどういう文脈で起きたのか、その出来事がのちの時代にどんな影響を及ぼしたのかといったことは、研究書を読めばわかりますが、リアルタイムでその出来事があったときに同時代の人たちが何を感じ、どういう表情やどういう言葉づかいでそれについて語ったのかは、その場にいた人間しか記憶していません。そういう「現代史の生き証人であるところの古老」というポジションに気がついたら立っていました。
この「男の子を育てる話」もある意味では、そうだと思うんです。僕に求められているのは、一般論ではなくて、「昔、男の子はこういうふうに育てられた」という個人的な見聞の証言ではないかという気がするのです。
「そんなのはあなた一人の個人的な経験や知見であって、一般性を要求できないよ」と言われたらその通りなんですけどね。でも、「証言」というのはもともと一般性を要求するものじゃない。むしろ「一般性を揺るがすもの」です。
よくドキュメンタリーに「昔の出来事を遠い目をして語る古老」が出てきますね。でも、彼らはすわりのよい結論を述べたり、わかりやすい教訓に落とし込んでくれたりはしてくれない。むしろ、そういう(ディレクターがあらかじめ仕込んでおいた)予定調和的なシナリオにはないことを呟いて物語を「脱臼」させる。
ですから、僕たちもその「古老」に倣ってはいかがかと思うのです。ここはできるだけ個人的な、偏頗なことを書いて、「子育て」についてのできあいの物語を混乱させる。混乱させるだけさせて、さっと逃げ出す。なんだかその方が誰にでも同意してもらえるような面白みのない「一般論」を語るより楽しそうだと思いませんか。
というところまでが前置きです。前便で三砂先生が振ってくださったトピックについて書きます。一つは「没入」ということ、もう一つは「10歳前後」ということです。論脈上はつながりのないこの二つ言葉に僕はつい強く反応してしまいました。それはその二つについて別のところに書いたばかりだったからです。その話をしますね。
*
先日、知り合いから大学でのセクシャルハラスメントの被害者女性の裁判闘争の支援を頼まれました。もしかしたら三砂先生もご存知かもしれませんが、早稲田の大学院で、文芸評論家としても高名な人物が、女性院生に対して研究指導に際して、繰り返し暴言を吐き、自尊心を傷つけただけでなく、指導や卒後の世話の代償に性的関係を求めてきた事件です。そのせいで女性は退学を余儀なくされ、心に深い傷を負うことになりました。教員は退職し、大学は事件の隠蔽をはかった教職員を訓戒しましたが、被害者に対する謝罪も補償もありませんでした。この女性は、大学がハラスメントが多発している事実を認め、それに適切に対処できる仕組みを作るように訴えを起こしています。
僕が彼女が書いているこの経緯を読んで、強い怒りを感じました。それは、師弟関係というのが、本来は弟子の側に「自己放棄」と師への「全幅の信頼」を求めることで成立するものだからです。自分についてくる人に「自分を手放すこと」を求めるからです。それを悪用したことを許し難く思ったのです。
たしかに中等教育や大学でも学部レベルでは、そこまでの「没入」は求められません。でも、大学院レベルになると、一人の教師と一人の院生が一つのことについて、余人の入り込む余地のないほど密度の高いやり取りをすることが起きます。研究職というのはある種の「ギルド」ですから、独特のジャルゴンが行き交い、世間の常識がしばしば通らない。でも、入会しようとする者は「清水の舞台から飛び降りる」つもりで、自分の手持ちの価値観や判断基準をいったん「かっこに入れて」、「メンター」の指示に黙って従う。そうしないと「ギルド」に入れてもらえないと思うからです。
その時、学ぶ者は一時的に非常に無防備になります。自己刷新のためには、それまで身にまとってきた「鎧」を脱ぎ捨てることが必要だからです。一時的にではあれ、とても脆く、傷つきやすい状態を過ごさなければならない。
この脆弱で、傷つきやすいプロセスにある人が外傷的な経験を受けないように気遣うことはメンターのとてもたいせつな仕事だと僕は思います。ほんとうに教え子の知的成熟を望んでいるなら、教師は教え子が「自分を手放す」プロセスを無事に通過できるように、じっと見守って、適切な指示を与え、励ましてあげるのが仕事だと思います。
でも、このセクハラ教師は、教え子がそれまで生き方を律していた個人的な規範を手放して、メンターの言に黙って従うことを決意したことにつけ込んで、おのれのせこい欲望を満たそうとした。これは単にこの人物の属人的な卑しさということ止まらない罪深いものだったと思います。彼がこの女性の「学び」への開かれを傷つけたからです。
これから先、彼女はもう新しいことを学ぶために無防備になるということができなくなったと思います。誰かを信じて心を開くということができなくなる。「謎めいたこと」を言う人間には興味を持つより先に嫌悪と不快を感じるようになる。忍耐強く相手の話を聴くよりも、「ひとりがたり」をしている方が落ち着くようになる。そうやって、自分に居着いてしまう。でも、これはお分かりでしょうけれど、知性的、感情的な成熟にとってはほとんど致命的なことです。
学びの場で受けた外傷的経験は単に「セクハラされて不愉快だった」ということでは済まされません。それは当事者の「学ぶ能力」そのものに深い傷を残すからです。
そんなのはもう過ぎたことなんだから、早く忘れた方がいいというような賢しらな助言をする人がいますが、それは傷の深さを理解していない人の言葉だと思います。学ぶ人がメンターから受けた傷は、遠く未来にも影響を及ぼすからです。
この女性が最近書いたものを読んで、僕はなんだか悲しくなりました。とても文章の上手な人なのです。論理的できちんとした、説得力のある文章を書くのです。でも、硬直しているのです。自分に触れてくる異物に対する不安と嫌悪で、文章の皮膚がかちかちに堅くなっている。彼女が、この事件以前にどんなものを書いていたのかを僕は知りません。でも、おそらくこれよりはもっと手触りの暖かい、風通しのよい文章を書いていたのではないかと思います。この人はある意味で「自分の声」まで奪われてしまったのです。
*
子どもたちが「没入」できることはとてもたいせつだ。このことについては僕たちはもうよく了解し合っていると思います。そうできるように支援するために、傍らにいる大人に何ができるでしょう。それは「自分を手放して、没入しても大丈夫だよ。怖いことないよ。誰も君を傷つけないから」という保証をしてあげることだと思うのです。
小さい子どもが大人の手をぎゅっと握って「放しちゃだめだよ」と言う時がありますね。あれは、彼らが「冒険」をしようとする時なんです。そういう時はしっかり握ってあげる。もし小さい時に、「放しちゃだめだよ」と大人に頼んだのに、手を放されたという経験をした子どもは、それからあと「冒険」することに対してずいぶん臆病になると思います。ですから、子どもたちが10歳くらいになるまでは、親はどんなことがあっても「手を放してはいけない」と思います。それくらいの年齢までに「自分を手放しても怖いことはない」「人を無防備に信じても裏切られることはない」という確信を子どもが持つことがとてもたいせつだからです。
前に講演のあとの質疑応答で、フロアから「内田さんのその根拠のない自信はどこから来るんですか?」というたいへん本質的な質問を頂いたことがあります(会場は爆笑していました)。「子どもの頃に内田家の人たち、父と母と兄から深く愛されて育ったからだと思います」とその時にはお答えしました。「愛されていた」というのは、言葉が足りなかったかも知れません。「愛されていた」というよりは「いつも見守ってもらっていた」という方が正確だと思います。子どもの頃に、自分が手をつかんだ時に、親から手を振り切られたという記憶がないのです。その体験のせいか、人に自分を委ねることが別に怖くない。信じることが怖くない。おかげで、僕は武道と哲学というふたつの分野で、「師に全幅の信頼を置く」という得難い経験をすることができました。以前、兄に「どうして樹はそれほど無防備に人を『先生』と言って後についてゆくことができるのか」としみじみ言われたことがありました。「お前は、『弟子上手』だな」と。その通りかも知れないと思います。兄は的確に見ていたと思います。そして、僕が「弟子上手」なのには、小さい頃に(この兄も含めて、家族から)「握っていた手を振りほどかれた」という外傷的経験がなかったことが大きく与っていると思います。
でも、それってやっぱり「10歳前後」までなんだと思います。その次の段階では「世の中には決して心を許してはいけない人間がいる」ということを大人は教えなければいけない。
僕の父親は僕が8~9歳の頃に、僕を前に座らせて「信用できる人間かどうかは、その人物の地位や学歴とは関係がない。哲学を持っていない人間を信用するな」と申し渡しました。子どもに向けて語る言葉にしては、あまりに堅苦しい言葉でしたし、父親の表情も真剣でしたので、忘れがたい思い出になっています。
父は満州事変の年に19歳で満州に渡り、敗戦の翌年に北京から帰国しました。15年間大陸にいて、大日本帝国の消長をつぶさに見てきた人です。驕った日本人たちが朝鮮半島や中国大陸で何をしてきたのかも見たし、帝国が瓦解するのにも立ち会った。その混乱の中で、父は「信用できる人間」と「信用できない人間」を見分けることは死活的に重要だということを思い知らされたのだと思います。
父が子どもの僕に「哲学を持っている人間」という言葉で言おうとしていたのは、「世間の人々」がどう言おうと、どうふるまおうと、ことの筋目を通す人のことだと思います。自分なりの条理を維持していて、損得勘定や私利私欲で言動がぶれない人間。おそらくそういう人に父は窮地を救われたことがあり、逆に学歴も地位も申し分ないが、平気で人を裏切る人間に煮え湯を飲まされたという個人的な経験があったのだろうと思います。
父が小学生の僕に教えようとしたのは、「世の中には決して信用してはいけないタイプの人間が存在する」という経験知でした。それを父は子どもがある年齢に達した時には「教えておかなければならないこと」だと思ったのです。「ある年齢に達したとき」という条件がつくのは、あまり幼いときから「世の中には信用してはいけない人間がいる」ということを口うるさく言うと、それは子どもの成長の妨げになるからです。
幼い子どもはまず「学ぶ」ことから始めなければならない。まずは心を開いて他者に接する無防備さを身につける。ある種の無垢さです。子どもたちの成熟を願うなら、まず人を信じること、人に身を預けることを教えなければならない。「誰も君の手を放さない」「誰も君を傷つけない」という保証を与えるところから始める。
でも、そんな子どもたちもいつか「世間」に踏み出してゆかなければなりません。そして、世間に出ればいつか必ず「決して信用してはいけないタイプの人間」に出会う。イノセントな向上心につけこみ、彼らから収奪し、致命的な傷を負わせて立ち去る人間に出会います。そういう人間はこの世間にはたくさんいます。だからこそ大学や職場でハラスメントがあれだけ起きるのです。そういう人間を見分けて、決して近づかない知恵が死活的に重要になります。
僕たちは子どもたちを育てる時に「信じろ」ということと「信じてはいけない」ということを二つ教えなければならない。時間順としては、まず「人を信じること」を教え、次に「信じてはいけない人がいる」ということを教える。そういう順序になると思います。そして、その二つのモードの切り替えが「10歳前後」ではないかというのが僕の仮説なんです。
「人を信じなさい」ということを教えてくれる心優しい親は多くいると思います。でも、子どもがある年齢に達した時に、子どもを前に座らせて「よく聞きなさい。世の中には決して信じてはいけない人間がいる。これからそれを見分ける方法を教えるから、よく聞いて忘れないように」と教えてくれる親はそれほど多くはない。
それは親の経験知でよいと思うのです。限定的な経験から絞り出したような言葉で十分だと思うのです。子どもが第一に知るべきなのは「どういう人間を信じてはいけないか」という識別法ではなくて、「世の中には決して信用してはいけない人間がいる」という事実の方だからです。
「ねえ、いったいどうすればいいの? 人を信じていいの? それとも信じちゃいけないの?」と子どもは泣訴するかも知れませんけれど、それに対しては「信じたり、信じなかったりするんだ」と答えるしかありません。「人間は葛藤のうちでしか成長しないのだから、それくらいは成熟のコストとして引き受けなさい」というところまで口に出して言っても、子どもには難し過ぎてわからないかも知れませんけれど。
長くなり過ぎたので、今日はここまでにしておきます。では。
内田樹 拝
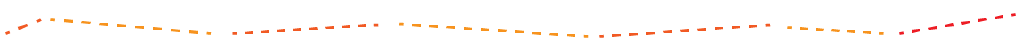
 内田樹(うちだ・たつる)
内田樹(うちだ・たつる)
1950年東京生まれ。凱風館館長。神戸女学院大学文学部教授。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。著書に『「おじさん」的思考』『こんな日本でよかったね』『コモンの再生』『日本習合論』など多数。『私家版・ユダヤ文化論』で第六回小林秀雄賞を、『日本辺境論』で2009年新書大賞を受賞。
三砂ちづる(みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。京都薬科大学卒業。ロンドン大学Ph.D.(疫学)。津田塾大学多文化・国際協力学科教授。著書に『女たちが、なにか、おかしい おせっかい宣言』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『オニババ化する女たち』『死にゆく人のかたわらで』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『少女のための性の話』など多数。

