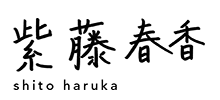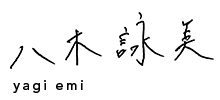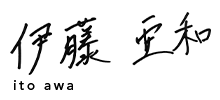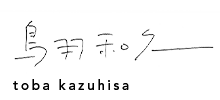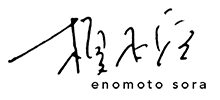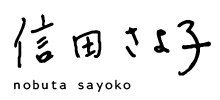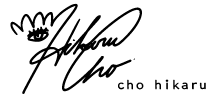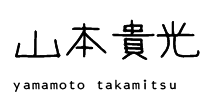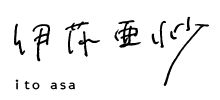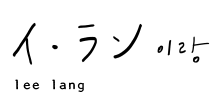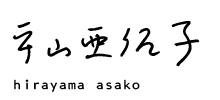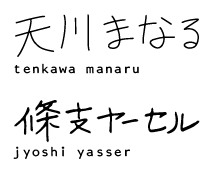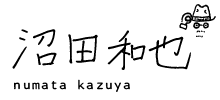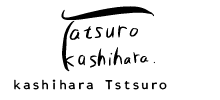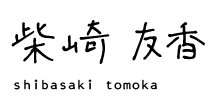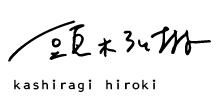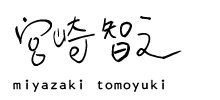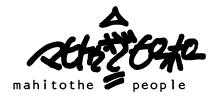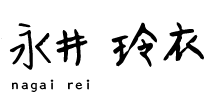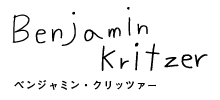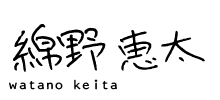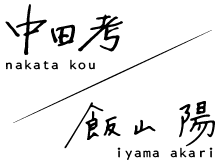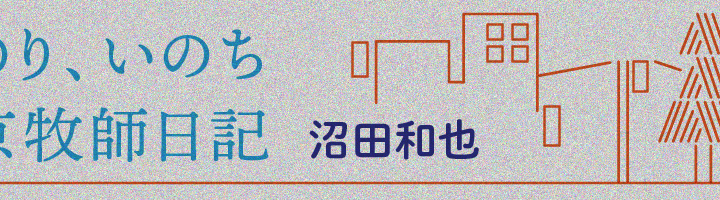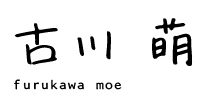膝の皿を金継ぎ
- 第8回 2月の日記(後半) 2024-03-28
- 第7回 2月の日記(前半) 2024-02-27
- 第6回 わからなさとの付き合い方 2024-01-29
- 第5回 サバイバル煮物 2023-12-28
- 第4回 ところでペットって飼ってます? 2023-11-30
- 第3回 喋る猫はいなくても 2023-10-31
- 第2回 夢のPDCA 2023-09-29
- 第1回 ここではない、青い丸 2023-08-31
アワヨンベは大丈夫
- 第8回 ウサギ小屋の主人 2024-03-17
- 第7回 竹下通りの女王 2024-02-15
- 第6回 ママの恋人 2024-01-11
- 第5回 Nogi 2023-12-11
- 第4回 セイン・もんた 2023-11-15
- 第3回 私を怒鳴るパパの目は黄色だった 2023-10-13
- 第2回 宇宙人とその娘 2023-09-11
- 第1回 オール・アイズ・オン・ミー 2023-08-11
旅をしても僕はそのまま
- 第5回 アシジと僕の不完全さ 2024-01-27
- 第4回 ハバナのアルセニオス 2023-11-15
- 第3回 スリランカの教会にて 2023-09-16
- 第2回 クレタ島のメネラオス 2023-06-23
- 第1回 バリ島のゲストハウス 2023-05-31
おだやかな激情
- 第11回 なめらかな過去 2024-04-04
- 第10回 ちぐはぐな部屋 2024-03-05
- 第9回 この世の影を 2024-02-02
- 第8回 映したりしない 2024-01-11
- 第7回 とばされそうな 2023-12-04
- 第6回 はらはら落ちる 2023-11-01
- 第5回 もしもぶつかれば 2023-10-02
- 第4回 つややかな舌 2023-09-02
- 第3回 鴨になりたい 2023-08-01
- 第2回 かがやくばかり 2023-07-04
- 第1回 いまこのからだで目に映るもの 2023-05-31
- 第4回 うまくいかなくても生きていく──『十二月の十日』ジョージ・ソーンダーズ 2023-09-25
- 第3回 元恋人の結婚式を回避するために海外逃亡──『レス』アンドリュー・ショーン・グリア 2023-04-21
- 第2回 とにかく尽くし暴走する、エクストリーム片思い──『愛がなんだ』角田光代 2023-01-17
B面の音盤クロニクル
- 第8回 その日はあいにく空いてなくてね──Bobby Charles, “Save Me Jesus” 2024-03-08
- 第7回 クリスマスのレコードはボイコットする 2023-12-22
- 第6回 とうとう会得した自由が通底している 2023-05-06
- 第5回 あれからジャズを聴いている理由──”Seven Steps to Heaven” Feat. Herbie Hancock 2023-04-04
- 第4回 「本質的な簡素さ」の歌声──Mavis Staples “We’ll Never Turn Back” 2023-03-01
- 第3回 我が家にレコードプレイヤーがやってきた──Leon Redbone “Double Time” 2023-01-08
- 第2回 手に届きそうな三日月が空に浮かんでいる──Ry Cooder “Paradise and Lunch” 2022-12-07
- 第1回 きっと私たちが会うことはもうないだろう Allen Toussaint “Life, Love, and Faith” 2022-11-04
- 第16回(最終回) 「本物の詐欺を見せてやるぜ」@ジョン・ライドン 2022-07-04
- 第15回 文明化と道徳化のロックンロール 2022-06-10
- 第14回 ミスマッチにより青年は荒野を目指す 2022-06-02
- 10 もうひとつの現実世界――ポスト・トゥルース時代の共同幻想(後編) 2021-07-06
- 9 もうひとつの現実世界──ポスト・トゥルース時代の共同幻想(前編) 2021-05-03
- 8 あるいはハーシュノイズでいっぱいの未来 2020-05-05
第9回 無傷では済まない
教会のなかで出遭う人。教会の外で不意打ちのように出遭う人。一時は精神を病み、閉鎖病棟にも入った牧師が経験した、忘れえぬ人びととの出遭いと別れ。いま、本気で死にたいと願う、そんな人びとと対話を重ねてきた牧師が語る、人との出遭いなおしの物語。いのりは、いのちとつながっている。
最初に赴任した教会で、とても親切にしてくれる、当時60代の一人暮らしの女性がいた。まだ新しい土地での生活に慣れていなかったわたしには、その人の親切さは有り難かった。だが、わたしはその人の親切な態度に対して、次第に違和感を覚えるようになっていった。不信感と言ってもよい。というのも、その人の親切さには、どこか尋常ならぬほどの過剰さがあったのである。とつぜんデジタルカメラを「いらないからあげます」と、わたしにくれたこともある。その語気には断ることを許さない雰囲気があった。「それでは使わせてもらいますね」と、わたしは幼稚園の行事などの撮影にそのカメラを使わせてもらった。「パソコンあげます」と、買ったばかりのデスクトップやプリンターをくれようとしたこともある。幼稚園でもらおうかなと考えていたら、悪質なリサイクル店が彼女に一銭も払わず持ち去ってしまった。彼女はこうして浪費をしては他人から騙し取られることもあったのだが、本人には自覚がないようだった。機嫌がよいとき、彼女はほんとうに饒舌だった。わたしと上司を自宅に呼んでごちそうをしてくれたりと、気前が良かった。
だが、ときおりゲリラ豪雨のように彼女は怒りっぽくなった。それがやってくると、彼女は今までの親切な人がらが豹変したように、わたしのやることなすことに嫌味を言うようになる。たまりかねたわたしが「そんなこと言わないでください」とやんわりたしなめると
「故郷に帰んなはい!」
と激怒するのであった。怒っているときの彼女には上司も手を焼いていた。なにしろ誰の注意も効果がない。そうやってほうぼうへ怒りを爆発させるうちに彼女はすっかり寝込んでしまい、しばらく教会には来なくなる。そして一、二か月ほどすると、まるで何事もなかったかのように彼女は再び、静かな笑みを浮かべながら教会に来るのである。ところが、しばらくすればまた、彼女の静かな微笑は哄笑に変わり、そして激怒へ。その繰り返しなのであった。
彼女はある精神疾患を患っていた。おそらくもっとも苦しいのは彼女自身であった。だが、わたしを含めた周りの人々は、症状への正確な理解がなかった。とくにわたしは経験も浅く、無知であったので、彼女の機嫌に振り回された。わたしは彼女といっしょに大笑いしたかと思えば、大喧嘩をしてしまう始末であった。
「なんてつきあいにくい人なんだろう。」
そう思っているうちに、彼女もこちらの教会ではもはや居場所がないと感じたのか、近所にあるカトリックへと移っていった。神の前に告白すると、わたしは彼女が去って残念というより、肩の荷が下りた。
わたしは今も精神疾患や精神障害について専門的な知識を持っているわけではない。だが精神科医らが書いた書物をとおして、当時よりは少しだけ学びを重ねた。たとえば、見知らぬ人が教会に来て
「じつは、わたしはイエス・キリストなんです」
と、ほんとうに真剣に、大切な秘密を打ち明けるように話してくれる。わたしはその人の言葉を、あえて比喩的に受け取った。そうだ。こうやってわたしが向きあっている何気ない人こそ、じつはキリストそのものなのだと。馬鹿にしてはいけないと。だからこう答えた。
「そうですね、あなたはきっとキリストですね。わたしにはそう見えます」
このように語ると情緒的であるが、そこには精神障害についての、わたしの冷めた知見が働いてもいる。「ああなるほど、たぶんあの障害による言動なのだろうな」という、医師ではないにせよ、なんらかの見当をつけて応対するのである。そういう冷めた知見があってこそ、落ち着いて目の前の人と向きあい、その人のいうキリストを、比喩的にであれ真面目に受け取ることもできるのだ。
わたしはこうして、精神的な病や障害を持つ人と、少しばかりは冷静に、誠実に向きあうことができるようにはなってきた。だが、今でもうまくいかないことは多い。そもそも、相手は精神疾患や精神障害という概念に手足が生えた存在ではない。目の前にいるのはまぎれもない、世界にたった一人の人間である。その人固有の人生を歩んできたのだし、その人ならではの性格もある。一方で、その人が自覚しているかいないかは別として、その人と不可分な状態としての精神疾患や障害があるのだ。うまくいかないときというのは、相手がわたしに失礼な(とわたしが感じる)言動をしてきたときである。それも繰り返し、まるでいつわたしが怒りだすのかを試すかのように、不愉快な言動を繰り返す人がいるのだ。それは疾患や障害によるものなのか。それとも不遇な生い立ちから来たものなのか。それとも────これを認めるのがいちばん苦しいし腹立たしいのだが────その人の性格が原因なのか。
わたしの理解が「この人はいやな性格をしている」へと振り切れそうになったとき、わたしは相手に対して怒りを露わにしてしまう。いやなことを言う人。いやなことをする人。いやな性格の人。いやなやつ!いちどそう感じ始めてしまうと、その人と向きあうことがつらくなる。ここから立ち去って欲しいと考えてしまう。一度や二度は我慢してどうにかやり過ごせても、三度目になってとうとう「もう来ないでください」と言ってしまうこともある。自分から「もう来ないでください」と言ってしまったときの、なんともいえない後味の悪さ。敗北感。教会は誰にでも開かれた場所、神の家のはずではなかったのか。
わたしは以前、閉鎖病棟に入院したことがある。だから、わたしもまた当事者の一人である。今は仕事ができる程度には回復しているが、念のため月一度は精神科に通い、臨床心理士によるカウンセリングも受けている。精神科医はとても忙しいので、医師との会話は「眠れているか、困りごとはあるか、次の来院予定」くらいである。だが臨床心理士とは1時間話すことができる仕組みになっている。それゆえ、わたしはむしろ臨床心理士との月一度の面談に精神の安定を得ている。わたしはあるとき上記の葛藤について相談をした。すなわち、自らも当事者の一人でありながら、精神疾患や障害のある人に対して嫌悪感を覚えたり、明確に拒絶したりしてしまうことがある問題についてである。臨床心理士からの回答はじつに明快であった。
「わたしたち病院で勤務する臨床心理士は、こうして決められた時間、決められた部屋で、白衣を着て、一定の労働対価をいただきながら患者さんと向きあっています。もしも不安定になった患者さんが暴力を振るいそうになれば、わたしはこの部屋から逃げることだってできます。部屋がそういう作りになっていますからね。
でも、沼田さんはちがいますよね。朝だろうが夜だろうが、とつぜん電話がかかってくる。予想もしない時間帯に、約束もなしにやってくる人もいる。そういう人たちに対して、いつでも職業人として丁寧に接することなんて、できなくて当然だと思いますよ。疲れているとき、眠いときに向こうが遠慮なく連絡してくるなら、冷静な対応ができないこともあるでしょう。
それに沼田さんは仕事場に住んでいますよね。とつぜんの見知らぬ来訪者を、自分の家に招き入れるわけです。それは、わたしたちには想像できないほどの緊張を伴うと思いますよ。沼田さんは自分の住所も電話番号も、みんな晒しているわけですからね。沼田さんには逃げ場がない」
臨床心理士の回答に、わたしは胸がすっとするのを感じた。よかった。わたしもただの人間なのだ。もちろん牧師という職業人として、せいいっぱい誠実かつ倫理的に、電話や来訪には応対する。けれども教会の二階にわたしは住んでいる。そこには妻も暮らしているのだ。いわば自宅ともいえる場所に見知らぬ他人を招き入れるという、現代ではとてつもなく無謀なことをわたしはしているのである。そんな条件下で、いつも平然とニコニコしていられるほうがおかしいではないか。相手の言動に苛立ちや怒りを感じることもあるだろう。ときには不気味さや、恐怖さえ覚えることもある(わたしは、幽霊よりも現実の人間のほうが怖さを醸し出すことがあるような気がする)。それに、ふだんならやり過ごせることであっても、真夜中で眠かったり、早朝で頭が働かなかったり、くたくたに疲れているときには、思わず怒りがこみ上げてしまうこともあるだろう。
ときおりツイッターで、わたしのちょっとした言動をもって、わたしのことを反人権的で差別的であると糾弾する人もいる。ツイッターでは論文のように慎重な推敲をしているわけではないので、わたしの未熟な差別意識が顔を覗かせてしまうのである。もちろん、指摘されたことに対しては真摯に改めたいと思う。ただ、鬼の首を取ったようにわたしを批判する人に対しては、こう言いたい。あなたはホームレスを家に泊めたことがありますか。そもそも、ホームレスがとつぜん家に尋ねてくるという体験をしたことがありますか。あなたは差別はいけないと言うけれど、重い精神疾患や障害を持ち、しかもその自覚がない人が、コミュニケーションが難しい状況で目の前に現れたとき、「どうぞお入りください」と家に入れてあげますか。まさか他人に対して指一本動かしてもいないのに、そのようなことをおっしゃっているわけではないですよね?
わたしが尊敬してやまない奥田知志牧師は、北九州の地でNPO法人抱樸をとおして、かれこれ30年以上もホームレス支援を続けている。そして、彼ら彼女らの社会復帰への支援だけではなく、今は派遣労働者その他、あらゆる追い詰められた人への支援へとその活動を広げている。その支援は上から目線で「してやる」のではなく、伴走型支援である。当事者と共に苦悩し、共に希望を見ている。当事者から力をもらい、当事者へ力を与えている。奥田牧師の講演を聞きに行ったとき、彼がこんなことを言った。
「社会とは、健全に傷つけあう関係のことです。でも今は、誰もが『人に迷惑をかけてはいけない』と思う、窮屈な社会になっています」
ずいぶん前に聞いたので彼の言葉どおりではないかもしれないが、わたしには天啓と響いたことはよく覚えている。傷つけてはならないことが配慮であるとわたしは思っていた。だが人と人との出遭いにおいて、傷つけあうトラブルは避けられないのだ。その事実を認めることは、牧師による相手へのハラスメントを正当化するのとはちがう。ハラスメントには幾つかのパターンがあるし、だからこそそれが起こらないよう予防することも可能だ。そうやってハラスメント予防を意識することを配慮というのである。
教会へと相談にやってくる人は、ただでさえ傷ついている。人と適切な距離感を保ったり、うまく関係をつくったりするのが苦手な人も多い。そういう人と向きあったとき、こちらも無傷では済まないことがある。だが、こちらが傷ついたときには、相手も傷ついているのだ。そういう傷つけあいも含めて「出遭っている」ということなのだとわたしは思う。
ところで上述した臨床心理士の先生は、こんなことも言っていた。
「患者さんのなかには、これみよがしに『先生はぜんぜんわたしの話を聞いてくれない』とか『前の担当の先生のほうがよかった』みたいなことを言ってくる人もいるんですよ。そういうときはモチベーションが下がりますねえ(苦笑)」
ほっとしたし、嬉しかった。なあんだ、先生もおんなじだな。わたしと同じことで悩んでらっしゃるんだな。臨床心理士だって人間だ。攻撃的なことを言われ続ければしんどくもなるだろうし、腹も立つ。だからといって「じゃあ帰れ。勝手にしろ」とは立場上言えないし。「そんなこと言うならお帰りください。わたしには受けとめられません」とキッパリ言えるわたしの立場のほうが、まだラクかもしれないな...いつもわたしの長話につきあってくださる先生に、感謝の思いがあふれた。
若い頃は、嫌われることがひたすら怖かった。面と向かってであれ陰であれ、否定されることを恐れた。でも最近はこう実感するようになってきた────あのイエスさまでさえ嫌われ、憎まれたんだぞ。礼拝堂に飾られている十字架がその証拠だ。あれだけ人々に治癒行為をし、希望に満ちた福音を説いたイエス・キリストでさえ、感謝されるどころか殺されてしまった。キリストじゃない、ふつうの人間でしかないわたしが、すべての人から好かれるなんてあるわけないじゃん。
わたしにとって愛に満ちたキリストが信仰の目標なのだとすれば、人から憎まれ、嫌われてでも言いたいことをキッパリ言うキリストもわたしの模範である。わたしはこれからも傾聴を志すだろう。伴走者として相手に寄り添いたいと願い続けるだろう。だが、それと同時に、ときには「それはちがうと思います」「わたしはこう考えます」とも言うだろう。誰かと出遭い、その誰かに伴走することは、その人に対して偉そうに振る舞うことでもなければ、その人に媚びへつらうことでもないのだから。