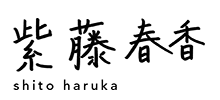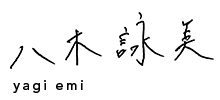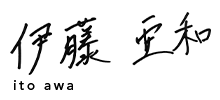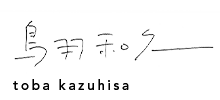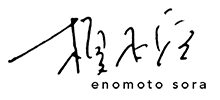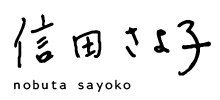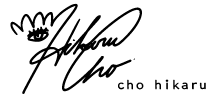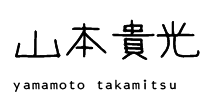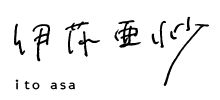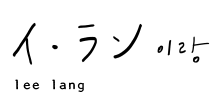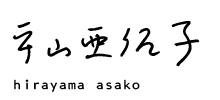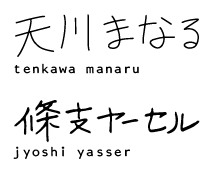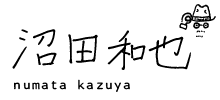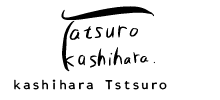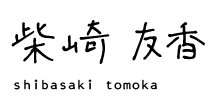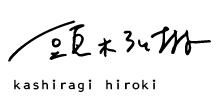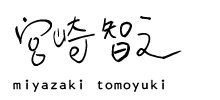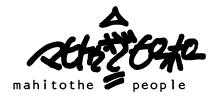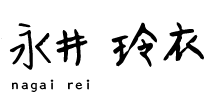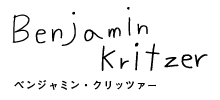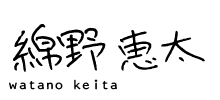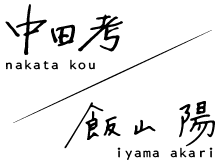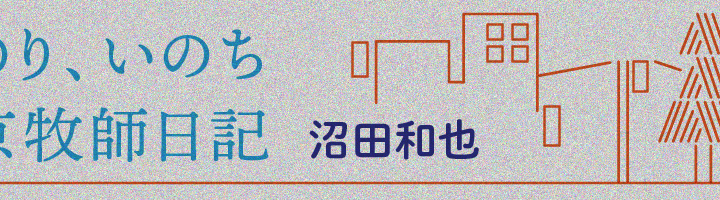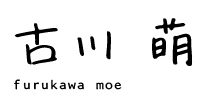膝の皿を金継ぎ
- 第8回 2月の日記(後半) 2024-03-28
- 第7回 2月の日記(前半) 2024-02-27
- 第6回 わからなさとの付き合い方 2024-01-29
- 第5回 サバイバル煮物 2023-12-28
- 第4回 ところでペットって飼ってます? 2023-11-30
- 第3回 喋る猫はいなくても 2023-10-31
- 第2回 夢のPDCA 2023-09-29
- 第1回 ここではない、青い丸 2023-08-31
アワヨンベは大丈夫
- 第9回 ごきげんよう(前編) 2024-04-18
- 第8回 ウサギ小屋の主人 2024-03-17
- 第7回 竹下通りの女王 2024-02-15
- 第6回 ママの恋人 2024-01-11
- 第5回 Nogi 2023-12-11
- 第4回 セイン・もんた 2023-11-15
- 第3回 私を怒鳴るパパの目は黄色だった 2023-10-13
- 第2回 宇宙人とその娘 2023-09-11
- 第1回 オール・アイズ・オン・ミー 2023-08-11
旅をしても僕はそのまま
- 第5回 アシジと僕の不完全さ 2024-01-27
- 第4回 ハバナのアルセニオス 2023-11-15
- 第3回 スリランカの教会にて 2023-09-16
- 第2回 クレタ島のメネラオス 2023-06-23
- 第1回 バリ島のゲストハウス 2023-05-31
おだやかな激情
- 第11回 なめらかな過去 2024-04-04
- 第10回 ちぐはぐな部屋 2024-03-05
- 第9回 この世の影を 2024-02-02
- 第8回 映したりしない 2024-01-11
- 第7回 とばされそうな 2023-12-04
- 第6回 はらはら落ちる 2023-11-01
- 第5回 もしもぶつかれば 2023-10-02
- 第4回 つややかな舌 2023-09-02
- 第3回 鴨になりたい 2023-08-01
- 第2回 かがやくばかり 2023-07-04
- 第1回 いまこのからだで目に映るもの 2023-05-31
- 第4回 うまくいかなくても生きていく──『十二月の十日』ジョージ・ソーンダーズ 2023-09-25
- 第3回 元恋人の結婚式を回避するために海外逃亡──『レス』アンドリュー・ショーン・グリア 2023-04-21
- 第2回 とにかく尽くし暴走する、エクストリーム片思い──『愛がなんだ』角田光代 2023-01-17
B面の音盤クロニクル
- 第8回 その日はあいにく空いてなくてね──Bobby Charles, “Save Me Jesus” 2024-03-08
- 第7回 クリスマスのレコードはボイコットする 2023-12-22
- 第6回 とうとう会得した自由が通底している 2023-05-06
- 第5回 あれからジャズを聴いている理由──”Seven Steps to Heaven” Feat. Herbie Hancock 2023-04-04
- 第4回 「本質的な簡素さ」の歌声──Mavis Staples “We’ll Never Turn Back” 2023-03-01
- 第3回 我が家にレコードプレイヤーがやってきた──Leon Redbone “Double Time” 2023-01-08
- 第2回 手に届きそうな三日月が空に浮かんでいる──Ry Cooder “Paradise and Lunch” 2022-12-07
- 第1回 きっと私たちが会うことはもうないだろう Allen Toussaint “Life, Love, and Faith” 2022-11-04
- 第16回(最終回) 「本物の詐欺を見せてやるぜ」@ジョン・ライドン 2022-07-04
- 第15回 文明化と道徳化のロックンロール 2022-06-10
- 第14回 ミスマッチにより青年は荒野を目指す 2022-06-02
- 10 もうひとつの現実世界――ポスト・トゥルース時代の共同幻想(後編) 2021-07-06
- 9 もうひとつの現実世界──ポスト・トゥルース時代の共同幻想(前編) 2021-05-03
- 8 あるいはハーシュノイズでいっぱいの未来 2020-05-05
第5回 伴走し続けることの難しさ、大切さ
教会のなかで出遭う人。教会の外で不意打ちのように出遭う人。一時は精神を病み、閉鎖病棟にも入った牧師が経験した、忘れえぬ人びととの出遭いと別れ。いま、本気で死にたいと願う、そんな人びとと対話を重ねてきた牧師が語る、人との出遭いなおしの物語。いのりは、いのちとつながっている。
伴走型支援という言葉がある。苦しみを抱えた当事者を助けてあげるのではなく、その人のそばで、その人の思いを受けとめつつ、こちらからもその人に思いを伝えながら、共に歩んでいこうとする試みを指す。伴走型支援が求められるのは、支援を必要とする人々が、モノとしての支援だけを求めているのではないからである。彼ら彼女らは今、孤立のなかにいる。そうした人々はしかし、明らかに追い詰められている状況であっても「放っておいて欲しい」と伴走を拒絶することもある。また、伴走しようとする人が本気で伴走してくれる気があるのか、試そうとすることさえある。拒絶されても、試され振り回されても、それでも伴走し続けることの難しさ。そして、それでも伴走することの大切さ。わたしはといえば、伴走することにことごとく失敗しながら、いつもそのことを考える。
イエス・キリストが十字架にかけられたとき、その両側には犯罪者も十字架に磔にされていたという。両側とは言うけれども、後世にイエスがキリスト(メシア、救い主)として篤い信仰を集めたからこその「真ん中」と「両側」なのであって、死刑を執行するローマ兵たちにしてみれば、べつにイエスが中心であるという意識はなかったであろう。帝国的に生かしておけない犯罪者をとりあえず今日は三人、並べて血祭りにあげるだけといった感覚だったのではないか。
十字架刑はただの死刑ではなく政治的な見せしめの刑であり、それに処せられるのは帝国に対して反乱を企てた者であったと言われている。イエスが少年の頃にもガリラヤのユダという指導者が立ち上がって謀反を起こしたが、鎮圧された。その際には2000人もの人々が磔にされたという(フスト・ゴンサレス『キリスト教史』)。2000もの死体がぶらさがる場所──息もできないほどの腐乱臭と共に、壮絶な光景が広がっていたことだろう。イエスはそれを見たかもしれないし、直接見ていなかったとしても、親類や地域の人々がその記憶に苦しむ姿は日々目にしていたかもしれない。その体験は直接間接に、まだ子どもであったイエスを傷つけたことであろう。戦地で生き延びた難民やその子どもたちが深い心の傷を負うのは、なにも現代だけではないはずだからである。イエスがキリストとして人々に福音を伝え、十字架で殺され、復活したことは、信仰的な文脈においては人々の救済のための神の意志である。そしてイエスは三位一体の子なる位格である。それを信じる信じないは別として、イエスもまたこの地上においては一人の人間として生涯を送った。そうであれば多感な子ども時代に戦乱を目の当たりにしたり、それの後遺症に苦しむ人々と接し続けたことは、彼の心身を深く傷つけたのではなかったか。その刻み込まれた傷痕と、彼が30歳を過ぎた頃、突如洗礼者ヨハネに続いて福音宣教を始め、自らもまたあの2000人のように磔にされる道をたどったこととは、無関係ではなかったであろう。
イエスはかくして、十字架に磔となった。そして上記のとおり、その両側には犯罪者が磔になっていた。
犯罪者は、個人的な強盗や殺人の犯人ではなかったかもしれない。もしも上記のとおり十字架刑が政治的なみせしめの意味を持つ、おもに反乱者を磔にする死刑であったのなら、これら二人の犯罪者は、なんらかの暴動を起こした者たちだったのかもしれない。犯罪者の一人がイエスをののしる。
「お前はメシアではないか。自分と我々を救ってみろ。」(ルカによる福音書23章39節 聖書協会共同訳)
ラーゲルクヴィストによる小説『バラバ』を、以前に読んだ。バラバはイエスの代わりに無罪放免された殺人者である。マルコやルカによる福音書によると、彼もやはり暴動の際に殺人をしたのである。だから体制にとって危険な人物という扱いになる。福音書において、彼の経歴や解放後の人生は語られない。そのバラバの、イエスの代わりに釈放されてからの歩みを想像して、ラーゲルクヴィストは小説にしたのである。小説では、バラバは最終的にもう一度捕まり、今度こそ十字架に磔となる。そこに至るまでの筆致については、ぜひ岩波文庫などを手に取っていただきたい。わたしがここで言いたいのは、たとえ福音書にはその名前すら記されていなくとも、十字架で磔になる人間にも人生があったということである。この犯罪者が十字架上で、隣にいるイエスをののしるに至るまでの歩みがあったのだ。そのことは、同じく磔になっている別の強盗の言葉からも分かる。彼はもう一人とはまったく別の人生を歩んできたのだろう。彼はもう一人をたしなめて、こう語る。
「お前は神を恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は、自分のやったことの報いを受けているのだから、当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。」(ルカによる福音書23章40-41節 同訳)
そして彼は続ける。
「イエスよ、あなたが御国へ行かれるときには、私を思い出してください」(同42節)
福音書において「二人の犯罪者」と一括りにされる彼らであるが、イエスへの態度は一人ひとりまったくちがう。いっぽう、ローマ兵たちからみて、ここには三本の十字架が立っているだけである。十字架の三人ともがみな、ほとんど同じ目の高さ、同じ激痛、同じ渇き、同じ窒息(十字架刑における主な死因は窒息といわれている。両腕を広げ、可能な限り後方へ引っ張ってみれば、喉が詰まる感じが分かる。)に苦しんでいる。彼ら三人は、いわば同じ苦しみを共有している。しかるに、そのうちの一人であるイエスに対しての、残り二人の態度は対照的なのだ。わたしはここに、その拘束と死のまぎわまで担保される、人間の自由を思わずにはおれないのである。
同じ苦しみ、同じ目の高さ。その目たちが見るのは、彼ら三人を嘲笑する群衆や兵士たちという、同じ光景。だが、三人がそれぞれが感じることはまったく異なる。三人それぞれが十字架上に至るまでの、その歩みがちがうからである。だが、それだけではない。どれだけ三人の人生を調べ尽くしたとしても、それでもなお、なぜ三人がこれほどに異なっているのかという、その最期の差異については、決して誰にも説明はできない。なぜ、一人の犯罪者はイエスを罵り、もう一人はイエスに救いを求めたのか。なぜ、両者は逆ではなかったのか。イエスに救いを求めたほうの犯罪者は、いったいいつからイエスに惹かれていたのか。十字架に磔にされる直前か。それとももっと前からなのか。なぜ、もう一人の犯罪者は、人生最期の瞬間を、これほど自暴自棄に他人をののしることに費やすのか。激痛と窒息のなかで、最期の力を振り絞ってイエスを罵倒する彼に、わたしは貴ささえ覚える。彼なりの最期の抵抗。彼なりの最期の自由の行使。
ある難病で苦しむ人と接したことがある。その人は難病の当事者会にも参加したという。だが、そこに参加していた別の人からの一言が、その人を深く抉った。
「あなたはまだ症状が軽いから、わたしよりずっといいよね」
難病の当事者同士が共に語りあうことをとおして、互いを支えあうことができる──健康な人の多くはそう考えるだろう。わたしもこの人の話を聞くまで、素朴にそう考えていた。もちろん、当事者同士だからこそ分かりあえることもある。だからこそ、このような当事者会が存在する。当事者が集まって語りあうこと自体が無意味なのではない。同じ痛み、同じ苦しみを抱えているとされる、その当事者同士が分かりあえないことが、げんにあるということが言いたいのである。
この問題に、わたしは牧師として何度も直面してきた。「苦しむ人同士の交流が、教会で出来たらいいですね」と言われることがある。じっさい、それができることもあるし、そう言ってもらえるのはとても嬉しいことである。だが、わたしから見て共通の苦しみを持つように思われる人同士が、分かりあえないこともあるのだ。そもそも、苦しむ当事者が「こんなに苦しいのは、わたしだけだと思う」と語るのを、わたしは何度も耳にしてきた。いや、それはその人が孤独だからそう言うだけじゃないか。じっさいに仲間と出会えれば、そんなこと言わなくなるよ……そうだろうか? なるほど、そういうこともあるかもしれない。だがわたしには、そんなに単純なこととは思えない。わたしの、わたしだけの苦しみ。この「わたしだけ」の「だけ」の部分にこそ、苦しみの苦しみたる所以があるのではないか。
十字架に磔となった犯罪者の一人は、なぜ同じ苦しみを味わっているはずのイエスを罵倒したのか。彼はこう思っていたかもしれない──イエスよ、お前はいいよな。だってほら、あそこ、お前の仲間たちが悲しそうに見ているぞ。お前のことを敬ってやまなかった女たちが。きっと男たちも、遠くから隠れて見ているだろうよ。お前は死ぬ。おれも死ぬ。だが、おれとちがって、お前はみんなに悲しまれながら死ぬことができるのだ。お前を憎む連中もいるが、お前を愛してやまない連中もいるだろう? そいつらがお前の死を泣き叫ぶ。なんて忌々しい! おれは独りで死ぬんだぞ。おれが生きていようが死んでしまおうが、誰もなんとも思わない。この連中を見てみろよ! おれが死ぬことが、こいつらの暇つぶし、憂さ晴らしなんだってよ。おれはつらい! 独りで生きてきて、独りで死んでいくんだからな。お前とおれを分けたのは、悲しんでくれる仲間の有無だよ。お前にはたくさん与えられて、おれには一人も与えられなかった! おれはどこで道を間違えたんだ?
この犯罪者は、自分から好きこのんで独りで生きてきたのか。自分で決断して「政治犯」になったのか。彼は後悔していなかったのか。いや、後悔しているからこそ、彼は最期まで抵抗したのではなかったのか。イエスに頭を下げることは、「わたしは独りぼっちでした。さみしかったんです」とイエスの前で泣くことだ。そんなことができただろうか。彼にとって自由を行使することは、最期まで悪党でい続けることだった。ではなぜ、もう一人の犯罪者はイエスに心を開いたのだろう。彼は、イエスをののしる男をたしなめさえする。この、イエスに心を開いた犯罪者は、最期の最期になって、自分が同伴者を求めていることを認めたのだ。ずっと独りで生きていた。あの男と同じように。だがもうこれ以上、独りでいることには耐えられない──そういう自分の弱さを、彼はイエスに告白したのだ。「イエスよ、あなたが御国へ行かれるときには、私を思い出してください」の「私を思い出してください」にこそ、この男の悲しみがある。このままこの世に存在しなかったかのように、すべての人々から忘却されること。おそらくはもう一人の男も恐れていることを、彼は言葉にした。最初からこの世にいなかったことになりたくない! 苦しんで死ぬけれども、せめて一緒に死ぬ、この目の前の人の記憶にとどめてもらいたい。この人が神の子であるなら、なおさら……。
ある夜、わたしのもとに一本の電話が鳴った。受話器を取ると、振り絞るような声が聴こえてきた。
「今から死にます。ただ、死ぬ前に、誰かには覚えておいて欲しかったんです。わたしが生きて、この世に存在していたということを」
その人は今まさに死のうとしていた。と同時に、誰かに自分の存在を覚えてもらおうとしていた。ということは、こうも言える。その人は誰かに覚えてさえもらえるのなら、生きのびることができる。その日以降、わたしはその人とのかかわりを持ち続けている。その人は他の人ともつながることができた。
その人は今でもわたしに「死にたい」と漏らす。その一つ一つの「死にたい」は本気である。しかし、ほんの数人であれ、その思いを漏らせる相手がいるという意味において、その人はまだ生きていられると思う。自分のことを覚えている人がいる。その事実は、ときに人を生かす力となる。
イエスと、その横で磔になった犯罪者と、さらにもう反対側で磔になった犯罪者。同じ状況で苦しむ彼ら三人、それぞれの思いは異なる。イエスは「私を思い出してください」と語った犯罪者に対して、こう答える。
「よく言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる」(同43節)
「あなたは今日、楽園にいる」ではないところに意味がある。「あなたは今日、私と一緒に楽園にいる」。孤立したこの男に、イエスは伴走することを約束したのである。楽園がどんな場所であるかなど、男にとってもはや問題にもならなかったはずだ。自分と一緒に最期まで、そして最期の向こうまで伴走してくれる人がいる。そのことこそが重要なのだから。
同時に、わたしはもう一人の男に想いを寄せずにはおれない。彼は最期までイエスを拒んだ。イエスをののしった。だが、イエスが伴走すべきは、まさにこのような人であった。イエスは「私を思い出してください」という言葉には「あなたは今日私と一緒に楽園にいる」という言葉で答えた。だが、「お前はメシアではないか。自分と我々を救ってみろ。」という言葉には答えなかった。間髪入れずに悔い改めたほうの男が彼をたしなめて「お前は神を恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに」と言ったから、イエスは彼に答えることができなかったのだ。もしも悔い改めた男が彼をたしなめず、あるいはたしなめるまでに間があいたなら、イエスはののしったほうの男に対しても必ず応えたであろう。イエスはこの不愉快な男にこそ伴走しようとしたであろう。わたしたちが、ときに「なんでこんなやつのために」と思う相手にこそ、支援の必要を感じるように。