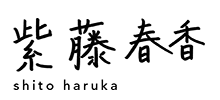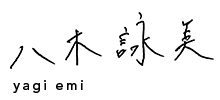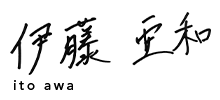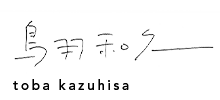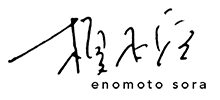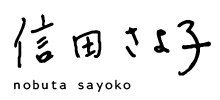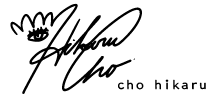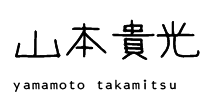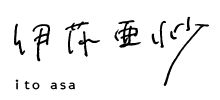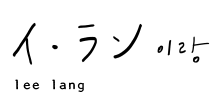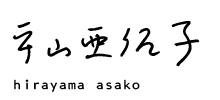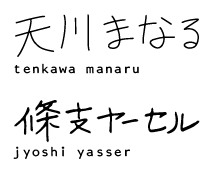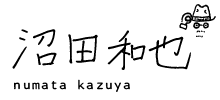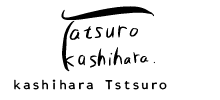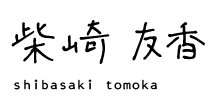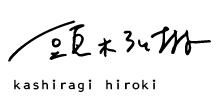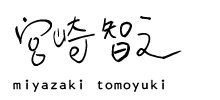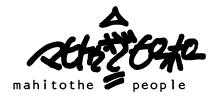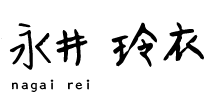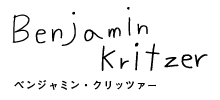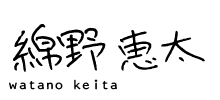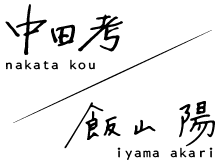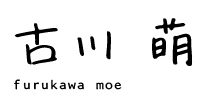膝の皿を金継ぎ
- 第8回 2月の日記(後半) 2024-03-28
- 第7回 2月の日記(前半) 2024-02-27
- 第6回 わからなさとの付き合い方 2024-01-29
- 第5回 サバイバル煮物 2023-12-28
- 第4回 ところでペットって飼ってます? 2023-11-30
- 第3回 喋る猫はいなくても 2023-10-31
- 第2回 夢のPDCA 2023-09-29
- 第1回 ここではない、青い丸 2023-08-31
アワヨンベは大丈夫
- 第9回 ごきげんよう(前編) 2024-04-18
- 第8回 ウサギ小屋の主人 2024-03-17
- 第7回 竹下通りの女王 2024-02-15
- 第6回 ママの恋人 2024-01-11
- 第5回 Nogi 2023-12-11
- 第4回 セイン・もんた 2023-11-15
- 第3回 私を怒鳴るパパの目は黄色だった 2023-10-13
- 第2回 宇宙人とその娘 2023-09-11
- 第1回 オール・アイズ・オン・ミー 2023-08-11
旅をしても僕はそのまま
- 第5回 アシジと僕の不完全さ 2024-01-27
- 第4回 ハバナのアルセニオス 2023-11-15
- 第3回 スリランカの教会にて 2023-09-16
- 第2回 クレタ島のメネラオス 2023-06-23
- 第1回 バリ島のゲストハウス 2023-05-31
おだやかな激情
- 第11回 なめらかな過去 2024-04-04
- 第10回 ちぐはぐな部屋 2024-03-05
- 第9回 この世の影を 2024-02-02
- 第8回 映したりしない 2024-01-11
- 第7回 とばされそうな 2023-12-04
- 第6回 はらはら落ちる 2023-11-01
- 第5回 もしもぶつかれば 2023-10-02
- 第4回 つややかな舌 2023-09-02
- 第3回 鴨になりたい 2023-08-01
- 第2回 かがやくばかり 2023-07-04
- 第1回 いまこのからだで目に映るもの 2023-05-31
- 第4回 うまくいかなくても生きていく──『十二月の十日』ジョージ・ソーンダーズ 2023-09-25
- 第3回 元恋人の結婚式を回避するために海外逃亡──『レス』アンドリュー・ショーン・グリア 2023-04-21
- 第2回 とにかく尽くし暴走する、エクストリーム片思い──『愛がなんだ』角田光代 2023-01-17
B面の音盤クロニクル
- 第8回 その日はあいにく空いてなくてね──Bobby Charles, “Save Me Jesus” 2024-03-08
- 第7回 クリスマスのレコードはボイコットする 2023-12-22
- 第6回 とうとう会得した自由が通底している 2023-05-06
- 第5回 あれからジャズを聴いている理由──”Seven Steps to Heaven” Feat. Herbie Hancock 2023-04-04
- 第4回 「本質的な簡素さ」の歌声──Mavis Staples “We’ll Never Turn Back” 2023-03-01
- 第3回 我が家にレコードプレイヤーがやってきた──Leon Redbone “Double Time” 2023-01-08
- 第2回 手に届きそうな三日月が空に浮かんでいる──Ry Cooder “Paradise and Lunch” 2022-12-07
- 第1回 きっと私たちが会うことはもうないだろう Allen Toussaint “Life, Love, and Faith” 2022-11-04
- 第16回(最終回) 「本物の詐欺を見せてやるぜ」@ジョン・ライドン 2022-07-04
- 第15回 文明化と道徳化のロックンロール 2022-06-10
- 第14回 ミスマッチにより青年は荒野を目指す 2022-06-02
- 10 もうひとつの現実世界――ポスト・トゥルース時代の共同幻想(後編) 2021-07-06
- 9 もうひとつの現実世界──ポスト・トゥルース時代の共同幻想(前編) 2021-05-03
- 8 あるいはハーシュノイズでいっぱいの未来 2020-05-05
第5回 犬のてんかんと偏頭痛(後編)
天気・体・社会。そこに関わる予感と予測の力。農家も流通業者も病気の人も、天気の恵みにあずかりながらも、ときに荒ぶるその流れにいかに沿うか腐心してきた。天気は予測できるのにコントロールできないという点で身体に似ている。どうやったら私たちは、天気とともに暮らし、社会を営むことができるのか。天気・体・社会の三者の関係を考える、天気の身体論/身体の天気論。
◎月と地球の交信
では、実際にセラフが亡くなる直前の二人はどんなやりとりをしていたのでしょうか。
最初にセラフにてんかんの症状があらわれたのは2020年の9月でした。そのときは玲那さんは入浴中でそばにはいませんでしたが、数日後に2回目が来て、そこから頻発するようになります。「普通に立ってるのがパターンって倒れちゃう。全身にぎゅーっと力が入って突っ張って、普段やらない動きなんですけど、反るみたいな感じになって、ガクガクってちょっとだけ小さく震えて、パターンって力が抜けて。そのぎゅーってなっている秒数を数えて記録していました。そのぎゅーが終わって、だらんとなって、軽ければすぐ目が開きます」[1]。それ以来玲那さんは、てんかんが来るのを常に「待つ」ような日々を過ごします。それは絶えず発作の可能性に対して緊張し続けるような時間でした。
しだいにセラフも発作の前兆を感じるようになります。「てんかんが3回目、4回目になってきた頃に、セラフが何かと戦っている感じなんですよね。ものすごくみけんにシワを寄せたりして、それでこっちも応答しているうちに、セラフのほうから予兆があると、私のところに来るようになりました。『れなー!くるー!』ってビームが来る感じです。それで何回目だったかな、カウントダウンできるようになりました」。倒れる瞬間を玲那さんも感じ取れるようになり、タイミングを合わせてセラフの体を支えてあげられるようになったと言います。「だんだん息があってくると、セラフの不安とかが分かって、その瞬間は分かるようになってくるっていう手応えはありました」。
さえさんとのやりとりは8月から続いていました。そのころからセラフは食欲のある日とない日の変化が激しい状態でしたが、さえさんが自分のその日の体調を玲那さんにメッセージで伝えていたのです。「『今日はすごい具合悪いけどセラくん大丈夫?』とか送ってくれると、セラフが食べなくても焦らないいで気長にやろう、みたいな気になれました」。他にも、さえさんの体調がいい午後の遅めの時間や夜に長い電話をしたり、セラフのトイレがうまくいかなかったときに、スマホでさえさんに見てもらって「セラフうんこ出してる?」と確認してもらったり、2人のやりとりは密度を増していきます。
ところが台風がやってくると、やりとりのトーンが変わります。本当に調子が悪くなると、メールや電話をすることすらできなくなるからです。でも、体に「しらせ」が来ていれば、メールや電話ができなくなることが、お互いに事前に予測できる。だから音信不通となる時間を前提としたコミュニケーションになるのです。玲那さんは、10月に台風が来たときのやりとりを鮮明に覚えていると言います。「台風が来て、小さい発作が断続的に続いていたんですけど、その日もさえちゃんから連絡もらってるんですよ。『具合悪い、来る気がする』『これから私寝込みます』みたいな内容で、お互いに台風が近づいてるっていうことは把握しているから、最終点呼みたいな感じですね(笑)」。
さえさんも、リアルタイムでコミュニケーションがとれないことを前提にしたやりとりをしていたと言います。「私も次の日の朝になっちゃうと具合悪くてメールが送れないかもって思うから、予感がしてるうちに、寝る前に玲那さんにメール送っとこう、みたいになる。リアルタイムで読んでくれなくても、やばそうな日のどこかでその情報をキャッチしてくれればいいかな、という感じです」。即時的なコミュニケーションが当たり前の現代において、あえてタイムラグを計算に入れてメッセージを送る。さえさんはここで、未来の玲那さんに向けてメールを出しています。明日の自分が経験するであろう体調の悪さと、明日の玲那さんが経験するであろう介護。その不安を見越して、「予感がしてるうちにメール送っとこう」と思う。このメールがあることで、玲那さんは、連絡がとれない間も「同志」として、さえさんと一緒に奮闘している感覚が得られていました。
このタイムラグを見越したコミュニケーションを、玲那さんは「地球と月の交信みたいだった」と話します。「地球と月みたいなやりとりですね(笑)。セラフが明らかに気候で体調悪くなると、さえちゃんもむこうで大変なんだろうな、って月を見上げる」。宇宙船が大気圏に突入するとき、しばらくは「ブラックアウト」と呼ばれる通信不能の時間帯に入ります。それと同じように、さえさんも体調が悪化するとしばらくは連絡がとれなくなってしまう。月を見上げるその時間は、いわば「祈る」ための空白でしょう。10月の台風でセラフが入院したときも、玲那さんはそのことをさえさんにすぐ伝えます。「あのときは本当にさえちゃんと『お疲れさまでしたー!』っていう感じでした。宇宙船と交信を切ってスタンバイしてるみたいな感じでしたね」。
◎違う病気が同期する
興味深いのは、このやりとりが、時間と空間を超えているだけでなく、異なる病どうしの連帯であることです。
この連載の第二回でも、同じような天気を介したやりとりをとりあげました。しかし、そのときに扱ったのは、あくまで病の当事者としては同じカテゴリーに入る人たちのコミュニティでした。しかし、このセラフ―玲那さん―さえさんのやりとりは、種も違ううえに病気も違います。セラフはてんかん、さえさんは身体表現性障害の当事者です。全く違う病の持ち主どうしが連帯しているのです。
このような連帯が可能になった原因のひとつは、さえさんの症状の「豊富さ」にあります。さえさんは10年以上病気とつきあうなかで、自律神経系の症状については「網羅するくらいの感じで経験している」と言います。だから、他の人の不調に関して、それがどんな症状であったとしても、たいていは似たような症状を自分の過去の経験から取り出すことができるのです。「たぶん拾えるところは多い」とさえさんは言います。さえさんはOriHime[2]を使ってカフェやその他のいろいろな場所で働いていますが、同じ職場の仲間のさまざまな話に対しても、自分なりに応えられることが多いと言います。「たぶんその子のがひどい状態だったとしても、薄めのグラデーションで自分もそういうことは経験してるから、話しやすいっていうのはちょっとあるのかな」。
セラフのてんかんに関しても、玲那さんの話を詳しく聞くうちに、それが「偏頭痛発作に近い」ことにさえさんは気づきます。さえさんにはてんかんの症状そのものはありません。しかし偏頭痛は持っていて、予防用に飲んでいた薬がてんかん用の薬だったのです。「私は20代から偏頭痛を持ってるんですけど、発作が起こるきっかけが偏頭痛と似てます。匂いとあと光、でも一番ひどいのはやっぱり気圧で、いきなり来て始まっちゃうとどうにもならないんですよ」。
こうしたさえさんの症状の特殊性に加えて、病気のちがいを超えた連帯を可能にしているより本質的な要因があります。それは、とりも直さず、天気が介在している、ということです。同じようなタイミングで症状が出て、ある人が症状で苦しんでいるときに、別の人も別の場所で苦しんでいる。そこに、通信不能な月と地球のような、「祈りあう」関係が生まれます。天気とは、いわば異なる病どうしを同期させる原理なのです。
これは、別の言い方をすれば、「原因」でなく「症状」に焦点が当たる、ということです。通常、体の不調はその原因によって分類されています。同じ吐き気という症状が出ていたとしても、原因が違えば「胃炎」と言われたり「適応障害」と言われたりする。しかし天気の変化によって不調が生じたとき、人々はまずはその症状に対応しようとして、工夫の知恵を交換しあいます。さえさんが実感を込めて語ってくれたように、「由来が何であったとしても、その症状自体は、意外と対処法って限られてたりする」。天気が生み出す同期のなかで、原因の違いを超えた似た症状どうしの連帯が生まれ、対処法をさぐりあいます。
この場合の対処法は、「体をあたためる」「部屋を暗くする」など、いわゆる対症療法的なものも含まれます。しかし、それだけではありません。「症状への向き合い方」のような、気持ちの持ち方に関するものも関係してくるからです。実は、玲那さんがさえさんから得ていたもっとも大きなものも、この部分に関するものでした。
セラフは、玲那さんが健康にきちんと気を使っていたこともあって、ずっと病気をしたことがありませんでした。だから「具合が悪い」という状態に慣れていない。食事やトイレなど何でも自分でやろうとして失敗してしまい、悔しそうだった、と玲那さんは言います。「セラフはやっぱり自分で排泄したいんですよね。決まったことをやりたい。ほんとに具合悪くなった経験ないヤツなんです。だから、食べたいし、動きたいし、自分でやりたい。足をカクカクなりながらトイレを自分で探しに行って、でも間に合わなくてうーってその場でしちゃう。まさに病気の経験がなくて、「悔しい」という感じでした。本人が対処できる前にどんどん次の段階に入っちゃって、それと彼は戦ってるなと思っていました」。
その状況は、まさにさえさんが病気になってから7−8年の状況に重なるものでした。さえさんは言います。「セラフがずっと健康だったから最初は具合が悪いことに慣れていない時期があったって玲那さんがさっき言ってたけど、その話も、私も最初は元気で、だんだん具合が悪い時期が健康な時期と同じぐらい長くなってきたから、体にそれほど丁寧な方ではないけど、なんか感覚で対処できるようになってきた」。症状そのものを抑えようとするのではなく、それがある前提で生活を送る方法を考えること。それを可能にしたものこそ、言うまでもなく「予兆」への敏感さと、コントロールの工夫でした。
玲那さんとセラフもまた、発作の予兆を捉えられるようになったこと、その結果、倒れたセラフの体を玲那さんが支えられるようになったことによって、てんかんとの付き合い方が変わってきます。「発作自体にセラフがあらがわなくなったんです。余計な不安を持たずに倒れられるようになった。そうしたらすごく楽になりました」。「不安を持たずに倒れられる」というのは、介助する側にとっても、介助される側にとっても、症状を前提とした生活のあり方です。こうして、病に対する態度のようなもの、天気に対する態度のようなものが、病気の違いを超えて、伝達されていくのです。
(この項了)
[1] 著者による、さえさんと西島玲那さんへの合同インタビューより。以下同様。http://asaito.com/research/2021/10/post_82.php
[2] オリィ研究所の分身ロボット。https://orihime.orylab.com/