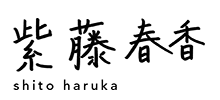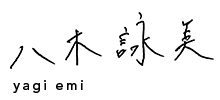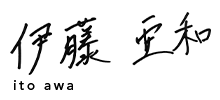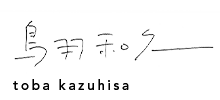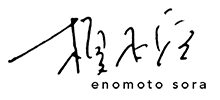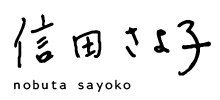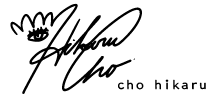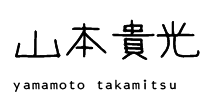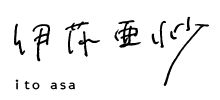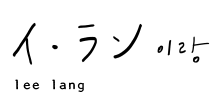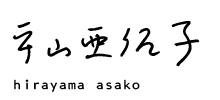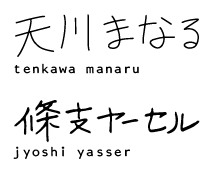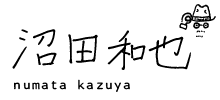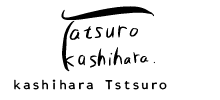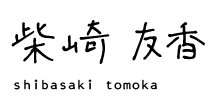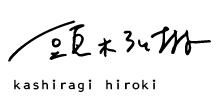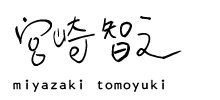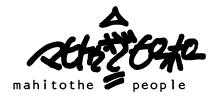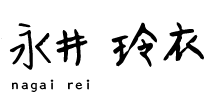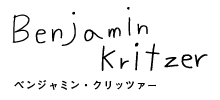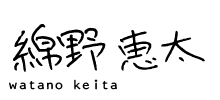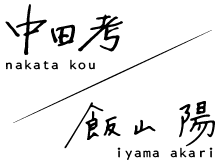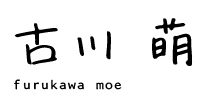膝の皿を金継ぎ
- 第8回 2月の日記(後半) 2024-03-28
- 第7回 2月の日記(前半) 2024-02-27
- 第6回 わからなさとの付き合い方 2024-01-29
- 第5回 サバイバル煮物 2023-12-28
- 第4回 ところでペットって飼ってます? 2023-11-30
- 第3回 喋る猫はいなくても 2023-10-31
- 第2回 夢のPDCA 2023-09-29
- 第1回 ここではない、青い丸 2023-08-31
アワヨンベは大丈夫
- 第9回 ごきげんよう(前編) 2024-04-18
- 第8回 ウサギ小屋の主人 2024-03-17
- 第7回 竹下通りの女王 2024-02-15
- 第6回 ママの恋人 2024-01-11
- 第5回 Nogi 2023-12-11
- 第4回 セイン・もんた 2023-11-15
- 第3回 私を怒鳴るパパの目は黄色だった 2023-10-13
- 第2回 宇宙人とその娘 2023-09-11
- 第1回 オール・アイズ・オン・ミー 2023-08-11
旅をしても僕はそのまま
- 第5回 アシジと僕の不完全さ 2024-01-27
- 第4回 ハバナのアルセニオス 2023-11-15
- 第3回 スリランカの教会にて 2023-09-16
- 第2回 クレタ島のメネラオス 2023-06-23
- 第1回 バリ島のゲストハウス 2023-05-31
おだやかな激情
- 第11回 なめらかな過去 2024-04-04
- 第10回 ちぐはぐな部屋 2024-03-05
- 第9回 この世の影を 2024-02-02
- 第8回 映したりしない 2024-01-11
- 第7回 とばされそうな 2023-12-04
- 第6回 はらはら落ちる 2023-11-01
- 第5回 もしもぶつかれば 2023-10-02
- 第4回 つややかな舌 2023-09-02
- 第3回 鴨になりたい 2023-08-01
- 第2回 かがやくばかり 2023-07-04
- 第1回 いまこのからだで目に映るもの 2023-05-31
- 第4回 うまくいかなくても生きていく──『十二月の十日』ジョージ・ソーンダーズ 2023-09-25
- 第3回 元恋人の結婚式を回避するために海外逃亡──『レス』アンドリュー・ショーン・グリア 2023-04-21
- 第2回 とにかく尽くし暴走する、エクストリーム片思い──『愛がなんだ』角田光代 2023-01-17
B面の音盤クロニクル
- 第8回 その日はあいにく空いてなくてね──Bobby Charles, “Save Me Jesus” 2024-03-08
- 第7回 クリスマスのレコードはボイコットする 2023-12-22
- 第6回 とうとう会得した自由が通底している 2023-05-06
- 第5回 あれからジャズを聴いている理由──”Seven Steps to Heaven” Feat. Herbie Hancock 2023-04-04
- 第4回 「本質的な簡素さ」の歌声──Mavis Staples “We’ll Never Turn Back” 2023-03-01
- 第3回 我が家にレコードプレイヤーがやってきた──Leon Redbone “Double Time” 2023-01-08
- 第2回 手に届きそうな三日月が空に浮かんでいる──Ry Cooder “Paradise and Lunch” 2022-12-07
- 第1回 きっと私たちが会うことはもうないだろう Allen Toussaint “Life, Love, and Faith” 2022-11-04
- 第16回(最終回) 「本物の詐欺を見せてやるぜ」@ジョン・ライドン 2022-07-04
- 第15回 文明化と道徳化のロックンロール 2022-06-10
- 第14回 ミスマッチにより青年は荒野を目指す 2022-06-02
- 10 もうひとつの現実世界――ポスト・トゥルース時代の共同幻想(後編) 2021-07-06
- 9 もうひとつの現実世界──ポスト・トゥルース時代の共同幻想(前編) 2021-05-03
- 8 あるいはハーシュノイズでいっぱいの未来 2020-05-05
第16回 吹雪の日には
「そういえば、この前実家に帰ってたんですね」と友人に言われて、そうですそうですと答えた。
近所に新しくできたスタバの隅の席で、「急に寒くなりましたねぇ」とか「夜なのに、田舎なのに人多いですねぇ」とか、こうして友人と二人、おしゃべりしている。お互い0歳児を育てながら、今夜は子どもを夫に任せて家を出てきた。友人は店内を見回しながら、かつて新宿で働いていたときのことを「昔はよくスタバ行ったな〜」とふり返る。しばらく店内にいると、ここがどこのスタバなんだかわからなくなってきますね、と話してちょっと笑う。
去年十一月に生まれた子どもを、まだ父と妹に会わせられていなかったこともあって、先日二年近くぶりに帰省した。夫は仕事で、子どもと二人、はじめての長旅にわたしはすっかり疲弊していた。しかし実家に来て三日経っても抜けきらない「気疲れ」があった。
その日は、わたしと子どもも合わせて家族全員で近所のジンギスカン屋に行った。授乳を終えて飲む念願のビールも、そこまで進まないしあまり酔いが回らない。家族でする外食自体がもう二年ぶりとか、と母は言っていた。遅れて合流した父は、この午後に次の自動車免許更新のためにはじめてメガネを作ってくると言っていた。しかし本人も母も妹も、そのことを話題にはしない。どんなメガネ選んだの、とかメガネ見せてよ、とか聞くでもない。父の方から見せるでもない。ただみんな、黙々と肉を焼く。誰も話さない。子どもが泣いて、わたしが一人で立ってあやしている間も会話はない。黙っていても間が持つからジンギスカンでよかった、と思った。
わたしが帰らなかった約二年の間に、わたしの知っていた実家は少し変わったようだった。家を出て、四年と少し。もちろんそこに暮らすメンバーが変われば関係性も変わるだろう。だから長いこと不在だったわたしが居づらく感じるのも、ほんとうはそんなにおかしいことじゃない。でも。ここは実家なのにな。わたしはいつでもここへ帰ってきて、両足を放り出してあー疲れた、って言えるはずじゃないんだろうか。実家って、無条件に居心地のいい場所なんじゃ、なかったっけ。そう考えるのはわたしの思い込みで、ただ甘えているだけ、図々しいんだ。
子どもとはじめて対面する妹も父も、ああこんな顔するんだと思うような破顔一笑、こんな声でこんな風に子どもに呼びかけてくれるんだ、とちょっと泣きそうになった。そうやって実家のリビングを好奇心いっぱい動き回る子どもを一緒に観察したり、母も父も妹も、それぞれと話すときは楽しいのに、わたしは、久しぶりに顔を合わせて話せることがこんなにもうれしいのに、なぜかもう、「みんな」で話すことはできなくなっている。会話のラリーってもっと自然に、たとえばわたしを除いた三人の間で誰かが話しかけて、そうやって関心をひらいて応えるということがない。そのことにわたしは帰省して三日目の夜に、ジンギスカンを焼きながらやっと気づいて、眠る前に少し泣いた。
「一番居心地のいい場所って変わりますよね」と友人は言う。そう、もうわたしは自分の帰る場所を新たに見つけたのだと言えばそうなのだ。だから家族はわたしが思うほど、別に大きく変わった訳じゃないのかもしれない。はたから見ればハラハラしても、本人たちは案外どうってことないのかもしれない。それでも、ずっと考えてしまう。
スタバからの帰り道、自転車を押しながら友人と並んで歩く。営業を終えた暗いガソリンスタンドの存在感に気づいて、「ここ、前からありましたよね?」「あったあった、ガソリンスタンドってやってない方が存在感あるんですねぇ」と言い合って通り過ぎた。またお茶しましょうねと手をふって別れてから、一人自転車を漕ぐ。「藤村食料品店」と書かれたぼろぼろのシャッターの前には小さなポストと、電話ボックスが隣り合って立っている。古式リラクゼーションの前の申し訳程度の弱々しいイルミネーションの光。整形外科の、煌々と白さを放つバカでかい看板。ペンキ塗りたての「歩行者注意」。夜だから、田舎だから、歩いている人はほかにいない。車もほとんど通らない。暗闇で生まれたての青い信号。呼応のような信号の点滅。街灯もわずかで、暗くて自転車を進めるのが怖い。ひゃ〜とか声に出て、ずんずん進む。いつもいつも、自転車に乗りながら感傷に浸るのはばかみたいだ。
わたしは実家の家族のことが大切だ。楽しかった、大切にされた記憶をいつまでも抱きしめて、ほんとうは一人ひとりが今考えていることを知らない。まだ小さい頃、父が母の手を繋ごうとして、わたしがそれを見つけて駆けて間に割って入って飛び跳ねながら帰った。思い出は漫画のコマのようにいつの間にか俯瞰される。あったことは変わらない。変わったのは関係なんだ。誰が悪い訳じゃない。それぞれの、父と母の、母と妹の、妹と父の関係をわたしは知らない。もしかしたら、許せないことがあったのかもしれない。ぶつかることをなんとか回避して、やってきたのかもしれない。「上手くやっている家族」として見過ごされない、消費されない、飲み込めない、えずくような脂身の塊のようなものがいつまでもあったのだとしたら。わたしはそれを知らずに、知ろうとせずにここまで来たのだ。
*
昼間、子どもが眠る横でムーミンとお茶をする。向かい合ってお茶を飲むのはわたしたちの日課で、夫がいることもあるが、たいてい二人でぽつぽつ喋りながら、あるいは黙ってお茶を飲む。
ムーミンはわたしの話を聞いて、「家族っていったい何なのでしょうね」と言った。うーん、と言ったきり黙っていると、
「私は、家族でしょうか」
いたって真面目な声。ムーミンの瞳は深い青色をしている。
ロマンチック・ラブ・イデオロギー吹雪から猛吹雪になるところがきれい 北山あさひ
好きな人と恋愛して、結婚して、子どもを産む。それが普通で正しい人間の営みなのだ、と掲げるロマンチック・ラブ・イデオロギーを、そのど真ん中を突き進みながらわたしはけれどいま、疑う。しあわせなわたしは、いつまでもこの状態だからしあわせなのか。しあわせだね、というまなざしをつねに誰かに向けられながら、それには微笑んで、けれど泣いて夫を罵る日がある。吹雪のなかを行くわれわれの視界は真っ白だ。目の前も、手を引き合う人の横顔さえも見えない。吹雪のなかでは風のうねりが耳を塞いで呼び合う声も聞こえない。さらに風は強くなり、雪がどんどん目や口に入る。猛吹雪に変わりつつあることを、渦中のわたしたちは知り得ない。それがうつくしいと言うひとは、ここではないどこかで、この吹雪を眺めている。
*
先日、いつも子どもと行くプレイルームで託児付きのワークショップが開かれた。ロープを編んで簡単な壁掛けのタペストリーを作るもので、抽選に当たった自分を含む「ママ」たちが集う。
講師の女性は明るかったが、参加者はなんとなく疲れて、コミュニケーションをこの場で取ることを始めから望んではいないようだった。おしゃべりしながらわいわいやるものだと思っていたから少し驚いて、しかしわたしもすぐにその空気に順応した。会議室に等間隔に座って手先に集中するそれぞれ、みんながみんな、同じように俯いている。全員が左手薬指に指輪を嵌めている。きれいに身なりを整えて俯きながら無言で黙々と指先を動かす一人ひとりが、そうするとみな重なりあってひとりになる――。
もしもわたしたちがこれからも一緒に生きていくならば。それは仮定ではなく、絶対の約束だった。運命なのだと、思い込んで微笑んで、みんなの前で誓い合った。今でもひどい言い合いの後には夫の首元に濡れた顔面を押しつけて「好きだよ」と言う。わたしたちを繋ぎ止めるこの「親密さ」こそが、誰にも渡せない、誰もほしがらない、このぐちゃぐちゃな編み目のマフラーだけが、吹雪のなかを進むためのたったひとつのアイテムなのだ。寒すぎる。凍えてしまう。家族は所与のものではない。だからきっと、わたしたちはわたしたちの家の窓を開けておかなければならないのだ。このほころびから、家族の破れ目から他者を招き入れて、お茶やお酒や、ご飯をふるまう。他愛もない話をいくらでもする。家族のほころびから生まれるだれかとの関係によって、束の間わたしたちの声は気丈さを取り戻すことができるのだ。
ふと、実家から帰る飛行機のなかのことを思い出す。子どもはひとしきりはしゃいだ後、こてんと寝た。着陸体制に入った飛行機がゆっくりと旋回して、そのとき光が太く、小さな窓に入ってわたしと、子どもの左頬を照らした。読んでいた本で子どもの頬を隠して、視界の端で陽光をわたしは感じていた。窓から覗く海面は深いみどりで、波はちいさく均されている。どんどん街が見えて、毎週行くスーパー、コジマ、ここいらでは高層のマンションの煉瓦色、そして街を象徴する興産の工場の、二本の煙突が見えた。高度を下げて、着陸する寸前まで煙突の煙がずっと見えて、ここに帰ってきたのだと思った。
家族のなかの、言葉がある。わたしたちだけのコミュニケーションがある。実家にもそれがあったのだ。「やだー」とか、「信じられないー」とか言って笑って、弾む会話があった。きっといまも、その破片をひとつず拾って、見せ合うことはできる。壊れたんじゃない。壊したのでもない。関係は、変わるのだからわたしはこれからも実家の家族が大切で、元気でいてほしくて、ほんとうは縋っているだけなのかもしれない。大切だからって壊さないように覆い被さってしまうのではなく、割れたって仕方ない。次はそう思ってひとりの他者として、子どもを連れてまた実家へ帰ればいい。家を離れた自分だから、束の間家族を繋ぐことができるかもしれない。
そしてわたしはわたしの家の窓を、寒くたって吹雪いてたって、いつも開けておかなければいけない。そのようにして、ムーミンはこの家にやってきたのだから。