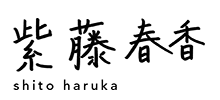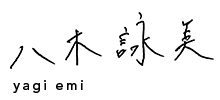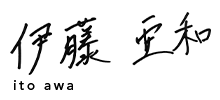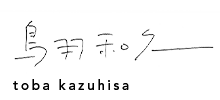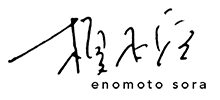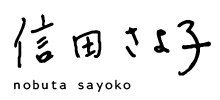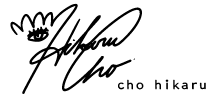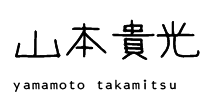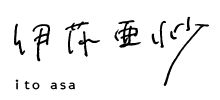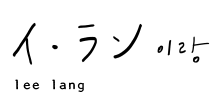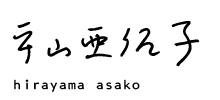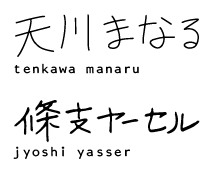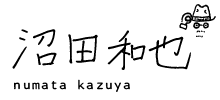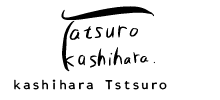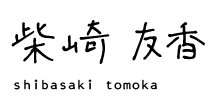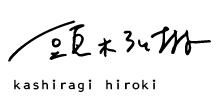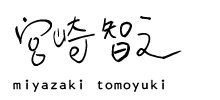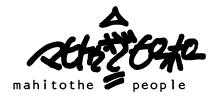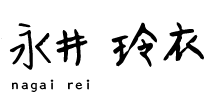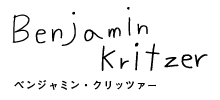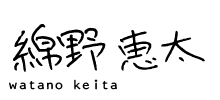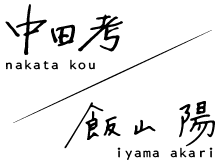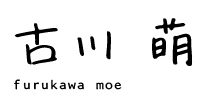膝の皿を金継ぎ
- 第8回 2月の日記(後半) 2024-03-28
- 第7回 2月の日記(前半) 2024-02-27
- 第6回 わからなさとの付き合い方 2024-01-29
- 第5回 サバイバル煮物 2023-12-28
- 第4回 ところでペットって飼ってます? 2023-11-30
- 第3回 喋る猫はいなくても 2023-10-31
- 第2回 夢のPDCA 2023-09-29
- 第1回 ここではない、青い丸 2023-08-31
アワヨンベは大丈夫
- 第9回 ごきげんよう(前編) 2024-04-18
- 第8回 ウサギ小屋の主人 2024-03-17
- 第7回 竹下通りの女王 2024-02-15
- 第6回 ママの恋人 2024-01-11
- 第5回 Nogi 2023-12-11
- 第4回 セイン・もんた 2023-11-15
- 第3回 私を怒鳴るパパの目は黄色だった 2023-10-13
- 第2回 宇宙人とその娘 2023-09-11
- 第1回 オール・アイズ・オン・ミー 2023-08-11
旅をしても僕はそのまま
- 第5回 アシジと僕の不完全さ 2024-01-27
- 第4回 ハバナのアルセニオス 2023-11-15
- 第3回 スリランカの教会にて 2023-09-16
- 第2回 クレタ島のメネラオス 2023-06-23
- 第1回 バリ島のゲストハウス 2023-05-31
おだやかな激情
- 第11回 なめらかな過去 2024-04-04
- 第10回 ちぐはぐな部屋 2024-03-05
- 第9回 この世の影を 2024-02-02
- 第8回 映したりしない 2024-01-11
- 第7回 とばされそうな 2023-12-04
- 第6回 はらはら落ちる 2023-11-01
- 第5回 もしもぶつかれば 2023-10-02
- 第4回 つややかな舌 2023-09-02
- 第3回 鴨になりたい 2023-08-01
- 第2回 かがやくばかり 2023-07-04
- 第1回 いまこのからだで目に映るもの 2023-05-31
- 第4回 うまくいかなくても生きていく──『十二月の十日』ジョージ・ソーンダーズ 2023-09-25
- 第3回 元恋人の結婚式を回避するために海外逃亡──『レス』アンドリュー・ショーン・グリア 2023-04-21
- 第2回 とにかく尽くし暴走する、エクストリーム片思い──『愛がなんだ』角田光代 2023-01-17
B面の音盤クロニクル
- 第8回 その日はあいにく空いてなくてね──Bobby Charles, “Save Me Jesus” 2024-03-08
- 第7回 クリスマスのレコードはボイコットする 2023-12-22
- 第6回 とうとう会得した自由が通底している 2023-05-06
- 第5回 あれからジャズを聴いている理由──”Seven Steps to Heaven” Feat. Herbie Hancock 2023-04-04
- 第4回 「本質的な簡素さ」の歌声──Mavis Staples “We’ll Never Turn Back” 2023-03-01
- 第3回 我が家にレコードプレイヤーがやってきた──Leon Redbone “Double Time” 2023-01-08
- 第2回 手に届きそうな三日月が空に浮かんでいる──Ry Cooder “Paradise and Lunch” 2022-12-07
- 第1回 きっと私たちが会うことはもうないだろう Allen Toussaint “Life, Love, and Faith” 2022-11-04
- 第16回(最終回) 「本物の詐欺を見せてやるぜ」@ジョン・ライドン 2022-07-04
- 第15回 文明化と道徳化のロックンロール 2022-06-10
- 第14回 ミスマッチにより青年は荒野を目指す 2022-06-02
- 10 もうひとつの現実世界――ポスト・トゥルース時代の共同幻想(後編) 2021-07-06
- 9 もうひとつの現実世界──ポスト・トゥルース時代の共同幻想(前編) 2021-05-03
- 8 あるいはハーシュノイズでいっぱいの未来 2020-05-05
第12回 捨てられない物
ここまで連載をお読みのみなさんは、うすうす気づいていると思いますが、私は、物を捨てられないタイプの人間だ。時代の流れに反するように、お菓子の包み紙も、山のようなCDも、タコの足を模した消えない消しゴムも、沖縄の海で拾った珊瑚も、捨てずにきた。熱い思いがこもっている品々もなくはないが、ちょっとそれとも違う。惰性で捨てないまま三十年あまりが経過したという物が中心のように思う。自分的にはその白黒つかない感じがたまらないと思っている。まとまらぬ人生だから文章を書いているのだとさえ思う。そんなわけで、時を閉じ込めたダンボールをいくつも保管してきた。
数年前に、妹が実家の片付けをしはじめ、納屋にためていた私の捨てられない物を捨てると言い出した。大反対した私にダンボールが何箱も届いた。「じゃあ、東京の家で保管せよ」ということだった。ダンボールを開けると同時に記憶の扉も開く。なるほど、物が記憶している風景があるのだ。
例えば、エビアンの空のペットボトル。これは、高校生のときに初めて行ったドイツで買ったものだった。ドイツのホームステイ先で、石鹸で顔を洗ったら乾燥して顔が真っ白に粉を吹いたことも思い出した。ドイツはものすごい硬水だったのだ。このエビアンも、日本の水とはまるきり違って牛乳のように重たかった記憶が蘇る。当時の私は、いちいち驚いて空のペットボトルを感動とともに日本へ持って帰ったのだった。いくら捨てられない私でも、今ならドイツのゴミ箱に入れて帰っただろう。このペットボトルは、十代の私の新鮮な驚きや感動を記憶していた。
もう別の人間だと言っていいくらいに、過去の私が好きだったものや感動した事柄は、今の私にはない感性によるものだ。それは、大学時代に作詞した曲を聴いていても思うことだけれど、全く別人の仕業なのだ。五年、十年、二十年、私達は環境に左右されながら、ゆっくりと脱皮を繰り返す。変化するというよりは、窮屈になって脱ぎ捨てるのに近い気がする。私が全部忘れても、物たちだけは残された殻の記憶を知っている。こんな時代もあったよね、と。だからこそ、全部捨てたい人がいることも分かる。思い出したくないことだってたくさんあるもの。それらは私も捨て去った。もう見ることもないので、思い出さない。それでいいと思う。
物は時代をまとっている。例えば、小学校の頃のお土産のキャラクターの顔。坂本龍馬がゆらゆら揺れる不思議な玩具も、水族館で買った鉛筆の上についたアシカも、小さなペンギンのぬいぐるみも、当時のキャラは、みんなサンリオ顔をしている。目が黒点で口がない、あの顔をしている。時代によって流行りがあるのだな、などと眺めるのも面白く、ますます捨てられない物になっていく。
いつだったか森美術館で開催されていたアンディ・ウォーホル展へ行った。彼は日常の物をそのまま600 箱以上ものタイムカプセルに詰め込んで保管していたそうで、その一部が展示されていた。チラシとか、切った足の爪、食べかけのサンドイッチまで入っていたそうだ。それを全部保管できる場所を持っている上に、アートに昇華できるのはウォーホルだからこそ。ただのトマト缶を、世界的なポップアートにしてしまう視点とか感性は流石だわと思いつつ、日常を見渡す。何気なく捨てているゴミは、「ゴミ」と思うから「ゴミ」になるだけで、しっかり「物」として意志を放っている。河原の石とか、森の木々にはない俗物的な面白さがある。ポスト投函されたチラシなどは、デザインが企業によって様々で面白く、なおかつ紙質や文言は一様に時代の流れをまとっていて、捨てる前に玄関で眺める。ウォーホルならタイムカプセルに入れるのだろう。こういうものこそ取っておいて十年後展示したら面白いのだろうな。
二〇一九年に、「捨てられない物展」を開催した。私の捨てられない物を陳列したガラクタ展になるはずだった。しかし……家にあれば迷惑がられるガラクタも、ギャラリーに美しく陳列された途端に息を吹き返し、物としての存在感を放っている。これは私自身がとても驚いたことだ。家を飛び出した途端に「物」はどれもこれも魂を震わせているではないか。
同時に「捨てられない物」というエッセイ集を作り、展示のキャプションにはエッセイの抜粋部分を添えた。訪れた人は「私もこれ持ってたなあ」とか「捨てなきゃよかったな」などと懐かしみながら見てくれた。この珍妙な展示に最初は人が集まらなかったけれど、次第に話題をよび、後半にかけて人が押し寄せたので一週間会期が延長になったほどだった。
四年が経った二〇二三年春、NHKの「阿佐ヶ谷アパートメント」という番組から連絡があった。〈捨てられない物〉と検索したら、私の「捨てられない物展」が出てきたらしい。「捨てられない物の特集をしたいのですが、高橋さんに出演いただけないでしょうか。捨てられない物とともに」。ついに時代が追いついた。
誰も、捨てなくていいんだよとは言ってくれなくて、追い立てられるように家中の物を捨てた人も少なくないだろう。しかし、番組の調査では、七〇%の人が捨てられないタイプだと答えていた。あれだけ、断捨離、断捨離と言われ、フランス人は服を少ししか持たないとか、三年使わないものは捨てよ、などと、捨てないことが悪とされてきたが、本当のところ捨てなくても良かったのだ。あの強迫観念はメディアによって作り出されたものだったのではないか。
捨てることと、持たないことは違う。ミニマリストなる人もこの頃増えてきたけれど、それはそもそも買わないことを前提としている。私も新しい服は買うし、捨てるものももちろんある。でも、そもそも炊飯器は持たないし、大きなテレビもない。捨てなくていいように、持たない選択を増やしている。そして、物のチャームポイントを見つけるのが得意なのかもしれない。それは、百均の物にもちゃんとある。デザイン性の高い物や高価な物だけが持っているわけではない。なんだか捨てられない物は、心の弱さとともにステイさせてやる勇気を持ちたい。
二〇二三年の暮れ、人々が大掃除をする中で、私は家中の捨てられない物を引っ張り出していた。「続・捨てられない物展」を吉祥寺のギャラリー芝生で開催することになったのだ。小さなギャラリーに美しく物を展示する。私一人ならこうはいかんだろう。ギャラリー芝生の目利きのオーナーが、その物の一番美しい角度と場所を見極めて展示してくれるからこそ、いっそう特別になるのだった。ガラクタとは言わせんぞと、生命を瞬かせている。
二〇一九年には並ばなかった、新しい捨てられない物も入ったこの展示は1月15日まで開催されているので(水・木・金は休み)間にあえば、あなたも埋もれてみてほしい。
好きなものを見せ合うよりも、捨てられない物を見せ合う方が、その人の本音の部分が分かるのではないかと思う。捨てられない物マッチング会なんて、いいんじゃないか。そこにトロフィーとかメダルを持ってくる人とは合わなさそうとか思ってしまう。写真とか、メダルは「捨てない物」に入るだろう。「捨てられない物」には無意識が詰まっている。無意識だからこそ、その人の生活の癖や根っこが見えてくるのかもしれない。