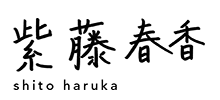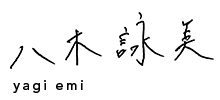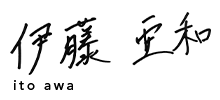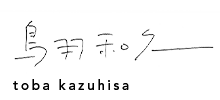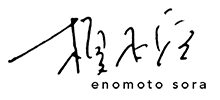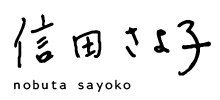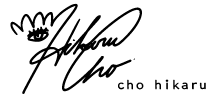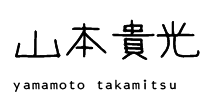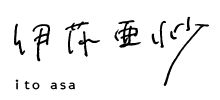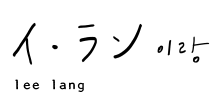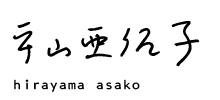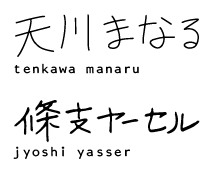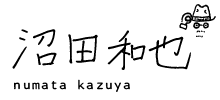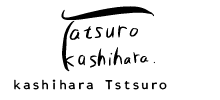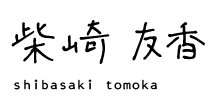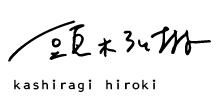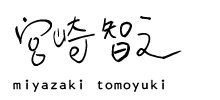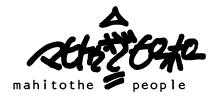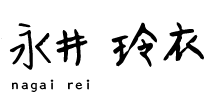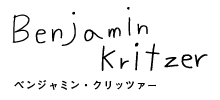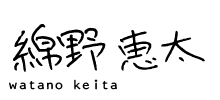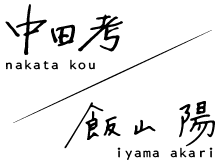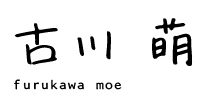膝の皿を金継ぎ
- 第8回 2月の日記(後半) 2024-03-28
- 第7回 2月の日記(前半) 2024-02-27
- 第6回 わからなさとの付き合い方 2024-01-29
- 第5回 サバイバル煮物 2023-12-28
- 第4回 ところでペットって飼ってます? 2023-11-30
- 第3回 喋る猫はいなくても 2023-10-31
- 第2回 夢のPDCA 2023-09-29
- 第1回 ここではない、青い丸 2023-08-31
アワヨンベは大丈夫
- 第9回 ごきげんよう(前編) 2024-04-18
- 第8回 ウサギ小屋の主人 2024-03-17
- 第7回 竹下通りの女王 2024-02-15
- 第6回 ママの恋人 2024-01-11
- 第5回 Nogi 2023-12-11
- 第4回 セイン・もんた 2023-11-15
- 第3回 私を怒鳴るパパの目は黄色だった 2023-10-13
- 第2回 宇宙人とその娘 2023-09-11
- 第1回 オール・アイズ・オン・ミー 2023-08-11
旅をしても僕はそのまま
- 第5回 アシジと僕の不完全さ 2024-01-27
- 第4回 ハバナのアルセニオス 2023-11-15
- 第3回 スリランカの教会にて 2023-09-16
- 第2回 クレタ島のメネラオス 2023-06-23
- 第1回 バリ島のゲストハウス 2023-05-31
おだやかな激情
- 第11回 なめらかな過去 2024-04-04
- 第10回 ちぐはぐな部屋 2024-03-05
- 第9回 この世の影を 2024-02-02
- 第8回 映したりしない 2024-01-11
- 第7回 とばされそうな 2023-12-04
- 第6回 はらはら落ちる 2023-11-01
- 第5回 もしもぶつかれば 2023-10-02
- 第4回 つややかな舌 2023-09-02
- 第3回 鴨になりたい 2023-08-01
- 第2回 かがやくばかり 2023-07-04
- 第1回 いまこのからだで目に映るもの 2023-05-31
- 第4回 うまくいかなくても生きていく──『十二月の十日』ジョージ・ソーンダーズ 2023-09-25
- 第3回 元恋人の結婚式を回避するために海外逃亡──『レス』アンドリュー・ショーン・グリア 2023-04-21
- 第2回 とにかく尽くし暴走する、エクストリーム片思い──『愛がなんだ』角田光代 2023-01-17
B面の音盤クロニクル
- 第8回 その日はあいにく空いてなくてね──Bobby Charles, “Save Me Jesus” 2024-03-08
- 第7回 クリスマスのレコードはボイコットする 2023-12-22
- 第6回 とうとう会得した自由が通底している 2023-05-06
- 第5回 あれからジャズを聴いている理由──”Seven Steps to Heaven” Feat. Herbie Hancock 2023-04-04
- 第4回 「本質的な簡素さ」の歌声──Mavis Staples “We’ll Never Turn Back” 2023-03-01
- 第3回 我が家にレコードプレイヤーがやってきた──Leon Redbone “Double Time” 2023-01-08
- 第2回 手に届きそうな三日月が空に浮かんでいる──Ry Cooder “Paradise and Lunch” 2022-12-07
- 第1回 きっと私たちが会うことはもうないだろう Allen Toussaint “Life, Love, and Faith” 2022-11-04
- 第16回(最終回) 「本物の詐欺を見せてやるぜ」@ジョン・ライドン 2022-07-04
- 第15回 文明化と道徳化のロックンロール 2022-06-10
- 第14回 ミスマッチにより青年は荒野を目指す 2022-06-02
- 10 もうひとつの現実世界――ポスト・トゥルース時代の共同幻想(後編) 2021-07-06
- 9 もうひとつの現実世界──ポスト・トゥルース時代の共同幻想(前編) 2021-05-03
- 8 あるいはハーシュノイズでいっぱいの未来 2020-05-05
第10回 思い出の医師・看護師たち(2)
患者の心理は敏感である。彼は病気の治療だけでなく、心の不安や孤独を慰めてくれるものに鋭敏になっている。わずかな医師の言葉や仕草のなかにも、彼はこの医師が自分の心の不安や生活の心配までわかってくれているか、それとも病気だけしか関心がないかを微妙に嗅ぎわけるだろう。
だから私は医学は科学の一つではあるが、たんなる科学ではないと思っている。医学とは臨床に関する限り、人間を相手にする人間学でもあるのだ。医学という学を通してはいるが、医師と患者とには人間関係があるのだということを絶対に忘れないでほしい。そしてその人間関係は医師と一人の苦しむ者との関係であるから、愛が基調にあってほしいと思うのは私だけではないだろう。
遠藤周作『春は馬車に乗って』文藝春秋
名医の見分け方(1)マニュアル医師と応用医師
名医の見分け方について、ついでに少し書いておこう。
これまでたくさんの医師と出会ってきた。たくさんの病院に通ったし、大学病院では、1、2年ごとに担当医が変わる。
それでだんだん、「ああ、こういう人は腕がよくないんだな」「こういう人は腕がいいんだな」ということがわかるようになってきた。
もちろん、確実なことではなく、例外もあると思うが、ある程度は参考になるはずだ。
まず、患者が何か質問したとき、医書に書いてある通りの返事しかしない医師がいる。こちらが聞き方を変えても、同じ返事をくり返すだけ。
そういう医師は、暗記力はあるのだろうが、応用力がない。そうすると、腕がよくない場合が多い。
というのも、患者は生き物なので、どうしてもひとりひとりちがいがあり、ある人にはよく効く薬が他の人にはあまり効かなかったりする。だから、医師は、患者ごとにさじ加減を変える必要がある。マニュアル通りの一律な治療では、うまくいかない。
腕のいい医師は、こちらが質問したことに対して、ちゃんと答える。医書に書いてあることそのままではなく、質問に合わせて、答え方を変えるのだ。どんなことを聞いても、その質問に対して答える。そして、わからないことはわからないと、ちゃんと言う。
あたりまえのようだが、これができる医師はそうとうレベルが高い。
名医の見分け方(2)例外嫌いと例外好き
患者が何か症状を訴えたとき、「それはこの病気とは関係ないですね」と言うのはいいのだが、それだけでスルーしてしまう医師も、名医とは言えない。
前回紹介した名医の場合は、そういう症状にけっこうこだわった。無視されないだけでも、患者としては嬉しいのだが、さらにそこから、意外な病状を発見したこともあった。
たとえば、潰瘍性大腸炎は、炎症が広がるときには直腸からひろがっていき、治るときには逆のほうから治っていくとされていた。ところが、直腸にはまったく炎症がないのに、「どうもおかしい」と言う患者がいた。そういうときには、たいてい「気のせい」とすまされてしまう。
しかし名医は、「気のせい」ですませず、大腸の途中から炎症が始まる場合もあるということを発見した。
(私は医師ではないので、この説明が医学的に本当に正しいかどうかはわからない。当時の見聞を書いている。ねんのため)
例外的な症状を嫌がり無視したがる医師は名医になることはなく、名医になるような人は、むしろ例外的な症状にとびつくようなところがある。そこから新発見があるかもしれないからだ。そして、無駄になることをおそれていない。
名医の見分け方(3)うるさがる医師と気さくな医師
患者は素人だから、おかしな質問もすることもある。「引っ越しをしたのがよくなかったんでしょうか」などと、わけのわからないことを言う場合もある。
そういうとき、うるさがって、話をさえぎるような医師も、あまりいいとは言えない。そうやって、「こっちは忙しいんだから、つまらないことは言うな」という態度をとっていると、患者のほうは、重要な症状までつい言わなくなってしまうからだ。
「昨日からお腹が痛いんだけど、言わなかった。いろいろ言うと、また怒られるから」などと、それは言うべきでしょということを、せっかく病院までやってきて言わない患者は少なくない。
名医と呼ばれる人には、患者と無駄話をする人が多い。これは、決して気さくということではなく、そういう話しやすい雰囲気を作ることで、患者から必要な情報をちゃんと得ているのだと思う。
名医の見分け方(4)疑われて怒る医師と歓迎する医師
患者が医師の治療法に疑問や不安を抱くこともある。「この薬で本当にいいのでしょうか?」とか「今の治療法でいいのでしょうか?」とか。
医師の側からしたら、よくない薬を出すわけないし、今の治療法がいいと思っているからやっているわけだから、うるさい質問だ。患者は黙って、こっちの言う通りにしていればいいんだ、と思うだろう。しかも、こっちを信頼していないということだから、不愉快でもあるだろう。
だから、不愉快そうにしたり、怒る医師もいる。
しかし、疑われて怒る医師というのは、だいたい腕がよくない。
私は大人になって水ぼうそうになってしまったことがあるのだが、ある大きな病院に行ったら、ただのカゼと診断された。もう水ぶくれとかできていたので、「こういうのができているんですが……」とあらためて言ったら、医師が怒り出した。
あとから看護師に、「あの先生はすごい先生なんだから、逆らったらダメよ。診てもらえるのはありがたいことなんだから」とさとされた。
しかし、私は経験上、診断を疑われて怒るような医師は、腕がよくないと可能性が高いと思っていたから、すぐに別の大きな病院に行った。すると、たちまち水ぼうそうと診断されて、隔離された。
なお、その怒った医師は、その後、何か大きなミスをしたらしく、患者から訴えられて、新聞記事にもなっていた。
とにかく、偉そうな医師というのは、まずあやしい。
医師に限らないが、本当に自分に自信のある人は偉そうにしない。なにしろ自信があるので、他人からさらに評価してもらう必要がないのだ。しかも、周囲からすでに高く評価されているから、もう承認欲求が充分に満たされている。患者から疑われても、そんなことは蚊に刺されたほども気にしないのだ。
患者にちやほやしてもらいたがる医師は、そうしないと承認欲求が満たされないということで、自信が不足していて、医師の間での評価も高くない可能性が高い。
医師の腕以外のことでコンプレックスを抱えているせいのこともあるから、絶対とは言えないが。
先の名医などは、患者から「その治療法にはこういう問題点があるのでは?」などと指摘されると、怒るどころか、じつに楽しそうに説明していた。治療法についてちゃんと理解を深めようとする患者をむしろ歓迎していた。ただ信じて従われるより、ちゃんと理解して納得してもらうほうがいいというのは、自分の治療法に自信のある人なら、それはそうだろう。
名医の見分け方(5)うろおぼえ医師と目の前に調べる医師
患者が薬について質問したりしたり、合併症について質問したりすると、目の前で薬事典を開いたり、医学書を開いたりして調べる医師がいる。
頭に入っていないのかと、不安になる患者もいるようだ。
しかし、これもむしろ自信のあらわれだ。患者の目の前で本を見たりすると権威が、と心配するようでは、自信のない医師だ。自信があれば、知らないことは、堂々と調べる。患者の前でも気にしない。むしろ、不正確な返事をすることをおそれる。
『壺算』という落語にこういうくだりがある。「昔、あるお大名が出入りの商売人を決めるときに、二人の商売人、どっちを出入り商人にしようかというときにやな、五文と五文でなんぼになる。片一方は十文でございます。片一方の商売人はそろばんを拝借……パチパチとはじいて、十文でございます。はあ、この男は堅いちゅうんで採用になったちゅうくらいのもんや」(『米朝落語全集 増補改訂版』創元社)
これと同じことだ。
患者の目の前で調べるのを恥と思い、うろおぼえで返事をする医師のほうが、信用ならない。
一生、よだれをたらしたままで、味もわからなくなる
名医と言えば、「神の手」と呼ばれる医師に治療してもらったことがある。
これは潰瘍性大腸炎ではなく、歯科のほうの話だ。
あるとき、歯の詰め物が取れた。これくらいは近所の歯医者でもいいわけだが、私は前にも書いたように、下血したときすぐに大学病院に行かなかったことを深く後悔していたので、このときはいきなり大学病院に行った。しかも、歯科を専門とする大学病院だ。当時はまだいきなり行くことができた。
大げさすぎたわけだが、これがけっきょく、よかった。親知らずが、横倒しに生えていて、隣の歯と接しているところが虫歯になっていることがわかった。
その親知らずは、少ししか歯ぐきから出ておらず、ほとんどが歯ぐきの中にあるということで、切開することになった。手術をして親知らずを取り出すのだ。
レントゲンを撮ると、その親知らずのすぐそばに神経が通っていることがわかった。私もレントゲンを見せてもらったが、歯のすぐそばに白い線があった。あれが神経ということだったのだろう(ちがうかもしれないが)。たしかに、近かった。
「神経にふれてしまう場合があり、そうすると麻痺が残る場合がある」と医師から言われた。
「麻痺? 麻痺すると、どうなるんですか?」
「程度によるけれど、口をちゃんと閉じられなくなって、よだれがたれてしまったり、味がわからなくなる場合もあります」
「それはどれくらい続くんでしょうか?」
「2、3カ月で治る場合もありますが、一生そのままということもあります」
これには驚いた。歯の詰め物がとれただけだったのが、下手すると、一生、よだれをたらして、食べものの味がわからなくなるかもしれないのだ。
それでなくても、食べることに苦労しているのに、さらに味がわからないなんて、あまりにひどすぎる。
「そんなことは、めったに起きないんですよね?」
手術の前はすべてのリスクを説明するから、今回もそれかと思った。それであってほしかった。
「そうでもないですね。わりと起きます」
いやな返事である。
しかし、よだれがたれたままの人とか、味がわからなくなった人というのは聞いたことがない。少なくとも身近にはいない。だったら、そうそうあることではないのでは?
と思ったら、いた。
ちょうどその後で打ち合わせをした編集者さんにこの話をしたら、「わたし、じつはそれになりました」と言われてしまった。
「よだれがたれていてもわからなくて、相手が変な顔をしているから、ようやく気づくという感じで。仕方ないんで、ずっとマスクをしていました。幸い、3カ月くらいで治りました」
たまたま打ち合わせをした編集者さんが体験者とは、これは逆に、かなりの人に経験ありなのか?
人は自分に病気や障害があっても、極力隠すから、本当は身近にそういう人がどれくらいいるのか、さっぱりわからない。
同意書へのサインをためらう人たち
ともかく、不安は高まったが、親知らずをこのままにしておくわけにいかないということだった。
麻痺が起きても文句を言いませんという同意書にサインするように求められた。それにサインしないと手術はできないと。
しかも、さらにいやなことを言われた。歯を抜くときに使う器具は、先が尖っている。しかも、かなり力を込めて使わなければならない。だから、ときどき、あごを突き抜いてしまうことがある。そういう場合もあるということを了承してほしいというのだ。
これもまた、すごく了承しづらい。金属の棒であごを突き抜くかもと言われて、しかたないですねとは、なかなか言えない。
歯医者というのは、歯を削られるのが痛い、おそろしいとずっと思っていたが、それよりも、もっとずっとおそろしいことがあるんだなあと、初めて知った。本当に、シェークスピアが言うように、「『どん底まで落ちた』と言えるうちは、まだ本当にどん底ではない」(『リア王』)。
同じ手術を受ける人が他にもいて、同じ長いテーブルに並んで、その同意書にサインをさせられた。大学生らしい若い男と、20代半ばくらいの女性と、私だ。みんな、ボールペンを持った手が、紙の上で止まっている。なかなかサインできるものではない。20代半ばくらいの女性が、思いきったようにががっとサインした。つられて、残りの2人もサインした。
手術はまた後日だ。
「神の手」現る
前置きが長くなったが、心が不安でいっぱいの私は、出会う人みんなにこの話をした。すると、その中に、医学書をたくさん作っている編集者さんがいた。そして、こう言ってくれた。
「ちょうど今、神の手と呼ばれる人の本を作っているんですけど、紹介しましょうか?」
その神の手のメールアドレスも教えてくれた。
医師に直接メールするというは初めてだったが、さすが神の手は偉そうにすることなく、メールで気軽にやりとりしてくれて、診てくれることになった。
なので、先の大学病院から、レントゲン写真を、その神の手がいる大学病院のほうに送ってもらえるよう手配もした。
そして、いよいよ神の手のところに行った。すると、まだレントゲン写真が届いていなかった。がっかりだった。検査からやり直しになるのかと思ったら、神の手はこう言った。
「レントゲンがなくても、外から見ればわかりますから、問題ないです」
さすが神の手だった。とはいえ、歯と神経の関係をレントゲンで診てもらわなくては、やっぱり不安だ。
「歯と神経がぎりぎりなんだそうです」
と私は説明した。
でも、神の手はぜんぜん平気で、
「大丈夫です。じゃあ、抜きましょうね」
と言い出した。
私は今日は診察だけで、手術は別の日と思っていたので、まるで覚悟がなかった。
「えっ! 歯ぐきを切る手術になるんですよね?」
と問いただすと、神の手は、
「そんなことしなくても大丈夫。ちょっとでも歯ぐきから歯が出ていれば、抜けますから」
と、これまたさすがの返事だ。
さらにもうひとつの心配もぶつけてみた。
「器具であごを突き抜いてしまうこともあると聞いたんですが……」
「ああ、そんなことはしないから大丈夫」
ということで、外来で、行ったその日に、親知らずを抜いてもらうことになった。
「神の手」の神ワザ
私は、さすがだと思いながらも、じつはかなり不安だった。
レントゲンも確認しないって、それはありなの? 本当に神の手だったらいいけど、インチキ神様だったら大変なことになる。だいたい、どういう経緯で本を出すことになったか知らないけど、本を出そうとするような医師は、いかさま師が多い。などと、いろんな思いが、頭の中をぐるぐるする。信じたい気持ちと、信じきれない不安。
親知らずは抜けた。痛み止めをもらって帰ったが、「たぶん、いらないと思いますけどね」という神の手の言葉通り、飲むことはなかった。痛くならなかったからだ。
中学のとき、抜歯をしたことがある。そのときは、痛くて痛くて、ひと晩中、眠れなかった。
大変なちがいで、感動した。
そして、麻痺は起きなかった。
神の手は、本当に神の手だったのだ。
なお、「私は虫歯の治療は苦手だから、させないほうがいいですよ」と言われて、他の医師を紹介してくれた。神の手は、抜歯と手術ばかりをやっているようだった。そんなに細かく専門化されているものなのかと驚いた。
名医が精神病院に
潰瘍性大腸炎のほうに話を戻そう。
先の名医に診てもらっているとき、入院しなければならなくなったのだが、大学病院のベッドに空きがなく、待っているわけにもいかなかったので、名医が「自分がいちばん信頼している弟子」というのを紹介してくれた。そちらの病院なら入院できるということで。
名医のもとを離れるのはなんとも残念だったが、しかたない。そこに行った。
すると、さすがに名医の弟子だけあって、その人も素晴らしい医師だった。やさしくて、腕がよかった。この両方がそろっていると、本当にありがたい。
このままこの医師にずっと診てもらってもいいかなと思っていた。
ところが、この医師が鬱病になって精神病院に入院してしまった。
患者仲間のうわさでは、性格がよくて、おとなしくて、腕がいいので、周囲の他の医師たちから妬みやそしりを受けて、雑用とかもどんどん押しつけられて、精神的な苦痛と過労から、ついにそういうことになってしまったということだった。
知らなかったが、医師が鬱病になることも少なくないとのことだった。とくに精神科の医師に多いそうで、それは意外だった。
柚の香りがする医師
やさしい医師で思い出したが、病院に入院しているとき、みんなが「あの先生はやさしい」と口をそろえて言うほど、やさしい医師がいた。
ところが、その医師は、とてもくさかった。体臭がではない。いつも柚の香りがするのだ。
柚の香りなら、いいにおいなわけだが、なにしろ強すぎるのだ。
その先生が通ったあとは、しばらく、「あっ、あの先生が通ったな」とわかる。六人部屋に入ったとき、もうその先生が去った後でも、「来ていたな」とわかる。
そばに来て話しかけられると、あまりににおいが強烈で、息をするのが苦しく、ちゃんと話ができない。しかし、いい先生だから、くさいというような顔はしたくない。いやな顔をしないようにするのに一生懸命で、何を話したかわからないほどだった。いい先生だから、そばにいてくれると嬉しいのに、一刻も早く去ってほしいと願ってしまう。
なんでこんなことになったかというと、その先生にずっとかかっている患者によると、医師というのは消毒薬のにおいがしたりして、患者さんの中にはそれで緊張してしまう人もいるから、柚の香りの香水をつけるようにしたのだそうだ。さすがにやさしい先生で、細やかな配慮だ。それで、患者さんたちからも、いい香りだと評判がよかった。で、それをずっと続けているわけだ。
問題は、においというのは、ずっと嗅いでいると、だんだん感じなくなる。だから、ずっとその香水をつけている当人が、ちゃんとにおいを感じるくらいつけていると、だんだん量が増えていくことになる。
その結果、大変なにおいになってしまったのだ。当人だけは、気がついていない。当人的には、ほのかに香っている程度なのだ。
普通、途中で誰か注意してあげるのだろうが、なにしろ、いい人なのである。そんないい人に、「くさいですよ」とは誰も言えない。
その結果、ずっとそのままなのだ。「どうしても言えない」と、みんな言っていた。
いい人だからこそ、言ってもらえたほうが助かることを言ってもらえないこともあるんだなと知った。
看護師さんに申し訳なかった話
ずいぶん話が長くなってしまった。
医師や看護師の話は、思い出していると、どんどん出てきてしまう。
看護学校からやってきた若い実習生たちの話とか、採血の練習をさせてくれと言ってきて、血管から血をぴゅーと噴出させて、キャーッと逃げていった医師のこととか。
きりがないので、これくらいにしておくが、最後に、申し訳なかったなあと思う看護師の話を。
病院のトイレで大便を漏らしてしまった話を『食べることと出すこと』(医学書院)に書いた。当時、20歳で、人前で漏らしたのは初めてだった。夜だった。通りかかった看護師から、トイレのバケツと雑巾で自分で始末するように言われた。
この話には、じつはつづきがある。
病室に戻った私は、尿道からバイ菌が入ったのではないかと気になってきた。パンツをはいた状態で、大量の下痢を漏らしたので、性器まで便まみれになった。拭きはしたが、なにしろ病院のトイレの雑巾だ。
大便のほうでさんざん苦労していたから、小便のほうは普通にできることが心の支えだった。これで小便のほうまで、膀胱炎とかになって、苦労するようになったら、もうとても心がたまらないと思った。
そこで、ナースセンターにいって、そこにいた看護師に、事情を話して、消毒してもらえないかと頼んだ。
その看護師は、「わかりました」と、消毒薬を用意してくれて、病室のベッドで私の性器を丁寧に消毒して、「これでもう大丈夫ですよ!」と安心させてくれた。
これはとてもありがたかった。
冷静に考えれば、あとから外側を消毒しても、もう細菌やウイルスが尿道まで入ってしまっていたら、なんにもならない。消毒は気休めでしかない。看護師も、それはわかっていたはずだ。それでも、患者の不安を取り除くために、つきあってくれたわけだ。
そもそも、夜は人数も少なくて忙しい。しかも、夜中のナースセンターにひとりでいたときに、ちょっと精神状態のおかしくなった20歳の男が、「オレの性器を消毒してくれ」と迫ってきたわけだ。その看護師は女性だった。もしかすると、性器を見せたいとか、さわらせたいという変態かもしれない。本当に看護師は大変だと思う。
うまくなだめてくれて、不安を取り去ってくれて、今度は冷たくされなかったことで、私はずいぶん助かった。
すごく感謝しているのだが、もう看護師としか思い出せず、顔も名前も思い出せない。
この看護師だけでなく、いろんな医師や看護師にお世話になってきて、とてもとても感謝している。
しかし、よほど特徴的な人でない限り、その顔や個性を思い出すことはない。
申し訳ないことだ。
医師や看護師をひとりの人間として見たくない
医師や看護師に、それぞれの顔、個性を認めるというのは、じつは患者側にとっては、ためらわれることでもある。
少なくとも、私はかなりためらう。
なぜかというと、医師や看護師を〝ひとりの人間〟として認識してしまうと、人間なのだから、当然、ミスもあるし、人をひいきしたり嫌ったりするということになる。
患者としては、ミスをされたり、嫌われたりというのは、とてもおそろしいことだ。そういう人間くささを、医師や看護師が持っていてほしくない。だから、あまり人間として認識したくないのだ。自分たちとはちがう、優秀な一族であってほしいのだ。
九州で生まれ育った女性で、とても優秀で、仕事もできる人なのに、何を話していても、「でも、男性はもっとできますよね」的なことを言う人がいた。
「そんなことはない、女性のほうが優秀な場合もいくらだってある」と言っても、絶対に受け付けない。「そうは言っても、やっぱり男性はすごいです」などと言う。
心から言っている様子を見て、男性社会で育てられると、こんなふうになってしまうものなのかと驚きを感じたが、洗脳されているだけではなかったのかもしれない。
医師や看護師を頼りにするしかしかたない私のように、男性社会で生きていくしかなかった彼女にとって、男性が優秀でなければ困ってしまう。だから、優秀であってほしい、そう信じたいという気持ちが強かったのかもしれない。私も、医師や看護師に、そういう願いを抱き、もしかするとろくでもない人間かもしれないという現実からは、目をそらしたかったから……。
個性を感じさせない人たちこそ、本当は素晴らしい!
思い出を語ろうとすると、どうしても個性のきわだった人たちのことばかりになってしまうが、本当は、いちばんすごいのは、目立たなかった人たちだ。
目立たなかった人たちというのは、きちんと治療し、きちんと看護した人たちだ。少なくとも、ひどいことをしなかった人たちだ。
特別なすごいことをしたということへの評価だけでなく、何もひどいことをしなかったというのも、もっともっと評価されるべきだと思う。医療の世界では、とくに重要だ。
きちんと治療し、きちんと看護する人たちによって、患者は生かされている。
いろいろ書いてきたが、基本的に私は、医師と看護師に深く深く感謝している。その人たちがいなければ、生きていられなかったのだから。今こうして、なんだかんだ書いていられるのも、その人たちのおかげだ。
申し訳ないことに、顔や個性は思い出さなかったりするが、背中をさすってくれた手、注射をしてくれた手、触診してくれた手、処方してくれた手……さまざまな手を思い出す。それは、ただの手ではなく、特別な手だ。
普通に仕事をしていると、たいして感謝もされず、何かあるとすぐに文句ばかり言われる。そう感じている医療者の方もおられるかもしれない。
患者も、病気のときは崖っぷちで落ちそうになって必死だから、冷静ではないし、対応が普通ではなくなる。
しかし、あとから、しみじみ感謝している患者は多いものだ。
私もまたそのひとりだ。
(この項了)