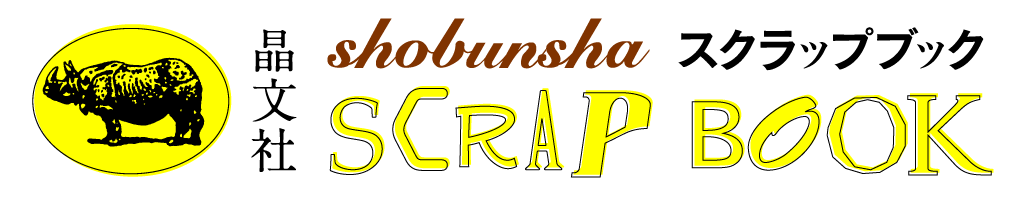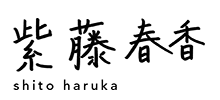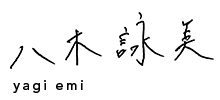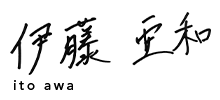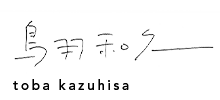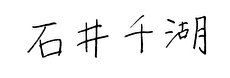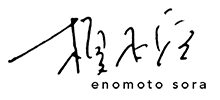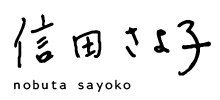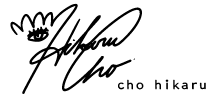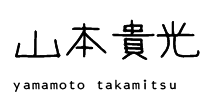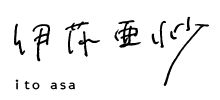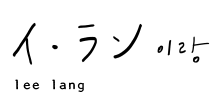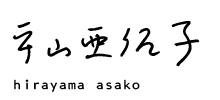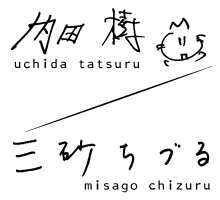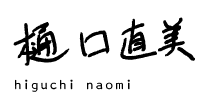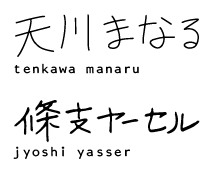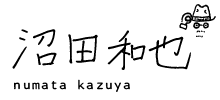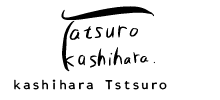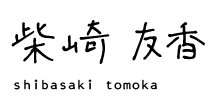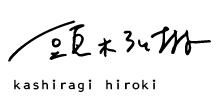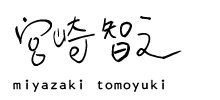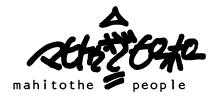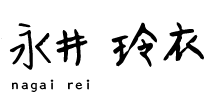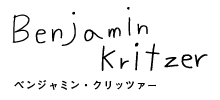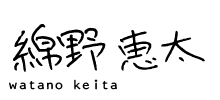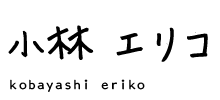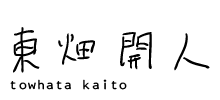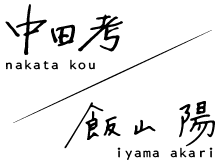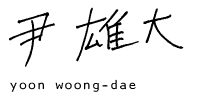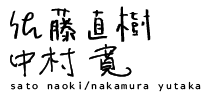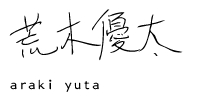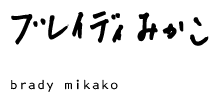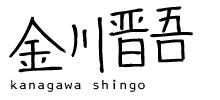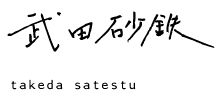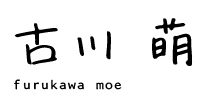膝の皿を金継ぎ
- 第8回 2月の日記(後半) 2024-03-28
- 第7回 2月の日記(前半) 2024-02-27
- 第6回 わからなさとの付き合い方 2024-01-29
- 第5回 サバイバル煮物 2023-12-28
- 第4回 ところでペットって飼ってます? 2023-11-30
- 第3回 喋る猫はいなくても 2023-10-31
- 第2回 夢のPDCA 2023-09-29
- 第1回 ここではない、青い丸 2023-08-31
アワヨンベは大丈夫
- 第9回 ごきげんよう(前編) 2024-04-18
- 第8回 ウサギ小屋の主人 2024-03-17
- 第7回 竹下通りの女王 2024-02-15
- 第6回 ママの恋人 2024-01-11
- 第5回 Nogi 2023-12-11
- 第4回 セイン・もんた 2023-11-15
- 第3回 私を怒鳴るパパの目は黄色だった 2023-10-13
- 第2回 宇宙人とその娘 2023-09-11
- 第1回 オール・アイズ・オン・ミー 2023-08-11
旅をしても僕はそのまま
- 第5回 アシジと僕の不完全さ 2024-01-27
- 第4回 ハバナのアルセニオス 2023-11-15
- 第3回 スリランカの教会にて 2023-09-16
- 第2回 クレタ島のメネラオス 2023-06-23
- 第1回 バリ島のゲストハウス 2023-05-31
おだやかな激情
- 第11回 なめらかな過去 2024-04-04
- 第10回 ちぐはぐな部屋 2024-03-05
- 第9回 この世の影を 2024-02-02
- 第8回 映したりしない 2024-01-11
- 第7回 とばされそうな 2023-12-04
- 第6回 はらはら落ちる 2023-11-01
- 第5回 もしもぶつかれば 2023-10-02
- 第4回 つややかな舌 2023-09-02
- 第3回 鴨になりたい 2023-08-01
- 第2回 かがやくばかり 2023-07-04
- 第1回 いまこのからだで目に映るもの 2023-05-31
- 第4回 うまくいかなくても生きていく──『十二月の十日』ジョージ・ソーンダーズ 2023-09-25
- 第3回 元恋人の結婚式を回避するために海外逃亡──『レス』アンドリュー・ショーン・グリア 2023-04-21
- 第2回 とにかく尽くし暴走する、エクストリーム片思い──『愛がなんだ』角田光代 2023-01-17
B面の音盤クロニクル
- 第8回 その日はあいにく空いてなくてね──Bobby Charles, “Save Me Jesus” 2024-03-08
- 第7回 クリスマスのレコードはボイコットする 2023-12-22
- 第6回 とうとう会得した自由が通底している 2023-05-06
- 第5回 あれからジャズを聴いている理由──”Seven Steps to Heaven” Feat. Herbie Hancock 2023-04-04
- 第4回 「本質的な簡素さ」の歌声──Mavis Staples “We’ll Never Turn Back” 2023-03-01
- 第3回 我が家にレコードプレイヤーがやってきた──Leon Redbone “Double Time” 2023-01-08
- 第2回 手に届きそうな三日月が空に浮かんでいる──Ry Cooder “Paradise and Lunch” 2022-12-07
- 第1回 きっと私たちが会うことはもうないだろう Allen Toussaint “Life, Love, and Faith” 2022-11-04
- 第16回(最終回) 「本物の詐欺を見せてやるぜ」@ジョン・ライドン 2022-07-04
- 第15回 文明化と道徳化のロックンロール 2022-06-10
- 第14回 ミスマッチにより青年は荒野を目指す 2022-06-02
- 10 もうひとつの現実世界――ポスト・トゥルース時代の共同幻想(後編) 2021-07-06
- 9 もうひとつの現実世界──ポスト・トゥルース時代の共同幻想(前編) 2021-05-03
- 8 あるいはハーシュノイズでいっぱいの未来 2020-05-05
第14回 フジロック2021
ひどい時代だと思う。今まで生きてきて、ここまで苦しい時代もない。分断は加速し、弾は飛び交ってないが代わりに言葉が飛び交い、見えない血を誰もが流してる。
感染者が増え続ける中で二日後から始まるフジロックフェスティバル。音楽とはなんだろうと心臓に突きつけられる。
同じ日に出演する盟友、折坂悠太から「マヒト君はどう考えている?」といった内容のメールで目を覚ます朝。つくづくしれっと逃げさせてくれないなと思いながら、胸の不安感に聴診器を当てる。フジロックの開催に否定的な意見が出てきてくるのは想像していたし、迷いがないと言えば嘘になる。
思えば、もうここ数年、潔白と呼べる状態はなく、常に濁りと混乱を携えながら生きてきたように思う。リスクを天秤にかけ、知らぬ間に何かの加害に参加し、見えない何かの暴力に加担していたり、一方で誰かの救いになっていたり。聖人君子などではない、叩けば埃の立ち上がる混乱の日々を、それでもできるだけ優しさと共にありたいと思いながら駆け抜けている。
昨日会った知人はフジロックのために二週間前からカレンダーに〇を打って好きな外出と酒を控えていると言った。「フジにこの夏の全てをかけている」と屈託のない笑顔で言った。命という絶対的な価値の前に、弁明にもならないなんでもない声なのは承知だが、一人一人かける想いや生きていることの意味や意義、そしてそのレイヤーはバラバラだ。
ライブをめぐるこのコロナ禍の日々はひどいものだった。十分な補償のない中で自粛しろという勧告が自動音声のように繰り返され、音の出る現場は槍玉に挙げられ袋叩きにあった。乱発する意味のあるのかないのかわからない緊急事態宣言に右往左往させられ、イベントは潰された。仕事を失って転職した音楽関係者を何人も知っているし、経営破綻するライブハウスの思い出を発表と共に熱く語ったところで時はすでに遅い。
フジロックはネームこそ大きいが巨大な自治だ。関係者の空気感から察するにもう一年延期する体力はないだろう。それほどまでに逼迫した現状はまず周知すべきだと考える。
生業にしてるのは音楽関係者だけではない。祭りにまつわるケータリングなどのフード出店も切実だ。巨大なビジネスに見えるがその内情は顔の見える個人店舗によって成り立っている。資本のあるオリンピックとそこは大きく違うだろう。
わたしはアーティストだ。音楽で生計を立てている。会社員が電車に乗って出勤するのと同じように、わたしは現場にいき、音を鳴らす。それが仕事だからだ。
「収束した折に」という弁もあるが、わたしたちは記号ではないし、この世界はゲームではない。セーブもできない日々は当然巻き戻しもできない。
事実、GEZANのオリジナルメンバーであるベースのカルロスは2021年1月1日のフジロックの配信ライブで、舞台を降りていった。突きつけられるコロナ禍が変えてしまったもの。比喩ではなく、腕がもがれたような痛みと共に目の前が真っ暗になった。恥ずかしい話、一人の部屋で何度泣いたかわからない。
命という絶対的な価値の前にはこれも自分勝手の一言で片付けられてしまうかもしれないけど、わたしたちには今しかない。そしてそんなわたしたちを生かすフジロックという稀有でオルタナティブな現場にこそ生き残って欲しい。
もっと個人的な話をする。八雲という新しい仲間ができた。
18年しか生きていないこいつの人生をわたしたちは変えた。宮崎からオーデションを受けにきた日から東京に住み始めた。灰野敬二の異次元のライブを見せつけられ精神を崩したり、およそ会ったこともない数の特殊な人間と交わり目を回しながら、晩には必ずスタジオに入り連日音を出し続けた。今ではフジが初ライブだってことを忘れるくらい、馴染みきっていて、ちゃんとGEZANの顔をしていて頼もしい。
これだってオリンピックの時にあった、選手は頑張ってるんだから論と何も変わらないよな。ただそのアスリートの特権を使いたいと願うほどに、わたしはステージの上の時間を今、懇願してる。

今こう記していて、俯瞰や客観のない、極めてオンの状態の視点からの言葉のチョイスだなと我ながら思う。なんらリスクについての言及などない稚拙な文章だと自覚する。
今日においてミュージシャンは音を出すだけの仕事でなくなった。その選択や振る舞いについても自覚が求められていて、見誤ると奈落の底に落ちる。オリンピックをめぐるゴタゴタもその一つの象徴に思う。
加害に参加しかねないというのは自覚というより覚悟の部類だろう。この先も覚悟はずっと試されていくことになる。仮に比喩ではない銃弾が飛び交う中で、こんな時に音楽なんてやっている場合か? そんな議論はこの先も常につきまとうだろう。
わたしはアーティストなのでアートや表現が人を真の意味で生かす可能性を信じている。
あらためて、音楽とは、生きるとはなんだろうか?
綺麗事でうまく絡めとりたいんじゃない。何かのためといった大義名分ではなく、主語を最小にした個人の意志でしかない。最後は誰かや何かのためじゃなく、わがままに極めて近いわたしの意志であり、あなたの意志だ。
出演するアーティストに言いたいのは、迷うことは当然として、主催に全責任をあずけたり、開催の是非について判断をくだせないというスタンスは卑怯だと思う。その前提のままステージに上がるのはフェスの運営にも失礼だし、議論を放棄して今日の開催というものは成立し得ない。
客も演者も主催も同じ船の上にいる。全感覚祭というフェスを主催する身としてそう言える。この時代はただの傍観者でいることを許さない。それぞれが何を大切にし、未来と呼ばれる時間に何を残すか、その選択が委ねられている。
批判や責任の一端を背負った上で、個人的な切実さを理由にわたしはフジロックのステージを全うする。
生きてるってこういうことだよなっていう一つの感触を、人と人が出会うことの意味を、2021年の混乱と光の同軸で鳴らし、記号ではない血の通った存在の振動でもって、苗場を爆発させる。

photography Yusuke Yamatani