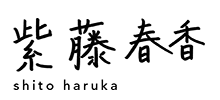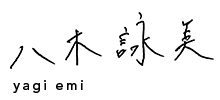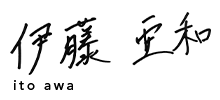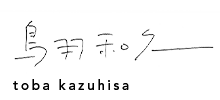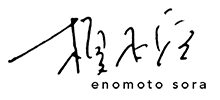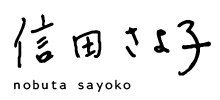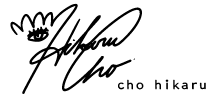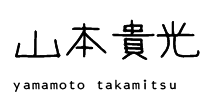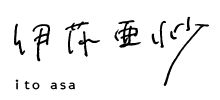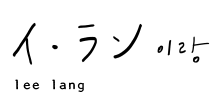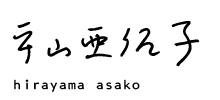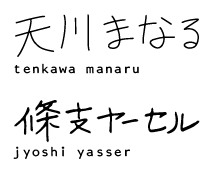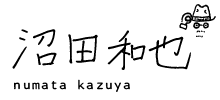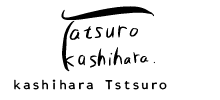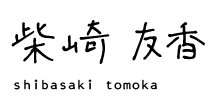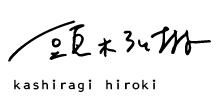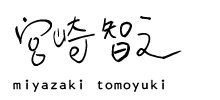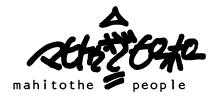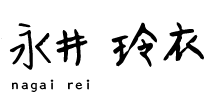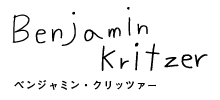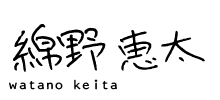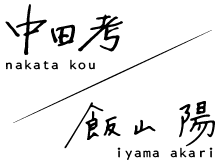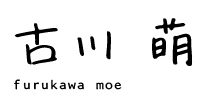膝の皿を金継ぎ
- 第8回 2月の日記(後半) 2024-03-28
- 第7回 2月の日記(前半) 2024-02-27
- 第6回 わからなさとの付き合い方 2024-01-29
- 第5回 サバイバル煮物 2023-12-28
- 第4回 ところでペットって飼ってます? 2023-11-30
- 第3回 喋る猫はいなくても 2023-10-31
- 第2回 夢のPDCA 2023-09-29
- 第1回 ここではない、青い丸 2023-08-31
アワヨンベは大丈夫
- 第9回 ごきげんよう(前編) 2024-04-18
- 第8回 ウサギ小屋の主人 2024-03-17
- 第7回 竹下通りの女王 2024-02-15
- 第6回 ママの恋人 2024-01-11
- 第5回 Nogi 2023-12-11
- 第4回 セイン・もんた 2023-11-15
- 第3回 私を怒鳴るパパの目は黄色だった 2023-10-13
- 第2回 宇宙人とその娘 2023-09-11
- 第1回 オール・アイズ・オン・ミー 2023-08-11
旅をしても僕はそのまま
- 第5回 アシジと僕の不完全さ 2024-01-27
- 第4回 ハバナのアルセニオス 2023-11-15
- 第3回 スリランカの教会にて 2023-09-16
- 第2回 クレタ島のメネラオス 2023-06-23
- 第1回 バリ島のゲストハウス 2023-05-31
おだやかな激情
- 第11回 なめらかな過去 2024-04-04
- 第10回 ちぐはぐな部屋 2024-03-05
- 第9回 この世の影を 2024-02-02
- 第8回 映したりしない 2024-01-11
- 第7回 とばされそうな 2023-12-04
- 第6回 はらはら落ちる 2023-11-01
- 第5回 もしもぶつかれば 2023-10-02
- 第4回 つややかな舌 2023-09-02
- 第3回 鴨になりたい 2023-08-01
- 第2回 かがやくばかり 2023-07-04
- 第1回 いまこのからだで目に映るもの 2023-05-31
- 第4回 うまくいかなくても生きていく──『十二月の十日』ジョージ・ソーンダーズ 2023-09-25
- 第3回 元恋人の結婚式を回避するために海外逃亡──『レス』アンドリュー・ショーン・グリア 2023-04-21
- 第2回 とにかく尽くし暴走する、エクストリーム片思い──『愛がなんだ』角田光代 2023-01-17
B面の音盤クロニクル
- 第8回 その日はあいにく空いてなくてね──Bobby Charles, “Save Me Jesus” 2024-03-08
- 第7回 クリスマスのレコードはボイコットする 2023-12-22
- 第6回 とうとう会得した自由が通底している 2023-05-06
- 第5回 あれからジャズを聴いている理由──”Seven Steps to Heaven” Feat. Herbie Hancock 2023-04-04
- 第4回 「本質的な簡素さ」の歌声──Mavis Staples “We’ll Never Turn Back” 2023-03-01
- 第3回 我が家にレコードプレイヤーがやってきた──Leon Redbone “Double Time” 2023-01-08
- 第2回 手に届きそうな三日月が空に浮かんでいる──Ry Cooder “Paradise and Lunch” 2022-12-07
- 第1回 きっと私たちが会うことはもうないだろう Allen Toussaint “Life, Love, and Faith” 2022-11-04
- 第16回(最終回) 「本物の詐欺を見せてやるぜ」@ジョン・ライドン 2022-07-04
- 第15回 文明化と道徳化のロックンロール 2022-06-10
- 第14回 ミスマッチにより青年は荒野を目指す 2022-06-02
- 10 もうひとつの現実世界――ポスト・トゥルース時代の共同幻想(後編) 2021-07-06
- 9 もうひとつの現実世界──ポスト・トゥルース時代の共同幻想(前編) 2021-05-03
- 8 あるいはハーシュノイズでいっぱいの未来 2020-05-05
第7回 おかまいなくの店
「おかえりなさい」と、家族みたいに迎えてくれる居酒屋さんがある。今日も寒かったですねと言って丁寧にお手拭きを出してくれたりして。最初は照れくさいけれど、こちらの心をじんわりと温めてくれ、いつしかほっとできる場所になっていく。
だけれど、今日は本当に一人になりたいわという日もあるわけで。仕事でもやもやしたり、理不尽なことに巻き込まれたり、お腹が空きすぎて血圧が下がっているときなどなど。一人になりたい。でも家には帰りたくない。かといって行きつけの居酒屋で「ただいま」と元気に言えそうもない。ましてや、カウンターで隣になった人に愚痴りたいテンションではないのだよ。
最寄り駅に到着した私は、蛍光灯の煌々と照らす黄色い看板の元に向かう。
「はーい。らっしゃいませ~」
やる気のない声で、女性店員が口を動かす。
「あ、一人です」
「お好きなところどうぞ」
私は、いつも奥から二番目の厨房のよく見えるテーブル席に腰掛ける。やさぐれたときに来る中華料理屋は、いつも東南アジア系の男女三人が働いている。何度行っても顔を覚えてくれる気配はない。笑いかけてくれることもない。ホールを一人で仕切る彼女は、小柄な体でビールジョッキを何個も運び、また空のジョッキを下げてくる。
「ビールと、小エビの素揚げと、もやしナムルと、タコの唐揚げをお願いします」
「はい」
数分後、運ばれてきた生中をぐびぐび飲んで、小エビを口に放り込む。この店、サイドメニューであろう小エビの素揚げが一番美味しい。その他は、美味しくも不味くもない。ものによっては、まずい寄りである。けれども、やさぐれている日の私にはそのくらいが丁度いい。めちゃくちゃ美味しい店になられては困るのだ。こんな日はあまり期待したくないのだ。
周りを見渡すと、私と同じようにむしゃくしゃした一日の締めに、ここで飲んでいそうな人が間隔を空けて座っている。ときどき家族連れもいるが、どのテーブルもただ無心にレバニラを食べて酒を飲んでいた。
厨房では、白いエプロンの料理人が中華鍋からボウッと火を立てていない。Tシャツとジーパン姿の、長身な東南アジアの青年二人がチャーハンを作っている。キャップを後ろ向きに被って。ハーフパンツのときもあるし、クロックスの時もある。公園でバスケでもしそうに、めちゃくちゃラフなのだ。
厨房のテーブルには何かよくわからない白いものが入ったでっかい袋が積み上がっていたりして、それを適当にえいやっと鍋に入れて混ぜている。唐揚げが、チャーハンが、餃子が、レバニラが、八宝菜が、どんどんできていく。カウンターに出すと、それを女性が運んでいく。淡々と繰り返される厨房の平熱を、私はぼうっと眺めている。作った料理が片っ端から、目の前にいる人達の腹におさまっていくのが、すごく健全な気がした。
まるで工業製品でも作るように、今日も明日も明後日も、黙々と繰り返される彼らの日常がここにある。見るからに老夫婦がやっていそうな町中華屋の中に、いつも無愛想な三人組。タイやカンボジアの食堂を思い出す。客もスタッフも平等なのだから、笑ったりせんでもええのだ。
新しい小説が始まりそうだ。けれども客とのハートフルな交流はなさそうだし、三人の仲が良さそうな感じもない。恋愛もの……ないなあ。この三角関係はないやろなあ。もしかしたら二人のボーイズラブの方が良さそうな気もするなあ。中華鍋を持つ二人を見てひとしきり妄想にふける。
とにかく放ったらかしである。お手拭きさえ、ティッシュさえ置いていない。下げてもくれないので皿が積み上がる。でも、不衛生というわけではない。トイレには緑色の液体石鹸もある。今日の私はいっこうに放置で構わない。絡まないでくれて助かっている。私は続いてハイボールを飲み、レモン酎ハイを飲む。
30年以上前からある店だと聞いたことがあるので、もともとは地元の人がやっていたのを、今はこの三人がやってたりするのかな。これはバイトで、彼らにもっと他の夢があるのかもしれない。
美味くも不味くもない中華屋を求める人々も、決して話しかけたり常連同士で仲良くなったりもしない。常連という概念もないだろう。それでも、まっすぐ家に帰りたくなくてここで人の平熱に触れていたいんじゃないかな。私もそうだ。食事のためだけでなく、今日できた傷や疲れを誰かの平熱で満たしたいのだと思う。それぞれが、ぼんやりと光る蛍光灯みたいに互いに気づかれない程度の明かりで照らし合っているんだ。
「天津飯お願いします」
ある日、散々飲んで食べた最後に天津飯を頼んでしまった。
「ハーフにしますか?」とか、「かなりのボリュームありますが大丈夫ですか?」とか聞いてくれればいいのに、彼女はもちろん何も言わない。やさぐれの私もそんなこと聞かない。
数分後、沼のような天津飯がほろ酔いの私の前に登場する。どう見ても、野球部のための天津飯である。
食べてみると、あれ、美味しい。もしかしたらこの店で一番の美味しさかもしれない。
最近気づいたけれど、どの料理も、行く度に少しずつ美味しくなっている気がする。彼らは本気で料理に目覚めたんじゃないだろうか。
「おかえりなさい」とか言いだしたらやだなあ。いや、でもそれはそれでいいか。
おつりを受け取って、
「ごちそうさま」と言う。
「ありがとざいましたー」といういつもの挨拶を聞きながら店を出た。お腹はぱつぱつ。私の憂鬱は半分に減っていた。