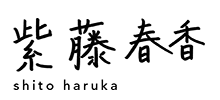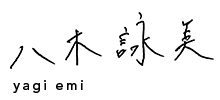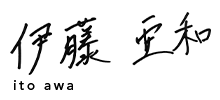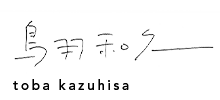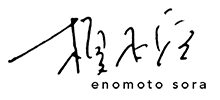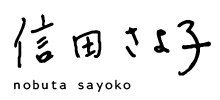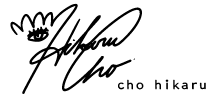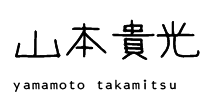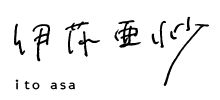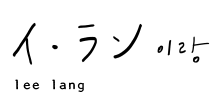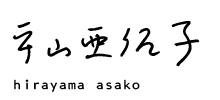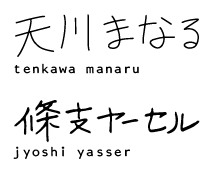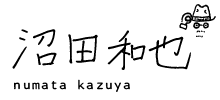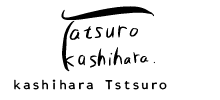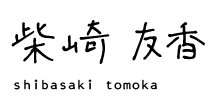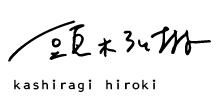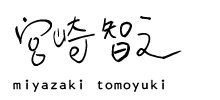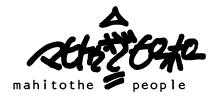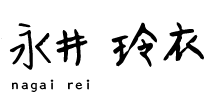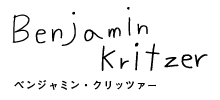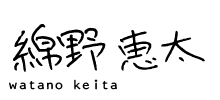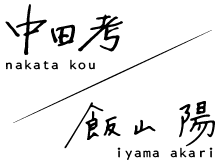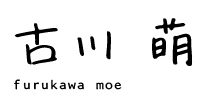膝の皿を金継ぎ
- 第8回 2月の日記(後半) 2024-03-28
- 第7回 2月の日記(前半) 2024-02-27
- 第6回 わからなさとの付き合い方 2024-01-29
- 第5回 サバイバル煮物 2023-12-28
- 第4回 ところでペットって飼ってます? 2023-11-30
- 第3回 喋る猫はいなくても 2023-10-31
- 第2回 夢のPDCA 2023-09-29
- 第1回 ここではない、青い丸 2023-08-31
アワヨンベは大丈夫
- 第9回 ごきげんよう(前編) 2024-04-18
- 第8回 ウサギ小屋の主人 2024-03-17
- 第7回 竹下通りの女王 2024-02-15
- 第6回 ママの恋人 2024-01-11
- 第5回 Nogi 2023-12-11
- 第4回 セイン・もんた 2023-11-15
- 第3回 私を怒鳴るパパの目は黄色だった 2023-10-13
- 第2回 宇宙人とその娘 2023-09-11
- 第1回 オール・アイズ・オン・ミー 2023-08-11
旅をしても僕はそのまま
- 第5回 アシジと僕の不完全さ 2024-01-27
- 第4回 ハバナのアルセニオス 2023-11-15
- 第3回 スリランカの教会にて 2023-09-16
- 第2回 クレタ島のメネラオス 2023-06-23
- 第1回 バリ島のゲストハウス 2023-05-31
おだやかな激情
- 第11回 なめらかな過去 2024-04-04
- 第10回 ちぐはぐな部屋 2024-03-05
- 第9回 この世の影を 2024-02-02
- 第8回 映したりしない 2024-01-11
- 第7回 とばされそうな 2023-12-04
- 第6回 はらはら落ちる 2023-11-01
- 第5回 もしもぶつかれば 2023-10-02
- 第4回 つややかな舌 2023-09-02
- 第3回 鴨になりたい 2023-08-01
- 第2回 かがやくばかり 2023-07-04
- 第1回 いまこのからだで目に映るもの 2023-05-31
- 第4回 うまくいかなくても生きていく──『十二月の十日』ジョージ・ソーンダーズ 2023-09-25
- 第3回 元恋人の結婚式を回避するために海外逃亡──『レス』アンドリュー・ショーン・グリア 2023-04-21
- 第2回 とにかく尽くし暴走する、エクストリーム片思い──『愛がなんだ』角田光代 2023-01-17
B面の音盤クロニクル
- 第8回 その日はあいにく空いてなくてね──Bobby Charles, “Save Me Jesus” 2024-03-08
- 第7回 クリスマスのレコードはボイコットする 2023-12-22
- 第6回 とうとう会得した自由が通底している 2023-05-06
- 第5回 あれからジャズを聴いている理由──”Seven Steps to Heaven” Feat. Herbie Hancock 2023-04-04
- 第4回 「本質的な簡素さ」の歌声──Mavis Staples “We’ll Never Turn Back” 2023-03-01
- 第3回 我が家にレコードプレイヤーがやってきた──Leon Redbone “Double Time” 2023-01-08
- 第2回 手に届きそうな三日月が空に浮かんでいる──Ry Cooder “Paradise and Lunch” 2022-12-07
- 第1回 きっと私たちが会うことはもうないだろう Allen Toussaint “Life, Love, and Faith” 2022-11-04
- 第16回(最終回) 「本物の詐欺を見せてやるぜ」@ジョン・ライドン 2022-07-04
- 第15回 文明化と道徳化のロックンロール 2022-06-10
- 第14回 ミスマッチにより青年は荒野を目指す 2022-06-02
- 10 もうひとつの現実世界――ポスト・トゥルース時代の共同幻想(後編) 2021-07-06
- 9 もうひとつの現実世界──ポスト・トゥルース時代の共同幻想(前編) 2021-05-03
- 8 あるいはハーシュノイズでいっぱいの未来 2020-05-05
第15回 文明化と道徳化のロックンロール
ロックとはなんだったのか? 情熱的に語られがちなロックを、冷静に、理性的に、「縁側で渋茶をすするお爺さんのように」語る連作エッセイ。ロックの時代が終わったいま、ロックの正体が明かされる!?
リヴィング・カラーのヴァーノン・リードが近年のインタビューにおいて非常に興味深いことを述べている。かいつまんで言うと、ロックの歴史において黒人のミュージシャンは不当な扱いを受けてきた、という異議申し立てである。1950年代の半ばにロックンロールが誕生した時には、黒人アーティストと白人のアーティストが入り乱れてノリの良い音楽を奏でた。ところが、ロックがカウンターカルチャーと結びついた60年代の後半になると、ロックはラブ&ピースを主張しながら白人中心の文化になってしまう。映画『ウッドストック』を観ればわかるけれども、あの映画で目立っている黒人はジミ・ヘンドリックスだけである。彼はもちろんアメリカで生まれてブルースやR&Bのバンドでキャリアを経たギタリストだが、一旦イギリスに渡ることでキャリアをロンダリングした。ビートルズの登場とブリティッシュ・インヴェイジョンは明確に文化の分水嶺である。ヘンドリックスはもちろん、それ以前から個性的なギターを弾いていたわけだがタイミングよくイギリスに渡って、英国から発信したアフロアメリカンのギタリストとして唯一無二の地位を築く。ところが、それ以降の70年代ロックにおいては黒人ミュージシャンの活躍があまり評価されない歴史が続くのである。マイケル・ジャクソンやプリンスが世界的な規模で音楽市場を塗り替えるのは、1980年代になってからだ。つまり、長い間ロックは白人中心の文化であり、イギリスから現れたジミ・ヘンドリックスだけは特別枠で賞賛されていたのだ。創世記のロックンロールは黒人アーティストと白人アーティストがどちらも大活躍していたのに、ラブ&ピースとカウンターカルチャーの60年代後半を経て、ロックは白人中心の文化になってしまい、マーケットにおいては黒人音楽との間に障壁を作ってしまった。リードはアイズレー・ブラザーズやシスター・ロゼッタ・サープといったロックの歴史に決定的な影響を与えたアーティストたちが、白人のロックという文脈では無視されてきたと訴える。アイズレー・ブラザーズにはジミ・ヘンドリックスも参加していたし、チャック・ベリーよりもひと回り上で戦前からゴスペル、ジャズ、ブルースと幅広い活躍をしたロゼッタ・サープのギタープレイを今聴くと、これは確かにチャック・ベリーのサウンドの源流と言うべきか、更に言うならばサープこそがロックンロールの発明者だったのではないか? と思えるくらい、後のロックンロールがやったようなことを1940年代に既にやっていたのである。1964年に彼女がマディ・ウォーターズと共にヨーロッパツアーを行った際には、客席に若き日のエリック・クラプトンやジェフ・ベック、キース・リチャーズ、ブライアン・ジョーンズたちがいた。ロバート・プラントに至ってはソープの楽屋に忍び込んだという。そんなソープは2018年にロックの殿堂入りをした。つい最近ではないか。多くのロックレジェンドから尊敬されていたにも関わらず、本格的な再評価の波が始まったのは21世紀になってからなのだ。英米の白人によるロックが黒人のブルース、R&Bの物真似から始まったことは明らかである。たとえばローリング・ストーンズのファンになった中学生が、バンド名の由来となったマディ・ウォーターズを聴くと、割とそのまんまそっくりではないかと思う、わけである。続けてエルモア・ジェイムズを聴くと、これがもう明らかにロックなギターサウンドである。なので60年代から70年代にかけてのロックに魅了された人たちの多くは、ロックの源流、ルーツを辿るようになり、戦前のブルースにハマる人も多かった。にも関わらず、サープが評価されたのはつい最近なのである。リードは続いてファンカデリックとそのギタリストであるエディ・ヘイゼルの名前を挙げ、彼らが紛れもないロックバンドであり、素晴らしい傑作を残しているのにも関わらずロックの文脈では評価されてこなかったことを指摘する。R&Bの歌手としてキャリアを始めた、Pファンクの総帥ジョージ・クリントンは、サンフランシスコに移住してヒッピー・ムーブメントの洗礼を受け、ピンク・フロイドのライブを観て、自分の手で黒人のためのピンク・フロイドを作ろうと思い立った。リードはこのエピソードをクリントンから直接聞かされたという。クリントンとヘイゼルは、堂々たる黒人によるロックを作り上げたが、ロックバンドとして認められることはなかった。だから彼らはファンク・R&B色を強めていったのではないかと、後進の黒人ロックギタリストであるリードは語る。そもそもの問題は黒人音楽と白人音楽のマーケットが分かれていたことにあるのは間違いない。だからこそアラン・フリードがラジオを通じて、白人の若者たちに黒人音楽を聴かせたことがロックという文化の誕生に繋がったのである。ただし、黒人音楽の市場と白人音楽の市場が融合したわけではなかったのだ。60年代後半のカウンターカルチャーは公民権運動、黒人解放運動、女性解放運動といったマイノリティのための運動と連動していたために、大きな流れになったが、各々の運動がきちんと連動していたわけではない。
白人主体のロックフェスであるウッドストックが行われた1969年の夏、ニューヨークでは黒人音楽の祭典ハーレム・カルチュラル・フェスティヴァルが行われていた。合わせて30万人が参加したというから規模的にもウッドストックに引けをとらないこのイベントは黒いウッドストックとも呼ばれているが、2021年に『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』というタイトルのドキュメンタリー映画が公開され、注目を集めた。イベントの翌年には映画が公開されていたウッドストックとはえらい違いではないか。69年の時点で黒人たちは、アフリカ系アメリカ人の音楽としての黒人音楽を確立しており、マーケットも存在していたわけだが、だからこそ黒人音楽と白人音楽のマーケットが融合するまでに時間がかかったという面もあるだろう。なので黒人音楽から出たものであり、白人のロックが黒人に影響を与えることもあったにも関わらず、白人は白人で、黒人は黒人でという歪な形で発展してしまった。ちなみに、アメリカの音楽事情は今でも複雑で、黒人が主体で演奏するブルースフェスティバルの観客の9割が白人というような状況がある。その場合、白人の聴衆は黒人音楽を明らかにリスペクトしているわけではあるが、なんとも複雑な気分にはなる。ちなみに黒人の聴衆が少ないのは、若い世代の黒人にとってブルースはお爺さんやお父さんの世代の音楽で、古臭いものに聞こえるからだという。
70年代に何があったのかを駆足で見てみよう。70年代の前半にはハードロックとプログレッシヴロックが隆盛し産業として拡大化の一途を辿ったわけだが、1976年には「アナーキー・イン・ザ・UK」でセックス・ピストルズが登場し、77年には『勝手にしやがれ‼︎』でアルバムデビュー。パンクの時代が到来してしまう。彼らはレッド・ツェッペリン(いわばハードロック代表だろうか)やピンク・フロイド(こちらはプログレッシヴロック代表だろう)といった先達(年齢的にはセックス・ピストルズの面々より一回り上くらいになる)を時代遅れであると口悪く貶し、「私はピンク・フロイドが嫌いだ」と書かれたTシャツを堂々と着ていた。パンクはゆるくてヌルいヒッピーの文化を批判し(もう、ヒッピーなんて限られた場所にしかいなかったのに)もっと過激にやるのだという姿勢であった。現代の視点から見るとパンクは、50年代ロックンロールへの原点回帰にも見えるわけだが、これはこれで説明しだすとややこしいのである。何がややこしいかというとですね、パンクというのは元々はアメリカはニューヨークの文化である。ヴェルベット・アンダーグラウンドやイギー・ポップがルーツとされ、パティ・スミスやテレヴィジョンがいた。ヴェルベット・アンダーグラウンドのルー・リードやパティ・スミスはレッド・ツェッペリンやピンク・フロイドのメンバーたちと概ね同世代にあたる。彼らの中でパティ・スミス、テレヴィジョンのトム・ヴァーレインが、若くして亡くなったドアーズのジム・モリソンのフォロワーであることはかなり重要なポイントだろう。言うまでもなくモリソンはロマン主義的であり象徴主義的な文学者である。パティ・スミスやヴァーレインの作品というのは、アメリカの西海岸から出たモリソンに対しての、東海岸からの文学的なレスポンスであったわけだ。セックス・ピストルズ以降のロンドンパンクに影響を与えたと思われるのはイギー・ポップだろうか。ところでイギー・ポップのワイルドな行動は、彼がビートニクの流れを継承しているからだ。つまり、ニューヨークパンクというのは、文学性の強いサブカルチャーのムーブメントであり、現代アートに理解のある都会の、幾分かはスノッブな文化だったわけだ。パティ・スミスもテレヴィジョンも高く評価されているが、ロンドンパンクのように若者のファッションに大きな影響を与えるタイプの作家ではない。彼らの文学性は、聴き手のパーソナルな心情に訴えかけるものであり、ロックがそのような表現を生み出したことは素直に賞賛すべきである。20世紀のロックの多様性は大したもので、大勢でノリノリになって騒ぐタイプの音楽とは違う文化も生み出しているのだ。アシッドフォークのようなものまで、ロックという言葉の範疇にあるのは、かなり凄いことである。ヒトは猿なので、皆と盛り上がるのは大好きだけれど、自分だけの時間も大切にしたいのである。面倒くさい動物なのは間違いないのだが、ロックは短い期間で文化進化を繰り返し、ホモ・サピエンスの多様なニーズに応えたわけである。とはいえ、ニューヨークパンクだけなら、狭い地域での先鋭的な文化として歴史に残っただけだろう。このパンクというアメリカの中でも都会でしか成立しづらい文化を、イギリス人が加工して輸入したわけである。マルコム・マクラーレンという一種のテキ屋と、デザイナーでファッションブランド、ブティックを経営していたヴィヴィアン・ウェストウッドが結託してセックス・ピストルズをプロデュースしたというのは有名な話である。ロックの歴史を1950年代半ばからだとして、飛躍的に革新的であった出来事というのは実はそんなには多くない。ボブ・ディランがエレキギターを持ったのと、ブリティッシュ・インヴェイジョンより大きな出来事は起きていない。むしろ、規模の小さなイノベーションが頻繁に起きるのがロックの良いところなのだ。セックス・ピストルズは確かに革命的であったが、音楽的にはむしろ、当時としては比較的保守的なパブロックを、意図的にラウドに演奏したわけで、音楽的な革新性はあまりなかった。むしろ当時としては目新しくもないロックンロールで、政治的にラディカルなことを歌ったのが効果的だったのである。セックス・ピストルズは、言ってみればヴィヴィアン・ウェストウッドという服屋のキャンペーンのために作られたバンドである。それが、圧倒的な影響力を持ち得たのはブリティッシュ・インヴェイジョンの時と同じように、アメリカで生まれた文化をイギリスに持ってきて加工したからである。今あるパンクのイメージを決定づけたのはジョニー・ロットンの過激な言葉と、シド・ヴィシャスの過激な生き様ないし死に様である。本来はアメリカで誕生したパンクだが、セックス・ピストルズ以降、アメリカのパンクバンドもロンドンパンクを意識せざるを得なくなった。『反逆の神話』のジョセフ・ヒースは、少年時代の自分がパンクスであったと書いているが、カナダ人であるヒースのパンクはニューヨークから直輸入されたものではなく、ロンドンパンクを経由したものである。ヒースの文章に時折見られる皮肉や諧謔は、ジョニー・ロットン改めジョン・ライドンの言動のようである。そして、10代のヒースがそうであったように、パンクファッションは基本的に安くつくから若者にとっては真似しやすかったのである。かくしてセックス・ピストルズ以降のパンクは、世界中の若者にインパクトを与えた。元々は作られたアイドルのようなものであったが、ジョニー・ロットンは馬鹿ではなかった。彼がロックの歴史上、屈指のイデオローグになったのは元から頭の良い人が、特殊な環境に置かれたからだろう。セックス・ピストルズが登場する以前に、セックス・ピストルズのメンバーのような経験をした人はいなかったのである。2代目のベーシストとしてバンドに参加したシド・ヴィシャスはロットンの友人だったが、ドラッグに耽溺しておりセックス・ピストルズの解散後はソロとして活動したものの薬物の影響でまともにステージをこなせないような状態で恋人のナンシー・スパンゲンと共に破滅的な生活を送り、78年にナンシーは滞在していたニューヨークのチェルシーホテルのバスルームで何者かに刺殺される。犯人はシドかとも思われたが、本人は無罪を主張、ナンシーが死んだ4ヶ月後にはヘロインのオーバードーズで死んでしまった。ナンシーの死因は永遠の謎となり、後には悲劇のみが残ったわけである。ヴィシャスがナンシー殺害容疑で逮捕された際に、彼のためにいち早く弁護士を用意し、その費用も全て支払ったのが誰かというとミック・ジャガーなのである。バンドの元メンバーがドラッグで不審死を遂げたり、自分が歌っている場所で警備員が観客を刺殺してしまうという経験のある人である。そして、どちらの件に関しても法律的な責任はともかくとしてミック・ジャガーにも何らかの責任はあったのである。だからこそ、業界の年長者として迅速に行動したのだろう。69年にブライアン・ジョーンズが亡くなってからシド・ヴィシャスが亡くなるまでに、ほぼ10年の月日が流れている。この10年はロックにとって、最も華々しい時代であったわけだが、ヒッピーたちのフラワームーブメントという夢が早い段階で潰えた上に、後からやってきた世代のセックス・ピストルズからは唾を吐きかけるように否定され、そのメンバーであったシド・ヴィシャスは恋人と共に悲惨な死を遂げた。ロックの歴史は死屍累々であった。セックス・ピストルズのデビューと、イーグルスの『ホテル・カリフォルニア』が、ほぼ同時期であったことはロックの歴史を語る上でかなり重要なことである。「ホテル・カリフォルニア」の歌詞は象徴的で、様々な解釈が可能ではあるが、明るくて楽しい歌ではないことだけは誰が聴いてもわかる。アメリカンロックが生み出した怨歌のようなものである。後ろ向きな歌である。かつて、何らかの夢を抱いた人たちがいたとして、その夢は終わったんですよと告げるような歌である。つまり60年代後半のアメリカにおけるヒッピーたちのフラワームーブメントは、イギリスの若僧からは唾を吐きかけるように否定され、アメリカの少し下の世代からは、夢は終わったんですよ、と言われてしまったのである。ローリング・ストーン誌のヤン・ウェナーはイーグルスに否定的だったというがその気持ちはわからないでもない。イーグルスはウェナーが愛した文化を終わらせるためにやってきたような存在だったのである。そして皮肉なことに、セックス・ピストルズもイーグルスも滅茶苦茶に売れた。方向性は真逆に見える両者だったが、どちらも聴衆の支持を得た。資本主義において勝利したのである。ロックと資本主義に関して、最も誠実であったのはジョニー・ロットンから改名したジョン・ライドンである。1978年の解散から20年近い時を経た1996年、ライドンはセックス・ピストルズを再結成しツアーを行った。その理由は「金が必要だから」である。再結成ライブを収録したアルバム『勝手に来やがれ』は画期的なアルバムになった。観客たちが全力で大合唱しているのである。収録曲はお馴染みの「ゴッド・セイブ・ザ ・クイーン」や「アナーキー・イン・ザ・UK」である。これらは皆で楽しく合唱するような歌ではないだろう。この時のライドン師はビール腹で贅肉がたぷたぷしていた。そんな見苦しい肉体を見せびらかすように、彼は「お前らに本物の詐欺を見せてやる」と言った。つまり、セックス・ピストルズの再結成とは、セックス・ピストルズの完全否定だったわけである。ロックの歴史上、ここまで完璧に伏線回収したバンドはおそらくない。見事である。歴史上、ロックは死んだという発言をした人は何人かいるのだが、ライドンは具体的にロックが死ぬところを演劇的に再現し、それをワールドツアーで公演して回ったのである。この時のツアーでは、もちろん日本公演も行われ、セックス・ピストルズのナンバーが懐メロのごとく演奏され、日本の観客たちも懐メロとして大合唱した。パンクが持っていたラディカルな要素を、戦車で踏み潰すかのような出来事であったが、それをやっているのがパンクの総本家たるライドンである。彼が資本主義を肯定することで、ロックの資本主義、商業主義批判は、一種の空念仏であることがはっきりしたのでたる。
ナンシーの死に際してミックはシドを助けようとしたわけだが、シド自身はナンシーの後を追うようにドラッグ死してしまう。この時のミックが何を思ったからわからないが、この少し後の時期から彼はジョギングを始め、健康的なアピールをするようになる。1981年のツアーは『スティル・ライフ』というライブアルバムになり、『夜をぶっとばせ』という映画にもなっている。映画の監督はヒッピー世代のハル・アシュビーだ。この時点でミックはドラッグをやめジョギングをして健康アピールをするようになっていた。成功したミュージシャンほど、ドラッグの売人が寄ってくる、というのはわかる。たとえばジム・モリソンに致死量のドラッグを融通したのはマリアンヌ・フェイスフルの恋人だったという。ミック・ジャガー自身、70年代の中頃まではドラッグに耽溺していたし、キースも耽溺していた。60年代においてはセックスとドラッグとロックンロールを体現したような人であったミックが、ジョギングと脱ドラッグアピールで業界の革新を画策したのである。シド・ヴィシャスの死に様はブライアン・ジョーンズの死に様よりも性急であった。こんなことが続いたら、ロックという業界に未来はないと思ったのではないか。
ロックの黄金時代であった70年代において、パンクと同じくらいに重要なのがディスコである。大きな声では言えないけれども、70年代がロックの黄金時代であったと思っているのはロックンロールが好きな白人と、その文化に魅了された日本人くらいである。実際の70年代はディスコの時代であった。実際にはディスコとロックの時代であったと言うのが妥当なところなのだろうが、これがなかなかに難しい話なのだ。ロックンロールもディスコも、後に登場するヒップホップも、基本的には若者たちが踊るための音楽である。集まってドンドコ踊るのを好むのはホモ・サピエンスの習性であるが、ローリング・ストーン誌によってロックジャーナリズムが登場し、ロックにおいてはロックを語る文化が重要になった。カウンターカルチャーが衰退した後も、政治的なアピールはロックの重要な要素であったし、ロックを語ることでその時代の文化を語ったり、自分語りをすることも可能になった。もちろん政治的なメッセージ性の強い踊る音楽というのは他にもあって、ジャマイカのレゲエや後のヒップホップがそうなのだが、白人のロックはロックを語ることと巨大な産業に成長することが深く結びついていた(だから面倒くさいロックおじさんが生まれてしまう)ために、ロックファンの多くは自分の好きなバンドのメンバーの名前を全員覚えていたり、出したアルバムは全て揃えなおかつそのアーティストに影響を与えたアーティストの音楽まで聴くようになったりする。ローリング・ストーンズのファンからマディ・ウォーターズやエルモア・ジェイムズを聴くようになり、更には戦前のブルースにたどり着いた人はゴロゴロいる。しかしながら、ディスコミュージックというのは別にアーティスト名を知らなくても良いし、極端なことをいうと曲名すら知らなくても別にかまわないのである。もちろんディスコミュージックにもバンドの歴代メンバーの名前を覚えアルバムを揃えるようなファンはいるわけだが、基本的に踊ることに特化した音楽である。ロックで重視されるような、そのアーティストの音楽を鑑賞するという姿勢がはなからないような人たちも聴くわけである。だから、やたらと裾野が広いのである。ディスコという文化は70年代の前半からあったが、最初のうちは黒人向けやゲイの人たちが集まる場所であった。それが78年に映画『サタデー・ナイト・フィーバー』によって世界的なブームとなる。この映画のサントラを担当したビージーズは63年にオーストラリアでデビューした息の長いバンドだが、70年代の半ばから試行錯誤の末にディスコミュージックに挑戦していた。古いファンからは、売れるために音楽性を変えたという批判もあったようだが、結果的には大成功であった。黒人音楽であるディスコを白人が吸収した上で自分たちのものにするというのは、白人が黒人の物真似をしたという点でロックンロールの誕生とよく似ている。白人によるディスコは、言わばロックンロールの再発明である。実は、ブリティッシュロックの老舗であるローリング・ストーンズやロッド・スチュアートも、この時代には積極的にディスコに挑戦している。ロッドの「アイム・セクシー」が78年。ローリング・ストーンズの「ミス・ユー」が同じ78年だが、この人たちは黒人音楽に関しては濃厚なオタクなので76年の『ブラック・アンド・ブルー』からディスコ的なアプローチを始めており、80年の『エモーショナル・レスキュー』を経て83年の『アンダーカバー』ではヒップホップをやっている。KISSは79年の「ラビン・ユー・ベイビー」で、クイーンは80年に「地獄へ道連れ」で、デヴィッド・ボウイは83年のアルバム『レッツ・ダンス』でディスコ的なアプローチを試みている。大御所ほど、時代の変化には敏感なようである。しかしながら、ディスコはあまりにも売れたので、そんなディスコという文化を敵視する人たちもいたのだ。1979年のことである。デトロイトのラジオDJであったスティーブ・ダールはdisco sucks(ディスコは最低!)というキャンペーンを始めた。ラジオ局のプレイリストから彼が愛していたローリング・ストーンズやレッド・ツェッペリンの曲に変わってヴィレッジ・ピープルやドナ・サマー、シックなどのディスコミュージックばかりが重宝されるようになったからである。ラジオDJのやったことなので、基本的にはトークの中のおふざけから始まったようなものなのだが、ディスコの台頭に対してダールは本気で危機感を持っていたらしく、「中西部の人たちにとってディスコの音楽は威圧的だったから嫌われた」と語った。ディスコ最低キャンペーンでは、リスナーからディスコミュージックのリクエストを募り、放送しながら爆発的な効果音を流して、それを破壊する、てなことをやっていたらしい。現代の我々には、今ひとつ事態を把握し難いところがあるのだが、ロックのことが大好きなおじさんが、ディスコミュージックを破壊すべし! という活動を始めたわけである。ダールにはスティーブ・ビークという売れないギタリストの知り合いがいた。ビークの父親はシカゴ・ホワイトソックスの本拠地であるコミスキーパークを所有していた。そして、ホワイトソックスはこの頃、不人気で観客が少なかった。上手く話をつけたダールは、ディスコのレコードを持ってきたら次のホワイトソックスのホームゲームに格安で入場できると発表した。その結果、普段は1万6千人しか集まらないホワイトソックスの試合に5万9千人もの観客がやってきた。もちろん、そのうちの1万6千人はダールの反ディスコキャンペーンなど知らない単なる野球ファンだったと思われるが、我々も良く知っているように不人気な球団のファンというのは、普段は理知的な人であっても球場に来ると理性を放棄してしまう動物である。なので、この時は一般の野球好きなおっさんたちも一緒になってディスコのレコードを叩き割り火をつけて燃やしたという。改めて書くけれども、この時点でのディスコは黒人とゲイが主体の文化であった。ダールたちは、それを叩き割って燃やしたのである。酷い話である。野蛮人かお前ら。このエピソードが79年であったことは象徴的である。端的に言うと70年代までのロックは理想主義的な側面を持ちながらも、いささか野蛮な文化であったのだ。歴史を顧みると人類は常に文明化する方向で歩んできた。アリストテレスやプラトンは、現代の我々から見ても理知的であるが、20世紀の半ばで第二次世界大戦が終わるまでは、誰もが戦争を絶対悪とは思わない程度に野獣だったのである。ヒトは、戦争は良くない! と言いながら、必要に応じて戦争をする動物だったのである。第二次世界大戦があまりにも酷い結果に終わったので、我々はようやく「戦争は全部ダメ!」という境地にたどり着けたのである。この度のウクライナ侵攻でロシアが幾多の先進国から責められているのは、せっかく長い時間をかけて文明化した社会にたどりついたのに、それをひっくり返すようなことをしたからである。文明化には、とにかく時間がかかるのであるが、基本的に文明化は止まることがない。70年代のディスコに対するヘイトは、黒人差別、ゲイ差別という側面を持っていたが故に現代の我々から見るとかなり野蛮であったが、半世紀近く前の話である。二度にわたる世界大戦を経た社会は、戦前と比べるとかなり文明化していたがそれでもまだマイノリティに対して無理解の多い野蛮な社会であったと言える。ロックとカウンターカルチャーの時代にアメリカでは暴力事件が増加したが、90年代にはかなり平和になる。81年のツアーにおいてローリング・ストーンズのミック・ジャガーは脱ドラッグと禁煙を打ち出し、ジョギングしている姿をメディアに載せた。あれほどドラッグとセックスとロックンロールだった人が健康アピールを始めたのだ(時期的にはシド・ヴィシャスの死の少し後になる)。そう、80年代に入った頃から不道徳の権化であったロックミュージシャンたちの道徳化が始まったのである。84年にデビューしたジョン・ボン・ジョヴィはドラッグをやらない。何故なら、自分を見ている若者たちに悪い影響を与えたくないからだと言う。生き延びたロックスターの多くは健康的になり、道徳を重んじるようになった。ジーン・シモンズが夭折したロックスターについての本を書くようになったのも道徳化の一環である。また、81年にはローリング・ストーンズはマディ・ウォーターズと共演している(もっと早い時期に共演する機会はあったろうに)。この頃から、ロックスターたちは自分に影響を与えたレジェンドたちを感謝の念を込めて顕彰するようになる。かくしてセックスとドラッグとロックンロールの蜜月時代は終わったのである。