日本人で文学好きの母と、瞬間湯沸かし器的にキレるセネガル人の父の間に生まれた亜和(愛称アワヨンベ)。祖父母、弟とさらにキャラの立つ家族に囲まれて、ときにさらされる世間の奇異の目にも負けず懸命に生きる毎日。そんなアワヨンベ一家の日常を綴るハートフルエッセイ。アワヨンベ、ほんとに大丈夫?
2週間ほど前、週末の休みにどこかへ出かけようと思い立ち、いろいろと調べていると、代々木公園で「アフリカヘリテイジフェスティバル」が開催されるという告知文が目に入った。竹下通りにいる「彼ら」と関係があるのかは分からないが、あの近辺には、アフリカの人々のコミュニティのようなものがあるのだろうかと考える。
今年の4月あたり、代々木公園に花見に行ったときも、公園内の少し離れたエリアにはそれらしき人たちが集まっていた。彼らが着ていた鮮やかな服は、遠い昔、私のためにパパがセネガルから持ち帰ってきたそれによく似ていた。セネガルの人たちかもしれない。私はその中の誰かと話をしたくなり、少し遠くで立ち止まって、5分ほど彼らのほうを見つめていた。大人たちが輪になって、音楽を流しながら楽しげに体を揺らし、その足元を、ちいさい頃の私によく似た子供たちが駆け回っている。ベンチに座っていた男たちが、長いあいだ立ち尽くしている私に気づいて、さっきまで交わしていた大声を潜めてコソコソと話をしはじめた。私はわざとらしくそっぽを向きながら「Hey, where are you from?」と呼び掛けられるのを待った。それから「シスタ、君もこっちへおいでよ」と誘われるのに期待した。しかし、彼らは私を見て訝しげな表情で数秒なにかを話した後、なんでもなかったようにまた元の会話に戻っていった。私はいつも通り、ストレートに伸ばした髪をおろして、暗い色のシンプルな服を着ていたから、同郷かどうか判断するには微妙なところだったのだろう。そもそも、国が同じだとしても、急に招き入れてくれるほうがおかしい。自分から話しかける勇気もなく、私は名残惜しげに何度も振り返りながらその場を離れた。
先月は、阿佐ヶ谷でアフリカンファッションショーがあると聞きつけて見物に行った。モデルを募集していると聞いて参加したいと申し出たが、事務所に所属していたため断られてしまった。ランウェイをはじめて歩くであろう人々が、緊張しながらも楽しそうに赤いじゅうたんの上を歩いているのを、私は少し離れた場所から眺める。背の高くて若い、セネガル人のモデルもいた。私のことを見つけた主宰者の女性が声を掛けてくれたが、気恥ずかしさで上手く話すことができず、私はショーがおわると同時にそそくさと立ち去った。
15年ほど前、パパに連れられて横浜のアフリカンフェスタに行ったことがある。赤レンガの前の大きな広場にいくつものテントが立っていて、アフリカのそれぞれの国がアクセサリーや料理を出していた。パパはセネガルのブースに私を連れて行って、仲間たちに会わせてくれた。みんな大きな手で勢いのある握手を求めてきて「元気?」と何度も私に聞く。私は小さな声で「うん」と言うか、なにも言わずにはにかんだまま首を縦に振るのを繰り返していたと思う。左手で握手をしようとしたら「握手は、右手。左手はダメ」と言われて、私は恥ずかしくなって小さくなった。きっと、彼らのなかには私がまだ知らない決まりごとがたくさんあって、なにも知らない私は、そのうちなにかとんでもないことをして、こっぴどく叱られてしまうのではないか。そのうえパパが仲間たちから「どういうしつけをしているんだ」と責め立てられたりしたらと思うと恐ろしい。早く帰りたい。パパが仲間たちと話しているあいだ、私はセネガルのブースから離れて、目的もなくテントの隙間をさまよい続けた。セネガルのブースが見えるとまた踵を返して反対側に向かい、テントの立っていない場所まで行きつくと今度は落ち着かなくなって、またテントの群れのなかに戻っていくのを繰り返した。結局、私は楽しそうに話す父を遠くに眺めながら立ち尽くして、せわしないジャンベの音と歌声が響く広場で時が過ぎるのをジッと待っていた。
15年前も今も、私はなにも変わっていない。彼らとの関わりかたがわからないくせに、楽しそうにしている彼らを指をくわえて遠くから眺めている。日本人として扱われないことに孤独を感じて、自分の中からパパの文化、あげくにパパそのものさえも追い払って好き勝手に10年ほど過ごしてきたというのに、今になってヒップホップやファンクを聞きはじめたり「アフリカ」と名の付くイベントに顔を出してみたりと、自分でも何がしたいのかよくわからなくなっている。ネットに公開した「パパと私」が話題になってからはとくにそうだ。パパとの記憶を思い出して文章にしていくたび、私の中でほとんどいなくなったも同然だったパパの姿が、再び輪郭を帯びて私の近くへとやってくる。いや、私が近づいていっているというほうが正しい。私は一体、なにを望んでいるのだろう。
デビュー作が刊行されて、一応は「作家デビュー」ということになった。長年具体的な目的もなくフリーターをしていた私にとっては、少なからずもの変化と言えるのではないだろうか。出版社からの取材、友人、お世話になっている人たち、みんな決まって「ご家族は喜んでいるでしょう?」と聞く。私は決まって「とくに」と返事をする。母は口に出さないだけで内心はそうなのかもしれないが、一緒に暮らしている祖父母には、本当に変化がないように見えているのだと思う。派手にテレビに出ているわけでもないし、今のところ派手に収入が上がったわけでもない。学校で読み書きの勉強の機会に恵まれなかった祖母の娯楽はもっぱらテレビだ。最近は、もともと不自由だった耳もさらに遠くなり、テレビドラマもほとんど雰囲気だけで楽しんでいる様子。渡した拙著は数ページ読まれただけでテレビの横に置かれていた。祖母は、私が出かけるときにはいつも「仕事? 遊び?」と聞く。だいたい2日続けて「遊び」と答えると「最近遊んでばっかりね」と言われる。付き合いとか、仕事とも遊びとも言えないようなことがあるので、意味もなくのんべんだらりと遊び回っていると思われるのは心外だ。祖母には相変わらずボーっと生きているようにしか見えないかもしれないが、私だってそれなりに需要を獲得して、毎日奮闘しているのだ。私は狩ってきた敵の首を掲げるように、仕事で頂いた菓子折りを祖母に渡す。「私はでっかい会社からうやうやしいお菓子を貰える立場になったのだ」と、祖母に示す方法はこれしかない。
ある日、上等なきんつばを頂いた。帰っていつものように祖母に手渡すと、祖母は貰ったきんつばを指でつまんでネチネチとこねくり回しながら「これ高いのよね」と言った。貰ったものを値踏みするのは祖母の癖だ。悪気はないのだが、真っ先に物の価値が知りたいタチなのだ。こう言われたら、私はいつものように黙って商品名をグーグル検索するしかない。たしかにまあまあ高い。祖母はそれを聞いて「そうよ」と得意げになったあと、今度はきんつばの入っていた箱を持ち上げてまじまじと底を見た。それから「やっぱり、こういうのは賞味期限ギリギリになってから渡すのよね。しょうがないのよ、そう」と言った。
それは違う。きんつばはそもそも賞味期限が短い。決して、会社で余ったものを賞味期限間近に寄越してきたわけではない。これは出版社の大人が“私のために”買ってきたきんつばである。腹が立って、祖母が聞き取れるように大声で「そういうもんなんだよ」と言った。もともと声が低いので、大声を出すとどうしても怒ったような声になってしまう。実際怒っていたし、語気はいつも以上に強くなった。どうやら私は、普段大きな声を出さないせいで、大きな声を出すと、それを聞いた自分自身がびっくりして感情が高ぶってしまうらしい。苛立った勢いのまま「そういう風にゴチャゴチャ言うのやめなよ」と続けた。祖母はそれを聞いて頭にきたらしく「知らないからしょうがないだろ」「こういうの食べたことないんだから」と怒鳴った。そしてそれきり、ぶすっと黙りこくってしまった。祖母はずっとお金に苦労して生きてきた、親に捨てられ、奉公先で意地悪をされながら必死で生きてきたころの記憶が、祖母の性格に大きく関わっているのだろう。もっと言えば、祖母の時間はそこで止まってしまっているように私には見えることがあった。なにも欲しいと言わないし、どこにも行きたいと言わないし、なんど価値のあるものを渡しても「こんなのははじめて」と言う。私は何度も祖母に贈り物をしてきたつもりなのに。いくら望みを叶えようとしても、祖母の顔はいつまでも晴れない。決して「今は幸せだ」とは言ってくれないのだ。この人は、最期までこんなふうでいるのだろうか。私はいちどだっていいから「いい孫を持った。私は幸せだ」と言ってほしいのに。たかがきんつばで、居間の空気は最悪になり、私は食いかけのきんつばを握りしめてわざとらしく音を立てて自室に戻った。きんつばを床に叩きつけそうになったので、メンタルクリニックで処方された癇癪止めのシロップを飲んだ。想像していたよりずっと苦くて涙が出た。怒りは水を掛けられたようにサッと消えて、悲しみだけがボロボロとこぼれだす。泣きながらきんつばをむさぼるように食べた。私はどうしてこんなに取り乱しているんだろう。べつに、本人がそれでいならいいじゃないか。
私は祖母に、家族になにを望んでいるのか。私はただ一緒に「美味しいね」と話したかった。それから「こんな美味しいものを用意してもらえるアワはすごいね」と言ってほしかった。そう、アワはすごいって言ってほしかった。私はただ、褒められたかった。私の家族は褒める言葉を持たない。褒める代わりに、鼻で笑ったり、他人の前でくさしてバランスを取る。家族のなかで、唯一私をまっすぐに褒めてくれていたのは、パパだけだった。
私はこのことに、今になってようやく気がついた。私が何かするたび「アワヨンベ! すごい!」と小さな私を肩車をして踊ってくれたのはパパだけだった。「アワはもっとすごくなる。頭がもっと良くなって、偉くなる」と、パパはいつも私を抱きかかえて言い聞かせてくれていた。今日この日まで蓄えておけるだけのたくさんの水を、私はあの日々の中で与えられていた。だから長い日照りも耐えることができる。私は大丈夫だと、すこしだけ信じることができる。私は今、パパに会いたい。あちこちに出向いてはパパの姿を探している。もしかしたらいるかもしれない。パパのことを知っている人がいるかもしれない。本当にいたら一目散に逃げだすくせに。会いたいなら、すぐ近くの家に行けばいいのに。私は遠い場所の人ごみの中にパパを探しに行く。「俺の娘はすごいんだ」と、きっとパパなら言ってくれる。そう思うと、私はまたしばらく大丈夫でいられる気がするのだ。車の後部座席に乗って家を出ると、前からパパが歩いてきた。パパが車に気づいて、運転席の祖父に会釈をする。私は座席の下に潜って、ジッと息を潜めていた。
夜、歌舞伎町を歩いていると、前に背の高い黒人の男が立っていた。この辺りのにこやかに話しかけてくる他の黒人たちと違い、彼は鋭い目で真っ直ぐ前を見つめていた。彼は右側から歩いてきた私にちらと目をやってまた目線を戻し、そのまま私のほうに手を差し出した。私も手を差し出して、握手をした。どうせそのまま引き寄せられてナンパされると思っていたが、彼は何も言わないまま、手をすっと放して私を自由にしてくれた。大丈夫、と言ってもらえたような気がして、私はまた少し泣いた。
(本連載に書き下ろしを加え、年内に書籍化を予定しています。どうかご期待ください)
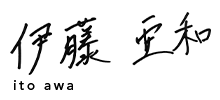
伊藤亜和(いとうあわ):文筆家/モデル。1996年 横浜市生まれ。学習院大学 文学部 フランス語圏文化学科卒業。Noteに掲載した「パパと私」がツイッターで糸井重里、ジェーン・スーなどの目に留まり注目を集める。趣味はクリアファイルと他人のメモ集め。第一作品集『存在の耐えられない愛おしさ』(KADOKAWA)が好評発売中。

