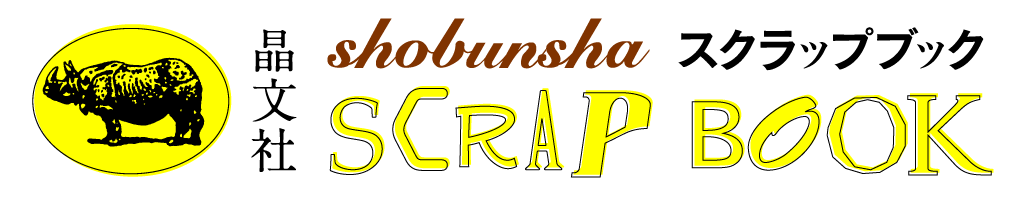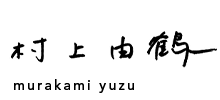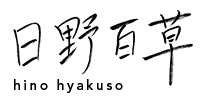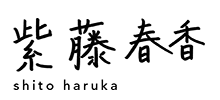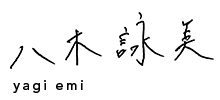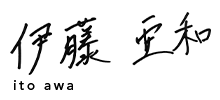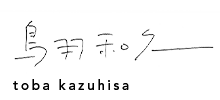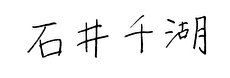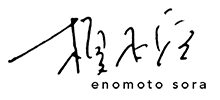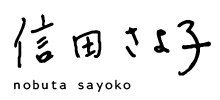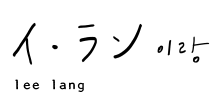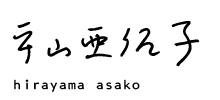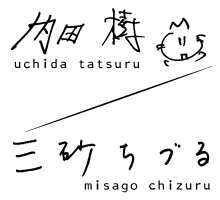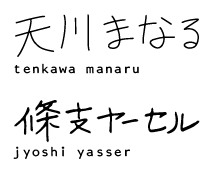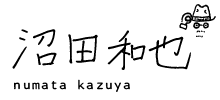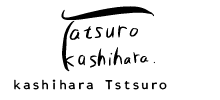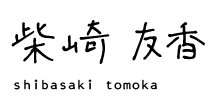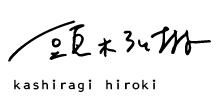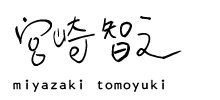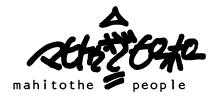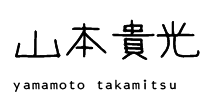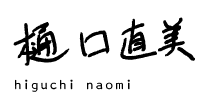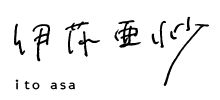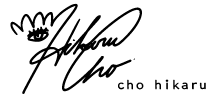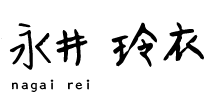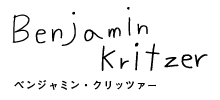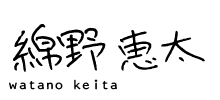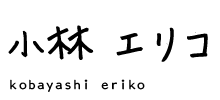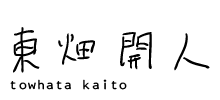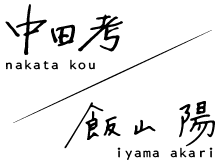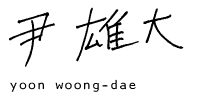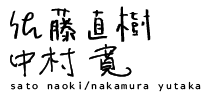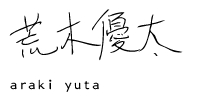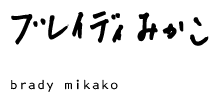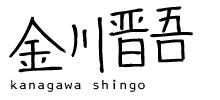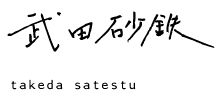ポリアモリー編集見習いの憂鬱な備忘録
- 第5回 だから私はレスバする 2024-06-04
- 第4回 ケアワーカーとしての編集者 2024-05-15
- 第3回 結婚式なんて大嫌いだ 2024-04-05
- 第2回 とにかく定時に帰りたい 2024-03-02
- 第1回 地獄の釜でたらふく食いたい 2024-01-31
膝の皿を金継ぎ
- 第11回 犬、カレー、子ども? 2024-06-27
- 第10回 2人もいる! 2024-05-30
- 第9回 牡蠣が見せる夢 2024-04-27
- 第8回 2月の日記(後半) 2024-03-28
- 第7回 2月の日記(前半) 2024-02-27
- 第6回 わからなさとの付き合い方 2024-01-29
- 第5回 サバイバル煮物 2023-12-28
- 第4回 ところでペットって飼ってます? 2023-11-30
- 第3回 喋る猫はいなくても 2023-10-31
- 第2回 夢のPDCA 2023-09-29
- 第1回 ここではない、青い丸 2023-08-31
アワヨンベは大丈夫
- 第12回 アワヨンベは大丈夫 2024-07-17
- 第11回 モンスター 2024-06-17
- 第10回 ごきげんよう(後編) 2024-05-15
- 第9回 ごきげんよう(前編) 2024-04-18
- 第8回 ウサギ小屋の主人 2024-03-17
- 第7回 竹下通りの女王 2024-02-15
- 第6回 ママの恋人 2024-01-11
- 第5回 Nogi 2023-12-11
- 第4回 セイン・もんた 2023-11-15
- 第3回 私を怒鳴るパパの目は黄色だった 2023-10-13
- 第2回 宇宙人とその娘 2023-09-11
- 第1回 オール・アイズ・オン・ミー 2023-08-11
旅をしても僕はそのまま
- 第6回 ジャワ島のミコの家で 2024-05-03
- 第5回 アシジと僕の不完全さ 2024-01-27
- 第4回 ハバナのアルセニオス 2023-11-15
- 第3回 スリランカの教会にて 2023-09-16
- 第2回 クレタ島のメネラオス 2023-06-23
- 第1回 バリ島のゲストハウス 2023-05-31
おだやかな激情
- 第12回 わたしの青空 2024-06-01
- 第11回 なめらかな過去 2024-04-04
- 第10回 ちぐはぐな部屋 2024-03-05
- 第9回 この世の影を 2024-02-02
- 第8回 映したりしない 2024-01-11
- 第7回 とばされそうな 2023-12-04
- 第6回 はらはら落ちる 2023-11-01
- 第5回 もしもぶつかれば 2023-10-02
- 第4回 つややかな舌 2023-09-02
- 第3回 鴨になりたい 2023-08-01
- 第2回 かがやくばかり 2023-07-04
- 第1回 いまこのからだで目に映るもの 2023-05-31
- 第4回 うまくいかなくても生きていく──『十二月の十日』ジョージ・ソーンダーズ 2023-09-25
- 第3回 元恋人の結婚式を回避するために海外逃亡──『レス』アンドリュー・ショーン・グリア 2023-04-21
- 第2回 とにかく尽くし暴走する、エクストリーム片思い──『愛がなんだ』角田光代 2023-01-17
偏愛百景
- 第12回 捨てられない物 2024-01-10
- 第11回 響け、鍵盤ハーモニカ! 2023-10-13
- 第10回 高校野球を見ると泣いてしまう大人たち。 2023-08-09
- 第9回 毒をもって毒を 2023-06-21
- 第8回 春うららと畑仕事 2023-04-05
- 第7回 おかまいなくの店 2023-02-20
- 第6回 A面B面 2022-12-27
- 第5回 割れ物注意 2022-10-13
- 第4回 うちわの少年 2022-09-08
- 第3回 夏の月とラジオ体操 2022-08-08
- 第2回 ありがたい人 2022-06-24
- 第1回 賞味期限 2022-05-23
B面の音盤クロニクル
- 第9回 それが自由でなくてなんなのだろう──Aretha Franklin, “Amazing Grace” 2024-06-06
- 第8回 その日はあいにく空いてなくてね──Bobby Charles, “Save Me Jesus” 2024-03-08
- 第7回 クリスマスのレコードはボイコットする 2023-12-22
- 第6回 とうとう会得した自由が通底している 2023-05-06
- 第5回 あれからジャズを聴いている理由──”Seven Steps to Heaven” Feat. Herbie Hancock 2023-04-04
- 第4回 「本質的な簡素さ」の歌声──Mavis Staples “We’ll Never Turn Back” 2023-03-01
- 第3回 我が家にレコードプレイヤーがやってきた──Leon Redbone “Double Time” 2023-01-08
- 第2回 手に届きそうな三日月が空に浮かんでいる──Ry Cooder “Paradise and Lunch” 2022-12-07
- 第1回 きっと私たちが会うことはもうないだろう Allen Toussaint “Life, Love, and Faith” 2022-11-04
- 第16回(最終回) 「本物の詐欺を見せてやるぜ」@ジョン・ライドン 2022-07-04
- 第15回 文明化と道徳化のロックンロール 2022-06-10
- 第14回 ミスマッチにより青年は荒野を目指す 2022-06-02
- 10 もうひとつの現実世界――ポスト・トゥルース時代の共同幻想(後編) 2021-07-06
- 9 もうひとつの現実世界──ポスト・トゥルース時代の共同幻想(前編) 2021-05-03
- 8 あるいはハーシュノイズでいっぱいの未来 2020-05-05
第3回 神の子は皆踊る
稀代のフィギュアスケーター、羽生結弦。いまだとらえがたいその実像と業績を、歴史のなかに位置づける。文筆家の日野百草がおくる渾身の羽生結弦論。
私はどうしていいか、いきなりわからなくなってしまった
あの日、私は「GIFT」公演において、こう記した。(※1)
2023年2月26日、東京ドーム「GIFT」。いま一度自分の原稿を読めば、こうもある。
私はただ受け取ればいい、そう思っていた。あまりに甘すぎた。火の鳥の羽根は美しいが、それを手にした者をも時に焼き尽くす。私にその覚悟がなかったということか
私の俗人的な思考を、羽生結弦という「火の鳥」はいとも簡単に焼き尽くした。この国は、とんでもない「怪物」を抱えてしまっている。私はあまりに羽生結弦という火の鳥、すなわち「神」を知らなすぎた
文中の「怪物」および「神」についてはフリードリヒ・ニーチェにからめて記しているが、ここでは措く。
私がもうひとつ、あの火の鳥に見たものは遥か100年以上前にこの世界を、すべての芸術を変えた舞踏集団「バレエ・リュス」であった。20世紀の西洋芸術とそれ以前は、このバレエ・リュスによって分けられる。
その、いまもって「空前絶後の最強バレエ団」とされるバレエ・リュス(※2)。それほどまでの革新を、私は羽生結弦が火の鳥として登場したその姿をジュニア時代といまそこにあるプロ転向後の羽生結弦、そして100年前のバレエ・リュスとに重ね合わせていた。交互に感情を侵蝕するそのプリズムに〈私はどうしていいか、いきなりわからなくなってしまった〉。
バレエ・リュスはロシア人、セルゲイ・ディアギレフを主宰に、当初は「セゾン・リュス」として1909年、フランス・シャトレ座で活動を始めた。
ロシア帝室劇場(マリインスキー劇場)の有力なスタッフであったディアギレフ、しかし組織内の軋轢と後ろ盾だったウラジミール大公の死によって事実上、居場所を失っていた。自身の活路を見出すためにも、海外公演で成功することは必然であった。
まず手掛けたのはロシア芸術をヨーロッパ各国に披露するための演奏とオペラ、そしてバレエを盛り込んだ、いわば合同公演のようなものだった。クラシック音楽やオペラに比べて当時のバレエはおまけのようなもので、とくに男性の舞踏に拒否感の強かったパリでは「野蛮なるもの」と呼ばれていた。(※3)
またディアギレフを嫌うロシア帝室劇場の伝統派は「ディアギレフのやり方では正しいロシア・バレエは見せられない」(※4)と否定的だった。
ディアギレフからすれば「それまでのやり方」ではいつまでも「野蛮なるもの」のイメージを覆すことができない。当時、最先端の芸術が集まるパリだからこそ「それまでにないもの」を創造するべきであり、そもそもロシア・バレエは他国が知らないだけで常に革新の積み重ねだったのではないか――ディアギレフの信念は揺るがなかった。借金を重ね、足りない時は自ら照明係までして公演を続けた。毀誉褒貶の激しい彼だが、芸術と伝統、そして祖国愛には真摯だった。
才能あふれるバレエダンサー――「神の子」の多くも彼を支えた。彼らの多くはすでに成功している者も、これからの者もロシアの外に出たがっていた。もしくはまだあまりに若く、その熱情は保守的な帝室劇場から羽ばたくチャンスを欲していた。立ち上げ初期に名前のあるダンサーたち、ミハイル・フォーキン、アンナ・パヴロワ、タマーラ・カルサーヴィナ、イダ・ルビンシュタイン、エカテリーナ・ゲリツェル、アレクサンドル・ヴォリーニン、リディア・ロポコワ――もちろん「踊る神」、ヴァツラーフ・ニジンスキーもそのひとりである。
そうしてディアギレフは1911年、正式に「バレエ・リュス」を結成する。世界初の総合芸術としてのバレエ団、20世紀芸術の幕開けだった。結成後もレオニード・マシーン、ジョージ・バランシン、ブロニスラヴァ・ニジンスカ(ニジンスキーの妹)らがディアギレフに見出される。
しかし、実はその一年前――1910年、ディアギレフの勝負は二度目のパリ公演にこそあった、あれはまぐれ、前回と劣ると言われてはならないからこそ大事な二度目のパリ公演、舞台はオペラ座。
二度目のパリ公演で披露する新しいプログラム、主要演目は三作品と決まった。まずロシア芸術を伝えるためにロシア人作曲家リムスキー=コルサコフの『シェエラザード』、パリの観客に馴染みのあるフランス人作家テオフィル・ゴーティエの『ジゼル』、そしてまったくの新作としてロシア民話『火の鳥』を新たにバレエに起こすと決まった。
作曲は当初、ロシア民話の楽曲化に実績のあるアナトーリ・リャードフだったが、「遅筆な彼では間に合わない」とディアギレフは新人音楽家、イーゴリ・ストラヴィンスキーの名を挙げた。会議の参加者の多くはその若者の名を知らなかった。
振付師でもあったダンサー、フォーキンは以前からロシア民話のバレエを自身の手で作りたいと思っていたので台本を書き、振り付けた。稽古に入るとダンサーたちはその聞いたこともないリズムとそれまでのバレエにないテンポとに困惑した。ストラヴィンスキー自ら稽古でピアノを弾き、フォーキンも大胆な振り付けで「身体で躍り込む」ことをダンサーたちに要求した。本番ではディアギレフが自らデザインした照明器具を使い、照明技師として現場に参加した。舞台上では本物の馬を使い、観客を驚かせた。(※5)
フォーキンが王子役を自らダンサーとして演じ、火の鳥の役は古典から新作まで器用にこなせるとしてカルサーヴィナが選ばれ、舞った。指揮者はフランス人で舞台音楽にも実績のあったロマン派のガブリエル・ピエルネ、美術はアールヌーヴォーを代表する芸術家であるアレクサンドル・ゴロヴィーンが担当した。(※6)
かくして『火の鳥』は上演された。ディアギレフの思惑通り翌日の新聞で大々的に絶賛され、公演は延長された。スケジュールの問題で火の鳥役のカルサーヴィナが降板せざるを得なくなったためマリインスキー・バレエのプリマ、ゲリツェルが代役に挙がった。しかしディアギレフは「彼女ではない」と拒否した。そこでフォーキンの紹介で、バレエ学校を出たばかりの少女が抜擢される。
リディア・ロポコワ、のちにその美貌と舞踏はパブロ・ピカソに影響を与え、20世紀最大の経済学者と呼ばれるジョン・メイナード・ケインズの妻となるバレリーナである。
彗星のごとく現れたその天才少女はほんの数日の稽古で火の鳥となり、そのデビューをバレエ・リュスのスタッフで『ディアギレフ・バレエ年代記』の著者でもあるセルゲイ・グリゴリエフは「素晴らしい第二回パリ公演の最後の事件」と記録している。フォーキンはダンサーとしてだけでなくコレオグラファーとしても認められ、ロポコワはスカウトされてアメリカへと渡る。もちろん『火の鳥』によってヨーロッパ全土にもっとも名を知らしめたのがストラヴィンスキーであったことは歴史が証明する通りである。(※7)
少し長くなったが『火の鳥』を中心としたバレエ・リュス(セゾン・リュス)の創立期とパリ公演とを書いた。新しき神の子らは20世紀の幕開けに皆踊り、私たちにたくさんの舞踏芸術という人類の宝を残してくれた。
このバレエ・リュスの物語と羽生結弦のプロ転向後の物語、実に重なる部分が多い。ニジンスキーの伝説も含めて、私は「RE_PRAY」公演を「ひとりバレエ・リュス」と書いた。
20世紀舞踏芸術の扉を開いた「バレエ・リュス」のプロデューサー、セルゲイ・ディアギレフと不世出のダンサー、ヴァーツラフ・ニジンスキー、音楽家のクロード・ドビュッシー、美術家のアンリ・マティス、装飾家としてのココ・シャネル、脚本家としてのジャン・コクトーという総合芸術を羽生結弦がひとりで成し遂げている――この私の夢想、本当に大胆過ぎるかもしれないし、実際は多くの協力者によって成し遂げられた『RE_PRAY』であることは承知だが、そう思わされるほどに、羽生結弦の興行は、一連のツアーはまさに「ひとりバレエ・リュス」の萌芽を思わせた。その可能性が、その才能が羽生結弦には、ある(※8)
もちろん羽生結弦はフィギュアスケーターなのだが、羽生結弦はフィギュアスケートにバレエ・リュスのような革新を芸術面でも、興行面でも展開し続けている。
例えばバレエ・リュスの第一回パリ公演を羽生結弦のプロ転向後の単独公演「PROLOGUE」とするなら、第二回パリ公演『火の鳥』は「GIFT」。そう、まさにあの羽生結弦が火の鳥となって登場した姿こそ、21世紀プロ・フィギュアスケートの幕開けを告げる姿であった。そのシンクロニティを目の当たりにした衝撃――故に〈私はどうしていいか、いきなりわからなくなってしまった〉ということだ。
ジュニア時代の『火の鳥』、そして「GIFT」の『火の鳥』、それは100年以上前のバレエ・リュスによって誕生した『火の鳥』から受け継がれている。フィギュアスケートでも『火の鳥』をプログラムとしたスケーターはいるが、羽生結弦の『火の鳥』はまさに革新の「継承」であった。その革新は「バレエ・リュス」同様にフィギュアスケート史のみならず舞踏芸術史、いや芸術史全般における革新として後世刻まれることだろう。
私たちもまた、100年前にバレエ・リュスを理解し、支持したパリの人々と同様に歴史の目撃者として、羽生結弦という時代を「神の子」と共に皆踊る。この時代を、歴史を創造する一体感もまた、羽生結弦という存在が「時代の子」である証左であることを確信している。
●参考文献
※1 日野百草「神となった羽生結弦の葛藤、自分自身と戦い続けた…応援者からの「GIFT」とともに帰ってきた「僕」」みんかぶマガジン, 2023年3月8日配信. https://mag.minkabu.jp/life-others/14605/?membership=1
※2 海野敏『バレエの世界史』 中央公論新社, 2023年, 202頁.
※3 アンナ・ガライダ『セルゲイ・ディアギレフによる芸術革命』ロシアNOW, ロシア・ビヨンド, 2017年. https://jp.rbth.com/longreads/dyagilev_ballet
※4 セルゲイ・グリゴリエフ, 薄井憲二監訳, 森瑠衣子ほか訳『ディアギレフ。バレエ年代記 1909-1929』平凡社, 2014年初版, 17頁.
※5 前掲書・グリゴリエフ, 32-37頁, 43頁.
※6 前掲書・グリゴリエフ, 37頁, 43-44頁.
※7 前掲書・グリゴリエフ, 45-46頁.
※8 日野百草「新たなる神話、「進化」のツアーは続く…「魂から滑らせていただきました」『RE_PRAY』横浜公演の完成度、そしてサプライズ。」みんかぶマガジン,2024年4月21日配信. https://mag.minkabu.jp/life-others/25040/?membership=1