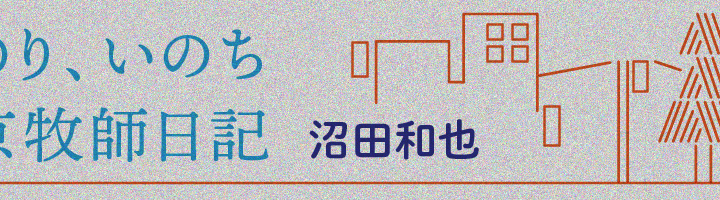教会のなかで出遭う人。教会の外で不意打ちのように出遭う人。一時は精神を病み、閉鎖病棟にも入った牧師が経験した、忘れえぬ人びととの出遭いと別れ。いま、本気で死にたいと願う、そんな人びとと対話を重ねてきた牧師が語る、人との出遭いなおしの物語。いのりは、いのちとつながっている。
最近、進藤龍也という男と友人になった。まだ知りあって一年にもならない。彼はペンテコステ派の牧師で、わたしとは信仰の背景もかなりちがう。むしろちがうからなのだろう、わたしは彼に強く惹かれるものを感じたのである。
彼は前科七犯の元ヤクザであり、だから牧師として正式に認定されてからすでに15年にもなるのに、たとえば教会の工事をしたりするときなど、銀行から融資を受けることができないという。それでも、彼は自らがどうやって立ち直ったのかについて、しばしばメディアをとおして語る。彼にとってはそれもイエス・キリストの福音を伝道するためであるが、なかには複雑な思いをする人もいる。「さんざん悪さをしておいて、立ち直ったらもてはやされるのか。真面目に生きてきて、ぜんぜん注目されない人間もいるというのに」。
わたしは進藤牧師が乗り越えてきたであろう壮絶な道のりに深い敬意を抱いている。だが同時に、彼に対して複雑な思いをする人がいる、その気持ちも分かってしまう。なぜなら、わたし自身がまさにそういう感情を、彼と出遭うまで持ってきた一人だからである。
じつは聖書に、ずばりこの問題と向きあった物語が収録されている。実際に起こった事件ではなく、イエスのたとえ話である。こういうたとえ話を即興で作ってしまうイエスには、現代でいうところの小説家や脚本家のような才能があったのかもしれない。要約するとその妙味が失われてしまうので、少し長いがそのまま引用する。なお、読みやすいよう段落分けを適宜加えた。
“ある人に息子が二人いた。弟のほうが父親に、「お父さん、私に財産の分け前をください」と言った。それで、父親は二人に身代を分けてやった。何日もたたないうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立ち、そこで身を持ち崩して財産を無駄遣いしてしまった。
何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それで、その地方に住む裕福な人のところへ身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって、豚の世話をさせた。彼は、豚の食べるいなご豆で腹を満たしたいほどであったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで、彼は我に返って言った。「父のところには、あんなに大勢の雇い人がいて、有り余るほどのパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここをたち、父のところに行って言おう。『お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。』」
そこで、彼はそこをたち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。「お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。」しかし、父親は僕たちに言った。「急いで、いちばん良い衣を持って来て、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足には履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を引いて来て屠りなさい。食べて祝おう。この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。」そして、祝宴を始めた。
ところで、兄のほうは畑にいたが、家の近くに来ると、音楽や踊りの音が聞こえてきた。そこで、僕(しもべ)の一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。僕は言った。「弟さんが帰って来られました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛を屠られたのです。」兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出て来てなだめた。しかし、兄は父親に言った。「このとおり、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために、子山羊一匹すらくれなかったではありませんか。ところが、あなたのあの息子が、娼婦どもと一緒にあなたの身代を食い潰して帰って来ると、肥えた子牛を屠っておやりになる。」すると、父親は言った。「子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。喜び祝うのは当然ではないか。」”
(ルカによる福音書15章11節~32節 聖書協会共同訳)
「さんざん好きほうだいやってきた人間が赦されて幸福になれるのなら、真面目に生きてきた自分の地道な努力はなんだったんだ」。
この感情を払拭することは多くの人にとってとても難しいし、払拭できないことは愚かでも未熟でもない。最近読んだある本によると、人間は太古の昔、社会というものを形成し始めたときから、いわゆるフリーライダー(タダ乗りする人間)に対しては敵意を持って排除することで協働生活を維持してきたらしい。
たしかに、サボっている人間がすぐ横にいるのに自分だけ真面目に働くのはあほらしい。その人間が罰せられないのなら自分だってさぼりたい。そうやって協働からの逸脱が連鎖していけば、社会は崩壊する。だから協働からの逸脱者には厳罰をもって臨む──なるほど、理にかなった推測だと思う。
しかしイエスのたとえ話は、フリーライダーへの厳罰則に逆らっているようにみえる。生き直そうとする放蕩息子に対して処罰ではなく、ふたたび幸福になれるチャンスを与えるのである。このような発想はキリスト教に限らないかもしれない。わたしは仏典に疎いが、おそらくブッダの教えを信じて出家した人にも、重い過去を背負った人がいたはずである。フリーライダーを赦さないことが原則の社会において、フリーライドしてしまった過去をリセットする機能が(すべてではないかもしれないが、かなりの)宗教にはあるように思われる。
放蕩息子の話を教会で聞くとき、たいていの人は放蕩息子に注目するし、自身の不信仰を彼に投影するだろう。だがその人はよほどの経験をしていない限り、社会的には放蕩息子ではなく兄のほうである。かつてのわたしにとっても、法的に逸脱した過去を持つ人はテレビニュースの向こうにいた。
わたしも含めた多くの人々は、報道をとおして事件に注目し、怒りや悲しみを覚える。しかし、罪を犯した彼ら彼女らがどのように裁判を受け、少年院や刑務所のなかでどのような服役をし、出所後はどんな生活をしているのかについて、わたしたちはほとんど知らないし、興味を持つこともない。犯罪者がどのように刑期を務めるのかなど知らなくても、生活に支障はないからだ。痛ましいニュースを見て感情を揺さぶられても、それは一時的にすぎず、忙しい生活のなかですぐに忘れてしまう。わたしたちは放蕩息子の受けた報いを、具体的に想像することが難しいのである。
しかしときには進藤牧師のように、元受刑者がみずから発信したり、取材を受けたりする場面に接することもある。そのとき、前科なく生きてきた人が、犯罪から更生した人を見て、苛立ちを覚えるのである。
「更生したらこんなに評価されるのか。自分はいっさい法を犯さず生きているが、仕事は厳しく、家にも居場所がない。でも、誰も『頑張っているね』なんて言ってくれない。元犯罪者がこんなに褒められるなんて、真面目に生きていることがあほらしい」。
法を犯していないからといって余裕のある生活ができているとは限らない。このように苛立つことは生理的というか、直感的な現象であると、わたしは思っている。もしもこの苛立ちを頭ごなしに「更生者への差別だ」と否定するなら、更生への社会的理解や受容はますます遠ざかるだろう。
学生の頃、ぜんぜん勉強しないで遊んでばかりいる友人がいた。あるとき、彼もいよいよ尻に火がついたのか、あわてて勉強しだした。すると、彼の持ち前の陽気さもあって、周囲から「やればできるじゃん!」と笑われていた。一方、もともと陰気な性格で、真面目に勉強することだけが取り柄だったわたしは、「ふだんから努力している人間は見向きもされないってわけだ」と、彼を逆恨みした。妬んだといってもいい。
わたしにもこういう経験の蓄積があるからだろう。わたしはこう思うのだ。誰かがそういう黒々とした感情を心に抱き、それを言い表したとき、「罪を犯した者がせっかく生き直そうと努力するようになったのに、喜んでやらないのか」と頭ごなしに責めるのであれば、責められたほうとしては、それこそふだんから真面目に努力してきたことがあほらしくなると。
たしかに、努力することや真面目であることは人から褒められるためにする行為ではない。とはいえ、である。自分の努力が他人から自明視され、いや、そもそも努力しているとすら気づかれなかったとき。いくら頑張っても努力とさえ見なされず、その頑張りがいっこうに注目もされないとき。そんなときに、以前は努力していなかった人間が、頑張りだしたら注目され、高い評価を受けるという事態が起こったとしたら。これまで真面目に生きてきた人は、「それはないだろう」という感情さえ抱いてはいけないのだろうか。むしろ、放蕩息子の兄のような感情が起こることを想定して、兄から見た弟の再起について考えるほうが現実的である。
ふだん不真面目なようにしか見えない人が「ときどき」頑張って評価されたとき。あるいは、過去にさんざん好き放題やった挙句に回心した人の、その回心がドラマティックに紹介されたとき。そんなときに湧き起こる「じゃあふだんから頑張っていて、誰からも注目も評価もされないわたしは?」という感覚。まさにこのわたしにも根強くこびりついている感覚。わたしはその感覚を正直に認めたうえで、他者の更生について考えたいのである。
わたしは放蕩息子ではなく、その兄である。そのように聖書を読むと、浪費の限りを尽くした弟と、父親の言うまま真面目に働いてきた兄との関係や、なぜ兄があんなに怒るのかが、ぜんぜんちがったふうに見えてくる。
そもそも放蕩息子はなぜ実家を出奔したのか。その理由をイエスは語らない。教会でこの話が読まれるとき、わたしたちもそこまで注意がいかない。だがイエスなら、そこは語らなくても意識はしていただろう。父親のもとから出奔せずにはおれなかった、息子の苦しい思いを。彼は結果として放蕩の限りを尽くした。なにもかもがうまくいかなかったわけだ。
キリスト教には罪という概念があるが、もとのギリシャ語を遡ると、それは戦争で槍を投げて、敵に命中しないことを言うらしい。「的外れ」ということである。戦争で槍を、ふざけて投げる兵士などおるまい。命がけで投げるだろう。だが敵には命中せず、ぜんぜん意味のない、あるいは間違えて味方のほうへと槍が飛んで行ってしまう。兵士にとっては致命的な自滅行為かもしれない。だが、彼は真剣勝負で槍を投げたのだ。放蕩息子の放蕩とは、そのふざけきった見かけにもかかわらず、彼の真剣勝負だった可能性はないだろうか。
前述したが、進藤牧師には七犯の前科がある。その詳細については、ぜひ彼の著作を読んでもらいたい。彼の前科について、わたしは当事者ではなく他人だからこそ、ひとつ言えることがある。それは、彼はヤクザになったときにも、彼なりに真剣な思いで、全力で槍を投げたのだということ。
進藤牧師の書斎には今、知的な書物がところ狭しと並んでいる。彼は今、学ぶこと、知ること、祈ることの喜びを知っている。そういう世界に今の彼は生きている。だが、ヤクザになった頃の進藤少年のまわりには、そういう世界があることを教えてくれる大人は誰もいなかった。本を読んだら楽しいかもしれないこと。教会に行ったら心が落ち着くかもしれないこと。喧嘩以外に物事を解決できる方法があるということ──そういう多様な世界が存在するということを、彼は知らなかった。彼は、彼の知っている力の世界のなかで、真剣勝負で力を振るおうとして、敗れたのだ。槍を投げても投げても、ことごとく的を外したから。彼が犯した罪は法的に裁かれた。そして彼はおのれの行いを法的に償った。だが法的な側面はともかく、彼の歩んできた人生におけるいくつもの過ちは、そのなにもかもが彼たったひとりの責任に帰されるものなのだろうか。わたしには、どうしてもそうは思えないのである。
今、社会には余裕がない。低賃金、重労働。恋愛や結婚の機会のなさ、孤立。苦しんではいるが法を遵守するマジョリティであるがゆえに、誰からも気にかけてもらえない人々が無数にいる。そういう人たちが、あるマイノリティに光が当たり応援されている姿を目の当たりにするとき、ときに強い怒りや悲しみを抱くことがある。わたしだって苦しいんだ! でも誰も助けてはくれないんだ。なぜおまえらだけ頑張りが評価されるんだ! わたしは認めないぞ、なにがマイノリティだ!──インターネットには弟の放蕩およびそこからの帰還を決して赦さず認めることのない、真面目な兄たちの悲痛な叫びがあふれている。
これらの叫びを「不寛容だ。マイノリティを差別し、抑圧しようとしている」として黙らせるなら、たしかに彼ら彼女らは黙るだろう。なぜならこの人たちは真面目だから。だが、そのはらわたは煮えくり返るだろう。いちど煮えくり返ったはらわたは、挫折した人間が生き直そうとすることを決して赦さず認めないだろう。
放蕩息子は果たして、ただふざけにふざけきって放蕩の限りを尽くしたのか。それは父の家における窮屈さへの反動ではなかったのか。窮屈だと感じた息子がなにもかも悪かったのか。それならなぜ父は無条件に放蕩息子を迎え入れたのか。父の側にもまた、息子を家にいられなくなるほど追い詰めてしまったことへの後悔はなかったか。
父のそばで黙々と働いてきた兄は、弟が帰還したとき初めて怒りをあらわにした。だが、怒りをあらわにしたのはこのときが初めてであったとしても、彼の心中はどうだったのか。彼は過酷な労働に耐えていた。だがこのときまで彼は父親から「子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。」という言葉を聞いたことがなかったのである。父親にとってそれは当たり前のことで、わざわざ言う必要もないことだと思っていたのかもしれない。だが長男からすれば、その一言こそが大切であった。その一言を、もっと前に言って欲しかったのだ。
前科がある人。あるいは法にはふれていなくても大きな挫折をし、社会的に見放された人。そういう人がやり直し、生き直しをはかるとき、それは放蕩息子の帰還に似ている。生き直そうとする人を受け入れる側の人々は、放蕩息子の兄である。帰還した弟に兄が「たいへんだったね。おれに協力できることはないかい?」と声をかけることができるためには、兄のほうもまた父親から「子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。」という肯定的な評価を、ふだんから分かるかたちで受けている必要がある。弟が帰還したとき初めて言われるのでは遅すぎるのだ。
元受刑者、あるいは他人に大きな迷惑をかけたり、傷つけてしまったりしたことのある人の社会復帰に複雑な思いを抱いている人々に、わたしは心から「おつかれさまです」と言いたい。あなたのその感情はおかしくない。なぜなら、あなたもまた黙殺されてきたのだから。でも、あなたが簡単には受け入れがたいと思っている、その人一人ひとりにも、あなたと同じように頑張ったのに報われなかったり、どう頑張ったらいいのか分からず苦しかった過去がある。だからいっしょに頑張ろう──わたしはそう、声をかけたい。
*この連載をもとに、大幅加筆した書籍『街の牧師 祈りといのち』が発売になりました。ぜひともご購読ください。
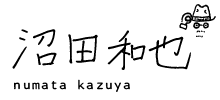 日本基督教団 牧師。1972年、兵庫県神戸市生まれ。高校を中退、引きこもる。その後、大検を経て受験浪人中、1995年、灘区にて阪神淡路大震災に遭遇。かろうじて入った大学も中退、再び引きこもるなどの紆余曲折を経た1998年、関西学院大学神学部に入学。2004年、同大学院神学研究科博士課程前期課程修了。そして伝道者の道へ。しかし2015年の初夏、職場でトラブルを起こし、精神科病院の閉鎖病棟に入院する。現在は東京都の小さな教会で再び牧師をしている。
日本基督教団 牧師。1972年、兵庫県神戸市生まれ。高校を中退、引きこもる。その後、大検を経て受験浪人中、1995年、灘区にて阪神淡路大震災に遭遇。かろうじて入った大学も中退、再び引きこもるなどの紆余曲折を経た1998年、関西学院大学神学部に入学。2004年、同大学院神学研究科博士課程前期課程修了。そして伝道者の道へ。しかし2015年の初夏、職場でトラブルを起こし、精神科病院の閉鎖病棟に入院する。現在は東京都の小さな教会で再び牧師をしている。
twitter