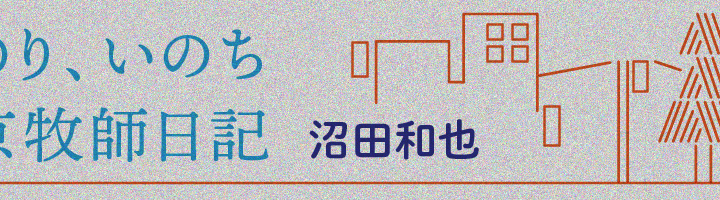教会のなかで出遭う人。教会の外で不意打ちのように出遭う人。一時は精神を病み、閉鎖病棟にも入った牧師が経験した、忘れえぬ人びととの出遭いと別れ。いま、本気で死にたいと願う、そんな人びとと対話を重ねてきた牧師が語る、人との出遭いなおしの物語。いのりは、いのちとつながっている。
"……あなたたち白人は人生に悲劇や喜劇を創れる。けれどもぼくには劇は存在しないのです。"
"なぜか、その瞬間ぼくは先ほど夕靄のポーチで近づけた糸子の平たい無感動な顔を思いうかべました。それは決して、この聖母の顔のモデルにすることのできない日本の女のあいまいな面貌でした……。"
(遠藤周作『白い人・黄色い人』)
今まで何人の人から、次の言葉を聞いてきただろう。
「『元気そうに見えるけど?』って言われるんですけどね」
言われるんですけどね────じっさいには、その人は元気ではない。元気ではないのに、元気だと見られるのである。
好意的に受け取るなら、こうなるだろう。つまり、まわりの人は、その人が見るからに元気がないことに気づいている。けれどもわざと「そんなことないよ、じゅうぶん元気そうだよ」と、本人を安心させようとしているつもりなのだと。相手から「最近しんどい」と打ち明けられて、うかつにも「そうだね。見るからに元気がないね」などと言ってしまえば、相手がますます落ち込むのではないかと。とはいえ「周りの人たちは安心させようとしてこのように言っている」では説明がつかない場合もある。それは、誰にも防ぐことのできなかった、より厳密に言えば、誰もその予兆に気づくことができなかった自死である。死んでしまう直前まで、ほんとうに元気そうだった。たしかに元気がない日もあったかもしれないけれど、最近はごくふつうだった。明日の予定とか、将来への希望さえ語っていた……。そういう人が唐突に命を絶つ。そういうケースは芸能界のニュースにも見られる。順調に活動している芸能人が、ある日とつぜん自死する。家族でさえその予兆に気づかない。ましてや一緒に仕事をしている人たちの誰一人として、その異変に気付くことがない。そういう場合、自死した本人以外の人々にとって、その人は死のまさに直前まで、まったくもって平常そのもの、元気に見えていたのである。
ある人が教会に電話をしてきた。この人からの電話はずいぶん久しぶりだ。受話器をとるまで、その人の存在を忘れていたほどである。「お久しぶりですね」というこちらの挨拶に対する相手の反応は重かった。受話器の向こうで言葉を選んでいるのか、ときおり沈黙しながら、声が聴こえてくる。
「やっと電話をかけられるほどには元気になりました。ほんとうに調子が悪かったときは、電話もできませんでした。そういうときって、相談する気力もないんです」
わたしがその人の存在を忘れてしまうほどの長期間、相手からは連絡がなかった。この、わたしの忘却を促した、相手の沈黙。これこそが、相手の最悪の不調を表現していたのである。相手が最も調子が悪かったときに、その絶不調ゆえの沈黙によって、わたしはその人のことを忘れてしまっていたのだ。ここに、人が調子を崩すことの本質がある。電車の広告で、自殺防止をアピールするポスターが貼られていた。そこには人が人を抱きしめるイラストと共に電話番号が書かれ、次のようなメッセージが添えられていた。
「独りで抱え込まないで」
独りで抱え込まないで、それは今すぐ相談しようという意味であるとすぐ分かる。けれどもわたしは思う。苦しんでいるのに相談しない人のなかには、そもそも苦しみを抱え込んでいるのではなく、抱え込む力さえ残されていない人もいるのではないかと。抱え込む力さえもはやないのだから、ポスターが「抱え込」んでいると表すところの苦しみを、誰かへと打ち明け、手放すだけの余力も残ってはいないのだ。苦しみを独りで抱え込めるだけの力がまだわずかでも残っている状態でこそ「独りで抱え込む」こともできるのだし、その苦しみを誰かに打ち明けようという気にもなりうる。教会に相談や打ち明け話をしにくる人、あるいは電話をかけてくる人は、そういう意味で、苦しむ人たちのなかで突出した人なのかもしれない。その背後には膨大な、もはや打ち明ける気力すら残っておらず、あとは斃れるのを待つばかりの人々がいるかもしれないのである。もちろん、そう語ったからといって、教会にアクセスできた人のほうが苦しみが少なかったというわけでは決してないのだが。
*
ところで、「元気そうに見える」理由はなんなのだろう。例えばうつ病のような、精神疾患として診断がなされている人でさえ、元気に見えることがある。だから「さぼっているのではないか」とか「甘えているのではないか」といった詮索をされて傷つくこともあるし、本人が先回りして「そんなふうに思われているのではないか」との焦燥感にかられることもある。いずれにせよ、そこにあるのは周りの人々と本人との認識の違いによる、当事者自身の孤立である。「誰にも分かってもらえないのだ」という孤立が、ただでさえ元気のない人に追い打ちをかける。
この「元気そうに見える」問題についてであるが、わたしは喜怒哀楽という概念が、苦しむ当事者と周囲の人々とのあいだに壁を作ってしまうのではないかと考えている。喜怒哀楽という四字熟語のルーツは儒教にあるという。『中庸』のなかに以下のような一文がある。
喜怒哀樂之未發,謂之中;發而皆中節,謂之和。(中庸章句 (國譯漢文大成) 出典Wikisource)
文意としては「喜怒哀楽がまだ発していない状態を中といい、喜怒哀楽が生じても節度があるときには和という」というところであろうか。中や和については「偏ることなく過不足がない」という程度に今は理解しておこう。とにかく、この一文が喜怒哀楽の語源となったわけである。人間の複雑な感情を簡潔にまとめた、見事な言葉である。ところで、喜び、怒り、哀しみ、楽しみは、お互いのあいだに明確な境界線を持っているのであろうか。なぜすぐれた人形劇は人形の精妙な動きによって、自在にその表情を変化させるのだろう。それは、人形師における動作の連続性と、人形の顔の連続性とがつながっているからではないか。もしも演者の身体の動きが固有の滑らかさを失ってしまったら、人形の顔はどの場面でも同じ、頭部にくっつけた仮面にしか見えないだろう。笑顔で泣いたり、怒りに燃えて歓喜したりすることは、一つ一つ区別された感情ではなく、それらの連続性や一体性のなかでこそ生まれるのだ。
ところで、ドラマではなくふだんの生活においても、わたしたちはそれら喜怒哀楽という表情理解から、他人の元気のなさも読み取ることができるはずである。じっさい、読み取れるからこそ「おつかれさま」とか「たいへんですね」といった声掛けもできるのだろう。けれども、顔に現われ出るものがいつもドラマのようにはっきりとしているとは限らない。もしもこれまで見たことのない表情を相手の顔に見いだしたとしたら、わたしたちはその表情を、なにを頼りに解釈するだろうか。案外、これまで見てきたドラマの集積から判断するかもしれない。ここでいうドラマとはアニメから実写、舞台に至るまでの、あらゆる演じられたもののことである。わたしたちの表情理解に対するドラマの影響は大きい。ドラマをたんに観るというよりも、日々浴びるように感受しているという意味において。
過日、舞台を観に行く機会があった。演劇については、わたしは素人程度の知識しかない。それでも劇場に行くとさまざまな感情を揺さぶられる。ところで舞台俳優はその演技において、後方席の観客にもよく分かるように身体を動かす。顔の表情もそうである。それこそ喜怒哀楽をはっきり、きっぱりと表すことで、会場の人たち皆と表情を共有する。もちろんあえて身体をほとんど動かさず、顔の表情もほぼ変えないような演技もあるだろうが、わたしのような演劇の初心者であっても楽しめるような演目であれば、俳優の演技はたいてい日常生活よりはるかにオーバーアクションである。
テレビドラマや映画の場合はどうであろうか。いずれもその性質上、遠くから見る観客への配慮は、舞台の観劇ほど必要ではない。それなら身体や顔の表情についても、演劇ほど大きな動きをしなくてよいかもしれない。とはいえ、大衆娯楽というか、肩の凝らないドラマ作品などを見てみれば、やはり登場人物の喜怒哀楽は分かりやすく演じられている。視聴者を退屈させないようテンポよくストーリーを展開させようとすれば、おのずとそうなるのだろう。ましてやアニメともなれば、目や口や鼻、身体の各部を表す記号の集合(鼻はしばしば省略されるのだが)で表情を作らなければならない。表情の演出はもっと大げさにならざるを得ないだろう。声優も声のみで演じる芸術なのだから、普通の人が日常的に会話する以上の情報を声に載せて演技しなければならないだろう。
こういったもろもろのドラマ群を、わたしたちは日ごろほとんど意識することなく、浴びるように見ているわけである。わたしたちは絶望の表情とか、深い悲しみの表情といったものを、そうした創作表現をとおしてあらかじめ蓄えている。人類が演じることの始まりは現実の模倣からだったであろうが、今や現実の表情を演技の振る舞いから学ぶわけである。わたしはこうした事実を批判しているのではない。子どもの頃からドラマに触れて育つことは、人間の感情を、そして感情の表現をゆたかにすると思っている。
ただ、ここで問題となるのが最初の話なのである。「元気そうに見えるね」と言われて、じつは元気ではない人がますます傷つき孤立してしまうという、この話である。「元気そう」の基準はなにか。見るからに元気いっぱいということではないにせよ、いわゆる「ふつうの顔」をしているということである。「ふつうの顔」とはなにかを説明するのは難しいが、消去法的には「顔色が悪くない」とか「哀しい顔をしていない」といったことになるだろう。しかしここで言われる顔色の悪さとか哀しそうな顔というイメージを、わたしたちはどこから手に入れたのか。身近な人の、体調不良で青ざめた顔や泣いている顔の記憶からかもしれない。しかし毎日のことで言うなら、とくに大人同士のつきあいのなかで、病院や斎場で働いているのならともかく、体調不良の人や泣いている人と出遭う頻度は少ない。そうした顔を見る機会はドラマのなかのほうがずっと多い。そして────これがわたしの最も言いたいことなのだが────ドラマの人間のような哀しい顔や絶望した表情を、じっさいに苦しんでいる人がすることは意外にも少ないのである。人々の予想に反して、わたしたちが漠然と「ふつうの顔」と見なしている顔のままで、人間は追い詰められていくのだ。ときには本人さえ自覚しないうちに。
元気そうに見える顔。そういう顔をともなって教会へと相談に来る人は、語り口も淡々としていることが多い。むしろ現実に生きている人が他人の前で、ドラマのような激しい感情を吐露することのほうが少ないとわたしは思う。教会に来て、わたしの想像を絶するようなつらい、ときには恐怖さえ覚える体験を、本人はといえばまるで他人事のように、ときには静かな微笑みさえ浮かべながら話すのである。
*
喜怒哀楽の語源として『中庸』の一文を紹介した。なるほど、中庸とまではいわないにせよ、わたしたちの顔の表情はじつにバランスがとれている。一気に泣き崩れたり、激しい怒りで顔を真っ赤にしたり、そういうことはあまりない。そういう顔をすることは、社会的に恥ずかしいとか、常軌を逸しているとか見なされるおそれもある。この社会的抑制が利きすぎてしまっているのか、そうとう苦しいことを内に秘めていてさえ、わたしたちの多くは「ふつうの顔」を保つことができてしまう。だから周りの人々からは元気そうに見える。その「ふつうの顔」の内側で人間は秘かに耐え忍んでいる。ある日とうとう耐えきれなくなったそのときには、遺された人々が口を揃えて「直前まで普段通りだった」と語る仕方で、二度と戻ってこなくなるのだ。
身近に悩んでいそうな人がいたら声をかけよう。独りで悩みを抱え込まないで、身近な人に相談しよう────だが、悩んでい「そうな」人は見つからない。いつもどおりの人が悩んでいるからである。そして、独りで悩みを抱え込む力さえ失った人には、身近な人に打ち明けるエネルギーも残されてはいない。全国各地に存在する命の電話やさまざまな相談機関が誠実に、懸命に支援活動をしているにもかかわらず、それでも自死をする人が後を絶たない背景には、このようなジレンマが横たわっている。
福音書にはイエス自身による、疲れはてた人への言葉がある。
"すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなたがたを休ませてあげよう。"(マタイによる福音書11章28節 聖書協会共同訳)
看板にこの聖句を掲げている教会もしばしば見かける。しかし現代を生きる人々は、重荷に圧し潰されそうになりながら「そろそろ休まないと危ない」ということにさえ気がつかない。奇妙に聞こえるかもしれないが、「疲れた、もうだめだ」と自覚することにさえ体力や気力がある程度必要なのだ。だから、すべてのエネルギーを使い果たしてしまった人は、誰かのもとに休みに行こうとも思わないだろう。気がつけば、いや、気がつかないままに、その人は重荷に圧し潰されてしまうのかもしれない。
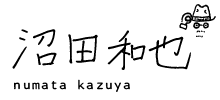 日本基督教団 牧師。1972年、兵庫県神戸市生まれ。高校を中退、引きこもる。その後、大検を経て受験浪人中、1995年、灘区にて阪神淡路大震災に遭遇。かろうじて入った大学も中退、再び引きこもるなどの紆余曲折を経た1998年、関西学院大学神学部に入学。2004年、同大学院神学研究科博士課程前期課程修了。そして伝道者の道へ。しかし2015年の初夏、職場でトラブルを起こし、精神科病院の閉鎖病棟に入院する。現在は東京都の小さな教会で再び牧師をしている。
日本基督教団 牧師。1972年、兵庫県神戸市生まれ。高校を中退、引きこもる。その後、大検を経て受験浪人中、1995年、灘区にて阪神淡路大震災に遭遇。かろうじて入った大学も中退、再び引きこもるなどの紆余曲折を経た1998年、関西学院大学神学部に入学。2004年、同大学院神学研究科博士課程前期課程修了。そして伝道者の道へ。しかし2015年の初夏、職場でトラブルを起こし、精神科病院の閉鎖病棟に入院する。現在は東京都の小さな教会で再び牧師をしている。
twitter