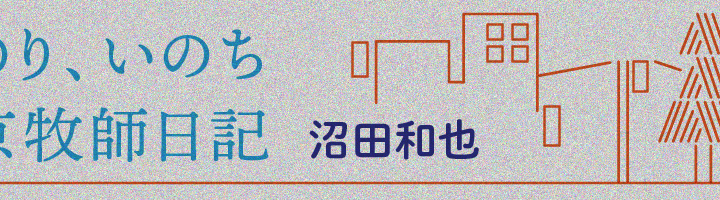教会のなかで出遭う人。教会の外で不意打ちのように出遭う人。一時は精神を病み、閉鎖病棟にも入った牧師が経験した、忘れえぬ人びととの出遭いと別れ。いま、本気で死にたいと願う、そんな人びとと対話を重ねてきた牧師が語る、人との出遭いなおしの物語。いのりは、いのちとつながっている。
わたしは一時期、牧師としての職がない状態、つまり赴任できる教会がない期間を過ごした。事実上の失業者、無職である。どこかの教会から招聘の声がかかる日はほんとうに来るのか、それさえも分からない不安定な状況。それでも声がかかったときにはすぐ応じられるように、あまり忙しいアルバイトをするわけにもいかなかった。結果的に、わたしは毎日なにもせず、しばらくはぶらぶらして過ごしていた。その間、先輩牧師たちのご厚意で、先輩たちが働いている諸教会や、定住牧師がいない教会の礼拝説教に呼んでもらえることもあった。呼んでもらえたときには御礼ということで1万円くらい貰えたので、とても助かった。そんななかで結婚式のアルバイトを紹介してくれた先輩もいる。
この結婚式というのが、なかなかやりがいのある面白いアルバイトだった。「結婚式場の牧師や神父はニセモノで、じつは英会話教室の教師」という噂がある。たんなる噂ではなく、ほんとうにそういうところもあるのかもしれない。じっさい、知人のキリスト教式の結婚式に参列したことがあるのだが、たしかにそこにいたのはアングロサクソン系とおぼしき白人男性であり、いかにもとってつけたような、もったいぶった片言の日本語を話し、その説教もキリストのキの字も出てこず、語るのはロマンチックラブばかりであった。
ただ、わたしが紹介されたホテルは違っていた。面接の際に「牧師であることの証明書をご持参ください」と言われた。わたしは日本基督教団の正教師認定の書類を持って行った。日本基督教団には補教師と正教師という二つの資格があり、補教師は一般的に伝道師と呼ばれ、正教師は牧師と呼ばれている。そして補教師は聖餐式や洗礼式を執り行うことができないが、正教師はできる。わたしが初任地において上司のもとで働いていたときは補教師だったため、礼拝説教はさせてもらえても、聖餐式や洗礼式はおろか、祝祷(そこにいる人々を神の名のもとに祝福する、礼拝の締めくくりの祈り)さえ許されていなかった。祝祷は必ず上司が行った。その教会での補教師の位置づけはあくまで見習い、上司の鞄持ちだったのである。
ただ、これについては日本基督教団内でも議論がある。というのも、地方の過疎地などに補教師が赴任した場合、礼拝の祝祷はもちろん自分でしなければならないし、聖餐式や洗礼式も、遠隔地の正教師をわざわざ呼んで執行してもらうのは大きな負担となるからだ。そういうわけで、正・補教師の制度が今のままでいいのか、それともいきなり牧師になれるようにするべきか、日本基督教団内では喧々諤々の議論が行われてきた。外部の人からすれば「そんなどうでもいいことにこだわらなくてもいいじゃないか」と思われるかもしれない。宗教における制度をめぐっての、お互いが譲れない議論というものは、たとえば天皇は男系であるべきか否かにまつわる議論のようなものである。フェミニズムなど現代の価値観からすればまったくどうでもよく聞こえても、天皇という存在自体が避けがたく宗教的な意味を帯びている以上、なぜ男系であることにあれほどこだわるのかについては、あるていどまでは理論で説明可能であっても、理詰めだけで語りきることはできない。それは信仰の領域に属するからである。
かくして、わたしは正教師認定の書類をホテルの事務所に持参し、それを現地でコピーしてもらって、結婚式場のアルバイトに採用された。おそらく僧侶や神職もそのようにして「本物である」ことを証明していると思われる。仏式や神式の結婚式においても、どこかの寺や神社で現在働いているか、過去に働いたことのある僧侶や神職が司式するからである。
ただ、いざ結婚式を始めてみると、ホテル側の注文は厳しかった。まず、典礼文のなかには必ず、ホテルの美しさを称える文言を挿入しなければならない。その場所で挙式ができること自体がめでたいという意味なのだろう。ホテルそれ自体を称えるなどおよそキリスト教的とはいえないが、アルバイトだから仕方ない。さらに、一日に何組もこなさないといけないので、新郎新婦の入場から退場まで、ぜんぶあわせて15分以内で納めなければならなかった。指輪交換がクライマックスなので、わたしが新郎新婦に伝えたい大切な神の言葉は、その前座のようなものだ。許された時間は5分。この短い時間に全力集中して、わたしは結婚についての説教をした。たった5分ではあったが、どの新郎新婦もわたしの顔をしっかり見て、メッセージを受けとってくれた。頷きながら聞いているカップルもいた。
わたしが話したのは、もちろんロマンチックラブではない。むしろその真逆である────あなたがた新郎新婦の前に十字架があるでしょう。あれは飾りではありません。キリストがそこで苦しみ、神と人とがその出来事をとおして和解したしるしなんです。これから結婚生活をするにあたり、毎日顔を突きあわせて暮らしていれば夫婦喧嘩もするでしょう。仕事や子どものことでつらい思いをすることもあるかもしれません。そういうときにこそ、あなたがたのその苦しみには意味があるということを、苦しみをご存知である神のまなざしのもと、ご夫婦いっしょに味わってください。キリストの十字架において神と人とが和解したように、あなたがたも何度でも和解してください。応援、お祈りしています────そんな話をした。
結婚式場のスタッフが、仕事のあいまに話しかけてくれた。
「キリスト教の結婚式に、そんな深い意味があるとは知りませんでした。勉強になりました」
思いがけない言葉が嬉しかった。信徒になってもらえるわけではないにせよ、福音に関心を持ってもらえるだけでも神の恵みを感じた。
その一方で、ホテル側の要求は回数を重ねるごとに厳しくなっていった。
「もっと短くできませんか。お話は3分以内でお願いします」
カップラーメンにお湯を注ぎ、フタを開けるまでのあいだに福音を届けなければならない。ようし、やってやろうではないか。わたしは要求どおり3分以内の話を考え、新郎新婦に語った。
わたしが立ちあった新郎新婦のほとんどが授かり婚、昔には「できちゃった婚」と言われていた人々であった。ホテルのスタッフも新婦の健康状態には細心の注意を払っていた。新郎新婦が親族と全体写真を撮る際、新婦が吐いてしまったこともある。真っ白なドレスは吐瀉物で汚れてしまった。親族はどよめき、ご本人も体調不良以上に身の置き場のない恥ずかしさを感じていることがありありと伝わってきた。あまりに痛ましかったが、ホテルのスタッフは慣れたもので、冷静かつ迅速に、あたたかく新婦のケアをしていた。一組一組のカップルに、式場に至るまでのそれぞれの事情があった。その一組一組、ひとりひとりに、神の祝福を祈らずにはおれなかった。
東京に来てからもボランティアで、何組かのカップルの結婚式を司式した。ある小さなバーを会場にして、招待客や居合わせた客と共に結婚を祝う光景は、ささやかながら美しかった。そこでもやはり、わたしは上記のような聖書の話をした。結婚生活は幸せなことばかりではない。困難なときにこそ試される。そんなときにこそ今日、この十字架の前に立ったことを想いだしてほしいと(バーには小さな木製の十字架を持参し、それをカウンターに置いて司式した)。式が終わった後には必ず新郎新婦に声をかけた。「困ったことがあったらいつでも相談してください」。
だが残念なことに、わたしが司式したカップルはその後、かなりの確率で離婚したのである。離婚した何組かのカップルの友人知人たちから、それぞれの事情を聞いているうちに、どのカップルにも共通した事情が浮き彫りとなった。すなわち、そもそもカップルというものがあまりにもクローズドな性質を持っているということである。カップルがカップルだけで閉じて完結しているという問題は、現代社会のさまざまな要素を凝縮しているように思われた。
たとえば地方出身の若者たちが東京で出逢い、二人暮らしを始める場合、そこには親族がいない。親戚づきあいなどのわずらわしさがないのは、たしかに気楽ではある。バーでのカジュアルな結婚式が象徴しているように、気の置けない友人たちとのカジュアルな付きあいが彼らの生活を織りなしている。だが、夫婦生活は楽しいことばかりではない。家事の分担はどうするのか。子育ては。お金の使い方をめぐっての、価値観の違い。楽しいデートをしていたときには予想もしていなかった問題が、次々に発生する。
では、友人たちに相談すればいいのか。必ずしもそうとは限らない。若者は遠慮することもある───ともだちはみんな忙しい。こんなことを相談すれば迷惑をかけてしまうかもしれない。そもそも、こんなことを人さまには言えない。みんなに祝ってもらったのに、今さらつらいなんて言えないよ。ともだちから距離を置かれてしまうかも。わたしにだってプライドがある。あの子とは/あいつとはたしかにともだちだけど、ライバルでもある。内心「ざまあみろ」と思われるのだけはいやだ────さまざまな想いが交錯する。親友にだけは話したくないことだってある。それは親しくないのとはぜんぜん違う。親しいからこそ話せないこともあるのだから。
遠くの父や母にも、会えない以上、相談できることには限りがある。親戚なんて、最後に会ったのはいつだろう……こうして相談の選択肢はどんどん狭まっていく。とりあえずは夫婦顔を突きあわせて、なんとか解決していくしかない。とはいえ、デートのときには楽しい話しかしたことがない。悩みを打ち明けても「たいへんだね」と言ってあげたり、言ってもらったりしたことしかない。あの頃はお互い余裕があったのだから。今さら「それはちがうと思うよ」と、面と向かっては言いにくい。相手を怒らせるのも、それに、自分が傷つくのも、いやだ。
そうやってお互い話しあうことを避けているうちにますます距離ができ、溝は深くなっていく。もやもやしたものが胸にうずまき、鬱憤がつもりにつもったある日、ちょっとしたことがきっかけで大喧嘩。溝は決定的となり、「じゃあ別れよう」。こうなってしまうのはカップルが未熟だったからなのだろうか。これは若い二人だけの責任なのだろうか。「まったく、いまどきの若者は」とため息をつくのが年長者の仕事だろうか。わたしは違うと思う。
わたしは近隣教会の牧師の紹介で、妻とお見合いをした。まったく知らない女性であった。お見合いで意気投合したのはいいのだが、わたしの任地は妻の実家からはるか遠くであったため、デートができたのはほんの数回に過ぎなかった。お互いのことをほとんど知らないまま、わたしたちは結婚したのである。戦前や戦後にはそういう結婚がふつうだったことを知ってはいたが、まさか自分がそんな仕方で結婚をするとは思ってもみなかった。
2000年代にもなって戦前戦後のような結婚をする難しさ。結婚生活の始まりは悲惨なものであった。妻はわたしの職場かつ住まいである教会へ、いわば「お嫁入り」してきた。もはや妻の両親も友人知人も、ここにはいない。妻は旧知の人が誰もいない、そして未だパートナーの正体さえも分からないところへ、独りで乗り込んできたのである。
妻が体調を崩したのは結婚後まもなくであった。布団から出てこなくなり、風呂にも入らない。わたしが食事を用意すればかろうじて食卓には就く。しかし食べればすぐ布団にもぐりこんでしまう。これではいったい、どうなってしまうのだろう。こんなことなら独身を謳歌したほうがよかったのだろうか。よその「元気な」牧師夫婦を見るにつけても羨ましさがこみあげた。
それでもわたしたちが離婚に至らなかったのはなぜかというと、夫婦だけで向きあうことをしなかったからだ。向きあうことから逃げたと言われればそのとおりである。わたしは自分が信頼している牧師に連日、相談の電話をし続けた。牧師がなんと答えてくれたのかは、相談の回数が多すぎて覚えていない。とにかく、そういう相談相手がいたということが重要だったのである。妻は妻で、なにかと口実を見つけては実家へと帰省し、旧友たちと会ったり、独身時代に通っていた教会でリフレッシュしたりしていた。その教会には彼女が打ち解けて話すことのできる年配の女性たちもいた。そうやって、お互いがお互いから逃げに逃げて、ぶつかりあうことは最小限に抑えて、夫婦生活はこんにちに至っている。それでも大喧嘩は何度もしたのであるが、そのたびにわたしは牧師に相談して頭を冷やしたあと、彼女に謝罪したし、彼女も謝ってくれたものだ。
わたしが相談していた牧師は、いわゆる「ともだち」ではない。恩師である。馴れ馴れしく話すことはできないが、そのぶん、打ち解けた友人たちには話せないようなこと、かなりプライベートでこみいったこと、たとえばお金や性の問題まで打ち明けることができた。それはその牧師が、わたしからも妻からもほどよく他人であり、利害関係がなく、かといってまったくの赤の他人でもなく、わたしたちのことをよく知ってはくれている、信頼できる存在だったからである。彼女にとっては教会の女性たちや、他にも幾人かの知人たちが、そういうほどよい距離感の人々であった。わたしたちにはそれぞれ、いわゆる親しい友人とはまた別の、客観的なまなざしでわたしたちのことを見てくれる、年長者の知りあいがいたのである。
わたしは最近、若いカップルの人たちにお節介をするようになった。若い人たちは遠慮をするから、それを額面通りに受け取って「彼らのことはそっとしておこう」というのが正論なのかもしれない。けれども若い人たちが交際しては別れ、結婚しては離婚するのを何組も見てきた今、あるていどの信頼を得た人たちに対しては、こちらから声掛けをするようにしているのだ。彼ら彼女らがツイッターに愚痴などを書いているのを見ると「最近うまくいっていないようだけど、大丈夫ですか」とダイレクトメッセージを送ったりする。「大丈夫です」と言われたら深入りはしないが、相手が「じつは」と相談してきたら、とことんかかわるようにしている。カップルの同棲する家にまで出向いたこともある。関係がぎくしゃくしている二人が、二人だけで顔を突きあわせて話しあうと、ますます険悪になってしまうこともあるからだ。そこでわたしがあいだに入り、二人にかわるがわる話をしてもらうのである。それで二人がうまくいくのかどうかは分からない。最後に決めるのは本人たちなのだから。ただ、できる限りのお世話は、たとえ結果的に「よけいな」お世話になってしまったとしても、してあげたいと思うのである。
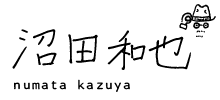 日本基督教団 牧師。1972年、兵庫県神戸市生まれ。高校を中退、引きこもる。その後、大検を経て受験浪人中、1995年、灘区にて阪神淡路大震災に遭遇。かろうじて入った大学も中退、再び引きこもるなどの紆余曲折を経た1998年、関西学院大学神学部に入学。2004年、同大学院神学研究科博士課程前期課程修了。そして伝道者の道へ。しかし2015年の初夏、職場でトラブルを起こし、精神科病院の閉鎖病棟に入院する。現在は東京都の小さな教会で再び牧師をしている。
日本基督教団 牧師。1972年、兵庫県神戸市生まれ。高校を中退、引きこもる。その後、大検を経て受験浪人中、1995年、灘区にて阪神淡路大震災に遭遇。かろうじて入った大学も中退、再び引きこもるなどの紆余曲折を経た1998年、関西学院大学神学部に入学。2004年、同大学院神学研究科博士課程前期課程修了。そして伝道者の道へ。しかし2015年の初夏、職場でトラブルを起こし、精神科病院の閉鎖病棟に入院する。現在は東京都の小さな教会で再び牧師をしている。
twitter