内田樹先生と三砂ちづる先生の往復書簡による、旧くてあたらしい子育て論。ともに離婚により、男手で女の子を育てあげた内田先生と、女手で男の子を育てあげた三砂先生。その経験知をふまえた、一見保守的に見えるけれども、実はいまの時代にあわせてアップデートされた、これから男の子・女の子の育て方。あたらしい世代を育てる親たちへのあたたかなエール。
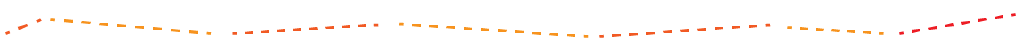
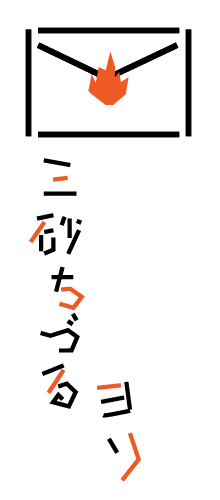
第12便・A
無条件に愛されること、無条件に見守られること
内田先生、こんにちは。
ごめんなさい、お返事遅くなってしまいました。すっかり季節がかわってしまいました。パソコンの目の前にあるお隣の大きな桜の木、ほとんど葉が落ちてしまっています。2022年も終わりに向かいますね。お変わりありませんか。
四月から全面対面授業に戻った勤め先の女子大も今年度最終タームに突入しました。ここでは、一年生から、ゼミの練習をするためのゼミ、というのをやっています。少人数で話をしたり、レジュメを作って発表をしたり、司会をしたりして、大学での勉強の仕方を一年かけて学びます。
先日、「ポル・ポト政権時代の仏教徒弾圧について」発表をしてくれた学生がいました。まだ10代半ばの頃にカンボジアを訪問して、キリング・フィールドとかツールスレン収容所跡などを訪ね、彼の国の歴史に深く思いを馳せることがあったようです。カンボジアの現代史について知っている学生もいれば、知らない学生もいますが、カンボジアのポル・ポト政権の時代って、あなたたちには世界史に書いてある「事項」かもしれないけれど、私自身がちょうど大学生くらいだった時にあったことですよ、というと、みんな、呆然としています。彼女たちにとって昭和の出来事、は、明治、大正、が歴史上の大昔……であるのとほとんど変わらない昔々あるところに……の話で、自分の目の前でそこそこ元気そうにしゃべっている人が、しっかり記憶のある青年時代に経験してきたこと、というふうにはとらえられないんですよね。
ソ連の崩壊、冷戦の終結とか、私が子どもを産んで育てていた、ほんの30年ほど前の出来事で、私くらいの年齢の人間にとっては、起きるはずがないと思うことが起こった、ということだったんですよ、というと、もっと片付かないような顔をしています。「歴史」ってね、思ったより身近なところで、「歴史」になっていっているわけですよ、というと、しん、とします。
今の大学生の祖父母世代である私たちは、自分の若い頃生きてきた頃のあれこれをその前の戦中戦後世代と比べて、どうやら語るに値しないこと、と思っているふうがありますよね。少なくとも大人になってから、食べるものに困る、死んでいく人が周りにたくさんいる、戦時状態である、とか、そういう前の世代のようなドラマティックなことを経験したわけではなくて、高度成長期から今まで、生活スタイルは通信、デジタル関係では様変わりしたものの、ずっと似たような、お金稼いでお金使って生活を豊かにもっと自由に、というエトスの中で生きてきたから、次世代に語るべきことなんてあんまりないよな、と思っているような気がします。内田先生が、「古老に聞く」タイプのお仕事に追われているということ、そして、「リアルタイムでその出来事があったときに同時代の人たちが何を感じ、どういう表情やどういう言葉づかいでそれについて語ったのかは、その場にいた人間しか記憶していません。そういう「現代史の生き証人であるところの古老」というポジション」で語る必要性があるんだ、とおっしゃることが、まことに腑に落ちていく感じです。語ることはないわけではなく、語っていい、と思っていなかったのですが、語る必要はないわけではありませんよね。
さらに1950年代後半生まれの私たちは、強大で影響力の強かった団塊の世代に遅れること10年、何をか語らん、何もいうことない、みたいな時代の雰囲気で20代をアパシーと共に過ごした年代ですから、自分が「古老」になれるはずない、と思っているところがあるのですが、どんどん年齢的にはそうなっていくわけで、自らの経験の細かなディーテイルにこそ、現代史があるのだ、と思って、語り始めるしかありません。
冒頭のゼミ生、高校生の頃に訪問したカンボジアに興味を持ち続けており、大学に入ったら、またすぐ再訪できると思っていたのに、できなくなってしまった・・・と話していました。2020年初頭からのCOVID-19パンデミックであっという間に世界の人の動きは止まってしまい、2022年も終わろうとする今、検疫の水際対策自体は緩和されてきていますけれど、移動する人の数はそれほどは戻っていません。それほどの人が移動していないところに、燃料も高騰しているわけですから、チケット自体がものすごく高い。びっくりするような燃料サーチャージがかるようです。ヨーロッパ往復はチケットを別にして、燃料サーチャージだけで12万とか13万とか・・・ちょっと前までチケット自体がその値段(あるいはもっと安く)で買えたものですけれども。輪をかけての円安。気軽に海外に出かけられる時代は、あっという間に終わってしまいましたね。
グローバリゼーション、とか浮かれて、いつでも好きな時に外国に行って、帰ってきて、やりたければどこでなんでもできるように見えていた時代は、もう過去のものです。その最中にいる時には、なんだか永遠に続くように思われるあれこれも、あっという間に変わってしまう。あの、能天気にみんなが世界を巡っていた時代のことも、また、語られることがあるでしょうか。
このところ、東京から沖縄、石垣に向かう便をよく使っています。どの曜日に乗っても、いつも若いカップルと家族で、飛行機はほぼ満員です。海外旅行があまりに高額なのと、円安なのと、まだまだパンデミックの余波で海外に気楽に出かけられないのと、全国旅行支援も始まったのと・・・などなどが相まって、海外の代わりに行く旅行先は本土復帰五十周年の沖縄、なのでしょうかね。
若いカップルはともかく、幼い子ども連れがとても多い。乳児、幼児、さらに、明らかに学齢期の子どもたち連れの家族がたくさん搭乗しておられる。学校の休みでもない時期の平日です。学校が休みでもない、平日に旅行する。親が休みさえ取れれば、それは、いいですよね、安いし。混まないし。で、親御さんたちはそういう決定をするようになったみたいです。ちょっと前まで、あまりこういうことはしませんでしたよね。親が子連れで田舎に帰ったり、旅行をしたり(だいたい親と「田舎に帰る」以外の旅行をする、ということが始まったのも、実はごく最近のことである気もしますが)するのは、学校が休みの時期であり、週休二日になってからは土日であり、少々重要な家族の行事があっても、子どもが学校に行っている時期なら、彼らの学校登校が優先していて、家族で子どもと出かける、とか考えることもなかったように思います。
十年暮らして、子どもを育てていたブラジルの学校のことを思い出します。学校は大した“力”を家族に対して、持っていませんでした。何があろうが、家族が優先でした。そのように見えていました。ブラジルの、普通の、小中高校は、ほとんどが二部制であり、午前中か午後か、どちらかにしか学校に行きません。朝7−12時か、午後1−6時か、希望して登校する時間を選ぶことができました。
小学生くらいですと、親の都合で子どもを午前登校か、午後登校か、親が適当に決めるのです。ああ、我が家は飲食業で親が夜遅い生活だから、子どもの学校は午後にしておこうとか、親の仕事に出かける時間が早いから(結構、7時代に仕事が始まったりしていました)、子どもの学校は午前中にしておこう、とかそういう感じ。世の中の子どもというものは、朝、早起きさせて、ご飯食べさせて送り出すもの、と思っていた私は、「午後登校」組の友人宅に遊びに行って、子どもたちが朝10時ごろぼやーっと起き出してきて、親も、うち、ほら、夜遅いからねえ、とか言っているのを見て、衝撃を受けました。それでいいのだ、と。
半日しか行かないブラジルの学校は、国語算数理科社会といういわゆる基礎教科だけを勉強するところであり、それだけ勉強するくらいの時間しか取れないから、音楽や体育という科目も本格的なものは何もなく、学級活動、にあたるようなものも、まったくありません。
そもそも午前と午後に違う生徒が来て教室をつかいますから、ホームルームもないので子どもにとって「自分の机」、「自分の場所」のような、親密な空間、というものも学校に出現しません。大きめの「学習塾」をイメージしてもらえばいいような空間でした。親のほうも、子どもの性格とか、集団での協調性とか、そういうことに対して学校なんかに口を出してもらいたいと思っていなくて、そういうのは家庭の領域だと思っていた(ように見えました)。要するに子どもの生活に占める学校の割合が日本に比べて極端に低い。
だから、家族の旅行や家族の都合で学校を平気で休ませていました。ああ、今日はね、休みが終わって初日だから、学校何にもないから、行かせなかったわよ、とか、家族でサンパウロ行くからね、とか、平気で学校を休ませていた。当時の私は、そんなものかな、それでいいんだな、と思っていたのは既に四半世紀前のことですが、日本もそうなりつつあるのでしょう。保育士や教員など子どもに関わる仕事をしている友人に聞くと、今の親御さんたちは、親側の都合で子どもの学校を休ませることは、ありだ、という雰囲気が確かにあるらしく、家族で旅行するから、とお休みする子も決して珍しいことではなくなっているそうです。東京―石垣便にたくさんの子どもが乗っていることも、さもありなん、なようです。
小中学生の不登校が25万人に近くなり、そうなると一クラスに一人か二人は学校に来ない子がいる、ということになるでしょうから、名実ともに「学校に行かない」ということがそんなに珍しいことではなくなりつつあります。「学校に行きたくない」、「学校はつらいところ」、「学校は行かなくてもいいなら行きたくないところ」、「学校は自分が行って楽しいところ」では、もはや、ない。というかそんなふうに学校が楽しい、なんて思っていた子どもは元々そんなにたくさんいなかったのかもしれませんね。私自身のことを思い起こしてみても、学校は少しも楽しいところではありませんでした。
元々今となっては親に申し訳なかったと思うくらい、不機嫌な子どもで、当然人と交わるのは苦手、外に出て遊ぶのもきらい。それは、小児喘息で体が弱いせいだ、と思われていたので、ずーっと家にいて、字が読めるようになったら、というか字を読むくらいしかやることがないために、早々に字を覚え、ひたすら何か読んでいた活字中毒の内向的な幼児が、幼稚園とか小学校とかに馴染めるはずもありません。
幼稚園は私の世代は行っている人が多かったので私も一年行きましたが、毎月休んでばかり。小学校に行っても、50分の授業に座っていることができず、トイレに行く、保健室に行く、と途中で何度も教室を出て行っては、人気のない学校の踊り場で呆然としながら、なんでこんなところにいなければならないのかなあ、と思っていました。学校は、自分にとって、決して居心地の良いところでも、安心できるところでもなかったのですが、行かねばならないから行っていた、というだけです。中学生になって、自分の意見の一つも言えるようになり、高校生になって何もかも言われる通りにやらなければならないわけではなくなり、立派な図書館の書庫の隅に自分の好きな場所を見つけることができるようになり、なんとかかんとか、小中高を終えた、と思います。
学校が嫌だったから、家が居心地がよかったのか、というと、後になって思えば、そんなに居心地がよかったわけではないんですね。前回のお手紙で内田先生が書いておられたように、「自分は、子どもの頃に、父と母と兄から深く愛されて育った、見守ってもらっていた」、と、そういうふうに長く自信を持って言えなかったのは、同居している祖父母が仲が悪く、また、自らの父と母も仲が悪く、祖母と母も、仲が悪く、そんな中で、子どもは長く私一人、という状況で育ったからだと思います。
子どもは一人しかいないのだから、みんな、子どもに愛情が行ってもいいはずなのに、今思うと、みんな、自分のことで結構大変だったんだな、と思います。家にいる対の関係が穏やかである、ということは全ての家庭生活を穏やかに推移していくための重要な条件でしょう。たとえ、それが対の片方が、一方的に忍従を求められていたとしても、家の中を穏やかにするために、それが必要だと思えば、それを意志をもって選び取られていたのではないか、と思われるくらいです。
祖母が祖父に声を荒げていた日々、単身赴任している父が家に帰ってくるたびに母と言い争いをしている日々がその家に住んでいる唯一の子どもである私に快適ではなかったのではないかな、と気づいたのは、大学生になって家を出て、一人で住み始めてからでした。子どもである、とは、自らの置かれている状況を客観的に捉えることはできない、ということですから。
それでも、私は、祖父母や父母の、彼らのとても大変な日常の中で、彼らのそういった時代と個人的状況の制限の中で、私のことを愛していてくれたんだな、それを私が十分に感じられなかったことも、彼らにとってはとても残念に思うことだっただろうな、と今は思います。
彼らに「無条件に愛された」という自信をもらい損ねたように見える私も、内田先生がおっしゃっている、もう片方の家族からの贈り物、「見守られていた」は、確実に、豊かに享受していたのです。毎日気持ちの良い暖かいお布団で眠り、洗濯されたきれいな服を着て、朝昼晩、とご飯を作ってもらい、帰宅すれば母がいた、祖父母がいた、という暮らし自体によって私が得ていた安定感は、何にも増して大きなものでした。そう思えば、子どもには「無条件に愛された」あるいは「無条件に見守られた」のどちらかを提供することができれば、「子育て」している親としては満点、なんじゃないか、とか思ってしまいますね。
内田先生の「できるだけ個人的な、偏頗なことを書いて、「子育て」についてのできあいの物語を混乱させ」ようという試み、自分のことも少し書きたくなりました。今日はこの辺りで。寒くなりますが、どうか、ご自愛くださいませ。
三砂ちづる 拝
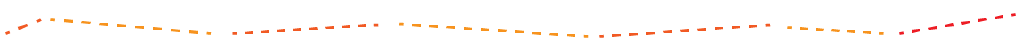
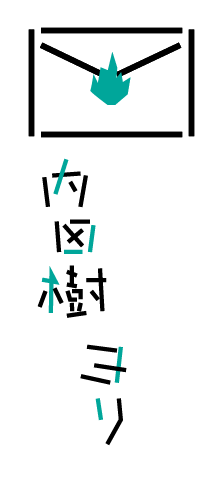
第11便・B
大人たちから子どもを守るために学校は生まれた
三砂先生
こんにちは。内田樹です。
今回は頂いてから10日ほどでご返事を書き始めることができました。ようやく大きな仕事のうちの一つ(「アメリカ論」)が片づいて、ちょっとだけ肩の荷をおろしたところです。少しだけ気持ちの余裕が出てきました。
前便でも書いたように、他の仕事は(資本論も農本主義もこの子育て論も)すぐに出さないと速報性を失って価値がなくなるというような種類の話ではないのですが、アメリカ論だけは国際関係がこの先激変してしまうと、リーダビリティを失う部分があるかも知れないので、ちょっと急いでいたのです。ウクライナ戦争の帰趨次第ではNATOとロシアの間で戦端が開かれるかも知れません。第三次世界大戦が始まってしまったあとになって、「世界はこれからどうなる」というようなことをのんびり書いた本を出すのもあまり意味がないかも知れないと思って急いでいたのです。でも、よく考えたら、それは子育て論だって同じですね。
それくらいに世界は激動のうちにあるわけですけれども、それでも僕がなんとなく「第三次世界大戦は起こらないんじゃないかな」と無根拠の楽観のうちにいられるのは、「第三次世界大戦が起きる」という不安のうちに少年時代を送り、そのうちにその不安に「慣れてしまった」という1950年生まれの「古老」の、これもまた特殊な経験のせいかも知れません。
僕が中学生の頃(1962年から65年)はSFが一気に人気ジャンルになった時代でした。SFという文学ジャンルがアメリカで発祥したのは、「人類が発明したテクノロジーによって人類が滅亡する」という、それまでの文学では扱うことのなかった主題がアメリカ人の目の前につきつけられたからです。映画でも「核戦争で人類滅亡」という人類の愚行が繰り返し描かれました。『博士の異常な愛情』も『渚にて』も、50年代に生産され消費された「人類滅亡物語」の膨大な蓄積の上に開花した「傑作」でした。
三砂先生は「世界終末時計」をご記憶だと思います。「世界滅亡まであと何分」を表示した時計ですが、1952年に米ソが水爆実験に成功した年に11時58分(滅亡まであと2分)を記録しました。実際に1962年のキューバ危機のときには「第三次世界大戦寸前」まで行きました。
ですから僕の少年時代はずっと「もうすぐ世界は滅びるかもしれない」という潜在的な不安のうちにありました。「終末観がデフォルト」という感じは、その時代の空気を吸っていない世代にはうまく伝えられないかも知れません。
敗戦国日本はとにかく生き延びるのに精一杯で、国際政治に関与して、地球の危機を救うような国力はありません。何かしたくても、何もできない。だから、もう「なるようになれ」と居直るしかない。その底の抜けた感じが、50-60年代の日本社会のワイルドで、アナーキーで、妙に明るい文化を生み出したと僕は思っています。
そういう時代を生きてきたので、いま「第三次世界大戦が起きるかも知れません」と言われても、あまりびっくりしない。「いつか見た風景」なので、なんとなく「あ、そうなんだ。でも、今度もなんとかなるんじゃないかな」とつい思ってしまう。人類は一度愚行を回避できたから、二度目も回避できるはずだという推論は成立しないんですけれども、それでも。
未来に対する不安を構成している大きな部分は「何が起きるかわからない」という情報の欠如だと思うんです。ですから、過去に「似たようなものを見た」という経験があると、未来への不安はいくぶんか軽減する。「過去の経験」というのは僕が個人的に見聞きしたことに限られません。人から聴いた話でも、本で読んだことでも、映画で見たことでも、「前にも同じようなことがあったよ」と教えてもらえると、なんとなくほっとして、ただ不安で思考停止して、フリーズしてしまうよりは多少知恵も働くし、手も動く。「古老」の仕事って、そうやって年下の人たちの不安を取り除いて、「そんなに怖がることないよ」と背中を押してあげることじゃないかなと最近思うようになりました。
例えば、いま学校に対して恐怖や嫌悪に近いものを感じている子どもの数が増えています。不登校25万人というような数字を見ると、不登校の子どもを持つ親も、子ども自身もずいぶん気鬱だろうなと気の毒になります。そういうときに「どうすれば他の子どもたちと同じように学校に行かせることができるか」というふうに問題を立てると、たぶんうまくゆかない。「同時代の、同学齢の、他の子どもたち」しか参照する当てがなくて、そのマジョリティと比較すると、不登校は「病的」で「異常」なふるまいに見えてしまうからです。
でも、もっと長いタイムスパンの中で「そもそも学校に通うというのは、何のために始まったことなのか」というふうに問いを立てると、「学校にゆかない」というのが病的でも異常でもなく、「それがふつう」だった時代もあるということがわかります。「学校にゆかないのがふつう」から「学校にゆくのがふつう」に社会は変化したのですけれど、その変化を衝き動かした動因は何かということを考えると、不登校ということの意味もまったく違ったものに見えてきます。
フィリップ・アリエスの『子供の誕生』やエリザベート・バダンテールの『母性という神話』を読むと、「子ども」や「母性」といったものが歴史的な条件によって構築されたものであることがわかります。それはかなり流動的なもので、ゆっくりとですけれども、ずっと変化し続けている。ですから、「子ども」が僕たちの考える子どもではなく、「母」が僕たちの知っている母とはほとんど別物であるような社会が過去にはいくつも存在していたことになります。でも、別にそれはそれらの社会が「未開」で、僕らの社会における「子ども」や「母」がより完全に近いものだということではなく、いつの時代のいつの社会も、それなりの合理性に基づいて「子ども」や「母」はその役割を演じていたのだと思います。
アリエスによると、現代の「子ども」概念に近いものがヨーロッパに生まれたのは15世紀以降のことだそうです。それまでは七歳までは親の手元に置くけれども、それ以後は7年から9年に他の家に徒弟奉公に出します。委託された子どもの主な仕事は「主人に仕えること」です。そこで修業して、実務経験を身につけて一人前になる。子どもを教育するのは、委託契約を結んだ他家の主人ですから、実の親子の親密な感情的つながりというものは期し難い。アリエスの文章を一つ引いておきます。
「こうした状況のもとで、子供はごく早期に自分の生まれた家族のもとをはなれていたのであり、後に大人になってそこに戻ることがあったにしても、それも常にそうだとは限らなかったのである。したがって、この時代に家族は、親子の間で深い実存的な感情を培うことはできなかったであろう。」(P.アリエス、『〈子供〉の誕生』、杉山光信他訳、みすず書房、1980年、346頁)
中世のヨーロッパの話ですけれども、「そんな遠いところの話なら、現代日本と関係ないじゃん」というわけにはゆきません。というのは、まさにこの「親子の間に深い実存的な関係が欠けている」社会で「学校」が登場してきて、親子関係を一変させるからです。
アリエスによれば、15世紀から家族のあり方と、家族意識が変容してゆきますが、その際立った兆候が「子どもを学校に通わせる」という習慣が定着してきたことです。それまでは他家に見習い奉公に出すことが教育でした。それが学校という独立した教育機関ができて、そこに通わせることになった。
ここで重要なことは、必ずしも学校は親たちの要請でできたわけではないということです。ヨーロッパで学校教育を先導したのはイエズス会士たちですけれども、彼らが子どもを学校に通わせるべきだというキャンペーンを展開したのは「若者を生まれたばかりの無垢のなかにとどめておくために、大人たちの穢れた世界から隔離しようという配慮」からです。何よりも親たちの非道な権力行使から子どもを守るためでした。
バダンテールの『母性という神話』は前近代ヨーロッパの子どもたちの無権利状態について、こう書いています。
「アンリ二世の布告(1556年)は、親の意志にそむいて結婚するものは永久に相続権を剥奪される、と宣言した。(…)アンリ三世の新しい布告は、親が同意しない未成年者の結婚は誘拐と同類と見なし、未成年者を『誘拐』したものは、いっさい容赦なく死刑に処すと宣言した。」(E.バダンテール、『母性という神話』、鈴木晶訳、1998年、55頁)
死刑ですよ。すごいですね。18世紀の後半になっても、「家庭の名誉と平安を危険にさらす可能性のある行動」をした若い男女への処罰は厳しいものでした。そう宣告された子どもたちは西インド諸島の流刑地に送られました。
「流刑地に送られた子どもたちは、厳重に監視され、ろくな食事も与えられず、過酷な労働を強いられた。」(同書、56頁)
これらの法律は、その時代において父親の子どもに対する権力がいかに強大なものであり、子どもには服従以外の選択肢がなかったことを示しています。だとしたら、「これほどの社会的圧力があったため、その他いっさいの感情が割り込むすきがなかった」のも当然です。
親子の愛情というものを僕たちは誰のうちにでも自存する、ごく自然な感情だと思っていますけれど、そんなものが「割り込むすきがない」ような親子関係がフランス革命前にはデフォルトだったのでした。
『母性という神話』は次のような印象深い逸話から始まりますが、僕はこれを読んでずいぶん驚かされたことを思い出します。これは1780年のパリの話です。
「毎年パリに生まれる二万一千人の子どものうち、母親の手で育てられるものはたかだか千人にすぎない。他の千人は―特権階級であるが―住み込みの乳母に育てられる。その他の子どもはすべて、母親の乳房を離れ、多かれ少なかれ遠く離れた、雇われ乳母のもとに里子に出されるのである。
多くの子は自分の母親の眼差しに一度も浴することなく死ぬことであろう。何年か後に家族のもとに帰った子どもは、見たこともない女に出会うだろう。それが彼らを生んだ女なのだ。」(同書、25頁)
アリエスについても、バダンテールについても、その所論についてはさまざま異論はあると思います。でも、前近代の家族は僕たちが思い込んでいるようなタイプの家族愛に基づいたものではなくて、もっと手触りのざらついたものだったということ、子どもたちがそういう冷たい家庭で精神的・肉体的に傷つけられるリスクを回避するために、彼らを大人から守るために「学校」という制度が作られたということは、たぶん事実だろうと思います。
近代において学校が作られたことの目的が「大人たちから子ども守る」ことだと聞いたら、いまの日本人はびっくりすると思います。でも、この本義は揺るがすべきではないと僕は思います。ここでいう「大人たち」には「世間」も「親」も含まれます。子どもを労働力として利用しようとする大人たち、子どもを自分に服従させようとする大人たち、その両方から子どもは守られるべきだという考え方を僕は適切だと思います。
アリエスの言うように「子ども」という観念は歴史的な発明品ですけれども、それは「子ども」というのは幻想だと言い切って終わりにできる話ではなくて、「子どもという観念」を発明したことで人類は少しだけ進歩し、この世界は少しだけ暮らしやすくなったというふうに解釈してよいと思います。せっかく「子どもという観念」が「誕生」したわけですから、それをできるだけ有用なものとして活用したい。
というところで話は戻りますけれども、不登校というのは、だから、ほんとうはあり得ないことなんだと思います。学校が子どもを守る場所であったら、子どもたちは、保護と支援を求めて、止められても、学校に行くはずですから。
でも、そうなっていない。それは家庭と学校を比べると、学校の方が、子どもにとってはより服従を強いられ、より自尊感情を傷つけられ、心身により深い傷を与えられる場になっているということです。学校の誕生の歴史的意味から考えれば、そうなります。家庭だって、それほど居心地がよいわけではないけれども、それでも家庭内では執拗ないじめとか、教師への服従の強制が求められることはありません。三砂先生が書かれているように、仮にそこが「愛のない家庭」であっても、子どもたちにとって生理的に快適な環境を整えるという気づかいはなされている。もちろん、それさえない「ネグレクト」された子どももいますけれど、それがデフォルトではなくなっている。それは「不適切」であるということについての社会的合意は存在する。
子どもたちの虐待ということが話題になると、僕がまっさきに思い出すのは、意外と思われるでしょうけれども、マルクスの『資本論』です。『資本論』というと、ほとんどの方は最初の方の「商品と貨幣」のところを読んでいるうちに、話があまりに抽象的なので、うんざりして止めてしまったと思います(僕もそうでした)。でも、がんばって読み進めると第六章「労働日」のあたりから、いきなり話が生々しくなるのですが、それは児童労働のところです。マルクスはこの辺からあとは当時のジャーナリストや学者が書いたプロレタリアの非道な収奪の実情を引用して頁を埋めてゆきますが、それがほんとうにすごいんです。
「夜中の二時、三時、四時に、九歳から十歳の子供たちが汚いベッドからたたき起こされ、ただ露命をつなぐためだけに夜の十時、十一時、十二時までむりやり働かされる。彼らの手足はやせ細り、体躯は縮み、顔の表情は鈍磨し、その人格はまったく石のような無感覚のなかで硬直し、見るも無残な様相を呈している。」(カール・マルクス、『資本論第一巻上』、今村仁司他訳、筑摩書房、2005年、357頁)
これはマルクスの書いた文章ではなく、1860年1月のロンドン『デイリー・テレグラフ』の記事です。もっとすごかったのはマッチ製造業についての記事です。マッチ製造は材料であるリンに暴露されることで「リン中毒性顎骨壊死」が起きることがマルクスの時代にはすでに知られていました。この病気は歯痛と歯肉の腫れから始まり、やがて膿が出て、歯が抜け落ち、最後には顎骨が壊死するという書き写すだけで悲惨な病気です。マルクスはこう書いています。
「マッチ製造業は、その不衛生さと不快さのためにきわめて評判が悪く、飢餓に瀕した寡婦等、労働者階級でもっとも零落した層しかわが子を送り込まないようなところだった。送られてくるのは『ぼろをまとい飢え死にしかけた、まったく放擲され教育を受けていない子供たち』である。ホワイト委員が聞き取りを行った証人のうち二七〇人が十八歳未満、四〇人が一〇歳未満、そのうち一〇人はわずか八歳、五人はわずか六歳だった。労働日は十二時間から十四、五時間にわたり、夜勤、不規則な食事、しかもほとんどがリン毒に汚染された作業場内での食事である。」(同書、361頁)
マルクスが資本主義の廃絶を強く望んだのは、このような非人道的な児童労働から利益を上げている資本家たちへのはげしい憤りからでした。これが160年前の文明国での出来事でした。いまも、非道な児童労働が行われているところはありますけれども、総じて子どもたちの権利や健康はこの時代に比べるとずいぶん保護されるようになってきていると言ってよいと思います。なにしろ、マルクスの時代のマンチェスターの労働者の平均寿命は17歳、リバプールでは15歳だったのですから。
アリエス、バダンテール、マルクスと、ふだん日本の教育論ではまず名前が出てこない人たちを引用したのは、学校と子どもについて考える時に、できるだけ長いタイムスパンの中で今起きている問題をとらえる方が、僕たちが「どこに向かっているのか」がわかるだろうと思ったからです。
マルクスが報告している19世紀英国の児童労働者たちは学校についに行くことなく生涯を終えました。ですから、たとえ一年に数週間でもいいから、子どもたちに「学校に通って欲しい」というのは、心ある大人たちの悲願だったと思います。
これも昔の話になりますが、すでに公教育が導入されていた19世紀末のアメリカでも子どもたちは農業労働の重要な働き手でしたから、親は子どもを学校に通わせることを嫌いましたので、開講されていたのは感謝祭が終わってから春までの農閑期の12週間だけでした。
でも、それでも「来ないよりはまし」だったと思います。ですから、その時代の教師たちが子どもに向かって告げたかった言葉は何よりもまず「お願いだから学校に来て」だったと思います。「ここは君たちのための場所だ。ここでは誰も君たちを苦しめたり、君たちを怒鳴りつけたり、君たちを殴ったりはしない。ここには親もいないし、雇い主もいない。ここでは君たちは守られている。」そう言ったと思います。教師は子どもたちに向かって「君がここに来ることを私たちは願っている」と懇願したと思います。
僕はそれが学校の原型だと思います。子どもたちを歓待し、保護し、承認すること。それが近代における学校の本務だったはずです。
年に12週の就学期間で子どもたちにどれほどの学力がついたのか、僕にはわかりませんが、教師たちは「この世には君たちを歓待する学校という制度が存在する」ということを子どもたちに知らしめるということが何よりもたいせつだと思っていた。読み書きができる、四則計算ができる、歴史や地理を学ぶこともたいせつだけれど、それ以上に「学ぶことを支援する制度がこの世には存在する」という情報それ自体を子どもに伝えることがたいせつだった。
もちろん、その時代にも「不登校」の子どもたちはいたでしょうけれども、たぶんその多くは親が「学校に行く暇があれば、仕事をしろ」と言って通学を妨害されたのだと思います。あるいは、「学ぶことを支援する制度が存在する」ということが最後まで理解できなかったのかも知れません。
でも、いまの不登校は違います。学校に行くことを拒否している子どもたちの多くは「学校が私を歓待していない。学校に私のための場所がない。学校が私の学びを支援してくれない」と感じている。学校はもう子どもたちを歓待することを主務とする場所ではなくなっている。子どもたちはそこで「値踏み」されたり、「格付け」されたり、「役割演技」を強いられたりして、ある条件を満たさない限りお前を受け入れないという査定的なまなざしにさらされている。
どこで掛け違ってしまったんでしょう。学校はその原点に戻って、いったい何のためにこんな制度を人類は創り出したのか、それを深く思量すべきだと思います。
またまたえらく長くなってしまいました。すみません。今日はここまでにしておきます。
ではまた来年。よいお年をお迎えください。
内田樹拝
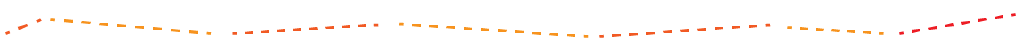
 内田樹(うちだ・たつる)
内田樹(うちだ・たつる)
1950年東京生まれ。凱風館館長。神戸女学院大学文学部教授。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。著書に『「おじさん」的思考』『こんな日本でよかったね』『コモンの再生』『日本習合論』など多数。『私家版・ユダヤ文化論』で第六回小林秀雄賞を、『日本辺境論』で2009年新書大賞を受賞。
三砂ちづる(みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。京都薬科大学卒業。ロンドン大学Ph.D.(疫学)。津田塾大学多文化・国際協力学科教授。著書に『女たちが、なにか、おかしい おせっかい宣言』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『オニババ化する女たち』『死にゆく人のかたわらで』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『少女のための性の話』など多数。

