内田樹先生と三砂ちづる先生の往復書簡による、旧くてあたらしい子育て論。ともに離婚により、男手で女の子を育てあげた内田先生と、女手で男の子を育てあげた三砂先生。その経験知をふまえた、一見保守的に見えるけれども、実はいまの時代にあわせてアップデートされた、これから男の子・女の子の育て方。あたらしい世代を育てる親たちへのあたたかなエール。
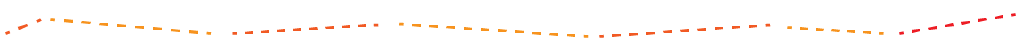
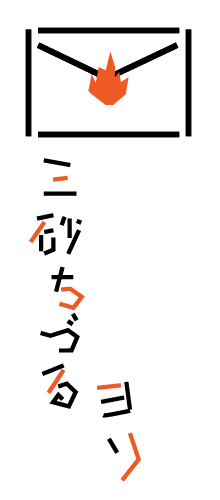
第1便・A
子育てって困難でしょうか?
内田先生、こんにちは。
ご無沙汰しております。三砂ちづるです。いかがお過ごしでしょうか。桜満開の東京よりお便りいたします。
新型コロナパンデミックで始まって、そして、終わってしまった2020年でした。専門は「えきがく」です、と、言っても、2019年までは、医療関係者ではない方で、口頭できいて一度で「疫学」、と、理解してくださる方は、ほとんどおりませんでした。ふだん、きものなど着ているものですから、「えきがく」とは、「易学」か、と思われたことも一度や二度ではありませんでした。もともと大変マイナーな医学の基礎分野のひとつである公衆衛生の、さらに地味な疫学、という分野でありまして、その名の通り、19世紀イギリスは、ロンドンのコレラのパンデミックあたりに学問的オリジンをもちつつ、その方法論を感染症から他の健康事象に広げていった、まあ、地味な、そして、地味でけっこう、な、分野だったのです。
それがなんということでしょう、今や「疫学」を聞いたことがない人は、だれもおりません。日々のニュースで疫学、という言葉を耳にし、保健所の「積極的疫学調査」のことを映像で見て、実効再生産数にアールノートに感度に特異度に感染致死割合……とか、学会でしか聞いたことなかったような言葉を一般の方々が普通に、まさに日常的に目にするようになってしまいました。「疫学」は、感染症から始まった学問ですが、いまはさまざまなことにその方法論がつかわれていて、生活習慣病から精神疾患まで、さまざまな分野の疫学者がおります。わたしは母性保健、つまりは女性のからだのことについて「疫学」を方法論として研究していました。感染症は疫学のオリジンとはいえ、疫学屋で感染症をやっておられる方は、現代ではマジョリティーではなく、こちら、わりとひっそりと研究なさっていたのに、昨年から、世界中で表に出て来て大活躍、本当に忙しくなられました。数理疫学モデル、などという、疫学を専門にしていてもその分野を専攻していなければ、さっぱりわからず、とてもついていけない、というようなことについてまで、世界中が常に話題にするようになりました。イギリスでは、疫学者のスキャンダルがタブロイド紙を騒がせたりして、こんなに疫学が有名になる時代はちっとも良い時代ではありません。
2020年当初から、これは、長丁場になりそうだ、と、言われていました。ワクチンができてからも、パンデミック以前に戻るのは、かなりかかるだろうと言われていましたし、その後さまざまな新しいニュースが届くにつけ、このCOVID-19はかなりめんどうくさいものであることが判明していくばかりで、パンデミックは、必ずいつかは終わるのではありますが、長丁場を覚悟、の状況は、そう簡単にかわりそうにありません。昨年度からの、匍匐前進のような日々は今しばし続き、お金と暇さえあれば、日本中のみならず、世界中どこでもいける、というような日々があったんだったよなあ、と、みんなで遠い目をすることはまだ続き、この状況を心身ともに少しでもましな状態で生き延びるすべを考える時間は、いましばし、続くのだと思います。
そんな中、内田先生と往復書簡、の企画をいただきました。お題は大きく言えば、男の子の育ち方について、そしてまずは、「ジェンダー・フリーが言われる時代で子どもを育てることの困難について」です。今の時代、「子どもを育てることの困難」ってどこでも言われることなんですけど、この言い方自体に、なんというんでしょうか、心が、痛むというか・・・なんとも言えない気がするんですよね。子どもの立場に立ってみたら、それって、ほんとうに、やるせないよなあ、と思ってしまう。子どもの立場に立つ、って、わたしたちみんな子どもでしたけれども、そういうことはよく覚えていない人も多い。だいたい、実際に子どもの立場に立つなんてそんな簡単じゃないだろう、誰にもわからないだろう、って言われてきたんですよね。「子どもの立場に立つ」というような誰にも証明できない非科学的なことを話題にするから、女性の共同参画が進まない、と国会で言われたこともあったらしく、そういう誰に聞いてもわからない子どもの立場、とかを、公的な議論に持ち出すことはよろしくない、と思われてきたようです。
でも本当にそれでよかったかなあ、と思います。「子育ての困難」って要するに、子どもの立場からすれば、自分が人の手を借りなければまだ生きられないときに、自分の存在が自分にとってすごく近しい人、多くの場合は母親とか父親とかだと思うんですが、そういう人に「困難」と思われる、ということですよね。自分の存在が、誰かにとっての「困難」つまりは、バッド・ニュースである、ということって、その人を深く損なう可能性のあるものじゃないだろうか、と思ってしまいます。ましてや自分が一番たのみとする人にとって、自分自身が困難な存在である、ということは、本人にとってけっこう厳しいことなのではないのでしょうか。
たとえば、いいとかわるいとか言っても、「不倫」ってなくなりません。もう還暦すぎまして、友人たちもそれ相応の年齢の人が多いわけですけれども、これくらいの年齢になってくると、長い間「不倫」を続けてきた人たちってなんだか、もう、ぬきさしならなくなっています。女性の側からも男性の側からも、この手の話を聞くことが少なくなかったのですけれども、圧倒的に、話を聞いてきたのは「男性が既婚」、「女性が独身」のパターンでした。まあ、いまどきダブル不倫だってめずらしくないようだし、女性が既婚、男性が独身、のパターンだってないわけじゃないですけれども、そちらのパターンは、やっぱり無理が大きいのかなあ、そんなに長く続くケースは見受けられないような気がします。データから話してるわけじゃないから、わからなくて、ただ、わたしの耳に入ってこないだけかもしれませんけど。で、女性独身、男性既婚の不倫カップルの場合、ほとんどは男性側は、奥さんとうまくいってない、一緒に住んでない、いつかは離婚する、と言っていて、女性側は、やっぱりいつかは結婚しよう、と思っている。そうこういっている間に生殖年齢も過ぎて、お互い初老の域に入ってきて、人生の終わりもなんとなくみえてくる、そうなると、もう、お互いにとっての大切な人を失うこと自体が怖いから、別れることなんて、絶対無理になってくる。言い方は悪いですけれども、なんとなく、別れきれず、だらだらつきあいつづけて、どちらかが死ぬまで続く、ということになる。
相手の家族にばれなければいい、他の人に実際の迷惑をかけてないからしょうがない、という解決の仕方にならざるを得ないわけだけれど、そういう女性たちを見ていると、やっぱり彼女たちのしんどさ、というんでしょうかね、それはどうしようもないところがあることがわかる。そのしんどさの根っこにあるのは、「自分がだれかにとってのバッド・ニュースである」ということの、形ははっきりしないけれども消し去ることのできないぼんやりした自覚のようなものである気がします。もはや奥さんが憎いとか憎くないとか、不倫相手に愛されているとか、いないとか、不甲斐ない相手に愛想が尽きるとか尽きないとか、そういうレベルじゃなくて、もう、お互いの存在を肯定するしかないんだけど、でもなあ、やっぱり自分の存在って、この人の奥さんや子どもにとってはバッド・ニュースだよなあ……。そういうことって、その人をやっぱりなんともいえない、きつい状況に、おく。人間の存在ってそこにあるだけで寿がれるもののはずなんだけど、表にできない「不倫」という関係性は、自分の存在を喜ばない人がいる、という状況を、不可避的に作り出してしまうのですよね。それに耐えることは、なかなかにきびしい影響を、日々、その人の上に積むことになるような気がします。
先日、北九州にある「抱樸(ほうぼく)」という団体の方のお話を聞く機会がありました。路上死を出さないように、路上から一人でも多く、一日でも早く脱することができるように、「ホームレス」、「ハウスレス」の人がいなくなるように、三〇年以上実践を続けてきた団体だそうです。「抱樸」とは、「素(そ)を見(あら)わし樸(ぼく)を抱(いだ)き」という老子の言葉だそうで、「樸」とは、荒木(あらき)、原木のこと。みんなそのままで生まれてきて抱かれて育ってきたのだから、人生の終わりにも、同じように抱かれる場所に戻れるように、と、誰をも「断らない」支援を模索してこられたのです。専門性を要する「制度」はもちろんぜったいに必要だけれど、同時に「制度」、は対象者を決めてしまって、そこから外れる人ができてきてしまう。家族のように、あるがままで、ただ、だれでも受け止める、と「制度と家族の間」をうめるべく、活動されてきた、といいます。「ホームレス」はおらず、「名前を持つ個人」がいるだけ、と語る代表者のお話は印象的でした。自立することは生きることとくらべたら、とても小さなことなのだ、と。
あるがままの状態で抱かれること、つまりは、存在そのものが寿がれることが、誰にも必要なのだ、と思います。誰も、誰かのバッド・ニュースにならなくてもいい、ということ・・・。
その話を聞きながら、あらためて、「生まれたときにあるがままで抱かれる」、のことを考えたのでした。「子育ての困難」って、「生まれた時とか小さい時にも、あるがままでは抱くのが難しい」って、言葉をかえて言っている、とはいえませんか。そんなことないよ、そういう話じゃないよ、だれにとっても子どもを育てるのって大変なんだから、とまた言われそうな気がしますが、大変だ、大変だ、っていわれるだけで、幼い人たちの存在は、バッド・ニュースになりませんか。赤ちゃんや子どもにはそんなことわかりませんよ、とも言われそうですが、いまどき、子どもや赤ちゃんの発達や行動を研究しておられる方から小さな赤ちゃんも本当に色々なことがよくわかっている、ということが示されています。だいたい、そんな研究結果をもちだすまでもなく、わたしたちおとなの態度は、こどもには、きっとよくみえているんじゃないでしょうか。自分の一番そばにいてくれるおとなが自分の存在を「困難」と思っている、うとましく感じている、そういう言葉にならない雰囲気は、感知されないはずはない、と思うのです。それってなにか、大きなことじゃなくて、とても小さなことのつみかさねで、たとえば、自分に向けられる一瞬の眼差し、とか、自分をのぞきこむ表情とか、自分にふれる手の感じ、とかそんなことだと思うのですがね。
でも、実際にそういう話をすると、「そんなに自分の子どもたちを傷つけたり損ねてしまったりする可能性があるなんて、怖くて子どもをもつことはできない」と、生殖年齢にある方々には、いっそう、言われてしまうのかもしれない。それでなくても「妊娠、出産、子育て」の語り口が総じて「困難」ということばで飾られているところに、さらに、それを「困難」と思うことで自分の子どもが傷ついたりしてしまうかもしれないなんて、いっそうおそろしくて、子どもはもてない、と思ってしまうのかもしれない。このように書くと、COVID-19と同じように、この国の少子化についてもなんら、明るいきっぱりした展望が描けない、ということになってしまいます。
「男の子はどのように育つのが良いのか」というような具体的な話に入る前に、この「子育ての困難」という言い方をごく普通のものにしてしまうことについてあれこれ考えてしまいました。内田先生はご存知のように私は男の子二人を育てました。自分がやすやすと子どもを育てた、といいたいわけはありません。やすやすと育てた、とも、勝手に育った、とも思っているわけではないし、2人の男の子を育てて、ふたりとも30前後、という年まで育って、これでオッケーだった!とか、思っているわけでもありません。思っているわけでもないけれど、還暦をすぎて、ふりかえってみると、というか、べつにふりかえってみなくても、子育ての真っ最中だったときも、「子どもを育てることが困難」、は、思ったことがありませんでした。過ぎたことだから、いいように解釈しているんだろう、というところもあるかもしれないし、内田先生とるんちゃんの往復書簡に出てくるように、親と子では全く同じことを違ったように解釈していることがある、ということも、よくあるんだ、ということを前提としても、それでも「子どもを育てることが困難」とは思わなかった。子どもを育てることは、楽しみであり、喜びであり、生まれてきた理由を完結させてくれるものであり、というか、子どもがそこにいるのだから、私の人生は彼らと共に生きる人生しかなくて、それが困難とか考えることすらなかった、という言い方しかできない……。あまりむずかしいことを考えていなかっただけかもしれませんが。すくなくとも、バッド・ニュースと考えたことは一度もなかった。そのことについて、子どもたちがどう思っているかについては、幸いというか、あいにくというか、知らないままなので、きいてみたら、それこそ親と子では違う解釈になるのかもしれませんから、なんとなく、聞かずにだまっておきたい、というような気がしています。
今日はここまでで筆を置くことにします。時節柄、どうかご自愛専一に、ご精励くださいませ。
三砂ちづる 拝
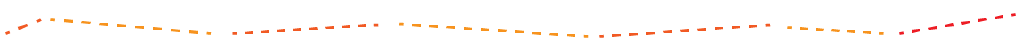
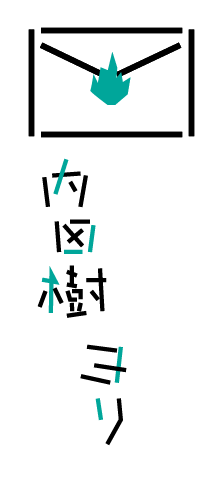
第1便・B
子どもは手離すときがむずかしい
三砂先生
こんにちは。内田樹です。
お久しぶりです。往復書簡、安藤さんから企画を頂いて即答で「やります!」とご返事しました。
往復書簡という形式が僕はわりと好きなんです。
以前、鈴木晶さんとも、平川克美くんとも往復書簡を本にしました。いまも経済学者の石川康宏さんと『若者よマルクスを読もう』というシリーズを出しています。マルクスの本を一冊選んで、それについて二人でああでもないこうでもないと熱く語り合うという趣向のもので、『共産党宣言』から始まって、ゆるゆると10年近くかけてようやく『資本論』にまでたどりつきました。石川さんから書簡をもらって、うっかりすると返事を書くまでに半年くらいかかるということがよくありました。でも、それくらい時間をかけてゆくといい感じに話が「熟成」するということはあるんです。
対談だと、そのときにとっさに思いついた話が意外に面白かったということがありますが、往復書簡だと「とっさに」がありませんが、その代わりに「じっくり」ができます。調べものも時間をかけてできますから、正確を期すことができる(対談だと、もうだいたい老人同士なので、「ほら、あれ、何て言ったっけ。ほら、あれだよ」と二人で言い合うばかりで、さっぱり話が前に進まないということがよくあります)。
今回は「子育て」についてのお話ですから、あまり文献やデータの引用とかはなくて済むと思いますけれども、デリケートな話柄ですから、適切な言葉づかいができるかどうか自信がありません。ですから、じっくり考えて、言葉を選ぶ時間が与えられるのはありがたいことだと思います。どうぞよろしくお願い致します。
新型コロナウィルスの感染が始まって1年以上が過ぎました。最初のうちはぼんやりと「年内には終息するだろう」くらいに思っていたのですが、第二波、第三波、そして第四波と同じようなパターンで感染者の増減を繰り返しているのを見て、日本での感染の終息は当分期待できないだろうという気がしてきました。今年も、会食を伴ったり、泊りがけで起居を共にするタイプのイベントはおおかた「ないもの」とみなして、スケジュールから消しました。もう当分は(あるいは永遠に)「コロナ以前の生活」に戻ることはないんじゃないか。なんとなくそんな気がしています。
でも、そういう心構えをしている人はどうも政策決定レベルにはあまりいないみたいですね。GoToトラベルとか、緊急事態宣言解除の前倒しとかを見ていると、「正常への復帰」を願うせいで、そのせいでむしろ「非常時」がずるずると延長されているように見えます。
非常時であるということをきちんと受け入れれば、正常への復帰もそれだけ早まる。そのことは感染抑制にこれまで成功した国の事例を見ればわかると思います。でも、日本政府はそれを学習する気がないらしい。国民も「成功事例を学習する気がない日本政府」をとくにきびしく批判する気がないらしい。
たぶん日本人は「平時」と「非常時」の切り替えがひどく苦手なんだと思います。どこの国民も多かれ少なかれ、そういうものかも知れませんが、日本人はとりわけ苦手なんじゃないかな。
平時から非常時へのモードの切り替えが恐ろしく下手というだけではなく、常日頃から「最悪の事態」を想定して、それに対する備えをしておくということができないようです。「リスクヘッジ」とか「フェイルセーフ」とか「バックアップ」という思想がそもそも固有の文化の中にないんじゃないでしょうか? だって、いま挙げたこの三つの単語って、どれも適切な日本語訳が存在しないでしょう? 「やまとことば」にこれに対応するものがないのは仕方がないとして、ついに適切な訳語が作られなかった。
訳語が作られなかったのはただの知的怠惰だと思う人がいるかも知れませんけれど、僕は違うと思う。たしかにある時期から横文字を漢字二語にするということが面倒になって日本人はしなくなりました。でも、「国風化」ということはありました。それは英語を「四文字」にするという言い換えの習慣です。「アンダーグラウンド」を「アングラ」と言い換え、「パーソナル・コンピューター」を「パソコン」と言い換え、「コミュニティ・センター」を「コミセン」と言い換え、「プログレッシブ・ロック」を「プログレ」と言い換え・・・枚挙にいとまがありませんけれど、「これはもとは外来のものだが、日本社会に定着した」という査定が下ったものについては「四文字」を与えた。そういうことじゃないかという気がします。でも、「リスヘジ」や「フェルセー」や「バクアプ」という語を僕は聴いたことがありません。誰かが言ってみても、たぶん通じないと思います。
ということは、これらの外来の概念については、日本人たちが習合的無意識のレベルにおいて「定着させない」という決断を下したからではないか。僕は何となくそんな気がします。そういうのはいいんだよ、うちの「家風」になじまないから、って。
なんか変な話から始めてすみません。
僕が言いたかったのは、日本人はとかく「正常」にこだわりすぎて、「非常時」への切り替えが集団的に苦手なんじゃないかという気がするということです。
ずいぶん前からそう思ってきました。
日本人の国民感情はたいへん惰性が強い。「今日の話は昨日の続き。今日の続きはまた明日」ということが不可疑の前提となっていて、状況が一変して、昨日までの判断基準がもう使いものにならないという現実を受け入れることができない。
その惰性の強さが日本社会で起きているすべての現象に伏流している通奏低音のようなものである気がします。
だから、コロナで可視化された「困ったこと」は、他の領域で起きている「困ったこと」にも構造的には同一なんじゃないかという気がするんです。
子育てについても。
子育てでいちばん難しいのは「子どもを手離すとき」だと僕は思うんです。親がそばにいて、子どもに対して「こういうふうに育って欲しい」ということを心の中で思っていると(口に出さなくても)、それが「縛り」になっていて、子どもの成長の道筋がどこかで塞き止められたり、ねじ曲げられてしまう。
子どもの中に潜在している才能の中で、親が肯定的に認められないもの、あるいは親がその存在さえ知らないものは、親が近くにいて、愛情深いまなざしを送っていればいるほど、むしろ発現することが困難になる。そういうことって、あるんじゃないかと思います。
子どもを守ることは親の最優先の課題ですけれど、ある段階まで子どもが育ったら、もう「守る」ことを諦めて、「好きにしなさい」と言って送り出さなければいけない。
これはたいへん困難なモードの切り替えだと思います。
この「平時から非常時への切り替え」の段差で、たいていの親は足がもつれる。
だって、「子どもを守る」というそれまでの人生で最優先であり、それを果たしさえすれば周囲から「よくやっている」とほめられて、親本人も「私は親としてやるべきことはやっている」と自己評価できた仕事が「それ、もういいです。子どもさん、迷惑がってますから」と言われるわけです。それもいきなり。
愕然としますよね。愕然として当然だと思うんです。
子どもからある日「あのさ、親の愛情とか、気づかいとか、もう要らないんだよ。迷惑なんだよね、正直」と告げられたときに「おお、ついにわが子もこのような成熟段階に達したか。善哉(よきかな)善哉」とにっこり笑える「できた親」なんてまずこの世にいないと思います。
でも、親にはこの「離別の宣言」をなんとかにこやかに受け止め、できることならそれを言祝ぐことができるようにならなければならない。つらい仕事ですけれど、しかたがない。「子育て」仕事の次は「脱・子育て」という仕事が待っている。どちらも親のたいせつな仕事だと僕は思います。
でも、いまの世の中では、「子育て」までは「親のたいせつな仕事」だというふうにひろく認識されてはいますけれど、「脱・子育て」もまた「親のたいせつな仕事」であり、親の側にさらなる人間的成熟を要求するという考え方はあまりされていないように思います。
子どもを愛し、気づかうということはわりと本能的にできます。
これは子育てをした親としての僕の実感です(あわてて言い添えますけれど、あくまで「わりと本能的に」です。だから、それが「できない」という人も当然います。それは消化器の蠕動とか、ホルモンの分泌とかと同じレベルのことですから、自己努力でどうこうできるものじゃない。でも、この話はまた別の機会にすることにしましょう)。
とりあえず、子どもを愛し、気づかうことはわりと本能的にできる。僕はそう感じます。でも、子どもから「もう愛したり、気づかったり、そんなに前みたいにしなくていいです」と言われて、それを受け入れるためには本能だけでは足りない。そこには感情の成熟が必要になる。
日本語では「感情教育(éducation sentimetale)」という言葉は日常語としては存在しませんけれど、僕は「感情教育」というのはたしかにあって、それは死ぬまで終わらないものだという気がします。
ただ、それは子どもの感情から若者の感情を経て、大人の感情になって、やがて老人の感情になるという単線的な変化のプロセスのことじゃなくて、子どもの感情の上に若者の感情が堆積して、その上にまた大人の感情が積み重なって、その上にまた…というふうに漬物みたいに、感情が重層的になってゆくことなんじゃないかと思います。
だから、感情教育のプロセスをきちんと踏んできた人においては、子どものイノセンスも、若者の冒険心も、大人の狡知も、老人の諦念も、すべてが心の中に並列的に存在していて、それらがまじりあって、独特の風味を醸し出す。そういうことだと思います。そして、日本の親たちが「脱・子育て」をあまり得意としないのは、感情教育に終わりはないということが常識として登録されていないからではないか、そんな気がします。
でも、最初からあまり先走ることはないですね。「子離れ」の話はまたいずれするとして、第一便ですから、もっとのんびり世間話に寄り道することにします。
三砂先生の話「不倫」のことから始まりましたけれど、これは実は僕は苦手な話題なんです。
『カジノ・ロワイヤル』でジェームズ・ボンド(ダニエル・クレイグ)がお目付け役のヴェスパー・リンド(エヴァ・グリーン)に向かって、「君はオレのタイプじゃない」と言い放つシーンがあります。ヴェスパーが皮肉っぽく笑って「頭がいいから?(Smart?)」と訊くと、ボンドが「独身だから(Single)」と冷たく答える。
そうなんです。ボンド君は「不倫専門」なんです。理由はボンド君的には明快で、「追いかけてこない」からですね。あくなき性的自由の探求者であるボンド君としては、「結婚して」と訴えてくるリスクがない女性がいちばんいい。
僕はぜんぜんジェームズ・ボンド的な人間ではないのですが、それでもあれこれとつらい経験した末に「不倫はいかん」という結論に至りました。「ウチダ君はどうしてそういう結論に至ったのであるか、その由来について具体的に述べよ」と言われると困ってしまうのです。まあ、いろいろあったけれど、不倫はいかんですということです。それでご容赦願いたいと思います。
それはやはり三砂先生がおっしゃるように、僕の存在そのものが誰かにとっての「バッドニュース」であるような生き方はどこかで心身に傷を残すということだからだと思います。
何より僕は嫉妬という感情がたいへん怖いのです。自分が嫉妬心を抱くときの身体が壊れそうになる痛みを考えると、僕を嫉妬の対象にした人が経験している痛みに対しても「申し訳ない」という気持ちになる。「申し訳ないじゃ済まされんぞ」と言われたら、ほんとうにそれまでなんですけれど。
嫉妬という感情は嫉妬する人も、される人も、関わる人全員を傷つけるとても危険で不毛な感情です。僕はできたらそういう剣呑なものとはもう二度とかかわりあいになりたくありません。ですから、できたら、誰にとっても「バッドニュース」でないような生き方をしたいと願っているのです。でも、わが身を顧みるとそれは難しそうです。
僕がどこかに場所を占めて、ある仕事をしていると、それだけでも「それがバッドニュースだ」と思う人がいる。これは避けがたいのです。僕がしている仕事をなぜか「私がすべき仕事」だと思って、それを僕が不当に横取りしたと思う人がいる。「ウチダがそこにいるせいで、オレの場所の日当たりが悪くなっている」と思う人がいる。それはどうにも避けられないのです。
たしかに、僕がどこにも出かけず、何もしなければ、人の虎の尾を踏むこともないんですけれど、そうもしていられない。そして、どこかで何かひとこと言うたびに、ある種の人々に向かって「バッドニュース」を告知することになる。
70年生きてきて、人を傷つけずに生きるということはたぶん誰にもできないのだろうなと思いました。
「七十にして心の欲するところに従って矩(のり)を踰(こ)えず」と孔子は言ってますけれども、そう言った夫子ご本人が晩年になっても13年間亡命生活を余儀なくされて、あちこちで難に遭っているわけですから、ご本人は「矩を踰えず」のつもりでも、周りから憎まれたり、嫌われたりすることは避けられなかったわけです。
孔子にできなかったことが僕たちにできるはずがない。僕たちにできることは、せめてそれについての「病識」を持つことだと思います。
僕が存在していて、何かしているせいで、それだけでもう傷つく人がいる。プライドを損なわれたり、自己肯定感を減じたりする人がいる。そのことは避けられない。僕に積極的な害意がなくても、その人のことを知らなくても、結果的に僕のふるまいで傷つく人はいる。
それについて口を尖らせて「そんなの知るかよ。オレの責任じゃないよ」と言い放つことはできない。そういう傷についてもやはり心の中で手を合わせて「ごめんね」と謝る。誰だか知らない相手ですけれども、心の中で謝る。謝ったからと言って、それで何か「いいこと」が起きるわけではないんですけれども、それでも。
さあ、書いているとどんどん長くなってしまいそうですので、今日はこれくらいにしておきます。のんびりと寄り道をしながら、三砂先生と子育てについてお話するのを楽しみにしています。
内田樹 拝
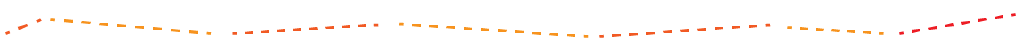
 内田樹(うちだ・たつる)
内田樹(うちだ・たつる)
1950年東京生まれ。凱風館館長。神戸女学院大学文学部教授。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。著書に『「おじさん」的思考』『こんな日本でよかったね』『コモンの再生』『日本習合論』など多数。『私家版・ユダヤ文化論』で第六回小林秀雄賞を、『日本辺境論』で2009年新書大賞を受賞。
三砂ちづる(みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。京都薬科大学卒業。ロンドン大学Ph.D.(疫学)。津田塾大学多文化・国際協力学科教授。著書に『女たちが、なにか、おかしい おせっかい宣言』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『オニババ化する女たち』『死にゆく人のかたわらで』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『少女のための性の話』など多数。

