内田樹先生と三砂ちづる先生の往復書簡による、旧くてあたらしい子育て論。ともに離婚により、男手で女の子を育てあげた内田先生と、女手で男の子を育てあげた三砂先生。その経験知をふまえた、一見保守的に見えるけれども、実はいまの時代にあわせてアップデートされた、これから男の子・女の子の育て方。あたらしい世代を育てる親たちへのあたたかなエール。
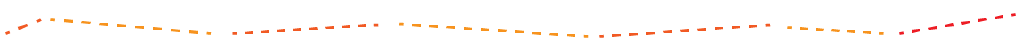
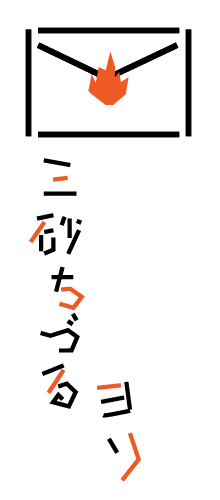
第10便・A
自分を手放せること/自立していくこと
内田先生
こんにちは。お便りありがとうございます。お返事遅れてしまいました。申し訳ありません。
2020年春以降、COVID-19パンデミックで、海外に出かけられていませんでしたが、3月にエルサルバドルという中米の小さな国と、初めての北米訪問になるメキシコに数日行きました。メキシコは北米なんですね。ラテンアメリカですけど、北米。つまり北米はアメリカ合衆国とカナダとメキシコ。すみません、ブラジルに10年住んでラテンアメリカはそれなりに知っているつもりだったのに、いまだに、メキシコが北米だ、と知らなかったのです。中米の国だと思っていました。中米、つまりは、セントラルアメリカと呼ばれる国は、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、エルサルバドル、コスタリカ、パナマ、ベリーズの7カ国で、メキシコは北米って、今更にして知りました。アメリカ合衆国にもカナダにも、飛行場のトランジットで降りたことがあるだけで、訪問したことはありませんからメキシコが文字通りの初北米、となりました。今となっては初めて訪問した北米がアメリカでもカナダでもなく、メキシコ、というのは、よかったな、と思います。
公衆衛生の中でも、とりわけ健康格差の大きな国でその格差の把握と受け入れられない格差の解消を模索する国際保健、という分野で仕事をしてきたので、海外に出ることは、もともと、日常の一つでありました。ほぼ二年間、どこにも出かけず、ずっと日本にいる、というのは、20代後半から、初めてのことだったような気がします。2022年のゴールデンウィークにかけて、帰国時の検疫がゆるめられましたから、観光で海外に出る人も増えたとは思いますが、3月には、まだ、成田空港はびっくりするくらいガラガラでした。メキシコシティー直行便も、申し訳ないくらい乗客が少なくて、CAさんたちに、実によくしていただきました。お手洗いを使おうとすると、扉を開けて、待っていてくださって、恐縮するばかり。
欧米諸国では、規制がどんどん緩和され、マスクをつけないことも日常になっていると言われた2022年春でしたが、エルサルバドルもメキシコも、水際対策自体はそんなに厳しくなくて、ワクチン証明書も陰性証明も出す必要がありませんでしたが、市中では、とにかく、全員マスクをしており、飲食店では、検温、消毒、が励行され、東京で生活しているのとほとんど変わるところがありませんでした。エルサルバドルで親しく働いている国立母子保健病院の二人のスタッフが父親をCOVID−19感染で亡くしていました。パンデミック当初の、この感染による感染致死リスクは大変高かったのです。
エルサルバドルは人口650万弱ですから、千葉県くらい、総面積は岩手県よりちょっと大きいくらい。国としては、とても小さい。ここで、「出産のヒューマニゼーション」という、日本の国際協力のお家芸の一つみたいな「出生と出産の場を、科学的根拠に基づいた形で、よりやさしくする」という、日本の助産師が大活躍するプロジェクトが、2018年から行なわれています。こんな小さな国なのに、1980年代から90年代にかけて、アメリカの介入が深く関わる内戦で7万人以上が亡くなっています。その時代は、エルサルバドルに限らず、ラテンアメリカにおけるアメリカ合衆国の介入は、あまりにも露骨なものでありましたから、当該国の方々のみならず、一度でもラテンアメリカに関わったことのある人は、あの当時のアメリカのありようを、忘れることはないと思います。内戦の記憶を生々しく留めるエルサルバドルで、次世代がよりやさしい環境で生まれることができるように、という出生と出産の場をよくしよう、という国際協力プロジェクトは、先に逝った世代の祈りのような気がします。思えば、この1990年代からJ I C A(Japan International Agency: 国際協力機構)は「出産のヒューマニゼーション」プロジェクトを行なってきたのですが、2000年以降、このプロジェクトは、アルメニアやカンボジアなど大虐殺の歴史を持つ国でも立ち上げられていったことは、今になると偶然とも思えません。
出産の場が穏やかなものになると、何が良いのかというと、産むお母さんが安心します。産むお母さんが安心してお産に臨むと、お産が良い感じで進むためのホルモンがよく機能することで、結果としてお産が安全になる。お産が怖い、とか、こんなところでお産をしている場合ではない、とお母さんが思うと、一言で言えば、お産が進まない。まあ、そうですよね。その昔、祖先の人間たちがジャングルだかサバンナとかで暮らしていた頃、夜中に産気づいて、お産しようと思ったら、猛獣が近寄ってきた、とか、何か危ないことが起きたとすると、あ、これはお産なんかしていると母子共に危ない、だから、陣痛も、ちょっと微弱陣痛くらいにしておいて、逃げなくちゃ、ということになりますよね。つまり病院でお母さんたちが微弱陣痛で、赤ちゃんが生まれるくらいのいい陣痛が来ない時、というのは、ひょっとしたらお母さんたちが「こんなところで産んでいる場合じゃない、こんなところで産めない、なんか、怖い」と、思っていることの結果であるかもしれない。だから助産師たちは、懸命にお母さんたちに寄り添い、励まし、優しくするのです。そのようにしっかりと受け止められて、あ、ここでお産して大丈夫、と安心してお産に望むお母さんたちは、自分を手放し、体がゆるみ、赤ちゃんを良い感じでこの世に送り出すことができるようになる。人間の生理学的なお産のプロセスは、そのようになっており、そのようになっているからこそ、人間が近代産科医学の医療介入の助けが期待できない時代でも、途絶えることなく続いてきた、と言えるのでしょう。
エマニュエル・レヴィナスは、人間にとって最も耐え難い苦しみは「自分が自分に釘付けになっていること」と言っておられる、とのこと。採り上げているのは不眠と恥辱と吐き気、そしてそれらの不快な状況はどれも「われわれが自分自身と手を切ることができないことから生じる」。内田先生のおっしゃるように、それは、誠に卓見ですね。眠れないこと、を特に取り上げておいでですが、確かにそうです。眠れないことは、自らが過剰で、自分自身のことをずっと考えてしまったり、なぜ眠れないのか悩んだり、一体自分はどうなっているのか詳細に記述しようとしたりする事が根底にある、と。眠る、ということは、ふっと自分を手放せることだ、とお書きになっています。
アカデミックの世界で、眠れない人、多いですよね。1990年代に10年くらいイギリスの大学で働いていましたが、sleeping pill(就眠剤)を飲んでいない人は、いなかったくらい、多くの同僚が不眠に悩まされ、それが職場の話題でした。職場は、公衆衛生大学院でしたから、みんな、それなりの医療関係者の集まりです。眠れないことも、就眠剤を飲み続けることも、きっとそれは健康に良いとは言えない、ということは頭ではわかっていても、眠りにつくことができないことはもっと困るから就眠剤に結果として頼らざるを得ない。心理カウンセリングに通うことと、就眠剤を飲むことは、日常の一環、となっていることがよくわかりました。その後ブラジルにも住みましたが、こちらでも大学関係者、研究者の友人たちは同じような感じで、眠れない悩みを抱えている人が多かった。アカデミックとか、研究者とか、そういう仕事は、仕事にきりがありません。職場から帰ってきたら仕事が終わり、ということがなくて、何か考えたいこと、何か先に進めたいこと、何か解決したいこと、があるからこそ、分野は違えど、研究者になっているのです。やりたいことがあって、やるべきことが目の前にあるのに、今日という日を終えることはとても困難。もうちょっと、もうちょっと、とパソコンや本の前にかじりついて、夜更かししてしまう、というのは研究者の日常です。どこでオフにしたらいいのかわからない。自分をふっと手放す、ということがもっとも難しい職業かもしれない。自らの観察ばかりしてしまう。
わたしが30年以上、出産の経験について研究してきたのは、他でもない、出産、というのは、先にちらっと書きましたように、最もパワフルな「自分を手放す」経験であり得る、ということが直感的に理解できたから、そしてそれをなんとかして見える形で示したい、と思ったから・・・、というところがあります。「自分を手放す」経験、というのは、いわば、何かもっと大きなものに自分を委ねる、という経験で、それこそ、現在の少しずつ積み上げ、文字を通して理解するような知識の体系とはあまり相性が良くない。アボリジニーの人たちが、旅に出るときは、何も持っていかない、世界に委ねて、旅をする、と言っていたのとおなじようなことです。近代的な知を積み上げていくことが私たちにとって学ぶ、ということなのですが、それとは対極にあるような経験です。
人間が人間を産む、というのは、なかなかのことで、助産師さんたちは、「あっちの世界に行ってしまうくらいにならないと」生まれない、という表現をなさったりします。トイレに行って、トイレのスリッパを揃えて出てくるようだと、まだ生まれない。もう何が何だかわからなくなって、トイレのスリッパ揃えるような余裕がなくなると、生まれる。産んでいた女性たちもそういう状態を「宇宙の塵になっていたように感じた」とか、「時間の感覚がなくなっていた」とか表現して、まさに、出産で自分を手放すような経験をされたのだなあ、と思う。そういうお産をすると、そのお産の経験自体に支えられて、それからの育児の日々を乗り越えて生きやすいようなのですね。だから助産師さんたちは、がんばる。それを手助けしようとしてくれる。自分を手放して、自分を委ねた、というパワフルな経験は、それからの人生を支えてくれるものなのだ、とご存じなのです。
珊瑚礁の海のすぐそばで、幼い頃を過ごした男性の、少年の頃の話を伺いました。日が暮れるまで、ひたすら、海で魚を追い続ける。潮が引き始めた10時ごろから海に入り、潮が満ちてくる午後4時ごろまで、6時間近くも海に潜って、素潜り漁をする。ひたすらに魚を追いかけているうちに、自分自身が海に溶けて、自分も魚になってしまったような感覚になる。それはとにかく、とても気持ちよく、心地よいことなのだそうです。自然のリズムの真ん中に、自分が溶け込んでいき、自分は手放され、自分がなくなる。無我の境地、っていうのかなあ、難しくいうと・・・。とにかく、すごく気持ちがよくて、心地よくて、まだ知らないわけだけど、天国ってきっとこういうところなんじゃないかなあ、とおっしゃっていた。
それを聞きながら、全ての幼い人は、そのようにしてこそ、育つべきなんだなあ、と思います。自分が何ものであるか、あるいは、何ものでもないか、それを少年の頃に体感すること。そしてそれは、「ものすごく気持ちの良いこと」であることを知ること。幼い頃というのは、もともと、容易に自分を手放すことができるとてもオープンな状態にあるのだと思います。時間のことなど全く気にせず、やりたいことを延々とやる、心惹かれることを続ける。
今ではよく知られたモンテッソーリ教育の創始者である、イタリアの教育者、マリア・モンテッソーリは、それこそが教育の原点であるべきだ、と言っていましたね。1870年、イタリアに生まれ、ローマで初めての女子学生として医学部に入学するのですが、当時、物乞いをしている母親の傍らで、つまりは、ひどい環境にある小さな女の子が、小さな一枚の紙切れでとても深く集中して遊んでいる姿を見かけます。その女の子は、集中しているからこそ、とても充実し、平和な状態に見えた。モンテッソーリは、どんなひどい逸脱状態にある子どもでも何かに集中することによって変わることができる、という考えを天啓のように受け取るのです。障害児教育や、当時のローマのスラム街で子どもたちの教育を担当し、環境としてはひどい状態のため、落ち着いてもおらず、集中力もなかったような子どもが、自分がやりたいことを見つけると、どんどん変わってゆく。見つけたやりたいことを繰り返してやっていくうちに、集中力も深くなり、学びが深くなっていった、その経験から、モンテッソーリは、自由に選ぶ、繰り返す、集中する、充実感、達成感を持って終了する、というステップを理解した時、子どもたちは内側から変わり、自立していく、というのです。
紙切れにでも集中できる子どもが、海の中で集中して魚を追うのであれば、それはいっそうその子どもの本来の意味での自立を促すでしょう。自分を手放すことと、内側から変わり、自立していくことは、本当はコインの裏表のようなことなのですね。自らを手放す経験が幼い人たちに多く開かれていることについて、あらためて、この、子どもたちがガジェットとゲームに否応なしに組み込まれている時代に、考えてしまうのでした。
今日はこの辺りで。またお便りいたします。
三砂ちづる 拝
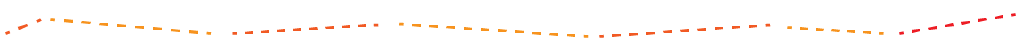
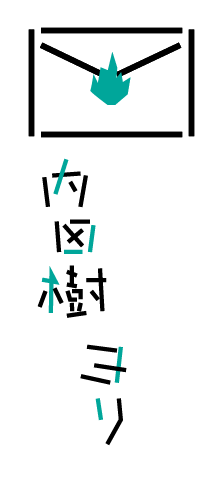
第10便・B
自我が消えてしまう時の解放感と愉悦
三砂先生
こんにちは。お手紙ありがとうございます。
最初に訪れた北米の地がアメリカではなく、メキシコとは驚きです。実は、僕もアメリカにはほとんど行ったことがないんです。若い頃に親類を訪ねてサンフランシスコに10日ほどいたのと、長じてからハワイに二度(兄とだらだらしに行ったのと妻とだらだらしに行った)だけで、東海岸も中西部も知りません。
僕はけっこうたくさん「アメリカ論」を書いているんですけど、考えてみたら、ネタはほとんどが小説と映画からでした。そもそも、アメリカ人の友人・知人が一人もいない・・・これはかなり偏っていますね。誰も指摘してくれなかったので、今まで気が付きませんでした。
鶴見俊輔は戦前にハーバード大学に留学していましたが、敵性国民として獄中に投じられている間に恩師のはからいで卒業証書をもらい、開戦直前に最後の日米交換船で日本に帰って来るのですが、それから二度とアメリカを訪れなかったそうです。別にアメリカに恨みがあるわけじゃないし、日本に義理があるわけでもないけれども、「負ける時は負ける側にいたい」と思って帰国して、ついそのままになった。
僕のアメリカとの「疎隔感」もそれに近いのかも知れません。日本は戦争に負けてアメリカの「属国」になりました。戦後しばらくは主権国家に戻りたいという願いを持っていましたが、もうそれも捨てて、「国家主権を回復したい。国土を回復したい」と願うことさえ止めた骨の髄までの「属国」になりました。その属国民であることの屈辱が僕をアメリカから遠ざけているのかも知れません。
『若草物語』や『あしながおじさん』の舞台であるニューイングランドなんか、個人的には「すごく行きたいところ」なんですけれど、それでもどうしても腰を上げて行く気になれない。たぶん、このままニューヨークもワシントンもシカゴも一度も訪れずに一生を終えるような気がします。
「不眠」の話は『レヴィナスの時間論』の中でかなり詳しく論じたトピックでした。三砂先生がおっしゃるように、眠るためには「自分を手放す」ことが必要です。でも、「自分を手放す」という行為は能動的・主体的にはできません。「自分を手放そうとしている自分」が前面に出てくると、自我は強化されるばかりですから。
睡眠薬にしても、薬を処方してもらったり、購入したり、服用したりするのは、自分自身ですから「自分で自分の眠りをコントロールしようとしている」という自我の過剰は解除できません。でも、ほんとうの意味でぐっすり眠るためには、自我の支配をどこかで終わらせないといけないんです。「ここから先は『自我』は入れません」と言って押し戻さなければならない。
よく「羊を数える」という就眠儀礼がありますけれども、あれはたしかに「自我の放棄」のためのエクササイズとしては合理的だと思います。「数える」というのは脳の働きですけれども、かなり単純な行為なので、自我が介入しなくても「羊をカウントする」作業だけは自動的にできる。そうやって自我の干渉を弱める。
武道では「有我有念」「有我一念」「無我一念」「無我無念」という四つの段階を仮説的に設定することがあります。
頭の中に煩悩や妄念がぐちゃぐちゃ渦巻いている状態が「有我有念」。それを(例えば「羊を数える」というふうに)単一の対象に集中するのが「有我一念」。その対象に没入しているとある時点で「無我一念」の境位に至る。「眠る」だけなら、この段階までくればもう十分です。
三砂先生がお書きになっていた「小さな女の子が小さな一枚の紙切れでとても深く集中して遊んでいる姿」というのは、たぶんこの子が「有我一念」から「無我一念」にレベルがシフトした瞬間の「没入感」をとらえたものではないかという気がします。集中がある強度を越すと「我」が消える。そういうことって、ありますよね。僕たちが苦しんでいる日々の悩みはほぼすべて「我」に絡みついているものですから、「我」が消えれば悩みも消える。経験的にはそうです。
武道の場合では「有我」というのは、脳が骨格や運動筋を操作して身体を「速く強く」使おうとするという「上意下達的なシステム」のことです。それは遅く、弱く、非合理な動きになります。100%脳が身体をコントロールしようとすると、どうしても選択的に随意筋だけを使い、それ以外の身体部位は「止める」ようになるので、仕方がありません。 だからすべての身体資源を活用しようと思ったら、「無我」で動かなければならない。
そもそも、「速い」とか「強い」というのは、速度や強度を競う相手がいて、それとの相対的な遅速強弱の「比較」にこだわっているから出てくる言葉です。「無我」の状態では、そういう対立や比較がなくなる。
僕たちのしている武道の稽古はそういう境地をめざしています。いわば「眠りながら動く」ような動きが理想的なものになるわけですね。周りのことなんかぜんぜん気にしないで、自在に動く。ジャッキー・チェンの「酔拳」というのはあれは術理的にはけっこう正しいんだと思います。
どうやって「無我」の状態に入るのかについては、武道でも宗教でも多年の蓄積を踏まえた具体的な技法があります。それを稽古ではあれこれと試してみます。
稽古しているとよく眠れるようになります。それはただ身体が疲れて休息が必要だからという生理的な理由だけではなく、稽古で「自分を手放す」ための技法をあれこれ工夫していることも関係があると僕は思います。
この「自分を手放す」経験の重要さを今の学校教育はどれくらい配慮しているのか、僕にはわかりません。たぶんまったく配慮していないような気がします。
三砂先生がモンテッソーリ教育について書かれたのは、言葉を換えて言えば、「ゾーンに入る」とか「フロー体験」とかいうことだと思います。
子どもたちにもぜひそれを経験して欲しいと思います。ある対象や、遊びにのめり込んでいるうちにふっと自我が消えてしまう時の解放感と愉悦をぜひ経験して欲しい。
前にもお話ししたことがあったかと思いますが、うちの娘がまだ小さい頃に、小学校からなかなか帰ってこなかったことがありました。学校からうちまでは細い上り坂一本で子どもの足でも歩いて5分とかかりません。娘の友だちが遊びに来ました。「まだ帰ってないよ」と言うと「一緒に校門を出たのに」と言うので、探しに行きました。そしたら、学校とうちの途中で座り込んでいました。何をしているんだろうと思っていたら、道端の草を見ているんです。ものすごい集中力で見つめていて、僕が近づいても気がつかない。そして、しばらく見てから深いため息をついて立ち上がり、数歩歩いてまた別の植物をみつけて、座り込んで観察を始めた。感動的な光景でした。子どもが対象に没入している。その集中の深さと身体から発熱している感じが伝わってきました。モンテッソーリが紙切れで遊んでいる女の子を見たときにも、たぶん似たようなものを感知したんじゃないかと思います。
僕自身も個人的な記憶としては、9歳くらいのときに似たことがありました。伊豆半島の養護施設にいたころの話です。病気がちの子どもたちを集めた施設ですので、勉強は午前中でおしまいで、昼からは友だちと遊んでもいいし、ひとりで本を読んでもいいし、何もしないでぼんやり過ごしてもいい。
その日は台風が近づいてきていて、僕は一人で音楽室にいました。窓の外を見ているうちに空一杯に黒雲が広がり、強い風が吹き始めました。竹林が風にたわんでほとんど90度に倒れてはまた起き上がるということを繰り返していました。その竹林を見続けているうちに、「竹と同化する」という不思議な感覚がありました。自分が自分の体から抜け出して、台風にあおられる竹林に入り込んでしまって、竹になって風にたわんでいる。その時のふるえるような解放感を長く忘れることができませんでした。
「没入すること」の喜びを人生の早い時期に経験するというのは、子どもにとってほんとうにたいせつなことだと思います。それこそ、僕たちが教師として若い人たちにまず伝えるべきことじゃないかという気がします。
娘が18歳になって家を出てから僕は一人暮らしになりました。25年ぶりの一人暮らしでしたので、もう好きなだけ本を読んで、好きな音楽を聴いて、好きな映画を観るという自由を満喫しました。
その年の夏休みに入ってから『レヴィナスと愛の現象学』を書き始めました。何時間も何日もぶっつづけで書き続けました。誰も止める人がいませんから。もう子どものためにご飯を作ったり、洗濯物にアイロンかけたりということをしなくていいわけですから、好き放題に時間が使える。
そういう生活を二週間くらい続けていたら、ある日「ゾーン」に入りました。「アカデミック・ハイ」と個人的に名づけることになった経験ですけれども、まだ論文を書いている途中だったのですが、書いている論文の最後までが全部見通せました。結論まで書き終わっている。そういう「ヴィジョン」が見えたのです。ほんの短い間の現象でした。必死になってその時の「書き終わった論文」について、何が書いてあったのか、メモを取ったのですけれど、後から読むと何が書いてあるかわからない文字列が残っただけでした。でも、その「ヴィジョン」を見た後、論文を書く進度は一気に上がりました。「この方向でよい」「自分はこの論文を書き上げることができる」ということについては、もう迷いや揺らぎがありませんでしたから。
そういうことって、あるんですよね。人間は、知的な働きでも、身体的な運動でも、短い時間だけれども、限界を超えて、深く、遠いところにたどりつくことがある。それは「自我」の拡大とか強化ということではありません。「自我」の向こう側に突き抜けてしまう。そういうことがあるんだよということを子どもに経験させてあげたい。
「ものすごく気分のよい状態」を知っている人というのは、そこが「戻るべき原点」になる。そういうことがあるような気がします。
僕が久しく尊敬する治療家の池上六朗先生は、患者さんのそばに立っているだけで、触りもしないで、身体の歪みを治してしまうという「特技」をお持ちです。どうしてそんなことができるのか、いろいろ理由を考えてみた結果、僕が得た仮説は「池上先生は、人生のある時点で、『どこにもつまりや痛みやこわばりやゆるみがない、100パーセント気分のよい状態』を経験したことがあって、その状態をありありと体感的に再現できるので、その体感を相手に伝えることで治療してしまう……というものでした。
その時に、池上先生に「もしかして、先生、子どもの頃に、『100パーセント気分がいい状態』を経験したことがありませんか?」とお訊ねしてみました。すると池上先生はしばらく考えてから、「そう言えば、ある」とお答えになりました。
まだ池上先生が少年だった頃。80年ほど前のことです。ある夏の日に、松本の家の近くのきれいな川で泳いだことがあるそうです。川の上には樹影が広がり、夏の日差しの下の川の水はひんやりしていた。水中に潜ったときに、「いま、100パーセント気分がいい」ということを実感したことがあるそうです。「思えば、あれが原点かもしれない」とおっしゃっていました。
三砂先生が書かれている「珊瑚礁のところで泳いでいると天国にいるような気がする男の人」もたぶん同じような経験をしているのではないかと思います。そういう原点を持っている人は自分の体のゆがみやこわばりがすぐに感知できる。どういう姿勢をしたり、動きをすればそれが補正できるかも直感的にわかる。休養であれ、栄養補給であれ、身体が何を求めているのかがわかる。そういう人が「健康」な人なんじゃないかと思います。
それは体重や血圧や尿酸値みたいなもので数値的に表示される「健常」とは別のものだと思います。自分固有の、自分だけにわかる「気分のいい状態」がリアルに感知できるので、必要なときにはいつでもそこに戻ることができる。
「ものすごく気持ちの良いこと」を知ること。それが子どもたちにとって最もたいせつな経験だと僕も思います。
果たして子どもたちはガジェットやゲームや仮想現実を通じて「ゾーンに入る」ことができるようになるかどうか、これは難しい問題だと思います。僕自身はそういうものに「没入した」経験を持たないので、断定的なことは言えません。でも、それらが子どもたちをある種の仕方で「限界を超えること」に誘い、「自我」の向こう側に突き抜ける経験をさせてくれるのであれば、教育的な意義はあるかも知れないと思います。実際に僕たちは子どもの頃にマンガに読みふけったり、映画に没入したり、音楽を聴いたりしながら、「我を忘れた」経験があるわけですから。でも、それが身体的に「ものすごく気持ちの良いこと」であるとは言えません。それだけでは足りないと思います。どうすれば子どもたちにそういう経験をしてもらうことができるのか。家庭教育でも、学校教育でも、それが一番たいせつなことではないかという気がします。
内田樹 拝
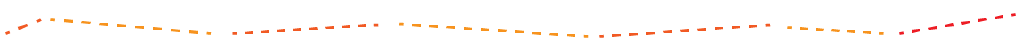
 内田樹(うちだ・たつる)
内田樹(うちだ・たつる)
1950年東京生まれ。凱風館館長。神戸女学院大学文学部教授。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。著書に『「おじさん」的思考』『こんな日本でよかったね』『コモンの再生』『日本習合論』など多数。『私家版・ユダヤ文化論』で第六回小林秀雄賞を、『日本辺境論』で2009年新書大賞を受賞。
三砂ちづる(みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。京都薬科大学卒業。ロンドン大学Ph.D.(疫学)。津田塾大学多文化・国際協力学科教授。著書に『女たちが、なにか、おかしい おせっかい宣言』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『オニババ化する女たち』『死にゆく人のかたわらで』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『少女のための性の話』など多数。

