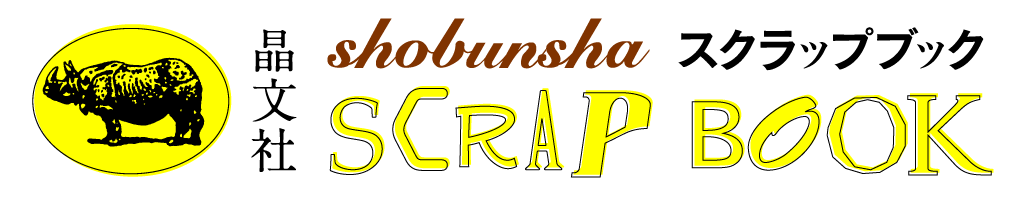内田樹先生と三砂ちづる先生の往復書簡による、旧くてあたらしい子育て論。ともに離婚により、男手で女の子を育てあげた内田先生と、女手で男の子を育てあげた三砂先生。その経験知をふまえた、一見保守的に見えるけれども、実はいまの時代にあわせてアップデートされた、これから男の子・女の子の育て方。あたらしい世代を育てる親たちへのあたたかなエール。
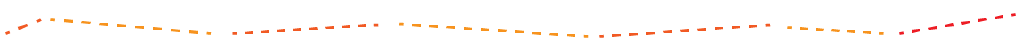
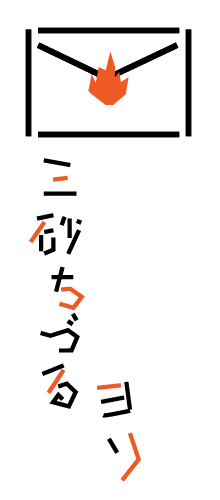
第13便・A
今日を機嫌良く生きていくことができたら
内田先生
お便りありがとうございます。お返事遅くなって申し訳ありません。新年明けてのご挨拶をするつもりが、節分明けて、のご挨拶となってしまいました。立春をすぎ、気温は低いですが、光は春、です。芽吹きの春、ですね。猫の額のような小さな畑を近所に借りて野菜を作っています。暖かい時はあんなに大変だった草むしりが、全く必要なくなる冬。ここを過ぎて少し暖かくなれば、また一斉にいのちが芽吹き始めるんですね。植物は律儀です。
前近代ヨーロッパにおいて、学校が作られたことの目的は「大人たちから子どもを守る」こと、であった・・・。なるほどなあ、と思いました。そして、“ヨーロッパで学校教育を先導したのはイエズス会士たちですけれども、彼らが子どもを学校に通わせるべきだというキャンペーンを展開したのは「若者を生まれたばかりの無垢のなかにとどめておくために、大人たちの穢れた世界から隔離しようという配慮」からです。何よりも親たちの非道な権力行使から子どもを守るためでした”・・・と書いておられる。幼いうちに大人の世界に組み入れられる子どもを守ろうとする。イエズス会士達の中に、このことに熱意を持った人たちがいたのですね、きっと。
全ての新しい試みは、誰かの意思、そして、それを共有するごく少数の人と共に始まります。マーガレット・ミードの有名な一節“Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.”(いつだって、思慮深く献身的な少人数の人たちが世界を変えてきた。というより、世界はいつもそのようにしてしか変わってこなかった。)を思い出しました。当時、学校、などという、逃れられる場所がある、と思っている子どもたちなど皆無でしたでしょうし、子どもたちを酷使している大人たちがそういうことをやってほしいと思ったはずもないし、大体そういう場が存在しうる、ということを子どもも大人も知らなかった。ただ、少数のイエズス会士が、とにかく始めた。うまくいくか追うかわからないけど、やってみようじゃないか、と、彼らの理念と、意思のみを恃みとして。内田先生がおっしゃっているような、15世紀、16世紀の時代背景の中で、学校、というところを、意志を持って開始した、おそらく若い、少人数の彼らの存在があったこと、を思うのです。
ずっと前にどこかでお書きになっていたと思うのですが、「ニーズがあるから学校ができる」、のではないですよね。学校というのは新しい理念や理想を提示するところであって、そこに「ニーズ」が認められるから、できる、というものではない。その時代、誰も賛成しない、誰も興味を持たないようなことでも、手を挙げて、理念を提示して、はい、こういう学校作りましたよ、と宣言することにより、そこに集まる人が出始める。そもそも学校はそういうものなのですから、「ニーズ」という言葉は、徹底的に馴染まない。イエズス会士たちも、ニーズなど考えていたはずがない。ニーズなど、皆無のところで、子どもたちのための場を作ろうとした。それが、大人から子どもたちを守るための学校となって行き、お書きになっているように、精神的・肉体的に傷つけられるリスクを回避し、子どもに安心できる場を提供し「学校」として制度化してゆく・・。
私の現在の職場、津田塾大学は、創立者、津田梅子が、たくさんの理想を掲げて、女子の英語の「ニーズ」なんてあるはずもなかった1900年に作った「女子英学塾」を母体としています。それから、120年以上、さまざまな理想を提示しながら、なんとか、ここまで生き残ってきました。都心の総合大学に人気があり、性の多様性が様々に語られる今、郊外の女子大という存在自体が大いなる時代遅れ、とも言えるのですが、今も風通しが良く、居心地の良い場を若い女性たちに提供できている(と思う)のは、何より、この提示してきた様々な理念と理想によるものだ、と思います。再度言いますが、「ニーズ」に応えてきたから、ではない。
そしてここには、学内保育所があります。いや、ありました。新型コロナパンデミックが始まる前まではよく機能していました。1980年にできた共同保育所を母体とし、のち、大学の管理のもとに置かれ、学生でも大学院生でも職員でも教員でも、使うことができました。常勤でも非常勤でも、アルバイトでも。長期でも、一日だけでも。大学という場で働いたり学んだりする人が、子どもを安心して預けられる場所、として機能していました。「健康教育」とか「ヒューマン・セクソロジー」とかいう講義を担当してきたので、学生たちに妊娠、出産という話題について話す機会がありますが、そこで、いつでも、「もし、妊娠して、子どもが産みたいと思えば、学内に保育所がありますよ。赤ちゃんを預けて安心して勉強できます。そういう選択をすることが可能な環境です」と、学生に語りかけられることは、私のこの職場にいる誇り、だった。実際、学生で、子どもを産んで赤ちゃんを預けて勉強している人も、常に誰か、おりました。東京都郊外小平市の緑あふれるキャンパスを遊び場として伸び伸びと育つ子どもたちの様子に憧れて、ここに子どもを預けて勉強するのが夢だった、と、社会に出て、子どもを産んで、大学院に戻ってきた人もいたくらいです。
新型コロナパンデミックでさまざまなルーティンが壊れてしまって、一斉にオンライン授業に移行した大学で、この保育所を使う人が激減しました。それに伴って運営の困難もいろいろ出てきて、とうとう保育所が閉まってしまった。「ニーズがなくなったから仕方ないですね」、という声が、大学運営上層部あたりから聞こえてきて、愕然とします。1980年代からの津田塾の学内保育所は、その存在だけで、すでに高く掲げられた理想だったのです。パンデミックが起こったり、近所の保育所に子どもたちが通うようになったり、いっとき子どもを預ける人が少なくなったとしても、「大学内に保育所がある」という理想を体現した現実の灯火は、決して消すべきではない。たとえば、いくら病人怪我人が何日もいなくても、学校の医務室を閉めてもいい、ということにはならないように、学内保育所も、いつもそこにある、ことで、理念と姿勢を示すものであったのだ、と思います。異次元の少子化対策、とか大きなことを言わなくても、女子大学は、そこに身を置く人が誰でも子どもを預けて学び、働ける場である、ということを可能にすることで、その理念と理想を示していた。それこそが大学の存在意義、学校の存在意義、です。このことが理解されて、学内保育所が復活することを、信じていたい。常に、理念を大事にしている学校だったのですからね。
それはともかく。イエズス会の皆様が理念を持って始め、大人たちや雇用主たちから、子どもを守り、子どもたちのための場所を確保する、学校がそのようなところであった、そういうものだった、ということを思い出すこと。おっしゃるようにそれは意義のあることです。国際保健、という公衆衛生の一分野で仕事をしてきました。いわゆる、開発、とか国際協力、とかの一環、と言える仕事ですが、保健や教育の分野の国際協力って、わかりやすいんですね。「医者のいないところには、医者がいるようにする」、「病院のないところには病院をつくる」、「学校がなければ、学校を作る」、「女の子が学校に行けないなんてとんでもない、行けるようにしよう」。そういう近代の作り上げた制度に疑問を持たず、提示することをためらわない。このことに、先進国の人たちは反対しません。そうあるべきだと思う。学校がない、学校に行けない、ということは、子どもたちがいるべき場所を持っていない、ということであり、子どもとしても守られていない、ということ。前便で、アリエスやバダンテール、マルクスを引用しておられる当時のヨーロッパの議論と同じです。
マルクスが報告している19世紀のイギリスの児童労働者たちのように学校に行くことなく生涯を終えることが、途上国と呼ばれる国の子どもたちに、今も起こり続けていくことをなんとかなくしたい。たとえ一年に数週間でもいいから、子どもたち、女の子たちに「学校に通って欲しい」と、今では、少数のイエズス会士ならぬ心ある先進国の大半の大人たちが考えているのです。かように今も昔も、ずっと学校は、子どもを救うものだった。学校に行くことが、子どもにとって子どもであることを保障するような場所だった。日本でも、子守りをやっているこどもは学校に行きたかったでしょう。女に学問なんかいらない、女は学校に行かなくてもいい、と言われた娘たちは学校に行きたかった。息子たちは文学をやりたかった。
そもそも元々は、どういうものであったのか、どういう意図で作り上げられた制度だったのか、それがどうであれ、時代と共に、変わってしまうのは、それが学校であっても、結婚であっても同じことですよね。学校は、そこに行かなければ労働に駆り立てられる子どもたちを救うものだった。結婚も、元々は、女性の地位を安定させ、安心して子どもを産み育てることができるように、稼いできてくれる男を担保するためのものだった。元々は学校も、結婚も、新しいものを提示し、社会の成員を救い、世の中をより良くするためのものだったのだと思います。でも、それは否応無しに時代と共に変わってくる。
思えば私たちの今は、前の世代の方々の希望の集積によって出来上がったものです。ほんの一世代前まで、親や周囲が決めた人と結婚することが当たり前だったけれど、本当はそんなことめんどくさい、結婚なんかせずに、好きに暮らしたい、一人で生きていきたい、と思った人たちも少なからずいて、そういう人たちの希望は、今、見事に結実していて、一人で生きていくことを誰もおかしいと思わなくなりました。男も女も、結婚せずに独身でいることで肩身の狭い思いをすることも無くなったのです。少子化、と言われていますが、70年代の人口爆発をどうするか、という議論の、今が集大成、子どもが増えすぎて困ると言われたことの結果、が今なのであり、望んだ結果だったわけです。母や妻や嫁として生きるのだけなんて嫌だ、と思っていた前の世代の女性たちの夢は、今、花開きました。行こうと思えば高校も大学も行けるようになったし、子どもたちも、全員が学校に行けて、親からひきはがされて理不尽な労働に追い立てられないし、親たちも産んだ子どもの育ちをみていけるようになりました。
かように、近代は、夢の達成のプロセスでありました。衣食住が豊かになり、一人ひとりが自由を手にし、理不尽な差別は許されなくなった。人間はやっぱり進歩しています。しかし近代は一筋縄ではいかない。昨年暮れに亡くなった、敬愛する渡辺京二さんの著作に『近代の呪い』というのがあるのですが、まさに、呪い。この豊かさと、理不尽さの消滅の裏に張り付く呪い。豊かになり、より良く生きるために作った、と思われるそれぞれの装置が、抑圧のシステムと化す。そしていま、学校は、そのようなところ、と認識されるようになりました。子どもは学校に行かなくても良いのかもしれない。これだけ多くの子どもが行かなくなると、考えざるを得ない。
十年暮らしたブラジルで、よく耳にする言葉がありました。Alguém tem que trabalhar em casa.「おうちで、誰かは、働かなくちゃね」、という意味です。家では誰かが稼いでこなきゃいけないね、誰かは働いていなきゃいけないね。みんな暮らしていかなくてはいけないからね。でも、それは、逆に言えば、誰かが働いていればいい、ということです。家の中で働かない人がいても、かまわない。だって誰かが働いているんだもん。ブラジルに住んでいた1990年代、周囲にいたブラジルの普通の中間層の人たちは、よく、先住民の発想を生活に生かすべきだ、と話していました。ボルソナロ大統領は資本を優先して先住民の多くを苦境に追いやった、と現在言われていますが、普通のブラジルの人たちは、アマゾンの先住民の人たちに心よりの敬意を持って過ごしていましたね。曰く、ブラジルの人は他のラテンアメリカの人より、穏やかなんだよ、それはアマゾン森林のインディオがおだやかだから。子どもに手をあげたりしないんだ、それはインディオが絶対にそういうことをしないから・・・。そして、これです、「おうちで、誰かが働かなきゃね」。フォトジャーナリストの長倉洋海さんがアマゾンのヤノマミを撮った写真集『人間が好き』には、「この誰かが働かなきゃね」がみごとに描かれています。狩が好きな人は狩りに行く、働くのが嫌な人は、働かないでハンモックで寝ている。誰も文句を言わない・・・・。全員が全員、働かなくてはいけないわけではない。確かにそうですよね。私たちの周囲にも、本当に働くのが好きな人もいますし、そうではない人もいる・・・。だから「誰かは働かなくちゃね」。全員でなくて、いい。
わたしたちは長い時代を経てやっと、若くて元気で働くこともできるような人に無理やり気に染まないことをやらせたり、子どもたちを強制労働に追い遣ったりすることなく保護できるようになった。しかし、その昔、子どもを解放するための装置であった学校は、その幻想を強化して、生の原基に敵対しているように見えます。つまりは、子どもたちが今日を生き生きと生きるために、学校が役だたなくなった。学校に行かなくても、家にいても、それで生きられるようになった。それは、実は、なんとも結構な世界なのではないでしょうか。子どもが学校に行かなくなる、あるいは、長じて、子どもがちゃんと稼がない、その不安はなんでしょうか。自分達がいなくなったあと、子どもが困るんじゃないかということでしょうね。でも、それはその時に、子どもが考えるしかない。
学校に行かなくてもいい、働かなくてもいい、でもこの人たちが今日を機嫌良く生きていくことができたら。これを人類の達成、と思って、働ける人が働く、で良い、ということにできないでしょうか。彼らが学びたくなった時、何かやりたくなった時、自らを教育することができる本や、そういった本にアクセスできるシステム、をもう、わたしたちはもっているのではないでしょうか。働かないなら、働いている人が助ければいい。親か兄弟か親戚の誰かが助ければいい。それがむりなら社会が助けたらいい。学校に行かないことの帰結、ひとなみに金を稼いでこないことの帰結、については、私たちはすでにそう悪くないストーリーを紡ぎ始めているような気がします。であれば、悩む必要はそうないのかもしれない。誰かが働いているなら、働いていない人が機嫌良く家にいてくれることだけを考える。そんなふうになれないでしょうか。楽観的にすぎる、と言われそうですが、そう言ってみたい気がしています。長くなりました。季節の変わり目、内田先生、ご自愛ください。
三砂ちづる 拝
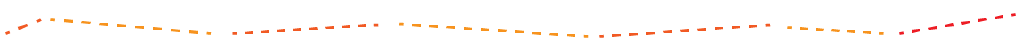
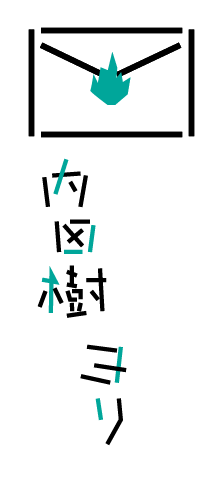
第13便・B
親族が存続するために最もたいせつなこと
三砂先生
こんにちは。内田樹です。
これが往復書簡の最終便なんですね。なんだか、あっという間に終わってしまったような気がします。安藤さんは「男の子の子育て」にフォーカスした本を作りたかったようですけれども、目論見通りにはゆかず、話頭は転々と奇を究めてしまいました。安藤さん、ごめんなさい。
でも、それは仕方ないと思うんです。親子のかたちも、婚姻のかたちも、家族のかたちも、社会のかたちもどんどん変わっているのですから、その流れの中にあって「変わらないもの」を見届けておかないと子育てについての話はできません。
子育てにおいて、どれほど時代が変わっても、場所が変わっても、変わらないものとは何でしょう。
レヴィ=ストロースが「親族の存在理由は親族を存続させること」だとどこかに書いていました。その通りだと思います。
親族を存続させるための方法はいろいろあります。集団ごとにローカルな取り決めがある。そもそも「親族」という語についても一意的な定義があるわけじゃないと僕は思っています。「親族」は必ずしも親子関係や婚姻関係で結び付けられた集団だけを意味するわけではない。法統を守る、学統を守る、先人から受け継いだ儀礼や技芸を守る…そういう目的のために形成された集団も「存続すること」が最優先である限りは広義での「親族」に含めることができるのではないかと僕は思います。その大筋のところさえ外さなければ、集団ごとの細かい異同や変遷はあまり気にしないでいいんじゃないでしょうか。
その上で改めて問うことになります。親族が存続するために最もたいせつなことは何か? これがこの書簡の中で、三砂先生と僕が暗黙のうちに語り合ってきた主題ではなかったかと思います。
親族が存続するために最もたいせつなことは何か?
それは次世代を担う子どもたちの知性的・感性的・霊性的な成熟を支援すること、それに尽くされる。子どもたちの成熟を支援すること。それが僕たちが親族の一員としてふるまうときの基本的な構えだと思います。それ以外はすべて副次的なことに過ぎない。
僕たちが子どもたちに接するとき、おのれの言動の適否の判断基準とすべきは「これは彼らの成熟に資するのか?」という問いです。それだけで十分です。
でも、今の日本の子育てを見ていて、僕が感じるのは、親にしても教師にしても「果たしてこれは子どもの成熟に資するか?」という問いをまず立てるという習慣をもう失ってしまったようだということです。こうすれば競争に勝てるとか、こうすればいい暮らしができるとか、こうすれば食うに困らないとか…そういう「アドバイス」はすぐに脳裏に浮かぶのでしょうが、何を措いても「これは子どもの成熟に資するか?」という問いが前景化するということはない。それが現代の子育ての最大の問題だと思います。
僕は落語が大好きなんです。今度も、膝の手術で長く入院生活を強いられたので、その間、たくさん落語を聴きました。落語というのは実に奥の深いものですね。そして、「いかにして人を成熟に導くか」ということは、多くの落語の隠された主題でもありました。今回、古典落語を数十席聴いて、しみじみそう思いました。
『唐茄子屋政談』という古典落語の名作があります。大店の若旦那の徳兵衛が吉原での遊びが過ぎて勘当されてしまう。額に汗して働いたことなんかないのに、「お天道様と米の飯はついてまわります」と親戚一同の前で啖呵を切って家を出てしまう。出たのはいいけれど、何の芸もありませんから、たちまち窮迫してしまう。頼りにしていた花魁(おいらん)にも、友だちにも愛想をつかされて、ついに乞食同様のなりに零落して、絶望のあまり吾妻橋から大川に身投げしようというところを通りがかった人に助けられる。これがたまたま実の叔父さんで、「なんだ徳か、だったら助けるんじゃなかった」と突き放されるのにとりすがって、前非を悔いて、まじめに働くことを誓います。
そこから話が面白くなります。聞かせどころは叔父さんが若旦那に「あきんどの道」を説くところです。今日から天秤担いで唐茄子を売れと命じられた若旦那が「天秤かついで唐茄子売っているところを知ってる人に見られたら恥ずかしい」とつまらない見栄を張る。すると、叔父さんがこう一喝するんです。「みっともねえ? いやだ? あそうか。だったら、やめな。それ脱いで、手前のきたねえ着物を着て、さっさと出てって川に飛び込め。何がみっともねえんだ。天秤かついで唐茄子売って、それでわずかでも口銭儲けりゃ、立派な商人だ。飯も食えねえでふらふらしているやつのほうがよっぽどみっともねえ。」
叔父さんに怒鳴られて、ちょっとだけ反省して重い天秤担いで売りに出た若旦那、慣れぬことですから、唐茄子は一つも売れず、炎天下をよろよろして、蹴つまずいて転んで唐茄子を道にぶちまけてしまう。通りかかった気のいい兄さんが事情を聞いて同情してくれる。「道楽が過ぎてうちを勘当されて、叔父さんところへ居候していて、今日はじめて商いに出た? ああそうか。若いときにはよくあるこった。ここでこう会ったのも何かの縁だ。荷を軽くしてやろうじゃねえか」と行き交う町内の人たちに片っ端から唐茄子を押し売りしてしまう。
叔父さんのきつい説教と見ず知らずの兄さんの法外な親切を半日のうちに経験することで、この若旦那「人の道」を知ることになります。どういうかたちで「人として」まともになるかは落語の方を聴いて頂くとして、深い話だなあと思いました。これ、両方とも要るんです。「説教」と「親切」。子どもを成熟に導くには、この二つが要る。「世間はきびしい」と「世間はやさしい」という二つの矛盾する命題を同時に子どもに教えなければならない。
叔父さんの家に転がり込んだ当初も若旦那は世間知らずなことばかり言って、叔父さんを何度も怒らせるんですけど、そのつど親切な叔母さんが取りなしてくれる。気のいい兄さんが唐茄子を売ってくれるときも、もちろん「見ず知らずの野郎から唐茄子なんか買う義理はない」と突っぱねる人もいます。その冷たい「経済合理性」を兄さんの「親切心」から発する熱い啖呵がやり込めるところもこの噺の聞かせどころです。
どの場面を切り取っても、「世間はきびしい」と「世間はやさしい」という対立する二つの命題が繰り返される。実によくできた説話構造だと思いました。どちらか一つじゃ足りないんです。両方が交互に来ないとダメなんです。
『唐茄子屋政談』の若旦那はいい年まで徹底的に甘やかされて育てられた人です。「世間は甘い」と思い込んで、そこで成熟が止まっていた。それが勘当と世間の風の冷たさに触れて、ちょっとだけ目が覚める。でも、「世間は冷たい」と気づいただけではまだ成熟には至りません。生きる意味を見失って死にかけたところを叔父さんに救われる。その叔父さんから商人のきびしさを叩き込まれて、ちょっとだけ薄目が開く。そして、見ず知らずの人の親切に触れてようやく目が開く。そういうプロセスなんです。
これは子育てのプロセス、子どもの成長プロセスそのままじゃないかと僕は思いました。
まず子どもは甘やかされて育ちます。なにしろ自分では移動することも、栄養補給もできないんですから、親がまるごと面倒見てあげるしかない。そして、この時の親たちの「子どもを守る」仕事はふつうの人ならほぼ本能的にできる。ときどきそれさえできない「ネグレクト親」ももいますけれど、それは例外的な存在だと思います。とりあえず、僕たちが生きている日本社会では、伝統的に(たぶん千年以上前から)赤ちゃんは親が守るという話になっています。
まず子どもを「守る」。こう言ってよければ「温室で育てる」。子どもがどんなに自由にふるまっても、手足を好き放題伸ばしても、それによって傷つけられることがないという環境を整える。それが親の最初の仕事です。
でも、どこかで「自分でできることは自分でやりなさい(自分でしないと、誰も代わりにそれをしてくれない)」あるいは「好き放題にも限度がある。世の中には守らなければならないルールがある(そのルールに違背すると罰を受ける)」ということを教える段階に達します。
子どもにとっては嫌な話です。そんなこと、できたらやりたくない。でも、それをやらないと、罰を受ける。傷を負う。それが深い傷になること、致命傷になることだってある。『唐茄子屋政談』の若旦那のように死ななければならないことにもなる。だから、それを回避するために子どもに何とかしてこの「苦役」を受け入れさせなければならない。
子どもに「お前は可傷的な存在である。でも、ある手だてを講じれば(その手立てはお前には『苦役』と感じられるだろうが)、傷を負わずに済む)」という事実を伝える。これが子育ての第二段階です。
でも、これ、すごく難しいんですよね。オールマイティな定型がないから。こういうふうに子どもに説教すれば、どんな子どもでも「ああ、そうですか。ご説明を伺って、事情はよくわかりました。では早速その苦役を担います」と飲み込んでくれるというような都合のいい理屈はありません。こればかりは「成熟するためには、ここを通らなければいけないんだ」という以外に言いようがない。そして、その言葉にどれだけ説得力があるかは、親の側の成熟度にかかっている。
ここが関門なんです。そして、たぶんここが子育ての一番深いところだと思います。ここで親が試される。親がどれくらい成熟しているかが試される。
子どもを甘やかす仕事には親の成熟は必要ありません。どんな親にもその仕事は務まります。でも、子どもに「自分でできることは自分でする」「世の中のルールを守る」という「苦役」を強いるためには、親の側に説得力のある言葉の用意がなければなりません。親自身が「成熟するためには、このプロセスをたどることがどうしても必要だ」ということを骨身にしみて感じていなければならない。親自身が未成熟であれば、そんな話はできません。成熟するということのたいせつさを親自身が身にしみて感じていなければ、子どもを成熟に導くことはできない。
いや、「できない」と断言するのは言い過ぎですね。そんなことはありません。親が未熟で、幼児的でも、子どもは成熟することができる。ただ、その道筋が「親が成熟している子ども」とは違う。親以外の誰かから「成熟せよ」という強い命令の言葉を突き付けられなければならない。そういう親以外の「メンター」に出会えればいいんですけれど、これは運任せです。
とりあえずは、親が子どもの成熟の導き手になる場合について話をしたいと思います。
親自身が「成熟することはたいせつだ」と本気で思っていたら、どんな言葉づかいで語りかけても、意のあるところは子どもに通じるはずです。でも、その時点の子どもにはまだ「成熟」ということの意味がわかりません。言葉だけは耳で聞き知っていたかもしれないけれど、その概念が受肉していない。何のことだかわからない。だから、これは子どもの頭じゃなくて、身にしみこませるしかないんです。
叱ってもいいし、説教してもいいし、諄々と「誠の道」を説いてもいいし、自分の経験談を語ってもいい。何をしてもいい。とにかく「成熟せよ」というメッセージを子どもの身体に叩き込む。身にしみ込ませる。そのときには理解できなくてもいいから、とにかく身体のどこかに刻み込む。
子どもにはその意味は分かりません。でも、「この人は何かを必死で伝えようとしている」ということまではわかる。そのときに「いったい、この人は私に何を言おうとしているのか?」という問いが子どもの中に立ち上がれば、とりあえずそれでオッケーです。
「あなたはそうすることによって何をしようとしているのか?」これはジャック・ラカンが「子どもの問い」と呼んだものです。別に悪い意味ではありません。子どもが成熟するためには、この問いを経由することが必要だからです。
「あなたはそうすることによって何をしようとしているのか?」という問いが意味するのは、「あなたのメッセージを私は理解できない。でも、そこには『私が早急に理解すべきこと』が含まれていることは、あなたの必死さからわかる」ということです。もちろん、子どもはそんなに論理的な言葉づかいをするわけじゃありません。でも、自分に向かって語りかける必死さからそれがわかる。いわば、それに気圧されて、子どもは自分の理解を超えたメッセージの解読のために、自分自身の手持ちの理解枠組みの「外へ」一歩を踏み出す。ここのかんどころは「自分に対する必死さ」に「気圧される」というところなんです。
人間は自分の理解を超えたメッセージであってもそれが自分宛てであるということはわかります。コンテンツの理解と「宛先」は別の次元に属するからです。そして、それが「ほらよ」とぽいと投げ出されて「理解できてもできなくても、そちらのご自由に」という差し出し方をされるのか、「お願い、わかって」と袖をすがるようにして差し出されたものかで、メッセージの受信の仕方は変わる。メッセージは「コンテンツが正しければいい」というものではないんです。懇請の度合いによって、それが届くか届かないかは決まる。そして、届かないメッセージでは意味がない。
北九州でホームレスの支援活動をしている「抱樸(ほうぼく)」という団体があります。その理事長をしている奥田知志牧師のことは三砂先生もご存じだと思います。
奥田さんはもう30年以上ホームレス支援をしています。でも、ホームレスの人たちって、最初は「ほっといてくれ」と言うんだそうです。食べるものも、寝るところもないのに、「お弁当上げます。寝るところも用意します。仕事も探します」と言っても「今度でいいわ」とか「ま、考えとくわ」という気のない対応をされるんだそうです。いったいどうして自分たちの支援の提案が彼らには届かないのか、奥田さんはずいぶん悩んだそうです。そういう人たちは自分のことを「もうどうでもいい命だ」と思っている。「生きていても死んでいても、誰も喜ばないし悲しまない」。そう思うから支援の手を振り切ってしまう。生きる意欲そのものがない。どこかでそれを根こそぎ失ってしまった。
それに対する奥田さんの対応は「助けたる」という呼びかけの「インフレ」だったそうです。その言葉をそのまま採録します。
「だからね、もう私は、ほとんど意味なく助けてというのを連呼するような、道を歩いていると『助けたろか』とか言いながら、『今度でええわ』とか言いながら、『本当助けたるから、お前ちゃんと言えよ』とかって言いながら、助けてをもうボンボン安売りする。私は助けてのインフレを起こせと言ってるんですけどね。ともかくハードル下げる。それを子どもたちが見ると、『ああ、言っていいんだ』という話になると思うんですね。」(後藤正文、「誰もが助けてと言える場所、『希望のまち』をめざして」、The Future Times)
奥田さんの「助けたろか」というメッセージは一回では終わらないんです。「まあ、ええわ」と言われても気にしないで、会うたびに「助けたろか」と言う。それを何回、何十回繰り返しているうちに、相手は奥田さんの懇請に「気圧されて」、ある日ついに「助けて」という言葉をつぶやいて、自分を閉じ込めていた檻から外へ踏み出す。
僕はこの「安売り」「インフレ」「ハードル」といった一連の語の選択に奥田さんの哲学を感じます。これ、ぜんぶ「程度」を問題にしているんです。「原理」の問題ではなく。
困窮者に向かって支援を申し出るのは「正しい」行為です。相手が「助けなんか要らないよ」と言ったので、そこで引き下がって、「では、さようなら」と立ち去ったとしても、支援を申し出たことの「正しさ」はいささかも揺るぎません。でも、奥田さんの相手が根負けして「わかった。じゃあ、助けて」と言って手を差し出すまで、会うたびに「助けたろか」と言い続ける。この「正しさ」は、助けを拒絶されて立ち去る人の「正しさ」とは違う「正しさ」です。
どちらが「より正しい」のかという議論をしているわけではありません。どっちも正しい。ただあっさりした言葉は相手に届かず、しつこい言葉は相手に届いたというだけのことです。でも、この程度差のうちに、一人のホームレスの人の生き死にがかかっていたということもある。
子どもが成熟の階梯に一歩踏み出すようにするために親はどういう言い方をすればよいのか、という話をしているところでした。
宛先ははっきりしています。目の前の子どもです。自分がメッセージの宛先だということは子どもには分かっています。あと必要なのは「迫力」です。メッセージの「強度」です。奥田さん的な「しつこさ」です。おせっかいの「安売り」です。コンテンツの論理性とか、政治的正しさとかはさしあたりどうでもよろしい。子どもの身体に浸み込むまでやることが必要なんです。
子どもたちは「自分には理解できないメッセージ」は基本的に「聴き流し」します。子どもだって忙しいですから、親のなんだかわからないぐちゃぐちゃした説教なんか聞きたくない。だから、強度や、しつこさや、必死さというものの助けを借りないといけない。
『唐茄子屋政談』の叔父さんの説教はかなり定型的です。でも、叔父さんの中に深く身体化している。だから、若旦那のへなちょこな世間知を一蹴することができる。
それが仮に「世の中、結局、金だよ」というような貧しい定型であっても、親がそれを深く身体化して、それ指針としてこれまで生き抜いてきたのなら、子どもを「甘やかされている段階」から次の段階へ進める「社会化」の装置としては十分に有用です。でも、この言明をただちに打ち消す「世の中、金だけじゃないよ」という反対命題もこれと同時に与えられなければならない。ここがかんどころです。
『唐茄子屋政談』だと「世間は厳しい」という叔父さんの説教のすぐ後に、それを打ち消すように、唐茄子を代わりに売りさばいてくれる気のいい兄さんが出てきて「世間には親切な人もいる」という対抗的命題を体現します。この二つが整わないと、子どもは成熟できない。どちらの言うことがほんとうなのか、子どもが混乱しないと、子どもは先へ進めない。葛藤しないと、成熟できない。
子どもは成熟のためには「甘やかす人」と「きびしく訓練する人」の二人の年長者を持たなければならないというのは、レヴィ=ストロースの理説ですが、別に『親族の基本構造』を読まなくても、『唐茄子屋政談』で同じ命題が語られている。『男はつらいよ』だって「そういう話」です。
レヴィ=ストロースは「伯叔父制」というシステムが世界中の多くの親族集団に見られると書いています。「伯叔父」というのは、男の子にとって母親の男兄弟のことです。その「おじさん」が「父」とは違う仕方で子どもに接する。
父親と息子が親密な集団では、「おじさん」が甥に厳しく社会的な規律を教え込む。逆に、父親が厳しく息子を訓導する集団では、「おじさん」が甥を甘やかす。『男はつらいよ』の博(前田吟)と寅さん(渥美清)と満男(吉岡秀隆)の関係が典型的ですね。
「おじさん」の教育的機能は、父の命じるあれこれの指示について「そんなの適当に聴き流しておきゃいいんだよ」と介入して、無効化することです。別に「おじさん」の言うことが「正しい」わけじゃありません。でも、同性の年長者で、それぞれに社会的経験を積んでいる人たちが「違うこと」を教えるということには深い意味があります。子どもに向かって「大人たち」が全く正反対のことを説くと、子どもの中に「この人たちは、ほんとうは何を言おうとしているのか?」という問いが兆すからです。
外形的にはまったく正反対のことを言うこの二人は、それにもかかわらず、子どもにどうしても伝えたいことがある。それは子どもにもわかる。それぞれの大人が語る言葉にひとかたならぬ「迫力」があるからです。
一体彼らは「違うことを言うことを通じて自分に何を言いたいのか?」子どもは当惑します。混乱します。葛藤します。それでいいんです。葛藤させるためにこそそういう仕掛けがあるんですから。子どもに正解を与えてもしかたがないんです。子どもの手持ちの判断枠組みでは「正否の判断ができない問い」を与えることがたいせつなんです。子どもは葛藤する。そして、葛藤のうちで成熟する。
レヴィ=ストロースの「伯叔父制」理論は「息子」についてだけで、「娘」について同様の仕組みがあるのかどうか、寡聞にして僕は知りません。娘の場合なら「母」と「(父の姉妹)である伯淑母」の間に同じような役割分担が成り立つはずなのですが、果たしてどうなんでしょうか。よくわかりません。
実際に娘を育てた経験から言えるのは、どうも娘というのは母親一人がいれば育つらしいということです。それは父子家庭だったときに、僕が「父親」ではなく「母親」を演じていたことでわかりました。父子家庭の12年間、僕は家の中では完全に女性ジェンダー化していました。親と子が二人きりなら、要るのは母親であって、父親ではありません。ご飯を作り、掃除をし、洗濯をし、アイロンをかけ、繕い物をし、布団を干し、子どもが生理的に快適な生活を送れることを最優先に配慮する大人は絶対に必要ですけれども、外に稼ぎに出かけて、夜帰ってきて、たまに思い出したように「学校はどうだ。勉強してるか、おい」くらいしか言わない男なんかいなくても全く困らない。
ただ、ずいぶん経ってからわかったのは、やっぱり男性が女性ジェンダー化して演じる「母親」は深みが足りないなということでした。僕はたしかに「親切なお母さん」ではありましたけれど、「怖いお母さん」ではなかった。針で刺すような一言で子どもを震え上がらせるような芸当はできなかった(別れた妻はそれが軽々とできました)。
なんとなく思うんですけれど(ほんの思いつきなんですから、あまり気にしないでくださいね)、娘にとって母親はその存在自体で、いわば単体で娘を「葛藤」のうちに叩き込むことができる存在なんじゃないでしょうか。あるときは無限に優しい母親が、あるときは娘の心の底まで射貫くようなすさまじく冷徹な母親の表情を見せる。「外面似菩薩(げめんじぼさつ)内心如夜叉(にょやしゃ)」というのは女性についてしか使われない形容です。男にはそんなすさまじい二面性を抱え込むだけの容量がない。
「母の呪縛」から逃れられない娘たちというのがよくいます。僕も女子大の教師でしたから、そういう事例にいくつも遭遇しました。どれもよく似ているんです。娘に対して圧倒的な支配力を行使できる母親というのは、娘を溺愛しているのですけれども、娘の弱点もまた熟知している。女の子にはそこに抑えられると身動きできなくなる、息が詰まるという「急所」があるんですけれども、そこに狙い澄ましたように一針を打ち込むことができる。「要するに、あなたはそこがダメなのよ。それ、一生治らないわよ」みたいな怖いことを言える。
そういう芸当をできる父親というものに僕は会ったことがありません。これができるのは母親だけです。それは母親が子どもの「弱さ」に意識をフォーカスする存在だからだと思うんです。だって、ちょっと気を許したら、子どもって死んでしまいますから。だから母親は「子どもの弱さ」については周りの誰よりも高感度であることを求められる。夜中に、隣の部屋にいる子どもがふつうの人には聞こえないようなかすかな声でうめいても、ぱちりと目を覚ます。母親って、そういうことができる。そういうふうにして子どもを無事に育て上げることができた。ですから、母親には、成長した後もわが子の「本質的な弱さ」がありありと見えるんだと思います。
娘を溺愛することと、娘を呪縛すること、母親はそれが同時にできる。だから、娘は葛藤できる。それゆえ母親さえいれば(父親がいなくても、伯叔母がいなくても)女の子は成熟できる。そういうことなんじゃないかと思います。別にレヴィ=ストロースがパターナリストだったとか、そういうことじゃなくて。
もちろん、男の子についても「母親の呪縛」というのはあります。けれども、それほどシリアスなものにならない。どうしてなんでしょうね。たぶん母親は男の子には「内心如夜叉」の部分をあまり見せないからなんじゃないでしょうか。「母親がなにかのはずみにふと見せた底知れず邪悪な横顔を見て寒気がした」というような経験を持っている男ってあまりいないような気がします(女性にはたくさんいます)。その違いでしょうか。
ああ、すみません。こんなややこしい話を最後の最後に持ってきて、すみません。段取りが悪すぎますね。
さあ、もう取っ散らかった話もこの辺で終わりにしますね。話は結局最後まで取っ散らかったままで、回収できませんでした。でも、仕方がないですよね。「子育てはこれだけすれば成功します」というようなシンプルな解は存在しないんですから。
僕が言えることは、親が成熟している方が、子どもは生きるのが楽だということくらいです。親が未成熟でももちろん子どもは育ちますし、立派に成熟することだってできます。でも、できたら親が成熟している方がいい。小さいときにはしっかり子どもを守り、ある時期になるときちんと「子離れ」できるようなもののわかった「大人の親」だと、子どもは生涯にわたってある種の「イノセンス」を保つことができるからです。
「イノセンス」というか「無防備さ」というか「お気楽さ」というか、そういうものです。別にそれ自体が高い社会的能力というわけではありません。けれども、「イノセンスを大人になっても持ち続けることのできる人」は、寝つきがいいとか、好き嫌いなくよくご飯を食べるとか、いろいろな人とすぐ仲良くなれるとか、そういうベーシックなところで「タフ」なんです。それがただちに権力や財貨や知的威信をもたらすわけではありませんけれど、それはさまざま能力や才能が開花するときの栄養豊かな「培養器」になれる。そして、その「培養器」の作成には親がかなり関与できるような気がする。親が成熟していると、子どもは大きくなっても、イノセンスを保つことができる。子育てについて、僕に言えるのはそれくらいですね。「イノセンスなんて、要らない」と言われたらそれっきりなんですけどね。
長い間、お付き合いくださって、ありがとうございました。
内田樹 拝
*本連載は今回で最終回になります。最終章(CODA)などを加筆のうえ、今秋単行本化の予定です。おたのしみにお待ちください。
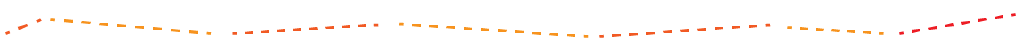
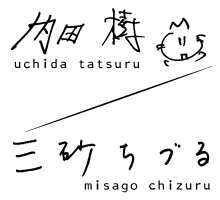 内田樹(うちだ・たつる)
内田樹(うちだ・たつる)
1950年東京生まれ。凱風館館長。神戸女学院大学文学部教授。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。著書に『「おじさん」的思考』『こんな日本でよかったね』『コモンの再生』『日本習合論』など多数。『私家版・ユダヤ文化論』で第六回小林秀雄賞を、『日本辺境論』で2009年新書大賞を受賞。
三砂ちづる(みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。京都薬科大学卒業。ロンドン大学Ph.D.(疫学)。津田塾大学多文化・国際協力学科教授。著書に『女たちが、なにか、おかしい おせっかい宣言』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『オニババ化する女たち』『死にゆく人のかたわらで』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『少女のための性の話』など多数。